
| 1 | 改正の趣旨 |
| 新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ有害性(発がん性)に関し調査を行い、その結果を労働大臣に届け出るよう義務づけられているが、新規化学物質の1年間の製造量又は輸入量が、労働者の暴露のおそれの少ない程度(100キログラム以下)である場合には、労働大臣の確認を受けることにより、当該新規化学物質に係る有害性調査の実施が1年間に限り免除されることとされている。 少量新規化学物質は複数年にわたって製造又は輸入されるのが実態であるため、手続きが事業者の負担となっていることと、労働者保護面からの要請とを勘案しつつ、検討した結果、少量新規化学物質の製造又は輸入に係る労働大臣の確認の有効期間について、1年延長し、2年間の確認期間とする。 |
|
| 2 | 改正の内容 |
| 少量新規化学物質の製造・輸入量が少量の場合に、労働大臣の確認により有害性調査を免除することができる期間を「1年」から「2年」に延長する。 |
| (1) | 新規化学物質の製造・輸入規制の概要 |
| 労働安全衛生法第57条の2において、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ有害性(発がん性)に関し調査を行い、その結果を労働大臣に届け出るよう義務づけられている。 | |
| (2) | 確認制度の概要 |
| 上記の規制については、1事業場における新規化学物質の1年間の製造量又は輸入量が、労働者の暴露のおそれの少ない程度(100キログラム以下)であるとき、労働大臣の確認を受けた場合においては、当該新規化学物質に係る有害性調査の実施が1年間に限り免除される。 |

| 1 改正の趣旨 | |
| (1) | 高齢化の進展等により脳・心臓疾患等につながる所見を有する労働者が増加しており、また産業構造の変化や技術革新の進展による労働態様の変化に伴い仕事や職場生活で悩みやストレスを感じる労働者が増加しているほか、「過労死」が社会的に問題となっている。 |
| (2) | このため、平成8年1月の中基審建議「労働者の健康確保対策の充実強化について」において、労働衛生管理体制等の充実強化とともに、現行の一般健康診断項目が脳・心臓疾患等の早期発見とその後の健康管理という観点からは必ずしも十分とは言えないことから、一定項目の追加の必要性と医師の判断による項目の弾力化の検討を行うことが提言された。 |
| (3) | この建議を受け、専門家による医学的な検討も踏まえ、脳・心臓疾患に関連して必要な一定の項目を追加するとともに、労働者の健康状況等を勘案し医師の判断により健康診断項目の省略等ができる範囲について、最新の医学的知見等を踏まえて見直しを行う。 |
| 2 改正の内容 | |
| (1) | 健康診断項目の追加 |
| 雇入時の健康診断、定期健康診断(特定業務従事者の健康診断及び海外派遣労働者の健康診断についても同様。)に次の項目を追加する。 ①HDLコレステロールの量の検査 (血中脂質検査への追加) ②血糖検査 |
|
| なお、これらの追加項目については、定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断においては、従来の貧血検査、肝機能検査及び血中脂質検査と同様に省略できることとする。また、尿中の糖の検査について、労働大臣が定める基準に基づき医師が必要でないと認めるときは省略できることとする。 | |
| (2) | 健康診断検査方法の弾力化 |
| 定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断における聴力検査について、45歳未満の者(35歳、40歳の者は除く。)については、医師が適当と認める聴カの検査をもって代えることができることとする。 | |

| (注) | |
| 1 | 下線①が今回の追加健康診断項目 |
| 2 | 下線②が今回検査方法を弾力化する項目 |
| 3 | 色覚は雇入時の健康診断のみで実施しなければならない項目 |
| 4 | 喀痰は雇入時の健康診断以外の健康診断で実施しなければならない項目 |
| (1) HDLコレステロールについて | |
| ① | HDLコレステロールは、コレステロールの1種。 総コレステロールは動脈硬化の程度を評価するために有用である。このうちHDLコレステロールは、特に虚血性の心臓疾患との関連が深く、総コレステロールと合わせて脳・心臓疾患の危険度をより的確に評価することができる。 |
| ② | HDLコレステロールの値が示す意味 低値:虚血性の心臓疾患(狭心症や心筋梗塞等)の危険度が高い。 |
| * | 脂質(コレステロール)の分類
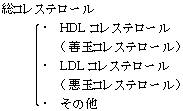
|
| * | 平成9年度の定期健康診断で血中脂質検査(コレステロール等)の有所見率は、20.9%と全検査項目の中で最も高率である。 |
| (2) 血糖検査について | |
| ① | 血糖検査は糖尿病の検査の一つ。 糖尿病が強く疑われる人は690万人、糖尿病を否定できない人を合わせると1370万人と推計される。 (厚生省 糖尿病実熊調査より) また、糖尿病は脳・心臓疾患とも関係が深い。 |
| ② | 現在、一般健康診断において尿糖検査のみを行っているが、血糖検査の方が、精度等の点で優れている。 |
| 1 改正の趣旨 | |
| (1) | 昭和37年のクレーン等安全規則制定の際は、当時の鋼材等の製造技術を勘案して、同規則に定める安全係数(つりチェーンの切断荷重の値を、当該つりチェーンの使用中にかかる荷重の最大の値で除した値)は5以上でなければならないこととされた。 |
| (2) | しかしながら、その後の鋼材等の製造技術の進歩により均質性の高い鋼材の生産が可能となり、近年、つりチェーンの切断荷重の値のばらつきも小さくなり製品の強度に対する信頼性が高まった。 このような状況を踏まえ、昭和63年に制定された日本工業規格(JIS B8816つりチェーンに係る性能、形状・寸法等について規定。)においては、つりチェーンの安全係数を4以上とすることができることとされたところである。 |
| (3) | また、主な外国における規格をみても、つりチェ一ンの安全係数は4となっている。 |
| (4) | こうしたことから専門家による検討も踏まえ、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則で定めるつりチェーンの安全係数について、製造段階において一定の強度試験に合格した場合にあっては、安全係数を現行の5以上から4以上として使用することができることとする。 | 2 改正の内容 |
| (1) | 対象 クレーン、移動式クレーン、揚貨装置、パワーショベル等の玉掛けに用いられるつりチェーン |
| (2) | 安全係数の見直し 製造段階において一定の強度試験(切断荷重の2分の1の荷重で引張った後、その永久伸びが0.5%以下であること等)に合格したつりチェーンについては、安全係数を現行の5以上から4以上とすることができる。 |
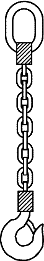
|

|
| つりチェーン | つりチェーンを用いた玉掛けの一例 |
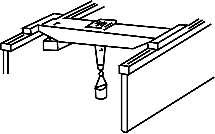 |
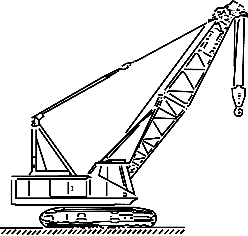 |
| クレーン | 移動式クレーン |
| | |
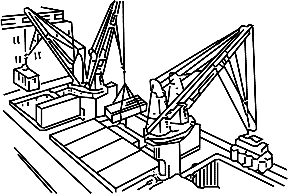 |
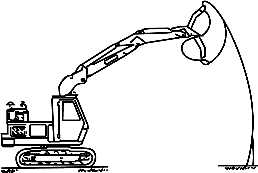 |
揚貨装置 | パワーショベル |