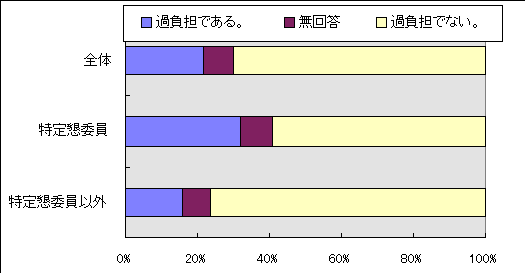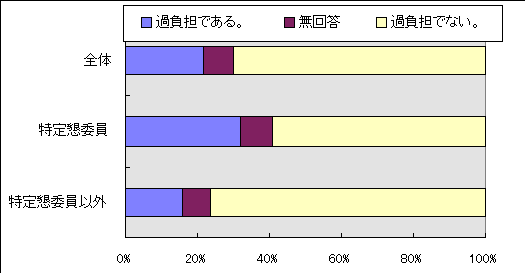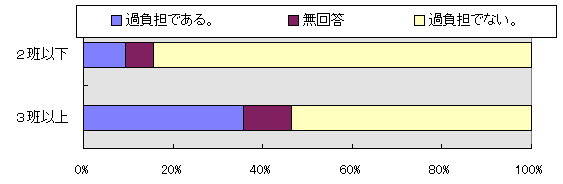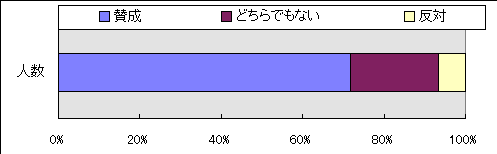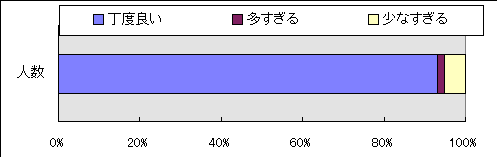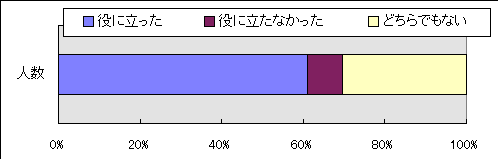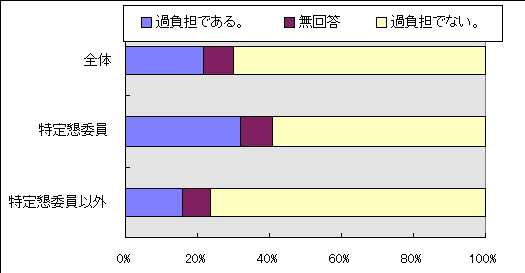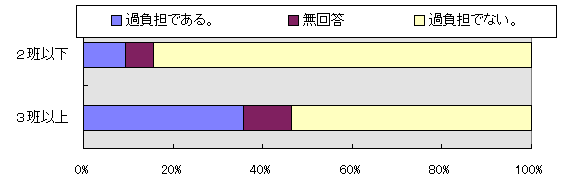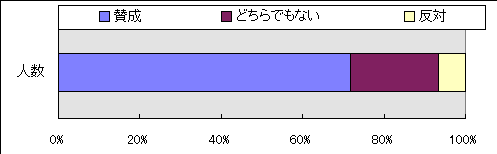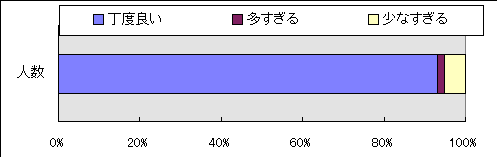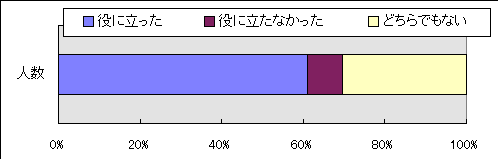参考資料2
評価体制に関するアンケート調査結果(評価(小)委員分)
平成10年8月13日
厚生省保健医療局エイズ疾病対策課
(概要版)
目的
特定疾患調査研究事業における、より良い評価体制を構築していくために、現在の評価(小)委員会体制に関するアンケート調査を行った。
対象及び方法
特定疾患調査研究事業において、割り当てられた研究班の評価を担当している評価小委員74名を対象とした。平成10年7月6日に各評価(小)委員に対しアンケート用紙をファックスで送付し、同月28日までに回収された60件について解析した。回収率は81%であった。
結果
○ 評価を担当している研究班数(便宜的に1分科会も1班とした。):2.5+/- 0.2 班(1〜6、中央値2)であり、その分布は以下のようであった。
| 担当班数 | 1
| 2 | 3
| 4 | 5
| 6 |
| 該当委員数 | 15
| 17 | 15
| 11 | 1
| 1 |
| (特定懇委員)
| 2 | 4
| 6 | 8
| 1 | 1
|
- 1班当たり評価時間(概算):(注:年2回班会議に出席された委員も集計上1回の計算になっている)
8.1 +/- 5.1時間
(0〜28時間、中央値
7.25時間)
- 1班当たり評価所要実時間(概算):
12.1 +/- 7.4時間
(0〜38時間、中央値10時間)
○ 評価(小)委員の業務は、過負担かどうか?(無回答5名)
- 過負担である。13名(22%) ・過負担ではない。42名(70%)
(うち特定疾患懇談会委員(以下、特定懇委員)・過負担である。7名(32%) ・過負担ではない。13名(59%)
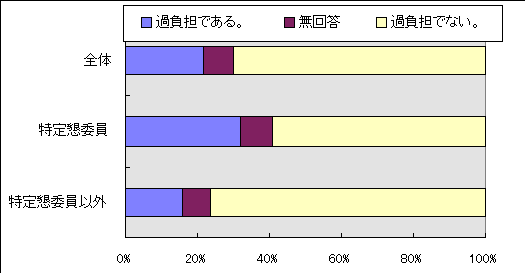
担当班数別による過負担感:
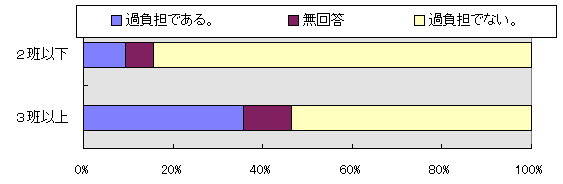
| 担当班数 | 過負担である |
過負担でない | 無回答 |
| 2班以下 | 3 | 27
| 2 |
| 3班以上 | 10 | 15
| 3 |
○ 現行の研究班に張り付いて、評価を行うことについて?
・賛成43名(72%)・どちらとも言えない13名(22%)・反対4名(7%)
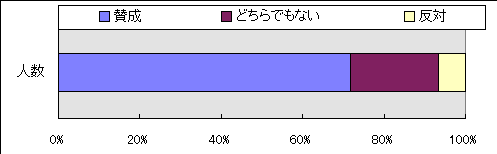
○ 現行の評価(小)委員会の人数(4〜5人)は?(無回答1名)
・ちょうど良い55名(92%)・多すぎる1名(2%)・少なすぎる3名(5%)
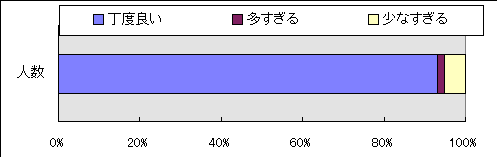
○ 評価(小)委員会に就任により、先生の本来の研究に役に立ちましたか?(無回答1名)
- 役に立った。36名(60%)・役に立たなかった。5名(8%)・どちらでもない。18名(30%)
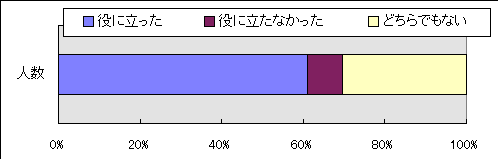
○ 先生は特定疾患対策懇談会の委員ですか?
・委員である。22名(37%) ・委員でない。38名(63%)
評価体制に関するアンケート調査結果(評価(小)委員分)
平成10年8月13日
厚生省保健医療局エイズ疾病対策課
目的
特定疾患調査研究事業における、より良い評価体制を構築していくために、現在の評価(小)委員会体制に関するアンケート調査を行った。
対象及び方法
特定疾患調査研究事業において、割り当てられた研究班の評価を担当している評価(小)委員74名を対象とした。平成10年7月6日に各評価(小)委員に対しアンケート用紙をファックスで送付し、同月28日までに回収された60件について解析した。回収率は81%であった。
結果
○ 評価を担当している研究班数(便宜的に1分科会も1班とした。): 2.5
+/- 0.2 班(1〜6、中央値2)であり、その分布は以下のようであった。
| 担当班数 | 1
| 2 | 3
| 4 | 5
| 6 |
| 該当委員数 | 15
| 17 | 15
| 11 | 1
| 1 |
| (特定懇委員)
| 2 | 4
| 6 | 8
| 1 | 1
|
- 1班当たり評価時間(概算):(注:年2回班会議に出席された委員も集計上1回の計算になっている)
8.1 +/- 5.1時間
(0〜28時間、中央値
7.25時間)
- 1班当たり評価所要実時間(概算):
12.1 +/- 7.4時間
(0〜38時間、中央値10時間)
○ 評価(小)委員の業務は、過負担かどうか?(無回答5名)
- 過負担である。13名(22%) ・過負担ではない。42名(70%)
(うち特定懇委員・過負担である。7名(32%) ・過負担ではない。13名(59%)
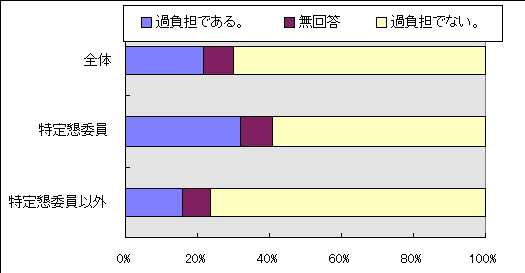
担当班数別による過負担感:
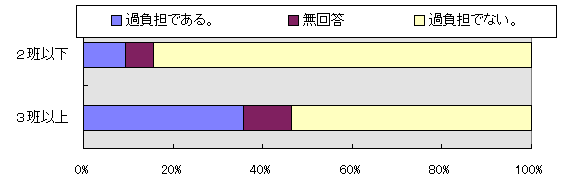
| 担当班数 | 過負担である |
過負担でない | 無回答 |
| 2班以下 | 3 | 27
| 2 |
| 3班以上 | 10 | 15
| 3 |
○ 現行の研究班に張り付いて、評価を行うことについて?
・賛成43名(72%)・どちらとも言えない13名(22%)・反対4名(7%)
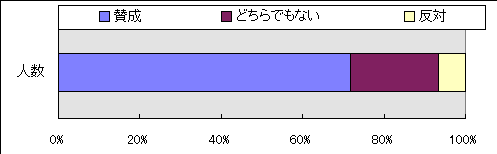
賛成のコメント:
- 発表を直接聞くことにより成績の評価が正確、公平に出来る。発表の抄録を少なくとも1ヶ月前には手に入れたい。類似論文を読み、オリジナリティの判定が必要である。
- 種々の専門家が客観的に評価し合うことは研究費をより有効に使うのに必須である。
- 4班は多すぎました。自分で希望又は申し出たのですから、自分の責任です。せめて2班ぐらいに減らしたいです。
- 経年的に内容を理解していかないと、進歩の評価が出来にくいので、現行で悪くないと思う。
- 自分の専門に近い分野の評価するのが一番良いと考える。
- 研究方針と実行の一貫性をみることが出来る。
- 詳細に評価することが出来る。
- 厚生省型の研究を文部省型の研究から区別して評価するためには班員の発表を聴いて評価しないと不可能である。
- 研究内容の抄録だけでなく報告会に出席し討議に参加しないと十分な評価をすることが出来ないので、研究班にある程度張り付くことは必要である。
- 各班毎に評価委員会が異なるのはあまり賛成できません。今後の改善の方向性として、
- もう少し広い範囲の複数の班を5〜10人程度のCommitteeがカバーすることで、班間の相対評価をある程度可能にする。
- Committeeが1日位時間をとって、班毎の具体的資料に基づいて踏み込んだ評価を行う(少なくとも新薬調査会ぐらいの労力をかける必要があるのでは?)
- 研究費の配分金額を考えても、この特定疾患研究班の性格を政策的にもっと正確にしないと評価基準を設定するのが難しいと思います。
- 適正な評価を行うためには、年1回研究班の発表を聴くのがよいと思う。しかし、大学の業務が忙しく過負担である。
- 特発性大腿骨頭壊死症と脊柱靱帯骨化症の2つの班が同時並行で発表会を行うため、評価のための成果聴取が1つの班しか出来ない。研究報告会の日を変えて行うことを強く要望する。
- 3年位は継続して評価することが必要。
- 報告会に参加できない場合もあるので、評価に耐えうる抄録があることが望ましい。(抄録があるものもある)
- 抄録だけでは分からない具体的な内容が分かる。
- 3班のうち2つは賛成。1つは不適。研究班の班長が評価(小)委員長の所属する同一機関の研究者なので、公平さに欠くとみられるので出来れば別機関の評価委員が評価委員になる方がよいと思う。
- 実際に会議に参加しないと研究内容が十分に把握できないので、張り付く必要がある。
- 1 研究班発表の日時に都合を合わせられない場合がある。
- 2 年2回(計4回)丸1日の発表会に時間を合わせるのは、かなり困難がある。
- スケジュール上困難な面もありますが、これ以外に方法がないのではないでしょうか。
- 班長、班員との意見交換の機会が少ない。食事は会議だと遠慮せず、推進する方向を取るべき。
- 研究班の方向性や成果を具体的に把握するには、張り付いていないと無理ではないか。
- 班研究の発表実施に緊張感をもたらし、班長のグループ研究の方向付けを支持すれば、グループ研究を推進し易くなるという利点があろう。
- 研究内容を詳細に把握出来る。
- 各委員は最大2つ位では?無理して3つです。私個人としては、来年から2つにしていただきたいと思っております。期日が重なり過ぎるので。
- 1 張り付いていない時に比べ、より具体的に評価が出来る。
- 2 その時々のコメントが次回に生かされている。(班長経由ではほとんど機能していない。)
- 実際の班会議に出席していると、業績、内容などレベル、質などが分かり良いと思います。しかし、これは望ましいとはいえ、時間的な負担が多いのです。何か考えないといけないですが、難しいですね。
- 基本的には意味があると思うが評価してある改善の方向を提案してもその対応が遅れるので、企画の段階で評価委員よりも審査される方が方針をある程度出していることが望ましい。
- 研究班の実際に接して評価することがまずは必要であろう。
- 調査研究班の新しい方向性を見届けるために一定期間(3年程度)張り付けて評価、指導を行うのがよい。
- 研究の現状、流れが良くわかり、評価しやすい。また、班員への助言も可能である。
反対のコメント:
- 4班の担当は機械的に割り振られたもののようである。従って、必ずしも自分の専門分野と一致していない。担当数を4班から2班程度に減らし、自分の専門分野と一致するようにしてほしい。
- 年2回の班会議に全て出席し、全員の発表を聴き評価するということは不可能のことが多いし、各班員の報告時間が短い上、発表される研究内容の多くは研究途上のものであり、評価し難い場合が多い。研究班としての評価は、あくまでも得られた成果とそれに基づく将来の研究の発展性に基盤をおくべきであり、この観点から、班長の研究成果報告書、業績報告書、将来構想を含め、例えば、毎年出版している研究班報告書などに基づいて評価を行うという方法もあるのではないか。
- 自分の専門領域と関連性がないため。
- 班長にとっては相談できるので楽であろう。しかしこの制度で実績が上がったかどうかは疑わしい。
どちらでも良いのコメント:
- 若干評価が甘くなる傾向がある。
- 一つの班は専門外であるため。
- どの位、評価委員の意見が班の構成、研究に反映させているのか掴めていないので、何とも言えない。
- 評価委員は、その領域の得意の人の方が良いと思います。
- 確かに有効な制度であるが、もう少し能率的に。
- 昨年評価を担当した2研究班のうち、1班については私自身の研究とも関連があり、かなり正しく評価出来たと判断しているが、もう1班については、関心があるが、私自身の研究と直接関連がなく、正しく評価出来たかどうか自身がない。この班については適任者ではなかったと自己評価している。
- 委員長が必要と判断されるのであれば協力いたします。
- 本人が判断することは難しいですが、より内分泌系が一番自信があります。
- 賛成であるが、口頭の報告のみでなく、報告書のsummary位は読んでおくことが必要か?abstractのみでは分からないところがある。
- 研究班の成果が上がっている場合は評価を行うことに関して問題は殆どないが、班研究の成果が芳しい成績でない場合は微妙な問題がある。正しい評価を行うためには現行でもやむを得ない。
- 評価は必要であるが、現行のやり方が適当かは疑問。評価委員が2つ以上の研究班を担当するのは、出来るだけ避けるべきではないか。評価委員の欠席が多い研究班もある。
○ 現行の評価(小)委員会の人数(4〜5人)は?(無回答1名)
・ちょうど良い55名(92%)・多すぎる1名(2%)・少なすぎる3名(5%)
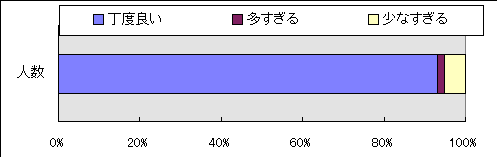
ちょうど良いの理由:
- 意見が適切な程度に出される。
- 余り多くても評価が一定しない。
- 多すぎると、意見を出しにくい。過負担の感が強くなるだろう。
- 臨床、基礎合わせて主体的な評価のために丁度良い。
- 多くとも5〜6名が丁度良いところでしょう。3名では少なすぎる。
- ただし、今までの権威、成り行きで班会議、評価委員会にも十分参加しないでいろいろコメントを言われる方がおられるのはどうかと思う。
- 3〜5人で丁度良いと思います。
- 4〜5名であるのが、実際に全員集まることは少ない。委員会が数が多すぎてもつけないが、少なすぎてもつけない。
- 委員は、出来るだけ分野別に選ぶ。(外科3名とかしないこと。しかし、班の研究内容にもよるが)
- 多いにこしたことはないが、1部の評価委員が過負担にならないためには、4〜5名が適当である。4名以下は少なすぎる。
- 人数は良い。しかし、もう少し、その分野の専門家をいれるべきでは?
- 私以外の方は適任と思われ、そうであれば、人数は4〜5人で十分と思われる。
- 形の上で多すぎる人数で欠席者が多い、或いは中途で退場する委員が多い場合は、このような人選は不適と考える。あまりに同じ人に安易に頼み過ぎていませんか?
- 数の問題でなく、適切なコメントを忌憚なく言えるかどうかの問題です。
- 研究会(班研究)発表の後での短時間の討議となりますので、あまり人数が多くてもまとめるのが大変な場合もあります。
- ただし、委員の構成は重要。
- いろいろな分野の人がいるので評価が公平になる。人数が少ないと評価に不公平が生じる。
- 日が合う委員は4〜5人中2〜3人であるが、一応1〜2人は必ず発表会には出られる。
- 全委員が自由に意見を出すのに丁度よい人数である。
- 多すぎると意見の要約が難しくなる。少なすぎると個人的見解の偏りが強く打ち出されるというおそれがある。
- 基礎2、臨床2のバランスは良い。(臨床を若干増やす方が良いかも知れない。)
- いろいろな分野の専門家がおられるので、良い委員会と思います。この点は将来も宜しくお願いします。
- 現行の評価委員は非専門家が多く、少なくとも2〜3人くらいは専門家である必要があろう。委員の数によっては、3人くらい(専門家1〜2名位)でもよい。(班への参加を限定したとき)
- テーマによるが、専門性の狭い班ではなるべく少人数の中性の人がよい。
- 臨床・基礎ということで、あらゆる条件を考えると現行でよいのではないかと思う。
- 臨床系、基礎及び社会医学系でそれぞれ2名の組み合わせは、評価視点の面からも略理想的と思われる。
- 臨床2、基礎2は評価委員同士の連絡もしやすく良い。
- 必ず出席していただければ、4〜5人でよい。
多すぎるの理由:
- 評価に責任を持たせるためには3人位が適当ではないか。
少なすぎるの理由:
- 班会議に出席できない評価委員が多くいる。より多くの評価委員で、適切な報告書に基づいて評価した方がfairと思われる。
- 5〜10人程度のCommitteeが10研究班以内のプロジェクトをまとめてゆくのがもっと効率的かと思われます。
○ 評価(小)委員会に就任により、先生の本来の研究に役に立ちましたか?(無回答1名)
- 役に立った。36名(60%)・役に立たなかった。5名(8%)・どちらでもない。18名(30%)
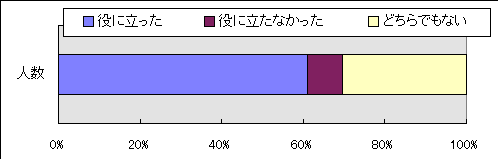
役に立ったの理由:
- 特に自分のグループの研究が国際的にみてどのような位置にあるかがわかった。良い論文、悪い論文がある発表会はその意味で興味がある。
- 新しい学術情報を知ることが出来た。
- 自分のカバー出来ない専門領域について詳細に内容の報告を知ることが出来たため。
- 疾患に関する最新の動向を知ることが出来た。
- 分野外の進展、方向性を知り得、私たちの基礎研究の貢献場所を考えるのに極めて有効。
- 担当分野は現在、直接には研究上の関わりはないが、従来私の専門とする生化学、分子生物学の手法がタッチ出来なかったものが、次第に可能になってきているので、興味深く役立つ。
- 自分の知見を広めるとともに、様々な人たちと知り合い、また、共同研究が発展している。
- 大変役に立ちました。勉強になりました。
- 臨床での研究の動向を知る機会となった。
- 一般的な研究動向を知ることが出来た。
- 自分の専門分野であるので。
- 実践と研究の関係をみれば、どんな評価も同じである。
- 発表をじっくり、あるいは批判的に聴くことにより、自分の勉強にもなる。
- 特に他の評価(小)委員との意見交換は興味深い。他の分野の人の視点が理解出来るようになった。
- 研究班の研究課題の中に研究成果を期待しているものが多いので大いに役に立っている。
- 1996年までNIHの一般研究費の常任審査委員かカナダの種々の研究費・fellowshipなどの審査委員を務め、日本のシステムとの違いをこの研究費の評価委員会に加わることで実感することが出来ました。その意味で良い経験をさせていただいております。ある程度の広い範囲の研究のprogressをモニターせざるを得ないという立場は私自身の仕事にも必ず何かの形で役立つものと考えております。これはどこの国におりましても同じであると思っております。
- アミロイドーシスに関して骨関節以外の分野の知見が広まった。
- 難病研究の動向が把握出来る。
- 特定疾患全体の研究事業を理解し、また、研究(班)のありようを大局的に考える上で役立った。
- 大変役立っており、自分の勉強にもなっているので、今後も続けたい。
- 視野が拡がった。
- 境界領域や関連の薄い領域の研究成果を学ぶことが出来、有益であった。
- 特に副腎過形成やPrader病について新しい知見を得られたのは、自分の研究にも役だった。
- 新しい視野が得られ、非常に有益であった。
- 全国レベル、動向が良くわかる。
- いろいろ勉強になります。役に立てるかどうかは本人次第でしょうが、人の研究を聴かせてもらうのは勉強になります。
- 日進月歩の領域であるため、極めて役に立っています。
- 神経変性疾患、運動失調症の2研究班については、基礎・臨床共に役立った。
- 私自身は現在研究現場には直接関与していないが、学内の研究動向の評価にも参考になることが多い。また、新しい分野で先端的研究のみに走って、臨床的基盤にやや乏しいと思われる感じる点もあり、その都度、疑問点を質してきた。
- 私は基礎研究者ですが、当該研究班の研究に関係する研究もしており、それを基礎として助言しております。また、我々の研究室でしか出来ないこともあり、最近研究班に関する疾病の病因に関する研究もし、この数年内に興味深い結果が出せると思います。
役に立たなかったの理由:
- 私の専門と関係なく、専門を超えた普遍的な事象が研究対象となる研究班ではないため。
- 自分の研究の役には立ちませんが、自分の視野を広げたり、専門外の人たちについてよく観察し、人材をみつける場としては、役に立ちます。
どちらでもないの理由:
- 自分の専門分野については役に立ったが、専門でない分野については役に立たなかった。
- 研究には役に立たないが、研究の動向が見えることは評価委員としてメリット(incentive)の一つと思う。専門誌のReviewと同じように思う。
- 一般的な知識を得るという観点から役に立つ場合もあるが、多くは学会や紙上発表ですでに予知できるもので、とくに班会議での発表が自分たちの研究に役立つをはいえない。むしろ、評価委員として研究の方向性などについて示唆を与えることの方が多い。
- 自分自身の研究にはあまり役だってはいない。しかし、班会議に出席し、新しい知識を得ることがある。特に分子生物学的研究は進歩の速い分野であるからその感が強い。
- 大変勉強にはなったが、私自身の本来の研究に直接役に立ったかどうかに関しては良く分からない。
- 臨床研究が多く、私の関連分野の基礎研究はほとんどないので、直接役立ちはしないが、関連分野の臨床研究があるので参考になりました。
- 大変勉強にはなったし、現在の問題点やトピックスが分かり参考になった。
- 先端的な知識を知ることが出来るが、直接役に立つことはなかった。
- レトロウイルスを専門としているのでこの話題はほとんどない。発表としては意味があり、刺激を受ける。
- 平成5年3月に大学を定年退職しているので、自らが積極的に研究することがないので。
- 自分の専門以外のところは大いに勉強になりました。臨床と基礎研究特に後者は必ずしもそのタイトルと合致しないものがある。これは関連する基礎疾患として大きなカテゴリーを作りまとめて討議して欲しい。
- 評価対象の研究班とは中立であり、評価委員就任が評価者の研究上に直接役立つことはない。
- 役に立った研究班もあれば役に立たなかった研究班もある。
○ 先生は特定疾患対策懇談会の委員ですか?
・委員である。22名(37%) ・委員でない。38名(63%)
○ 現行の評価体制について御意見がありましたらご記入下さい。
コメント:
- 評価体制は適切であると考えられるが、その運用は十分でない。
- 1 班会議は年2回開催されても、評価小委員が出席できるのは、年度末の1回のみである。(旅費が年1回しかでない。)従って、年度末の会議では、各班委員は1年分の成果をまとめて発表してもらわなければ、評価小委員は1年分の成果を評価できない。それにも拘わらず、各班委員が1回目の班会議分は除外し、2回目の分のみを発表していることがある。これでは、評価できない。
2 班会議終了後に、全員の前で評価委員の意見を求められることがあるが、これは評価小委員の責務となっているのか?評価が低い場合は正直に言いがたいし、正直に言えば恨まれる。班会議の席上で評価委員に評価発言を求めるのはやめて欲しい。
- ほぼ妥当と考える。
- 会議に出席しなくても、計画書/結果報告症というドキュメントをReviewする方が良いと思う。そうすれば、Reviewerの名前も班員に出なくて公平(正)感が保たれると思う。文章による年度始めの計画Reviewと年度終わりの結果Reviewをして、各Reviewerが、責任Reviewer(評価委員長)に報告する形を望む。出席の不要、Blind
Reviewのメリットあり。
- 限られた予算をより有用に使うため、大変良いシステムである。
- 責任ある報告書に基づいて多くの評価委員の評価を受けるという方法が最もfairであると考える。なお、評価委員長による特定疾患対策懇談会での評価報告は、時間的制約があるなどの問題を含め再考が必要と考える。
- 評価結果がどのように予後に反映されてゆくのか、又は、されたのか、今一つはっきりしない点がある。予後とは予算の傾斜配分等も含む。
- もっと若手のactivityの高い人々を評価委にすべきである。まだ、あまりにも多くを担当している人がいる。
- 朝から夕方まで班会議を全部聴くことは大変疲れます。班会議への出席は都合のつく時間にしていただき、そのかわりに、やはり班長さんによるまとめのプレゼンテーション(30分前後)を評価委員のみにしていただきたいと思います。そこで質疑応答を行い、その後、評価委員同志による検討会がやはり1時間前後あるべきと思います。現状では、班長の説明がほとんどなく、また、評価委員同士の検討や相談も非常にpoorです。
- 評価委員長が総括して報告するだけでなく、研究班班長に成果内容を報告させ、そこでもっと質疑応答をする時間を作るべきと考える。
- 評価体制はこれでよいが、研究班の発表のうち半数以上は、研究班の目標とする事業と無関係の発表であるので、それにぴったりつき合わされるのはちょっとつらい。事業と関係ある発表のときのみ張り付くべきと思う。
- 新しい評価体制でスタートしたので、もう少しこのままでVerlaufをみては如何ですか。
- 1 懇談会委員の構成について:臨床委員と基礎委員のうち、基礎委員に遺伝子・免疫・疫学はあるが、病理委員がないのはよくない。難病を「総合的見地からみているのは病理医」であると思う。
2 班の評価委員長が自分の関係する班の評価を高めるために、良い点のみを懇談会で述べるのは客観的でない。
3 評価項目が(懇談会での)「よい点」「不十分な点」「目標に対しどの程度の完成度か」などを明確にすべき。
- 詳細に検討した訳ではないが、特に問題はないものと判断している。
- フィードバックが欲しい。
- 若手の専門家を評価委員に加え、厳しくpeer
Reviewすべし。その方が、研究班員にもプラスになる。
- むしろ広く国際的に専門家の評価を受けた方が良いでしょう。(英語で)
- 研究の当初から、研究事業を班長並びに班員に明確に伝え、文部省支援型(科研費型)研究との違いを明瞭にすべきである。
- 委員長が大変良く、他の委員のコメントに耳を傾けられる方ですので、良い評価体制であると思います。
- 評価体制は、このままで良いと思います。あまり、しばしば変更しては評価体制の評価が困難となる。
- ある程度の相対評価を可能とすることとし、もう少し内容のある議論を具体的にできるようにすること、きちんとしたレポートとして評価を記録に残すことなどが必要であると思います。NIHの委員会の資料などご参考になればと思います。
- 1人の評価委員が担当する研究班2班以下とすべきと思います。
- 1 適任者が評価委員を務めているかどうか。
2 方針にしたがって評価が実施されているかどうか。
以上の2点について多少の疑問を感じている。
- 遠隔地の委員の都合を優先して、会を設定して欲しい。なぜなら、遠隔地の委員は一日かけて出席することになり、近郊の委員は調整しやすいはずである。
- 1 報告会に出席できない場合もあるので、評価に耐えうる抄録があることが望ましい。
2 評価方法に関して:適当であった。適当でなかったの2段階で評価する項目があるが、3〜5段階程度の段階があった方がよい。
- 今の評価体制は極めて形式的である。懇談会には班長は出席を求められていない。評価はやはり班長が出てきて長時間かけて班研究の説明を行い、質問を受けるべきと思う。評価委員が3分ほど説明する現在のやり方は意味がない。
- 評価(小)委員長が班の成果を説明するのではなく、班長が説明し、それに評価委員がコメントすればよいのでは。
- よいと思う。各班の評価委員はいろいろな分野の人で構成するのがよい。
- このままで2〜3年続けてはどうか。委員が段々高齢になるので少しずつ若い人を入れる方がよい。
- 適当な時期に各分科会のリーダーとの会を持って、それぞれのサマリーと問題点を出してもらって、将来に対しての意見を交換したい。
- 評価体制が毎年のように変わるのは問題。3年くらい同じ体制で続けてみてその上で見直す。
- 評価はopenにして、各評価委員が直接、班研究の終了時に講評を伝え、評価している。複数の委員による評価は評価委員相互にとっても有益であった。
- 施行期間中と考えるので現体制で1クールやってみるとよい。
- 評価小委員会の評価体制は良いと思うが、横断的な評価体制との関係が小委員会レベルでは、見えていないように思う。
- 班により極端なレベル差がある。pureな学問的なもの(基礎を含む)とQOLなどを中心とした社会医学的なもの、これらは分けて評価する必要はないか?
- 直接参加の方式は極めて有効なので、同一人が複数掛け持ちにならぬようにして負担を減らすのが良い。懇談会での総合評価も必要である。
- 施行錯誤とは思いますが、仲間内だけでない評価が一般的になってきた傾向は良いことです。勉強という意味からは、もっと若手の30〜40前半の人を何人か入れるのは次の世代の育成の面からもよいと思います。
- 現行の研究班長に世話による評価(小)委員会に加えて、評価(小)委員長を中心に評価(小)委員だけでの検討の時間を設けても良いのではないでしょうか。
- 本来はどんな研究班でも十分な時間と十分な研究費を与えて計画のままやらせた上で評価すべきで、中途半端な研究の細切れを評価しても余り進歩や改善は生じがたい。
- 評価が客観的にしかも専門性を生かした現行は良く機能していると思う。
- 評価体制は試行錯誤によって良いものが出来てくるもので、3年が終了した時点で多少見直しを必要とするかも知れない。しかし、大幅な修正はここ2〜3年はしない方が良いと思う。
- 評価する基礎資料として、班会議前に班会議プログラムとともに当年度の研究申請書並びに班員協力研究者への割り当て予算額等の資料を評価委員へ送付されることが望ましい。
- 班研究報告会は、同一日に重なって午前と午後の掛け持ちとなった。班により抄録が会場で配布された。(小グループの班でこの傾向がある。)
- それなりに機能しているとは思うが、実効性がどの程度上がっているかは疑問。研究班長及び班員に対して牽制球程度の役割はあると思う。
- 評価体制は有効で私の知る以前の研究班に比べ格段に研究が進んでいると思います。評価委員の存在、助言がかなり大きな力となっております。評価委員は研究歴も長く、研究班の研究に役立つ研究組織を持っている方であるので、その研究を生かすことも特定疾患の病因解明のために必要ではないでしょうか。
- 特にないが、学術学会とはいかなくても学術発表会であるので、患者代表が出席するのは本来あるべき学術内容を曲げて発表する可能性がある。出版物等で公開しているので討論会場への出席はどうかと思う。フリーな立場からの質疑も出来なくなると思われます。
○ 特定疾患調査研究事業に対する御意見がありましたらご記入下さい。
コメント:
- 厚生省に関係する研究費も特定疾患調査研究事業、長期慢性疾患総合研究事業、遺伝子研究など研究者が重複しているものが多い。しかし、その分野の優秀な研究者は無限と言うことではない。このことはそれらの人々が少し研究題名を変えることで複数に応募している。他方、研究成果の発表を聞いたり、発表文献でみると、あまり成績が上がっていない人もいる。これなどはある意味では研究費のバブル現象で後日その運営体制に批判が集まる。従って、ある応募論文の評価に対し、応募者からの反論が出来るような制度を作ったらどうだろうか。これはNIHの研究費配分の一部に取り入れられており、査読者も真剣に判定せざるを得なくなる。査読者も40歳代前半の人が好ましい。
- 旧来からある研究班であるという理由のみで班を集結するのは必ずしも妥当でないと思う。
- 厚生省の行う事業であるため、余り基礎的な研究は好ましくない。この点、班長による研究班に委員の選択と班の運営に関する指導性が大切と考える。
- いつも新しい試みが次々と展開され、行政の方に敬服している。
- 基本的には極めて重要かつ有意義な事業であり、将来ともに発展を促す必要があると考える。
- 事業内容がどのように一般社会に還元されているのか、情報発信の質の向上、公開等含めて、再検討して欲しい。
- もっと分子医学研究の発表をbaseとした特定疾患の診断、治療、並びに予防につながるoriginalな研究が出来るよう、promotionするような評価体制と班研究を行うべきである。
- テーマの中には存続する価値があるのか疑問に思われる(何の成果が出ているのか考えられない)研究班がある。そのような班は、厳しい評価をして消滅させるべきである。
- 研究事業を整理の上、重点化すべきと思う。
- 調査研究事業は大変重要であり、今後とも継続して欲しい。将来同じ厚生省の例えば「厚生省精神・神経疾患委託費」などの他の班研究を一本化することは出来ないでしょうか。
- 班員であったときの感想としては、以下の様な問題を感じた。
- 班員の人数が多く、班員1人当たりの研究費が少ない。
- 研究費の支給が遅く、研究計画に沿って適当に使用されているかどうか疑問がある。
- 他の研究事業(例えば、文部省科研費)と重複した研究者、研究テーマが多い。
- 以前の総花的から比べて段々と改善している。
- むしろ広く国際的に専門家の評価を受けた方が良いでしょう。(英語で)
- 研究の当初から、研究事業を班長並びに班員に明確に伝え、文部省支援型(科研費型)研究との違いを明瞭にすべきである。
- どのような基礎研究も特定疾患の成因、病態、治療、予後などに具体的にどのように貢献するのかを常に意識して行うべきと考える。上記の点に本研究事業の特徴がある。
- 小児科専門ですので、小児慢性特定疾患では長年研究班で、厚生省にもお世話になっており、感謝致しております。特定疾患の方は共通疾患についてお世話になってきておりますが、難治性疾患の一日も早い治療進歩を願っております。
- 疾患の解決には、別途により高額の支援をするとすれば、全体の状況をカバーし、問題点を見出すのには適当かもしれない。
- 政策的にこの研究助成がどのように位置付けられているのか良くわかりません。この数年の”バブルグラント”と比べて明らかに見劣りする金額と旧来の枠組みで配布するとこを再考する必要があると思います。ただし、”バブル”の方もそろそろしぼみ気味のようにも見受けられますので、この程度の金額で多くの研究者を一つのテーマでともかく”集める”というだけでも意味があることかも知れません。ともかくCost/Performanceという観点から、この事業を科学技術予算・公衆衛生政策の両面からどのように位置付けるのかをはっきりさせる必要があると思います。
- 昨年度の評価会議における各評価委員の発表は3分でしたが、これは実質的ではないので、もし日程の都合で1日でやる必要があるのなら、文章による提出で良いのではないか。
- 調査研究の具体的な目標を掲げ、その目標を達成できる可能性の高いメンバーで班を構成すべきであるが、必ずしもそうでない面がある。
- 我が国の難病に対する研究を飛躍的に発展させたので、厳密な評価を行いながらも今後も継続して行うことを要望する。
- 班の構成がよくない。班員の数を減らしたことが致命的となった。臨床研究班では、疾患の統計が取れなくなった。形の上で横断的研究班とリンクしているが過去のデータの分析を行っており、今日のデータは集められていない。研究費が倍になっても研究の実績は倍にならない。
- 評価委員に対して謝金、もしくは研究費を出すこと。このような配慮は全くない。極めて日本的で驚くべきことと思う。
- 政策的な面と本邦の研究者が世界に向けて成果を発信できる面とのバランスの必要性を感じる。
- 1 特定疾患調査研究事業は今後も強化推進して頂きたい。
2 現在の評価システムは班研究に緊張と刺激をもたらし、研究の活力ある推進に役立っていると思われる。
3 将来のために若手の研究者育成、その研究助成の姿勢は大きな希望達成に必ず役立つと思われる。それにしてもう少し長い目で育成して頂きたい。
- 基本的には現在の形でよいが、新しい疾患を加える。古い疾患は整理・統合する必要が強く感じられます。原因の分かったもの、治療が分かったものはまとめては如何かと思いますが。
- かなり、変わってきたと思いますが、信頼の置けるプロ(少ない!どの分野でも!*)を班長にして3年間かなり自由にやらせてみるのだ良いでしょう。(*:これが日本の特徴。どの分野でもそうです。)
- もっと少ない重要項目に成果を期待できる研究を十分やらせることが望ましい。
- 評価は分かれるが、本事業は集積された患者を対象にその病態生理を研究するものであって、まず、臨床をしっかりとらえた基盤が必要で、サイエンスとして評価されても、疾患との関連性を十分に吟味して評価すべきであろう。
- 班研究の能率を高めるため研究班評価は欠かせない。実際に即した評価法の実施が望まれる。そのためにも評価の”評価”と評価の公開が必要となる。
- 再編成計画により、少し改善されたが、まだ、各個研究が多い。班長のリーダーシップが充分に発揮されていない感もある。プロジェクト研究を主体とし、発表もラウンドテーブル形式にしても良いし、また、年毎にテーマにより班員(協力班員)の構成を変えてでも班としての研究を心がけて欲しい。
- 特定疾患それぞれ患者がいるので、特定疾患を絞り込んでいくより、より効率の良い研究をする方略を探るのが良いのではないでしょうか。研究班同志で共通する部分は両研究班で1つとする。例えば呼吸不全、びまん性肺疾患研究班での治療法の1つと期待されている肺移植や、QOLをあげるための呼吸困難対策等です。