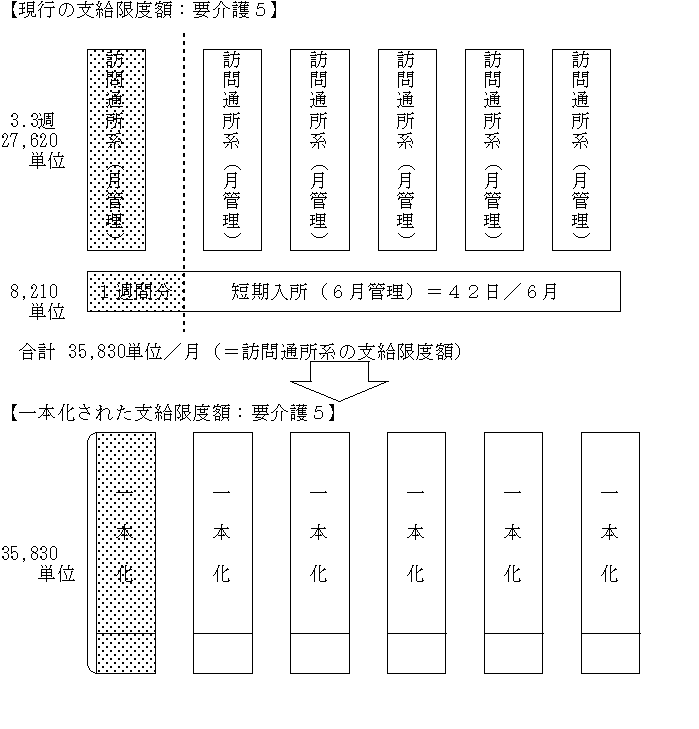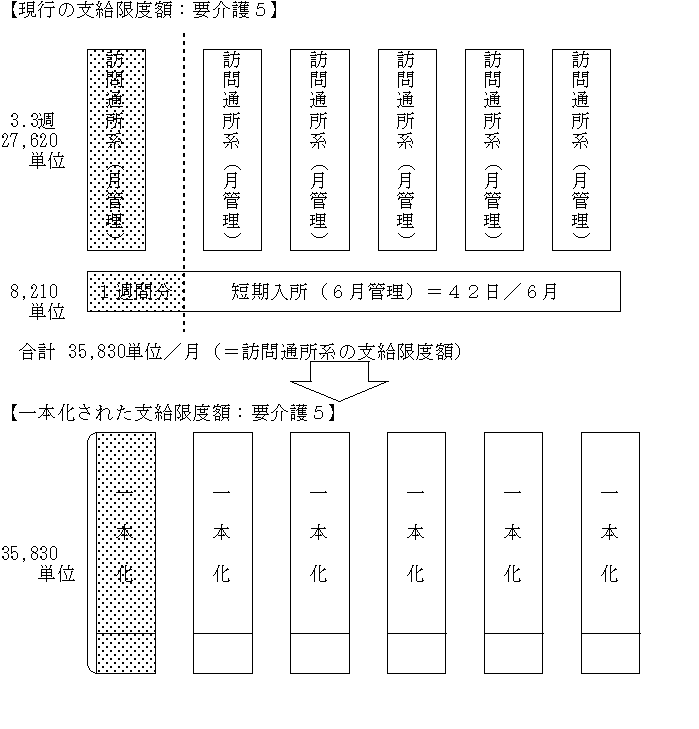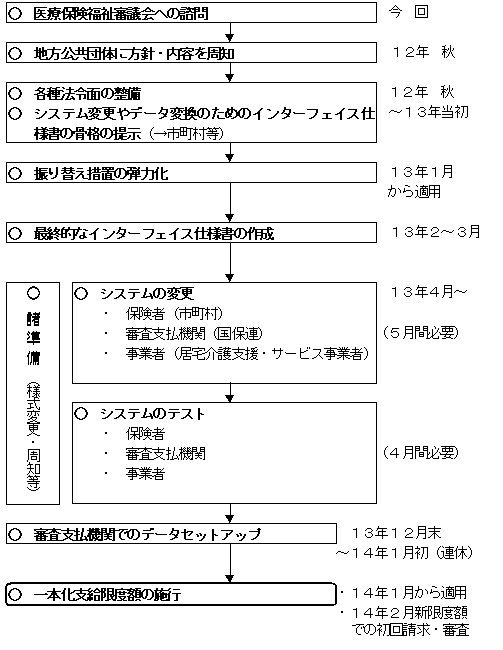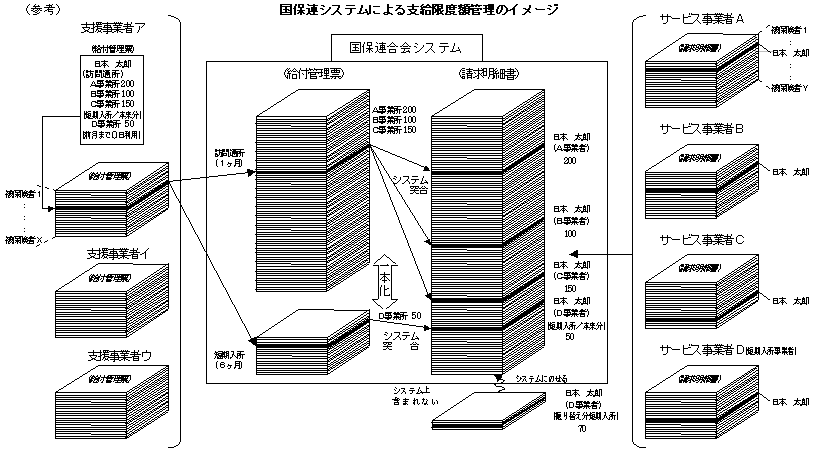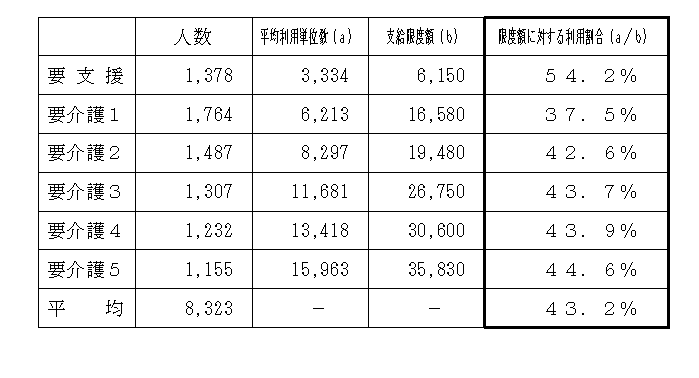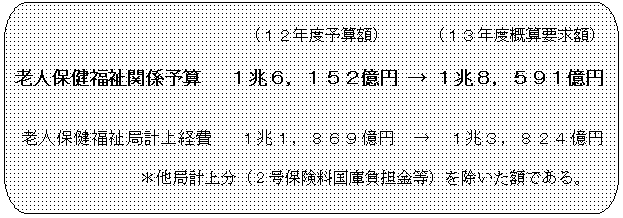介護保険制度についてへ戻る
医療保険福祉審議会 老人保健福祉部会
・介護給付費部会合同部会(第29回)について
-
1.諮問書
2.答申書
3.訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化について
4.支給限度額の一本化についての改正事項の概要
5.介護保険制度の定着に向けた改善方策について
6.介護保険制度の最近の動きについて
7.参考
8.医療保険福祉審議会 老人保健福祉部会・介護給付費合同部会(第28回)議事要旨
厚生省発老第139号
平成12年10月31日
医療保険福祉審議会
老人保健福祉部会長 井形 昭弘 殿
医療保険福祉審議会
介護給付費部会長 星野 進保 殿
厚生大臣 津島 雄二
諮 問 書
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)及び居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年2月厚生省告示第33号)の一部を別添要綱のとおり改正することについて、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条、第41条第5項、第43条第6項、第55条第6項及び第81条第3項の規定に基づき、貴会の意見を求めます。
(別添)
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令案等要綱
第1 介護保険法施行規則の一部改正(省令)
(1)訪問通所サービス区分(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与(以下「訪問通所サービス」という。)からなる従来の居宅サービス区分。以下「旧訪問通所サービス区分」という。)と短期入所サービス区分(短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)からなる従来の居宅サービス区分。以下「旧短期入所サービス区分」という。)の2つの居宅サービス区分を1つの区分に統合すること。
(2)(1)により統合された居宅サービス区分(以下「新居宅サービス区分」という。)に係る区分支給限度額管理期間は、1か月間(歴月単位)とすること。
(3)新居宅サービス区分に係る区分支給限度基準額は、月途中で要介護状態区分等の変更があった場合においては、変更の前後で程度の重いものに応じた区分支給限度基準額により算定すること。
(4)要介護認定等の更新又は変更認定の申請の際に、当該申請が行われた月の3か月前の月及びその前月のそれぞれにおいて、当該申請に係る被保険者に支給された旧訪問通所サービス区分に係る保険給付額の総額が旧訪問通所サービスに係る区分支給限度基準額の9割に6割を乗じて得た単位数に満たない場合等に当該認定に係る旧短期入所サービス区分に係る支給限度額を拡大する措置を、廃止すること。
(5)種類支給限度基準額を設定できる居宅サービスの種類に、短期入所サービスを追加すること。
(6)その他所要の改正を行うこと。
(7)この省令は平成14年1月1日から施行すること。
第2 居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額の一部改正(告示)
(1)新居宅サービス区分に係る区分支給限度基準額を次のとおりとすること。
| (1) 要支援 |
6,150単位 |
| (2) 要介護1 |
16,580単位 |
| (3) 要介護2 |
19,480単位 |
| (4) 要介護3 |
26,750単位 |
| (5) 要介護4 |
30,600単位 |
| (6) 要介護5 |
35,830単位 |
(2)(1)の規定が施行されるまでの間、短期入所サービスを利用する日数の合計が通常の旧短期入所サービス区分に係る区分支給限度基準額法定限度額の日数(以下「法定限度日数」という。)に至った月(以下「超過月」という。)以後の各月において、旧訪問通所サービス区分に係る区分支給限度基準額から現に利用した旧訪問通所サービスの単位数の合計を控除して得た単位数を次に掲げる要介護状態区分等に応じてそれぞれ次に掲げる単位数で除して得た日数(以下「振替日数」という。)を、旧短期入所サービス区分に係る区分支給限度基準額に加えることができる特例措置について、振替日数を算定する際に、1日未満の端数を生じた場合にはこれを切り捨てることとするとともに、振替日数が超過月において旧訪問通所サービス区分に係る区分支給限度基準額を次に掲げる要介護状態区分等に応じてそれぞれ次に掲げる単位数で除して得た日数から法定限度日数内の短期入所サービスを利用する日数を控除して得た日数を超えるときは当該控除して得た日数とすること。
| (1) 要支援 |
954単位 |
| (2) 要介護1 |
984単位 |
| (3) 要介護2 |
1,032単位 |
| (4) 要介護3 |
1,079単位 |
| (5) 要介護4 |
1,126単位 |
| (6) 要介護5 |
1,173単位 |
(3)振替日数を算定する月の前月から連続して短期入所サービスを利用する場合において振替日数を算定する際には、(2)にかかわらず、当該利用に係る利用日数の合計が30日を超えるときは30日から前月における当該利用に係る利用日数を控除して得た日数とすること。
(4)この告示は、(1)に係る改正規定は平成14年1月1日から施行し、(2)及び(3)に係る改正規定は平成13年1月1日から施行すること。
第3 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正(告示)
(1)連続して30日を超える短期入所サービスについては、短期入所生活介護費及び短期入所療養介護費は、算定しないこととすること。
(2)この告示は平成14年1月1日から施行すること。
第4 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正(省令)
(1)指定居宅介護支援の具体的取扱方針に、介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意するものとし、要介護認定等の有効期間における短期入所サービスの利用日数が要介護認定等の有効期間の概ね半数を超えないようにしなければならない旨を追加すること。
(2)この省令は平成13年1月1日から施行すること。
平成12年10月31日
厚生大臣 津島 雄二 殿
医療保険福祉審議会
老人保健福祉部会長 井形 昭弘
医療保険福祉審議会
介護給付費部会長 星野 進保
答 申 書
平成12年10月31日厚生省発老第139号をもって諮問のあった、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)及び居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年2月厚生省告示第33号)の一部改正については、これを了承する。
なお、一本化に伴う市町村等のシステム改修に要する費用については、過重な負担とならないよう、国において十分な配慮を行うこと。
訪問通所サービスと短期入所サービスの
支給限度額の一本化について
1.支給限度額の一本化について
訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額については、利用者の選択性・利便性の向上の観点から、一本化を図ることについて、本年7月24日の合同部会でご審議をいただいたところ。
(1)支給限度額の一本化の趣旨
- (1) 支給限度額の一本化により、支給限度額内のサービス利用の選択性・利便性を高める。
- (2) 支給限度額の管理方法を簡素化して、わかりやすくする。
- (3) 在宅生活を維持する上で、本来の短期入所サービスの利用枠に加えて、短期入所サービスの利用の拡大が必要な者については、振り替え利用を可能としているが、制度的に現物給付化することで、利用手続きを簡素化して、利用しやすくする。
(2)内容(案)
- (1)訪問通所サービスと短期入所サービスを統合した区分とし、支給限度額管理の期間を月単位(暦月)とする。
- (2) 支給限度額管理の方法は、サービスの単位数による方法に統一する。
- (3) 支給限度額の水準は、現行の訪問通所サービスの支給限度額で既に各月の標準的な短期入所サービスの利用を見込んでいることから、現行の訪問通所サービスの支給限度額とする。
ただし、短期入所療養介護に特有な出来高的医療部分である緊急時施設療養費及び特定診療費については、支給限度額管理の対象外の費用とする。
- (4) 次期要介護認定期間の3ヶ月及び4ヶ月前の訪問通所サービスに係る保険給付実績が利用が訪問通所サービスの支給限度額の6割未満である場合に、短期入所サービスの利用枠を拡大(要支援〜要介護4 2倍、要介護5 1.5倍)する措置(いわゆる「次期拡大措置」)については、支給限度額を短期入所サービスを含めて月単位に統合することを踏まえ、廃止する。
- (5) 施設入所と変わらない短期入所の利用を防止するとともに、他の利用者の短期入所サービスの利用を確保するため、短期入所サービスの連続した利用は、30日間までを報酬算定の限度とする。
- (6) 連続して30日を超えない利用であっても、短期入所サービスは在宅生活を継続していく上で利用するサービスであることを踏まえ、居宅介護支援事業者の運営基準上、介護支援専門員のケアプラン作成に当たって、要介護認定期間中の短期入所サービスの利用日数はその概ね半数を超えないようにするといった歯止めを設け、指導することとする。
(2)移行スケジュール等について
一本化後の支給限度額管理を行うための、市町村や国保連、事業者のシステム変更・テスト期間や準備時期等を考慮して、平成14年1月から、新支給限度額を適用する。
2.支給限度額一本化までの対応について
(1)平成14年1月からの一本化を実施までの間においても、短期入所サービスの利用枠の拡大が必要な利用者に対して、利用しやすい形で需要に応えるため、受領委任方式により、振り替え利用を実施するよう、市町村に周知徹底を図っているところ。
※ 「振り替え利用」…痴呆や同居家族が高齢・疾病であることなどにより短期入所サービスを拡大して受けなければ在宅介護の継続が困難である者について、本来のショートステイの利用枠を使い切った後に、訪問通所サービスの支給限度の利用可能な枠の範囲で、短期入所サービスに振り替え利用するもの。
(2)この振り替え利用については、短期入所サービスの本来の支給限度額 を含めて、1月当たり2週間を限度としているところであるが、サービスの選択性の向上という観点から、一本化までの間においても、市町村の判断で、この限度を拡大し、訪問通所サービスの利用枠の範囲内であれば、30日まで短期入所サービスに振り替え利用できるようにする。
(実質的な支給限度額の一本化の前倒し)
(参考)
介護保険制度の定着へ向けた改善方策について(抄)
(平成12年9月27日 自由民主党・公明党・保守党)
2.ショートステイについて
(1)支給限度額の一本化の早急な実現
- 支給限度額の一本化の早急な実現を図る。また、それまでの措置として、訪問通所サービスのショートステイへの「振り替え利用」枠を2週間から30日に拡大するなど、一本化後と同等の水準で利用できるようにする。
|
(3)上記措置を実施するために、今回、あわせて、支給限度額一本化までの措置として、振り替え措置に係る支給限度額告示の改正を行う。
(4)この措置は、支給限度額の一本化後と同様、
- ア振り替え措置を行う場合、連続した短期入所サービスの利用は30日まで、
イ居宅介護支援事業者のケアプラン作成に当たって、要介護認定期間中の短期入所サービスの利用日がその概ね半数を超えないようにするといった歯止めを設けた上で行う。
(5)この措置は、平成13年1月から適用する。
I 支給限度額の一本化についての改正事項の概要
1 介護保険法施行規則及び関連告示の改正
(1)居宅サービス区分
-
(現行)
| 訪問通所サービス区分 |
(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与)と |
短期入所サービス区分
の2区分 |
(短期入所生活介護、短期入所療養介護) |
(改正後)
上記のサービスを一区分とする。
(2)区分支給限度額管理期間
-
(現行)
| 訪問通所サービス区分… |
1ヶ月(暦月単位) |
| 短期入所サービス区分… |
原則6ヶ月
(暦月単位、※要介護認定の有効期間に対応) |
(改正後)
1ヶ月(暦月)に統一
(3)区分支給限度額の上限の算定方法
-
(現行)
要介護認定期間中に要介護状態区分が変更された場合は、訪問通所サービスは、変更月の重い方の要介護状態区分に応じた支給限度額を適用し、短期入所サービスは、認定の効力が生じた月の翌月から新たな支給限度額を適用する。
(改正後)
短期入所サービスも、訪問通所サービスと同様、要介護認定期間中に要介護状態区分が変更された場合は、変更月の重い方の要介護状態区分に応じた支給限度額を適用する。
(4)次期拡大措置
-
(現行)
訪問通所サービスの利用が少ない場合の次の要介護認定期間の短期入所サービスの支給限度額の拡大措置がある。
(改正後)
支給限度額の一本化に伴い、短期入所サービスもその月の支給限度額 の範囲で利用できるようになることや、制度の簡素化の要請を踏まえ、次期拡大措置を廃止する。
(5)支給限度額管理の対象外となる費用
-
(現行)
(1)訪問介護の特別地域加算 (2)訪問入浴介護の特別地域加算 (3)訪問看護の特別地域加算 (4) 訪問看護のターミナルケアに係る加算 (5) 福祉用具貸与の特別地域加算
(改正後)
上記費用のほか、
短期入所療養介護の緊急時施設療養費(介護老人保健施設)及び特定診療費(療養型病床群を有する病院・診療所、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院、介護力強化病院)を追加
(6)種類支給限度基準額を設定できるサービス
- (現行)
訪問通所サービス区分に属するサービス
(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与)
- (改正後)
上記のサービスのほか短期入所生活介護、短期入所療養介護を追加
(7)その他
支給限度額の一本化に伴い、被保険者証の様式の一部が改正されるが、既に交付されている従前の様式による被保険者証も有効とする経過措置を設ける。
2 居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(告示)の改正
- (現行)
| |
訪問通所サービス |
短期入所サービス ※ |
| 要支援 |
6,150単位/月 |
7日(1週間)/6月 |
| 要介護1 |
16,580単位/月 |
14日(2週間)/6月 |
| 要介護2 |
19,480単位/月 |
14日(2週間)/6月 |
| 要介護3 |
26,750単位/月 |
21日(3週間)/6月 |
| 要介護4 |
30,600単位/月 |
21日(3週間)/6月 |
| 要介護5 |
35,830単位/月 |
42日(6週間)/6月 |
※ 要介護認定期間が6ヶ月以外の場合は、その月数に比例した日数
(改正後)
| |
居宅サービス区分 |
| 要支援 |
6,150単位/月 |
| 要介護1 |
16,580単位/月 |
| 要介護2 |
19,480単位/月 |
| 要介護3 |
26,750単位/月 |
| 要介護4 |
30,600単位/月 |
| 要介護5 |
35,830単位/月 |
3 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(告示)の改正
連続して30日を超えて利用される短期入所生活介護費及び短期入所療養介護費は、算定しないこととする。
4 指定居宅介護支援事業者等の事業の人員及び運営に関する基準(省令)の改正
指定居宅介護支援の具体的取り扱い方針に以下の規定を追加する。
「介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置づける場合には、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意するものとし、これらのサービスの利用日数が、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えることとならないようにしなければならない。」
5 施行期日
平成14年1月1日(4の改正は、平成13年1月)
II 支給限度額一本化までの振り替え措置の弾力化について
(趣旨)
支給限度額の一本化までの間においても、市町村の判断で、振り替え措置を弾力化して、短期入所サービスを一本化後と同等の水準で利用できるようにする。
(内容)
1 現行の振り替え措置に代えて、以下の措置を市町村が実施できるように支給限度額告示を改正
(1)振り替え措置を実施する市町村において、振り替え措置の対象となる居宅要介護被保険者に係る短期入所サービスの支給限度額については、各月の訪問通所サービスの区分支給限度額の未利用分の範囲内の単位数を、以下の単位
数で除して得た額(1日未満は切り捨て)とすることができることとする。
| イ 要介護1 |
984単位 |
|
ロ 要介護2 |
1,032単位 |
| ハ 要介護3 |
1,079単位 |
二 要介護4 |
1,126単位 |
| ホ 要介護5 |
1,173単位 |
|
(注)現行は、振り替え利用を行った月は、本来分の支給限度額の利用日数を含めて、各月2週間を限度としているが、この制限をなくし、本来の支給限度額とあわせて、振り替え利用により、最大で以下の短期入所サービスの利用が可能となる。
| 要介護度 |
振り替え利用を行う月の短期入所サービスの最大利用日数 |
| 要介護1 |
16日/月 |
(16,580単位 ÷ 984単位) |
| 要介護2 |
18日/月 |
(19,480単位 ÷1,032単位) |
| 要介護3 |
24日/月 |
(26,750単位 ÷1,079単位) |
| 要介護4 |
27日/月 |
(30,600単位 ÷1,126単位) |
| 要介護5 |
30日/月 |
(35,830単位 ÷1,173単位) |
(2)上記措置は、支給限度額の一本化後と同様、
- (1)振り替え措置を行う場合、連続した短期入所サービスの利用は30日まで、
- (2)居宅介護支援事業者のケアプラン作成に当たって、要介護認定期間中の短期入所サービスの利用日がその概ね半数を超えないようにするといった歯止めを設けた上で行う。
2 施行期日 平成13年1月
(参考資料)
(参考1)
支給限度額の一本化のイメージ
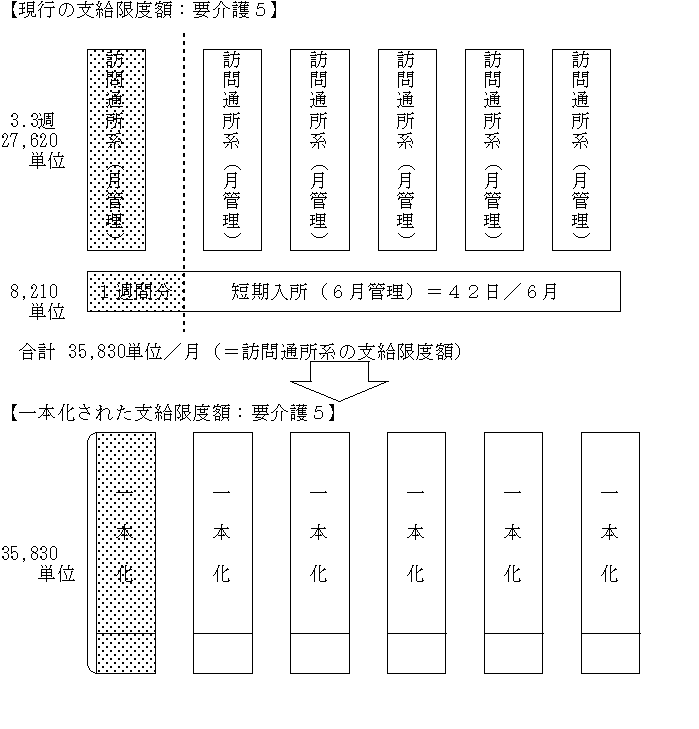
※ 短期入所サービスの利用が施設入所の助長につながらないように、
(1)短期入所サービスの連続した利用は30日まで、
(2)短期入所サービスは6か月でそのおおむね半数を超えないようにすといった歯止めを設けつつ、ひと月に短期入所サービスをどの程度利用するかは、利用者の選択に委ねる。
●一本化後の支給限度額をもとに短期入所サービスのみ利用した場合/1月
| |
要支援 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
| 利用可能日数/月 |
6.4日 |
16.8日 |
18.8日 |
24.1日 |
27.1日 |
30日 |
(注)短期入所サービスのうち、平均的なサービス単価をもとに算出。
(参考2)
今後の支給限度額一本化までのスケジュール
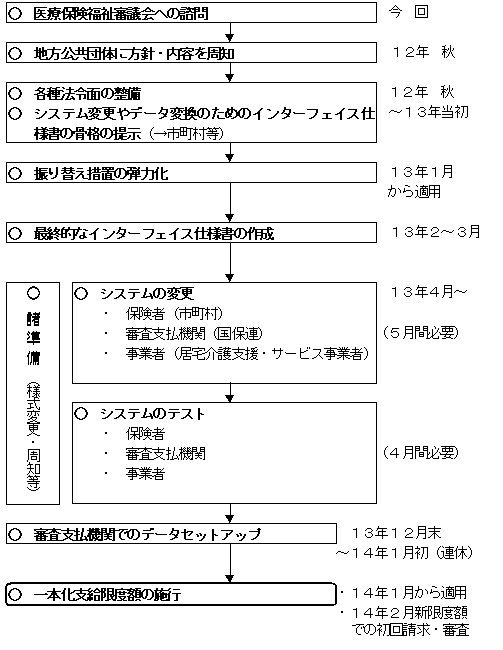
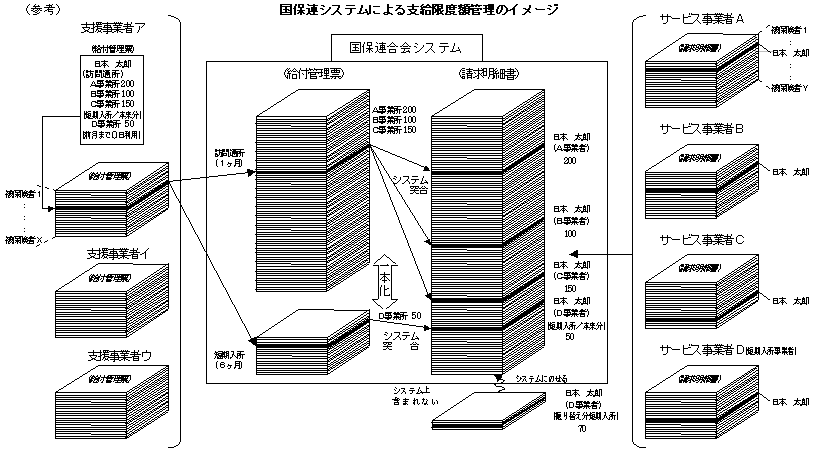
(1) 審査支払では、被保険者ごとに給付管理票と請求明細書情報を区別してサービスの受給状況を名寄せして突合し、複数事業所の複数のサービスの利用が支給限度額の範囲内にあるかどうかの処理を行う必要がある。この処理を大量かつ支払時期に間に合うように行うためには、システム処理することが不可欠。
- (参考)東京都の7月審査分受付件数:給付管理票 14万件 請求明細書 44万件
(2) 現在、振り替え分短期入所はシステム処理されていないが、支給限度額の一本化により、他のサービスを含めて給付管理票情報と突合して、支給限度額内のサービスであるかどうかをシステム処理することとなる。
(3) 国保連ではなく、市町村で審査支払業務を行うこととした場合には、事業者が所在地の国保連に送っていた給付管理票・請求明細書を被保険者ごと保険者別に仕分けして送付する必要があるとともに、市町村においても(1)で述べた業務を行うための独自のシステムの開発等が必要となる。
(参考4)
介護保険制度施行直前のショートスティに関する
利用者の意見と利用状況について
(1)施行直前のショートスティに関する利用者の意見
厚生省では、介護保険制度施行前に、「介護保険:御意見大募集」と題して、広く国民から介護保険制度に関する意見等を募集したところ、ショートスティに関するものが最多であった。
(主な要望の内容)
○訪問・通所サービス区分、短期入所サービス区分ごとの利用枠の上限を撤廃し、特にショートスティについて各要介護度の枠内で介護サービスの各メニューの組み合わせが自己の状況に応じて選択できるようにしてほしい。
(2)ショートスティ利用者の他のサービス利用状況について
ショートスティに関する意見が多数寄せられたことから、厚生省でショートスティの利用状況を全国の複数の市町村に対して行った緊急調査結果によると、ショートスティを多く利用している者(全90事例)は、ショートスティのみを利用する者が大半であり、他のサービスの利用は少なかった。
ショートスティ以外のサービスを利用していない者の割合
| 訪問介護 |
訪問看護 |
訪問入浴 |
通所介護 |
通所リハビリ |
| 69% |
84% |
99% |
33% |
79% |
(注)通所介護については、約2/3が利用していたが、このうち2/3が週1回の利用であった
介護保険制度の定着へ向けた改善方策について
平成12年9月27日
自由民主党
公 明 党
保 守 党
自由民主党・公明党・保守党の与党3党は、施行後半年を迎えた介護保険制度が国民の間に定着し、より信頼されるものとなるよう下記のとおり、改善方策を取りまとめ合意した。
1.訪問介護のあり方について
(1)現在の利用状況
介護保険による訪問介護の給付は身体介護(1時間単価4020円)、家事援助(1時間単価1530円)及び両者の複合型(1時間単価2780円)の3類型で行われている。
訪問介護の平成12年7月の実際の利用状況をみると、3類型のうち、身体介護約46%、家事援助約34%、複合型約20%となっている。家事援助のうち、高齢者以外の同居者がいる世帯の利用は約25%であり、訪問介護全体における比率は、8.5%である。
(2)保険給付として適切な範囲を逸脱した家事援助の是正
しかしながら、保険給付としては適切な範囲を超える家事援助の提供例(別紙参照)もある。保険の受給権が濫用されれば、被保険者の制度への信頼を損なうことにつながるおそれがあるので、基本的には制度実施者である市町村の裁量に委ねるべきではあるが、国も、次のような措置を実施する必要がある。
- (1) 保険給付として適切な範囲の周知徹底
- 国において、保険給付としての家事援助の範囲を明らかにした訪問介護の適正な利用に関するリーフレット等を作成し、広く利用者、ケアマネジャー等に配布する。
- (2) ケアプランに家事援助の必要な理由の記載
- ケアプランに家事援助を必要とする理由を記載するように改め、保険者(市町村)が保険給付としての適否を確認しやすくする。
- (3) ケアマネジャーへの研修
- ケアマネジャーの研修プログラムに、家事援助の適切な提供に関する内容を盛り込む。
(3)「身体介護」の利用の促進
様々な理由により、訪問介護の中核となるべき身体介護の利用を受給権者がためらっている状況もうかがえるので、次のような方策を講じ、身体介護の利用を促進し、その比率を高めるべきである。
- (1) 利用者が身体介護を受けやすくなるような情報の提供を充実する。
- (2) 訪問介護事業に対する規制緩和を行い、身体介護の事業に特化できるような途を開く。
(4)他の社会資源の活用
介護保険の適用を受けないサービスについては、例えば、シルバー人材センター、市町村の一般行政施策、NPOなど、他の社会資源の活用を進める。また、こうした活用が進むように、ケアマネジャーに対する研修を充実させる。
2.ショートステイについて
- (1) 支給限度額の一本化の早急な実現
- 支給限度額の一本化の早急な実現を図る。また、それまでの措置として、訪問通所サービスのショートステイへの「振り替え利用」枠を2週間から30日に拡大するなど、一本化後と同等の水準で利用できるようにする。
- (2) ショートステイ床の弾力活用
- ショートステイ床については、概ね5割まで特別養護老人ホーム床に転換できるようにするとともに、一時的に特別養護老人ホーム床として活用できるようにする。
3.低所得者対策について
低所得者の利用料負担については、既に、負担月額上限の特例や訪問介護利用者の経過的軽減措置などが実施されている。
さらに、個々の利用者の状況に応じ社会福祉法人が利用者負担を原則として1/2に軽減する措置が講じられているが、全国的に十分には浸透していない状況にあることから、この措置について次の取り組みを行う。
- (1) 全国的な実施の推進
- この措置が全国的に実施されるようにする。また、市町村における利用相談窓口の設置など利用しやすい体制の整備を促進する。
- (2) 対象となる低所得者の範囲の拡大
- 市町村が、地域の実情を踏まえ、第1号被保険者の1割程度までこの措置の対象とすることができるようにする。
- (3) 社会福祉法人に対する協力要請
- 社会福祉法人に対し、その社会的役割にかんがみ、軽減措置に積極的に取り組むよう要請する。
4.介護基盤の整備について
- (1) 介護施設の整備
- 特別養護老人ホームなどに長期間待つことなく入所できるよう、介護施設の整備を急ぐ。また、単独型の痴呆性高齢者グループホームや民家や民間宿泊施設等を改造したデイサービスセンターといった小規模な施設の整備を推進する。
- (2) 介護予防拠点の整備
- 生きがい対応型デイサービスや介護予防教室などの介護予防事業の活動拠点について、今年度補正予算により整備を推進する。
- (3)「老いの住まい」づくり
- 高齢者が要介護状態になっても、できる限り自宅や住み慣れた地域で老後生活が継続できるよう、居住環境の整備や地域の生活支援体制づくりを推進する。
5.ケアマネジャーの資質の向上等について
- (1) 事務負担軽減・資質向上
- ケアマネジャーの事務負担の軽減を進めるとともに、現任研修等の実施によって資質の向上を図る。
- (2) ショートステイ振り替え業務等の支援
- 訪問通所サービスのショートステイへの振り替え措置に関する業務等について、現在介護報酬の支払いの対象となっていないので、必要な支援策を講ずる。
- (3) 市町村等による業務支援
- 市町村や都道府県において、ケアマネジャー支援相談窓口の設置や情報交換の場づくりなどといったケアマネジャーの支援体制を整備するよう、周知徹底を図る。
6.その他
上記の各事項のほか、次の事項についても適切に対応していく。
- (1) 国保連の審査支払事務の支援
- 国保連のコンピュータの機能強化など審査支払事務の向上を図るための支援措置を講じる。
- (2) 個人の尊厳に対する配慮と介護サービスの質の向上
- 介護保険事業従事者の守秘義務の徹底など利用者の個人としての尊厳に十分に配慮するとともに、介護サービスの質の向上を図るための施策を充実する。
- (3) 制度の積極的PRの推進
- 高齢者の保険料負担がなぜ必要であるか、介護保険制度のメリットは何であるかなどがわかるよう、制度の積極的なPRを推進する。
- (4) 介護保険施設の保険外負担の取扱い
- 介護保険施設の保険外負担については、施設に対して、利用者から負担を求めることができる費用の範囲を周知徹底するとともに、各施設において保険外負担の実際の取扱いに関する情報の提供を推進する。
7.今後における検討
与党介護保険に関するプロジェクトチームは、今後の制度の実施状況を見ながら、本制度の適切かつ円滑な実施が図られるよう引き続き検討を行うものとする。
(別紙)
一般的には介護保険の家事援助の範囲に含まれないと
考えられる事例
A「直接本人の援助」に該当しない行為
| 主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 |
- a.利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
b.主として利用者が使用する居室等以外の掃除
c.来客の応接(お茶、食事の手配等)
d.自家用車の洗車・清掃
等
B「日常生活の援助」に該当しない行為
| 1 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為 |
- a.草むしり
b.花木の水やり
c.犬の散歩等ペットの世話
等
- a.家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
b.大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
c.室内外家屋の修理、ペンキ塗り
d.植木の剪定等の園芸
e.正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理
等
介護給付費支払状況(暫定集計値)
(単位:億円)
| 区分 |
5月審査分 |
6月審査分 |
7月審査分 |
5〜7月審査分計 |
| 在宅サービス |
600 |
820 |
960 |
2,380 |
| 施設サービス |
1,540 |
1,900 |
1,980 |
5,430 |
| 小計 |
2,140 |
2,720 |
2,940 |
7,810 |
| |
| 支払特例分 |
280 |
140 |
90 |
520 |
| 支払特例精算分 |
− |
△90 |
△170 |
△260 |
| 合計 |
2,420 |
2,780 |
2,870 |
8,070 |
| (注) |
1.各都道府県国民健康保険団体連合会が、サービス事業者に支払った金額を集計したもの。 |
| 2.利用者負担を除く介護給付費(9割)ベースである。 |
| 3.福祉用具購入費、住宅改修費など市町村が利用者に直接支払う費用は除く。 |
| 4.審査分は、国保連が審査を行った月で表示しており、例えば5月審査分であれば4月サービス提供分である。 |
| 5.支払特例分は、請求額の一部を特例の扱いとして概算払で支払ったものであり、支払特例精算分は、概算払分を翌月以降精算したものである。 |
| 6.数値は、10億円未満四捨五入のため、計に一致しない。 |
(単位:億円)
| 種 類 |
5月審査分 |
6月審査分 |
7月審査分 |
5〜7月分計 |
| 訪問通所サービス(小計) |
465 |
639 |
768 |
1,873 |
| |
11訪問介護 |
98 |
157 |
200 |
455 |
| 12訪問入浴介護 |
17 |
27 |
31 |
75 |
| 13訪問看護 |
48 |
65 |
81 |
194 |
| 14訪問リハビリテーション |
1 |
2 |
3 |
6 |
| 15通所介護 |
158 |
207 |
237 |
602 |
| 16通所リハビリテーション |
138 |
169 |
199 |
505 |
| 17福祉用具貸与 |
4 |
12 |
19 |
35 |
| 短期入所サービス(小計) |
50 |
67 |
63 |
180 |
|
21短期入所生活介護 |
39 |
50 |
47 |
135 |
| 22短期入所療養介護(老健) |
11 |
16 |
15 |
42 |
| 23短期入所療養介護(病院等) |
1 |
1 |
1 |
3 |
| その他の単品サービス(小計) |
20 |
31 |
36 |
87 |
|
31居宅療養管理指導 |
7 |
11 |
12 |
30 |
| 32痴呆対応型共同生活介護 |
5 |
8 |
9 |
22 |
| 33特定施設入所者生活介護 |
7 |
13 |
15 |
35 |
| 43居宅介護支援 |
68 |
82 |
93 |
243 |
| 在宅サービス計 |
602 |
820 |
960 |
2,382 |
| 施設介護サービス計 |
1,539 |
1,904 |
1,984 |
5,427 |
|
51介護老人福祉施設 |
733 |
877 |
899 |
2,508 |
| 52介護老人保健施設 |
530 |
640 |
659 |
1,830 |
| 53介護療養型医療施設 |
276 |
387 |
426 |
1,089 |
| 食事提供費用(再掲) |
218 |
266 |
279 |
764 |
| |
51介護老人福祉施設 |
115 |
137 |
141 |
393 |
| 52介護老人保健施設 |
71 |
85 |
89 |
245 |
| 53介護療養型医療施設 |
32 |
44 |
49 |
126 |
| 合 計 |
2,141 |
2,724 |
2,944 |
7,809 |
(注)数値は、億円未満四捨五入のため、計に一致しない。
介護保険の在宅サービスの利用状況について
平成12年10月
1.支給限度額に対するサービス利用量について
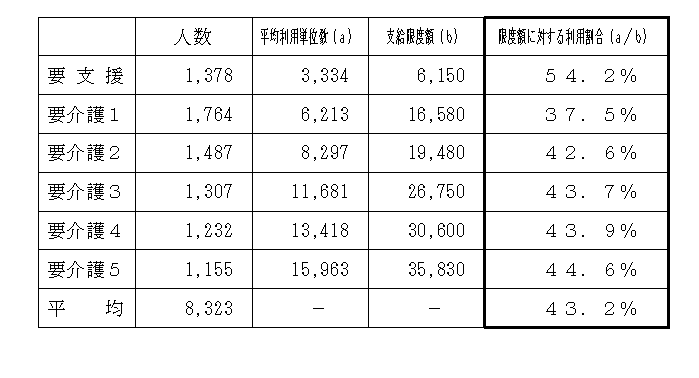
| 注1 |
106保険者(定点市町村)8,323人についての調査
(ケアプラン無作為抽出方式。原則として平成12年7月サービス分の調査) |
| 注2 |
「平均利用単位数」は、訪問通所サービスと短期入所サービスの合計の平均 |
※ 支給限度額に対する利用割合について
- (1) 支給限度額は、在宅介護の重視を基本理念として、現在のサービス水準をかなり上回る水準で設定されている。
- (2) 実際の利用割合は、本人の希望やサービスの供給量によって決まってくるものであり、今後の制度の定着状況やサービス供給量の増加によって、将来的に増えていくと見込んでいる。
- (3) 平成12年度予算上の見込みでは、サービスを全く利用しない人も含め支給限度額に対する利用割合を約33%としている。
- これに対し、上記の43.2%は実際にサービスを利用している人の調査であるため、それらを勘案すると、当初の見込みを若干上回っているものと推定される。
2.介護保険実施によるサービス量の変化(平成12年3月と7月を比較)
-
| |
サービス量が増加 |
ほぼ同じ |
サービス量が減少 |
| 合 計 |
852(67.5%) |
187(14.8%) |
224(17.7%) |
| 要支援 |
111(52.9%) |
42(20.0%) |
57(27.1%) |
| 要介護1 |
145(67.8%) |
30(14.0%) |
39(18.2%) |
| 要介護2 |
148(70.1%) |
38(18.0%) |
25(11.8%) |
| 要介護3 |
143(68.8%) |
24(11.5%) |
41(19.7%) |
| 要介護4 |
156(73.9%) |
30(14.2%) |
25(11.8%) |
| 要介護5 |
149(71.3%) |
23(11.0%) |
37(17.7%) |
注 108保険者(定点市町村)1,263人についての調査 (単位:人)
(参考)介護サービス量が減った理由
(「減った」と回答した224人についての調査:複数回答あり:単位(人))
-
| 理 由 |
人数 |
割合 |
全体割合 |
| (1) これまで受けていたサービスが現在の利用限度額を超えていたため |
25 |
11.0% |
2.0% |
| (2) 短期入所を緊急時のための取っておくため |
11 |
4.9% |
0.9% |
| (3) サービス事業者が予約でいっぱいだったため |
2 |
0.9% |
0.2% |
| (4) 家族との同居等により、これまでほどはサービスが必要でないため |
10 |
4.5% |
0.8% |
| (5) 利用者負担を支払うのが困難だったため |
32 |
14.3% |
2.5% |
| (6) 利用者負担は支払えるが、従来受けていたサービスが必ずしもすべて真に必要なサービスではないと考えたため |
35 |
15.6% |
2.8% |
| (7) その他(本人の状態の回復、入院のためなど) |
40 |
17.9% |
3.2% |
| (8) 回答なし |
81 |
36.2% |
6.4% |
注 「割合」はサービスが減った人に対する割合、「全体割合」は調査対象全体に対する割合
介護保険サービス選択のための評価の
在り方に関する検討会の開催について
1 趣 旨
○ 本年4月から実施されている介護保険制度においては、行政が個々人への介護サービスの内容を決定していた従来の措置制度から、要介護認定等を受けた者が自ら介護サービスの内容を選択・決定する契約制度へと大きく転換した。
○ このような状況において、数ある介護サービス事業所の中から、利用者が自らのニーズに合致した事業所を適切に選択できるよう、利用者の選択に役立つ事業所の評価の手法等を検討することを目的として、「介護保険サービス選択のための評価の在り方に関する検討会」を開催するものである。
2 検討事項
検討会においては、次の事項について検討を行うものとする。
- (1) 「利用者の選択」という視点からの評価手法について
- (2) 評価の指標等について
3 検討会の組織
- ・検討会委員は、別紙のとおりとする。
- ・検討会の庶務は、厚生省老人保健福祉局において処理する。
4 検討スケジュール
- ・11月2日 第1回検討会開催(予定)
- ・以後月1回程度を目途に開催を予定
介護保険サービス選択のための評価の在り方に関する検討会
メンバー表
| 岩村正彦 |
(東京大学法学部教授) |
| 上野桂子 |
(聖隷福祉事業団訪問看護ステーション担当部長) |
| 岡本祐三 |
(神戸市看護大学教授) |
| 木間昭子 |
(国民生活センター主任研究員) |
| 柴田範子 |
(上智社会福祉専門学校専任教員) |
| 田中 滋 |
(慶応義塾大学教授) |
| 永島光枝 |
(呆け老人をかかえる家族の会理事) |
| 野中 博 |
(野中医院 医院長) |
| 橋本正明 |
(立教大学教授、至誠ホーム長) |
| 牟田悌三 |
(俳優、世田谷ボランティア協会理事長) |
(敬称略)
要介護認定調査検討会設置要綱
平成12年8月11日
1 設置目的
要介護認定における一次判定の仕組みについて、専門的・技術的検討を行うことを目的として、要介護認定調査検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
2 組織等
(1) 検討会の委員は学識経験者のうちから厚生省老人保健福祉局長が委嘱する。
(2) 委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。委員長は検討会を総理する。
(3) 検討会の庶務は、厚生省老人保健福祉局老人保健課において行う。
3 検討事項
(1) 現在の要介護認定における一次判定の仕組みに係る技術的検討
(2) 介護の手間を反映する指標についての技術的検討
- ア 最近における高齢者介護の実態把握の方法の検討(施設と在宅の両者を含む。)
- イ 高齢者の心身の状況の把握方法の検討
- ウ アとイのうち、特に痴呆の有無に応じた検討
- エ 上記ア〜ウを踏まえた統計・分析手法の検討
(3) 上記(1)及び(2)を踏まえた一次判定の仕組みに関する技術的検討
- ア 認定調査項目の検討
- イ 痴呆の有無に応じた判定のあり方の検討
- ウ 施設と在宅の両者を含めた分析手法の検討
- エ 要介護認定等基準時間の設定に関する技術的検討
4 検討会の運営等
(1) 参考人の招致
委員長は、討議の必要に応じ、適当と認められる有識者等を、参考人として招致することができるものとする。
(2) 審議の公開
審議は、原則として非公開とする。
要介護認定調査検討会名簿
| 今井 幸充 |
聖マリアンナ医科大学東横病院精神科部長 |
| 遠藤 英俊 |
国立中部病院内科医長 |
| 大内 東 |
北海道大学工学部教授 |
| 太田 喜久子 |
宮城大学看護学部教授 |
| 開原 成允 |
医療情報システム開発センター理事長 |
| 加藤 伸司 |
北海道医療大学看護福祉学部助教授 |
| 関 庸一 |
群馬大学工学部助教授 |
| 高木 安雄 |
日本福祉大学経済学部教授 |
| 鳥羽 研二 |
杏林大学医学部教授 |
| 内藤 佳津雄 |
日本大学文理学部専任講師 |
| 村川 浩一 |
日本社会事業大学社会福祉学部教授 |
| 村嶋 幸代 |
東京大学医学部助教授 |
(五十音順、敬称略)
参 考 人 一 覧
| 池上 直己 |
慶應義塾大学教授 |
| 岡本 祐三 |
神戸市看護大学教授 |
| 川越 雅弘 |
日医総研主任研究員 |
| 齊藤 正身 |
霞ヶ関南病院院長 |
| 田部井 康夫 |
デイみさと施設長 |
| 時田 純 |
潤生園園長 |
| 山田 和彦 |
医療法人社団健成会理事長 |
| 横田 喜久恵 |
新宿訪問看護ステーション管理者 |
(五十音順、敬称略)
要介護認定調査検討会論点整理メモ
〈 現在指摘されている主な問題点 〉
○ 痴呆性高齢者の要介護度が、実際に要する介護の必要性と比べて低く評価されているのではないか。
○ 在宅の高齢者について算出される要介護認定等基準時間は実際の在宅ケアの状況を十分に反映していないのではないか。
1 痴呆及び在宅の調査について
- (1) 痴呆
- ○ 痴呆の認定の基礎データとするにはどのような調査(調査施設、調査対象者等)を行うべきか。
- ○ 痴呆性高齢者に対するケアの実態を把握するためには、どのような「高齢者の状態に関する調査」の項目及び提供されるケアの内容に関する「ケアコード(T.C.C.等)」を設定したら良いのか。
- (2) 在宅
- ○ 調査対象とする在宅ケアの範囲、提供者の範囲等についてどう考えるか。
- ○ 在宅用のケアコードを作ることは可能か。
- ○ 環境上の要因(手すりの有無など)の影響をどのように考えるか。
2 本年度実施の実態調査全般(「1」の論点を含む)について
○ 実態調査における調査項目をどのように設定するか。
- 1) 高齢者の状態に関する調査の項目
- 2) ケアコード
- 3) 医療関連行為
○精神的・身体的負担感を測定することは可能か。
○ どのような施設等で調査を行うのか。
○ 樹形モデル等の分析手法の観点から調査方法について注意すべき点は何か。
平成13年度老人保健福祉関係予算概算要求の概要
平成12年8月25日
−老人保健福祉局−
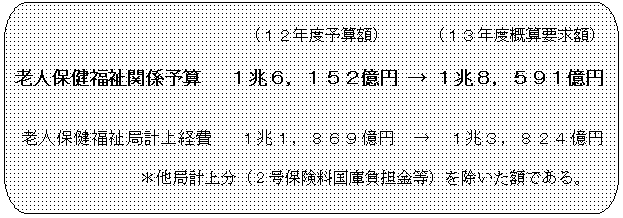
【主要事項】
| I 介護給付に対する国の負担等 |
(13’要求額)
1兆5,187億円 |
|
1.介護給付費負担金
9,071億円
各市町村における介護給付及び予防給付に要する費用の20%を負担。
2.調整交付金
2,268億円
全市町村における介護給付及び予防給付に要する費用の5%を負担。
(各市町村間の後期高齢者割合等に応じて調整)
3.財政安定化基金負担金
221億円
都道府県が設置する財政安定化基金に対し、国がその3分の1を負担。
4.要介護認定事務費交付金
250億円
市町村が行う要介護認定・要支援認定の事務処理に要する費用を交付。
| II 介護保険制度の着実な実施 |
(13’要求額)
2,600億円 |
|
1.ゴールドプラン21の推進による介護サービス基盤の整備
2,272億円
(1)特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、痴呆性高齢者グループホーム等の整備
1,313億円
| |
(13’整備量) |
| (1)特別養護老人ホーム |
10,000人分 |
| (2)介護老人保健施設 |
7,000人分 |
| (3)介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス) |
5,000人分 |
| (4)高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス) |
230か所 |
| (5)短期入所生活介護(ショートステイ) |
6,000人分 |
| (6)通所介護(デイサービス) |
1,200か所 |
| (7)痴呆性高齢者グループホーム |
500か所 |
| (8)訪問看護事業所(訪問看護ステーション) |
1,000か所 |
(2)施設整備形態の多様化の促進【事項要求】
- (1)単独型グループホームの整備の促進
- 従来の併設型の整備費補助に加え、新たに特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等との連携や、地域との交流が確保された単独型のグループホームを整備する場合についても整備費を補助。
- (2)民家改修型デイサービスの整備の促進
- 民家を改修して実施するデイサービスセンターが、地域における介護予防事業等を併せて行う場合に、初度設備費を補助することによりその整備を促進。
- (3)高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)の併設要件の緩和
- 従来の、デイサービスセンターとの併設要件を緩和し、新たに介護老人保健施設との併設・隣接及びデイサービスとの隣接(利用可能な範囲)を可能とすることにより整備を促進。
(3)離島等の介護サービスの確保
2.8億円
離島等における介護サービスの確保対策を推進するため、事業者説明会の開催や参入に必要な情報の提供などにより、事業者の参入を推進。
(4) 在宅福祉事業等の推進
956億円
- (1)在宅介護支援センター運営事業
214億円
介護予防プランの作成など、介護予防・痴呆介護の拠点としての機能を充実。
- (2)高齢者世話付住宅(シルバーハウジング等)生活援助員派遣事業
4.7億円
高齢者の自立した在宅生活を支援するため、高齢者の生活に配慮した設備、構造を有する公営・公団住宅及び民間の高齢者向け優良賃貸住宅に生活援助員を配置。
2.介護サービスの質の向上
24.2億円
(1)身体拘束ゼロ作戦の推進
0.4億円
都道府県においてサービス提供者、利用者代表、行政関係者などをメンバーとする身体拘束ゼロ作戦推進会議を開催するとともに、身体拘束相談窓口を設置。
(2)痴呆介護技術等に関する研究と指導者の養成
6.3億円
- (1)高齢者痴呆介護研究センター運営事業
4.0億円
全国3か所の高齢者痴呆介護研究センターにおいて、痴呆性高齢者の介護技術等に関する研究を推進し、その成果を全国に普及。
- (2)痴呆介護指導者養成事業
2.3億円
痴呆介護技術等の向上を図るため、高齢者痴呆介護研究センターにおける痴呆介護の指導者養成及び都道府県における実務者研修を実施。
(3)介護支援専門員(ケアマネジャー)に対する支援策の充実
2.6億円
- (1)介護支援専門員活動支援モデル事業
1.2億円
介護支援専門員が行う介護サービス計画(ケアプラン)の作成等の業務を支援するため、介護サービス計画の事例の研究、インターネットの活用等による必要な情報の提供を実施。
- (2)介護支援専門員現任研修及び実務研修事業
1.4億円
介護支援専門員の新規養成研修及び現任者の資質向上を目的とした現任研修を実施。
(4)訪問介護員(ホームヘルパー)人材確保支援事業
11.5億円
訪問介護員の供給が困難な離島等における人材確保のための研修を実施するほか、現に訪問介護員として活動している3級課程修了者が、適切に身体介護業務に対応できるようにするための資質向上を目的とした2級課程研修を実施。
3.より良い介護保険制度の実現に向けた取組み
304億円
(1)訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額一本化
45.8億円
訪問介護などの訪問通所サービスと短期入所サービスとの支給限度額を一本化するため、市町村及び国民健康保険団体連合会のシステムを整備。
(2)高齢者ITケアネットワーク支援事業【日本新生特別枠】
2.5億円
痴呆性高齢者の徘徊を探知できるシステムや在宅の高齢者の安否確認が容易にできる緊急通報システムの構築など、市町村のIT化への取組みに対し支援。
(3)要介護認定の仕組みの検討のための事業
5.1億円
一次判定のあり方の検討を行い、要介護認定に係るモデル事業を実施し、その結果を検証。
| III 介護予防・生活支援の推進 |
(13’要求額)
596億円 |
|
1.介護予防・生活支援事業の推進
500億円
高齢者ができる限り寝たきりなどの要介護状態にならずに自立した生活を送ることができるよう、転倒骨折予防教室、配食サービスなどの介護予防・生活支援策や、家族介護教室などの家族への支援策を総合的に推進。
13年度より新たに、成年後見制度の利用支援やボランティアによる地域介護支援などを実施。
2.高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)の整備の推進(再掲)
常時の介護は必要としないが在宅での一人暮らしが困難な高齢者などが生活する施設として、高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)の整備を推進。
1.保健事業第4次計画の着実な推進
304億円
生活習慣病などの疾病の予防、早期発見、早期治療を図り、要介護状態になることを防止するため、健康教育、健康相談、健康診査等の保健事業を推進。
2.個別健康教育の充実【日本新生特別枠】
0.2億円
「高血圧」「高脂血症」「糖尿病」「喫煙」の4分野について、老人保健事業の個別健康教育において指導的役割を果たす保健婦等に対する研修を実施。
(参 考)
ゴールドプラン21の推進
ゴールドプラン21により、介護保険施設等を計画的に整備
今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)に基づく平成16年度における介護サービス提供量を確保できるよう計画的に整備を行うため、平成13年度においても所要の整備量の確保を図る。
| 区 分 |
平成13年度
整 備 量 |
(参考)
平成16年度
見 込 量 |
| 特別養護老人ホーム |
10,000人分 |
36万人分 |
| 介護老人保健施設 |
7,000人分 |
29.7万人分 |
痴呆対応型共同生活介護
(痴呆性高齢者グループホーム) |
500か所 |
3,200か所 |
短期入所生活介護/
短期入所療養介護 |
−
6,000人分
(ショートステイ専用床) |
4,785千週
9.6万人分
(短期入所生活介護専用床) |
通所介護(デイサービス)/
通所リハビリテーション(デイ・ケア) |
−
1,200か所 |
105百万回
(2.6万か所)※ |
訪問看護
訪問看護ステーション |
−
1,000か所 |
44百万時間
( 9,900か所)※ |
| |
介護利用型軽費老人ホーム
(ケアハウス) |
5,000人分 |
10.5万人分 |
高齢者生活福祉センター
(生活支援ハウス) |
230か所 |
1,800か所 |
注:平成16年度( )※の数値については、一定の前提条件の下で試算した参考値である。
10月からの保険料徴収へ向けて実施した広報等について
1.ポスターの掲示
全国の自治体の窓口(全国で500,000枚配布)、主要鉄道駅、車内に保険料納入をPRするポスター(モデル 牟田 悌三氏)を掲示
2.パンフレットの作成
従来のパンフレットの改訂(「みんなでささえる介護保険」)のほか、新たにQ&A方式のパンフレット(「なるほど・あんしん介護保険」)、漫画方式のパンフレットを作成。
3.新聞広告
(1)10月前半に、全国紙5紙、ブロック紙4紙及び地方紙34紙に保険料徴収開始をPRする新聞広告(7段(紙面半面))を実施。
(2) 9月中旬に、全国紙5紙、ブロック紙3紙及び地方紙67紙に保険料徴収開始をPRする突き出し広報を実施。
4.ラジオ
(1) 10月から12月までの3か月間、毎週1回、全国33局ネットで、保険料徴収をはじめとする介護保険制度の内容を説明する番組を放送。(「宮崎美子のみんながほっと介護保険」)
(2) 政府広報番組を活用して、保険料徴収の趣旨を説明。(「メイコのいきいきモーニング」など。)
5.テレビ
(1) 10月以降、保険料徴収開始をPRするスポットCMを放送。
(2) 政府広報番組のお知らせコーナーを活用して、保険料徴収開始のPRを実施。(「大調査!!なるほど日本人」など)
医療保険福祉審議会 老人保健福祉部会・介護給付費部会
第28回合同部会議事要旨
1 日時及び場所
平成12年7月24日(水) 13時00分から15時12分
厚生省 特別第一会議室
2 出席委員
星野、井形、青柳、岡、加藤、喜多、京極、見坊、下村、多田羅、田中、中西、中村、野中、橋本、樋口、堀江、水野、山口、山崎の各委員
小島参考人
3 議題
- (1)介護保険制度の施行状況について
- (2)訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化について
- (3)養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正について
- (4)その他
(1)介護保険制度の施行状況について
○資料106「介護保険の実施状況について」
資料107「利用者等に対するアンケートの結果について」
資料108「当面の課題と対応について」
について、神田企画官より説明
(見坊委員)
- ケアマネジャーの業務量が適正であるかについて、過重な業務が課せられているように感じられる。ケアマネジャーの質の向上を図るために色々な対策を講じたり、支援することは必要であると思うが、何かもう少し業務を合理化できないか。また、ケアマネジャーが無理のない形で仕事を遂行できないか。事務当局として何かあればお伺いしたい。
(村上課長)
- ケアマネジャーの負担が重いという話は事業者から聞くが、その主な要因は、特に制度スタートの最初ということでケアプラン作成及び請求にかなり手間がかかったということが考えられる。今後、請求事務の機械化が進めば事務の負担も軽減されるし、回数を重ねることにより慣れてくるということがある。
ケアマネジャーは、地域の事業者の状況をよく把握し、アセスメントに慣れてきてはじめて立派なケアプランがつくれるわけであり、そういう意味でも質の向上のための支援策は大変重要であり、現場の実態も踏まえて支援策を検討する必要がある。
また、ケアマネジャーの現任研修は本年度から予算もついており、実施していくための準備を進めている。
(見坊委員)
- これから利用が増大すれば、当然ケアマネジャーにかかる業務はますます増えていく。余裕を持って仕事をしなければ、利用者としても十分相談できないということになるので、業務量が適正であるかどうか検討していただきたい。
(田中委員)
- 家事援助について、家族のためのサービスや草むしりといった事例が起きているのは事実だろう。家事援助は、要介護者のみならず誰でも受けとってうれしい財であり他の介護保険給付と性質が違う。しかし、介護保険給付に合っていないとはいえ家事サービスは必要である。拒否するとか、禁止するというのではなく、介護保険サービスと一緒に利用しても、個人の望みによる横出しサービスであるから別料金体系をとっていいとか、保険制度の中に含めるのであれば自由料金制をとるべきだ。禁止事例を書くのは必要なステップだとは思うが、それだけではなく、いますぐ制度改正は難しいかもしれないが、家族のためのサービスを使いたい人は自己負担で使うといった、もう少し柔軟な方向に変えていったらどうか。
(橋本委員)
- 家族の生活を介護保険制度によって支えるということはありえないと思う。ただ、家事援助行為の不適正な事例の中で、主として利用者が使用する場所以外の場所の掃除となっているが、利用者も使うこともあり、このあたりの解釈は非常に難しい。
家族に過重な負担をさせないといってきた訳であり、家族も利用者も受けるサービスについてはできるだけ柔軟でいいのではないか。
ホームヘルパーが柔軟できめ細かいサービスをしてくれると在宅生活の期間を伸ばすが、これが自由に使えないとどうしても入所型のサービスに移行してしまう。ホームヘルパーが使えないときのこととして、「軽度生活支援事業、配食サービス等の生活支援サービス、シルバー人材センター、ボランティア等によるサービス等の有効な活用が必要である」と示されているが、こういうサービスは、ボランティアは別にして、10割自己負担となる。そうなると低所得者は入所型のサービスに移行する日が早くなるので多少は柔軟に考えてもいいのではないか。
(樋口委員)
- 例えば、歯科に行けば、保険適用できるものと自由診療、自己負担のものがあり、家事援助というのはそのあたりで重なる部分だと思う。
ドイツで一人暮らしのお年寄りを訪問した時に、ヘルパーさんが応接してくれた時のことが印象に残っているが、極端なことは論外として、一人暮らしのお年寄りなどが外部とのコミュニケーションを増やすための窓口となる方向にこの介護保険制度が働いてほしいと思っている。
(堀江委員)
- 実情に即して柔軟にということは分かるが、家事援助についての今の議論は時期尚早である。まずは保険制度の枠内でのサービスの評価をした上で、いまのような問題、新しく発生する、あるいは従来から行政が取り組んできた分野をどう対応するかを議論すべきである。問題提起としてはよく分かるが、現時点において介護保険制度内で議論するのはあまりにも時期尚早である。
(野中委員)
- 保険者の立場から考えれば、家族の洗濯や炊事、庭の草むしり等ということが現実に行われたということに大きな問題を感じる。
1、2ヵ月の間に事業者がこんなところまで踏み込んでいったのは何が原因なのか、厚生省は把握をしているのか。そのことをきっちりと整理するとともに、介護保険の範囲内というものを明確にして、それ以上の横出しや上積みは自己負担で対応していくという節度をもって対応してもらいたい。業者が先んじて対応していたら、それは利用者のために、それは家族のために、という形でどんどん幅が広がっていけば保険者は大変なことになる。
(橋本委員)
- 介護保険制度をつくるときに家事援助についてかなり議論を行ったが、要介護認定を受けて介護が必要な人たちは、家事がいらないということはあり得ない。また、支給限度額の範囲の中でのサービスの利用であり、そういうことも念頭において議論したい。
(京極委員)
- 普通日常的に行っているものについて、これは不適切であると整理していくと、ほとんどのものは不適切となってしまう。利用者にとって大事なことであれば、家事援助の範囲内でできるものは行った方がむしろいいのではないか。事例については、明らかに社会的に認められないものに限定したほうがいいのではないか。
(山崎委員)
- ケアマネジャーについては、ケアプランをどのようにつくるかという研修も大事であるが、実際のケアプランを収集したり、ケア担当者会議の運営、給付管理業務の実態、受け持ち人数、採算、今の仕組みで公平中立性に矛盾はないかといった仕組み全体を、国の責任できっちりと検証していただきたい。
質の評価についての取り組みをどの範囲のサービスまで検討会で議論するのか。
(神田企画官)
- 家事援助に関しては、事業者が進んでやっているというよりも、ケアマネジャーが利用者からの申し出にとらわれすぎているということが事業者や市町村の意見交換で出ている。基本的なあてはめの考え方をきっちりと踏まえた上で、現場のケアマネジャー、ホームヘルパーの事業者が説明できるようにすることがまず必要ではないかと考えている。
その中で、ご指摘があったように、ただサービス提供を拒否するということではなく、日常生活の軽度な支援といったような補助事業を行っているので、そうしたサービスの活用ということもアドバイスしていくべき。家事援助のあり方については、まずそういう取り組みをした上で、この場でご議論いただきたい。
(村上課長)
- サービス評価については、今年度できるだけ早くスタートしたいと考えている。利用者が選ぶ際、参考になるような観点からの評価の基準を考えていきたいということで、現在準備を進めている。
(青柳委員)
- 利用者等アンケート調査であるが、調査結果は非常によい結果が出ているが、定点市町村でスムーズにいっている市町村にお願いをしたのか。この調査結果を全国に広げて解釈してもよいのか。
要介護認定の問題で、検討会をつくって本格的に検討し直すということであるが、痴呆の問題に限定したものではないと聞いているがその理解で良いか。
家事援助について、事業者やケアマネジャーが説明するという整理も一つの案だが、介護保険とはどういうものであって、どういうものが保険給付の対象になるということを利用者がまずよく理解することが大事であり、そのためにも、国が中心となって、利用者にわかりやすく内容を説明していくという努力がもっと必要ではないか。
(神田企画官)
- アンケート結果については、回答が出てきたのがここに示している市町村であり、特別によいところをとった訳ではない。今後も出てくれば紹介していきたい。
介護保険制度の理解を求めるようにしていくということについては、パンフレットなどを通じて利用者にできるだけわかりやすく御理解いただくよう努力していきたい。
(西山課長)
- 要介護認定の件については、痴呆だけでなく、要支援と自立の関係や、在宅のデータをとることも含めて広範に検討してもらいたいと考えている。
(山口委員)
- 介護報酬のレセプト請求は初めてということで現場は大変であったが、国保連により格差はあったものの、概算払いなど臨機応変の対応をとっていただいた。厚生省からも都道府県や国保連に対して概算払いなどの措置を実施してもらうよう依頼した。こういう臨機応変の対応は、初めての制度を動かしていく上で非常に大事なことである。
4月以後の不服審査の申立ては非常に微々たるものであったが、10月に保険料徴収が始まれば増えると思う。保険料の徴収が始まる10月以後も臨機応変の対応をお願いしたい。
(下村委員)
- 家事援助について、すべて現場のホームヘルパーの判断だけに偏ってしまっては困る。ある程度の弾力性はあってもいいが、考え方の筋道ははっきりとしてもらわないと保険制度としてはやっていけないのではないか。そういう意味で、ここに示している考え方については賛成である。
ケアマネジャーは利用者の代理人であり、利用者の委託を受けて、利用者の立場に立ってケアプランをつくる。国保連の仕事の下請をやっているような話が出ているがそれは違うのではないか。その立場きっちりとケアマネジャーにわかっていてもらわないと困る。基本的な給付についての考え方を要介護老人や家族が十分に理解できないという面があることから、ケアマネジャーが生まれたという側面もあり、そういうことをケアマネジャーに徹底させてもらいたい。
ケアマネジャーの負担は重いということであるが、色々な支援をしばらくやってみるより差し当たりは仕方がないのではないか。概算払いは例外的に行われたようだが、全体でどのくらい行われたのか。例外的に概算払いが行われて、大部分はきっちりとした支払いが行われたとのことであるが、事実関係はどうだったのか。
要介護者で介護保険の給付を受けているということが医療のレセプトに明記されるということであったが、4月分のレセプトには明記されていないがどうなっているのか。
医療保険に老人医療費を請求する場合に、この人は要介護認定を受けて介護保険の給付を受けているということを明示してほしい。
(神田企画官)
- 概算払いの扱いについては、国保連によっては貸付という対応をされたところもある。
介護保険と医療保険の重複請求については、医療保険の療養担当規則で、介護保険と重複するようなサービスを受ける場合には、被保険者証で要介護者であることを確認し、費用請求する場合にはレセプトの適用欄にマル介という印を書いて請求することになっている。4月の段階では十分徹底できてない点があると思うが、制度上は最終的に医療保険者で要介護認定を受けている人の請求書かどうか分かるようになっている。
(下村委員)
- 4月請求については全くマル介という印がなかったとのことなので徹底させてほしい。
概算払いと貸付を合わせると4月分支払いのほぼ100%となるのか。
(高井課長)
- 通常の支払いが請求の8、9割であり、エラーが出たところにについて概算払いや貸付をしているという状況。
(西山課長)
- レセプトの関係については介護保険の請求があったのかどうか、両方見ないとわからない。
(樋口委員)
- 280万件の申請件数は、大体予測どおりであったのか。未申請の人は何割ぐらいいると見ているのか。
介護保険は概ね順調に回転しはじめていると思い、ほっとしているが、メディアに出る介護保険の問題点との落差をどう考えたらよいか。私も、介護保険になって細かく計算されてお金がかかるようになったというような苦情をよく聞く。
介護サービスで働くホームヘルパーが働きにくくなったり、収入が減ったりしている。介護保険は新たな雇用の創出という点からも非常に期待されていた面があったが、どうか。厚生労働省一体で取り組んでほしい。
(神田企画官)
- 要介護認定の申請に関しては、ちょうど280万人ぐらいで、そのうち13万人ぐらいは自立であるが、ほとんどの人が申請をされていると考えている。当初、市町村で調べてもらった見込み人数がちょうど280万人だったので、それに近い申請は上がってきているのではないかと考えている。
(多田羅委員)
- 介護保険全体としては順調に進んでいるということであるが、介護支援専門員については、期待されている役割を十分果たせていない状況が見られるという認識が示されている。具体的に、どういったことを課題として支援会議を推進するのか教えてほしい。
(橋本委員)
- 介護支援専門員は期待どおり動いていない。また、在宅介護支援センターと居宅介護支援事業がごちゃごちゃに運営されている。介護支援専門員を支援する事業も大切であるが、介護支援は実例のない制度であり、3年後、5年後の見直しに向けて実態をきっちりと把握してほしい。
(山崎課長)
- 実態はどう動いているのかを十分踏まえた上で、特にケアマネジャーの場合、制度施行当初で業務が増えているという問題もあり、ケアマネジャーをまわりから支え、育ていくということで支援会議を運営していきたいと考えている。
(小島参考人)
- 要介護認定基準について、一次判定の痴呆性の問題を早急に改善していただきたい。また、現場の痴呆に詳しい人をメンバーに加えていただきたい。
サービスの質の向上という点からホームヘルパーの働き方がどういう実態なのかということを調査していただきたい。連合の立場でも調査したいと考えている。
(2)訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化について
○資料109「医療保険福祉審議会答申書(写)(平成12年3月16日)」
資料110「訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化について(案)」
資料111「現行の訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額」
資料112「短期入所の振り替え措置の実施状況について」
について、高井介護保険課長より説明
(中村委員)
- 訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化については賛成である。ただ、一本化した後のショートの利用量は、利用者の判断を中心に運用していただきたい。また、それまでの間の振り替え措置を利用するか否かも、利用者の判断に委ねるようにしていただきたい。平成14年1月適用ということであるが、できる限り前倒ししていただき、ぜひ突貫工事でお願いしたい。
また、旧制度でのショートステイの場合、特養待機者が圧倒的に多かったが、もう一方では、家族の介護力が弱く、緊急的に要支援、要介護にかかわらず利用する方も多かった。規制を緩和するだけでなく、もう一度利用ニーズを分析して、抜本的な見直しをしていただきたい。例えば、要支援、要介護判定以外の方でもショートステイが一般財源で利用できるよう考えていただきたい。
(青柳委員)
- そもそも審議会で通所系と入所系の限度管理期間を同一にしようという意見があったが実現しなかったことは反省すべきである。
(喜多委員)
- 一本化に伴うシステム変更について、予定を組んで、平成14年1月からということについては評価するが、システムソフトの変更には膨大な費用がかかり、全国的には相当の費用となる。その予算については国が当然持ってくれるのか。
(山口委員)
- 3月16日の答申書にも、一本化については検討することとなっている。3月に答申したのにすぐに変更するとはどうなっているのかというような誤解を招かないようにしていただきたい。
一本化については、以前から意見が出ていた分野であり、保険者、国保連合会、ケアマネジャー、サービス事業者及び利用者の理解と認識が必要である。各論については、現場が混乱しないように十分な配慮をお願いしたい。
(野中委員)
- 一本化は当然の方向であると思っており、できるだけ早く対応してほしい。
システム変更については、保険者の負担にならないように強く要請する。
短期入所サービスの相当長期間にわたる連続利用には一定の制限を設けるとされているが、ショートステイが長期入所的になってきたという経緯があり、まずショートステイとは何かということを利用者や家族に理解していただく必要がある。ただ、退所が可能となった段階で在宅に復帰することを促進するとあるが、現実として至難な問題であることは事実である。ショートステイとは何かということを制度的にきっちりと位置づけて対応していただきたい。現場で混乱が起きないよう遺憾のないようにしていただきたい。
(見坊委員)
- 一本化については一刻も早くお願いしたいが、システムを電算化したためにシステムの変更に大変な時間と費用がかかる。新しい問題が出る都度にシステムの変更がネックになるのではないか。方法や考え方を転換して、もっと迅速なやり方や市町村の考えでできるような仕組みを検討してほしい。
(山崎委員)
- ショートステイの連続利用の制限についてきっちりと議論をしていただきたい。ショートステイは在宅のリリーフであり、施設入所の前倒しではないので、支給限度額のことも含めてしっかりと議論しないと、結局、介護保険も施設に流れるのかということになってしまう。
(下村委員)
- ショートステイについて議論が必要であれば、平成14年1月からといった中途半端な見直しはしないほうがいいのではないか。次回の全体の見直しの時に課題として残したらどうか。
(山崎課長)
- ショートステイの中に特養の入所待機者がいるということは事実であるが、一本化自体の必要性というよりも、ショートステイ自体を特養に転換するなど別の方策を検討する必要があるものと理解している。
(下村委員)
- 現物給付化すると書いているが、法律を改正する必要はないのか。
(高井課長)
- 在宅サービスについては、現物給付化できるような法律となっている。現在、振り替え分についてのみ償還払いとなっているが、振り替えは応急的な措置であり、システムが間に合わなかったため償還払い、受領委任払いで対応したものであり、それを本来の姿に戻そうという考えである。
(下村委員)
- 走りながらやっていき、また半年ぐらいたったら見直すということはやめたらどうか。
(野中委員)
- ショートステイはあくまで居宅介護に対する支援体制であって、長期入所のための便法ではないということを明確にするべきである。ショートステイで足りない人は当初から施設入所のような、ショートステイが長期入所につながるというような書き方はしないでいただきたい。
(中村委員)
- 一本化でショートステイの問題がすべて解決する訳ではない。
一本化は今年中にできると思っているが、14年1月ならば、これまで特養待機者が多かったので、ショートステイの一本化と同時に、施設サービス的にショートステイを利用していた人への対応についても議論していただきたい。
(京極委員)
- 一本化の方向は大賛成であるが、システム変更までの間、何か便法的なやり方はないか。
(高井課長)
- 現物給付化となる振り替え措置の受領委任方式を各市町村にとっていただくようにしていきたい。
(星野部会長)
- それでは、一本化についてはこういう方向で作業は進めさせていただいて、なお、具体的な問題についてはご議論を今後いただくということにさせていただきたい。
(3)養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正について
○資料113「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正について」
について、山崎計画課長より説明
(喜多委員)
- 養護老人ホームをどうしていくのかということに対していまだに姿勢がはっきりとしてないということに苦情を言っておきたい。
(山崎課長)
- 十分承知している。色々な面でさらに検討を進めていく必要があると考えている。
(星野部会長)
- それでは本日はこれをもって閉会とさせていただく。
(了)
介護保険制度についてへ戻る