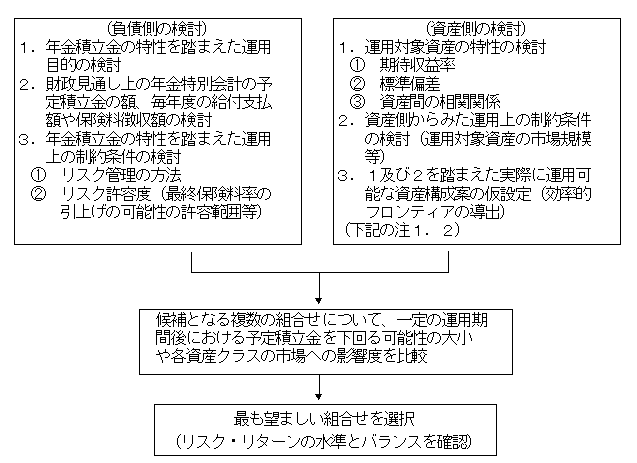
| 審議会議事録等 | HOME |
年金積立金の運用の基本的考え方
○ 年金積立金の運用は、運用収入によって将来の保険料負担増を抑制し、年金財政の安定化に資するために行う。
○ 必要なリターンを得るには相応するリスク負担が不可避であるが、公的年金においては確実な年金給付が必須であり、運用収益の大幅な下方変動による保険料の予期せざる引上げは抑制する必要。
(運用の基本)
基本ポートフォリオ
| 目標収益率 | 標準偏差 | 予定利率 |
| 4.50% | 5.43% | 4.00% |
(%)
| 国内債券 | 国内株式 | 外国債券 | 外国株式 | 短期資産 |
| 68(±8) | 12(±6) | 7(±5) | 8(±5) | 5 |
※ ( )内は乖離許容幅。
※ 基本ポートフォリオは移行期間終了後に適用される。
※ 基本ポートフォリオは毎年1回の検証及び少なくとも5年に1回の財政再計算の際に検討するほか、随時見直す。
財投改革に伴う経過措置
○ 財投債(国債)の引受条件は、年金にとって不利なものとならないよう対応。
○ 財投債も市場運用が基本であるが、財投改革等のため多量の国債が市場に流入する当面の間は、市場の混乱を招かないよう慎重に対応。
○ 財投債の引受が年金財政に与える影響が明らかとなるよう積立金全体について運用評価する。なお、満期保有する債券については、企業会計原則にならい簿価によるディスクロージャーとし、参考情報として時価評価を行う。
運用に当たっての留意事項
○ 市場変動リスク等資産運用に伴う様々なリスク管理を徹底。
○ 市場の価格形成等を歪めないように、市場への資金の投入・回収の分散化に留意。
○ 年金資金運用基金は、自ら株主議決権の行使はせず、基本的考え方をガイドラインとして示すにとどめ、運用受託機関の判断に委ねる。
○ リスク管理の観点や公的資金による民間企業への影響の排除の観点から、同一企業発行銘柄への投資は一定割合以下に制限。
○ 投機目的のデリバティブズの使用は禁止。
○ 厚生労働省・基金における専門性の確保、人材の育成に努めることが重要。
年金積立金の運用の評価
○ 毎年度、運用の状況が年金財政に与える影響を検証し、積立金の実績が計画通り推移していない場合は、原因を分析し必要な対応を行う。
○ 移行期間中は、既往の預託や財投債も含め年金積立金全体の運用評価を行う。
基本方針の見直し
厚生労働大臣は、少なくとも毎年1回「運用の基本方針」に検討を加え、それが常に年金積立金を巡る運用環境や年金財政の状況に即した内容となっているかを検証し、必要な変更を行う。
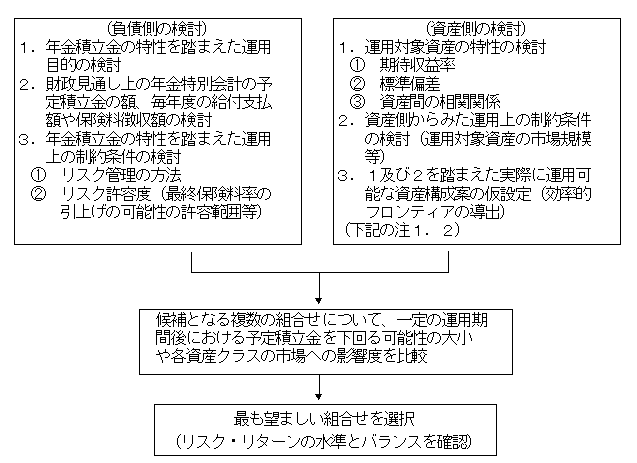
(注1)効率的フロンティア導出に当たっての期待収益率、標準偏差、相関係数の設定
2.個別資産の期待収益率・標準偏差、相関係数の推計値
期待収益率・標準偏差
(%)
| 短期資産 | 国内債券 | 国内株式 | 外国債券 | 外国株式 | |
| 期待収益率 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 7.0 |
| 標準偏差 | 3.38 | 5.45 | 21.62 | 14.67 | 20.30 |
相関係数
| 短期資産 | 国内債券 | 国内株式 | 外国債券 | 外国株式 | |
| 短期資産 | 1.0000 | ||||
| 国内債券 | 0.2734 | 1.0000 | |||
| 国内株式 | −0.1031 | 0.1876 | 1.0000 | ||
| 外国債券 | 0.0647 | 0.0049 | −0.2270 | 1.0000 | |
| 外国株式 | −0.2288 | −0.0575 | 0.1441 | 0.6682 | 1.0000 |
(参考)リターン・リスク、相関係数導出の考え方
(1) リターン(期待収益率)
ビルディング・ブロック方式(収益率を構成する様々な要素を積み上げて各資産の期待収益率を算出する方式)を採用。
1973年〜1999年の27年間の実績データを使用
(3) 相関係数
1973年〜1999年の27年間の実績データを使用。
| 内海 孚 | (財)国際金融情報センター理事 | |
| 奥田 碩 | 日本経営者団体連盟会長 | |
| 杉田 亮毅 | (株)日本経済新聞社代表取締役副社長 | |
| 竹内 佐和子 | 東京大学大学院工学研究科助教授 | |
| 寺田 徳 | 厚生年金基金連合会常務理事 | |
| 福井 俊彦 | 富士通総研経済研究所理事長 | |
| 吉冨 勝 | アジア開発銀行研究所長 | |
| 吉原 健二 | (財)厚生年金事業振興団理事長 | |
| 米澤 康博 | 横浜国立大学経営学部教授 | |
| ○ | 若杉 敬明 | 東京大学大学院経済学研究科教授 |
| 鷲尾 悦也 | 日本労働組合総連合会会長 |
(五十音順・敬称略)
(○は座長)
| 浅野 幸弘 | 横浜国立大学経営学部教授 | |
| 榊原 茂樹 | 神戸大学大学院経営学研究科教授 | |
| 鮫島 正大 | 日本銀行企画室参事役 | |
| 寺田 徳 | 厚生年金基金連合会常務理事 | |
| 中田 正 | 日興リサーチセンター副理事長 | |
| 三浦 良造 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 | |
| ○ | 米澤 康博 | 横浜国立大学経営学部教授 |
| 若杉 敬明 | 東京大学大学院経済学研究科教授 |
(五十音順・敬称略)
(○は専門部会座長)
【検討会】
第1回(12.9.5)
第2回(12.10.16)
第3回(12.11.15)
第4回(12.12.1)
第5回(12.12.22)
【専門部会】
第1回(12.9.18)
第2回(12.9.29)
第3回(12.10.10)
第4回(12.10.24)
第5回(12.11.10)
第6回(12.11.28)
第7回(12.12.8)
VII 基本方針の見直し
平成13年4月から、従来の資金運用部預託に代わり、年金積立金の自主運用、すなわち市場運用が行われる。これにあたり、厚生年金保険法及び国民年金法は、厚生労働大臣に、基本ポートフォリオを含む「運用の基本方針」の策定を求めている。それを受け、本検討会は、厚生大臣が主催する検討会として、平成12年9月より「運用の基本方針」に盛り込むべき事項等についての検討を開始した。
I 年金積立金の運用の基本的考え方
1.運用の目的
公的年金制度における年金積立金の運用の目的は、現在の我が国の年金財政運営の考え方では、世代間の負担の不公平を是正するためその運用収入によって将来の保険料負担の増加を抑制し、年金制度の財政運営の安定化に資することにある。
2.年金積立金の運用と年金財政との関係
年金積立金の運用には、他の資産運用と同じく、リターンに応じたリスクを伴う。運用収益が予定されていた運用収入を上回り、将来の保険料を引き下げる可能性がある反面、予定していた運用収入を下回り、将来の保険料を引き上げなければならない可能性もある。したがって、年金加入者の保険料負担を軽減するためにはある程度のリスクを負担する必要があるが、公的年金の場合、安定的な財政運営を確保することが最優先の課題であるので、運用結果によって最終保険料率の大きな変動につながることは避けなければならない。特に、運用収益の大幅な下方変動による保険料率の予期せざる引上げは、年金加入者にとって大きな負担となるので、下方変動のリスクを管理し、最終保険料率の引上げの可能性を抑制することが不可欠である。
3.運用における留意事項
上記の基本的考え方に基づき年金積立金の運用を行うが、運用に当たっては、年金加入者が将来にわたり年金給付を確実に受けることができるよう、以下のような点に留意する必要がある。
4.責任体制の明確化
年金積立金の運用は、年金加入者から徴収した保険料の集積である年金積立金を厚生労働大臣が運用するものであり、その結果は、将来の保険料負担の増減という形で年金加入者に帰属する。
なお、資産運用においては、いかに適切にリスク管理を行おうとも、市場変動に伴うリスクを始めとする様々な要因による収益の変動を避けることができない。それゆえ、運用結果である運用利回りが期待リターンを下回り、積立金額が計画値を下回るという事態も生じ得る。
年金積立金の運用に携わる厚生労働省の職員及び基金の役職員は、この責任を重く認識し、必要な知識・技術の修得を行う最善の努力をしなければならない。
5.情報公開の徹底
4.に述べたように、年金積立金の運用は、その結果如何により将来の保険料水準に影響を及ぼすなど年金加入者の利害に大きく影響する。このため、運用がどのような方針に基づき行われており、その結果積立金の状況はどうなったのか、またその年金財政に与える影響はどうかについて、年金加入者に対する徹底した情報公開が行われるべきである。丁寧かつ分かりやすい情報公開は、年金積立金の運用に対する国民の理解や信頼を得るためにも、また、国民の持つ運用に関する英知を受け止め生かすためにも不可欠である。
II 基本ポートフォリオ
1.基本ポートフォリオの重要性
一般に、資産を安全・確実かつ効率的に運用するためには、リターン・リスク等の特性が異なる複数の資産クラスに分類し、それらの間に分散投資することが適切であるとされている。この経験的原則は、公的年金積立金の運用にも適用できる。
2.策定の基本的考え方と運用対象資産
(1) 基本的考え方
年金積立金の基本ポートフォリオの資産構成割合の策定に当たっては、Iに述べたように適切な分散投資を図るとともに、年金財政安定化の視点から特に運用収益の下方変動リスクを一定範囲に抑えるよう資産構成に配慮することが基本であるが、その他にも次のような点に留意する必要がある。
ア.名目ではなく、基本ポートフォリオの期待収益率から予想される物価や賃金の上昇率を引いた実質的な運用収益率が一定の目標水準を確保すること。
イ.年金給付に必要となる現金収入(キャッシュフロー)を効率的に確保できるよう、インカム(債券利子、株式配当等)及び流動性(換金性)に配慮すること。
ウ.年金積立金が保有する資産の規模やその売買活動により、市場の資金配分や民間の投資行動が歪められないよう、各種資産の市場規模を考慮すること。
(2)運用対象とする資産
3.策定の手順
基本ポートフォリオは、リスク・リターンの効率性という観点から、現代投資理論に基づき実務的に確立された標準的な手法に従い効率的フロンティア上の効率的ポートフォリオの中から選択することが望ましい。同時に、年金財政の安定性・健全性という観点から、負債サイドの諸条件を最も安定的に満たすことができるポートフォリオという条件にも適っていなければならない。資産の運用はまさに負債サイドから発生する支払いの原資を確保するために行われるものであるからである。要するに、基本ポートフォリオは、リスク・リターンに関する効率性の分析と年金財政についての資産と負債の総合分析とに基づいて決定される。
(注1)
4. 基本ポートフォリオと乖離許容幅
(1)基本ポートフォリオと乖離許容幅
以上の手順に従い、最も望ましい基本ポートフォリオを導出すると、以下のとおりとなる。
はじめに
年金積立金の自主運用については、これまで、「年金自主運用検討会」(平成9年9月報告)及び「年金積立金の運用の基本方針に関する研究会」(平成10年6月報告)において検討が行われてきた。そこでとりまとめられた基本的考え方の多くは、本年3月の年金制度改正の際に、自主運用関連法に盛り込まれている。本検討会においては、これまでの検討及び研究結果を踏まえ、基本的な事項について再確認するとともに、さらに具体的な検討が必要と指摘されていた事項及びこれまでに十分に議論されなかった事項を重点的に検討した。
検討会の検討課題として掲げた項目のうち、基本ポートフォリオ策定のためのシミュレーション等、技術的な検討が必要なものについては、専門部会を設け、そこで技術的・専門的な検討を行った。
このようにして、検討会を5回、専門部会を7回各々開催し、精力的に検討を行った。その結果、「運用の基本方針」に盛り込むべき事項及びその他年金積立金の自主運用に関する留意事項等について検討会としての結論を得るにいたったので、ここに報告する次第である。
検討会として、厚生労働大臣が本検討会の検討の趣旨を踏まえ、速やかに「積立金の運用の基本方針」を策定し、万全を期して年金積立金の自主運用を開始することを要請するものである。
年金積立金の運用については、このような目的を達成できるよう長期的観点に立って安全確実を基本としつつ効率的に行う必要がある。
このため、次のような基本的考え方に立って年金財政と整合性をもった年金積立金の運用を行う必要がある。
今後、制度の成熟化に伴い、年金給付費が更に増大し、より多くの運用収入を給付に充てていくことも考えられるため、これに見合う現金収入(キャッシュフロー)を確保することが必要となる。
その結果、預託されている年金積立金は、平成13年度から7年間にわたり毎年度平均して約20兆円の規模で年金特別会計に償還され、年金資金運用基金(以下「基金」という。)に寄託される。また、基金は年金福祉事業団の廃止に伴い、同事業団が運用していた27兆円にのぼる資金を承継して運用する。基金が運用する額は、最終的には、140兆円を超える額となる。
このように基金が市場で運用することとなる額は、運用の対象となる資産の市場規模に比して非常に大きいので、運用に当たっては、市場規模を考慮するとともに、市場の価格形成や民間の投資行動を歪めないよう配慮する必要がある。
したがって、年金積立金の運用に当たっては、責任体制の明確化を図り、年金積立金の運用に関わるすべての者について、受託者責任を徹底することが必要である。このため、関連する法律は、厚生労働省の職員や基金の役職員について受託者責任に関する以下のような二つの義務を規定し、その内容を明確化している。
このような場合であっても、「運用の基本方針」の決定及び運用管理が適切に行われ、実際に的確な運用が図られているのであれば、結果に関する責任を問うのは適当ではない。もちろん、その過程に重大な瑕疵がある場合には、厳しく責任を追及されなければならない。このように、運用関係者は、結果ではなく、資産運用のプロセスに責任を負うという受託者責任の考え方は、年金資産運用の先進国である英米において確立されている。年金積立金の運用においても、この考え方がとられるべきである。
更に、各段階における意思決定の過程を事後的に確認することができるよう、文書等の記録に留め管理しておくことが重要である。
また、受託者責任の徹底を図るためには、事後的な情報公開により、上記の忠実義務及び注意義務が遂行される過程を明らかにすることが必要であるとともに有効である。一般に高い透明性の下にあっては外部から見られることにより、規律が働くからである。その意味で、受託者責任の確保は、情報公開と表裏をなすものである。
このような観点から、法律上、厚生労働大臣が「運用の基本方針」を公表すること、また積立金の運用結果を毎年度公表することが制度化されている。また、基金は、財務諸表についての監査法人の監査を受けること、財務諸表等について閲覧に供すること、また各事業年度における時価による年金資産の額及びその構成割合、運用収入の額等を記載した業務概況書を作成し、公表することが求められている。
厚生労働省及び基金は、市場に対する不測の影響を与えないよう留意しつつ、これまでの年金福祉事業団によるディスクロージャーの実績も踏まえ、年金積立金の運用の考え方や運用の状況を分かりやすく伝え、年金積立金の自主運用に関して国民のより一層の理解と協力を得るよう努める必要がある。
分散投資において重要なことは、資産クラスの分類をどのように行うかということとともに、どの資産クラスにどれだけの資金を配分するかを決定することである。
米国における研究によれば、資産運用の結果の90%程度がポートフォリオの構成比率によって説明されると言われている。それとともに資産運用においては、短期的な市況により構成比率を変更するよりも、基本となる比率を定め、それを長期間維持していく方が、投資期間全体を通しては効率的な結果をもたらすことが知られている。
長期間安定的な積立規模が維持される年金積立金の運用においては、基本ポートフォリオを明示的に定め、年金財政や経済等の前提条件に著しい変化がない限り維持することが望ましい。
以上のことから、厚生年金保険法等においては、厚生労働大臣が基本ポートフォリオを含む「運用の基本方針」を定めることを求めている。
ここで「運用の基本方針」の中心をなすものは、年金積立金が目標とするリターンとリスクの大きさとそれを実現するための基本ポートフォリオの資産構成割合である。
年金積立金においては、市場の規模、データの有無等を考慮し、伝統的な基準に従いこれらを国内債券、国内株式、外国債券及び外国株式に分類し、運用対象とする。これらをどのように細分化するかを含め、基本ポートフォリオに関して資産をいかに分類するかは、投資の重要なノウハウである。より適切な資産分類があるか否かについて常に注意を払っていくことが必要である。
ただし、外貨建て証券(外国証券)については、期待収益率の推計値に現れないコスト(管理コスト等)が大きく、リスクの推定値に現れないリスク(政治的リスクや決済リスク等)があること、また、年金積立金は最終的に円建てでの実質的な収益確保を目的としていることから、単にリスク・リターンの効率性の観点からのみ最適な外国証券の割合を決定すべきではない。したがって、外国証券の保有比率に関しては先験的な制限を置くことも必要であろう。また、外国資産の運用に当たっては、特にリスク管理に留意することが必要である。
効率的フロンティアは、(1)各資産の期待収益率、リスク及び相関係数に関する予想、及び(2)各資産の保有割合に関する制約条件によって決定される。
負債・資産の総合的な分析は、効率的フロンティア上のポートフォリオのそれぞれについてシミュレーションを行い、将来において予定積立金を下回る確率、その場合に引き上げなければならない保険料率を計算することによって行われる。これら二つの分析から、年金財政の効率化と安定化に最も寄与する最適ポートフォリオを決定する(下図参照)。
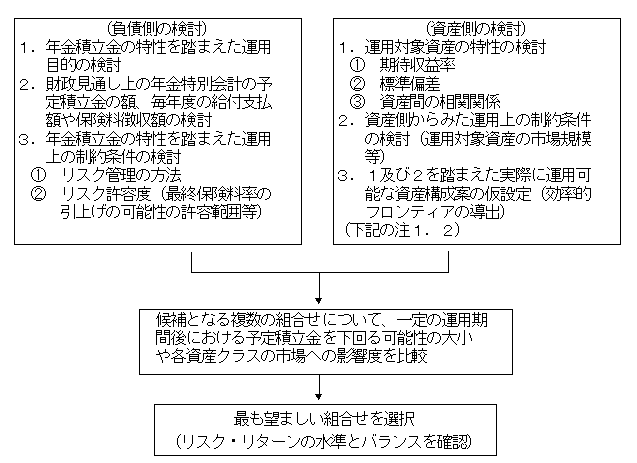
(注2) 効率的フロンティアの導出に当たっては、以下の制約条件を設定している。
| 目標収益率 | 標準偏差 | 予定利率 |
| 4.50% | 5.43% | 4.00% |
| 国内債券 | 国内株式 | 外国債券 | 外国株式 | 短期資産 |
| 68% | 12% | 7% | 8% | 5% |
(注)外国債券、外国株式に関しては、為替変動リスクをヘッジしないもとでの保有となっている。
市場の変動により各資産クラスの時価構成比は常に変化し、その資産構成は基本ポートフォリオから乖離するが、リバランス(資産の入替)の取引コストを考慮すると、常に基本ポートフォリオに一致させるべく資産を入れ替えることは必ずしも効率的ではない。基本ポートフォリオの資産構成割合は長期的には維持されるべき基準であるが、一時的・短期的にはそこからの乖離を許容する方が長期的には効率的な運用をもたらすことが考えられる。つまり、基本ポートフォリオの各資産クラス毎の構成比について一定の範囲での乖離を認めることが望ましい。
各資産クラス固有の収益率の変動の大きさ、基本ポートフォリオにおける組入比率水準、取引コスト等を総合的に勘案すると、以下のとおり乖離許容幅を設定することが適当である。
(%)
| 国内債券 | 国内株式 | 外国債券 | 外国株式 | |
| 乖離許容幅 | ±8 | ±6 | ±5 | ±5 |
| 資産の変動幅 | 60〜68〜76 | 6〜12〜18 | 2〜7〜12 | 3〜8〜13 |
(2)中短期ポートフォリオ
なお、実際の運用においては、投資環境見通しを考慮して中短期的に基本ポートフォリオとは異なる資産構成を持つことが望ましいことも生じ得る。この場合にも、乖離許容幅の範囲内で行われなければならない。また、その決定に当たっては明確な手続きを経るとともに、基本ポートフォリオからの乖離を図る理由及び意思決定の過程を記録に留め管理する必要がある。
5.移行期のポートフォリオ
基本ポートフォリオは、全額が市場運用されるとの前提で策定されたものである。他方、年金積立金の全額自主運用が開始される平成13年4月までは、年金積立金は資金運用部の預託金という形をとっている。これは平成13年度からの7年間にわたって償還されるが、その間は財投協力(財投債の引受)が行われることになっている。また、基金は、これまで年金福祉事業団が資金運用部からの借入れによって行ってきた運用事業の資産を承継することになっている。
このように全額自主運用開始時の運用資産は、年金積立金として基金に寄託される資金の他に、資金運用部預託と年金福祉事業団から承継する資産とから構成される。預託は国内債券に準ずるものと考えることができるが、そのように考えてもなお全額自主運用開始時の資産構成割合は、乖離許容幅を超えて基本ポートフォリオのそれとは異なり得る。
したがって、基本ポートフォリオは、平成13年度以降7年かけて資金運用部から償還される預託金の配分を通じて最終的に実現を図ることが望ましい。
基本ポートフォリオを実現するまでの経過的なポートフォリオ、すなわち移行ポートフォリオについては、効率的な運用を目指すと同時に、最終的に、円滑に基本ポートフォリオを実現するということも考慮して策定する必要がある。
なお、基本ポートフォリオの実現時期については、預託償還期間中の財投協力を考慮すると償還終了時とすることはかなり困難と考えられるが、できるだけ速やかに基本ポートフォリオの実現を図る観点から、移行ポートフォリオの策定に当たり、目標となる時期を定めておく必要がある。
6.基本ポートフォリオの見直し
基本ポートフォリオは、年金財政及び運用環境の見通し等々、いわば現状で考え得る将来のすべてを想定して策定したものである。その想定外の事態が生ずれば、基本ポートフォリオを変更することが必要になるかもしれない。近年、我が国及び世界の経済の構造変化が著しく加速化していることを考慮すると、その可能性は決して小さいとはいえない。移行期間中も含めて、基本ポートフォリオが想定した運用環境や円滑な年金制度の運営に適合しているかを常に検証することが不可欠である。法律の定める(1)毎年1回の検証、及び(2)少なくとも5年に1回行われる財政再計算の際に、必ず基本ポートフォリオについて検討する他、必要に応じて随時見直すことが求められる。
III 財投改革(義務預託制度の廃止)に伴う経過措置
1.財投債の引受け
前述のとおり、資金運用部に預託されている年金積立金は、平成13年度から毎年度平均すると約20兆円前後が7年間にわたって年金特別会計に償還される。このことにより、財政投融資制度に混乱を生じさせないため、年金特別会計が一定の財投債(国債)を毎年直接引き受けることが経過措置として法律上規定されている。具体的には、毎年度の財投債の引受額や引受条件を前年末の予算編成において、財務大臣と厚生労働大臣が協議し決定し、基金は厚生労働大臣から寄託される年金資金をもって、当該決定額相当の財投債を引き受け、管理運用を行うこととなる。
2.引き受けた財投債の管理運用
財投債は国債として発行される債券であり、金融市場において運用を行っていくことが基本である。しかしながら、財投改革に伴い大量の国債が市場に流入する可能性があり、年金による引受財投債の市場売買が、債券価格の大幅な変動など債券市場を大きく混乱させる契機とならぬよう、慎重に対応することが求められる。したがって、財投債の管理運用に当たっては、経済全般の状況や金利水準、市場の状況等を考慮して、財投債の売買の時期や量について、慎重に判断しなければならない。
3.財投債の運用評価
年金積立金全体の自主運用の評価においては、財投債の引受けが年金財政に与える影響が明らかとなるよう、当該財投債部分も含めて運用の評価を行うことは当然である。
IV 運用に当たっての留意事項
1. リスク管理
公的年金積立金の運用には、下表のように市場の変動に伴うリスク等様々なリスクを伴うが、年金積立金運用においては、これらのリスクを適切に管理することが重要である。
上述のような基本ポートフォリオの検証や見直しの結果として、基本ポートフォリオを変更する必要があると認められる場合には、最適基本ポートフォリオの改訂を速やかに実行すべきである。
財投債の引受けに当たっては、法律上「国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の安定的運営に配慮しつつ」と規定されていることを踏まえ、その引受条件や年限構成については、年金制度にとって不利なものとならないよう、以下のような点に留意して対応すべきである。
しかしながら、大量の国債発行に加え、財投改革により財投債が相当量発行されることから市場の状況を勘案すると、引き受けた財投債のかなりの部分は満期まで保有するという運用になることも予想される。
満期保有の債券については、満期までの間のクーポン収入が運用の目的となり、その間の債券価格の変動によって生ずる評価差額は、本来、認識する必要はない。したがって、満期まで保有する意図をもって引き受ける財投債については、明確に区分した上で、企業会計原則にならい原価法(引受価格と券面額との間に差がある場合には償却原価法)による運用評価とディスクロージャーを行うこととし、参考情報として時価評価を行うことが適当と考えられる。
| 主なリスクの種類 | 概 要 | |
| 市 場 関 連 リ ス ク |
価格変動リスク | 株価、金利、為替等の資産価格の変動によるリスク |
| 信用リスク | 債券、株式等の発行体の倒産等により、返済や受け渡し等が実行されなくなるリスク | |
| 流動性リスク | 資産の流動性が低いために売却時に価格が低下したり、売却そのものが困難になるリスク | |
| オペレーショナル・リスク | 事務上のミスや管理システムの障害によるリスク | |
| コンプライアンス・リスク | 関連法規違反や内部不正によるリスク | |
| その他 | モデルリスク 等 | |
| 負債サイドのリスク | 予定外の債務の変動や運用収益の不足により、積立水準に不足するリスク、給付に必要なキャッシュの確保に係るリスク | |
(1)リスク管理の基本的枠組み
リスク管理の枠組みは、負債に対応した資産構成割合を定めるとともに、資産について、基本ポートフォリオを中心とする「運用の基本方針」を策定することが基本である。次に、このような厚生労働大臣レベルの枠組みの下で、基金は、「管理運用方針」を定めるとともに、個別運用受託機関に運用のガイドラインを示して運用管理を行う。
したがって、運用に伴う様々なリスクについては、厚生労働大臣、基金、運用機関それぞれのレベルにおいて管理する必要がある。
(2)リスク管理の具体的方法
(ア)負債を考慮した資産の総合的なリスク管理
年金積立金の運用は確実な年金給付のために行うものであり、厚生労働大臣は、負債の状況(予定積立金額、積立度合、キャッシュフロー)を考慮して、年金積立金全体としてのリスク管理を行う必要がある。この場合の基本的視点は次の2点である。
基本ポートフォリオの策定及びそれに基づく運用管理のプロセスによるリスク管理である。基本ポートフォリオは、運用結果が負債側の予定する積立金額を下回った場合の年金財政への影響度合というリスクを考慮した上で、最適な資産構成割合として選択されている。
実際の運用においては、積立金の大部分は民間の運用機関に配分され、委託運用される。運用受託機関は、基金が、「運用の基本方針」に基づいて定める「管理運用方針」に従って運用することになる。これに対して、基金は、自家運用するものを含め、厚生労働大臣から寄託された資金全体の運用を総括する。そこでは、資産全体、資産クラスごと及び運用受託機関ごとにきめ細かいリスク管理が不可欠である。具体的には、次のような取組みを行うことが求められる。
なお、基本ポートフォリオは、市場のベンチマークをベースとして策定されているが、基金が運用受託機関を通していわゆるアクティブ運用を目指す場合には、運用受託機関がアクティブ運用として成果を上げることが期待できると判断した根拠を明確にするとともに、期待通りの運用を行っているか、特にリスクの観点から管理しなければならない。
(ウ) 財政検証と基本ポートフォリオの見直し
(エ)キャッシュフローの確保
企業年金等の資産運用においては、予備のためのバッファー資金を持たないフル・インベストメントが理想とされているが、公的年金積立金は巨額であり実際に各種市場に投入するまで時間がかかること、給付に充てるための現金を準備する必要があること等から、積立金の一定割合を流動性の高い短期資産で保有せざるを得ない。
なお、キャッシュフローの確保に関しては、年金特別会計の管理者(社会保険庁)と基金の間で年金特別会計の資金繰りの状況についての緊密な情報交換を行い、効率的な現金管理を図るべきである。
(オ) 運用受託機関の信用リスク等の管理
金融・資本市場の構造変化は運用受託機関及び資産管理機関の経営にも影響を与えるので、運用受託機関及び資産管理機関の信用リスクを管理することが不可欠である。また、運用受託機関同士の吸収・合併(M&A)に伴う運用受託機関の運用体制の変更やファンドマネージャー等の人材の流出にも注意していく必要がある。
資産管理機関については、信用リスクの管理と併せて、分別管理が適切に行われていることを確認する必要がある。この場合、資産管理機関に対し運用指図を行う投資顧問会社にも、資産管理機関の分別管理の状況をチェックさせることが有効である。
(カ)意思決定プロセスの明確化
運用受託機関における意思決定プロセスや責任の所在が不明確であるために、必要な判断がなされない、あるいは判断が遅れ、運用成果に重大な影響が生じるというようなリスクを発生させてはならない。そのために、基金は、運用受託機関がいかなる意思決定プロセスで受託資産の管理を行っているのか管理体制について概略を知っておかなければならない。
基金自身においても、同様の問題を生じないよう管理体制を確立しておかなければならないことはいうまでもない。
また、年金積立金の運用は、厚生労働大臣、基金、運用受託機関という3つのレベルにより担われるが、常に相互に十分な意思疎通を図るとともに、非常事態が発生した場合の対応を事前に確立しておくことが必要である。
2.運用手法と運用機関構成
(1)運用手法と運用機関構成
平均的にみると市場は効率的であり有利な銘柄を継続的に事前に見つけだすことは容易でないことから、市場ポートフォリオに擬した広範な分散投資を行うパッシブ運用が、通常の投資家にとっては結果的には優れた成果を生むことが知られている。運用管理が容易であり、コストが低いこともその成果を支えている。
アクティブ運用は市場の不均衡を利用するもので、情報化のもとで市場の効率化が進んでいる金融資本市場では、そのようなアクティブ運用の機会は存在するものの、その規模は決して大きくない。ただし、アクティブ運用は、効率的な価格形成を通じて、国民経済上、資源の効率的配分に寄与するのであるから、それ自体は否定されるものではない。
したがって、市場に対する影響を配慮する必要があるほど巨額な資金を持つ年金積立金においては、各資産クラスともパッシブ運用を中心とすべきであり、リスクに見合った収益以上の超過収益を目指すアクティブ運用は、確たる根拠がある限定した場合に限るというパッシブ運用中心の姿勢がとられるべきである。
アクティブ運用においては、特化型運用とバランス型運用がある。バランス型運用は、政策的資産構成割合からの乖離の調整を運用機関の裁量に任せることができるといった利点があるが、バランス型のマネージャーの多くは短期的な資産配分効果も追求する運用を行っており、かつ各資産クラスに分散投資が適用されやすいため、多数のバランス型マネージャーを採用すると、相殺取引コストの問題や、ポートフォリオ全体がインデックス・ファンド化するという懸念が大きくなる。その点、特化型運用は、バランス型運用に比較して委託手数料が割高になるとのデメリットがあるものの、運用ガイドラインを適切に設定し、かつ運用スタイル等を効率的に組み合わせれば、運用評価が容易であり、マネージャーの選択を適切に行えば、上のようなバランス型運用の問題点も回避しやすい。
アクティブ運用を行う場合には、以上のような点を考慮して運用機関選択を行うことが重要である。
(2)基金における自家運用
年金積立金の運用は、民間運用機関の専門性を最大限活用する観点から、外部の運用機関に委託する外部委託運用が基本となるが、資金の一部については、基金が自ら運用する自家運用とすることが考えられる。法律上も債券について基金自身による自家運用が認められている。
自家運用には、意思決定に必要な情報収集、取引管理システムの整備やファンド・マネージャーの育成、運用と管理の明確な役割分担とそれを可能とする組織の確保といったコストがかかる。他方で、自家運用は、外部委託運用と比べ、運用報酬及びエイジェンシー・コストを節減することができるほか、職員の市場への理解を深め、実務的なノウハウを蓄積できるなどのメリットがある。したがって、基金においては、人材の確保や体制の充実を図り、一定の範囲内で自家運用を行うことが適当である。
その場合、自家運用は、国内債券パッシブ運用の中心ファンドとして位置づけるとともに、委託運用における資産の入替(リバランス)や運用機関の変更を行う際の調整、引受財投債の管理、国庫納付金の納付等に必要な流動性の確保という役割を果たすものとして、有効に活用することが考えられる。
(3)運用受託機関の数
パッシブ運用について、基本的には、銘柄等が十分に分散されているならば、各資産クラスごとに、ファンドは1つずつ設定すれば足りる。しかし、基金のように資金規模の大きなパッシブ運用の場合は、自家運用ファンドのほか、複数のファンドに運用を委託することが適当と考えられる。
アクティブ運用の場合は、ひとつの資産クラスにおいて必要以上に多数の運用機関に委託すると、その資産クラス全体として分散投資が過剰になるため、超過収益の可能性が低下するとともに、運用報酬・コストの増大を招くことにつながりかねない。超過収益の確保が狙いであることを踏まえ、運用機関の数は運用スタイルごとに絞り込むことが適当である。
(4)運用受託機関の選定、評価
基金は、定性評価及び定量評価に基づき、運用受託機関を選定・評価する。定性評価、定量評価とも評価基準を明確化するとともに、特に、定性評価の重要性に鑑み、重点とする評価項目の設定、合理的な評価方法の確立等を行うべきである。
また、基金は、運用受託機関の新規採用、資金配分及び解約に関するルールを予め明確にする必要がある。特に、運用成績がベンチマークに対し劣後を続けたり、過大なリスクを取っている運用受託機関に対する注意・警告及び解約に至るプロセスについて予めルール化し、迅速に対応すべきである。
3.市場への資金の投入及び回収の分散化
年金積立金の市場運用額は巨額になることから、自ら過大なマーケット・インパクトを蒙ることがないよう努めるとともに、市場の価格形成や民間の投資行動を歪めることがないよう配慮する必要がある。特に、市場への資金の投入及び回収に当たっては、特定の時期への集中を回避することが望ましい。
4.個別銘柄株の選択及び株主議決権の行使の制限
株式運用において、個別銘柄の選択は、企業経営や他の投資家に与える影響を考慮し、基金が直接行うべきではない。
また、正当な投資収益を確保するために、必要に応じて議決権を行使することは、投資収益を目的とする株主としての当然の権利であるが、公的機関である基金が直接議決権を行使する場合、国が民間企業の経営を支配する、あるいはこれに影響を与えようとしているといった懸念を生じさせるおそれがあるので、基金が直接行うのではなく、運用を委託した民間運用機関の判断に委ねるべきである。
具体的には、基金は、運用受託機関への委託に際し、基金の資産を構成する株式に係る議決権の行使は専ら基金の経済的利益を増大させることを目的として行われるものであることを明示し、これを受けて当該株式を運用する運用受託機関は、議決権行使の目的は長期的な株主利益の最大化を目指すものであることを理解の上、その裁量に基づいて行うこととする。
基金は、このような株式議決権の行使に関する基本的考え方を「管理運用方針」に定めるとともに、議決権の行使に関する運用受託機関の方針や行使状況について報告を求めることとする。なお、企業に反社会的行為があった場合の運用受託機関の対応方針や対応状況についても基金は報告を求めることとする。
5.同一企業発行銘柄への投資の制限
分散投資による年金積立金全体の運用リスクの管理、当該有価証券の市場における価格形成の効率性の確保、公的資金による民間企業への影響の排除の観点から、同一企業発行有価証券の保有について一定の制限を課すものとし、具体的には、以下のとおりとする。
6.デリバティブズの利用の制限
年金積立金の運用においては、安全性・確実性及び効率性の確保が重要である。金融派生商品(以下「デリバティブズ」という。)の利用は、この基本的考え方のもとに、価格変動リスクのヘッジ、外貨建資産運用における為替変動リスクのヘッジや原資産の代替を目的とするものに限定し、投機目的の利用は行うべきではない。
デリバティブズの利用限度については、デリバティブズの想定元本が原資産によりカバーされている範囲を上限とする。
また、基金は、運用受託機関からデリバティブズの利用状況について定期的に報告を受け、年金積立金全体のリスクの状況を定期的に確認することが望ましい。
基金の自家運用における利用についても、そのリスク低減効果がもたらす運用の効率性の向上とデリバティブズを利用する上でかかるコストを十分に勘案し、その在り方について検討することが必要である。
7.運用費用の合理的な支出
運用受託機関に支払う運用報酬等運用に要する費用については、運用コストに照らして合理的に判断するものとする。
V 年金積立金の運用の評価
(1)財政検証
年金積立金の運用の評価については、法律上、厚生労働大臣は、毎年度、運用の状況が年金財政に与える影響を検証することとされている。
(2) 基金の運用状況の評価
厚生労働大臣は、年金積立金全体の運用評価の一環として、基金の運用状況を評価する。
(3) 運用受託機関の運用状況の評価
基金は、特化型運用機関に対しては、その委託資産のベンチマークを示し、その市場平均収益率により評価する。また、バランス型運用機関に対しては、委託資産の資産構成割合と各資産クラスのベンチマークを示し、これらから計算される複合市場平均収益率により評価する。
2.移行期間中の運用評価の留意点
移行期間中は、償還時期が到来していない既往の預託分や引受財投債が存在するが、厚生労働大臣による年金積立金の運用評価においては、これらも含め積立金全体の運用評価を行う必要がある。
VI 運用管理体制の確立と専門性の確保
1.運用管理体制の確立
基金においては、運用機関の選定とガイドラインの設定及び資金配分の決定といった「運用の計画段階」、運用機関との契約の管理や運用状況の管理をする「実行段階」、運用機関の評価や基金全体についての評価を行う「評価段階」それぞれについて、担当部署の役割分担を明確にする必要がある。
2.専門性の確保
年金積立金の運用は専門的な分野であり、責任ある運用を行うためには、厚生労働省及び基金は専門性の確保及びそのための人材の育成に努めることが極めて重要である。
VII 基本方針の見直し
「運用の基本方針」は、法律に基づき、少なくとも毎年一回は検討を加え、必要な見直しを行うこととされており、厚生労働大臣は、「運用の基本方針」が常に年金積立金を巡る運用環境や年金財政の状況に即した内容となっているか検証し、必要な修正を加えることになる。特に、基本ポートフォリオについては、策定の基礎となっている経済等の前提条件に著しい変化がない限り維持していくことが基本であるが、他方で、各資産のリスク・リターン特性の変化等運用環境に構造的な変化があり、長期的に運用目的の達成が困難と判断される場合には、最適な基本ポートフォリオへの変更を速やかに検討すべきである。また、年金財政のリスク許容度やキャッシュフローの変化、新たな運用対象商品の出現、新たなリスク管理手法等の出現等を踏まえ、必要な修正を加えることを基本とする。
また、売買執行に伴う取引コストについては、委託手数料、価格スプレッド、マーケット・インパクト等を含めた総コストについて運用受託機関による取組みを促すとともに、その最小化に努めるべきである。
1.年金積立金の運用の評価
財政検証に当たっては、毎年度の運用の結果積み上がる積立金の実績と財政再計算で策定された財政計画上の予定積立金を比較・評価し、計画通りに推移していない場合には、その原因や財政計画への影響等を分析し、必要な対応を取ることとなる。
なお、先に述べたように、公的年金においては実質的な運用利回りが維持される限り、基本的には、年金財政は影響を受けないことから、運用の財政評価は実質的な運用利回りについて行うべきである。
具体的には、基本ポートフォリオと各資産のベンチマーク収益率から計算される複合市場平均収益率により基金の運用パフォーマンスを評価することとなる。基金の運用パフォーマンスが複合市場平均収益率に劣後している場合は、その原因を究明し、基金の管理運用業務の見直し等必要な対応を指示する必要がある。
各資産のベンチマークについては、次に掲げる条件を満たす必要がある。
投資可能性:投資可能な有価証券により構成されていること
透明性・客観性:指標の詳細についてディスクローズされており、銘柄の組み入れ基準が客観的に定められていること
安定性:銘柄の入れ替えが少なく、指標として安定していること
継続性:十分な過去データがあること、将来に向けて長期にわたり利用が可能であること
なお、アクティブ運用においては、運用スタイルに応じた固有のベンチマークが存在しており、かつ基金がそのベンチマークが合理的であると判断する場合には、そのベンチマーク収益率により運用受託機関を評価することも認めるべきである。
運用受託機関の実績が、その運用受託機関に与えられたベンチマークに複数年にわたり劣後している場合は、その原因の究明を運用受託機関に指示し、対応策を講ずることを命ずる必要がある。なお、改善が見られない場合には、予め定めたルールに則り、資金の回収・解約も含め適切な対応をとるべきである。
なお、基金が示すベンチマークその他のガイドラインについては、それが適切なものかどうか常に確認していくことが必要である。
運用受託機関の評価期間については、年金資金が長期投資になじむものであることを踏まえ、米英の代表的な年金基金にも見られる3年から5年程度の期間とすることが適当である。
基金の自家運用については、基金内部の役割分担や責任体制を明確にし、委託運用と同様の基準で基金自らが厳格に評価すべきである。
また、各部署にできるだけ権限を委譲し、迅速かつ責任のある意思決定プロセスを確保することが重要である。
特に自家運用においては、法令遵守(コンプライアンス)上の要請が厳しくなること等を踏まえ、運用執行部門、運用管理部門及び事務部門の役割分担の明確化、権限委譲及び相互牽制機能の強化が重要である。
また、基金が自家運用を行うに当たっては、民間の受託機関に求められる専門性と同水準の専門性が求められる。
資産運用については、民間部門に専門性・経験の蓄積があり、これまでの年金福祉事業団における運用事業の経験を活かしつつ、民間部門の専門性を最大限活用することも有効である。優秀な人材を民間部門から職員として中途採用することも検討に値する。
基金においては、金融・経済に関する高度に専門的な知識・経験を有する投資専門委員を設置することとしており、投資専門委員が核となって基金全体の専門性の向上が図られることが期待される。
また、優秀な人材を育成し、基金においてその能力を発揮させるためには、特殊法人という制約は受けるものの、給与・処遇の面の改善・工夫も検討課題である。
| 審議会議事録等 | HOME |