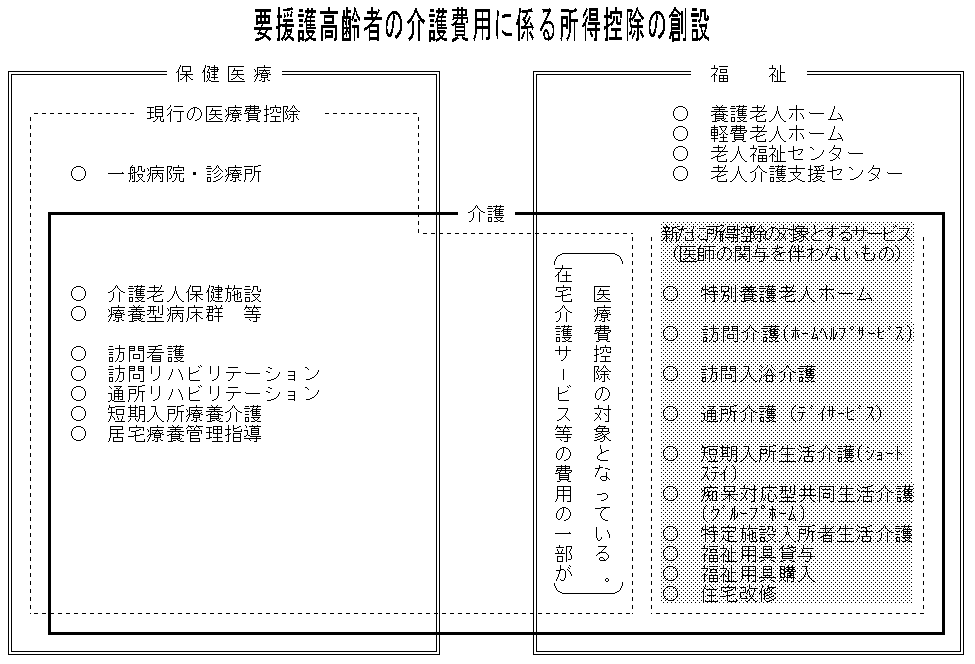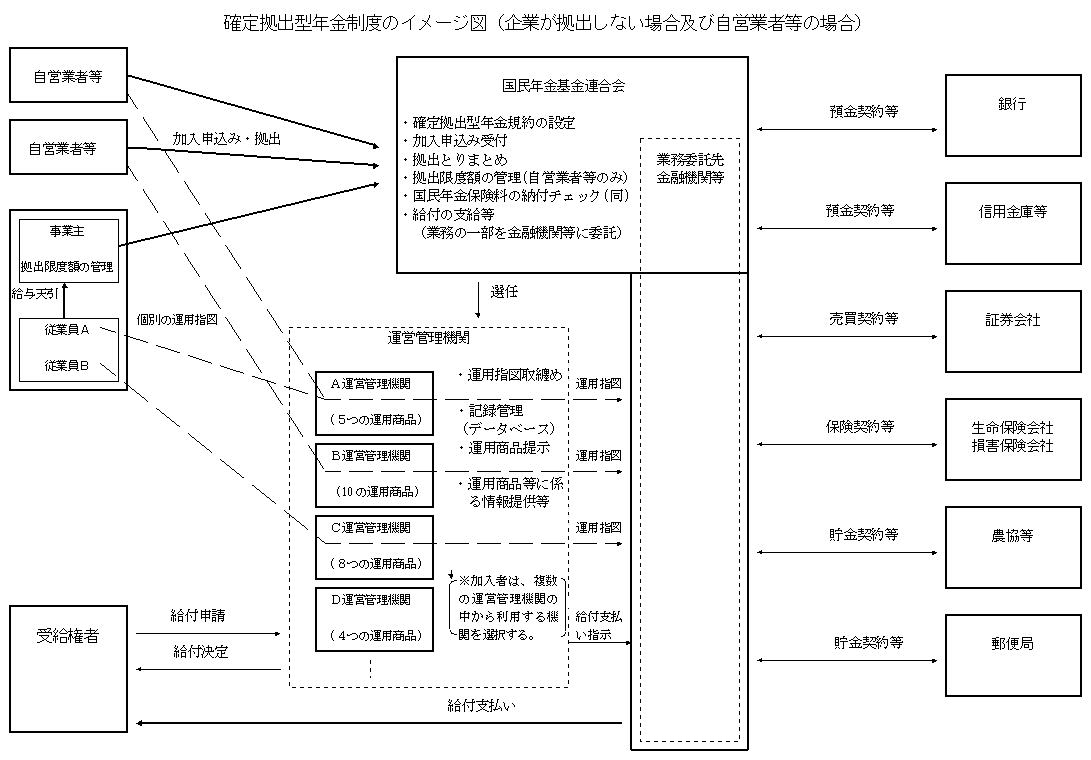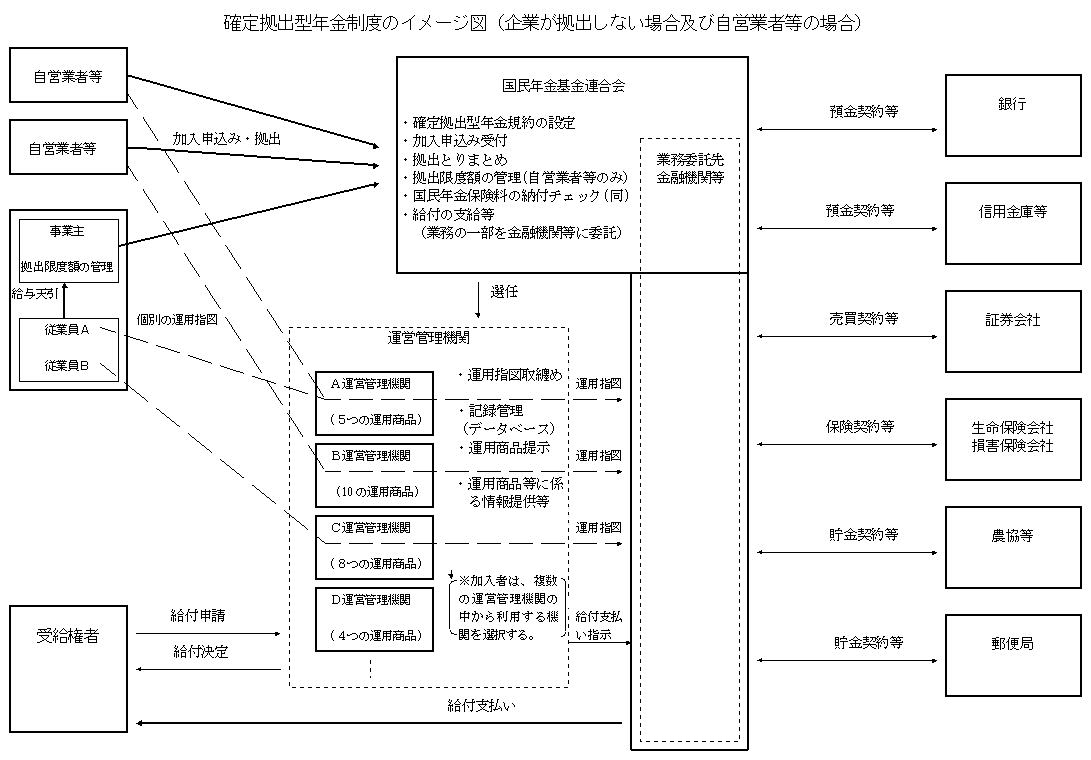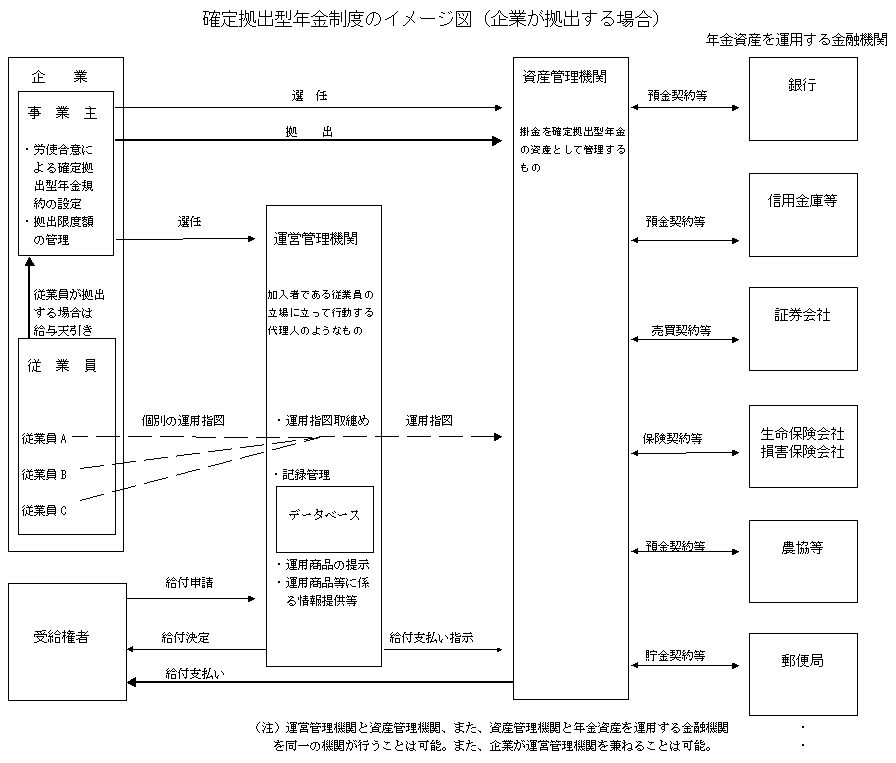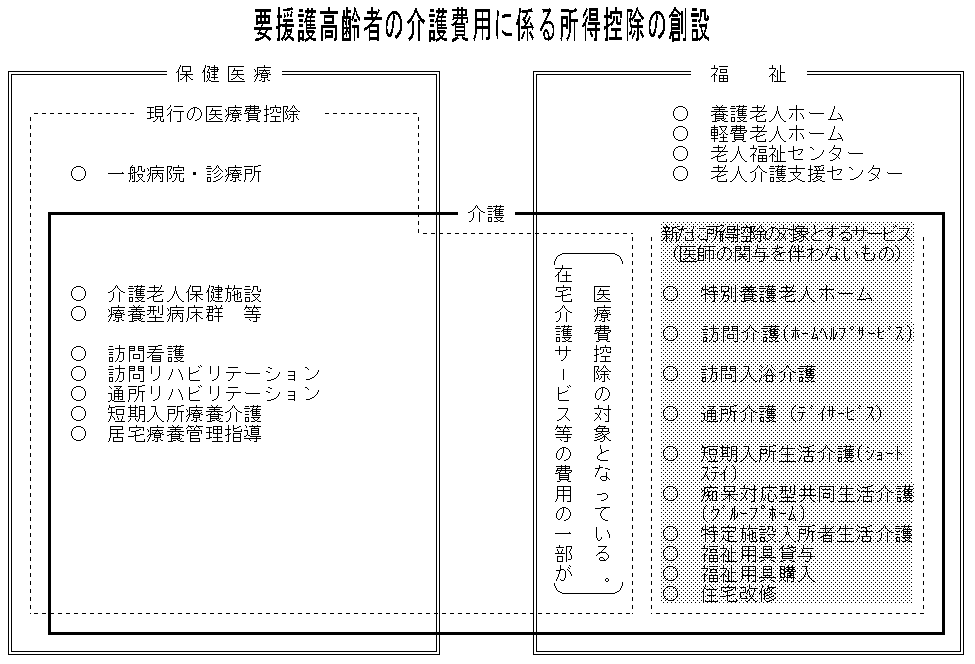平成12年度厚生省税制改正要望項目
○確定拠出型年金制度の創設等による老後の所得保障の充実
○高齢者介護に対する社会的支援の推進
○良質かつ効率的な医療制度の構築
○ニ−ズに対応した社会福祉施策の新たなる展開
○環境衛生、廃棄物対策の推進による生活環境の向上 |
| 1.確定拠出型年金制度の創設等による老後の所得保障の充実 |
○確定拠出型年金制度の創設に伴う税制上の所要の措置
- 21世紀の高齢社会を控え、老後の生活の備えを一層安定したものとするため、平成12年度に確定拠出型年金制度を導入することとしており、制度の創設に向け、税制上の所要の措置を講じること。(制度の具体的な仕組みについては、別添1のとおり)
- <税制改正要望の概要>
- ・拠出時 加入者の拠出は所得控除、企業の拠出は損金算入
- ・運用時 非課税
- ・給付時 年金の場合は公的年金等控除を適用
- 一時金の場合は制度への加入年数を勤続年数とみなして退職所得課税を適用
- ・加入者が離転職し、年金資産を移管した場合には、税制上の措置を継続
- <拠出限度額>
- ・自営業者等(国民年金の第1号被保険者及び第3号被保険者) 年額81万6千円(月額6万8千円)
- (国民年金基金等に加入している場合、国民年金基金等の掛金を控除した額)
- ・企業の従業員(国民年金の第2号被保険者) (加入者の拠出額と企業の拠出額の合算)
年額43万2千円(月額3万6千円)
- (厚生年金基金、適格退職年金等に加入している場合、年額21万6千円(月額1万8千円))
○厚生年金基金の積立不足の償却期間の短縮化
- 厚生年金基金における積立不足の償却期間を「最短3年」から「最短1年」に短縮する。
○要援護高齢者の介護費用に係る所得控除の創設
- ・ 要援護高齢者が福祉サ−ビスを利用するために必要な介護費用を新たに所得控除の対象とする。(別添2参照)
- 新たに所得控除の対象とするサ−ビス
- (1)訪問介護等の在宅サ−ビスを利用するために必要な介護費用
- (2)特別養護老人ホ−ムを利用するために必要な介護費用
- 所得控除の対象となる額 10万円〜200万円
- (注)介護費用のうち医療分野で提供される介護サービスについては、現行の医療費控除の対象となっている。
○民間介護保険加入者に係る所得控除の創設
- 民間介護保険の加入者の支払保険料に対し、現行の生命保険料控除・損害保険料控除と別枠の所得控除(5万円)を創設する。
- (現行)
-
| 生命保険料控除 |
所 得 税
5万円 |
個人住民税
3万5千円 |
個人年金保険料控除(別枠) |
所 得 税
5万円 |
個人住民税
3万5千円 |
-
| 損害保険料控除 |
所得税 長期 1万5千円
短期 3千円 |
個人住民税 長期 1万円
短期 2千円 |
○公益法人等が行う介護保険給付の対象となる社会福祉事業の非課税措置の存続
○介護保険事業計画に基づき整備が必要な地域において開設される老人保健施設の用に供される建物等の固定資産税の軽減措置の継続
- 老人保健施設については、新ゴ−ルドプランの目標が未達成であるため、さらなる整備の促進を図る必要がある。
○介護保険給付の対象となる事業を過疎地域における特別償却制度の対象とすること
- 新たな過疎対策として、介護サ−ビス事業者の参入を促進するとともに、地域における雇用の創出を図る。
○国民健康保険税の課税限度額の見直し
- 国保に加入している介護保険第2号被保険者に係る介護保険料徴収に伴う課税限度額の見直し。
(1)医療提供体制の充実
- ○社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置の存続
- ○医療法人に係る事業税(自由診療分)の軽減措置の存続
- ○医療法人・特定医療法人に係る法人税率の引下げ
- ○特定医療法人に係る要件の緩和
- ○療養支援機器に係る固定資産税の軽減措置の適用期限の延長
- 対象機器 特殊浴槽・介護リフト
- ○救急医療用機器に係る固定資産税の軽減措置の適用期限の延長
- 対象機器 人工呼吸器等
- ○医療機器の耐用年数の短縮
- 医療機器の法定耐用年数を実態に即して短縮する。
- ○中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制)の対象設備の拡大及び適用期限の延長
- ○国立病院・療養所の再編成に伴う移譲等を受けた場合における登録免許税・不動産取得税の軽減措置の適用期限の延長
- ○恩賜財団済生会について固定資産税・都市計画税を非課税とすること
- ○国立看護大学校(仮称)において教育として行う役務の提供に係る消費税の非課税措置の適用
- ○固定資産税等の非課税措置の対象施設となっている医療従事者養成施設の範囲の拡大
(2)医薬品・医療機器産業の振興
- ○中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制)の対象設備の追加及び適用期限の延長
- ○エネルギ−需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)の適用期限の延長
- ○公害防止用設備に係る特別償却制度・固定資産税の軽減措置の適用期限の延長
- ○増加試験研究費の税額控除措置における特別試験研究費の適用対象の拡大
- ○バイオテクノロジ−試験研究設備に係る固定資産税の軽減措置の適用期限の延長
(3)医療制度の見直し関係
- ○医療保険制度の改正に伴う税制上の所要の措置(検討中)
- ○医療提供体制の見直しに伴う税制上の所要の措置(検討中)
(4)その他
- ○国民健康保険税の軽減基準額の見直し
- ○障害者控除及び寡婦(寡夫)控除の引上げ
- ・ 障害者控除及び寡婦(寡夫)控除
所得税 27万円(現行)→36万円
住民税 26万円(現行)→32万円
-
○精神障害者地域生活支援センタ−の法定化に伴う税制上の所要の措置
○(財)日本障害者スポ−ツ協会を特定公益増進法人とすること
○消費生活協同組合における自然災害共済事業新設に伴う損害保険料控除及び異常危険準備金の適用
| 5.環境衛生、廃棄物対策の推進による生活環境の向上 |
(1)環境衛生関係営業の振興
- ○中小企業新技術体化投資促進税制(メカトロ税制)の適用期限の延長
- ○エネルギ−需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)の適用期限の延長
- ○公害防止用設備に係る固定資産税の軽減措置の適用期限の延長
- ○公衆浴場に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置の拡大
- ○日帰り介護事業を実施するシルバ−スタ−登録旅館に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置の創設
(2)ダイオキシン対策
- ○公害防止用設備に係る特別償却制度の対象設備の拡大及び適用期限の延長
- ・ 廃油及び廃プラスチック類を処理する産業廃棄物処理用設備等
(3)リサイクルの推進
- ○再商品化設備等の特別償却制度の対象設備の拡大及び適用期限の延長
- ・容器包装リサイクル法の対象となる再商品化設備の追加
・家電リサイクル法の対象となる再商品化設備の追加
- ○廃棄物再生処理用設備に対する固定資産税の軽減措置の対象設備の拡大及び適用期限の延長
- ○廃棄物減量推進小売店に対する事業所税の特例措置の創設
- ○再生資源分別回収設備の特別償却制度の適用期限の延長
(4)PFI法関係
- ○PFI法の成立に伴う税制上の所要の措置
(5)その他廃棄物対策の推進
- ○最終処分場に係る維持管理積立金制度の適用期限の延長
- ○廃棄物処理施設に係る固定資産税軽減措置の適用期限の延長
- ○産業廃棄物の処理に係る特定施設の用に供する土地等に係る事業所税・特別土地保有税の非課税措置の適用期限の延長
- ○広域臨海環境整備センタ−業務の用に供する土地等に係る非課税措置の適用期限の延長
(6)その他制度の見直し関係
- ○廃棄物処理法等の改正に伴う税制上の所要の措置(検討中)
問い合わせ先
厚生省大臣官房政策課
担当:宮崎敦文、森真弘
代表[現在ご利用いただけません](内線2254)
(別添1)
確定拠出型年金制度の具体的な仕組みについて
1 制度の基本的な考え方
(1)確定拠出型年金制度の必要性
- 現行の確定給付型の企業年金等は、公的年金を補完するものとして機能してきてい る。しかしながら、以下のように確定給付型の企業年金等だけでは社会経済環境の変 化に十分に対応できなくなっており、確定給付型の企業年金等に加え、新たな選択肢 として、自己責任を原則とする確定拠出型年金制度を導入することが必要である。
- (1) 確定給付型の企業年金等(厚生年金基金、適格退職年金及び国民年金基金)につ いては、中小企業や自営業者に普及しておらず、確定給付型の企業年金等だけでは、 実態として公平に自助による老後の所得保障の実現を図ることが困難である。
- (2) 若年層を中心とする転職に対する意識の変化や、国際競争の激化や産業構造の変 化に伴う企業の雇用慣行の変化を背景に、近年、労働移動が加速している。また、 企業の賃金体系等が長期雇用を前提としたものから能力主義的なものに変化しつつ ある。こうした中で、個人の持分が明確でなく、また、長期勤続者が有利である確 定給付型の企業年金等では、転職の際の年金資産の移管(ポータビリティー)が十 分確保されておらず、また、転職する者に不利となり、労働移動への対応が困難で ある。
- (3) 景気が大きく変動する中では、企業の業績の影響を受けることから、確定給付型 の企業年金だけでは従業員にとって老後の備えが不安定になりやすい。
- 例えば、確定給付型の企業年金においては、景気変動等により運用環境が変化し ていく中、積立金の実際の利回りが予定利回りを下回る場合には、積立不足が生じ、 給付水準の引き下げや、予定された給付を履行するための追加的な拠出が必要とな る。また、景気変動等の影響を受けて企業が倒産した場合には、期待する企業年金 や退職金を十分受けられないケースも出てくることとなる。
- 実際、近年の低金利状態が影響し、給付水準の引下げや追加拠出も多く見られる ほか、更に企業年金の解散等も増加しており、従業員にとって不利益となるケース が出てきている。
- こうした中で、受託者責任の明確化、個人が自由意思で運用指図が行える環境の整 備、制度の周知徹底等を前提として、個人が自己責任において運用を行い、その運用 実績により給付が行われるという仕組みの方がむしろよいと感じる者が増加していく と考えられ、確定給付型の企業年金に加え、確定拠出型年金を組み合わせることによ り、国民に老後の安心感を与えることができるものと考えられる。
- また、確定拠出型年金は、確定給付型の企業年金と異なり追加拠出が求められない ため、中小企業にとって導入が容易であるほか、個人ごとの持ち分が明確で転職等の 労働移動に対応することができる。
(2)確定拠出型年金制度の位置づけ等
- (1) 確定拠出型年金制度は、老後の所得の確保のため、公平の観点から設定される限 度額の範囲内で企業又は個人が掛金を拠出し、個人ごとの持ち分が明確となった年 金資産について個人が自己責任において運用を行い、原則として60歳に到達した 以降、掛金及びその運用収益の総額を原資として、年金又は一時金として受給する 制度であり、現行の確定給付型の企業年金等に加え、新たな選択肢の1つとして導 入する。
- (2) 今後、世代間扶養の考え方に立った強制加入の公的年金を基本としつつ、自己責 任の考え方に立つ確定拠出型年金と、企業等の集団の相互扶助に基づく確定給付型 の企業年金等を組み合わせて、高齢期の多様な生活需要に対応する。
2 具体的な仕組み
(1)制度に加入し得る者の範囲(対象者)
- ○ 第3号被保険者を含め65歳未満の国民年金の全被保険者を対象とする。
(2)制度への加入・拠出
イ 企業が拠出する場合の企業の従業員
- (イ) 加入
- (1) 企業は、労使合意に基づいて制度の内容を規定した確定拠出型年金規約を定め、 主務大臣の承認を受ける。
この場合、企業の中で事業所等の単位ごとに確定拠出型年金規約を定めることを認める。また、複数企業により規約を定めることも認める。
(確定拠出型年金規約に規定する主な項目)
- ・対象者の範囲
- ・企業の拠出の額の計算方法(企業が規約を定める場合に限る)
- ・運用商品の範囲に関する基本的考え方
- ・運用指図の方法
- ・預替えの機会の頻度
- ・企業の拠出に係る受給権付与の条件(企業が規約を定める場合に限る)
- ・支給事由
- ・支給形態、方法
- ・運営管理機関及び資産管理機関の具体的な名称等
- ・事務費用の負担方法や負担割合
- など
- (2) 企業の従業員は、確定拠出型年金規約の定めにしたがって加入者となる。
- なお、例えば既存の企業年金からの一部移行に際して新規採用の従業員から適用することなど、既存の企業年金や退職金との関係も含めて全体として公平な取扱いを行っていると認められる場合には特定の者を加入者とすることを認める。
- (ロ) 拠出
- (1) 企業は、確定拠出型年金規約に基づき、掛金を拠出する。
- (2) 従業員も、企業の拠出に加え、自ら拠出することができる。この場合、掛金額 は従業員が任意に決定する。
- (3) 拠出には限度額を設ける。
- 限度額は、企業の拠出額と個人の拠出額との合計で年額43万2千円(月額3 万6千円)とする。
ただし、厚生年金基金、適格退職年金等に加入している場合には、限度額は年 額21万6千円(月額1万8千円)とする。
- (4) 拠出限度額の管理は企業が行う。
- (企業は、個人別リスト等により、毎年の拠出額が企業拠出分・個人拠出分合計 で拠出限度額の範囲内であることを確認する義務を負う。)
- (5) 企業は、従業員の掛金について従業員の給与から天引きし、企業の掛金ととも に、予め選定した資産管理機関(拠出された資産を企業財産から分離して保全す る等のための機関として制度上位置付けるもの)に払い込む。
- (6) 資産残高は、個人ごとに記録管理される。この記録管理は、予め選任した運営 管理機関(記録管理のほか個別の運用商品の提示や個別の運用商品等に係る情報 提供等を行うための機関として制度上位置付けるもの)が行う。
(資産管理機関)
- (1) 次の要件を満たすことができる者を資産管理機関とする。
- ・拠出された掛金を、会社財産又は加入者の財産から明確に分離し、年金資産として保全することができること
- ・運営管理機関の選定する運用商品について、当該商品を提供する金融機関と契約し、又は自ら運用商品を用意することにより、対応することができることなど
- (2) 確定拠出型年金規約を定める企業は、加入者のため確定拠出型年金規約を適切に実施することができる資産管理機関を選任し監督する義務を負い、当該機関と資産管理契約を締結する。
- (3) 資産管理機関については、その行うべき業務等を法定するとともに、法令及び確定拠出型年金規約を遵守し、加入者に忠実に業務を遂行する責任を負うものとする。
(運営管理機関)
- (1) 運営管理機関となろうとする者は、次の業務の全部又は一部を適切に実施できる体制が整っているなどの一定の適格要件を満たすものとして、主務大臣の登録を受けなければならない。
- ・個別の運用商品の選定
- ・個別の運用商品等に係る情報提供
- ・加入者個人の運用指図のとりまとめ
- ・加入者個人ごとの持分等に係る記録管理
- ・給付に係る事務など
- (2) 運営管理機関については、その行うべき業務等を法定するとともに、法令及び確定拠出型年金規約を遵守し、加入者に忠実に業務を遂行する責任を負うものとする。
- (3) 確定拠出型年金規約を定める企業は、加入者のため確定拠出型年金規約を適切に実施することができる運営管理機関を選任し監督する義務を負い、当該機関と運営管理契約を締結する。
- (4) 企業は、自ら運営管理機関に係る業務の一部又は全部を行うことができる。さらに、資産管理機関が運営管理機関を兼ねることも認める。
- (ハ) 離転職時のポータビリティー等
- (1) 加入者が離転職した場合には、加入者の申出に基づき、離転職先の制度に加入 者の年金資産を移管する。
- (2) 加入者が、一定期間(例えば6か月)以上年金資産の移管の申出を行わない場合、国民年金基金連合会の実施する制度に加入者の年金資産を自動的に移管する。
- (3) 企業が拠出した掛金であっても、少なくとも3年以上勤続する者に対しては全 額受給権を付与し、離転職時に年金資産の移管を認めなければならない。
ロ 企業が拠出しない場合の企業の従業員、自営業者等
- (イ) 加入
- (1) 企業が拠出しない場合の企業の従業員、自営業者等の加入の申込みの受付け、 掛金のとりまとめ等を行うための機関として国民年金基金連合会を制度上位置付 け、それを法律上規定する。
- (2) 国民年金基金連合会は、確定拠出型年金規約を定め、主務大臣の承認を受ける。
- (3) 従業員、自営業者等は、国民年金基金連合会に申請することにより、制度に加 入する。
- (4) 国民年金基金連合会は、基礎年金番号により、重複加入の審査等を行う。
- (ロ) 拠出
- (1) 従業員、自営業者等は、掛金額を任意に決定し、拠出する。ただし、国民年金 の保険料を滞納している期間等は、拠出することができない。
- (2) 企業は、従業員が拠出する場合において、従業員の拠出に加え、上乗せ拠出を 行うことができる。
- この場合、企業は、あらかじめ行った労使合意に基づき掛金を拠出する。
- (3) 拠出には限度額を設ける。
- 企業の従業員については、限度額は、個人の拠出額と企業の拠出額(企業が上 乗せ拠出を行う場合)の合計で年額43万2千円(月額3万6千円)とする。
- ただし、厚生年金基金、適格退職年金等に加入している場合には、限度額は年 額21万6千円(月額1万8千円)とする。
- 自営業者等については、限度額は、年額81万6千円(月額6万8千円)とす る。ただし、国民年金基金等に加入している場合には、年額81万6千円(月額 6万8千円)から国民年金基金等の掛金の額を控除した額を限度額とする。
- (4) 拠出限度額の管理は、企業の従業員については企業が、自営業者等については 国民年金基金連合会が行う。(企業は、個人別リスト等により限度額の管理を行 う。また、国民年金基金連合会は、基礎年金番号等により限度額の管理を行う。)
- (5) 企業の従業員については、企業は、従業員の掛金について従業員の給与から天 引きし、企業の上乗せ拠出に係る掛金とともに(企業が上乗せ拠出を行う場合)、 国民年金基金連合会に払い込む。また、自営業者等については、自ら国民年金基 金連合会に掛金を払い込む。
- (国民年金基金連合会における運営管理機関及び資産管理機関)
- (1) 国民年金基金連合会は業務を行うことを希望する登録運営管理機関をすべて選
- 任するものとする。
- (2) 加入者は、加入の申込み時に、国民年金基金連合会に選任された運営管理機関
- の中から、加入者自身に係る運営管理業務を行う機関を指定する。
- (3) 国民年金基金連合会が実施する確定拠出型年金制度においては、国民年金基金
- 連合会に掛金が払い込まれることにより会社財産又は加入者の財産からの分離が
- 果たされるようにすることから、資産管理機関は置かれない。
- (4) 国民年金基金連合会の他の事業に係る財産との混同が生じないよう区分経理す
- るなどの措置をとる。
- (ハ) 離転職時のポータビリティー等
- (1) 個人ごとの資産残高は、運営管理機関によって記録管理されるとともに、加入 者が離転職した場合には、加入者の申出に基づき、離転職先の制度に加入者の年 金資産を移管する。
- (2) 従業員の拠出に加えて行われる企業の上乗せ拠出については、拠出時に全額受 給権を付与し、離転職時に年金資産の移管を認めなければならない。
ハ 公務員の取扱い
- ○ 公務員については、個人の拠出は企業の従業員と同様に認められる。また、事 業主の拠出の可否については、公務員関係省庁において引き続き検討する。
(3)運用
イ 運用指図
- (1) 加入者に係る年金資産については、企業拠出分、個人拠出分を問わず、運用の 指図は加入者が行う。
- (2) 加入者は、運用の指図を運営管理機関に対して行い、運営管理機関は、加入者 ごとの運用指図をとりまとめた上で、企業が拠出する場合の企業の従業員につい ては資産管理機関に、企業が拠出しない場合の企業の従業員および自営業者等に ついては国民年金基金連合会に指図を行う。この場合、資産管理機関または国民 年金基金連合会は、運営管理機関の指図に基づいて、個別の運用商品を提供する 金融機関と運用に関する契約を締結する。
- (3) 個々の従業員の意思に反して事業主が一括して運用指図することは認めない。
ロ 運用商品の範囲
- (1) 運用商品は、時価評価が可能で流動性に富んでいること等の要件を満たすもの とする。
- (2) 具体的には、金融商品のうち、預貯金、公社債、投資信託、保険等とする。 (動産、不動産は運用商品として認めない。個別株、自社株についても運用商品 として認める。)
ハ 個別の運用商品の提示・運用商品の預替え・情報提供等
- (1) 運営管理機関は、加入者に対して一定数以上の個別の運用商品の提示、一定の 頻度での預替えの機会の提供、個別の運用商品等に係る情報提供等を責任をもっ て行うものとする。
- (具体的な内容)
- (2) 運営管理機関は、確定拠出型年金規約に示された運用商品の範囲に関する基本 的考え方に従って、3つ以上の商品を選定し、加入者に提示する。
- 運用商品を選定する場合には、元本確保商品を1つは選定するものとし、個別 株(自社株を含む)又は個別社債を運用商品に選定する場合には、それらとは別 に3つ以上の商品を選定しなければならないものとする。
- (3) 運用商品の預替え頻度については、少なくとも3ヶ月に1回以上は預替え機会 が提供されるようにする。
- (4) 運営管理機関は、加入者に対して次のような運用商品等に係る情報提供を行う ものとする。この場合、運営管理機関は、提示した個別の運用商品を推奨しては ならない。
- (提供すべき情報)
- ・個別の運用商品のリスクリターン特性
- ・個別の運用商品の資産構成
- ・個別の運用商品の価額、過去及び現在の運用利回り、運用の見込みが示され うる場合の運用見込み
- ・加入者ごとの資産残高(運用商品ごとの現在の価額等)
- 等
- (5) 確定拠出型年金規約を定める企業及び国民年金基金連合会は、確定拠出型年金 制度の内容(確定拠出型年金規約の内容)に関する情報の提供を行うものとする。
- (6) 一般的な投資教育のあり方については検討中。
(4)給付
- (1) 給付形態は、年金支給又は一時金支給とする。
- (2) 一定の年齢(例えば60歳)への到達、死亡及び高度障害を支給事由とする。
- (3) 給付時は、加入者からの申請に基づいて運営管理機関が受給資格を確認し、そ の通知に基づいて、企業が拠出する場合の企業の従業員については資産管理機関 が、企業が拠出しない場合の企業の従業員及び自営業者等については国民年金基 金連合会が支給を行う。
- (4) 加入者は、60歳以降の任意の年齢時から受給を開始することができるが、遅 くとも70歳までに受給を開始しなければならないものとする。
3 税制について
- (1) 確定拠出型年金に係る税制上の措置については、拠出時・運用時非課税、給付時 課税とすることを基本とする。
- (2) 本人拠出は所得控除、企業拠出は損金算入とする。
- (3) 運用時は非課税とする。
- (4) 給付時課税については、年金の場合は公的年金等控除を適用する。また、一時金 の場合は、この制度への加入年数を勤続年数とみなして退職所得課税を適用する。
- (5) 加入者が離転職し、年金資産を移管する場合には、税制上の措置を継続する。
4 法整備について
- (1) この制度については、制度の普及促進及び加入者の保護を図る観点から、既存の 企業年金等に係る関連法律とは別に確定拠出型年金法(仮称)の整備を行う。
- (2) 制度全体として加入者の保護を図る観点から、次の事項について法定化する。
- ・確定拠出型年金としての適格性を担保する観点から、主務大臣は、確定拠出型年 金規約を審査し、承認を行う。
- ・確定拠出型年金規約を定める企業、国民年金基金連合会、運営管理機関及び資産 管理機関は、法令及び規約を遵守し、加入者に忠実に業務を遂行する責任を負う。
- ・主務大臣は、確定拠出型年金規約を定める企業、国民年金基金連合会、運営管理 機関、資産管理機関に対して必要な監督を行う。
5 既存制度からの移行
- (1) 既に既存の企業年金等がある企業においては、新規採用の従業員から確定拠出型 年金を導入することや、各従業員について今後の将来期間分から確定拠出型年金を 導入するという形で確定拠出型年金に移行することができる。
- (2) 一定の条件のもとで、既存の企業年金等の過去期間分に係る年金資産等を個人ご とに分配し、確定拠出型年金に移管することも認める方向で検討する。
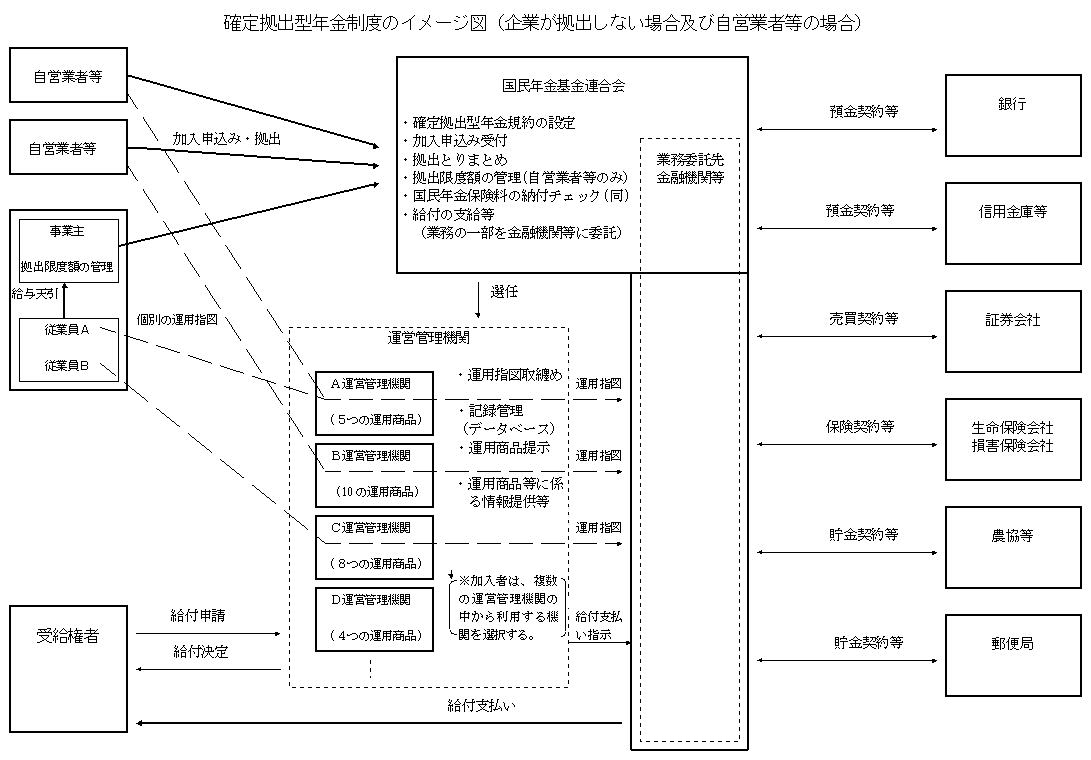
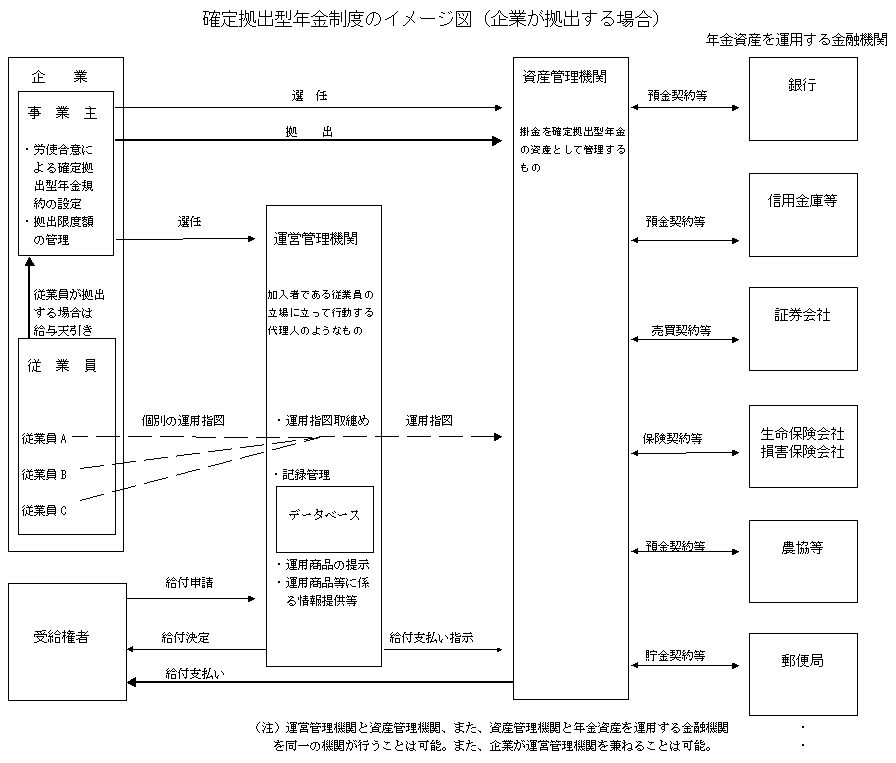
(別添2)