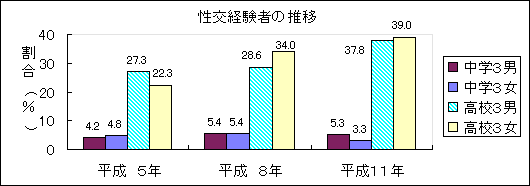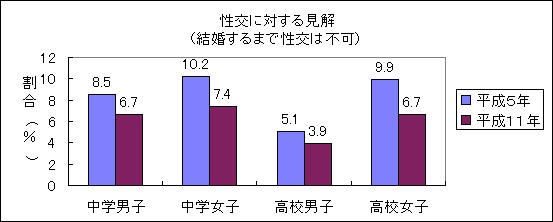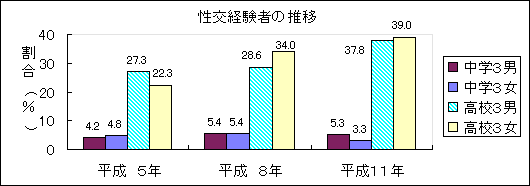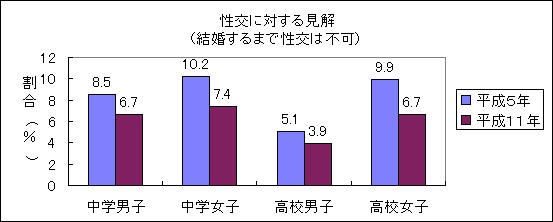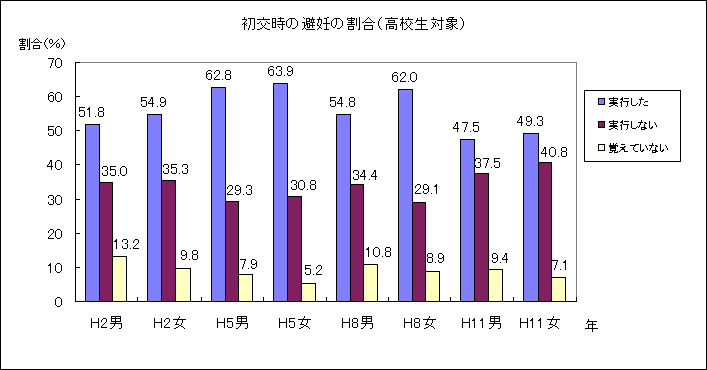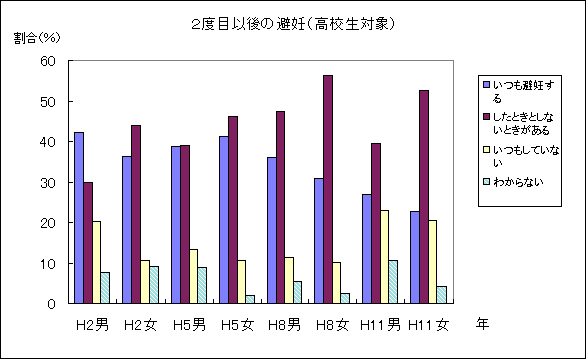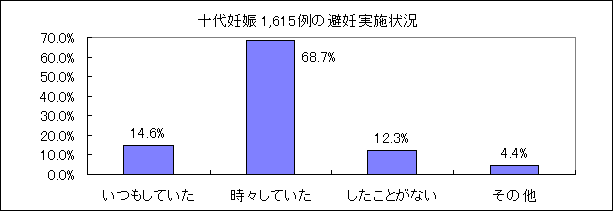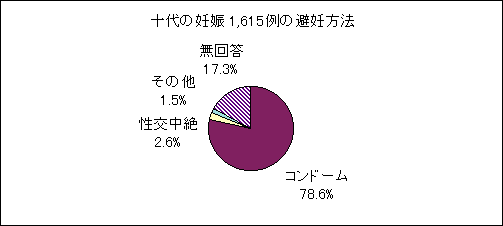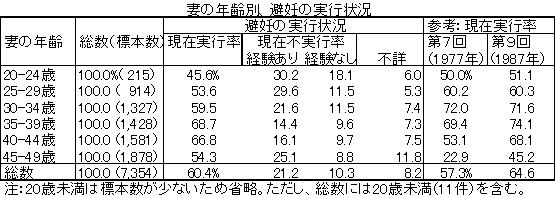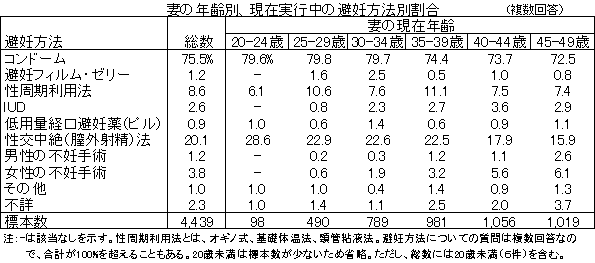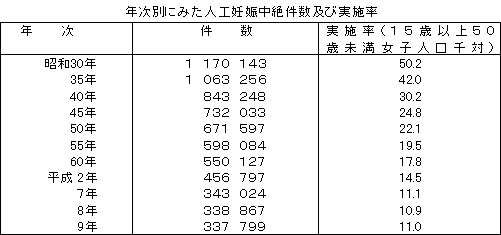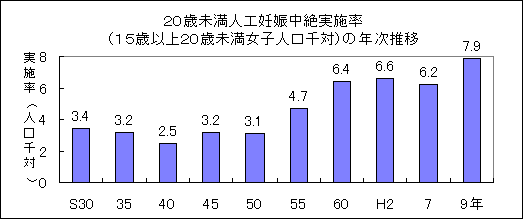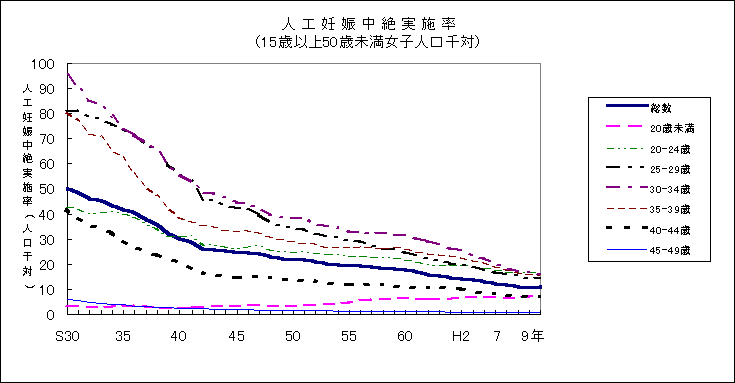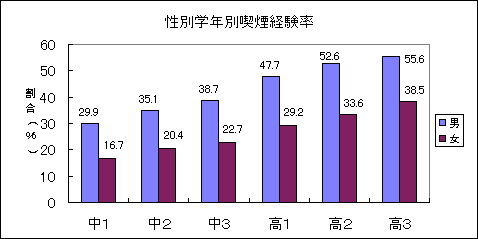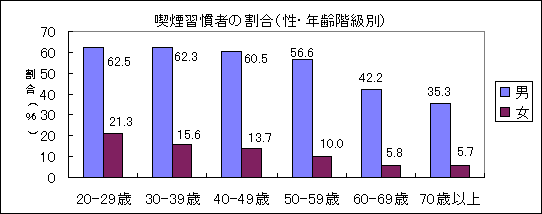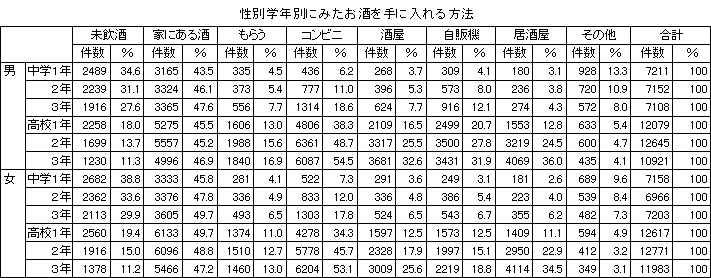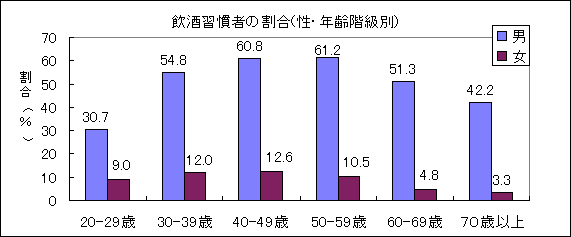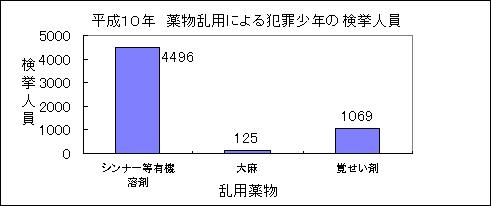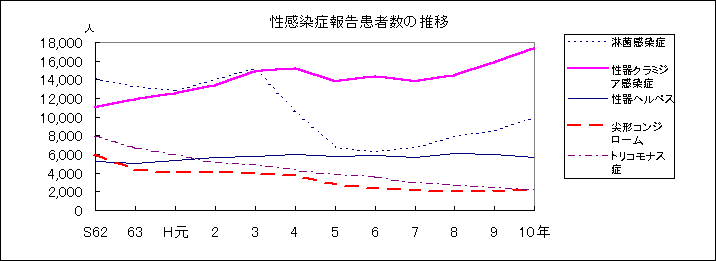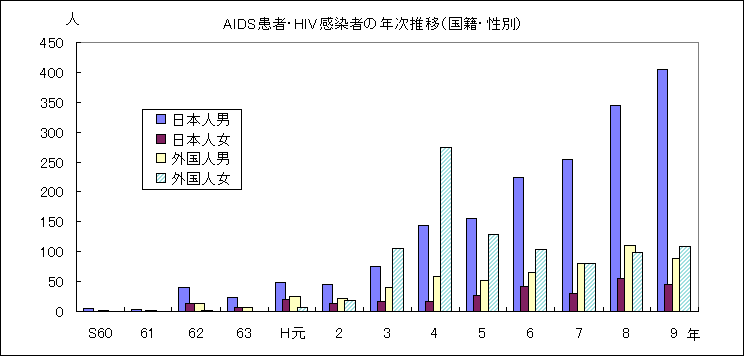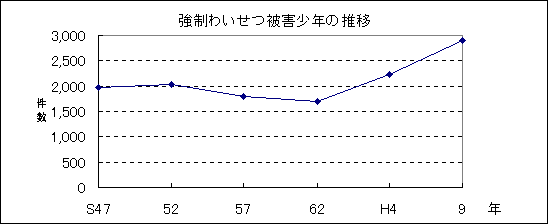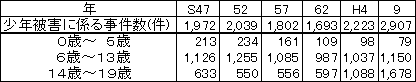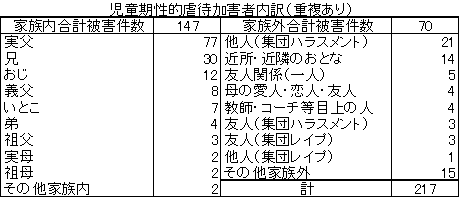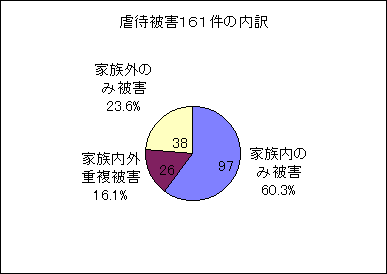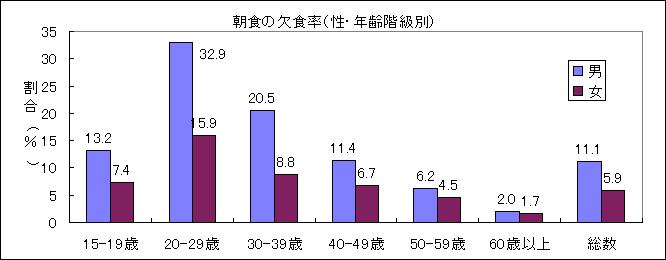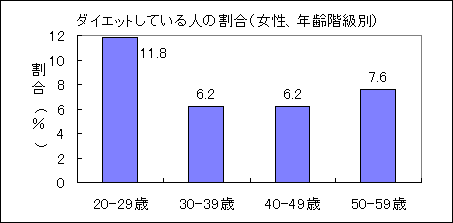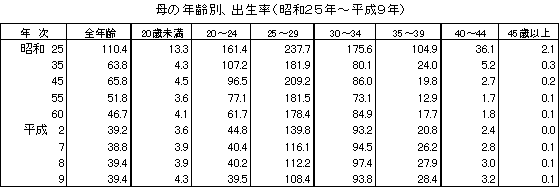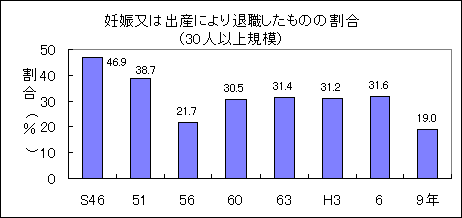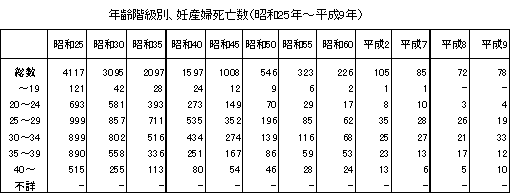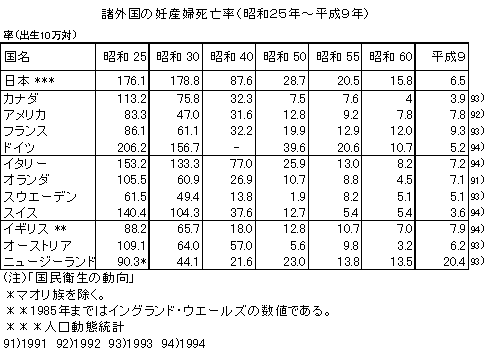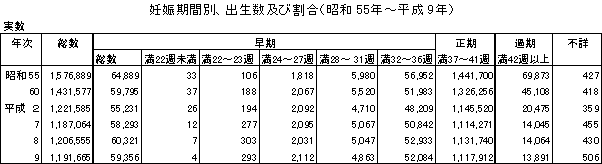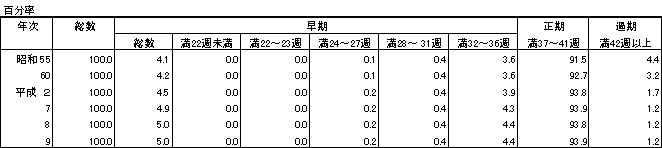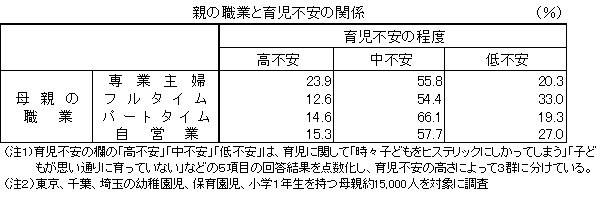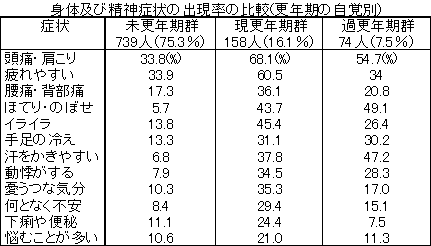生涯を通じた女性の健康施策に関する研究会報告書について
6月17日、第8回生涯を通じた女性の健康施策に関する研究会(最終回)が行われ報告書がとりまとめられたところであるが、修正が必要な部分があり座長に一任されていたところである。
今般、その修正が終了し最終報告書がまとまったので公表する。
生涯を通じた女性の健康施策に関する研究会
1.目的
- 生涯を通じた女性の健康づくりを推進する観点から、さまざまな角度から女性の健康に関する問題点を整理し、具体的施策と推進方法について総合的に研究を行い、生涯を通じた女性の健康支援施策に資するものとする。
2. 背景
- 平成7年、北京において開催された第4回世界女性会議において、リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)については重要なテーマとして討議された。
我が国の女性の健康施策においては、平成8年12月に策定された「男女共同参画2000年プラン―男女共同参画社会の形成の促進に関する平成12年(西暦2000年)度までの国内行動計画―」に、重点目標として「生涯を通じた女性の健康支援」が盛り込まれたところである。
これらの新しい動きを踏まえ、横断的な新たな検討が求められている
3. 委員(別紙のとおり)
- 専門家、行政関係者、一般等(各分野で活躍中の女性を中心に、保健、医療、教育、労働等の各分野を包括して広範囲から人選した委員)
4.検討内容
- 女性の健康等に関わる現行の行政施策に対して、総合的、横断的な見地から評価、提言をいただく。〔提言のまとめは報告書(案)35p第3章〕
5. スケジュール
| 第1回研究会 |
平成10年5月14日 |
関連省庁・関連課の施策説明 |
| 第2回研究会 |
7月 8日 |
妊娠可能期 |
| 第3回研究会 |
11月14日 |
幼児期〜思春期 |
| 第4回研究会 |
平成11年1月21日 |
閉経期以後 |
| 第5回研究会 |
3月25日 |
報告書の検討(1) |
| 第6回研究会 |
4月21日 |
報告書の検討(2) |
| 弟7回研究会 |
5月20日 |
報告書の検討(3) |
| 第8回研究会 |
6月17日 |
報告書まとめ |
生涯を通じた女性の健康施策に関する研究会
(委員)
|
秋元 かおる |
ゼンセン同盟常任中央執行委員 |
| ◎ |
安達 知子 |
東京女子医科大学産婦人科助教授 |
|
稲田 恵子 |
港町診療所産婦人科保健婦 |
|
北村 邦夫 |
日本家族計画協会クリニック所長 |
|
早乙女 智子 |
東京都職員共済組合青山病院産婦人科医 |
| ○ |
住友 眞佐美 |
東京都衛生局母子保健課長 |
|
田能村 祐麒 |
田能村教育問題研究所長 |
|
坪井 美智子 |
都立小石川高校養護教諭 |
|
長井 聡里 |
松下電工(株)本社健康管理室室長 |
|
野末 悦子 |
コスモス女性クリニック院長 |
|
東 優 子 |
お茶の水女子大学大学院 |
|
丸本 百合子 |
同愛記念病院産婦人科医 |
|
三橋 順子 |
さいとうクリニック副院長 |
|
毛利 多恵子 |
毛利助産所助産婦 |
○ 座長、◎副座長
-
- (事務局)
厚生省 児童家庭局母子保健課
-
- ★ なお、以下の省庁の担当課から出席いただき、現行施策についての説明を聴取した。
| 総理府 |
男女共同参画室 |
| 警察庁 |
生活安全局少年課 |
| 文部省 |
涯学習局男女共同参画学習課 |
| 文部省 |
育局学校健康教育課 |
| 労働省 |
女性局女性労働課 |
照会先:厚生省児童家庭局母子保健課
新野(3178)武田(3179)
電話 [現在ご利用いただけません](代)
03-3595-2544(直)
生涯を通じた女性の健康施策に関する研究会
報告書
平成11年 7 月
厚生省児童家庭局母子保健課
目 次
第1章 はじめに
第2章 女性の生涯の各ステージごとにみた健康面の現状と問題点
- 第1節 思春期
- 1 性意識・性行動、避妊、人工妊娠中絶
2 喫煙、飲酒、薬物乱用
3 性感染症
4 いわゆる援助交際等の売買春、性的虐待
5 食生活の乱れと拒食・過食
-
- 第2節 出産可能期
- 1 月経障害
2 不妊
3 妊娠・出産・産褥
4 育児ストレス等
-
- 第3節 閉経期以降
- 1 更年期障害
2 骨粗しょう症
第3章 今後、重点を置くべき生涯を通じた女性の健康施策のあり方について
- 1 各省庁総合的、横断的、計画的な生涯を通じた女性の健康施策の推進体制の創設
2 女性の健康施策の目標と具体的施策の提言
3 新たな課題への対応
参考資料(ここでは省略する)
- 1 WHO出産科学技術についての勧告
2 WHOが推進するお産のケア、実践ガイド
3 年齢別月経中の身体的不快症状
4 主なる人口動態統計と人口
-
- (注:図表中、Sは昭和、Hは平成を表す。)
第1章 はじめに
リプロダクティブヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康/権利)という概念は、子どもを産む産まない、産むとすればいつ、何人産むかを女性が自己決定する権利を中心課題とし、広く女性の生涯にわたる健康の確立を目指すものであり、平成6年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱されてから、その重要性が国際的に認識されてきている。
我が国においても、平成8年6月の母体保護法改正の際、参議院厚生委員会において、「リプロダクティブヘルス/ライツの観点から、女性の健康等に関わる施策に総合的な検討を加え、適切な措置を講ずること」との附帯決議がなされるとともに、同年12月に策定された「男女共同参画2000年プラン−男女共同参画社会の形成の促進に関する平成12年(西暦2000年)度までの国内行動計画−」の重点目標の中に、リプロダクティブヘルス/ライツの観点から、「生涯を通じた女性の健康支援」が盛り込まれたところである。
このような流れの中で、近年、女性の健康施策が拡充されてきたところであるが、一方 で女性の健康支援施策は各省庁にまたがって実施されており、必ずしも総合的・横断的な対応がなされているとはいえない状況にある。
女性の社会進出の進展、高齢出産の増加、更年期以降の女性の増加等、女性の健康を取り巻く環境が急速に変化している今日、女性の生涯にわたる健康支援はますます重要な課題となっており、女性の健康施策を総合的・横断的に推進することがより一層求められている。
このため、「生涯を通じた女性の健康施策に関する研究会」が平成10年5月に厚生省児童家庭局に設置され、それ以降本研究会において、女性の健康を取り巻く状況についての現状を把握するとともに、現在実施されている女性の健康に係る施策の評価を行い、新たな施策の方向性について検討してきたところであり、今般、この検討結果をとりまとめたので報告する。
なお、生涯を通じた女性の健康に関連する課題にはこのほか、生活習慣病、乳がん、子宮がん等があるが、この研究会では、女性の性と生殖を中心とした以下の項目について検討を行った=@
第2章 女性の生涯の各ステージごとにみた健康面の現状と問題点
女性は生涯の各ステージごとに様々な健康課題に直面する。本章ではそれぞれのステージごとの健康課題についての現状と問題点、それに対する施策について分析・評価し、今後の対応のあり方を検討することとする。
第1節 思春期
1 性意識・性行動、避妊、人工妊娠中絶
(1)現状と問題点
1)性意識・性行動
- 東京都幼・小・中・高・心障性教育研究会の調査によれば、最近の中高校生の性交経験率は年を追って上昇しており、特に高校生の増加傾向が顕著である。平成11年の高校3年生の性交経験率は男子は37.8%、女子は39.0%に達している。
性に関する情報源としては、中学生は男女ともに雑誌やテレビが最も多く、高校生では男女ともに友人や先輩が最も多くなっている。また、中学生の男子ではアダルトビデオ、高校生の男子ではポルノ雑誌も多くなっており、若年者は性に関して、必ずしも正確な情報を得ていない可能性があると考えられる。
- 性交に関する意識をみると、平成11年の同調査では、「結婚または婚約するまでは不可」と答えた者の割合が高校3年生の男子は3.9%、女子は6.7%となっている。「好意を持っている人から性交を求められた場合、相手の求めを受けて性交する」と答えた者の割合は高校生の男子では16.3%、女子は3.8%、「雰囲気によって応じる」が高校生の男子では23.1%、女子は14.8%となっており、これらの項目はいずれも平成5年、8年の調査と比べて年を追って上昇している。毎回の調査で男女ともに37〜38%の者は「その時にならないとわからない」と答えている。
思春期における性交経験者については、このような性交に対する意識の変化のほか、身体の早熟化、性情報の氾濫等の要因により、今後ますます増加するものと思われる。
日本産科婦人科学会が20歳未満で妊娠した1,634名の女性に対し、平成7年から8年にかけて行った「わが国における思春期妊娠調査」によると、性交を行った動機については、「何とはなしに」が41.1%、「好奇心から」が19.1%、「わからない」が17.5%となっており、「自分で希望」が8.8%であった。婚前交渉に対する意識については、「愛していればよい」が64.2%である一方、「愛していなくても同意があればよい」が12.2%となっている。また、性交経験をした相手の人数については、「2〜5人」が最も多く42.3%となっており、次いで「6〜9人」の11.4%となっている。
このように、若年女性で性交した者については、その動機は、積極的あるいは明確な自らの希望による者が少なく、性交に対する意識は、愛情に基づかなくてもよいと考える者が多く、多人数の者と性交経験をもつ者が多くなっている。
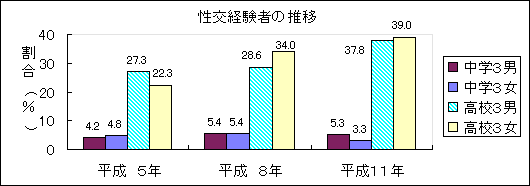
出典:平成11年 東京都幼・小・中・高・心障性教育研究会調査報告
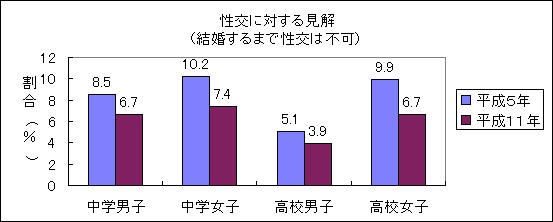
出典:平成11年 東京都幼・小・中・高・心障性教育研究会調査報告
2)避妊
- 前述した東京都の平成11年の調査によれば、初交時に避妊を実行した女子高校生の割合は、49.3%であり、40.8%の者は実行していない。また、2回目以後については、いつも避妊を実行する者は22.6%に減少し、52.6%の者は「した時としない時がある」、20.6%の者が「いつもしない」と回答している。
避妊しない原因としては、若年層については、避妊についての情報不足、避妊しなかった結果についての認識不足などが考えられる。
また、日本産科婦人科学会が行った前出の調査によれば、避妊を「いつもしていた」と答えた者が14.6%、「時々していた」と答えた者が68.7%であり、この両者が行っていた避妊法は、コンドームが78.6%、性交中絶法が2.6%となっている。
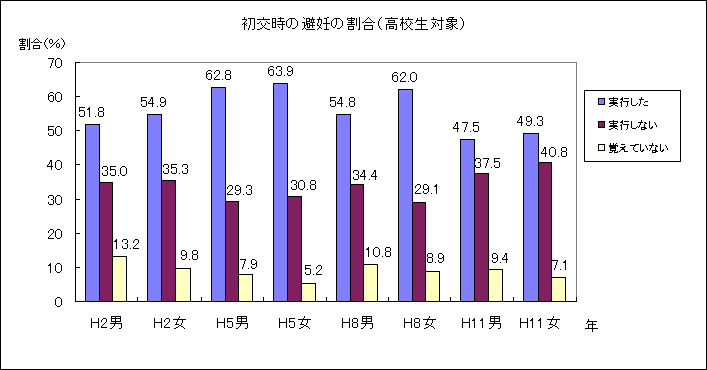
出典:平成11年 東京都幼・小・中・高・心障性教育研究会調査報告
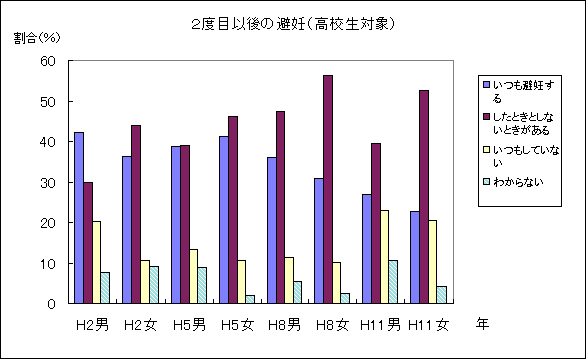
出典:平成11年 東京都幼・小・中・高・心障性教育研究会調査報告
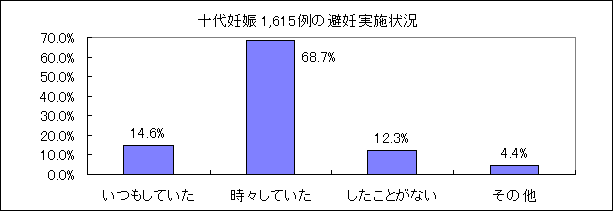
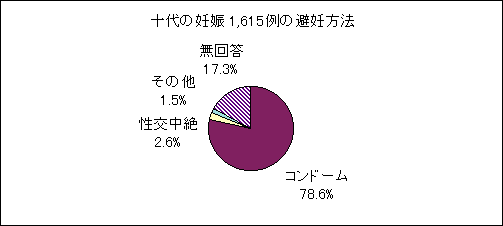
出典:平成9年 生殖・内分泌委員会報告 日本産科婦人科学会
- 20代以上の既婚者では、国立社会保障・人口問題研究所が平成9年に実施した調査によると、避妊の実施率は60.4%となっており、4割弱の女性が避妊を実施していない。
また、この調査によると、避妊方法については、コンドームが75.5%と圧倒的に多く、次いで性交中絶法が20%強となっている
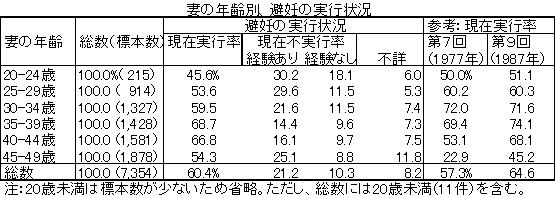
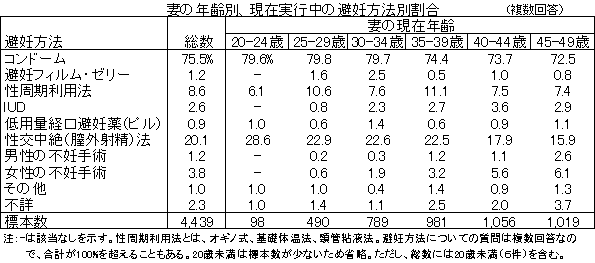
出典:第11回出生動向基本調査 国立社会保障・人口問題研究所
- このように限られた避妊法を選択せざるを得ない理由としては、わが国においては、これまで、低用量経口避妊薬(ピル)等の女性が自ら主体的に避妊できる方法がほとんどないことのほか、避妊についての教育が十分でないこと、女性が性を主体的に捉え、避妊が性の自己管理のための手段であるという意識を育む教育や情報提供が不足していること等があり、これらのことにより女性が主体となって避妊する意識が不足していることなどが考えられる
3)人工妊娠中絶
- 人工妊娠中絶については、中絶件数は昭和30年と比べて、平成9年では3分の1以下に減少している。これは、避妊についての知識や避妊方法が長期的に普及してきているためであると考えられる。しかしながら、一方で、20歳未満の人工妊娠中絶については増加傾向がみられる。
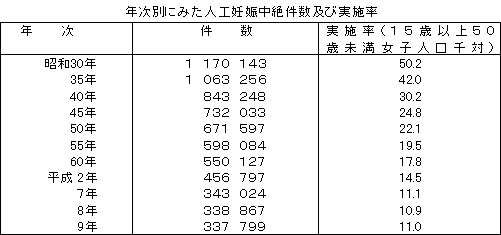
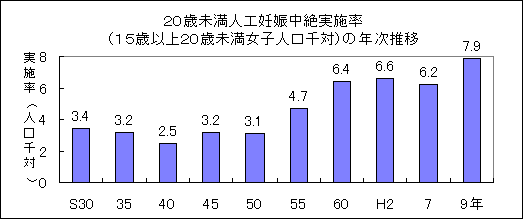
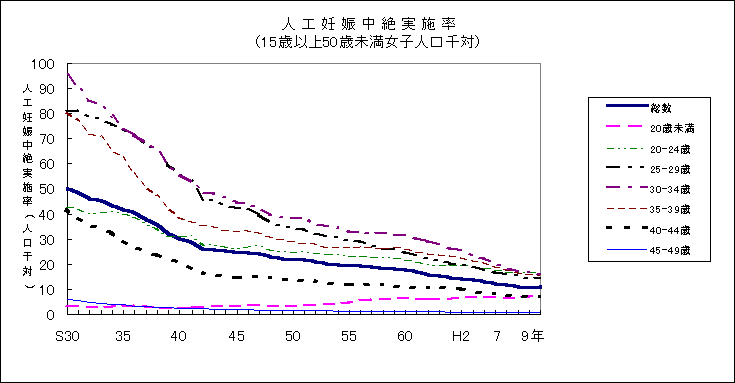
出典:平成9年母体保護統計報告 厚生省
- これは、近年、初交年齢が低年齢化している一方で、10代の若者の間に、適切な避妊方法や人工妊娠中絶が心身に及ぼす影響等に関する知識が普及していないこと、女性が主体的に利用できる避妊方法がほとんどないこと等から、適切かつ継続的な避妊が行われていないことが原因として考えられる。
(2)現在の行政の対応
1)保健施策としての対応
- 避妊、家族計画については、市町村の保健婦等が婚前学級や新婚学級において指導を行うとともに、病院や受胎調節実地指導員である助産婦が開設している助産所等において避妊の指導を実施している。
特に若年者については、市町村保健センターにおいて、性の悩みや不安の相談、避妊の相談・指導、中絶の健康影響の指導などを行う「健全母性育成事業」、日本家族計画協会において医師が家族計画や避妊の相談等に応じる「思春期クリニック事業」等が行われている。
しかしながら、受胎調節実地指導員については、その実地指導を行うペッサリー等の避妊用器具の需要が少なく、実地指導の件数は少なくなっている。「健全母性育成事業」についても平成9年度では70か所と実施市町村が限られており、「思春期クリニック事業」も全国で4か所と実施地域が限られている。
2)教育施策における対応
- 学校教育における性教育については、体育、保健体育、理科、家庭等の教科や、道徳、特別活動などを中心に児童生徒の発達段階に応じ、学校教育活動全体を通じて実施されており、避妊についての科学的な知識の普及等も行われている。また、教職員に対する研修、研究推進地域での実践活動なども行われている。さらに、現在、文部省において、学習指導要領を改訂し、発育・発達や性に関する内容の充実が図られている。
社会教育においては、公民館等の社会教育施設を拠点に開設される各種の学級・講座の中で、生命や性に関する学習機会が設けられている。
しかしながら、これらの問題への取組みについては、学校間や教師間で格差が大きいのが現状である。特に学校における避妊やエイズを含む性感染症についての科学的な知識の普及については、医師・助産婦などの専門的な知識と経験を有する者の活用が十分でない。
(3)今後の対応の方向性
1)性に関する教育・指導についての考え方
- 前述したように、中高生で性交経験をもつ者の割合は年々、増加している。
その一方で、中高生の性に関する知識や情報は、アダルトビデオやポルノ雑誌等から入手している場合が多く、正確性に欠けていることが考えられる。このことが、10代の中絶の増加、性感染症の拡大、いわゆる援助交際等の売買春や、性的虐待の増加につながっていることが危惧される。
このため、性教育においては、性と生殖に関する体の仕組みについての正しい科学的な知識を、避妊、中絶、性感染症などとともに、子どもの発達段階に応じた教え方で、なるべく早期から教育・指導する必要がある。
また、特に思春期の男女は、商業的な性情報が氾濫していることもあり、性行動に関し、自己の性欲や好奇心を満足させることのみを希求する傾向があり、愛情や相手を思いやる気持ちが欠如していることが指摘されている。
このため、性教育においては、性と生殖に関する身体の科学的な仕組みを教えることにとどまらず、「いのち」の大切さや、人間尊重、男女平等の精神等をつちかう教育・指導をあわせて行う必要がある。
また、リプロダクティブヘルスの観点からは、特に女性が性交や避妊について自己決定することの重要性についての意識を啓発するとともに、その自己決定が実践できるよう、性交を求められた場合の拒絶の仕方等意志表示の方法等について指導することを検討する必要がある。
さらに、パートナーである男性に対する教育にも取り組んでいく必要がある。
2)避妊・人工妊娠中絶
- 若年者に限らず、望まない妊娠を防ぐためには、避妊の実施率を高める必要がある。このため、避妊や家族計画についての意識の向上、避妊に関する正確な情報の提供、避妊しなかった結果、すなわち妊娠や中絶が心身に及ぼす影響等についての知識を普及することが必要である。
また、避妊についての指導は、単に避妊方法の普及だけでなく、「1)性に関する教育・指導についての考え方」の中で述べた事項に留意して行われる必要がある。
このため、学校教育において、性教育の中で避妊についての指導を促進するとともに、保健所、市町村保健センター、都道府県や指定都市の女性センター等において、避妊や妊娠についてはもとより性に関する諸問題についての相談窓口の設置や生涯学習活動等を通じて保健知識の普及を図る必要がある。
また、わが国における避妊方法は、コンドームによるものが大半を占めていることから、コンドームの正しい使用方法を徹底するとともに、今般承認された低用量経口避妊薬(ピル)等、コンドーム以外の避妊方法に関する情報提供を積極的に行う必要がある。特に、女性が主体的に避妊できるよう意識の啓発を図るとともに、低用量経口避妊薬(ピル)のほかにもフィーメール・コンドーム(女性用のコンドーム)等女性が自ら避妊できる方法を幅広く選択できるようにしていく必要がある。
2 喫煙、飲酒、薬物乱用
(1)現状と問題点
1)喫 煙
- 喫煙は、ニコチンによる依存性があり、がん、虚血性心疾患、脳卒中のみならず、慢性気管支炎や肺気腫等の危険因子である。若年期からの喫煙は、がんや心臓病のリスクが特に大きくなる。特に女性については、妊娠中の喫煙により低体重児の出生や早産の頻度が高くなるといった問題や乳幼児の周囲での習慣的喫煙は、乳幼児突然死症候群(SIDS)の発症のリスクを高めることも指摘されている。
女性の喫煙については、平成9年度の厚生科学研究費補助金による調査研究の結果によると、中学校3年生の女子で22.7%、高校3年生の女子で38.5%の者に喫煙の経験があり、学年が上がるほど喫煙経験者は増加している。喫煙の動機としては、「友達からの勧め」が高い割合を占めている。
また、平成9年の厚生省の国民栄養調査によると、女性の喫煙習慣者の割合は20〜29歳が21.3%とピークになっており、その後は下降がみられる。一方で男性は20代から40代までは60%台で推移し、50歳以降で減少がみられる。このことから、女性自身が喫煙を止めていても、喫煙習慣のある者が周囲にいることにより、女性や子どもが環境中のたばこの煙に暴露している場合が多いと考えられる。
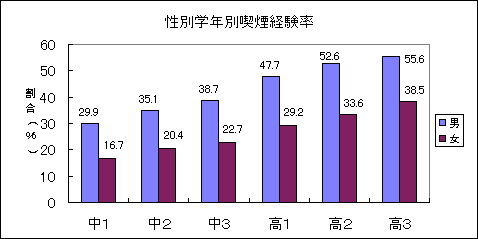
出典: 「未成年者の喫煙行動に関する全国調査」平成9年度厚生科学研究費補助金研究
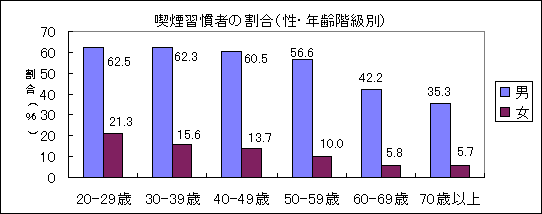
出典: 平成9年 国民栄養調査 厚生省
2)飲 酒
- 飲酒は、肝疾患、高血圧、糖尿病等の生活習慣病の危険因子であり、また、アルコール依存症等により通常の社会生活がおくれなくなったり、過度の飲酒は家族への暴力等を助長すること等を通じて家庭崩壊の原因となることもある。特に女性については、男性よりアルコール性肝障害を生じやすいとの報告もあり、また、妊娠中の飲酒による胎児への影響の問題もある。
- 平成8年度の厚生科学研究費補助金による調査研究の結果によると、月1回以上飲酒する者が中学校1年生の女子で13.0%、高校3年生の女子では36.1%となっている。

出典: 「未成年者の飲酒行動に関する全国調査」平成8年度厚生科学研究費補助金研究
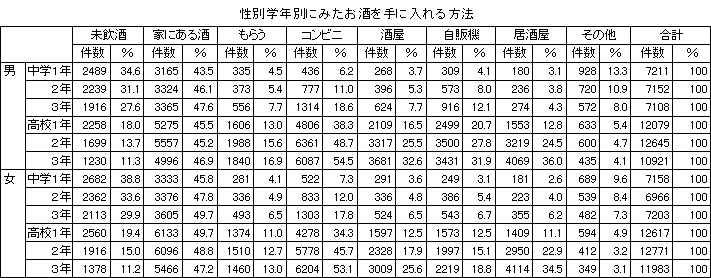
出典: 「未成年者の飲酒行動に関する全国調査」平成8年度厚生科学研究費補助金研究
- 同調査によれば、酒類の入手経路については、「家にある酒」が男女ともに4〜5割であり、中学校1年生から高校3年生までに大きな変化はみられない。しかし、「コンビニエンスストアで買う」、「酒屋で買う」、「居酒屋等で飲む」、「自動販売機で買う」については、男女ともに年齢が高くなるにつれて割合が高くなっており、特に「コンビニエンスストアで買う」は中学校1年生の女子で7.3%であったものが高校3年生の女子で53.1%と急増している。
また、飲酒習慣のある女性の割合は、40〜49歳がピークで12.6%となっている。
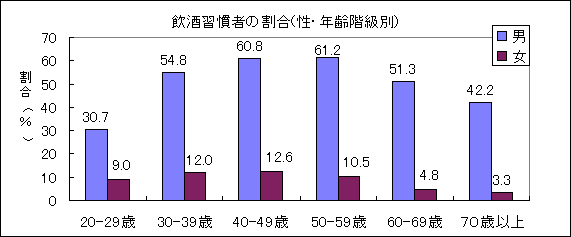
出典:平成9年 国民栄養調査 厚生省
3)薬 物
- 乱用される薬物は中枢神経に対する作用が大きく、精神的又は身体的な依存性があり、肉体的、精神的に健康をむしばむだけではなく、家庭崩壊や犯罪につながるおそれがあるなど社会的な問題もある。女性については、妊娠期は胎児への悪影響があり、出産後は、子どもへの暴力を助長するといった問題がある。
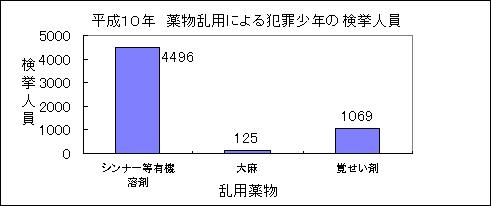
出典:警察庁調べ
- 平成10年犯罪白書によると、平成9年の女子の受刑者のうち、過半数は覚せい剤取締法違反を罪名とするものとなっている。
また、警察庁によると、平成10年の薬物乱用により検挙された犯罪少年が乱用した薬物は、シンナー等有機溶剤、覚せい剤、大麻の順に多く、覚せい剤の乱用による補導人員は昭和57年をピークに減少傾向にあったが、平成7年から9年まで再び増加に転じている。また、そのうち約半数は少女による乱用となっている。
(2)現在の行政の対応
1)喫 煙
- 喫煙の心身への影響に関する指導は、学校教育においては体育、保健体育、理科、家庭等の教科や、道徳、特別活動などを中心に学校教育活動全体を通じて実施されている。また、新学習指導要領に基づき、小学校段階から喫煙と健康について指導することとされている。
- 保健施策においては、厚生省は平成7年のたばこ行動計画検討会報告書において示された、防煙・分煙・禁煙支援の3本柱を中心にたばこ対策を進めている。また、厚生省の「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」の検討の中で、たばこに関する分科会を設け、具体的な数値目標を盛り込んだ今後の施策の方向性について、検討を進めている。さらに、分煙の環境づくりについて、厚生省、労働省、人事院、東京都等がそれぞれ指針を示し対策を進めている。
2)飲 酒
- 飲酒の心身への影響に関する指導は、学校教育においては、体育、保健体育、理科、家庭等の教科や、道徳、特別活動等を中心に学校教育活動全体を通じて実施されている。また、新学習指導要領に基づき、小学校段階から飲酒と健康について指導することとされている。保健施策としては、アルコール乱用患者に対する治療、社会的支援体制の準備が進められている。さらに、生活習慣病対策の観点からも、厚生省の「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」の検討の中で、アルコールに関する分科会を設け、検討を進めている。
3)薬 物
- 薬物乱用防止に関する指導は、学校教育においては、保健体育、道徳、特別活動などを中心に教育活動全体を通じて実施されている。具体的には、生徒用教育教材(パンフレット、ビデオ)の作成、教員用の指導資料の作成、教員に対する研修を実施するとともに、「薬物乱用防止教室」を全中学・高等学校で開催することを目標として実施している。同教室は、警察庁の調査では、平成10年度中、全国で4,249校の高等学校、6,762校の中学校で合わせて12,411回開催し、4,389,125人の生徒が参加している。また、新学習指導要領に基づき、小学校段階から薬物乱用防止について指導することとされたところである。
- 文部省は、各都道府県教育委員会や全国的な青少年団体、PTA団体、スポーツ団体等に対して、覚せい剤等薬物乱用防止対策の推進に関する通知を発出し、地域における薬物乱用防止への指導を要請している。
- また、全国高等学校PTA連合会においては、薬物に関する意識調査を実施したほか、全国大会をはじめ各種の研修会等において、薬物問題を取り上げて議論するなどの取り組みが行われている。
- さらに、公民館等の社会教育施設を拠点に開設される各種学級・講座において、薬物についての学習機会が提供されている。
- 警察庁においては、少年に薬物乱用の危険性・有害性についての正しい認識を持たせるため、警察職員を学校に派遣して薬物乱用防止教室を積極的に開催しているほか、地域の実情に応じてより効果的に実施するため、平成11年度中に薬物乱用防止広報車を全国的に配備することとしている。
- 厚生省においては、薬物乱用防止対策の推進を図るため、「ダメ。ゼッタイ。」をキャッチフレーズとする普及運動等を全国的に展開しているほか、薬物乱用防止キャラバンカーによる学校等への巡回、麻薬取締官OB等による薬物乱用防止教室での講演、薬物乱用防止読本を全国の中学・高等学校へ配付、中学・高校生の保護者用の読本の配付等、薬物乱用防止のための広報啓発に努めている。
(3)今後の対応の方向性
- 喫煙、飲酒については、その健康被害に関する正確な情報を提供し、薬物に関してはその危険性を含めて乱用防止を徹底する必要がある。特に、飲酒については、若年者での急性アルコール中毒などの問題も看過できないこと、喫煙や飲酒が胎児や生殖機能に影響を及ぼす危険性があること等についても十分情報を提供する必要がある。また、妊婦や乳幼児を持つ親に対しては、喫煙は、乳幼児突然死症候群(SIDS)をはじめとする種々の疾患の危険因子である旨の広報を積極的に行う必要がある。さらに、女性や子どもが環境中のたばこの煙に暴露することによる健康への影響を減少させるため、周囲の者に対する禁煙支援や啓発などを行う必要がある。
- 未成年者の喫煙、飲酒を予防するためには、家庭における教育はもとより、学校教育においても低学年からの指導が必要である。また、保健所、保健センターの医師や保健婦の活用等有効な指導を積極的に推進していく必要があり、家庭、学校、地域が一体となってこの問題に取り組むことが求められている。
- 薬物については、乱用薬物の供給を遮断することはもとより、薬物乱用を未然に防止する教育・啓発の推進、少女等の末端乱用者の早期発見、再乱用の防止のための取組みを推進する等、薬物乱用を許さない社会環境の形成を推進する必要がある。
- さらに、インターネットによる薬物売買の取締りや、地方自治体による薬物追放宣言などの地域における取組みの強化が必要である。
3 性感染症
(1)現状と問題点
- 性感染症は、性的接触を通じて感染する病気で、知らない間に他者に感染させるなどの健康上の問題がある。しかも、男女の性器の解剖学的、生理学的な差異等もあり、性感染症は一般に男性から女性への感染の方が感染率が高いだけでなく重症化する傾向が強いことが指摘されている。また、女性にとっては、性感染症のり患は、慢性的な骨盤内感染症、母子感染、不妊症の原因になるなど、生涯を通じた女性の健康を脅かすことが指摘されている。
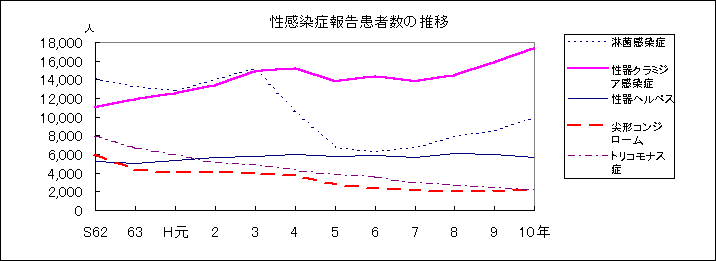
出典:感染症サーベイランス情報 厚生省
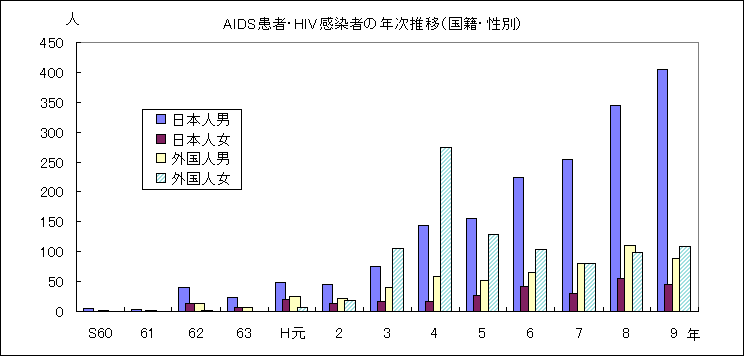
出典:エイズ発生動向年報 厚生省
- 性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローム、トリコモナス症は横ばいあるいは漸減しているものの、性器クラミジア感染症は増加傾向にあり、淋菌感染症は平成6年までは減少傾向にあったが平成7年からは増加傾向に転じている。年齢別の患者発生状況をみると、男女ともに20歳代の発生が多い。
(2)現在の行政の対応
1)保健施策による対応
- 性感染症については、これまで性病予防法とエイズ予防法に基づき施策を講じてきたが、これらが廃止され、新たに「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が平成11年4月1日に施行された。同法に基づき、性感染症、エイズ等の原因の究明、発生の予防及びまん延の防止、医療の提供、研究開発の推進、国際的な連携等について、特定感染症予防指針を策定し、この指針により、国等が対策を総合的に推進していくこととされている。
2)教育施策による対応
- 学校教育においては、性感染症は性行為を通じて感染する疾患であるという知識を与える必要があり、体育、保健体育、理科、家庭等の教科、道徳、特別活動などを中心に学校教育活動全体を通じて行われる性教育の一環として取り上げられている。また、エイズについても学校教育活動全体を通じて指導されるとともに、教材や、教員の指導資料の作成、推進地域における実践研究、エイズ教育情報ネットワーク整備事業が推進されている。
- さらに、新学習指導要領に基づきエイズ及び性感染症の内容を教育内容に加えることとされている。
- 社会教育においては、公民館等の社会教育施設を拠点に開催される各種の学級・講座においてエイズについての学習機会が提供されている。また、教育委員会の社会教育関係職員や公民館等の社会教育施設の職員を対象に、エイズに対する正しい理解を深めるため研修を実施するとともに、エイズに関する正しい指導を行うため、社会教育指導者向けの指導資料が作成・配付されている
(3)今後の対応の方向性
- 性感染症については、今後とも正しい知識の普及・浸透に努めるとともに、予防、健康診査、相談、治療などの対策の充実を図る必要がある。
- エイズについては、国民が正しい知識を持って感染を防止するとともに、患者や感染者に対する偏見等を払拭し、正しい知識に基づいて行動がとれるよう、積極的な啓発活動、相談窓口の設置、医療体制の充実、治療薬の研究開発等の総合的な対策を推進する必要がある。特に、思春期の者に対しては、発達段階に応じた正しい知識を身につけ、人間尊重の精神に基づいた行動がとれるようにするため、学校教育や地域においてエイズについての正しい知識の普及・啓発をより一層推進することが必要である。
- また、性感染症に伴う負担は女性に大きくかかることを考慮し、性感染症を女性のリプロダクティブヘルスの推進を脅かす問題の一つとして位置づけ、その改善には、女性が正確な情報をもてるようにするだけでなく、パートナーである男性に対する教育にも取り組んでいく必要がある
4 いわゆる援助交際等の売買春、性的虐待
(1)現状と問題点
1)いわゆる援助交際等の売買春
- 近年、女子中高生がテレホンクラブ、ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル、インターネットといった情報媒体を通じて、いわゆる援助交際等の売買春を行う事例がみられることが報道されている。
- 思春期におけるこうした売買春は、性感染症のり患や望まない妊娠、意図しない性行為を強要されること等により心身の健康に悪影響を与えることが危惧される。
- 過去10年間に性の逸脱行為により補導・保護された女子少年(注参照)の動機別状況をみると、平成6年までは、「興味(好奇心)から」が最も多かったが、平成7年以後は「遊ぶ金が欲しくて」が最も多くなっている。
- また、科学警察研究所の報告によれば、こうした行為を行う者では「セックスしてお金をもらうことが恥ずかしいことではないという本人の商品化の積極的志向に加え、家庭での不満を強く持ち、学校不適応状態にある者が多いと考えられる。」としている。
-
- (注)「性の逸脱行為で補導・保護した女子少年」とは、下記の者をいう。
- ・売春防止法違反事件の売春をしていた女子少年
- ・児童福祉法第34条第1項第6号(淫行させる行為)違反事件の被害女子少年
- ・刑法第182条(淫行勧誘罪)の被害女子少年
- ・青少年保護育成条例による「みだらな性行為の禁止」違反事件の被害女子少年
- ・ぐ犯送致をした不純な性行為をしていた女子少年
- ・その他の不純な性行為を反復していた女子少年
2)性的虐待
- 警察庁の調査によると、少年(女子少年を含む)が被害者となった強制わいせつの事件数は、平成9年は昭和47年と比べ、約1.5倍に増加している。
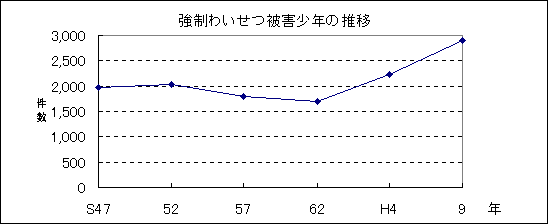
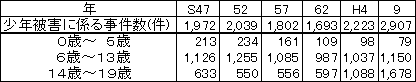
出典:警察庁調べ
- 児童期の性的虐待については、平成10年のさいとうクリニック(東京都港区)の来院患者の調査によれば、被害者のうち、家族内での被害が76.4%となっており、その加害者の内訳では、実父による被害が5割となっている。また、家族外の被害としては、他人や近所・近隣の大人からの被害等もみられる。
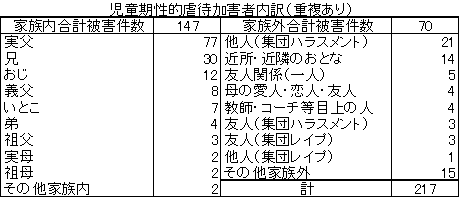
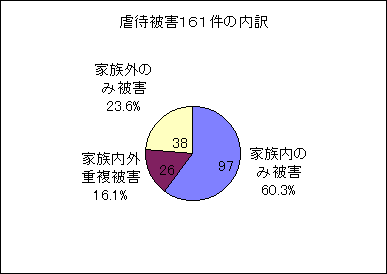
出典:平成10年 さいとうクリニック
- 性的虐待は、被害者の心に大きな傷を残し、その後の人生において、性交渉への恐怖、嫌悪感等の心身に対する長期的影響を及ぼすおそれがある。ただ、性的虐待については、その実態がつかみにくく、これまで全国的な発生件数等も把握されていないが、児童福祉、リプロダクティブヘルス等の観点からも積極的な対応を図る必要がある。
(2)現在の行政の対応
1)教育施策による対応
- 性に関しては、体育、保健体育、理科、家庭等の教科や道徳、特別活動などを中心に学校教育活動全体を通じて、発達段階に応じて、科学的知識を与えるとともに、人間尊重と男女平等の精神に基づく人間関係を形成していくための支援が地域や学校の実情に応じて行われている。また、教員用の指導資料の作成や教員に対する研修、研究推進地域での実践事業等が行われている。
2)警察による対応
- 警察においては、広報啓発活動を推進して性非行の防止を図るとともに、いわゆるテレクラ営業規制条例の適切な運用や援助交際の相手方となる大人等に対する青少年保護育成条例、児童福祉法、売春防止法の違反行為としての取り締まりが行われているところである。また、被害にあった少女に対しては、必要に応じ、医療機関や家庭等と連携してカウンセリング等の支援が行われている。
3)保健・福祉施策による対応
- 性的被害にあった少女については、早期対応を図ることが重要であり、児童相談所等が相談を受け、専門職員による調査・判定を行い、施設入所等の措置あるいは心理療法やソーシャルワーク等による在宅指導を行っている。また、心身症や神経症等を発症した少女に対しては、児童精神科等を担当する医師によるカウンセリングを受けるよう医療機関の斡旋が行われている。
(3)今後の対応の方向性
1)いわゆる援助交際等の売買春への対応
- 少女のいわゆる援助交際等の売買春の背景には、心のさびしさ、性のモラルの低下、金銭の獲得欲求等、大人社会からの影響を少なからず受けていることが考えられるが、一方、家庭や学校への不満等が引き金となっている可能性もある。このため、家庭や学校教育においては、性に関する教育や指導の推進を図るとともに、これらの問題行動をする少女の心のさびしさや不満について、学校、家庭、地域において、いち早く察知し、カウンセリングを行い、不満等の解消を図るシステムの整備等を行う必要がある。また、こうした行動をあおるようなマスコミの報道等については自粛が求められる。さらに、生涯にわたる女性の健康支援の観点から、自ら自分の体を大切に思い、心身の健康を保持増進できるよう発達段階に応じた指導、支援を行う必要がある。
2)性的虐待への対応
- 性的虐待については、先般、通常国会において成立した、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」により、性的虐待の加害者である男性や児童買春についての取締り等の対策を強化する必要がある。
- また、児童相談所や保健所等においては、被害者への対応のみならず、これらの被害を未然に防止するため、医療機関、学校等とも協力して、性の悩みや心の悩みに対する相談などを積極的に実施する必要がある。
5 食生活の乱れと拒食・過食
(1)現状と問題点
1)朝食欠食等の食生活の乱れ
- 思春期における朝食欠食等の食生活の乱れは、成長期に必要な栄養摂取を妨げ、将来の健康に大きな影響を与えるおそれがある。
- 平成9年の国民栄養調査によれば、15歳から19歳の朝食の欠食率が、男子で13.2%、女子で7.4%となっている。
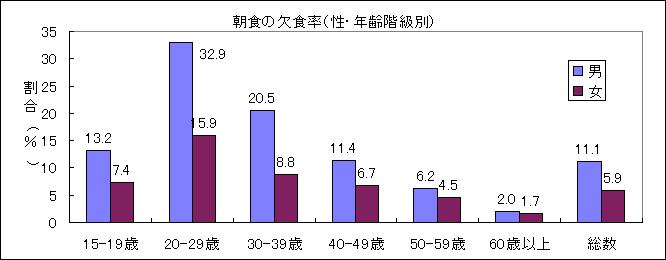
出典:平成9年国民栄養調査 厚生省
- また、20歳代の朝食欠食者について、朝食欠食が習慣になった時期をみると、「小学生から」が4.6%、「中学生、高校生の頃から」が28.1%、「高校卒業後の頃から」が33.9%となっている。
- さらに、同調査によると、朝食を欠食する人は夕食も不規則であり、夕食後の間食も多く、1日を通して食生活のリズムに乱れが生じていることが分かる。
2)拒食・過食
- 思春期においては、様々な身体的変化があることから、容姿、体格、体型など自己の体のイメージを気にするようになる。また、自分が他人の目にどう映るかはこの時期の女性の重大な関心事である。このため近年、思春期の女性の間ではスリム化指向が強く、やせすぎや拒食傾向といった問題が増加している。
- 女子栄養大学の宮城が行った高校、専門学校、短期大学、大学の女子学生・生徒1,014人を対象としたアンケート調査結果によると、BMI(Body Mass Index:体重(Kg)/身長(m)2)による肥満度判定が「普通」であっても、やせたいと思う女性は85.2%、「やせ」であってもやせたいと思う女性は16.7%となっている。
- 平成8年の国民栄養調査によると、20歳代女性の11.8%がダイエットを行っているが、BMIによる肥満度の判定では、このうち60%は「普通」、15%は「やせ」と判定されている。
- 無理なダイエットによる拒食は、無月経の原因となるとともに、成長期であるにも関わらず、栄養のバランスを欠くことから、将来の身体発育や妊孕性(妊娠する能力)にも重大な影響を及ぼし、老後の骨粗しょう症等につながる可能性もある。
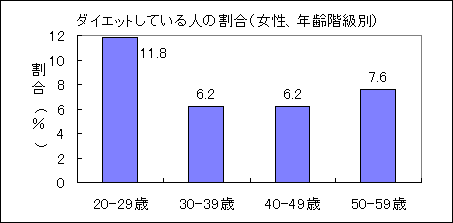
出典:平成8年国民栄養調査 厚生省
- また、過食は、子どもの頃からの生活習慣や家庭、学校におけるストレスなどが原因となることが指摘されているが、過食による10代の肥満は成人の肥満に結びつく傾向があり、糖尿病や循環器疾患等の生活習慣病の原因となる場合がある。
(2)現在の行政の対応
- 食生活については、体育、保健体育、家庭、技術家庭、特別活動などを中心に学校教育活動全体を通じて指導が行われている。また、新しい学習指導要領においても、望ましい食習慣の形成など、食に関する指導内容の充実が図られたところである。
- さらに、厚生省においても、食生活改善推進員によるボランティア活動を推進しているところであり、厚生省の「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」の検討の中で、栄養・食生活に関する分科会を設け、検討を進めている。
(3)今後の対応の方向性
- 思春期の食生活の乱れや拒食、過食等は、前述したとおり、成長を阻害し、将来の健康に影響があることから、家庭においてはバランスの良い食生活に努めるとともに、小さいうちから基本的な食習慣を身につけさせる指導が行われる必要がある。このため、保健所や市町村保健センター等において、望ましい食生活についての普及・広報を行うとともに、食事が健康に与える影響について適切な情報提供を行う必要がある。
- また、学校教育においても、家庭との連携を図り、生徒が自分を自ら大切にし、健康を守るための力をつけさせるため、食事、運動、休養等の生活習慣に関する指導を行う必要がある。
第2節 出産可能期
1 月経障害
(1)現状と問題点
- 月経障害として問題となるものには、PMS(月経前緊張症)、下腹痛・腰痛・頭痛等に代表される月経困難症、無月経等がある。また、月経困難症を引き起こす疾患として子宮内膜症や子宮筋腫等がある。ここでは特に、月経痛、月経困難症を引き起こす疾患、無月経を中心に述べることとする。
1)月経痛
- 月経痛の悩みを訴える女性は多いが、症状が重い場合は、月経困難症として捉えられ、女性の学習や労働など社会活動に支障を来したり、家庭生活に影響を与える場合があり、これを放置すると不妊症等の原因となる場合がある。
- 全国各地域に居住する8〜64歳までの女性27,106人について平成2年に行われた月経に関する調査(MSG研究会:月経研究会)によれば、月経による身体的不快症状は、月経前では腹痛(45.5%)、腰痛(31.6%)がみられ、乳房緊満感(15.4%)については月経中より感じる者が多くなっている。また、月経中では腹痛(67.3%)、腰痛(46.3%)、全身倦怠感(36.3%)などの症状が顕著であるとしている。さらに、月経前の気分の変化については、月経前は、「いらいらした」(40.3%)、「気分の変化はなかった」(39.7%)、「怒りっぽくなった」(28.3%)が多く、月経中は「いらいらした」(35.5%)、「憂うつになった」(30.8%)、「気分の変化はなかった」(24.8%)が多くなっている。
- また、月経の症状については、非常に苦痛であるという者が22.6%であり、特に16〜18歳が多くなっている。一方、月経痛のない者はわずか11.8%となっている。
- 月経痛への対応は、「横になって休む」が48.9%、「我慢する」が43.3%であるなど、消極的な対処法が高率であり、「身体を暖める」「指圧やマッサージをする」「体操をする」などの積極的な対処法を行っている者は少ない。「鎮静剤(痛み止め)を服用する」とする者は30.2%いるが、医師に相談する者はわずか0.7%となっている。
- 月経痛については、相当な女性が体験しているが、必ずしも適切な対処が行われているとは言えない。これは、月経障害についての知識が不足しているとともに、健康相談の場が不足していることによると考えられる。
2)月経困難症を引き起こす疾患
(1)子宮内膜症(子宮腺筋症を含む)
- 子宮内膜症については、平成9年度の厚生科学研究費補助金による調査によると、我が国における子宮内膜症の受療患者数は約128,000人と推定されており、10歳〜60歳の女性における受療率は人口10万対で298人であると報告されている。また、受療率は30代前半の女性がピークであり、20代後半から30代前半のいわゆる出産可能期で高くなっている。
- また、同調査によると、症状として月経困難を訴えるものは88%であり、そのうち7割は鎮痛剤を使用している。月経困難を訴えるもののうち鎮痛剤を使用しても日常生活に支障を来す重症のものは18%となっている。また、月経時以外の下腹部痛・腰痛は46%、性交時痛・排便痛は30%となっている。さらに、不妊を訴えるものは30%であり、調査時点における不妊期間の平均は5.3年となっている。
(2)子宮筋腫
- 子宮筋腫については、厚生省の患者調査によると、平成8年の患者数は14,000人と推計されており、近年、わずかずつではあるが増加傾向となっている。
- 一般に、40歳代の女性の1/4が子宮筋腫を持っていると言われており、筋腫の発生部位や大きさによって様々な症状を引き起こす。また、子宮内膜症の合併率も高い。
3)無月経
- 無月経は、不妊の原因になるが、これは、過度のストレスやダイエット等が原因となる場合がある。患者調査によれば、平成8年の患者数は1,200人と推計されているが、近年、特に患者数に変化はみられない。
(2)現在の行政の対応
1)教育施策としての対応
- 学校教育における性教育は、児童、生徒の発達段階に応じて体育、保健体育、理科、家庭等の教科や道徳、特別活動などを中心に学校教育活動全体を通じて実施されており、月経についても、性教育の一環として指導されている。また、養護教諭を中心に月経に関する個別相談や指導も実施されている。
2)保健施策としての対応
- 月経障害を含む女性特有の健康問題については、保健所等において、「生涯を通じた女性の健康支援事業」や一般相談等の中で、相談や指導を行っている。
3)労働施策としての対応
- 労働基準法は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を使用者に対して請求した場合に、その女性を就業させることを禁止している。
(3)今後の対応の方向性
1)適切な情報提供等
- 月経障害については、女性自身の知識の不足や社会の理解が進んでいないことなどから、自分一人で我慢してしまい、適切な対応が行われていない場合があること等が指摘されている。また、職場等の理解が進んでいないため仕事を休みにくい等の状況がある。このため、適切な情報提供を行い、女性の月経に関する理解を深める必要がある。
- 学校教育においては、月経の仕組みや月経障害について教育を行うとともに、保健施策においては、地域の保健婦等による指導やパンフレットによる情報提供等あらゆる機会を通じて知識の普及を図る必要がある。その際、月経を「女性にとって妊娠の準備状態であり、我慢しなければならないもの」と捉えるのではなく、「女性の健康状態を示す指標」であり、「その症状がひどい場合は社会生活を疎外する要因となり、治療等の対応が必要なもの」として意識させるような健康教育・相談が必要である。
- 特に子宮内膜症などにより症状が重い場合には、女性の活動の阻害要因となる場合があるため、月経について職場や家庭での理解を深めるよう、事業主や家族への適切な情報提供が必要である。さらに、月経日に快適な生活が送れるよう、学校、職場の洗面所やトイレ等の設備面の配慮が必要である。
2)相談機関の整備
- 月経については、女性が一人で悩まず身近で気軽に健康相談を受けられる体制を整える必要がある。
- 学校においては、児童・生徒が保健室で気軽に適切な健康相談を受けられるようにする必要がある。そのため、教職員に対する研修に、月経についての内容を盛り込むことなどにより、教職員がこれらについて正確な知識を持ち、対応できることが望まれる。また、市町村保健センター、保健所等の身近な施設の医師や保健婦、地域産業保健センター、産業医等に気軽に相談できる体制を整える必要がある。
- また、職場で、月経困難にも関わらず、生理日の就業が著しく困難な女性が本来取得し得る休暇を取得できない状況を改善するためには、産業医等が月経障害に精通し、適切な助言・相談を行うことが望まれる。
3)医療機関への受診の勧奨
- 重い月経痛は、子宮内膜症や子宮筋腫等の疾病が原因となっている場合があるため、医療機関受診の必要性についての情報提供を行うとともに、相談機関から医療機関に紹介する体制の整備を図り、女性が気軽に医療機関を受診し、適切な診断や処置を受けられるような体制を整える必要がある。
4)研究の推進
- 月経障害については、症状の判断が難しく、個人差もあることから、十分な治療法が確立しているとはいえない。このため、月経障害については、より一層の研究を推進する必要がある。
2 不妊
(1)現状と問題点
- 不妊に悩む者は、夫婦の約1割といわれ、不妊治療の進歩とともに、積極的に治療を受ける夫婦が近年増加傾向にあり、厚生科学研究費補助金による平成11年の調査によれば、現在、約285,000人の者が不妊治療を受けていると推測している。また、平成8年の日本産科婦人科学会の調査によると、体外受精の登録施設における体外受精・胚移植の実施件数は、治療周期総数では年間43,413件であり、出生児数は7,410人となっている。この数は、近年急増する傾向にあり、平成元年の約13倍になっている。非配偶者間人工授精(AID)については、昭和24年に我が国で開始されて以来、出生児数は約1万人に達していると言われ、年間約200人が出生しているといわれている。
- このように不妊治療が普及している一方で、多くの夫婦が不妊について様々な悩みを抱えていることが指摘されている。子どもができないことについての家族や社会からの精神的圧迫、自分自身の不安や自信喪失、不妊治療やその医療機関についての情報不足、経済的な負担が大きいことなどが指摘されている。特に男性不妊については、十分な情報が提供されておらず、まだまだ、不妊は女性の責任と考えられる傾向があることも、女性の精神的負担を大きくしている原因の一つとなっている。
- また、現在、不妊治療のうち、生殖補助医療については妊娠率は一般に人工授精1回当たり約6%、体外受精で1回当たり約20%と言われ、この妊娠率は女性の年齢が高くなるほど低下するが、1回当たりの妊娠率等を含めた不妊治療に関する正しい情報が普及していないため、不妊治療に過度の期待が持たれている傾向がある。
- さらに、生殖補助医療による多胎妊娠などの安全面、第三者の精子・卵子の提供等における倫理面や、出生児の法的地位が確立していないなどの法的問題を含め未解決な問題が残されている。
(2)現在の行政の対応
- 現在、全国9カ所において、不妊についての情報提供や悩みについての相談に応じる不妊専門相談センター事業が大学病院等に委託され実施されている。
- 第三者の精子、卵子の提供等を含めたわが国の生殖医療のあり方については、厚生科学審議会において安全面、倫理面、法的な面から検討が行われている。また、生殖補助医療による多胎妊娠についても、同審議会で議論されているところであるが、平成11年度の厚生科学研究費補助金により、その予防方法等の研究が行われている。
(3)今後の対応の方向性
1)情報提供と相談体制の整備
- 不妊治療については、適切な情報が十分提供されておらず、女性が不安や精神的負担等を感じる原因となっている。また、リプロダクティブヘルス/ライツの観点からも、女性が出産を望む場合に必要な治療が受けられるよう、不妊治療についての適切な情報を提供するとともに、不妊の夫婦の悩みに対応するため、専門的な相談を受けられる場を整備する必要がある。
- なお、不妊治療についての情報提供や相談を行う場合には、女性に子どもを生むことを強いることがないように配慮する必要がある。
2)研究の推進
- 不妊治療の中でも、人工授精、体外受精といった生殖補助医療技術については、多胎妊娠の危険があるなど医学的な問題が残されていることから、不妊に悩む夫婦が安心してこれらの技術を利用できるようにするため、不妊の原因や治療についての研究をより一層推進する必要がある。
3)治療環境の整備
- 生殖補助医療技術の中には、安全性や倫理的な問題が指摘されている技術もあり、また、第三者から提供された配偶子(卵子・精子)を用いた受精技術によって出生した子どもの法的な親子関係が不明確であり、これらの技術を許容するべきかどうか意見が分かれている。
- こうした中で、不妊に悩む夫婦が安心してこれらの技術を利用できるようにするためには、これらの問題を整理する等の環境の整備が必要である。現在、厚生科学審議会の専門委員会を設けて、これらの問題について検討されているところであり、この議論に期待したい。
4)経済的負担の軽減の検討
- 不妊治療の中でも生殖補助医療技術については、1周期当たり、配偶者間及び非配偶者間人工授精で数千円から3万円、体外受精で20数万〜60万円の費用がかかると言われ、患者の大きな負担となっており、不妊に悩む人が比較的安価に不妊治療を受けられるよう、経済的負担の軽減について検討する必要がある。
3 妊娠・出産・産褥
(1)現状と問題点
1)妊娠・出産の現状
- 平成8年に妊娠した者は妊娠届出数の年次推移からみると、約125万人と晩婚化等を反映し、昭和56年の約5分の4に減少している。また、出生児数は、約120万人と昭和35年の約4分の3となっている。また、合計特殊出生率は平成10年に1.38と昭和45年の約7割となっている。

出典:地域保健事業報告 厚生省
- 出産する者の年齢は、平成8年では、初産婦では25歳〜29歳が最も多く、48.2%となっており、ついで20〜24歳が23.9%、30〜34歳が20.6%となっている。昭和55年では平成8年と同様25〜29歳が最も多く50.5%であり、ついで20〜24歳が33.9%、30〜34歳が11.4%となっており、近年初産年齢が高くなっていることがわかる。また、妊娠出産した女性労働者のうち退職した者の割合は昭和46年には46.9%であったものが、平成9年では19.0%となっており、妊娠又は出産により退職する者の割合は減少している。
- このように、晩婚化を反映し、女性がはじめて妊娠・出産する年齢は上昇している。また、妊娠中や出産後も働く女性が増加している。

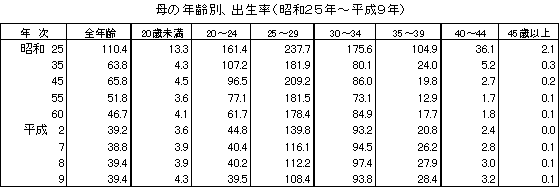
出典:人口動態統計 厚生省
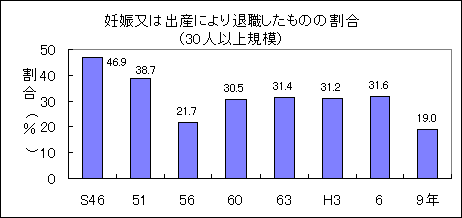
出典:平成9年度女性雇用管理基本調査 労働省
2)妊産婦死亡
- 平成9年の妊産婦死亡率は出生10万対で6.5であり、昭和55年の20.5と比べ大幅に減少している。実数でみると平成9年は78人が死亡している。欧米先進国の妊産婦死亡率と比較すると、アメリカ7.8、ドイツ5.2と同程度であるが、カナダ3.9、スイス3.6のような低位の国に比べ高くなっている。
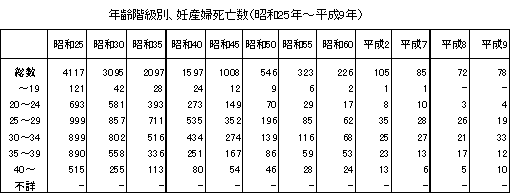
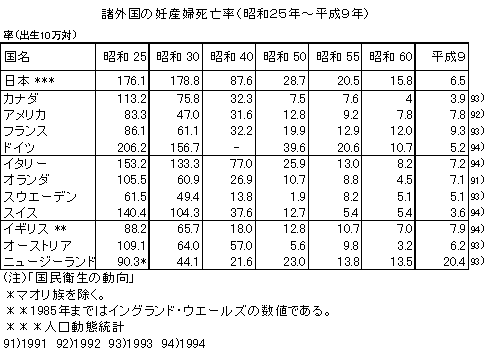
|
出典:
|
Journal of Health and Welfare Statistics, Vol.45, Number 10, 1998
World Health Statistics Annual,1950〜1995
|
- また、平成9年における妊産婦死亡の原因をみると、産科的塞栓12.8%、分娩後出血9.0%、妊娠、分娩、産褥における浮腫、たんぱく尿及び高血圧性障害9.0%、前置胎盤及び(常位)胎盤早期剥離7.7%、子宮外妊娠3.8%となっている。
- また、平成8年度の厚生省心身障害研究費補助金による妊産婦死亡例の実態調査では、平成3、4年において197例中で49例が陣痛促進剤を使用していたと報告されている。
3)多胎・早産・未熟児
- 単胎と多胎出生の全出生に対する割合では、昭和45年では単胎99.0%、多胎1.0%であったものが、平成8年では単胎98.2%、多胎1.8%となっており多胎の増加がみられる。その原因としては、生殖補助医療技術による影響等が考えられる。日本産科婦人科学会の調査によると、生殖補助医療技術による多胎妊娠率(新鮮胚、凍結胚、顕微授精を含む)は、平成8年では18.9%となっている。
- また、早産は昭和55年では4.1%であったが、平成9年には5.0%に増加しており、出生体重2,500g未満の低出生体重児が増加している。
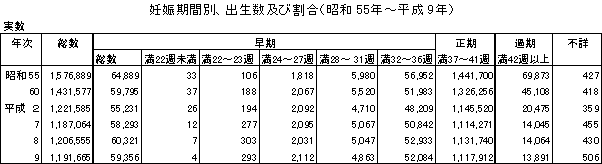
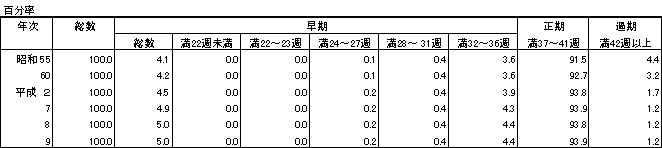
出典:人口動態統計 厚生省
- さらに、特に出生体重1,000g未満の超低出生体重児は、昭和60年では2,154人であったものが、平成9年では2,656人となっており、近年、増加傾向にある。この原因として周産期医療技術の進歩や生殖補助医療技術の影響が考えられる。
4)産科ケア・医療の現状
- 平成8年度の厚生省心身障害研究費補助金による調査によると、日本の病院、有床診療所をあわせた単位人口当たりの産科入院医療施設数は著しく多くなっている。しかし、英・米のようにオープンシステム(個人の開業医や助産婦が分娩を大きな病院で取り扱うシステム)が普及しておらず、また英・米は分娩実務を扱う医師は、昼夜に分かれた勤務体制となっているのに比べ、日本では昼間全員勤務が一般的であるなど、我が国の周産期医療体制は国際的にみて整備状況が不十分であることが指摘されている。
- 出生場所については、昭和35年では自宅・その他が49.9%であったものが平成9年では0.2%となり、施設内分娩(病院・診療所・助産所)が99.8%を占めている。
- また、高齢妊娠やハイリスク妊娠等の増加のためか帝王切開娩出術が平成2年では10%、平成8年では12%に増加している。
- 施設内の出産についての情報提供は、広告規制等により、産む側の女性が情報を得にくい仕組みとなっているとの指摘もある。
(2)現在の行政の対応
1)保健施策としての対応
- 妊娠・出産に関しては、市町村や保健所等により、母子保健サービスが提供されている。この内容は、妊娠の届出時に母子健康手帳が交付され、妊娠・出産に関する情報提供が行われるとともに、健康記録欄により健康の自己管理が図られている。また、市町村により健康診査や母親学級や両親学級等の保健指導が実施されており、妊娠中毒症等の異常が発見された場合には、療養援護も実施されている。
- ハイリスク妊娠・出産に対応するため、周産期医療体制の整備が行われており、総合周産期母子医療センター(平成10年度で全国15カ所)を中心とした地域の周産期医療ネットワークの整備が行われている。
- 未熟児が出生した場合には、都道府県等が指定する養育医療機関に移送し、公費負担により医療を提供する未熟児養育医療制度がある。
2)労働施策としての対応
- 労働基準法において、妊娠中の女性労働者については、産前産後の就業制限、深夜業や時間外労働の免除、危険有害業務の就業制限などの規定がある。
- 男女雇用機会均等法において、事業主に対し、妊娠中の女性労働者の健康診査等を受ける時間の確保、医師等の指導事項を守るための措置を講ずることなどを義務付けている。また、妊娠中の労働者が、医師等の指導事項を事業主に明確に伝えることができるように「母性健康管理指導事項連絡カード」の使用が推進されている。
(3)今後の対応の方向性
- 妊娠・出産については、高齢出産や妊娠中に働く女性が増加しているため、これらの影響について研究等を推進することにより、働く女性に対し適切な保健指導や医療を提供できるようにする必要がある。
- また、周産期医療体制の整備が我が国では不十分であることから、より一層の体制整備を図る必要がある。この場合、施設の整備に加え、24時間体制等の十分な医療体制を整備するためには、施設の医師や助産婦の確保対策を講じる必要がある。多胎妊娠が増えていることからも、こうした周産期医療体制の整備を推進するとともに、生殖補助医療技術における多胎の予防を図る必要がある。
- さらに、陣痛促進剤の不適正使用により死亡する妊産婦も報告されていることから、陣痛促進剤についての知識の普及と投与する際のインフォームド・コンセントの徹底を図り、過剰な陣痛促進剤の使用を抑制する必要がある。
- また、出産については、安全性や安心感に加え、プライバシーの確保等も含めた快適さについても妊婦のニーズが高まっていることから、WHOの勧告や出産ガイド「お産のケア・実践ガイド」などを参考にしながら、快適な出産を支援するための方策について検討する必要がある。
- さらに、男女雇用機会均等法において義務付けられている健康診査等を受診するための時間の確保や労働基準法上の産前産後休業について労働者や事業主に情報の提供や周知徹底を図るとともに、母性健康管理指導事項連絡カードの普及を図る必要がある。
4 育児ストレス等
(1)現状と問題点
- 産褥期の女性は、一過性の軽うつ状態といった症状のマタニティブルーとなることが少なくない。その発生頻度は欧米では全褥婦の1/2〜1/3、日本では6.5%と報告されている。また、新生児を持つ女性は、慣れない育児や2〜3時間毎の授乳により、精神的負担に加え身体的負担が大きい。産褥期から育児期の女性は、日々のストレスから精神障害を引き起こすことがある。さらに現在、少子化や核家族化により家庭の養育機能が脆弱化している中で、氾濫する育児情報に翻弄され、育児に自信をなくしている保護者が増加している。
- ベネッセ教育研究所の平成8年の調査によると、どの職業でも5割を越える母親が中程度の不安を、また、専業主婦では23.9%が強い不安を抱いているという報告もある。
- こうした育児期のストレスや精神状況の悪化は、女性の健康面に影響を与えるだけでなく、子どもが精神的に不安定になったり、子どもに対する虐待の原因となることが指摘されている。
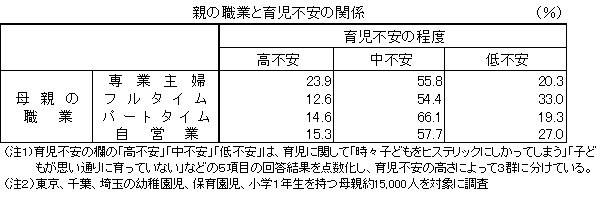
出典:平成8年 ベネッセ教育研究所
(2)現在の行政の対応
1)保健・福祉施策としての対応
- ア)母子保健施策
- 育児ストレスに関しては、新生児の訪問指導や乳幼児健康診査の機会に保健婦等が保護者の悩みの相談に応じている。また、母子相互作用等についての調査研究を進めるため、厚生科学研究費補助金により、「妊産褥婦および乳幼児のメンタルヘルスシステム作りに関する研究」を行っている。
-
- イ)保育施策
- 保育所においては、一時保育の対象となる理由に、平成8年度から、「保護者が育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するため」などの理由が加えられた。
- また、一部の保育所においては、平成5年から「地域子育て支援センター事業」として、在宅で子育てをする親からも育児に関する相談に応じるとともに、地域の子育てサークルへの保育室等の開放、子育て講習会などの開催、ベビーシッターなどの情報提供を実施する等、地域における育児支援を行っている。
- さらに、平成9年の児童福祉法改正により、全ての保育所において、在宅で子育てをする親からも育児相談に応じるなどの子育て支援に努めることとされた。
-
- ウ)少子化対策
- 厚生省では少子化対策として、平成11年3月に、子育て支援のための小冊子「それでいいよ だいじょうぶ」を600万部作成し、乳幼児を持つ保護者等に配布しており、これにより、保護者の育児の悩みに応え、保護者を勇気づけることにより、保護者の育児不安の解消を図っている。
- また、育児は男性の協力も必要であることから、若者の間で人気の高いダンサーSAM氏とその息子(同氏と歌手の安室奈美恵氏の子ども)を起用し「育児をしない男を父とは呼ばない。」をコピーとするポスターを作成・配布するとともに、テレビ・新聞等の媒体を使っての啓発活動が行われた。
2)教育施策としての対応
- 文部省では、一人一人の父親、母親が家庭を見つめ直し、それぞれ自信を持って子育てに取り組んでいく契機とするため、家庭でのしつけのあり方などを盛り込んだ「家庭教育手帳」を500万部作成し、平成11年4月から、乳幼児期の子どもを持つ親に対して、市町村の乳幼児健康診査等の機会などを活用して配布している。
- また、家庭教育に関する悩みや不安を抱く親に対して適切なアドバイスを行えるよう、都道府県教育委員会において家庭教育に関する電話相談窓口を開設するとともに、平成10年度からは、家庭教育に関して専門的な知識や能力を有するカウンセラーを活用し、相談体制の充実強化を図るための調査研究を実施している。
(3)今後の対応の方向性
- 育児不安等については、身近な機関で気軽に保護者等が相談できる機会を増やす必要がある。また、育児不安の解消には、育児経験を積んだ女性との交流が効果的であると考えられるため、こうした女性を相談等の場に活用したり、特に肉体的、精神的に負担が大きい産褥期に、家庭において、相談や家事の援助が受けられるような体制づくりを検討する必要がある。
- また、女性ばかりに育児を押しつけることが女性の育児ストレスの原因となると考えられることから、少子化対策の観点からも男性の育児参加を促進する必要がある。このため、時間外労働や休日労働を減じる措置の強化、職場優先の企業風土の見直し、性別による固定的な役割分担(意識)の解消等、総合的な対策を検討する必要がある。
- さらに同じ悩みを抱える女性たちの交流を広げることも育児ストレスの解消には効果があると思われることから、孤立化しやすい在宅で子育て中の女性がサークル活動をすることに対する支援等を行うことも検討する必要がある。
- そして、家庭教育に関する悩みや不安を抱く親が、1日の家事や仕事を終えた後に相談したり、夜間、精神的に不安定になるようなケースにも対応できるようにするために、家庭教育に関する電話相談の開設時間を夜間・深夜にまで延長していくことが望まれる。
第3節 閉経期以降
1 更年期障害
(1)現状と問題点
- 更年期障害は、加齢による卵巣ホルモンの減少が原因で生じ、その症状は血管運動神経系症状(のぼせ、発汗、動悸など)、精神神経系症状(憂うつ、不眠など)、運動器系症状(肩こり、腰痛、関節痛など)、泌尿・生殖器系症状(外陰部・ の萎縮性変化)に分類される。
- 岐阜大学の杉浦等が行った35歳〜65歳の女性1,275人を対象としたアンケート調査結果によると、現在更年期であると自覚している者(現更年期群)については、頭痛・肩こりは68.1%、疲れやすいは60.5%、ほてり・のぼせは43.7%、イライラは45.4%の者が自覚している。
- 更年期障害は、この時期の女性にとって通常みられる症状であり、自覚症状には個人差があるが、症状が重い場合には、女性の労働など社会活動に支障を来したり、家庭生活に影響を与える場合がある。
- 更年期障害については、老化現象の一つとして放置されている場合があるが、適切な医療や相談を受けることにより改善されることもある。しかし、現時点においては情報の不足により更年期障害に関する女性の知識が十分でなく、また、相談の場も不足しており、更年期障害に対する適切な対応が十分なされていない。
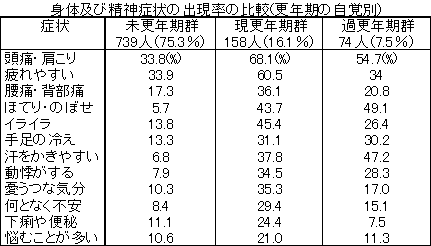
|
出典:
|
杉浦 浩子他 35〜65歳の女性の更年期の自覚、健康意識および身体・精神症状について、
日本更年期医学会雑誌、6(2),179-185,1998
|
(2)現在の行政の対応
- 保健施策としては、「生涯を通じた女性の健康支援事業」により、保健所等において、更年期障害を含む女性特有の健康状況に応じた相談や指導が行われている。
(3)今後の対応の方向性
1)適切な情報提供
- 更年期障害については、その症状等によっては適切な医療や相談を受けることにより改善されることもあるため、生活指導、運動療法、食事摂取、ホルモン補充療法や漢方薬投与等に関する適切な情報提供を行い、理解を深める必要がある。このため、地域の保健婦等による指導やパンフレット等による情報提供の機会を増やす必要がある。
- また、更年期障害は、社会の理解が進んでいないために社会生活に不適合を来す可能性もあり、今後、職場や家庭での理解を深めるため、女性のみならず、事業主や家族への適切な情報提供が必要である。
2)相談機関の整備
- 女性が一人で悩まず身近で気軽に健康相談を受けられるよう、保健所、市町村保健センター等の身近な施設の医師や保健婦、職場では産業医や地域産業保健センターなど専門機関に相談できる体制を整える必要がある。
3)医療機関への受診の勧奨
- 重い更年期障害は、医療機関において適切な診断や治療を受けることが必要であることから、相談機関から医療機関に紹介する体制を整備するとともに、治療に関する情報を提供していく必要がある。
4)研究の推進
- 更年期障害については、個人差が大きく、症状も様々である。そのため、その病態の解明や治療方法に関する研究はもとより、相談体制の構築等も含め、その対応方法について検討していく必要がある。
2 骨粗しょう症
(1)現状と問題点
- 骨粗しょう症は、加齢による骨量の減少等により骨構造の脆弱性が増大する疾病であり、転倒から骨折し寝たきりの状態になる場合もある。
- 東京都老人総合研究所の鈴木らの平成6年の調査によれば、骨量を減少させる要因として、若い女性では無理なダイエットによるカルシウム摂取の不足、閉経期の女性では、閉経そのもの、すなわち急激な女性ホルモンの減少があげられている。
- また、骨粗しょう症の予防には、若い頃からのカルシウムの摂取に加え、適当な運動、バランスの良い食事が必要であることが指摘されている。さらに、超高齢化社会に向け、高齢者の骨折による寝たきりを防ぐためには、家庭内はもとより、社会全体として転倒防止のための注意や工夫、環境整備が重要である。
- また、平成8年の患者調査によれば、骨粗しょう症の受療者数は489,000人であり、平成9年の国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計人口によると、その潜在的なり患者数は平成12年には1,100万人に達すると予測している。
(2)現在の行政の対応
- 老人保健事業における重点健康教育で骨粗しょう症等の予防健康教育を実施するとともに、40歳と50歳の女性を対象に総合健診(節目健診)において、骨粗しょう症健診を実施している。
(3)今後の対応の方向性
- 骨粗しょう症については、特に若い時からの食生活の乱れなどが原因となると考えられるため、早い時期から骨粗しょう症についての知識の普及を図り、食生活についての注意を喚起する必要がある。このため、食事について、学校教育や親への指導、PTA活動などを通じた家庭への働きかけが必要である。
- また、この疾病の予防を図るためには、若い時期から骨量の測定の機会を提供することについて検討する必要がある。さらに、予防のための保健指導のなかに、ストレッチ等の運動療法についても盛り込むことが必要である。
第3章 今後、重点を置くべき生涯を通じた女性の健康施策のあり方につい て
- 以上のように、女性の生涯の各ステージごとの健康についての現状と問題点、それに対する施策について、分析・評価し、今後の対応のあり方を検討してきた。これらを踏まえ、今後、重点を置くべき生涯を通じた女性の健康支援施策のあり方について提言する。
- 今後、厚生省はこの提言を踏まえ、関係省庁と連携し、これらの施策の推進に努めることが望まれる。
1 各省庁総合的、横断的、計画的な生涯を通じた女性の健康施策の推進体 制の創設
- これまでみてきたように、女性には生涯の各ステージごとに様々な健康課題があり、リプロダクティブヘルス/ライツの観点を踏まえ、保健施策、教育施策、労働施策等の多様な施策手段により、総合的、横断的、計画的な対策を講じる必要がある。
- このため、政府においては、厚生省、文部省、労働省、警察庁、総理府等の関係省庁が参集する女性の生涯を通じた健康施策についての連携の場を設けること等により、総合的、横断的、計画的に女性の健康施策を推進すべきである。
2 女性の健康施策の目標と具体的施策の提言
- 生涯を通じた女性の健康支援施策を強力に推進していくため、今後10年間で達成すべき目標と具体的に実施すべき施策を提言する。
(1)生涯を通じた女性の健康支援体制の確立
| 目標: |
広く情報提供を行い、全国民にリプロダクティブヘルス/ライツの意 識の浸透を図る。 |
1)リプロダクティブヘルス/ライツに関する知識等の普及
- (1)人生の思春期、出産可能期、閉経期以降といった、各ステージごとの健康課題に 関する情報を掲載したリプロダクティブヘルス手帳を作成し、思春期の女性を中 心に配付し、生涯を通じた女性の健康づくりについての知識と理解を高めるとと もに、人間関係の築き方についての学習を促進する。
- (2)学校教育における性教育の充実、社会教育における性に関する学習機会の充実を 図る中で、リプロダクティブヘルス/ライツ等に関する知識の普及を図る。
- (3)教師や保健所、市町村保健センター等の担当職員に対する研修を強化する。
- (4)医師会、看護協会、助産婦会等の関係団体の協力も得て、医師、保健婦、助産婦 等に対する研修会等を開催し知識の普及を図る。
- (5)母子保健推進員、愛育班員などのボランティアの資質向上を図る。
- (6)関係機関や関係団体が連携して、リプロダクティブヘルス/ライツに関するシンポ ジウムや講演会等を開催する。
2)「生涯を通じた女性の健康支援事業」の拡大
- ○「生涯を通じた女性の健康支援事業」を行う保健所等の数の拡大や健康教育等の 内容の充実を図り、避妊、月経困難症、不妊、更年期障害等について適切な情報 の提供と相談体制の確保を図る。
(2)望まない妊娠の予防
| 目標: |
人工妊娠中絶件数を1/2に減少させる。特に、10代の人工妊娠中 絶件数を減少傾向に転じさせる。 |
1)思春期の子どもたちに対する性教育の推進
- (1)新しい学習指導要領に基づき、小・中学校、高等学校における性教育を一層推進 する。
- (2)小・中、高等学校の保健、特別活動、総合的学習等において医師、保健婦、助産 婦等の専門家を特別非常勤講師として活用して授業を行うなど指導方法の工夫改 善を図る。
- (3)性やその相談についての養護教諭等の研修を推進する。
2)女性が主体的に避妊するための支援
- (1)低用量経口避妊薬(ピル)や銅付加IUD等、女性が主体的に使うことができる 避妊具に関する知識の普及や正しい使用方法についての指導が受けられるよう努 力するとともに、フィーメール・コンドーム等を含め、避妊具の選択肢の拡大を 図る。
- (2)避妊や人工妊娠中絶についての情報提供、日常生活上の注意点等を盛り込んだ小 冊子の配付を行うとともに、保健所、市町村保健センターや医療機関における保 健指導やカウンセリングを推進する。
- (3)反復中絶を避けるためにも、人工妊娠中絶後の保健指導は重要であり、母体保護 法指定医の研修等を通じて中絶後の指導の推進を図る。
- (4)関係各団体や女性団体等と協力して、性や避妊、人工妊娠中絶に関する議論を通 じて、女性の生き方や健康等について考えるフォーラムを開催する。
(3)安全で快適な妊娠・出産の実現
目標:妊産婦死亡率を1/2に減少させる。
1)妊産婦死亡率の改善
- (1)総合周産期母子医療センターを早急に全都道府県に最低1ヶ所設置する。
- (2)総合周産期母子医療センターを核として、各都道府県に数カ所設置される地域周 産期母子医療センターとのネットワーク化を図る。
2)早産の予防
- (1)原因究明とその予防に関する研究を推進する。
- (2)総合周産期母子医療センターの早急な全国整備と各都道府県における周産期医療 システムの確立を図る。
3)多胎の予防
- ○生殖補助医療における多胎防止の研究を推進する。
4)働く女性の妊娠・出産への支援
- (1)働く女性に対し、適切な保健指導や医療を提供できるよう、労働が妊娠・出産に 与える影響に関する研究を推進する。
- (2)働く女性が妊産婦のための健康診査や保健指導を受けやすくするための環境づく りを推進するとともに、その指導事項を事業主に正確に伝達し適切な措置が講じ られるよう、母性健康管理指導事項連絡カードの普及を図る。
5)快適な出産の普及のための支援
○関係団体との協力のもと、出産に係る医療についてのインフォームド・コンセン トや自己決定の支援を図る。
3 新たな課題への対応
- 生殖補助医療技術の医学的、倫理的、社会的問題に関する検討や、性的虐待に関する研究を推進する。