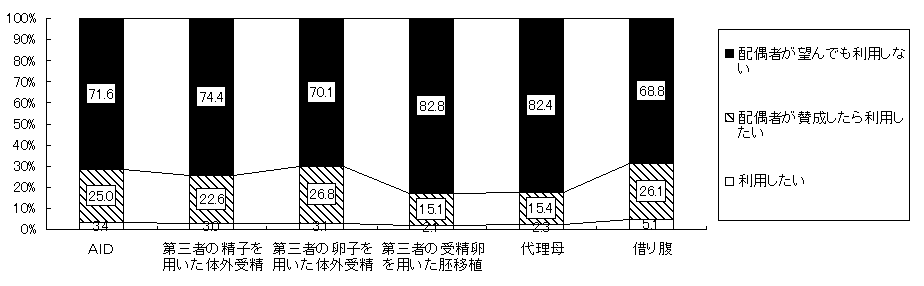
| 報道発表資料 | HOME |
平成11年5月6日
○ 本日午後1時30分から午後4時30分まで、第5回厚生科学審議会先端医療技術評価部会・生殖補助医療技術に関する専門委員会が開催された。
○ まず、「生殖補助医療技術についての意識調査」について、同調査を実施した厚生科学研究費補助金厚生科学特別研究「生殖補助医療技術に関する医師及び国民の意識に関する研究班」の主任研究者である昭和大学矢内原巧教授(専門委員会委員)と分担研究者である山梨医科大学山縣然太朗助教授から調査結果について御報告があった。
○ 次に、「生殖補助医療における法的問題」について、石井美智子委員から御説明があった。
○ さらに、「生殖補助医療技術についての意識調査」及び石井委員の御説明について、質疑と意見交換が行われた。
○ 最後に、次回専門委員会は6月22日午後1時30分から開催することとされた。
平成11年5月6日
調査方法等
|
○調査主体 厚生科学研究費補助金厚生科学特別研究「生殖補助医療技術に対する医師及び国民の意識に関する研究班」主任研究者 昭和大学 矢内原巧教授、分担研究者 山梨医科大学 山縣然太朗助教授
○対象者 一般国民(4,000名)、日本産科婦人科学会体外受精登録医療機関の産婦人科医(402名)、その医療機関を受診している患者(804名)、その他の産婦人科医(400名)、小児科医(400名)の合計6,006名
○調査方法 一般国民は全国の保健所の職員による訪問配布(一部郵送)、患者については、郵送した医師からの手渡し、その他は郵送法により調査を実施。
○調査期間 平成11年2月、3月
○回収率 一般国民70.4%、登録産婦人科医60.4%、患者40.7%、その他の産婦人科医41.6%、小児科医46.5%
|
1 一般国民を対象とした調査
(1)技術の利用
ほとんどの技術について、7割以上の者が「配偶者が望んでも利用しない」と回答。特に第三者の受精卵を用いた胚移植と代理母については、8割以上が、「配偶者が望んでも利用しない」としている。
(設問)あなたが子どもを望んでいるのになかなか子どもに恵まれないとしたら、あなたはこの技術を利用しようと思いますか。
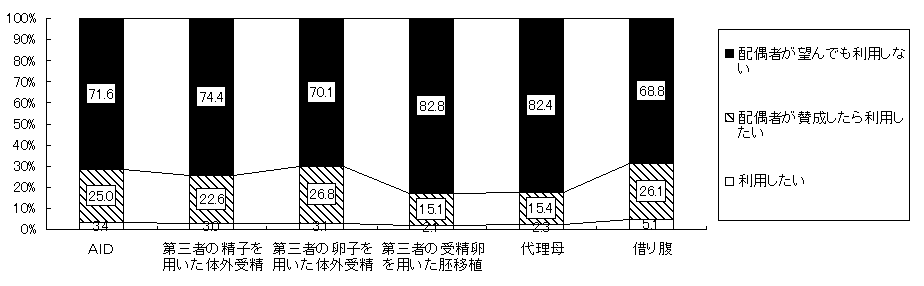
(2)利用しない理由
「配偶者が望んでも利用しない」とする理由は、「家族(親子)関係が不自然になるから」と「妊娠はあくまで自然になされるべきだと思うから」が全ての技術で6割以上となっている。また、代理母と借り腹では「親権や遺産相続などでいろいろなトラブルが生じる可能性があるから」が3割前後となっている。
(設問)「配偶者が望んでも利用しない」と答えた方にうかがいます。その理由は何ですか。
(3)各技術の是非
一般論としては、第三者の受精卵を用いた胚移植と代理母を除く技術について、「認めてよい」又は「条件付きで認めてよい」と答えた者が5割を超えている。
(設問)一般論としてお聞きします。このような技術を社会的に認めるべきだと思いますか。
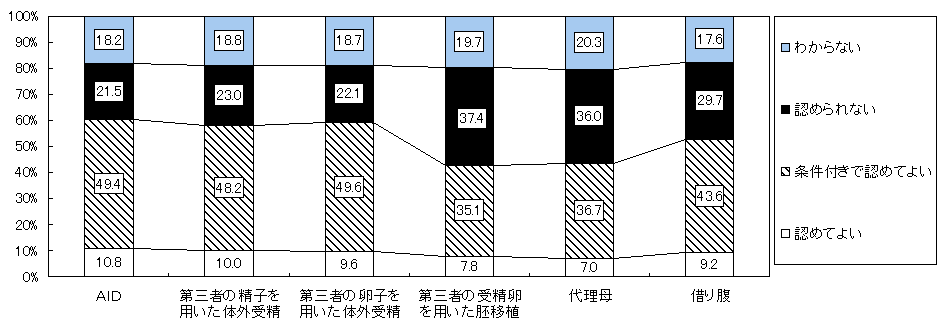
(4)親子関係
「依頼者夫婦の実子とすべき」と答えた者が、AID、第三者の精子を用いた体外受精、第三者の卵子を用いた体外受精、借り腹で6割弱となっているが、第三者の受精卵を用いた胚移植と代理母では、約4割となっている。また、第三者の受精卵を用いた胚移植、代理母、借り腹では「わからない」と答えた者が約4割となっている。
(設問)親子関係を考えた場合、生まれた子供はどのようにすべきと考えますか。
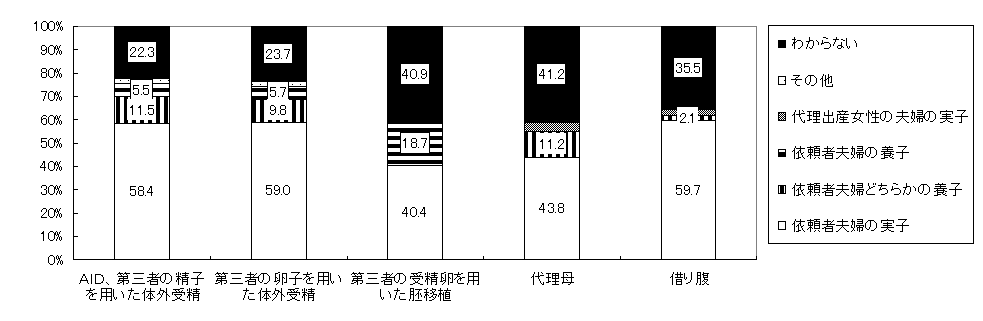
(5)出自を知る権利
生まれた子供が自分の遺伝的な親を知る権利については、いつかの時点で知る権利があるとした者は36.4%となり、「知らないでいるべきである」と答えた者を若干、上回っている。
(設問)生まれた子供は第三者を知る権利についてどのようにすべきだと思いますか。
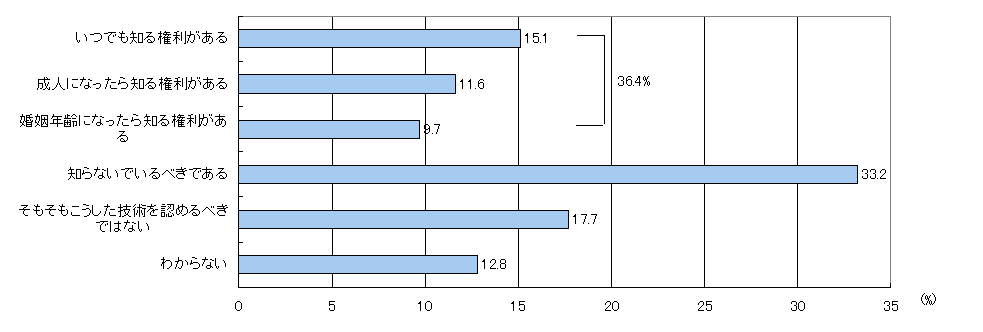
2 患者を対象とした調査
(1)技術の利用
全ての技術について、7割以上の者が「配偶者が望んでも利用しない」と回答。特に第三者の受精卵を用いた胚移植と代理母については、8割以上が、「配偶者が望んでも利用しない」としている。##なお、全ての技術で、「配偶者が望んでも利用しない」と答えた者の割合が、一般国民を上回っている。
(設問)あなたが子どもを望んでいるのになかなか子どもに恵まれないとしたら、あなたはこの技術を利用しようと思いますか。
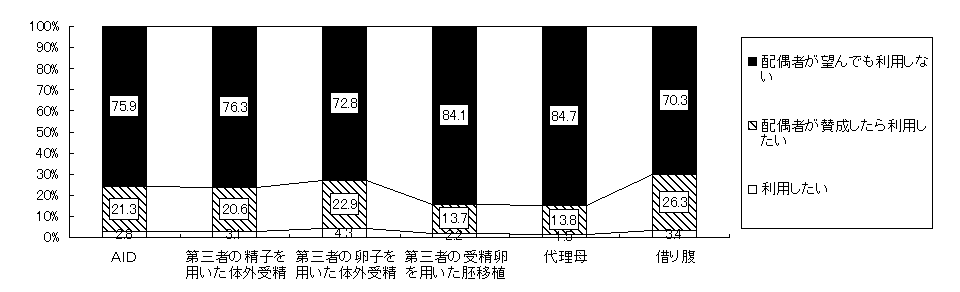
(2)利用しない理由
「配偶者が望んでも利用しない」とする理由は、「家族(親子)関係が不自然になると思うから」がほとんどの技術で6割以上と多くなっている。
(設問)「配偶者が望んでも利用しない」と答えた方にうかがいます。その理由は何ですか。
(3)各技術の是非
一般論としては、全ての技術について、「認めてよい」又は「条件付きで認めてよい」と答えた者が5割を超えており、特に、AID、第三者の精子を用いた体外受精、第三者の卵子を用いた体外受精については、8割弱となっている。
(設問)一般論としてお聞きします。このような技術を社会的に認めるべきだと思いますか。
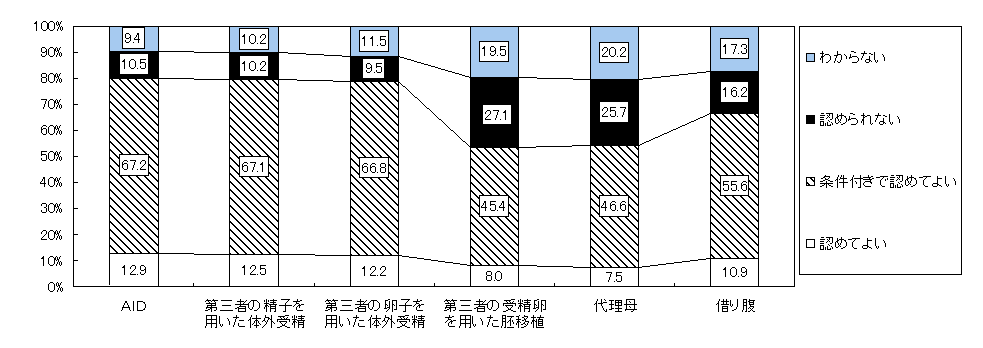
(4)親子関係
「依頼者夫婦の実子とすべき」と答えた者が、AID、第三者の精子を用いた体外受精、第三者の卵子を用いた体外受精、借り腹で7割前後となったが、第三者の受精卵を用いた胚移植と代理母では、5割前後となった。また、第三者の受精卵を用いた胚移植、代理母、借り腹では「わからない」と答えた者が約3割となっている。
(設問)親子関係を考えた場合、生まれた子供はどのようにすべきと考えますか。
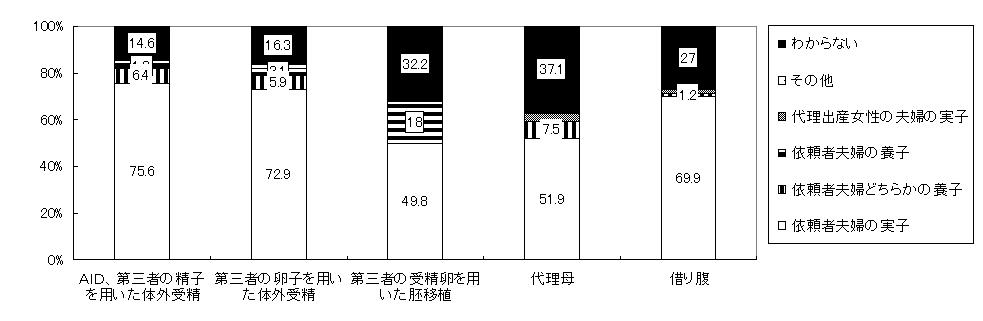
(5)出自を知る権利
生まれた子供が自分の遺伝的な親を知る権利については、いつかの時点で知る権利があると答えた者は43.8%であり、「知らないでいるべきである」と答えた者を上回っている。
(設問)生まれた子供は第三者を知る権利についてどのようにすべきだと思いますか。
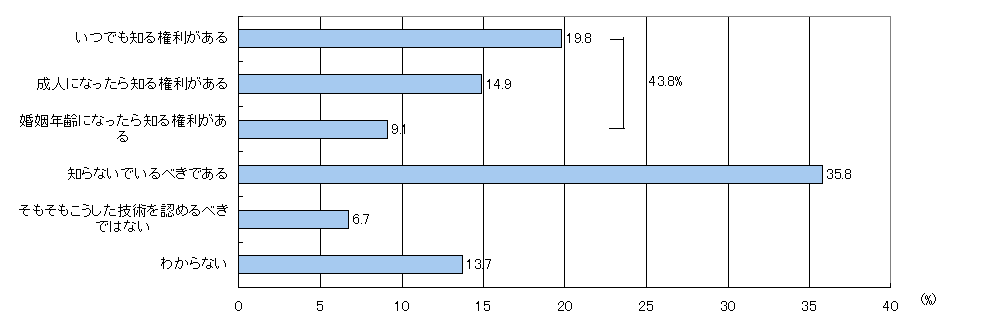
3 医師を対象とした調査
(1)AIDの是非
「認めてよい」又は「条件付きで認めてよい」と答えた者は、体外受精登録産婦人科医で73.7%となっているが、小児科医では、44.8%に止まり、「認められない」 が5割を超えている。
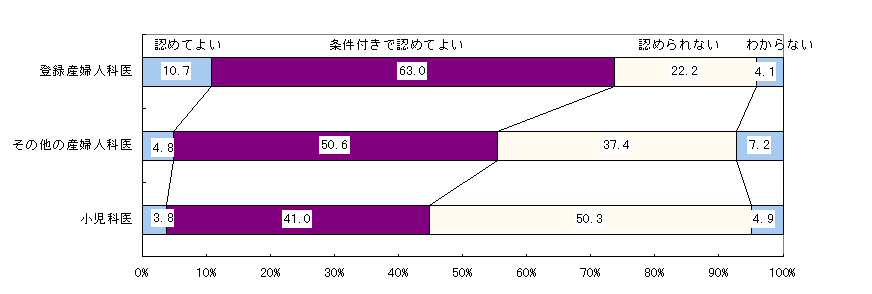
(2)第三者の精子を用いた体外受精の是非
「認めてよい」又は「条件付きで認めてよい」と答えた者は、体外受精登録産婦人科医で65.7%となっているが、小児科医では、45.1%に止まっている。
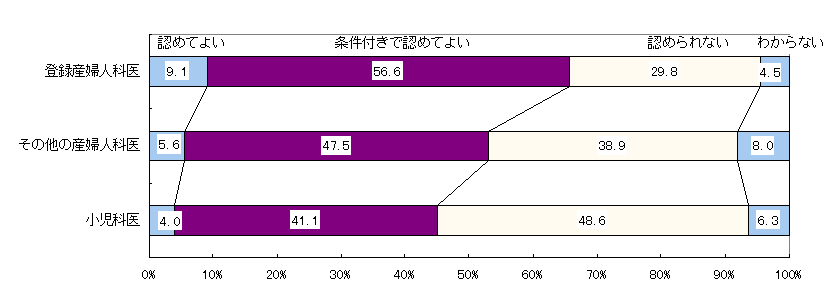
(3)第三者の卵子を用いた体外受精の是非
「認めてよい」又は「条件付きで認めてよい」と答えた者は、体外受精登録産婦人科医で56.2%となっているが、小児科医では、42.9%に止まり、「認められない」が5割を超えている。
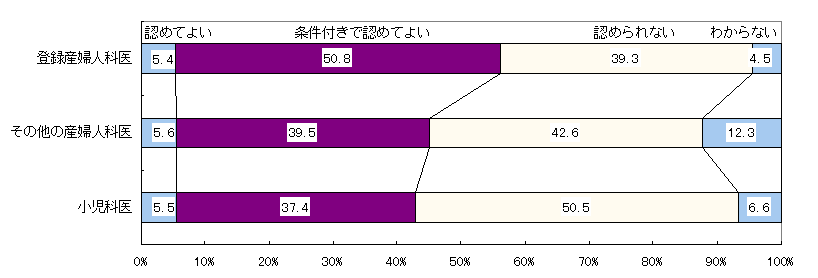
(4)第三者の受精卵を用いた胚移植の是非
体外受精登録産婦人科医、その他の産婦人科医、小児科医の全ての属性で「認められない」が5割を超えている。
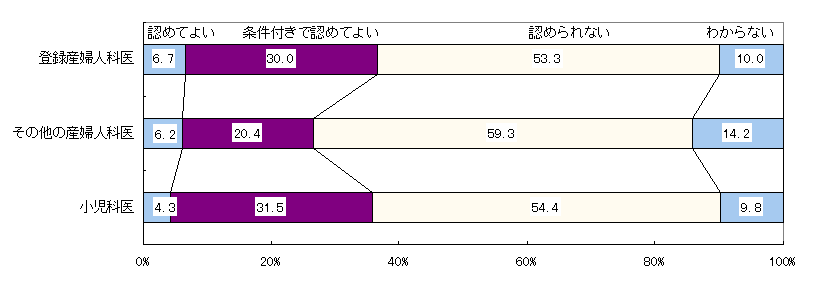
(5)代理母の是非
体外受精登録産婦人科医、その他の産婦人科医、小児科医の全ての属性で「認められない」が5割を超えている。
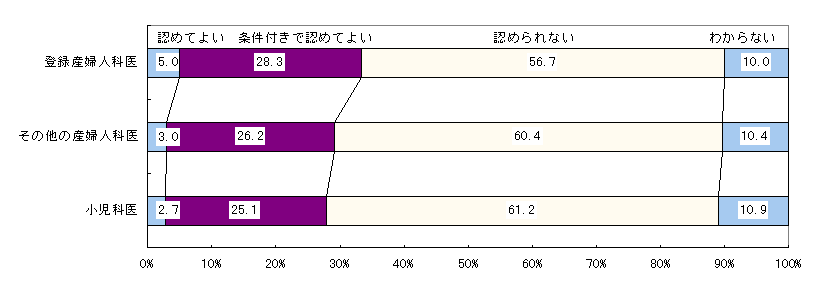
(6)借り腹の是非
体外受精登録産婦人科医では「認めてよい」又は「条件付きで認めてよい」と答えた者が5割を超えているが、その他では、5割を下回っている。
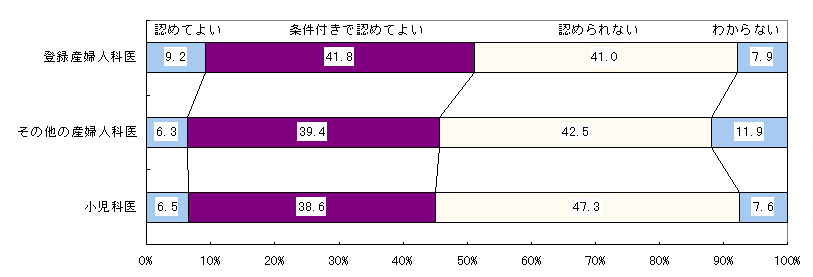
用語の解説
|
○AID:夫以外(第三者)の男性から精子の提供を受けて人工授精を行い妊娠、出産すること。
○第三者の精子を用いた体外受精:夫以外(第三者)の男性から精子の提供を受けて体外受精を行い妊娠、出産すること
○第三者の卵子を用いた体外受精:妻以外(第三者)の女性から卵子の提供を受けて体外受精を行い妊娠、出産すること
○第三者の受精卵を用いた胚移植:夫婦の両方の原因で子どもができない場合に、第三者から提供された精子と卵子でできた受精卵を夫婦が利用し妊娠、出産すること
○代理母:夫婦のうち、妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の女性に人工授精しその女性に妊娠、出産してもらい、その子どもを依頼者夫婦の子どもとすること
○借り腹:夫婦のうち、夫の精子と妻の卵子が使用できるが、子宮摘出等により妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の女性の子宮に入れて、その女性に子どもを出産してもらうこと
|
照会先:厚生省児童家庭局母子保健課 北島(内3173) 武田(内3179) (代表)[現在ご利用いただけません] (直通)03-3595-2544
| 報道発表資料 | HOME |