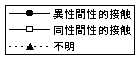
概要
1.エイズ発生動向調査(サーベイランス)の概要
2.診断基準
3.集計方法の対象と方法
4.集計結果を見る上での留意事項
発生動向の分析結果
1.平成9年報告例の主な内訳
2.平成9年12月31日までの累積報告例の内訳
3.HIV及びAIDSの動向
4.都道府県別の報告件数
5.まとめ
表
添付資料
1.ウインドウ・ピリオド中の献血血液によるHIV感染について
エイズ発生動向調査(サーベイランス)は1984年から開始され、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律が1989年に施行されることによって整備され現在に至っている。報告の流れとしては、HIV感染者あるいはAIDS患者を診断した医師が都道府県・指定都市・中核市に「エイズ病原体感染者報告票」(以下、初回報告票と呼ぶ)を7日以内に提出し、その報告票が都道府県・指定都市・中核市から厚生省保健医療局エイズ疾病対策課に集められる。初回報告票がすでに提出されたHIV感染者あるいはAIDS患者に病状の変化(HIV感染者がAIDS発病または死亡、AIDS患者が死亡)があった場合、「エイズ病原体感染者報告票(病状に変化を生じた事項に関する報告)」(以下、病変報告票と呼ぶ)が同様の流れで集められる。いずれの報告票もエイズ動向委員会による審査を通して確定される。なお、凝固因子製剤による感染はこの報告の対象外である。
初回報告票の内容は、HIV感染者・AIDS患者の別、国籍、感染経路、性、年齢、感染場所(日本国内・海外)、居住地(都道府県・指定都市・中核市)、診断年月日、報告年月日などである。病変報告票の内容は、病状の変化の状況とその年月日が入ることを除けば、初回報告票とほぼ同じである。なお、いずれの報告票でも、氏名、生年月日などの個人を特定できる情報は含まれていない。
2.発生動向調査(サーベイランス)のためのAIDS診断基準は下記のとおりである
I HIV検査で感染が認められた場合
酵素抗体法(ELISA)又はゼラチン粒子凝集法(PA法)といったHIVの抗体スクリーニング検査法の結果が陽性で、かつWestern Blot法又は蛍光抗体法(IFA)といった確認検査法の結果も陽性であった場合、または抗原検査、ウイルス培養、PCR法などの病原体に関する検査(以下、「病原検査」という。)によりHIV感染が認められた場合であって、下記の特徴的症状(indicator Diseases)の1つ以上が明らかに認められるときはAIDSと診断する。
II 周産期に母親がHIVに感染していたと考えられる生後15ヶ月未満の児の場合 周産期に母親がHIVに感染していたと考えられる生後15ヶ月未満の児については、HIVの抗体確認検査が陽性であっても、それだけではHIV感染の有無は判定できないので、さらに以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合で免疫不全を起こす他の原因が認められないものをAIDSと診断する。
※ ※ 肺結核及び浸潤性子宮頸癌については、HIVによる免疫不全を示唆する症状または所見がみられる場合に限る。 (厚生省エイズサーベイランス委員会,1994) |
3. 集計の対象と方法
1997年12月31日までに厚生省エイズ動向委員会によって確定されたHIV感染者とAIDS
4.集計結果を見る上での留意事項
HIV感染者の多くは、感染後のかなり長い期間、特定の症状がなく、検査を受けてはじめて感染が判る。診断されたHIV感染者のエイズサーベイランスへの報告漏れは比較的少ないと思われるが、検査を受けていないHIV感染者がいるために、国内に存在するすべてのHIV感染者の内で報告されている者の割合は必ずしも高くない可能性がある。一方、AIDS患者は特定の症状を有することが多く、医療機関を受診する。診断されたAIDS患者の医療機関からの報告率がきわめて高いことを考慮すると、AIDS患者の報告率はかなり高いと考えられる。
患者を集計対象とした。なお、前述の通り、この中には、凝固因子製剤による感染は含まれていない。HIV感染者に関する情報は初回報告票から、AIDS患者に関する情報は初回報告票と病変報告票から得た。
HIV感染者とAIDS患者を、日本国籍と外国国籍ごとに、年次、感染経路、性、年齢、感染場所、居住地の別およびそれらの組み合わせの別に集計した。年次は診断時点、報告時点ではなく、エイズ動向委員会での確定時点としたが、詳細は4に記す。感染経路は異性間性的接触、同性間性的接触、静注薬物濫用、母子感染、その他、不明の6区分とした。同性間性的接触には両性間性的接触を含めた。また、女性には同性間性的接触がないので、男性のみを集計した。その他の感染経路には輸血や臓器移植などとともに、可能性のある感染経路が複数あるケース(同性間性的接触と静注薬物濫用のいずれかなど)を含めた。
エイズサーベイランスでは、同一者に対して複数の初回報告票を提出しないこと、病状が変化しない限り、同一者に対して複数の病変報告票を提出しないことが定められている。ただ、前述の通り、報告票には個人を特定できる情報が含まれていないために、報告に若干の重複がある可能性を否定できない。HIV感染者とAIDS患者の間には病変報告分の重複がある。本集計では、HIV感染者とAIDS患者を別々に重複して数えており、そのために、それらを合計しても意味がない。
本集計では、日本国籍と外国国籍を別にしているが、これは、両者の感染経路の状況や年次推移の傾向などが大きく異なるためである。
前述のように、年次を診断時点でなく、エイズ動向委員会の確定時点とした。多くの症例では報告は診断後速やかに行われ、直ちにエイズ動向委員会が審査・確定している。ただ、様々な事情から報告が遅れるケースもある。1990~1997年にエイズ動向委員会により確定されたHIV感染者の中で、確定されたのが診断の翌年であったケースは3.5%、2年以上遅れたケースは0.4%であった。同様に、1990~1997年に確定されたAIDS患者では、確定されたのが診断の翌年のケースは5.4%、2年以上遅れたケースは2.9%であった。報告票の年齢欄には診断時点あるいは報告時点などの規定はないが、確定が診断や報告よりも極端に遅れるケースはきわめて稀であるので、年齢を診断時点あるいは報告時点のいずれのものとみても、全体像を把握する上で大きな問題はない。
発生動向の分析調査
| 図1 HIV及びAIDS患者の国籍、感染経路別年次推移 | 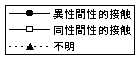 |
| a日本国籍HIV感染者
|
b外国国籍感染者
|
|
| c日本国籍AIDS患者
|
d外国国籍AIDS患者
|
|
| 図2 HIV感染者及びAIDS患者の国籍、性別年次推移 | 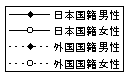 |
| aHIV感染者
|
bAIDS患者
|
(1)HIVの動向
日本国籍男性の場合:異性間と同性間性的接触がほぼ同数(443 v.s495)で報告件数の大半を占め、かつ増加の中心である(以上表5)。異性間性的接触は、年齢のピークが30-34歳、国内感染が大半(59.8%)を占める(以上表9-1)。国内感染例の割合は近年緩やかに増加しつつある(図3)。居住地別では、関東甲信越ブロック(以下東京都を除く)45.6%、東京都31.6%で、ほぼ全ブロックで増加が続いている(以上表9-1)。一方、同性間性的接触では、年齢は25-29歳がピークでやや若く、国内感染の比率がさらに大きい(79.6%)(以上表9-2)。異性間性的接触の場合と同様、国内感染例が緩やかに増加しつつある(図3)。東京都57.2%、関東甲信越ブロック22.2%と、東京都の比率が大きく(図4)、東京都では増加が続いているが、近畿ブロックでも1997年に報告数が急増した(以上表9-2)。
日本国籍女性の場合:異性間性的接触が、増減しつつも緩やかに増加している(以上表5)。年齢のピークは25-29歳で、感染場所の大半はほぼ一貫して国内(72.5%)であり、居住地は、関東甲信越ブロック38.5%、東京都28.6%で(以上表9-3、図4)、日本国籍男性に比べると、これらの地域の占める割合がやや小さい(以上表9-3)。
外国国籍男性の場合:異性間性的接触が同性間性的接触の約1.6倍で、いずれも1996年までは緩やかな増加傾向を示し、1997年に減少した(以上表5)。異性間性的接触の年齢のピークは、30-34歳、感染場所は海外が大半(66.9%)であるが、国内感染も15.3% 存在する。居住地は、関東甲信越ブロックと東京都がほぼ同数で、計75.8%を占める(以上表9-4、図4)。同性間性的接触は、年齢のピークが25-29歳とやや若く、66.7%が東京都に集中している(以上表9-5、図4)。感染経路不明例は、数、年次推移ともにほぼ異性間性的接触に近い(以上表5)。
外国国籍女性の場合:異性間性的接触が、1992年に大きなピークを示した後減少し、過去3年間ほぼ横ばいの状態にある(以上表5)。年齢のピークは、20-24歳ともっとも若く、感染場所は国外感染と不明が多いが、国内感染も15.0%存在する。居住地は、関東甲信越ブロックが68.6%、東京都が21.0%を占める(以上表9-6、図4)。感染経路不明は、数、年次推移ともにほぼ異性間性的接触に近い(以上表5)。
| 図3 日本国籍HIV感染者の感染場所の年次推移 |  |
| a異性間性的接触の男性
|
b同性間性的接触の男性
|
|
| c異性間性的接触の女性
|
| 図4 感染経路、国籍、性別の居住地の分布 |
| aHIV感染者
|
bAIDS患者
|
(2)AIDSの動向
日本国籍男性の場合:異性間性的接触が報告件数、増加傾向いずれも最も大きく、同性間性的接触は過去4年間40件前後でほぼ横ばい状態にある(以上表5)。異性間性的接触では、年齢のピークは45-49歳、感染場所は、1994年までは海外感染が主であったが、1995年以降は国内感染が主となった。累計では国内感染が50.3%である。居住地は、関東甲信越ブロック46.0%、東京都26.3%で(以上表9-1、図4)、1997年に北海道、近畿ブロックで報告が増加した(以上表9-1)。同性間性的接触では、年齢のピークは40-44歳で、感染場所は、国内が中心(64.8%)でその傾向は1991年以降一貫している。居住地は東京都が中心で57.7%、関東甲信越ブロックは23.3%であり(以上表9-2、図4)、多くのブロックで1997年に報告数が減少した(以上表9-2)。感染経路不明例が21.1%存在する(以上表5)。
日本国籍女性の場合:異性間性的接触は、1995年以来年間約10件と横ばいで(以上表5)、年齢のピークは30-34歳、国内感染が主(60.0%)で、居住地は相対的には関東甲信越ブロックに多いが、全国に分散している(以上表9-3、図4)。感染経路不明例が23.8%存在する(以上表5)。
外国国籍男性の場合: 異性間性的接触が1992年以来優位で、1996年まで増加を続け、1997年に減少した。同性間性的接触は年間数例にとどまっている(以上表5)。異性間性的接触では、年齢のピークは30-34歳、海外感染が主(66.7%)で、東京都、関東甲信越ブロックに72.0%が集中している(以上表9-4、図4)。同性間性的接触では、年齢のピークは30-34歳、海外感染が主(54.1%)で、東京都に62.2%が集中している(以上表9-5、図4)。感染経路不明例が41.6%存在する(以上表5)。
外国国籍女性の場合:異性間性的接触と感染経路不明例がほぼ同数で、少数ではあるが緩やかな増加傾向にある(以上表5)。異性間性的接触の年齢のピークは25-29歳、感染場所は海外(38.1%)、居住地は関東甲信越ブロック(66.7%)が中心である(以上表9-6、図4)。
| 図5 人口10万対報告件数の国籍別都道府県別の分布 | 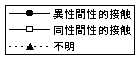 |
| a日本国籍HIV感染者
|
b外国国籍感染者
|
|
| c日本国籍AIDS患者
|
d外国国籍AIDS患者
|
|
(2)外国国籍者の報告が、なお少なからず存在する。
(3) 感染経路は、凝固因子製剤による感染以外では、HIV、AIDSとも性感染によるものが 大半で、静注薬物濫用や母子感染によるものはなお少数にとどまっている。
(4) 性感染の感染場所は、日本国籍者の場合HIV、AIDSとも大半(50-80%)が国内で、男性のHIVでは国内感染の比率が近年さらに高まりつつある。外国国籍者にも、少なからず国内感染例が報告されている。
(5) 報告例の居住地は、一般に関東甲信越ブロックと東京都に集中し、同性間性的接触による感染例はとりわけ東京都に集中している。
(6)献血のHIV抗体スクリーニング開始後の国内血液輸血で感染した症例が初めて報告された。
添付資料
5.まとめ
(1)HIVとAIDSの報告件数は依然増加基調にあり、その中心は日本国籍の男性である。
| 伊 藤 章 | 横浜市立大学医学部助教授 | |
| 河 﨑 則 之 | 国立療養所福井病院長 | |
| 栗 村 敬 | 大阪大学名誉教授 | |
| 島 田 馨 | 東京専売病院長 | |
| 曽 田 研 二 | 横浜市立大学医学部教授 | |
| 田 島 和 雄 | 愛知県がんセンター研究所疫学部長 | |
| 根 岸 昌 功 | 東京都都立駒込病院感染症科医長 | |
| ※ | 山 崎 修 道 | 国立感染症研究所長 |
| 山 田 兼 雄 | 聖マリアンナ医科大学客員教授 |
| (50音順) | ||||||||||||
|
問合せ先 厚生省保健医療局エイズ疾病対策課 池田(内線2358) 大澤(内線2355)