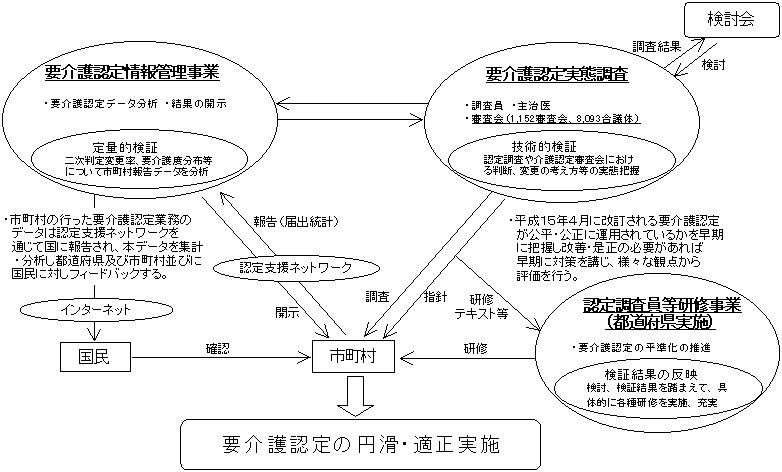
| 事業評価書要旨( |
|
・事後) |
| 評価対象(事務事業名) | 広域化等保険者支援事業費 | |
| 担当部局・課 | 主管課 | 老健局介護保険課 |
| 関係課 | ||
| 番号 | ||
| 基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
| 施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
| I | 介護保険制度の適切な運営を図ること |
|
||||||||
| 1.広域化市町村分 小規模市町村が、市町村合併や広域連合等の介護保険広域化を図る場合。 2.離島等市町村分 介護報酬の離島等加算分(15%)が行われている場合。 3.その他加算分 その他特別な事情がある場合。 |
||||||||
|
||||||||
| H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
| − | − | − | − | 1,756 | ||||
| 目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度 | ||||||||||||||||
| アウトカム指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 | |||||||||||
|
本件の政策効果は、実際に介護保険広域化を行った市町村数や保険料の引き下げ効果で測るしかないと考えられるが、具体的な目標値の設定については、
等から困難であるが、小規模市町村ができるだけ広域化を行うよう、都道府県と協働して周知に努めていく。 |
||||||||||||||||
| (説明) 介護保険にかかる広域化を実施する市町村 |
(モニタリングの方法) 介護保険課調査等 |
||||||||||||||||
| 参考指標(過去数年度の推移を含む) | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | ||||||||||||
| 介護保険広域化保険者数 (参加市町村数) |
− (−) |
− (−) |
− (−) |
59 (441) |
63 (457) |
||||||||||||
| (説明) 介護保険にかかる広域化を実施した保険者(参加市町村数は広域化前の数字) |
(モニタリングの方法) 介護保険課調査(各年度11月1日現在) |
||||||||||||||||
| 公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
|||
| (理由) 小規模保険者が広域化を図ることは、その地域の介護保険の安定的な運営をもたらすものであり、ひいては住民の生活に資すること。 |
||||
| 国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
|||
| (理由) 現在、政府としても市町村合併プラン等に基づき広域化を強力に推進しているところであり、介護保険においても、上述のように制度の安定的な運営を図る観点とあわせて、国が支援を行う必要がある。 |
||||
| 民営化や外部委託の可否 |
|
|||
| (理由) 市町村介護保険財政への支援であり、民間・外部委託になじまないこと。 |
||||
| 緊要性の有無 |
|
|||
| (理由) 広域化は制度が完全に定着していくまでの間に促進していくことが重要であり、現時点で支援する意義が大きい。 |
||||
| 政策効果が発現する経路 |
| 広域化支援体制の整備 →各市町村における介護保険広域化等の論議の活発化 →広域化実施保険者増による介護保険運営の安定 |
| これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
| 15年度からの本件実施により、各市町村にとって第二期事業運営期間内における広域化実施の検討が円滑に進められる。また合併の検討にも効果がある。 |
| 政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
| なし |
| 事業評価書要旨( |
|
・事後) |
| 評価対象(事務事業名) | 要介護認定実態調査事業 | |
| 担当部局・課 | 主管課 | 老健局老人保健課 |
| 関係課 | ||
| 番号 | ||
| 基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
| 施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
| I | 介護保険制度の適切な運営を図ること |
|
||||||||
| 要介護認定は、介護保険の給付の条件であることから、同じ状態にあるものは同じ要介護度となる客観性の確保が重要であるが、この客観性を確保するためには二次判定が適切に行われる必要がある。しかしながら、一次判定結果を二次判定で変更する割合は地域(市町村)によって一様ではない。 このため、平成15年4月から導入される改訂要介護認定ソフトに基づく要介護認定について、要介護認定が適切に行われているかを把握し、適正化・平準化の観点から、市町村の実施状況についての検証を行い、得られた結果について、二次判定指標の作成の検討や、認定調査マニュアル等の研修資料、介護認定審査会運営要綱等の通知等の作成に反映させることによって二次判定による要介護度の変更割合の地域差を是正し、もって要介護認定の客観性を確保することを目的とする。 |
||||||||
|
||||||||
| H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
| − | − | − | − | 57 | ||||
| 目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度(政策効果発現時期) | |||||
| アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
| 実態調査件数 | ||||||
| (説明) 当該実態調査を実施した件数(うち二次判定による変更件数) |
(モニタリングの方法) 事業実績報告によりモニタリング |
|||||
| 公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
| (理由) 要介護認定は公平・公正に行われる必要があることから行政が行う必要があり、その実態に係る調査も行政が行う必要がある。 |
|||||
| 国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
||||
| (理由) 要介護認定は全国的に同じ根拠・解釈に基づいて行われる必要があるため、その実態に係る調査は国が中心となって行う必要がある。 |
|||||
| 民営化や外部委託の可否 |
|
||||
| (理由) 当該実態調査事業については、外部委託によって実施する予定である。 |
|||||
| 緊要性の有無 |
|
||||
| (理由) 平成15年度から改訂一次判定ソフトの使用が始まることから、改訂ソフトの一次判定結果を受け公平・公正な二次判定を行えるよう、当該実態調査事業は早急に行う必要がある。 |
|||||
| 政策効果が発現する経路 |
| 別紙1参照 |
| これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
| 当実態調査事業の実施によって、二次判定変更率の地域差が是正され、もって要介護認定の客観性が担保される。ひいては介護保険制度に対する国民の信頼を高めることとなり、制度の安定運営に寄与する。 |
| 政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
| 他の政策の影響としては、要介護認定の適正化のために行う他の事業(介護認定平準化研修事業、要介護認定情報管理事業)がある。 |
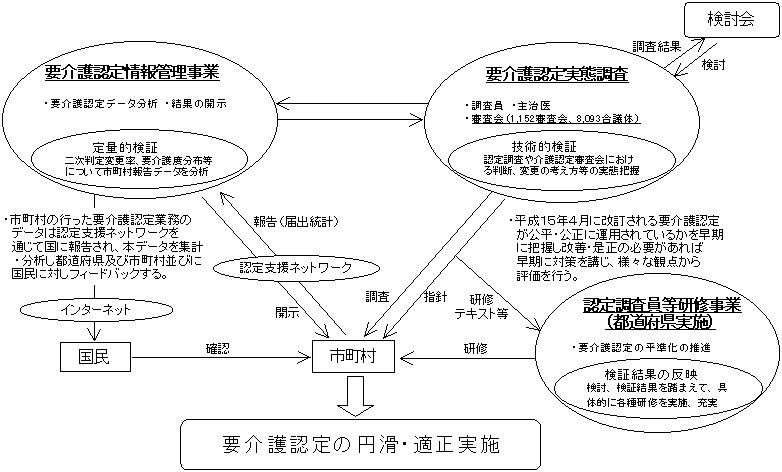
| 事業評価書要旨( |
|
・事後) |
| 評価対象(事務事業名) | 介護認定平準化研修事業 | |
| 担当部局・課 | 主管課 | 老健局老人保健課 |
| 関係課 | ||
| 番号 | ||
| 基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
| 施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
| I | 介護保険制度の適切な運営を図ること |
|
||||||||
| 要介護認定は、介護保険の給付の条件であることから、同じ状態にあるものは同じ要介護度となる客観性の確保が重要であるが、この客観性を確保するためには二次判定が適切に行われる必要がある。しかしながら、一次判定結果を二次判定で変更する割合は地域(市町村)によって一律ではない。 このため介護認定審査会委員長、合議体の長及びこれに準ずる委員並びに市町村職員を対象に、審査判定が困難な事例における審査会の進め方、事例の考え方等に関する研修を実施し、審査会の運営方法の確認及び審査判定に迷う事例検討等を実施し、二次判定による要介護度の変更割合の地域差を是正し、もって要介護認定の客観性を確保する必要がある。 |
||||||||
|
||||||||
| H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
| − | − | − | − | 84 | ||||
| 目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成15年度(政策効果発現時期) | |||||
| アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
| 研修受講者数 | ||||||
| (説明) 当該研修を受講した人数(うち二次判定による変更件数) |
(モニタリングの方法) 事業実績報告によりモニタ |
|||||
| 公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
| (理由) 要介護認定は公平・公正に行われる必要があることから行政が行う必要があり、その平準化に係る研修も行政が行う必要がある。 |
|||||
| 国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
||||
| (理由) 要介護認定は全国的に同じ根拠・解釈に基づいて行われる必要があるため、その平準化に係る事業は国が中心となって行う必要がある。 |
|||||
| 民営化や外部委託の可否 |
|
||||
| (理由) 当該研修事業については、研修の適正な実施・運営が担保されれば外部委託は可能と思われる。 |
|||||
| 緊要性の有無 |
|
||||
| (理由) 平成15年度から改訂一次判定ソフトの使用が始まることから、改訂ソフトの一次判定結果を受け公平・公正な二次判定を行えるよう、当該研修事業は早急に行う必要がある。 |
|||||
| 政策効果が発現する経路 |
| 別紙1参照 |
| これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
| 当研修の実施によって、二次判定変更率の地域差が是正され、もって要介護認定の客観性が担保される。ひいては介護保険制度に対する国民の信頼を高めることとなり、制度の安定運営に寄与する。 |
| 政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
| 他の政策の影響としては、要介護認定の適正化のために行う他の事業(要介護認定実態調査事業、要介護認定情報管理事業)がある。 |
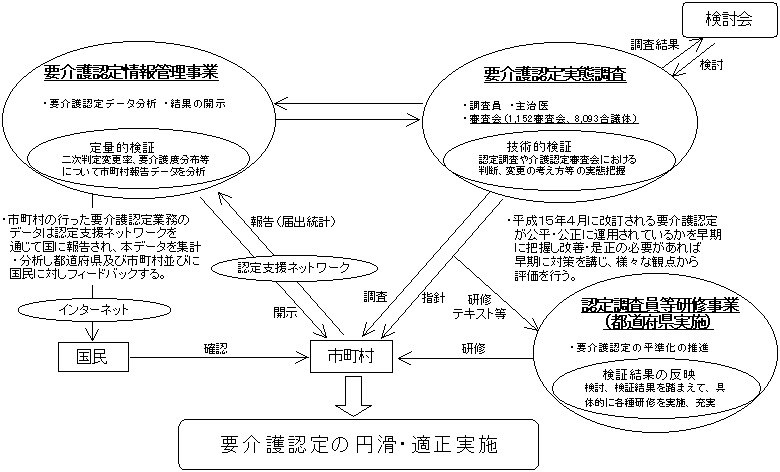
| 事業評価書要旨( |
|
・事後) |
| 評価対象(事務事業名) | 介護報酬調査検討事業 | |
| 担当部局・課 | 主管課 | 老健局老人保健課 |
| 関係課 | ||
| 番号 | ||
| 基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
| 施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要な高齢者への支援を図ること |
| I | 介護保険制度の適切な運営を図ること |
|
||||||||
| 介護報酬の改定見直しを行うに当たっての調査のための調査手法の検討、調査票の作成、電子回収のためのシステム開発、検票システムの開発を行う | ||||||||
|
||||||||
| H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
| − | − | − | − | 39 | ||||
| 目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成16年度(次回調査時) | |||||
| アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
| (説明) 当該実態調査を実施した件数 |
(モニタリングの方法) 実態調査報告書としてモニタリング |
|||||
| 公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
||||
| (理由) 各種利害関係者がいる中、公平・公正な介護報酬の改定見直しを行うためには行政で調査を行う必要がある |
|||||
| 国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
||||
| (理由) 介護報酬は、介護保険サービスの価格として全国に適用されるものとして国が定めるものであり、その基礎資料となる調査は、国で統一して行う必要がある。 |
|||||
| 民営化や外部委託の可否 |
|
||||
| (理由) 秘密の保持が担保されるのであれば可能と思われる |
|||||
| 緊要性の有無 |
|
||||
| (理由) 次回改定予定は平成18年度であり、調査を行うのが平成16年度からとなるため平成15年度中にシステムの開発等を行っておく必要がある。 |
|||||
| 政策効果が発現する経路 |
| 当検討事業を行うことにより、次回調査の際には、新たな調査票、電子回収システム、検票システムによって調査を行うことが可能となり、正確な数値の把握、迅速、的確な分析が可能となる。それによって、より公平・公正な介護報酬の改定見直しを行うことが可能となる。 |
| これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
| 調査対象者の記入者負担が軽減される。正確な調査結果を得ることができ、それに基づく介護報酬見直しがおこなわれることになり、国民の信頼を高めることになる。 |
| 政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
| 特になし |
| 事業評価書要旨( |
|
・事後) |
| 評価対象(事務事業名) | 苦情・事故事例活用研修事業 | |
| 担当部局・課 | 主管課 | 老健局振興課 |
| 関係課 | ||
| 番号 | ||
| 基本目標 | 9 | 高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること |
| 施策目標 | 4 | 介護保険制度の適切な運営等を通じて、介護を必要とする高齢者への支援を図ること |
| II | 質・量両面にわたり介護サービス基盤の整備を図ること |
|
||||||||
| 介護サービス事業者の管理・監督者層を対象に、 ・苦情の背景・要因分析とサービスの質への反映 ・事故防止対策と事故発生時の対応(リスクマネジメント) についての、組織的な取組手法に関して自治体が研修を実施する場合に一定の補助を行う。 |
||||||||
|
||||||||
| H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||||
| 58 | ||||||||
| 目標達成年度(又は政策効果発現時期) | 平成17年度 | |||||
| アウトプット指標 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | 目標値/基準値 |
| 研修修了者数 | ||||||
| (説明) 修了予定者数 14,100人/年 |
(モニタリングの方法) 自治体へのヒアリング |
|||||
| 公益性の有無(主に官民の役割分担の観点から) |
|
|||
| (理由) 介護保険制度が施行されその枠組みは定着をしてきたが、今後本制度を円滑に実施していくためには、介護サービスの質的な確保・向上が重要な課題であり、介護サービスの質を向上させるための苦情対応手法やリスクマネジメント手法を適正に普及・定着させるために、公が一定の役割を果たす必要がある。 |
||||
| 国で行う必要性の有無(主に国と地方の役割分担の観点から) |
|
|||
| (理由) 介護保険制度をより一層定着させ、安定的に運営するためには、介護サービス事業者の健全育成を図り、多様な事業主体による健全な競争を通じた効率的な介護サービス供給を確保することが必要であり、国が一定の役割を果たす必要がある。 |
||||
| 民営化や外部委託の可否 |
|
|||
| (理由) 事業実施主体である都道府県が適当であると認められる団体に委託し、実施することが可能。 |
||||
| 緊要性の有無 |
|
|||
| (理由) 介護保険制度が施行されその枠組みは定着をしてきたが、今後本制度を円滑に実施していくためには、介護サービスの質的な確保・向上が重要な課題である。その取組の中心となる苦情対応手法やリスクマネジメント手法をできるだけ早期に普及・定着させる必要がある。 |
||||
| 政策効果が発現する経路 |
| 研修を受講した介護サービス事業者が、組織として継続的に苦情対応及びリスクマネジメントに取り組むことで、良質かつ安全なサービスが供給され、政策効果が利用者からの評価(満足度等)により発現するものと考えられる。 |
| これまで達成された効果、今後見込まれる効果 |
| 研修を受講した介護サービス事業者が、良質な介護サービスを供給することにより、介護保険制度の一層の定着及び円滑な実施が期待される。 |
| 政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項 |
| なし |