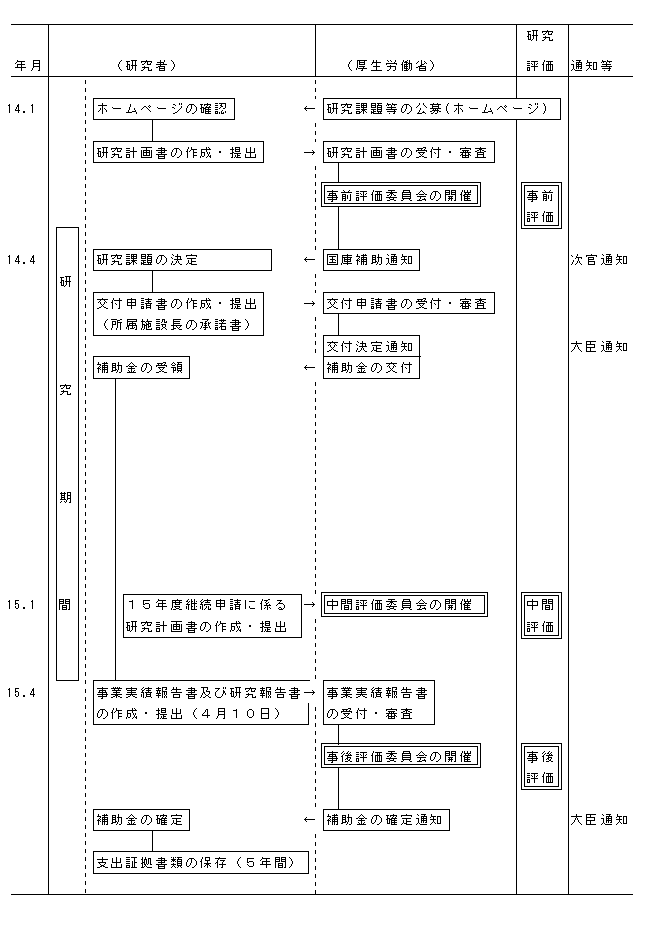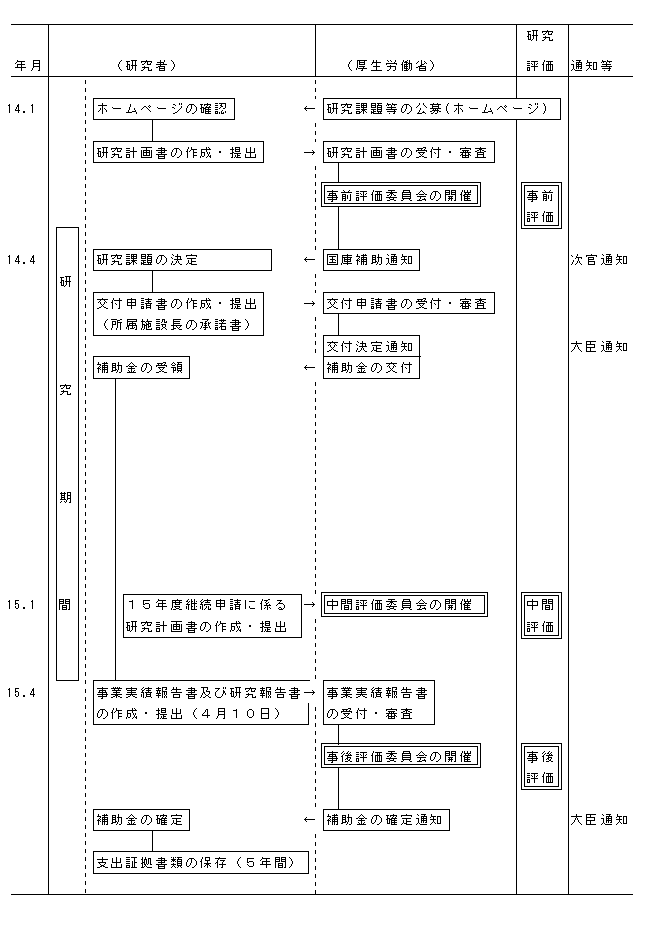公募要項目次
前ページ
次ページ
5.公募研究事業の概要等
(1)各研究事業の概要及び新規課題採択方針等
ア.政策科学推進研究事業
- <事業概要>
- 社会保障制度に対する国民の関心は高まっており、今後も重要視される問題であり、社会保障政策を進めていくうえで専門的・実務的な観点からの実証的研究を踏まえた政策の企画立案が求められている。
このような観点から、本研究事業は人文・社会科学系を中心とした人口・少子化問題、社会保障制度全般に関する研究、年金に関する政策科学研究等に積極的に取り組み、厚生労働行政施策の企画立案及び効率的な推進に資することを目的としている。
- <新規課題採択方針>
- 人口・少子化問題に関する調査研究、社会保障制度全般、社会保障と社会・経済、社会保障分野における情報化・政策評価、医療・介護の経済的評価、年金に関する政策科学研究。
多職種による共同研究で施策に直結する実証的研究で短期間で具体的な成果を上げることが見込まれるものを積極的に評価。
| 研究費の規模: |
1課題あたり1,000千円以上(1年当たり) |
| 研究期間: |
1〜3年 |
| 新規採択予定課題数: |
45〜50課題程度 |
- <公募研究課題>
- (1) 人口問題に関する調査研究(14010101)
- (ア) 婚姻、離婚等結婚行動の変化及びその今後の動向に関する調査研究
(イ) 夫婦の出生過程に及ぼす影響要因、その今後の動向及びこれらに対する政策的対応に関する調査研究
(ウ) 人口、世帯及び家族の構造の変動及びその今後の動向に関する調査研究
(エ) 地域、家族等の私的ネットワーク機能の変動及びその今後の動向に関する調査研究
(オ) 人口及び世帯推計の手法に関する調査研究
(カ) その他人口問題に関する調査研究(国際比較研究を含む。)
- (2) 少子化問題に関する調査研究(14010201)
- (ア) 少子化が社会及び経済に与える影響に関する調査研究
(イ) 少子化の進行要因の分析及びその対策に関する調査研究
(ウ) 少子化対策の評価に関する調査研究
(エ) 家族政策の在り方に関する調査研究
(オ) その他少子化問題に関する調査研究(国際比較研究を含む。)
- (3) 社会保障全般に関する政策科学研究(14010301)
- (ア) 社会保障と低所得及び貧困との関係に関する調査研究
(イ) 社会保障とソーシャル・インクルージョン(貧困者や失業者、ホームレス等社会から排除されている人々の社会的参入)との関係に関する調査研究
(ウ) 社会保障におけるサービス提供主体の在り方(社会福祉法人、民間企業、非営利団体等)に関する研究
(エ) 措置制度から契約制度への移行に伴って必要となるサービス利用者との契約の在り方等社会保障分野における法律学的な分析及び研究
(オ) その他社会保障に関する政策科学研究(国際比較研究を含む。)
- (4) 社会保障と経済及び社会との関係に関する政策科学研究(14010401)
- (ア) 人口、経済及び社会保障の総合的なモデルに関する研究
(イ) 社会保障の財源及びその経済効果に関する研究
(ウ) 社会保障負担における資産の取扱いに関する研究
(エ) 社会保障制度が家計等経済主体に及ぼす影響に関する研究
(オ) 個人レベルの社会保障の給付と負担に関する情報を各人に提供する仕組みに関する研究
(カ) 社会保障政策と労働政策との連携に関する研究
(キ) 就労形態の変化と社会保障との関係に関する研究
(ク) 家族構造及び女性のライフコース(一生を生きていく道筋)の変化と社会保障との関係に関する研究
- (5) 社会保障分野における情報化及び地域政策推進に関する政策科学研究(14010501)
- (ア) 情報化社会における社会保障政策の在り方に関する研究
(イ) 情報化による社会保障行政の効率化に関する研究
(ウ) 社会保障分野における個人情報の保護及び利活用に関する研究
(エ) 社会保障分野における情報化の進展が経済及び社会に及ぼす影響に関する研究
(オ) 地方分権、市町村合併、まちづくり等の観点を踏まえた地域特性に応じた社会保障政策の在り方に関する研究
(カ) 社会保障政策の形成における地域住民の参加に関する研究
- (6) 社会保障分野における政策評価の在り方に関する政策科学研究(14010601)
年金、医療、福祉等の社会保障分野ごとの政策評価の手法に関する研究(国際比較研究を含む。)
- (7) 医療に関する制度及び施策並びに経済的評価に関する研究(14010701)
- (ア) 医療行為及び医療機関の管理費用の評価に関する研究
(イ) その他医療に関する制度及び施策並びに経済的評価に関する研究(国際比較研究を含む。)
- (8) 介護及び社会福祉に関する制度及び施策並びに経済的評価に関する研究(14010801)
- (ア) 介護保険制度のマクロ経済への影響に関する研究
(イ) 介護予防対策の費用対効果に着目した経済的評価に関する研究
(ウ) 介護サービスの利用に伴う高齢者の経済的負担に関する研究
(エ) 地域福祉の在り方に関する研究
(オ) 福祉の人材の在り方に関する研究
(カ) その他介護及び社会福祉に関する制度及び施策並びに経済的評価に関する研究(国際比較研究を含む。)
- (9) 年金に関する政策科学研究(14010901)
- (ア) 共働き世帯の年金保障の在り方に関する研究
(イ) 年金制度における人口変動及び経済変動に対応した安定化方策の組込みに関する研究
(ウ) 短時間労働者の年金制度適用に伴う労働者行動及び企業行動の変化と年金財政上の効果に関する研究
(エ) その他年金に関する政策科学研究(国際比較研究を含む。)
イ.統計情報高度利用総合研究事業
- <事業概要>
- 少子・高齢化の進展や国民のニーズの多様化に伴い、厚生労働行政を推進するうえで、今後ますますきめ細かい、正確で使いやすい統計情報が必要とされる。
これに対応するため、本研究事業では保健、医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に係る統計調査の在り方に関する研究及びこれまでの厚生労働統計調査で得られた情報の高度利用に関する研究を実施し、厚生労働行政の推進に資することを目的とする。
- <新規課題採択方針>
- 患者調査における客体設定の在り方、医療施設動態調査・病院報告の在り方、医師・歯科医師・薬剤師調査の在り方、地域の健康状態に影響を与える因子の解明に向けた保健統計等の活用に関する研究。
| 研究費の規模: |
1課題当たり3,500千円程度(1年当たり) |
| 研究期間: |
1〜2年程度 |
| 新規採択予定課題数: |
4課題程度 |
- <公募研究課題>
- (1) 患者調査における客体設定の在り方に関する研究(14020101)
(2) 医療施設動態調査・病院報告の在り方に関する研究(14020201)
(3) 医師・歯科医師・薬剤師調査の在り方に関する研究(14020301)
(4) 地域の健康状態に影響を与える因子の解明に向けた保健統計等の活用に関する研究(14020401)
ウ.社会保障国際協力推進研究事業
- <事業概要>
- 感染症、栄養、災害等の従来の問題に加え、近年は人口の急速な高齢化、都市部への人口集中、疾病構造の変化などに伴い、医療保険・年金、公衆衛生等を含めた広義の社会保障分野全体を視野においた国際協力が重要性を増しており、同時に国際協力の効果的、戦略的実施の必要性も高まっている。
このため、本研究事業は、このような状況に対応した、社会保障に係る国際協力の効果的実施に資することを目的とする。
- <新規課題採択方針>
- 医療保険・年金、公衆衛生等を含めた広義の社会保障分野における国際協力の在り方、国際協力を推進するための方策及び効果的・効率的な国際協力を推進するための戦略的重点的方策に関する研究。
| 研究費の規模: |
1課題当たり2,000千円〜10,000千円程度(1年当たり) |
| 研究期間: |
1〜3年程度 |
| 新規採択予定課題数: |
6課題程度 |
- <公募研究課題>
- (1) 戦後の我が国における保健衛生指標の急速な改善の経験を途上国保健医療システム強化支援に活用するための方策に関する研究(14030101)
- (2) WHO保健システム評価手法の妥当性及びその活用に関する研究(14030201)
- (3) 途上国の保健システム評価手法を応用した途上国保健医療システム強化支援のあり方に関する研究(14030301)
- (4) マルチ・セクトラルアプローチを踏まえた国際協力を推進するための新たな人材確保や育成を含む国内体制強化の方策に関する研究(14030401)
- (5) 我が国の社会保障に係る国際協力のための資源の有限性を踏まえ、より効果的・効率的な国際協力を推進するために必要な支援分野の重点化・戦略化に関する研究(14030501)
- (6) 公的機関と民間の新しいパートナーシップによる財政支援体制の台頭を踏まえた、マルチ分野における事業評価のあり方に関する研究(14030601)
エ.がん克服戦略研究事業
- <事業概要>
- 平成6年度から平成15年度までを目標とする「がん克服新10か年戦略」を策定し、従来のがんの本態解明の研究の充実と併せて、本態解明の研究成果を生かした新しい予防法・診断法・治療法の開発に研究の重点を置いて研究事業を推進することを目的とする。
- <新規課題採択方針>
- 「がん克服新10か年戦略」に対応したがんの本態解明及びがんの発生予防、新しい診断法、新しい抗がん剤の開発等による効果的な治療法の開発、患者の生活の質(QOL)等に関する研究。
| 研究規模: |
1課題あたり10,000千円程度 |
| 研究期間: |
2年 |
| 新規採択予定課題数: |
20課題程度 |
- <公募研究課題>
- (1) 発がんの分子機構に関する研究(14040101)
(2) 転移・浸潤およびがん細胞の特性に関する研究(14040201)
(3) がん体質と免疫に関する研究(14040301)
(4) がん予防に関する研究(14040401)
(5) 新しい診断技術の開発に関する研究(14040501)
(6) 新しい治療法に関する研究(14040601)
(7) がん患者のQOLに関する研究(14040701)
オ.長寿科学総合研究事業
- <事業概要>
- 我が国は、国民の1/4が高齢者という超高齢化社会を世界に類を見ないスピードで迎えようとしており、今後も活力ある社会を保ち続けるためには高齢者が健康で生きがいをもって生活できるようにすることが大切である。
また、社会が「寝たきり」等で介護するようになった高齢者を無理なく受け入れ、国民が安心して生涯を過ごすことができる社会へと転換していくことが不可欠となっている。
このため、「ゴールドプラン21」に対応した長寿科学研究に積極的に取り組み、総合的に推進することを目的とする。
- <新規課題採択方針>
- 老化、老年病、リハビリテーション及び看護・介護に関する研究、支援機器及び居住環境、社会科学、漢方及び東洋医学に関する研究など加齢・高齢者に関する総合的研究。
特に、ゴールドプラン21等に基づく厚生労働行政への応用や、臨床等の実際のサービス提供への応用が可能な研究について積極的に評価。
| 研究費の規模: |
1課題当たり3,000〜50,000千円程度(1年当たり) |
| 研究期間: |
1〜3年(ただし、中間評価により継続を認めない場合がある。) |
| 新規採択予定課題数: |
20〜30課題程度 |
- <公募研究課題>
- (1) 老化分野(14050101)
- (ア) 老化の防御及び予防に関する研究のうち次に掲げるもの
- (a) 生体防御機能と老化との関係に関する研究
(b) 高齢者の口腔機能及び消化機能の維持(栄養の維持を含む。)に関する研究
- (イ) 個体機能保持に関する研究のうち次に掲げるもの
- (a) 高齢者の社会活動を支える身体的要因及び精神的要因に関する研究
(b) 体力の保持と運動及び生活習慣との関係に関する研究
(c) 老化に伴う精神機能、高次脳機能及び神経機能の保持に関する研究
- (ウ) 老化に関する長期縦断疫学研究のうち次に掲げるもの
- (a) 老化因子と加齢に伴う身体機能変化に関する研究
(b) 百寿者の長寿要因の解明に関する研究
(c) 地域特性から見た長寿及び高齢者の自立要因に関する研究
- (エ) 老化モデル実験動物に関する研究のうち次に掲げるもの
- (a) 加齢実験動物を使用した老化に関する研究
(b) 遺伝子改変動物の作成及びその研究応用に関する研究
- (オ) その他老化分野に関する研究
- (2) 老年病分野(14050201)
- (ア) 主要老年病に係る病態の解明、治療法の開発及び普及並びに予防法及び予防体制の確立に関する研究のうち次に掲げるもの
- (a) 高齢者の痴呆に関する研究
(b) 高齢者の骨疾患及び関節疾患に関する研究
(c) 高齢者の多臓器障害に関する研究
(d) 高齢者の免疫不全に関する研究
(e) 医科及び歯科の分野における高齢者の摂食及び排泄障害に関する研究
(f) 高齢者の生活習慣病に関する研究
(g) 高齢者の感染症に関する研究
- (イ) 高齢者手術の安全性の向上及び術後合併症の予防に関する研究
(ウ) 老年病に対するホルモン補充療法等の薬物療法の有効性に関する研究
(エ) 高齢者の再生医療及び再建医療の開発に関する研究
(オ) 高齢者の終末期医療に関する研究
- (3) リハビリテーション及び看護・介護分野(14050301)
- (ア) 機能障害のリハビリテーション及び看護・介護に関する研究のうち次に掲げるもの
- (a) 痴呆等精神機能に関する研究
(b) 咀嚼機能及び嚥下機能に関する研究
- (イ) 高齢者のターミナルケアに関する研究
(ウ) 要介護者等の評価及び介護サービスに関する研究のうち次に掲げるもの
- (a) 要介護状態の評価に関する研究
(b) 要介護状態に応じた介護サービスの提供に関する研究
(c) 介護に係る計画及び施設の評価に関する研究
(d) 訪問看護及び訪問介護に関する研究
(e) 介護保険施設における看護管理及び介護管理に関する研究
- (エ) 家族等の介護者の介護負担及びその軽減に関する研究
(オ) 身体拘束ゼロ作戦の推進に関する研究
(カ) 介護支援専門員の資質向上等に関する研究
- (4) 支援機器及び居住環境分野(14050401)
- (ア) 高齢者への支援機器に関する研究のうち次に掲げるもの
- (a) 屋外移動モニター及び緊急時通報システムに関する研究
(b) 移動支援機器及び移乗支援機器の開発に関する研究
(c) 介護予防・看護・介護機器等の開発、利用法及び評価に関する研究
(d) 高齢者のレジャー、スポーツ、レクリエーション等の社会参加のための支援機器の開発に関する研究
- (イ) 高齢者の居住環境に関する研究のうち次に掲げるもの
- (a) 高齢者の特性に応じた施設構造、建築等に関する研究
(b) 高齢者在宅生活支援システムの開発に関する研究
(c) 要介護状態に応じた住宅改修に関する研究
- (5) 社会科学分野(14050501)
- (ア) 高齢者の健全な社会生活を促進する研究のうち次に掲げるもの
- (a) 高齢者の生きがい及び生活の質(Quality of Life)の評価法に関する研究
(b) 高齢者の心理及び満足感に関する研究
(c) 高齢者の家庭及び家族関係に関する研究
(d) 高齢者の社会参加及び社会貢献に関する研究
- (イ) 高齢者の終末期状態に関する研究
- (6) 漢方及び東洋医学分野(14050601)
- (ア) あんま、マッサージ、指圧、はり及び灸の除痛効果、鎮痛効果等に関する研究
(イ) 高齢者の虚弱予防のための漢方及び東洋医学に関する研究
カ.障害保健福祉総合研究事業
- <事業概要>
- 「障害者プラン」が平成7年12月に策定され、障害者が住み慣れた地域社会の中で、社会の構成員として地域の中で共に生活を送るべきであるというノーマライゼーションの理念に基づいて、各種施策を推進することが重要な課題となっている。
そのため、身体及び精神の障害に関する予防、治療及び訓練並びにもっと身近な市町村においての住宅・施設サービスをきめ細かく提供できる体制づくり等、障害者の総合的な保健福祉施策に関する研究を推進することを目的とする。
なお、平成14年度においては、精神障害者の医療と保健に関する研究の一部について、最先端バイオ・メディカル技術を活用するべく、「こころの健康科学研究事業(仮称)」に組替を行った。
- <新規課題採択方針>
- 「障害者プラン」に対応した、障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくり(ノーマライゼーション)及びリハビリテーションの理念に基づいた障害保健福祉施策の推進のための基盤的施策や、身体障害・知的障害・精神障害等に関する研究。
障害者の就労支援や社会参加、資格取得等に向けた支援機器の開発に関する研究。
| 研究費の規模: |
1課題当たり5,000〜20,000千円程度(1年当たり) |
| 研究期間: |
1〜3年 |
| 新規採択予定課題数: |
12課題程度 |
- <公募研究課題>
- (1) 障害者プラン(障害者基本法第7条の2に規定される障害者基本計画を具体化するための重点施策実施計画)、それに基づく行政サービス等の評価指標に関する研究(14060101)
- (2) 障害者の心身機能、社会参加、活動及び生活環境についての評価に関する研究(14060201)
- (3) 障害者ケアマネジメントの効果的な実施及び評価に関する研究(14060301)
- (4) 障害者に係る支援機器に関する研究のうち次に掲げるもの(14060401)
- (ア) 障害者の就労や資格取得、社会参加の促進などに向けた支援機器の開発及び利用に関する研究
(イ) 重度または重複障害者を対象とした、生活の質(Quality of Life)の向上のための支援機器利用に関する研究
(ウ) 高位頚髄損傷者や重症心身障害児・者の自立支援機器の開発に関する研究
- (5) 障害者に係る情報バリアフリーの促進(IT技術の導入)に関する研究(14060501)
- (6) WHO国際障害分類改訂版(ICF)の活用のあり方に関する研究(14060601)
- (7) 重度あるいは処遇が難しい障害者に対する適正な医療、リハビリテーション等の提供に関する研究(14060701)
- (8) 障害者の授産施設などにおける訓練から職業復帰に向けたサービスの充実に関する研究(14060801)
- (9) 障害者の社会的理解の促進及び自己決定の支援、自己選択の支援等の権利擁護に関する研究(14060901)
- (10) 障害者に対する保健福祉サービスの従事者の資質向上の在り方に関する研究(14061001)
- (11) 施設内での処遇から地域生活への移行に向けた、障害者に係る地域生活の支援及び家族の支援に関する研究(14061101)
キ.子ども家庭総合研究事業
- <事業概要>
- 乳幼児の障害の予防、乳幼児及び生涯を通じた女性の健康の保持増進等について効果的・効率的な研究の推進を図るとともに、少子化等最近の社会状況を見据えて、児童を取り巻く環境やこれらが児童に及ぼす影響等についての総合的・実証的な研究に取り組むことにより、母子保健の推進及び子育て支援を総合的・計画的に推進するための児童家庭福祉の向上に資することを目的とする。
なお、本研究事業は、総合的かつ効果的な推進を図るため研究課題によっては文部科学省との共同・連携を図っていくこととしている。
- <新規課題採択方針>
- 「健やか親子21」及び「新エンゼルプラン」に対応した、母子保健及び子育て支援を総合的・計画的に推進するための児童家庭福祉、乳幼児の障害の予防、母性・乳幼児の健康及び生涯を通じた女性の健康の保持増進に関する研究。
| 研究費の規模: |
1課題当たり2,000〜20,000千円程度(1年当たり) |
| 研究期間: |
1〜3年 |
| 新規採択予定課題数: |
20課題程度 |
- <公募研究課題>
- (1) 母子保健施策の推進に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 遺伝子医療の基盤整備に関する研究(14070101)
(イ) 乳幼児突然死症候群のガイドライン作成に関する研究(14070201)
(ウ) 母子健康手帳の学校保健等における活用に関する研究(14070301)
- (2) 思春期の保健対策の強化及び健康教育の推進に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) ピアカウンセリング・ピアエデュケーションのマニュアル作成及び効果的普及に関する研究(14070401)
- (3) 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 生殖補助医療の実態及びそのあり方に関する研究(14070501)
(イ) 快適な妊娠・出産を支援する基盤整備に関する研究(14070601)
- (4) 小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 小児慢性疾患の診断精度及び治療成績の向上のための方策に関する研究(14070701)
- (5) 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 保健医療福祉スタッフのためのメンタルケアマニュアル開発に関する研究(14070801)
- (6) 小児科・産婦人科若手医師育成に関する研究(14070901)
- (7) 生涯を通じた女性の健康支援に関する調査研究に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 生涯を通じた健康の管理・保持増進のための健康教育・相談支援等の充実に関する研究(14071001)
(イ) 望まない妊娠、人工妊娠中絶を防止するための効果的な避妊教育プログラムの開発に関する研究(14071101)
- (8) 児童虐待防止対策の推進に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 児童虐待予防のための地域における家族支援システムのあり方に関する研究(14071201)
(イ) 児童相談所における介入方法と予後に関する研究(14071301)
(ウ) 児童福祉施設における被虐待児童の実態及び家族再統合に向けた支援のあり方に関する研究(14071401)
- (9) 女性の保護に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 児童問題と家庭内暴力との関係等に関する研究(14071501)
- (10) ひとり親家庭等の自立支援に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) ひとり親家庭や再婚家庭の実態及び支援のあり方に関する研究(14071601)
- (11) 児童の健全育成に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 非行・ひきこもり等の児童問題対策に関する研究(14071701)
(イ) 児童福祉施設等における地域支援のあり方に関する研究(14071801)
- (12) 保育需要の把握及び将来推計に関する研究(14071901)
- (13) 保育が乳幼児の心身の発達に及ぼす影響に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 保育所給食のあり方に関する研究(14072001)
(イ) 保育の国際比較に関する研究(14072101)
(ウ) 望ましい保育環境のあり方に関する研究(14072201)
- (14)子どもの発達と家庭への支援方策の推進に関する研究(14072301)
ク.ヒトゲノム・再生医療等研究事業
- <事業概要>
- 新しい千年紀のプロジェクト、すなわち「ミレニアム・プロジェクト」のうち、高齢化分野のプロジェクトを構成する事業の一つとして、高齢者等の主要な疾患の遺伝子の解明に基づく個人の特徴に応じた革新的な医療の実現、自己修復能力を利用した骨、血管等の再生医療の実現、生命工学を利用した疾患予防・健康維持のための高機能食品の開発などを目指す。また、これらに関わる安全性の確保のための研究を進める。
なお、本研究事業は、総合的かつ効果的な推進のために、文部科学省、農林水産省、経済産業省との共同・連携を図っていくこととしている。
- <新規課題採択方針>
- (ヒトゲノム分野)
高齢者等に主要な疾患(痴呆、がん、糖尿病、循環器疾患及び喘息を除く。)に関連する遺伝子の解析等に関する研究、遺伝子治療の基盤となる研究。
| 研究費の規模: |
1課題当たり30,000〜50,000 千円程度(1年当たり) |
| 研究期間: |
1〜3年(中間評価により中途で終了することがある。) |
| 新規採択予定課題数: |
9課題 |
- (生命倫理分野)
ヒトゲノム分野、遺伝子治療分野及び再生医療分野研究に関連する倫理に関する研究。
| 研究費の規模: |
1課題当たり5,000〜7,000千円程度(1年当たり) |
| 研究期間: |
1〜3年(中間評価により中途で終了することがある。) |
| 新規採択予定課題数: |
2件程度 |
- <公募研究課題>
- (1) ヒトゲノム分野
- (ア) 高齢者等の主要な疾患(痴呆、がん、糖尿病、循環器病及び喘息を除く。以下同じ。)に関連する遺伝子の同定等に関する研究(14080101)
- (イ) 高齢者等の主要な疾患に関連する遺伝子、たんぱく質等の機能の解明に関する研究(14080201)
- (ウ) 高齢者等の主要な疾患に用いる薬剤の反応性に関連する遺伝子の同定等に関する研究(14080301)
- (エ) 高齢者等の主要な疾患に用いる薬剤の反応性に関連する遺伝子、たんぱく質等の機能の解明に関する研究(14080401)
- (オ) 遺伝子治療に用いるベクターの開発研究(14080501)
- (カ) 遺伝子治療に用いるベクターの安全性及び有効性評価方法に関する研究(14080601)
- (2) 生命倫理研究分野
遺伝子解析研究、再生医療等の先端医療分野における生命倫理に関する研究(14080701)
ケ.新興・再興感染症研究事業
- <事業概要>
- 近年、新たにその存在が発見された感染症や既に制圧したかにみえながら再び猛威をふるいつつある感染症が世界的に注目されている。これらの感染症は、その病原体感染源、感染経路、感染力、発症機序、診断、治療法等について解明すべき点が多い。
また、日米包括経済協議の一環として、地球的展望に立った協力のための共通課題 (コモン・アジェンダ)において、1996年4月に新たに追加された協力分野として「新興・再興感染症」についての研究協力が求められている。
このため、本事業は、国内外の新興・再興感染症研究を推進し、研究の向上に資するとともに、新興・再興感染症から国民の健康を守るために必要な施策を行うための研究成果を得ることを目的とする。
なお、本研究事業は、総合的かつ効果的な推進のために農林水産省との共同・連携を図っていくこととしている。
- <新規課題採択方針>
- ウイルス、細菌、寄生虫・原虫による感染症等に関する研究で、それらの解明、予防法、診断法、治療法、情報の収集と分析、行政対応等に関する研究を行う。
| 研究費の規模: |
1課題当たり10,000〜50,000千円程度(1年当たり) |
| 研究期間: |
1〜3年 |
| 新規採択予定課題数: |
10課題程度 |
- <公募研究課題>
- (1) 結核菌症の病態解明に基づく新たな治療法等の開発に関する研究(14090101)
- (2) 赤痢アメーバ症等寄生虫症ハイリスク群に対する予防法等の開発に関する研究(14090201)
- (3) ビブリオ・バルニフィカス等による重篤な経口感染症に関する研究(14090301)
- (4) 生物テロに使用される可能性の高い病原体による感染症のまん延防止、予防、診 断、治療に関する研究(14090401)
- (5) 国内での発生が稀少のため知見が乏しい感染症対応のための技術的基盤整備に関する研究(14090501)
- (6) 大規模感染症発生時における行政機関、医療機関等の間の広域連携に関する研究(14090601)
- (7) 都市部における一般対策の及びにくい特定集団に対する効果的な感染症対策に関する研究(14090701)
- (8) 経口細菌感染症の広域的・散発的発生時の実地疫学的・細菌学的調査手法等の開発に関する研究(14090801)
- (9) インフルエンザ予防接種のEBMに基づく政策評価に関する研究(14090901)
- (10) その他新興感染症及び再興感染症に係る疫学的研究並びに予防、診断及び治療に関する研究であって、重要性及び緊急性が特に高いもの(14091001)
コ.エイズ対策研究事業
- <事業概要>
- 我が国のエイズをめぐる状況は、患者・感染者とも年々増加している。特に国内における日本人男性の同性間性的接触による感染者数と、異性間性的接触による患者数の増加が見られ、我が国におけるエイズのまん延が懸念されている。
また、世界においてもUNAIDSは2001年末において約4,000万人がHIVに感染していると推計しており、エイズ研究のより一層の推進が求められている。
さらに、HIV訴訟の和解を踏まえ、恒久対策の一環として、エイズ治療・研究をより一層推進させることが求められており、モデル的、先駆的な治療のための臨床研究の拡充、エイズ拠点病院を中心とした診療体制のあり方に関する研究等、我が国独自の研究を今後とも重点的に推進していく必要がある。
このため、本事業は、エイズに関する基礎、臨床、社会医学、疫学等の研究を推進するとともに、エイズ対策に必要な施策を行うための研究成果を得ることを目的とする。
なお、本研究事業は、総合的かつ効果的な推進のために文部科学省との共同・連携を図っていくこととしている。
- <新規課題採択方針>
- HIV/AIDSに関する臨床医学、社会医学研究。
| 研究費の規模: |
1課題当たり10,000千円程度(1年当たり) |
| 研究期間: |
1〜3年 |
| 新規採択予定課題数: |
1〜3課題 |
- <公募研究課題>
- (1) 臨床医学研究のうち次に掲げるもの
HIV診療支援ネットワークを活用した診療連携に関する研究(14100101)
- (2) 社会医学研究のうち次に掲げるもの
個別施策層(青少年、外国人、同性愛者、性風俗産業の従事者及び利用者)に対する固有の対策に関する研究(14100201)
サ.感覚器障害研究事業(仮称)
旧「感覚器障害及び免疫アレルギー等研究事業」については、平成14年度政府予算成立後速やかに事業名の変更を行います。
- <事業概要>
- 我が国においては、約66万人が視覚または聴覚の障害を有している。感覚器の障害は日常生活の質を損なう。また、障害の種類によっては疾病の進行等により障害も重症化する。
そのため、感覚器の障害について、その原因疾患の病態・発症のメカニズムの解明、発症予防、診断・重症化防止方法等の研究を行うとともに、視覚・聴覚等の障害を補う福祉機器等の開発やリハビリテーション手法等に関する研究を推進し、もって感覚器障害の予防、診断、治療の向上その他感覚器障害対策の推進に資することとしている。
- <新規課題採択方針>
- 視覚・聴覚・平衡覚領域における障害及び重複障害又は日常生活上支障となる症状について、原因疾患発症機序の解明とその予防・治療方法、支援機器の開発・改良に関する研究及び視覚・聴覚・平衡覚障害者及び重複障害者の社会参加に関する研究。
| 研究費の規模: |
1課題当たり10,000〜20,000千円程度(1年当たり) |
| 研究期間: |
3年 |
| 新規採択予定課題数: |
9課題程度 |
- <公募研究課題>
- (1) 視覚、聴覚及び平衡覚の障害並びにそれらの重複障害に係る疫学的研究及びそれら障害に関する予防、医療、リハビリテーションに関する研究(ドライアイを除く)(14110101)
- (2) 視覚、聴覚及び平衡覚の障害並びにそれらの重複障害により廃した機能を代償する機器の開発及び改良に関する研究(人工網膜を除く)(14110201)
- (3) 視覚、聴覚及び平衡覚の障害並びにそれらの重複障害の程度及び社会生活における障害の影響を評価する手法の開発(14110301)
- (4) 視覚、聴覚及び平衡覚の障害に関連する感覚器官の疾病に関する研究(14110401)
シ.食品・化学物質安全総合研究事業(仮称)
旧「生活安全総合研究事業」については、平成14年度政府予算成立後速やかに事業名の変更を行います。また、平成13年度まで、生活安全総合研究事業で行われていた生活環境総合研究分野、化学物質総合対策研究分野(シックハウス対策研究分)及び飲料水関連分野については、平成14年度より、生活衛生総合研究分野(シックハウス対策研究を含む)及び健全な水循環の形成に関する研究分野として健康科学総合研究事業で行います。
- <事業概要>
- 食品については、近年、国民の嗜好の多様化、科学技術の進歩による応用食品等の登場などに伴い、非常に多様なものが存在するようになった。食品はすべての国民が生涯を通じて摂取するものであり、既存添加物も含め、その安全性に関する研究は、長期的視野に立って適切に進めることが国民の健康確保にとって必要不可欠である。
ダイオキシン類は、廃棄物の処理過程等で発生する毒性の強い化学物質であり、ダイオキシン類による人体汚染や健康影響等に対する不安が国民の間で高まっており、その実態把握や健康影響に関する研究の推進は緊急の課題となっている。
また、人の内分泌系をかく乱する恐れのある内分泌かく乱化学物質が社会的に大きな問題となっており、その毒性発現のメカニズムや次世代の健康影響に至る一貫した研究をダイオキシン関係の研究と調整を図りつつ、推進していく必要がある。
食品や化学物質に関する研究は相互に密接に関連しており、化学物質を中心として、生活環境における種々の汚染源と汚染状況を把握し、生活環境の安全と健康の確保にかかる研究を総合的かつ効率的に推進する必要がある。
このため、本事業においては、ダイオキシン類を始めとする微量化学物質や微生物の安全性や健康影響等に対して、食品、化学物質等の分野の研究者が相互に連携を保つとともに、化学物質対策等の生活の安全に係る研究を実施する関係各省庁と密接に連携を図りつつ、様々な研究を総合的に実施し、的確な対策を打ち出すことにより、国民の不安を解消し、安全な生活の確保を図ることを目的とする。
なお、本研究事業は、総合的かつ効果的な推進のために経済産業省、農林水産省、環境省等関係各省庁との共同・連携を図っていくこととしている事業である。
- <新規課題採択方針>
- 食品の安全性や、内分泌かく乱化学物質、ダイオキシン類、微量化学物質並びに家庭用品に含まれる有害物質の健康影響に関する研究。
| 研究費の規模: |
1課題当たり30,000千円以上(1年当たり) |
| 研究期間: |
1〜3年 |
| 新規採択予定課題数: |
35課題程度 |
- <公募研究課題>
- (1) 食品安全推進総合研究分野
- (ア) 食品衛生法で規定されている既存添加物の安全性に関する研究のうち次に掲げるもの
- (a) 反復投与毒性試験や発がん性試験等の実施による既存添加物の安全性評価に関する研究(14120101)
- (b) 既存添加物の安全性確保上必要な品質問題に関する研究(14120201)
- (イ) 食品産業における健康危機管理に関する研究(14120301)
- (2) 化学物質総合対策研究分野
- 1) 内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 内分泌かく乱性の順位付けに関する研究(14120401)
(イ) 試料分析の信頼性確保と生体暴露量のモニタリングに関する研究(14120501)
(ウ) 低用量域の作用の再現性を確立するための研究(14120601)
(エ) 疫学の方法論に基づく次の研究
- (a) 各種の生体試料の保存を含む疾病発生状況コホート研究(既存のコホートの利用を含む)(14120701)
(b)妊婦や乳幼児を対象としたコホート研究(14120801)
(c)男性生殖機能への影響に関する疫学研究(14120901)
(d)職域集団を対象とした疫学研究(14121001)
- (オ) リスクについての情報伝達の実践に関する研究(14121101)
(参考)課題採択にあたっては、「内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会中間報告書追補(平成13年12月)」(http://www.nihs.go.jp/mhlw/ocs/index.htmlにて閲覧可能)を踏まえた調査研究を優先する。
- 2) ダイオキシン類(臭素化ダイオキシンを含む。)の健康影響に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 測定分析の信頼性確保と生体暴露量のモニタリングに関する研究(14121201)
(イ) 高暴露コホートの男性生殖機能への影響に関する疫学研究(14121301)
(ウ) リスク評価と耐容摂取量の設定の在り方に関する研究(14121401)
- 3) 生活環境中の微量化学物質等の健康影響に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 種差及び個体差、特に胎児や高感受性弱者への長期的な影響に関する研究(14121501)
(イ) 微量金属等の中枢神経系への影響や発がん性等に関する研究(14121601)
- 4) 家庭用品に含有される有害化学物質の安全性に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 衣料品、家具、家電製品などの家庭用品から溶出又は揮散する可能性のある有害物質の相互作用と生涯にわたる生体暴露評価に関する研究(14121701)
(イ) 製品表示と理解度との関連及び誤使用・被害事故との関連の検証に関する研究(14121801)
ス.医薬安全総合研究事業
- <事業概要>
- 医薬品、医療機器は現代医療において診断・治療等の分野において不可欠の存在であり、国民が安心して医療を受けられるためには、これらの安全性の確保は極めて重要である。
近年のバイオテクノロジーや電子・通信技術等の科学技術の急速な進歩により、新規に開発される医薬品、医療機器には、いわゆる切れ味の鋭いものや複雑な構造の電子機器等が増加しており、未知の有害作用等が潜む可能性も考えられるなどの状況から、安全性確保のためには従来にも増して、より高度な技術を駆使する必要が生じてきている。
また、我が国の薬物乱用状況は乱用者の低年齢化等憂慮すべき事態にあり、不正薬物の供給の阻止と需要の削減の両面からの対策の充実強化が求められており、総理大臣を本部長とする薬物乱用対策推進本部が平成9年にまとめた薬物対策推進要綱において薬物対策の1つの柱として研究の推進を謳っているところである。
このため、本事業においては、(1)医薬品・医療用具等の品質等の評価、(2)医薬品・医療用具等の安全性向上、(3)医療機関における安全確保対策、(4)乱用薬物(不適正使用薬物)等に関する調査研究の実施といった4つの観点から、薬事関連及び医事関連規制による安全性確保の社会的要請等に応えるため、国際的な動きも視野に入れた総合的かつ計画的な研究を推進することを目的とする。
なお、本研究事業は、総合的かつ効果的な推進のために文部科学省、経済産業省、農林水産省及び警察庁との共同・連携を図っていくこととしている事業である。
- <新規課題採択方針>
- 医薬品・医療用具等の評価に関する研究、医薬品・医療用具等の安全性向上に関する研究、医療機関における安全対策に関する研究、乱用薬物対策等に関する研究。
| 研究費の規模: |
1課題当たり7,000千円以上(1年当たり) |
| 研究期間: |
1〜3年 |
| 新規採択予定課題数: |
16課題程度 |
- <公募研究課題>
- (1) 医薬品、医療用具等の評価に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 医薬品および医療用具製造における最新の品質管理システムのあり方・手法に関する研究(14130101)
- (イ) 日本薬局方改正に向けた医薬品の最新の品質管理技術の開発等に関する研究(14130201)
- (ウ) 遺伝子多型に関する基本情報を利用した薬物代謝に関連する民族間比較に関する研究(14130301)
- (エ) 医療機器の耐用期間設定評価手法に関する研究(14130401)
- (2) 医薬品、医療用具等の安全性の向上に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 市販直後調査時の病院内における副作用情報等の組織的な収集・管理・提供の在り方に関する研究(14130501)
- (イ) 致命的な循環器系副作用の症例情報の収集及び併用薬剤等のリスク要因の解明に関する研究(14130601)
- (ウ) 医薬品の分類に応じた医薬品情報の国民的視点に立った提供方法等に関する研究(14130701)
- (エ) 血液製剤の安全性向上に係る各種方策の評価に関する研究(14130801)
- (オ) 適用する医薬品の脂溶性等とプラスチック製医療用具に使用される可塑剤の溶出度の相関性に関する研究(14130901)
- (カ) 医療用具の適正使用に係る添付文書情報の提供システムの開発に関する研究(14131001)
- (キ) 薬事関連法規の遵守の徹底化等を図るための企業体制の整備に関する研究(14131101)
- (3) 医療機関における安全対策に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 病院等における薬剤師業務の質の向上に関する研究(14131201)
(イ) 医療機器のヒューマンファクターエンジニアリングに関する研究(14131301)
(ウ) 医療行為に伴い排出される放射性廃棄物の適正管理に関する研究(14131401)
(エ) 医療被ばく測定手法の開発と個人の医療被ばくの管理方策に関する研究(14131501)
- (4) 乱用薬物及び麻薬原料植物等の分析及び鑑定法の開発並びに不正栽培の防止に関する研究(14131601)
セ.健康科学総合研究事業
平成13年度まで、生活安全総合研究事業で行われていた生活環境総合研究分野、化学物質総合対策研究分野(シックハウス対策研究分)及び飲料水関連分野については、平成14年度より、生活衛生総合研究分野(シックハウス対策研究を含む)及び健全な水循環の形成に関する研究分野として健康科学総合研究事業で行います。
- <事業概要>
- 健康の増進、生活習慣に着目した疾病の予防、総合的な保健サービスの提供等、予防医学の基礎及び応用研究から、地域住民に保健サービスとして提供する体制及び評価や水道及び生活環境の向上に関する研究に至るまでの総合的な健康科学に関する研究を推進する。
このため、栄養・食生活、運動、睡眠、喫煙、飲酒等の生活習慣と疾病予防・健康増進に関する研究、保健医療福祉に係る効果的・効率的な地域保健サービス等に関する研究、飲料水、建築物など生活環境の衛生及び安全性に関する研究を実施し、その成果が健やかでゆとりある長寿社会の基盤となる環境の整備に資するとともに、国民の健康に関するQOLの向上に資することを目的とする。
なお、本研究事業は、総合的かつ効果的な推進のために文部科学省、農林水産省、環境省等の関係省庁との共同・連携を図っていくこととしている事業である。
- <新規課題採択方針>
- 栄養・食生活・運動・睡眠・喫煙・飲酒等の生活習慣と疾病予防・健康増進に関する研究、保健医療福祉に係る効果的・効率的な地域保健サービスの提供・評価に関する研究、生活習慣病の病態・診断・治療、患者の生活の質(Quality of Life,QOL)の向上等に関する研究、建築物等に関連する生活衛生に関する研究。
| 研究費の規模: |
1課題あたり5,000千円以上(1年当たり) |
| 研究期間: |
1〜3年 |
| 新規採択予定課題数: |
10課題程度 |
- <公募研究課題>
- (1) 地域保健サービスに関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 生涯を通じた保健サービスに関する費用対効果の分析等の経済的研究(14140101)
- (イ) 地域における健康危機発生時の対応に関する実証的研究(14140201)
- (ウ) 青壮年者の健康づくり対策及び疾病予防対策に関する研究(14140201)
- (エ) 地域、職域、学校の連携による生涯を通じた健康づくりのための保健サービスの提供に関する研究(14140301)
- (オ) 地域保健関係職種の資質の向上に関する研究(14140401)
- (2) 健康づくりに関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 行動科学的手法等を用いた食生活改善に関する研究(14140501)
(イ) 運動の健康増進効果及び運動習慣獲得・継続に関する研究(14140601)
(ウ) 健康増進と睡眠、温泉利用等の関係に関する研究(14140701)
(エ) 成年の喫煙、飲酒習慣改善、または未成年の喫煙、飲酒防止の手法開発のための研究(14140801)
(オ) 日常生活における腰痛・膝痛・肩こり等の予防に関する研究(14140901)
(カ) 日常生活における事故の防止に関する研究(14141001)
- (3) 生活環境に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 建築物の生活環境の衛生に関する研究(14141101)
(イ) その他生活環境の安全性に関する研究(14141201)
ソ.医療技術評価総合研究事業
- <事業概要>
- 労働集約型サービスである医療サービス分野は、人口の少子・高齢化において、医療ニーズの多様化・高度化に適切に対応するため、より一層の省力化と効率化した医療提供体制の構築と良質な医療サービスの提供、また、医学・医療技術や情報通信技術の進歩等を活用して、時代の要請に応じた効率的な医療システムを構築し、豊かで安心できる国民生活の実現が求められている。
このため、良質な医療を合理的・効率的に提供する観点から、医療技術や医療システムを評価し、医療資源の適切な配分を行うなど、時代の要請に速やかに対応できるよう、既存医療システム等の評価研究を実施するとともに、医療の質と患者サービスの向上のために必要不可欠な医療安全体制確保に関する研究、根拠に基づく医療(Evidence-based Medicine:EBM)に関する研究を実施するものである。
なお、本研究事業は、総合的かつ効果的な推進のために経済産業省及び郵政事業庁との共同・連携を図っていくこととしている事業である。
- <新規課題採択方針>
- 良質な医療を合理的・効率的に提供するための診療技術・医療情報技術の評価、医療提供体制基盤整備等に関する研究、医療の質と医療安全体制確保に関する研究、根拠に基づく医療(Evidence-based Medicine:EBM)に関する研究。
| 研究費の規模: |
1課題当たりEBMは10,000千円〜50,000千円程度、その他は3,000千円〜20,000千円程度(1年当たり) |
| 研究期間: |
1〜3年 |
| 新規採択予定課題数: |
EBM7課題程度、その他40課題程度 |
- <公募研究課題>
- (1) 診療技術の評価(特に客観的評価法又は技術の経済的分析)に関する研究(14150101)
- (2) 診療機能の評価(特にアウトカム評価)に関する研究(14150201)
- (3) 医療情報技術の開発、評価及び普及に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 電子診療録の普及促進に関する研究(14150301)
(イ) 情報技術の導入及び推進による医療サービスの向上に関する研究(14150401)
(ウ) 医療情報の標準化の開発及び評価に関する研究(14150501)
- (4) 医療提供体制基盤整備に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 医療提供体制(特に小児医療)の充実に資する研究(14150601)
(イ) 医療機関の機能分化(役割分担)と連携を推進する方策に関する研究(14150701)
(ウ) 救急、災害(テロを含む)又はへき地医療の提供及び評価に関する研究(14150801)
(エ) 医療関係職種の資質の向上(特に医師・歯科医師の卒後臨床研修及び国家試験の質の向上)に関する研究(14150901)
(オ) 医療における情報提供の推進に資する研究(14151001)
- (5) 看護技術の開発、評価及び看護提供体制に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 看護技術の開発及び評価に関する研究(14151101)
(イ) 看護制度の改革に資する研究(14151201)
(ウ) 看護サービスの質の向上に関する研究(14151301)
- (6) 医療の質及び医療安全体制の確保に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 医療事故を防止する方策を立案するための要因分析手法の開発に関する研究(14151401)
(イ) 医療事故を防止するための対策の効果的な実施及び評価に関する研究(14151501)
(ウ) 医療事故を防止するための建築及び構造設備に関する研究(14151601)
(エ) 認知心理学、人間工学等を学際的に用いた人的要因(Human Factor)に起因する医療事故の予防に関する研究(14151701)
(オ) 医療の質の向上に資する管理手法(クリティカルパスを含む)の開発に関する研究(14151801)
(カ) 他領域や諸外国における安全対策の応用に関する研究(14151901)
(キ) 医療安全推進に関する法的問題に関する研究(14152001)
- (7) 根拠に基づく医療(Evidence-based Medicine:EBM)の手法を用いた医療技術の体系化に関する研究のうち次に掲げるもの
- (ア) 診療ガイドラインの活用、評価及びその手法に関する研究(14152101)
(イ) EBMの普及・推進に関する研究(14152201)
(ウ) 日本人の特性に配慮した診療ガイドラインの作成に関する研究(14152301)
(2)公募研究事業計画表
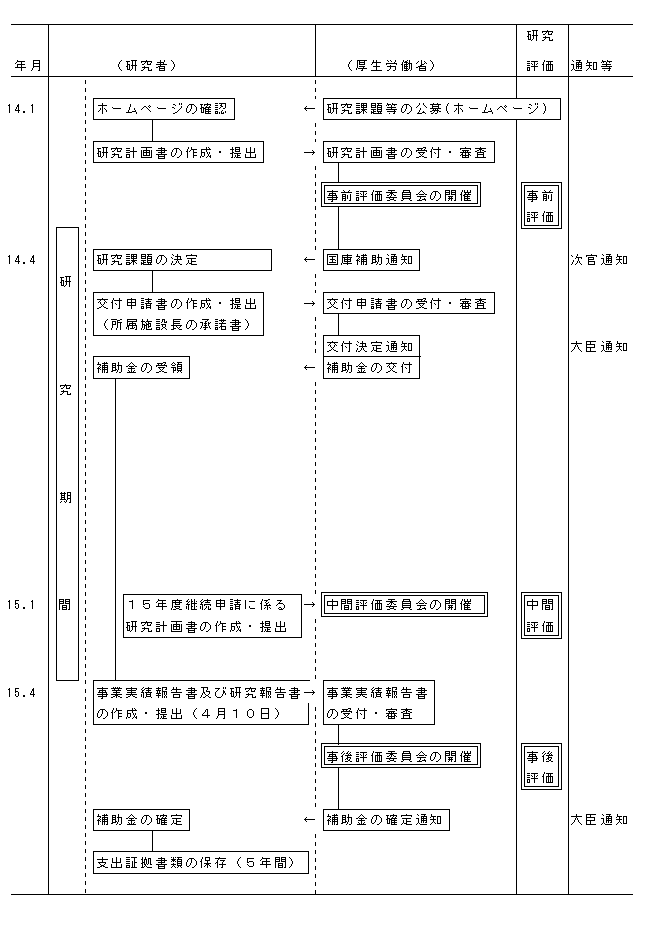
トップへ
公募要項目次
前ページ
次ページ