1 はじめに
我が国では、平均寿命の大幅な伸びと出生率の低下により、世界に類をみない速度で急速に高齢化が進展している。2005年(平成17年)時点で我が国の国民の約5人に1人が65歳以上の高齢者(2,567万人)であるが、10年後の2015年(平成27年)には国民の約4人に1人(3,378万人)が65歳以上となる見込みである。
それに伴い、就労意欲があり働くことができる人口を示す労働力人口(就業者数+完全失業者数)の高齢化も見込まれており、2005年(平成17年)の推計によれば、2015年(平成27年)には、労働力人口の約6人に1人が60歳以上の高齢者になることが見込まれている。また、労働力人口の総数も2004年(平成16年)から2015年(平成27年)にかけ約110万人の減少が見込まれている。
そのような状況下で、我が国の経済活力を維持していくために、国際的にみても高い就労意欲を有する我が国の高齢者が長年培った知識と経験を活かし、社会の支え手として活躍していく社会が求められている。
このため、我が国では、高年齢者雇用安定法が改正され、高年齢者が少なくとも年金支給開始年齢(男性の年金支給開始年齢にあわせた男女同一の年齢)までは働き続けていくことができるよう、2006年(平成18年)4月から事業主の方々に「高年齢者雇用確保措置」の実施を義務づけたところである。
一方、欧米主要国でも人口の高齢化は着実に進行している。高齢化のスピードは我が国ほど速くはないが、日本より就労意欲が低い(といわれる)高齢者を抱えるこれらの国々が、高齢化に対しどのようなアプローチで対策を講じているかは我が国においても参考となる部分は少なくないと考える。
そこで、特集部分では、EU、アメリカ、イギリス、ドイツ及びフランスを対象とし、各国における高齢者の就労に関連する施策を広義の「高齢者雇用対策」と捉え、調査することとした。調査事項は、大きく5つに分け、(1)高齢者の雇用失業情勢、(2)(年金、失業保険などの)社会保障制度、(3)年齢に関する法規則、(4)段階的な引退の支援制度、(5)積極的な就業促進政策(狭義の高齢者雇用対策)とした。また、参考のため、統計値についても極力日本の数値を入れているが、以下、「各国」又は「いずれの国」と言及した際は調査対象国を指し日本は含まない点にご留意いただきたい。
2 諸外国における高齢者の雇用失業情勢
まず、各国の総人口、65歳以上の高齢者人口及び生産年齢人口の推移を確認し各国の高齢化の見込みを把握するとともに高齢化の一因となっている少子化の現状を確認する。
(1)人口の動向
a 将来の人口に係る推計
各国とも高齢者(65歳以上)人口の増加が見込まれている。一方、働き盛りの人口である生産年齢(15〜64歳)人口は、アメリカは増加し続けるが、イギリスはほぼ横ばい、フランスは微減、ドイツは減少が見込まれている(表1−1)。
また、高齢化率(総人口に対する65歳以上人口の割合)についても今後、いずれの国も上昇が見込まれている。高齢化率の2005年時点の水準はドイツ(18.8%)、フランス(16.6%)、イギリス(16.0%)、アメリカ(12.3%)の順となっており、ドイツ及びフランスがアメリカ及びイギリスより高齢化が進んでいることがわかる(図1−1)。
逆に、総人口に対する生産年齢人口の割合は、今後いずれの国も下降する見込みである(図1−2)。
〈表1−1〉各国の総人口、生産年齢(15〜64歳)人口及び高齢者(65歳以上)人口の推移
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
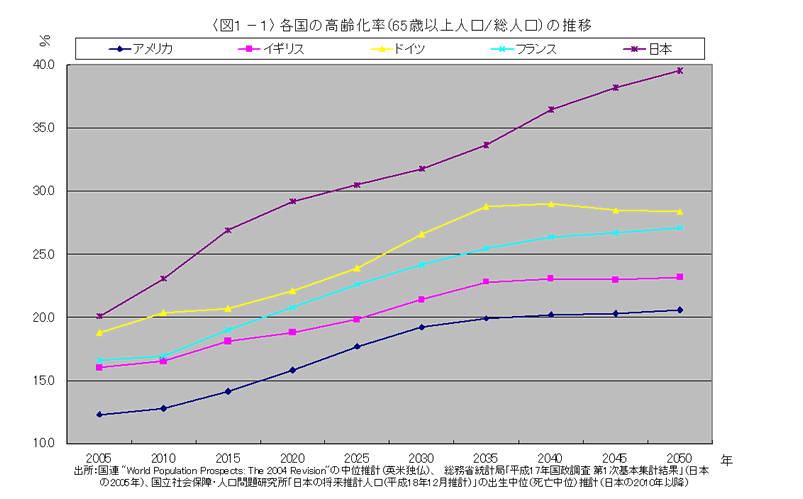
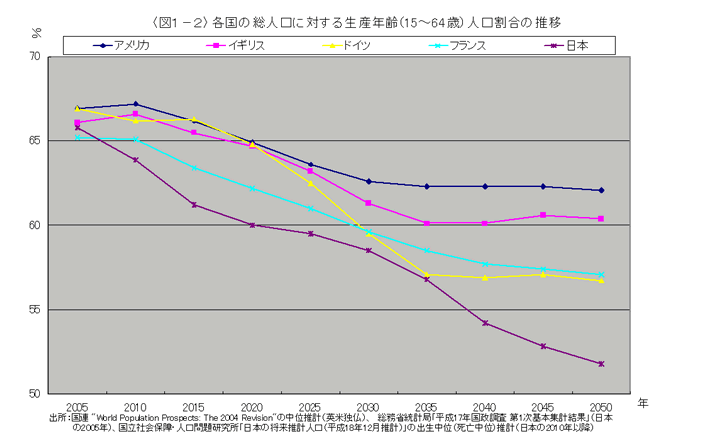
b 合計特殊出生率の推移
このような高齢化率の上昇の一因には出産数の低下、つまり少子化があげられる。合計特殊出生率(女性が一生の間に出産する子供の数に相当)は、1960年代後半以降、各国とも下降傾向にあったが、アメリカは1980年代半ば、フランス及びドイツは1990年代半ば、イギリスは2000年代初頭より上昇に転じている。なお、2004年の合計特殊出生率は、アメリカ(2.05)、フランス(1.92)、イギリス(1.77)、ドイツ(1.36)となっており、いずれの国も人口維持の目安となる2.08(人口置換水準)を下回っているが、その水準は、各国間の差が大きい(図1−3)。
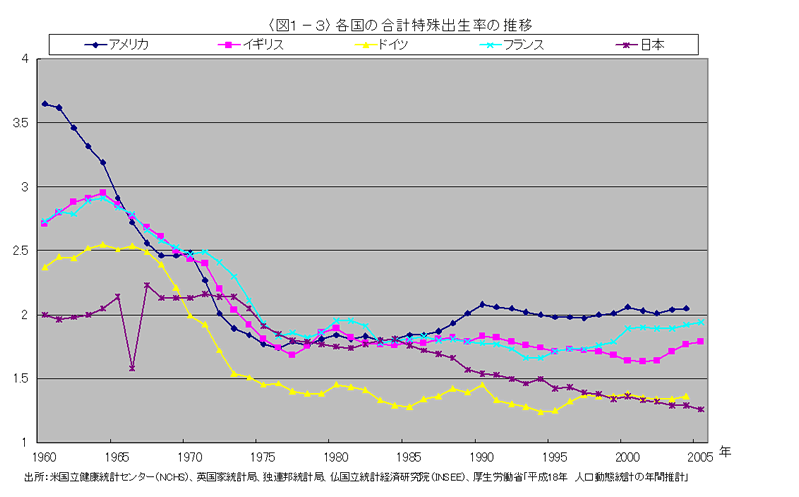
(2)労働市場の動向
前述のとおり、各国とも程度の差はあるが65歳以上の高齢者が増加し、生産年齢(15〜64歳)人口割合が減少する見込みであることが分かった。
次に各国の労働者の引退(退職)時期や引退前の現役世代である55〜64歳の高齢者の労働市場の状況を調査し、同世代の高齢者の就労意欲を確認する。
a 高齢者の引退年齢
2004年における各国の公式引退年齢(公的老齢年金を満額受給可能な最低年齢)は、概ね65歳となっているが、フランスの男女及びイギリスの女性については60歳となっている。
一方、実引退年齢(40歳以上の者が労働力を離れた(継続就労の意思なく退職した)年齢の平均値)は、公式引退年齢を下回っている国が多く、満額年金受給開始前に何らかの手段により早期に引退していることが分かる。また、アメリカ、イギリス及びドイツでは女性のほうが男性より早く引退している。
なお、アメリカ及びイギリスに比べ、ドイツ及びフランスのほうが実引退年齢の水準が低いことから、より早期引退傾向が強いことがわかる(表1−2)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b 高齢者の就業率の推移
高齢者(55〜64歳)の就業率については、いずれの国(統計値のないイギリスを除く)も1960年代後半から1980年代半ばまで下降し、その後、上昇に転じるU字型のカーブを描いている。
1960年代後半からの高齢者(55〜64歳)の就業率の下降については、特にドイツ及びフランスの下降幅が大きい。これは、当時の欧州の関心が若年者雇用対策にあり、高齢者はむしろ自発的に早期に退職(引退)し、若年者にポストをゆずるという高齢者の早期引退促進施策が積極的に推進されていたことが一因である。
高齢者(55〜64歳)の就業率については、アメリカ及びイギリスに比べ、ドイツ及びフランスが一貫して低水準という特徴がある。なお、2005年の就業率は、アメリカ(60.8%)、イギリス(56.8%)、ドイツ(45.5%)、フランス(40.7%)となっている(図1−4)。
また、高齢者(55〜64歳)の就業率は、年齢計(15〜64歳)の就業率に比べ各国とも低い水準にある(参考:[年齢計(15〜64歳)の就業率(2005年)]アメリカ(71.5%)、イギリス(72.6%)、ドイツ(65.5%)、フランス(62.3%))。
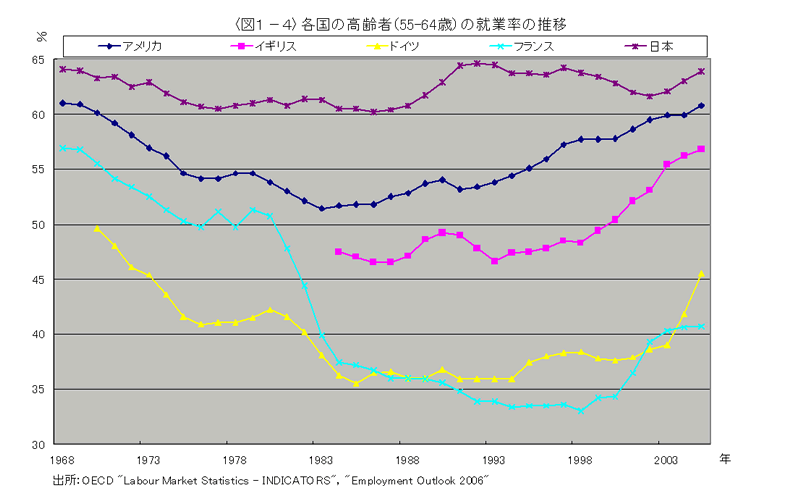
注:就業率は就業者数/人口 |
c 高齢者の失業率の推移
高齢者(55〜64歳)の失業率は、1973年のオイルショック以降1980年代前半まで上昇した。その後は、各国によって異なる推移をみせるが、ドイツは上昇傾向であり、イギリスは下降傾向であることがわかる。
2005年の高齢者(55〜64歳)の失業率は、ドイツ(12.7%)、フランス(6.8%)、アメリカ(3.3%)、イギリス(2.7%)となっており、失業率の水準についてはアメリカ及びイギリスに比べ、ドイツ及びフランスが高水準である(図1−5)。
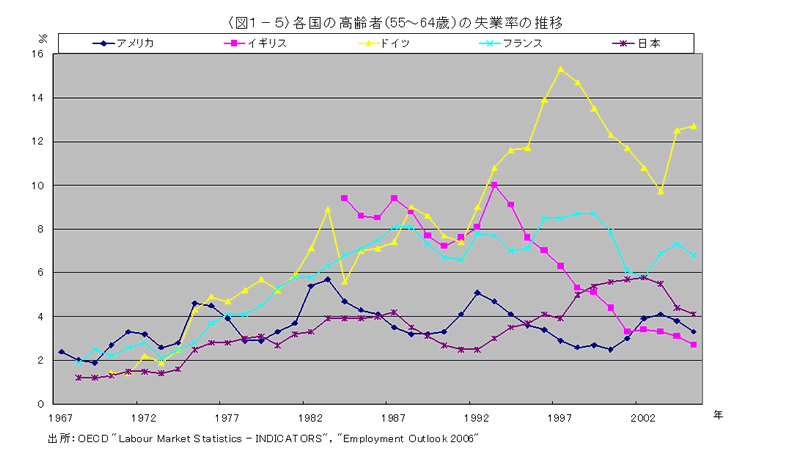
注:失業率は失業者数/(失業者数+就業者数) |
d 年齢計失業率との比率
次に、年齢計(15〜64歳)と高齢者(55〜64歳)の失業率を比較してみる。アメリカ、イギリス及びフランスなど1倍以下になっている国は、他の世代に比べ、高齢者の失業のおそれが低い国といえる。一方、1倍を超えるドイツは、高齢者の失業情勢が厳しい国といえるが、その比率は1995年の1.43から2005年には1.12まで低下している(表1−3)。
〈表1−3〉年齢計(15〜64歳)失業率に対する高齢者(55〜64歳)失業率の比率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 諸外国における高齢者雇用対策
以上のとおり、各国とも65歳以上の高齢者が増加し、生産年齢(15〜64歳)人口割合が減少する見込みである。つまり、これは社会を支える働き盛りの人口割合が減り、年金等社会保障制度の受益者が増加することを意味する。
また、各国とも高齢者は早期引退傾向があり、かつ、55〜64歳の高齢者の就業率が年齢計就業率に比べ低い、特にその傾向はドイツ及びフランスにおいて顕著であるが、近年いずれの国の就業率も上昇傾向にある。
ここでポイントとなるのは早期引退している55〜64歳の高齢者が現役世代として活き活きと働き続けることが、社会の活性化につながり、かつ、彼らが社会保障制度の受益者から支え手になることを意味する点である。そして、就業率の上昇を見る限り、各国ともそれに成功しつつある。以下、各国は具体的にどのような施策を採用しているかみていくこととする。
ここでは、まず、EUがイギリス、ドイツ、フランスなどのEU加盟国に対し、高齢者雇用対策の推進をどのように求めているのか把握し、次に各調査対象国の(1)(年金、失業保険などの)社会保障制度、(2)年齢に関する法規則、(3)段階的な引退の支援策、(4)積極的な就業促進政策、を高齢者の就業促進の観点から確認する。
(1)EUにおける取組み
従前のEC(現EU)各国では、主に若年失業者対策のため、高齢者の早期引退を促し、若年者のためのポストを確保する施策が行われていた。しかし、肝心の若年失業率の改善は実現せず、進展する高齢化により、年金等社会保険財政状況が急速に悪化したため、各国は社会保険財政の担い手確保のため、高齢者の引退促進施策から就業促進施策への転換を図った。
また、EUは、高齢者(55〜64歳)の就業率を2010年までに50%とし、労働市場からの平均引退年齢を約64.9歳に引き上げる目標を示している。そしてその目標達成のため、EUは加盟国に対し「活力ある高齢化(アクティブエージング)」という高齢者雇用政策の方針を打ち出している。「活力ある高齢化」の内容は、高齢労働者に対する(1)継続的な訓練機会を提供、(2)職場の安全衛生条件の改善、(3)弾力的な作業編成による多様な働き方の実現、(4)早期引退促進制度の廃止、(5)積極的労働市場施策の活用、などである。また、高齢者の就業率向上及び社会保障財政安定のため、「働くことが(経済的に)見合うようにする(メイク・ワーク・ペイ)」という方針を掲げ、(1)社会保障給付の水準(replacement rate)及び支給期間、(2)求職活動及びエンプロイアビリティ向上施策に関連させた適切かつ効果的な(社会保障)給付、(3)在職給付(in-work benefits)を適切に改善することも加盟国は求められている。
なお、EUは、2000年に一般雇用機会均等指令を制定し、年齢、障害等に係る雇用・職業に関する一切の差別の原則禁止(定年制など多数の例外あり)をEU加盟国に求めている。最も対応が遅かったイギリス、ドイツにおいても2006年中に法律が成立し施行されている。
(2)各国における取組み
a 引退と社会保障制度
労働者の引退(再就職の意思なく退職すること)には、年金や失業保険など所得を保障する社会保障制度が大きく関わっている。それは、年金等が十分に支給されれば、働かなくとも生計が維持できるためである。
ここでは、(老後の所得保障制度の中心となる)老齢年金制度、及び(年金受給までの所得保障として機能しうる)失業保険制度などにつき、それぞれの特徴と各国の改革について確認する。
(a)老齢年金制度
労働者の多くは、引退後の生計を老齢年金に頼るため、年金制度の設計は労働者の引退時期に大きく関わる。
労働者の就労・引退に影響を与える要因としては、(1)(満額)年金支給開始年齢、(2)繰上げ支給制度、(3)繰下げ支給制度、(4)支給水準、(5)在職老齢年金制度、の5つがあげられる。
ア (満額)支給開始年齢
年金額が減額されずに満額受給できる年齢である(満額)支給開始年齢は、アメリカ(65歳8か月)、ドイツ(65歳)、イギリス(男性65歳、女性60歳)、フランス(60歳)となっている(2006年時点)。
〈表1−4〉各国の(満額)支給開始年齢(2006年時点)
| アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス |
| 65歳8か月 | 男65歳、女60歳 | 65歳(重度障害者は63歳) | 60歳 |
| ※ 2003〜2027年にかけ65歳から67歳に引上げ中 | ※ 女性は2010〜2020年にかけ65歳に引上げ予定。 ※ 男女とも2024〜2046年にかけ68歳に引上げ予定(法案審議中) |
※ 2012〜2029年にかけ67歳へ引上げ予定(閣議決定) | (被保険者期間が40年以上の場合のみ満額支給) |
イ 繰上げ支給制度(老齢年金の早期支給制度)
イギリス以外の国は、一定の要件(例、(35年以上など)長期間に渡り保険料を納付した者、女性等)を満たす者等については、(満額)支給開始年齢以前に受給可能となる繰上げ支給制度がある。アメリカ及びドイツは、繰上げ(早め)た期間に応じ、年金給付額が減額され、その額が一生続くことになるが、フランスは56歳から受給でき、その上、受給額も減額されない。
高齢者の就労を促進するためには(1)繰上げ支給対象者となる要件の厳格化又は廃止、(2)繰上げ支給可能な年齢の引上げ、(3)減額率を高くすること、が効果的であり、実際、ドイツは主な繰上げ支給制度を2016年末に廃止する予定としている。
一方、長期間に渡り保険料を納めた労働者(以下、「長期被保険者」という)に対しては、他の労働者より早期に引退を可能とする措置をドイツ及びフランスは実施、又は予定している。これは、既に長期に渡り就労し社会に貢献した者に対してはその分早く引退できるように配慮することで、他の(勤続期間の短い)労働者に対し長期勤続を奨励している政策とのバランスを図っているものと考えられる。
なお、繰上げ支給可能な年齢は、フランス>ドイツ・アメリカ>イギリスの順で低くなっており、この年齢が低いほど高齢者の就労意欲を削ぎ、早期引退を促進する。また、減額率はフランス>ドイツ>アメリカの順で低くなっており、減額率が低いほど高齢者は容易に繰上げ受給するため早期引退を促進する。
〈表1−5〉各国の繰上げ支給制度(老齢年金の早期支給制度)
|
||||||||||||||||||||||||||||
ウ 繰下げ支給
各国とも「(満額)支給開始年齢」以後に受給開始を繰下げ(遅らせ)た場合、開始時期に応じて受給額が増額され、その額が一生続く繰下げ支給制度がある。
高齢者の就労を促進するためには(1)繰下げ支給可能な年齢制限の引上げ又は廃止、(2)増額率を高くすること、が効果的であり、実際、アメリカ、イギリス及びフランスでは、近年、前述の方法による制度改正を実施している。
また、現在の増額率の水準を比較すると、イギリス>アメリカ>ドイツ>フランスの順に高くなっており、高い国ほど高齢者の就労促進に対するインセンティブが大きいといえる。
〈表1−6〉各国の繰下げ支給制度((満額)支給開始年齢以降の支給制度)
|
エ 所得代替率
所得代替率(平均的収入の労働者の(税引き後の)手取り年金額/現役世代の平均的な労働者の手取り収入額)が高いほど、老後の収入の不安が少なくなり、高齢者の早期引退を促進する要因となりうる。
各国の所得代替率は下表のとおりであり、社会保障が手厚いとされるドイツ及びフランスがアメリカ及びイギリスより水準が高いことが特徴である(表1−7)。
〈表1−7〉各国の所得代替率(男性:2002年)
|
オ 年金受給中の就労について(在職老齢年金)
年金受給可能な在職者について、就労しても年金を全額支給(減額しない)する制度を適用すれば就労促進のインセンティブが働くこととなる。一方、一定水準以上就労すると年金給付が減額又は支給停止される制度を適用すれば、労働者の就労意欲を削ぐこととなるが、現役世代(保険料負担者)との公平感は保たれ、年金の財政面も安定する。
イギリスは前者の年金給付を減額しない制度を選択し、フランスは後者の年金給付を減額する制度を採用している。
一方、アメリカ及びドイツは、繰上げ支給時のみ年金給付を減額する制度を採用している。なお、アメリカ及びフランスは近年、高齢者の就労を促進する方向での改革を行っている(表1−8)。
〈表1−8〉年金受給中の就労に対する各国の対応
| アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | ||
| (満額)支給開始年齢 | 前(繰上げ支給時) | 在職者の年金額は賃金額が一定水準以上になると賃金額に応じ減額される。 | (繰上げ支給制度自体なし) | 在職者の年金額は賃金額が一定水準以上になると賃金額に応じ減額される。 | 年金額と賃金額の合計が引退(年金支給開始)直前の賃金額を越えない場合、年金額は減額されない。 ※2007年1月から引退直前の賃金が低水準な者については年金額と賃金額の合計額が最低賃金(SMIC)の1.6倍まで就労しても年金額が減額されなくなった。 |
| 後 | 在職していても年金額は減額されない。 ※1999年以前は(満額)支給開始年齢から69歳までの年金受給者が就労した際、年金額が減額されていたが、2000年に廃止。 |
在職していても年金額は減額されない。 | 在職していても年金額は減額されない。 | ||
カ 早期引退実績(2004年)
以上のようにドイツ及びフランスについては、アメリカ及びイギリスに比べ、年金の給付水準が高いうえ、繰上げ支給可能な年齢が低く、また繰り上げ時の年金給付の減額率が低いなど、高齢者の就労意欲が保ちづらい制度設計になっている。そのため、近年改革を進めているものの、ドイツでは2004年に新たに老齢年金を受給し始めた81万人のうち実に6割近くの46万人が繰上げ支給をし、65歳になる前に引退している。
また、フランスについても、年齢階級別の老齢年金受給者数を見ると55〜59歳時点で16万人、60〜64歳時点で166万人となっており、相当数の者が65歳前に引退している。
キ 私的年金制度等
公的年金の上乗せ部分として、より安定した老後の生活を国民に保障することができる私的年金(企業年金及び個人年金)等について各国は様々なアプローチの仕方をしている。
イギリス及びドイツは、新たな年金の枠組みを作り、加入促進を図っている。また、フランスについては、1972年の法改正で、公的年金の一般制度(1階部分)に加入する被用者につき、2階部分である企業年金(補足年金制度)への加入を義務づけている。なお、アメリカでは、企業年金の提供が法的に強制されているわけではないが、企業年金が全事業所の約半数で提供されるなど広く普及している(表1−9)。
〈表1−9〉各国の私的年金(企業年金及び個人年金)等加入促進措置
| アメリカ | 企業年金プランの創設は事業主の任意であるが、公的年金の上乗せとし て企業年金が発展している。2006年3月時点で企業年金を提供している 事業所は全事業所の約半数となっている。 |
| イギリス | 【ステークホルダー年金:2001年4月〜】 毎年の保険料拠出に上限を設けるとともに、管理手数料に上限(年金 積立額の1%まで(最初の10年間は1.5%まで))を設け、中低所得者に 加入しやすいものとした個人年金である。掛金は全額、税制上の所得控 除となり、償還額は自動的に年金の積立金に入金される。 |
| ドイツ | 【リースター年金(Rister-Rente):2002年1月〜】 任意加入の積立方式の私的年金(企業年金又は個人年金)であり、保 険料が税制上の所得控除の対象となり、低所得の企業年金加入者に対し、 ( 子供がいる場合は)子1人あたり月額185ユーロが保険料として助成 される。なお、保険料拠出の上限は2002年から2008年にかけ所得の1% から4%に引き上げられる予定である。 |
| フランス | 【補足年金制度(les regimes complementaires)】 補足年金制度は、一般制度(民間の商工業被用者向け公的年金)など 基礎年金制度(1階部分)に上乗せされる2階部分の企業年金の総称であ る。1972年の社会保険法改正により一般制度の被用者が強制加入となる など、現在は公的年金の性格を強く帯びる制度となっている。また、3階 部分としてさらに追加補足年金制度があるが、こちらは任意加入の企業 年金となっている。 |
(b)失業保険制度
仕事を探している失業者の生活を支える失業保険制度も(1)容易に受給でき、(2)給付内容が充実している場合は、労働者の就労意欲を削ぎ、実質的に早期引退を促進する恐れがある。
ア 高齢者に対する求職活動義務の免除
失業保険は一般的に「働くことができるが、仕事がなく、仕事探し(求職活動)を行っている者」に対し支給されるのが原則である。しかし、一部の国では、高齢者に対して求職活動をしなくとも失業保険の受給を認める特例(求職活動義務の免除)措置を実施しており、高齢者の就労を阻害する要因となっている。
今回の調査対象国ではドイツが58歳以上の者、フランスが57.5歳以上の者の求職活動義務を免除しており、ドイツでは23万人の高齢者がこの措置を利用している(2005年実績)。
なお、ドイツでも高齢者に対する求職活動義務免除措置の是非について議論され、2007年末には同措置を廃止するとしている。
イ 給付内容(給付水準及び給付期間)
給付水準が高く長期に渡り受給できる失業保険制度がある場合、年金受給までの橋渡しとなり、高齢者の就労意欲を削ぐ結果となる。
各国の給付水準については、各国の算定方法が異なるため単純比較はできないが、給付水準はドイツ≒フランス>アメリカ>イギリスの順に高いといえる。また、最長給付期間については長い順にフランス>ドイツ>アメリカ≧イギリスとなる。従って、失業保険についても老齢年金と同様にドイツ及びフランスはアメリカ及びイギリスより給付内容が手厚いことがわかる(表1−10)。
しかし、ドイツ及びフランスにおいても失業者の就労促進のため、高齢失業者を含めた失業給付期間を短縮する改革を近年実施している。
〈表1−10〉各国の失業給付内容(給付水準及び給付期間(2006年末現在))
| アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | |
| 制度名 | 連邦・州失業保険 (UC) |
拠出制求職者給付 (JSA) |
失業給付 (Arbeitslosengeld) |
雇用復帰支援手当 (ARE) |
| 給付水準 | 州毎に異なるが、概ね課税前所得の50% | 週57.45ポンド(約1万2千円) ※25歳以上の者の場合 |
離職前の手取り賃金の67% (扶養する子がない者は60%) |
離職前の課税前賃金(日額)の57.4% ※離職前の課税前賃金月 額が1,846ユーロ(約25 万円)以上のフルタイム 労働者の場合 |
| 給付期間 | 州毎に異なるが、概ね最長26週 (失業情勢が悪化した場合、最長39週) |
最長182日 (26週) |
55歳未満の者は最長12か月 55歳以上の者は最長18か月 ※ 2006年2月改正前の給付期間は、57歳以上の場合で最長32か月。 |
50歳以上の者は最長36か月 57.5歳以上の者は最長42か月 ※ 2006年1月改正によ り57.5歳以上で満額年金 が受給可能な者の失業給 付の期間が最長42か月か ら36か月に短縮。 |
(c)失業扶助制度
イギリス、ドイツ及びフランスには、主に失業給付受給が終了した求職者に対する生活保障の手当として失業扶助がある。失業扶助は、求職中の失業者の生活保障手当である点では失業保険的であるが、税財源(全額国庫負担)により賄われ、(資力調査等があり)一定水準以下の資力(収入及び資産)の者のみ受給できる点で公的扶助(生活保護)的であるため、失業保険と公的扶助(生活保護)との中間的な性格を持つ制度である。
失業扶助の給付水準は公的扶助と同程度のため、それほど高くはない。ただし、受給要件を満たしていれば支給期間を更新することにより、年金支給開始年齢まで受給できるため高齢者の就労意欲を削ぐ可能性がある。
また、各国とも高齢者に対しては求職活動をしなくとも失業扶助の受給を認める特例(求職活動義務の免除)措置を実施しており、高齢者の就労を阻害する要因となっている(表1−11)。
〈表1−11〉各国の失業扶助制度
|
|||||||||||||||||||||||||||
注:アメリカには失業扶助制度はない。 |
|||||||||||||||||||||||||||
(d)高齢者の就労と関連するその他の社会保障制度
アメリカでは65歳未満の国民を広く(普遍的に)カバーする公的医療保険制度がないことが結果として早期引退を抑制していると考えられる。
一方、イギリス及びドイツでは、疾病や障害によって就労できない者に対し所得保障をする給付(日本の障害年金に相当)が、本来の趣旨と異なり、実態上(老齢)年金受給までの所得保障として機能しており、高齢者の早期引退を促しているといわれている。
また、フランスには年金制度の長期被保険者に対し、公的に(老齢)年金受給まで所得を保障する制度がある(表1−12)。
〈表1−12〉高齢者の就労と関連するその他の社会保障制度
| アメリカ | 全国民をカバーする公的医療保険制度の不在 |
| 【制度概要】アメリカには65歳以上の者を対象とした公的医療保険(メディケア)はあるが、全国民をカバーする公的医療保険がなく、現役世代の多くの者は、企業が福利厚生の一環として提供する医療保険に頼っている。これが、結果として労働者に就労のインセンティブを与え、早期引退を抑制していると考えられる。 | |
| イギリス | 就労不能給付(Incapacity Benefit) |
| 【制度概要】疾病や障害によって全く就労することができない者に対し、年金支給開始年齢(男性65歳、女性60歳)まで支給される保険給付である。給付水準は就労不能になってから52週を超える者については78.5ポンド(約1万6千円)/週となっている。利用者は1980年以降増加を続けている。 | |
| 【実 績】 50〜64歳の受給者数 約83万人(2005年2月) | |
| 【近年の改革】 受給者の仕事への復帰を促すため、就労不能給付に替え、「雇用及び生活補助手当(Employment and Support Allowance)」を新設する法案が2006年7月に議会に提出された。 「雇用及び生活補助手当」受給希望者は審査を受け、就労能力があると判定された者は、就業に向けた活動が義務づけられる。 |
|
| ドイツ | 障害年金(Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit) |
| 【制度概要】 疾病や障害によって1日に6時間未満しか就労できない65歳(年金支給開始年齢)未満の者に対し、支給される障害年金である。 障害発生時点からいつでも受給できるが、63歳以前に受給する場合は、最大10.8%年金給付額が減額される。2004年末時点の平均給付月額は739ユーロ(約10万1千円(旧西ドイツ地区))である。就労能力に見合う職場がない場合も受給できるため、労働市場情勢の悪化に伴い受給者が増加傾向にある。 |
|
| 【実 績】 受給者数 約170万人(2004年末) | |
| 【近年の改革】2001年1月から障害年金の繰上げ(早期)受給者に対し年金給付額を減額する措置が導入されている。 | |
| フランス | 年金相当給付(AER:allocation equivalent retraite) |
| 【制度概要】 被保険者期間が40年以上の失業者に対し、60歳(年金支給開始年齢)まで所得を保障するため、支給される手当である。ただし、一定以上の月収(夫婦の場合2123ユーロ(約29万1千円))がある場合は受給できない。支給基準月額は936ユーロ(約12万8千円)で収入に応じ減額される(数値はいずれも2006年1月1日現在)。2002年制度創設以降受給者数が急増している。 | |
| 【実 績】 受給者数 約6万人(2006年11月末)(対前年同月伸び率44.1%) | |
| ※ 失業扶助制度(ASS)又はAERが受給できない場合、「最低社会復帰扶助(RMI:日本の生活保護に相当)」が活用できる。 | |
b 年齢に関する法規則
事業主が労働者を募集、採用、解雇等する際に高齢者を年齢により差別しないように促すことも高齢者の就業促進のため重要である。ここでは各国が高齢者の差別禁止のためどのような法制をとっているのか把握した後、高齢者の退職に大きく関与する定年制及び解雇法制における高齢者の取扱いなどを確認する。
(a)(雇用分野における)年齢差別禁止法
アメリカは、1967年という他国より相当に早い段階で年齢を理由とした募集、採用、解雇、賃金、労働条件などの差別を禁止する「雇用における年齢差別禁止法(ADEA)」を制定している。同法は40歳以上という中高齢者のみの差別を禁止している点が特徴である。
一方、イギリス、ドイツ及びフランスについては、年齢、障害等に係る雇用・職業に関する一切の差別の原則禁止を加盟国に求めるEU指令(一般雇用機会均等指令)が2000年12月に施行されたため、各国とも国内法制化に取組み、法制化期限となっていた2006年末までに国内法令を施行している(表1−13)。
EUの一般雇用機会均等指令は年齢要件を中心に定年制など多くの例外規定が定められており、イギリス、ドイツ及びフランスの国内法令もそれにならっている。
〈表1−13〉各国の(雇用分野を含む)年齢差別禁止の根拠法
| アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | |
| 年齢差別禁止根拠法 | 雇用における年齢差別禁止法(ADEA) | 2006年雇用均等(年齢)規則 | 一般雇用機会均等法(AGG) | 労働法典L.122-45条(差別防止に関する一般規定)など |
| 施行年月 | 1967年 | 2006年10月 | 2006年8月 | (2001年11月に改正) |
| 保護対象年齢 | 40歳以上のみ | 全年齢 | ||
(b)定年に関する法制度
定年制は、労働者が一定年齢(定年年齢)に達することにより、労働契約を終了(労働者が退職)する制度である。定年制は、労働者の就労意思や就労能力に関わらず退職させる点で、継続就業を希望する高齢労働者に対する年齢差別と捉えることができる一方、解雇規制が強い国々では、少なくとも定年年齢までは雇用が維持され、その後、定年年齢到達という客観的な事実により労働契約が終了するため、労働者は定年後の人生計画が、企業は人事計画が立てやすいという面がある。
今回の調査対象国では、イギリス、ドイツ及びフランスは定年制を認めているのに対し、アメリカは原則認めていない。また、設定可能な定年年齢については、いずれの国も65歳以上と年金の支給開始年齢を意識したものとなっている(表1−14)。
〈表1−14〉各国の定年に関する法制度
|
||||||||||||||||||||||
(c)高齢者の解雇に対する特別な保護
高齢者に対し、一般の労働者より解雇要件を厳しくし、特別に保護した場合、既に雇われている高齢労働者の雇用が維持されやすくなる。その反面、事業主が労働者を新たに雇い入れる際、解雇が容易にできないことから高齢者の採用を敬遠する可能性も否定できない。
アメリカは、随意雇用の原則(employment at will)に基づき、使用者がいついかなる理由でも労働者を解雇できる国である。ただし、高齢者に関しては先述の年齢差別禁止法により、年齢を理由とした解雇から保護されている。さらに、長期勤続者を優遇する先任権制度も高齢者に対し有利に働くことが多い。ドイツやフランスもアメリカ同様、高齢者の解雇保護を一般の労働者より手厚いものとしている。一方、イギリスは65歳以上の高齢者を解雇保護制度の適用対象から外していた。
最近の動きとしては、フランスが高齢者の解雇保護制度のひとつである「ドラランド拠出金」について2010年までに廃止する方針を示し、イギリスは高齢者に対する解雇保護制度の適用除外措置を廃止しており、両国は高齢者の解雇保護を一般労働者に近づける方向で動いている(表1−15)。
〈表1−15〉高齢者の解雇に対する特別な保護等及びその動き
| アメリカ | ○ 先任権制度 労働協約において勤続年数の長い者はレイオフ(一時的解雇)やリコール(再雇 用)等の際に優先的に処遇される権利を定めている場合が多い。 |
| イギリス | ○ 高齢者に対する雇用保護制度の付与(適用除外措置の廃止) 従来は、65歳以上の者について、(1)不公正に解雇されない権利及び(2)余剰人員整 理解雇手当の請求権、の適用が除外されていたが、2006年雇用均等(年齢)規則の 施行に伴い、この年齢制限が撤廃された。 |
| ○ 65歳以上の者の就労請求権 労働者は、65歳を超えて就労を請求する権利を有しており、使用者はそれを考慮 する義務がある。 |
|
| ドイツ | ○ 解雇制限法による高齢者の解雇保護 不当解雇された労働者が、元の条件で職場復帰できない場合、和解金が支払われ る。対象者が、50歳以上の場合、和解金が上乗せされる。 |
| フランス | ○ 高齢者の解雇時の追加負担制度(ドラランド拠出金)の廃止 50 歳以上の労働者を解雇する場合、企業が失業保険の拠出金を支払う制度(ドララ ンド拠出金)を2010年までに段階的に廃止していく方針。 |
| ○ 整理解雇時における高齢者等への配慮義務 企業が経済的な理由による解雇(整理解雇)を行う際に定めなければならない解 雇の順番の基準において、高齢者等の状況を特に考慮しなければならない。 |
c 段階的な引退を支援するための制度
高齢者の就労意欲、就労能力は千差万別であるため、就労時間を減らし、引退(退職)までの期間をできるだけ長くする選択肢を用意することも高齢者の就労促進には効果的である。
ただし、段階的な引退支援制度の代表例であるドイツの「高齢者パート就労促進制度」は、実態として早期引退に用いられているため、2009年末に廃止予定となっている。また、フランスにも「段階的引退制度(RP)」があるが、利用者は少ない。
なお、イギリスにおいては従前、退職後でなければ、企業年金を受給できなかったが、2006年4月からは企業年金の支給開始年齢以降も同一事業主の元でパートタイム(フルタイムも可)で働きながら企業年金の一部(又は全部)を受給することが可能となった。これも段階的な引退制度のひとつといえよう。
d 積極的な就業促進政策(狭義の「高齢者雇用対策」)
(a)供給側(求職者及び労働者)に対する施策
求職者に対する支援には、職場の提供(アメリカ)、職業相談及び各支援策の組み合わせ(イギリス)、高齢労働者の賃金保障(ドイツ)などがある。
また、ドイツ及びフランスでは、在職中の高齢労働者の職業訓練への参加率が他の年代に比べ低いため、職業訓練参加支援策を実施している(表1−16)。
〈表1−16〉求職者及び労働者に対する主な積極的就業促進施策
| アメリカ | ○ 高齢者地域社会サービス雇用事業 55歳以上で低所得の者を対象とした事業であり、州・地方政府や、指定を受けた 非営利団体が、事業の全経費を連邦政府の負担で、実施する。 対象者は、最低賃金相当の賃金を得ながら週20時間程度、福祉サービス業に従事 することとなる。定員は約6万人であり、年間延べ約10万人程度の参加が見込まれている。 |
| イギリス | ○ ニューディール50プラス(New Deal 50+) 50歳以上で、本人又は配偶者が求職者給付(拠出制及び所得調査制)、就労不能 給付、などを6か月以上受給している者を対象とした事業である。 対象者は、公共職業安定所(ジョブセンター・プラス)で、プログラムを通して 同一のパーソナル・アドバイザーから、就職促進のため職業相談、履歴書の書き方 の指導、訓練機会の提供、ボランティアの仕事の提供などを受ける。このプログラ ムの対象者を採用した事業主は対象者の在職訓練のための訓練補助金が受給で きる。なお、プログラムへの参加は任意である。本プログラムにより、約15万人が 就職した(2000年4月から2005年8月末まで)。 |
| ドイツ | ○ 高齢者向けの職業継続訓練の促進(Fbw) 従業員100人未満の企業の50歳以上の労働者で職業継続訓練に参加する者に対 し、訓練受講料、交通費、子の養育費、泊まり込みの場合の宿泊・食事費用が訓練 期間中支給される。 ※ 政府は、適用範囲を拡大する方向で検討中である。 |
| ○ 高齢労働者の賃金保障(EGS) 50歳以上の失業者で失業給付の受給残日数が180日以上ある者が再就職した際、 失業前の手取り賃金と新たな職の手取り賃金の差額の50%を、失業給付の受給残日数 と同期間分支給する。利用実績は、約4千人(2005年)である。 |
|
| フランス | ○ 「被用者の職業人生にわたる訓練機会」に関する全国業種横断的協約 フランスの企業は、社員への訓練機会の付与が法律で義務づけられており、労使 が高齢労働者・熟練労働者のための様々な訓練参加権を労働協約で規定し、参加促 進を図っている。 例) 20年以上の職務経験がある45歳以上の被用者で勤続1年以上の者は、優先的 に技能検定を受講できる他、時間外の職業訓練を受講する場合は、給与の50%相 当の教育訓練手当が企業から支給される。 |
(b)需要側(事業主)に対する施策
事業主に対する支援には、年齢差別是正のためのキャンペーン実施(イギリス)、高齢失業者雇入れ時の賃金助成(ドイツ及びフランス)などがある。
なお、アメリカは、機会均等の下での自由競争を重視しているため、高齢者の就業促進を事業主側に働きかける施策は特段認められなかった(表1−17)。
〈表1−17〉事業主に対する主な積極的就業促進施策
| イギリス | ○ エイジ・ポジティブ(Age Positive) 年齢差別是正キャンペーンであり、ウェブサイト上で政府の年齢差別是正政策や好 事例についての情報提供等を実施している。なお、事務局は雇用年金省に置かれて いる。 |
| ドイツ | ○ 統合助成金(EGZ) 就職困難な失業者を雇い入れる事業主に対し、対象労働者の賃金の50%を12か月間 支給する。失業者が50歳以上の場合は、特例として支給期間は36か月までとなる。 ただし、12か月経過するごとに助成は10%ずつ減額される(特例措置は2009年12 月末日まで有効)。2005年の利用実績は約6万1千人であり、うち50歳以上の者は 約2万4千人となっている。 ○ 失業保険料の免除 55歳以上の失業者を新たに雇用した事業主に対し、事業主負担分の失業保険料(賃 金の2.1%)を免除する(2007年末まで有効)。 |
| フランス | ○ 雇用主導契約 (CIE) 公共職業安定所(ANPE)とCIE協定を結び、高齢者や障害者等就職に困難を抱え る者をCIEに基づいて雇用した事業主に対し、最低賃金(SMIC)の47%を上限に、 最長2年間の賃金補助を実施する。2005年のCIE利用者に占める50歳以上の割合は 17.5%で同年5〜12月の契約数は約15,000件である。 ○ 50歳以上の求職者を採用する使用者に対する逓減支援(ADE + 50ans) 50 歳以上で失業期間3か月以上の失業保険給付受給者を、期間の定めのない雇用 契約(CDI)又は12〜18か月の有期雇用契約(CDD)により雇用した企業に対し対象 者の賃金補助を実施する制度である。 |
(3)まとめ
以上のとおり、各国の高齢者雇用対策を(1)(年金、失業保険などの)社会保障制度、(2)年齢に関する法規則、(3)段階的な引退の支援制度、(4)積極的な就業促進政策、の項目ごとに確認してきた。
各調査対象国ごとに社会保障制度に対するスタンス、労働事情、労働法制、社会背景などが異なり単純比較はできないが、各国の高齢者雇用対策の特色は以下のとおりである。
アメリカは、ドイツ及びフランスに比べ社会保障制度の給付水準が低い。また、一般労働者の解雇規制が少ない反面、各国に先駆けて制定した雇用における年齢差別禁止法により高齢者に対する保護を手厚くしている。さらに、労働協約により広く認められている先任権も高齢者に有利に働くことが多い。このような環境の中で、アメリカの55〜64歳の就業率は既に比較的高い水準にあり、近年さらに上昇中である。現在、年金の(満額)支給開始年齢が65歳から67歳に引き上げられていることから、アメリカは65歳以上世代の就業促進についても視野に入れつつある。
イギリスは、ドイツ及びフランスに比べ社会保障制度の給付水準が低い。さらに、年金の繰上げ支給制度がなく、繰下げ支給時の給付増額率も高い。このように、年金制度や失業保険制度などの社会保障制度は調査対象国の中で最も高齢者の就労意欲を高めるようなつくりとなっている。一方、就労不能給付(日本の障害年金に相当)が本来の趣旨と異なり早期引退に利用されているため、現在制度改革が検討されている。なお、年齢差別禁止に関しては1999年から是正キャンペーンを実施しており、2006年には雇用均等(年齢)規則も施行された。規則施行以前は、65歳以上の高齢者に対し雇用保護制度の適用除外措置がとられていたが、同措置も廃止されている。このような環境の中で、イギリスの55〜64歳の就業率はアメリカに次ぐ高い水準にあり、近年さらに上昇中である。現在、年金の支給開始年齢の68歳への引上げ法案が議会で審議中であり、イギリスについても65歳以上世代の就労促進に向け動き始めている。
ドイツは、アメリカ及びイギリスに比べ社会保障制度の給付水準が高い。また、年金の繰上げ支給制度が多数あり早期引退者も多い。また、失業保険制度、失業扶助制度、障害年金などの所得保障制度も充実し、さらに、段階的な引退支援制度である「高齢者パート就労促進制度」を実態上早期引退に用いることが可能なため、高齢者の就労意欲が保ちづらくなっている。これらの制度については、高齢者の早期引退を抑制する観点から、廃止又は改善に向けての取組みが行われている。
なお、ドイツは2006年に一般雇用機会均等法を施行し、年齢による差別(又は優遇)を原則禁止したが、解雇については既存の(高齢者保護が手厚い)解雇保護法が適用されるなど高齢者保護は他の年齢層と比べ高いレベルに保たれている。また、ドイツは55〜64歳の失業率が他の年代に比べ相対的に高いため、近年、高齢者のための積極的就業施策を充実させるよう取り組んでいる。
このような環境の中で、ドイツの55〜64歳の就業率はアメリカ及びイギリスほど高くはないが、近年急上昇中である。現在、年金の支給開始年齢の65歳から67歳への引上げが閣議決定されたところであり、ドイツについても65歳以上世代の就労促進に向け動き始めている。
フランスは、アメリカ及びイギリスに比べ社会保障制度の給付水準が高い。また、年金の(満額)支給開始年齢が男女とも60歳であり、他国より早期に満額年金を受給できる。さらに42年以上保険料を納めた者については56歳から減額措置のない年金を繰上げ受給できる。失業保険制度(ARE)、失業扶助制度(ASS)、年金相当給付(AER)など他の所得保障制度も充実しており、高齢者の就労意欲が保ちづらくなっている点はドイツと共通する特徴である。これらの制度については、主に就労継続に対する権利付与という方向で改善が進められている。一方、フランスは、現時点で年金の(満額)支給開始年齢を引き上げる予定はない。これは、早期引退(制度)が国民の間に広く定着しており、それを廃止する方向での改革は国民的合意を得ることが難しいためともいわれている。なお、フランスは2002年に「差別禁止に関する法律」を施行し、年齢差別による差別(又は優遇)を原則禁止したが、高齢者に対しては既存の解雇に対する保護制度により特別に保護している。しかし、高齢者保護の手厚さは、企業が高齢者の新規雇用を躊躇する要因となっているため、高齢者に対する解雇保護制度の一つである「ドラランド拠出金」の廃止を打ち出している。
なお、フランスは、2000年に政労使の代表等で構成される年金方針評議会(COR)を設置し、年金制度の在り方や高齢者の就業問題に対する方針について、国民的合意を得られるよう努力している。
このような環境の中で、フランスの55〜64歳の就業率は近年上昇傾向にあるものの、今回の調査対象国で最も低い水準となっている。
4 今後の取組み
EUが2010年までに高齢者(55〜64歳)の就業率を50%とし、労働市場からの平均引退年齢を約64.9歳に引き上げる目標を示していることもあり、EU各国は現在さまざまな改革案を打ち出している。イギリスでは、2006年11月に年金の(満額)支給開始年齢を2050年までに68歳に引き上げる法案が議会に提出された。また、ドイツでは高齢者就業促進施策のパッケージである「イニシアチブ50プラス」を2006年9月に閣議決定し、施策内容を連立政権内で調整している。フランスでも2006年6月に(1)高齢者の雇用確保、(2)引退に関する制度の整備、(3)高齢者の再就職促進、(4)高齢者への労働市場における偏見をなくすキャンペーンを柱とする高齢者雇用促進のための政府行動計画(2010年までの5か年計画)が発表されている。
一方、アメリカにおいては、現在、年金の(満額)支給開始年齢を67歳まで段階的に引き上げている最中である。
今後、これらの施策が功を奏し、各国の高齢者就業率が引き続き上昇し、平均引退年齢を引き上げることができるのか注目されるところである。