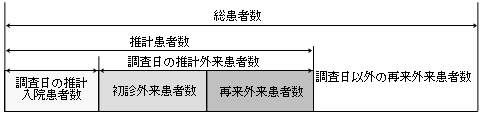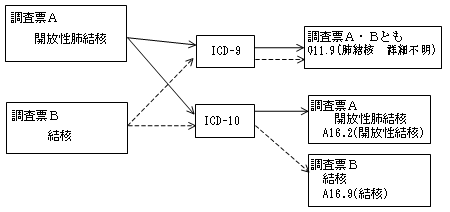(正)
3頁
1 患者調査の概要
調査の目的及び沿革
この調査は、病院及び診療所を利用する患者について、その傷病状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資
料を得ることを目的とする。
その前身は昭和23年11月に1週間にわたって実施された「施設面からみた医療調査」である。その後、おおむね
毎年調査が実施され、昭和28年には統計法に基づく指定統計第66号「患者調査」となった。
患者調査は、患者の診療録の内容に基づく1日調査として毎年実施されたが、昭和59年からは、調査内容を充実
し地域別表章が可能となるよう客体数を拡大し、3年周期で実施することとなった。
調査設計の推移
| |
昭和59年 |
昭和62年 |
平成2年 |
平成5年 |
平成8年 |
平成11年 |
平成14年 |
| 調査対象施設数 |
6,053 |
9,941 |
12,054 |
13,732 |
13,519 |
13,348 |
13,763 |
| |
病院 |
|
2,377 |
3,080 |
5,086 |
6,865 |
6,649 |
6,463 |
6,452 |
| 入院 |
… |
… |
… |
… |
6,649 |
6,463 |
6,452 |
| 外来 |
… |
… |
… |
… |
3,172 |
3,076 |
3,076 |
| 一般診療所 |
2,905 |
5,875 |
5,973 |
5,884 |
5,879 |
5,902 |
6,037 |
| 歯科診療所 |
771 |
986 |
995 |
983 |
991 |
983 |
1,274 |
| |
|
| 客体数(万人) |
|
| |
病院 |
入院・外来 |
67.5 |
95.4 |
131.4 |
235.3 |
179.5 |
203.8 |
197.3 |
| 退院 |
17.5 |
24.0 |
25.5 |
58.5 |
63.5 |
78.7 |
82.8 |
| 一般診療所 |
入院・外来 |
15.9 |
30.7 |
30.0 |
29.1 |
29.1 |
26.0 |
24.2 |
| 退院 |
0.9 |
1.5 |
1.3 |
1.4 |
1.3 |
1.3 |
1.0 |
| 歯科診療所 |
外来 |
2.1 |
2.7 |
2.5 |
2.3 |
2.2 |
1.9 |
2.3 |
| |
|
| 傷病分類(※) |
ICD9 |
ICD9 |
ICD9 |
ICD9 |
ICD10 |
ICD10 |
ICD10 |
| |
|
| 抽出率 |
病院 |
入院 |
2.5/10 |
3/10 |
5/10 |
7/10 |
7/10 |
7/10 |
7/10 |
| 外来 |
2.5/10 |
3/10 |
3.3/10 |
7/10 |
3.3/10 |
3.3/10 |
3.3/10 |
| 一般診療所 |
4/100 |
7.5/100 |
7.5/100 |
7.5/100 |
7.5/100 |
7/100 |
7/100 |
| 歯科診療所 |
2/100 |
2/100 |
2/100 |
2/100 |
2/100 |
1.6/100 |
2/100 |
| |
|
| 表章可能区分 |
病院 |
入院 |
都道府県 |
都道府県 |
二次医療圏 |
二次医療圏 |
二次医療圏 |
二次医療圏 |
二次医療圏 |
| 外来 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
二次医療圏 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
| 一般診療所 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
| 歯科診療所 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
| (退院票)病院 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
二次医療圏 |
二次医療圏 |
二次医療圏 |
二次医療圏 |
| (退院票)一般診療所 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
※ 世界保健機関の「国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD)」に基づき分類。
調査の期日
調査各年の10月上旬の3日間(火〜木)のうち医療施設ごとに指定した1日とした。
なお、退院患者については、調査各年の9月1〜30日までの1か月間とした。
調査の方法
医療施設の管理者が記入する方式によった。
調査の系統
| 厚生労働省 |
|
── |
|
都道府県 |
|
────── |
|
保健所 |
|
── |
|
医療施設 |
| └── |
保健所設置市 |
─┘ |
| 特 別 区(平成8年までは政令市を含む。) |
(正)
4頁
2 用語の解説及び使用上の注意
この報告書は患者調査の数値を用いている。
傷病分類
傷病の分類に当たっては、世界保健機関(WHO)の「国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD)」に基づき分類している。
このICDは医学の進展に伴い、約10年ごとに改訂が行われており、この報告書においては、昭和59年〜平成5年は「第9回修正国際疾病、傷害及び死因統計分類」(ICD-9)、平成8年〜14年は「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回修正」(ICD-10)による傷病分類を用いている。
この、第10回修正ICDにおいては、分類体系の大幅な変更などがあったため、ICD-9とICD-10において、傷病によっては年次比較できないものもある。(8頁参照)
傷病名
調査日現在(退院患者の場合は入院期間中)、医療施設(複数の診療科を有する場合は当該診療科)において主として治療または検査した病態をいう。
推計患者数
調査日当日に、病院、一般診療所、歯科診療所で受診した患者の推計数。
千人単位で表章している。(0.0は該当件数50未満をあらわす。)
数値は単位未満を四捨五入しているため、内訳の合計が総数と合わない場合もある。
受療率
推計患者数を人口で除して人口10万対であらわした数。
受療率(人口10万対)=推計患者数/推計人口×100,000
総患者数
調査日現在において、継続的に医療を受けている者(調査日には医療施設を受療していない者も含む。)の数を次の算式により推計したものである。
千人単位で表章している。(0は該当件数500未満をあらわす。)
総患者数=入院患者数+初診外来患者数+再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数(6/7)
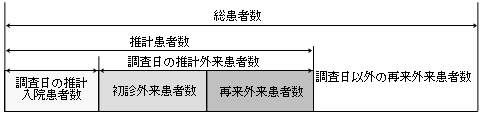
推計退院患者数
各調査年の9月1日〜30日に病院、一般診療所を退院した患者の推計数。
千人単位で表章している。(0.0は該当件数50未満をあらわす。)
施設の種類
| 病院 |
|
医師または歯科医師が医業または歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の収容施設を有するものをいう。
|
| 一般診療所 |
医師または歯科医師が医業または歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く。)であって、患者の収容施設を有しないものまたは患者19人以下の収容施設を有するものをいう。
|
| 歯科診療所 |
歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の収容施設を有しないものまたは患者19人以下の収容施設を有するものをいう。 |
紹介の有無
| 1 病院から |
|
病院の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。
|
| 2 一般診療所から |
一般診療所の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。
|
| 3 歯科診療所から |
歯科診療所の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。
|
| 4 介護老人保健施設から |
介護老人保健施設の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。
|
| 5 介護老人福祉施設から |
介護老人福祉施設の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。
|
| 6 その他から |
上記「1〜5」以外の場合をいう。(医師・歯科医師以外の紹介及び院内紹介はこれに含まれる。) |
救急の状況
| 1 救急車により搬送 |
|
当該医療施設に救急車で搬送され受診したものをいう。
|
| 2 救急外来を受診 |
当該医療施設の救急外来窓口を経由して受診したものをいう。
|
| 3 診療時間外の受診 |
当該医療施設が表示する診療時間以外に受診したものをいう。 |
病床の種別
|
精神病床 |
|
医療法第7条第2項に規定する精神病床。
|
老人性痴呆
疾患療養病棟 |
精神病床のうち、精神症状や問題行動を有し慢性期に至った老人性痴呆疾患(認知症)患者に対し長期的に治療を行う病棟で、「厚生労働大臣が定める施設基準」に適合しているものとして都道府県知事に届け出られたもの。
|
| 感染症病床 |
医療法第7条第2項に規定する感染症病床。
|
| 結核病床 |
医療法第7条第2項に規定する結核病床。
|
| 老人病床 |
医療法に定める「経過的旧その他の病床」のうち、「特例許可老人病床」または「特例許可以外の老人病床」。
|
療養病床
(療養型病床群を含む)
|
医療法第7条第2項に規定する「療養病床」および「経過的旧療養型病床群」。
|
| 一般病床 |
医療法に定める「一般病床」および「経過的旧その他の病床」(「経過的旧療養型病床群」および「老人病床」を除いたもの。)。
|
| 経過的旧その他の病床 |
旧医療法第7条第2項に規定する「その他の病床」であって、「医療法等の一部を改正する法律」の施行後、「療養病床」または「一般病床」のいずれかに移行する届出をしていない病床(平成15年8月までの経過措置)。
|
| 経過的旧療養型病床群 |
「経過的旧その他の病床」のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための一群の病床(平成15年8月までの経過措置)。 |
入院の状況
| 1 |
|
生命の危険は少ないが入院治療、手術を要する
|
|
退院が決定している患者を含む。
|
| 2 |
生命の危険がある |
生命の危険がある重篤な患者をいう。
|
| 3 |
受け入れ条件が整えば退院可能 |
退院は決まってないが退院可能な状態にある患者をいう。
|
| 4 |
検査入院 |
検査のために入院した患者をいい、健康な者に対する一般的検査のための入院患者も含む。
|
| 5 |
その他 |
上記「1〜4」以外の場合をいう。 |
心身の状況
自分でできる能力があるかではなく、調査日当日の状況で把握されたもの。
老人性痴呆疾患療養病棟、療養病床(療養型病床群を含む)、老人病床の患者のみ調査項目とした。
(一般診療所については、療養病床の患者のみ調査項目とした。)
(1) 移乗
| 1 |
自立 |
|
這って動いても、移乗が自分でできる場合も含まれる。 |
| 2 |
見守りが必要
(介護側の指示を含む) |
直接介助する必要はないが、事故等がないように常時または時々見守る場合、移乗の際そばにいて確認する場合等をいう。 |
| 3 |
一部介助が必要 |
自分では移乗はできないが、介護者が手を添える、運ぶ等の介助によって移乗ができる場合をいう。 |
| 4 |
全介助が必要 |
自分では移乗が全くできないために、介助者が抱える、運ぶ等の介助によって移乗ができる場合をいう。 |
(2) 食事摂取
| 1 |
自立 |
|
介助や見守りなしで食事をしている場合をいう。 |
| 2 |
見守りが必要
(介護側の指示を含む) |
介助なしに食事をしているが、見守りや指示が必要な場合をいう。 |
| 3 |
一部介助が必要 |
食事の際に(食卓で)、小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等、食べやすくするために何らかの介助が必要な場合をいう。 |
| 4 |
全介助が必要 |
自立して食事をしていない、スプーンフィーディング(食べ物を口に運んで食べさせる)、中心静脈栄養(IVH)、胃瘻や経管栄養の場合も含まれる。 |
(3) 嚥下
| 1 |
できる |
|
常時、自然に飲み込める場合をいう。 |
| 2 |
見守りが必要
(介護側の指示を含む) |
飲み込む際に見守りや声かけが必要な場合をいう。 |
| 3 |
できない |
常時、飲み込むことができない場合をいう。
中心静脈栄養(IVH)、胃瘻や経管栄養の場合も含まれる。 |
(4) 排便の後始末
| 1 |
自立 |
|
自分1人で排便後の後始末ができる場合をいう。 |
| 2 |
見守りが必要
(介護側の指示を含む) |
介護者が紙の用意をしたり、排便後にトイレを汚した時に便器まわりの掃除をする等の間接的援助が必要である場合をいう。 |
| 3 |
一部介助が必要 |
排便後に身体の汚れたところを介護者に拭いてもらう、自分でも拭くが不十分なため介護者がきれいにしなければならない等の直接的援助が必要な場合をいう。 |
| 4 |
全介助が必要 |
オムツ等を使用している場合や、身体の汚れた部分を拭くことを含め、排便にかかわるすべての動作を介護者が行う必要がある場合をいう。 |
|
表章記号の規約
| 計数のない場合 | − |
| 計数不明または計数を表章することが不適当な場合 |
… |
| 統計項目のあり得ない場合 | ・ |
|
|
○傷病分類の年次比較について
昭和59年〜平成5年と平成8年〜14年調査の結果の比較を行う場合、平成5年以前のデータをICD-10のコードを用いて同じ分類で比較する必要がある。
しかし、平成5年以前の傷病分類別データはICD-9の傷病コードに変換したものしか存在しないため、ICD-9コードをICD-10コードへ変換しなければならない。
その場合、次のような問題が生じる。
| (例) |
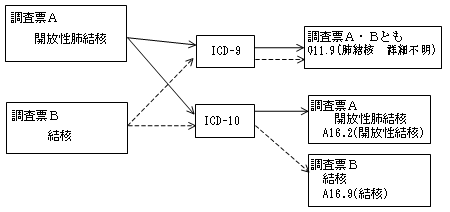 |
上記の例は、調査票に記載されている傷病名は異なるが、ICD-9を用いてコード付けすると同じ傷病コード(011.9)が付くが、ICD-10では、(A16.2)と(A16.9)と別々の傷病コードが付くことを示している。
このような場合、ICD-9コード(011.9)だけに着目すると、A16.2とA16.9のどちらのコードに変換すべきか判断できないため、事実上コード変換は不可能であり、年次比較はできないことになる。
これに該当する傷病は12頁以降の「傷病別年次推移の目次」で一覧できるようになっており、21頁以降の「傷病別年次推移表」では傷病名の左側に「×」を付してあるので注意して利用されたい。
|
(誤)
3頁
1 患者調査の概要
調査の目的及び沿革
この調査は、病院及び診療所を利用する患者について、その傷病状況等の実態を明らかにし、医療行政の基礎資
料を得ることを目的とする。
その前身は昭和23年11月に1週間にわたって実施された「施設面からみた医療調査」である。その後、おおむね
毎年調査が実施され、昭和28年には統計法に基づく指定統計第66号「患者調査」となった。
患者調査は、患者の診療録の内容に基づく1日調査として毎年実施されたが、昭和59年からは、調査内容を充実
し地域別表章が可能となるよう客体数を拡大し、3年周期で実施することとなった。
調査設計の推移
| |
昭和59年 |
昭和62年 |
平成2年 |
平成5年 |
平成8年 |
平成11年 |
平成14年 |
| 調査対象施設数 |
6,053 |
9,941 |
12,054 |
13,732 |
13,519 |
13,348 |
13,763 |
| |
病院 |
|
2,377 |
3,080 |
5,086 |
6,865 |
6,649 |
6,463 |
6,452 |
| 入院 |
… |
… |
… |
… |
6,649 |
6,463 |
6,452 |
| 外来 |
… |
… |
… |
… |
3,172 |
3,076 |
3,076 |
| 一般診療所 |
2,905 |
5,875 |
5,973 |
5,884 |
5,879 |
5,902 |
6,037 |
| 歯科診療所 |
771 |
986 |
995 |
983 |
991 |
983 |
1,274 |
| |
|
| 客体数(万人) |
|
| |
病院 |
入院・外来 |
67.5 |
95.4 |
131.4 |
235.3 |
179.5 |
203.8 |
197.3 |
| 退院 |
17.5 |
24.0 |
25.5 |
58.5 |
63.5 |
78.7 |
82.8 |
| 一般診療所 |
入院・外来 |
15.9 |
30.7 |
30.0 |
29.1 |
29.1 |
26.0 |
24.2 |
| 退院 |
0.9 |
1.5 |
1.3 |
1.4 |
1.3 |
1.3 |
1.0 |
| 歯科診療所 |
外来 |
2.1 |
2.7 |
2.5 |
2.3 |
2.2 |
1.9 |
2.3 |
| |
|
| 傷病分類(※) |
ICD9 |
ICD9 |
ICD9 |
ICD9 |
ICD10 |
ICD10 |
ICD10 |
| |
|
| 抽出率 |
病院 |
入院 |
2.5/10 |
3/10 |
5/10 |
7/10 |
7/10 |
7/10 |
7/10 |
| 外来 |
2.5/10 |
3/10 |
3.3/10 |
7/10 |
3.3/10 |
3.3/10 |
3.3/10 |
| 一般診療所 |
4/100 |
7.5/100 |
7.5/100 |
7.5/100 |
7.5/100 |
7/100 |
7/100 |
| 歯科診療所 |
2/100 |
2/100 |
2/100 |
2/100 |
2/100 |
1.6/100 |
2/100 |
| |
|
| 表章可能区分 |
病院 |
入院 |
都道府県 |
都道府県 |
二次医療圏 |
二次医療圏 |
二次医療圏 |
二次医療圏 |
二次医療圏 |
| 外来 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
二次医療圏 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
| 一般診療所 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
| 歯科診療所 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
| (退院票)病院 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
二次医療圏 |
二次医療圏 |
二次医療圏 |
| (退院票)一般診療所 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
都道府県 |
※ 世界保健機関の「国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD)」に基づき分類。
調査の期日
調査各年の10月上旬の3日間(火〜木)のうち医療施設ごとに指定した1日とした。
なお、退院患者については、調査各年の9月1〜30日までの1か月間とした。
調査の方法
医療施設の管理者が記入する方式によった。
調査の系統
| 厚生労働省 |
|
── |
|
都道府県 |
|
────── |
|
保健所 |
|
── |
|
医療施設 |
| └── |
保健所設置市 |
─┘ |
| 特 別 区(平成8年までは政令市を含む。) |
(誤)
4頁
2 用語の解説及び使用上の注意
この報告書は患者調査の数値を用いている。
傷病分類
傷病の分類に当たっては、世界保健機関(WHO)の「国際疾病、傷害および死因統計分類(ICD)」に基づき分類している。
このICDは医学の進展に伴い、約10年ごとに改訂が行われており、この報告書においては、昭和59年〜平成5年は「第9回修正国際疾病、傷害及び死因統計分類」(ICD-9)、平成8年〜14年は「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回修正」(ICD-10)による傷病分類を用いている。
この、第10回修正ICDにおいては、分類体系の大幅な変更などがあったため、ICD-9とICD-10において、傷病によっては年次比較できないものもある。(8頁参照)
傷病名
調査日現在(退院患者の場合は入院期間中)、医療施設(複数の診療科を有する場合は当該診療科)において主として治療または検査した病態をいう。
推計患者数
調査日当日に、病院、一般診療所、歯科診療所で受診した患者の推計数。
千人単位で表章している。(0.0は該当件数50未満をあらわす。)
数値は単位未満を四捨五入しているため、内訳の合計が総数と合わない場合もある。
受療率
推計患者数を人口で除して人口10万対であらわした数。
受療率(人口10万対)=推計患者数/推計人口×100,000
総患者数
調査日現在において、継続的に医療を受けている者(調査日には医療施設を受療していない者も含む。)の数を次の算式により推計したものである。
千人単位で表章している。(0は該当件数500未満をあらわす。)
総患者数=入院患者数+初診外来患者数+再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数(6/7)
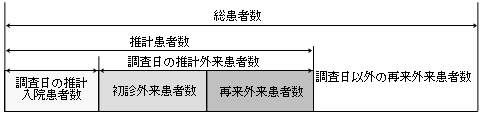
推計退院患者数
各調査年の9月1日〜30日に病院、一般診療所を退院した患者の推計数。
千人単位で表章している。(0.0は該当件数50未満をあらわす。)
施設の種類
| 病院 |
|
医師または歯科医師が医業または歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の収容施設を有するものをいう。
|
| 一般診療所 |
医師または歯科医師が医業または歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く。)であって、患者の収容施設を有しないものまたは患者19人以下の収容施設を有するものをいう。
|
| 歯科診療所 |
歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の収容施設を有しないものまたは患者19人以下の収容施設を有するものをいう。 |
紹介の有無
| 1 病院から |
|
病院の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。
|
| 2 一般診療所から |
一般診療所の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。
|
| 3 歯科診療所から |
歯科診療所の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。
|
| 4 介護老人保健施設から |
介護老人保健施設の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。
|
| 5 介護老人福祉施設から |
介護老人福祉施設の医師・歯科医師の紹介によるものをいう。
|
| 6 その他から |
上記「1〜5」以外の場合をいう。(医師・歯科医師以外の紹介及び院内紹介はこれに含まれる。) |
救急の状況
| 1 救急車により搬送 |
|
当該医療施設に救急車で搬送され受診したものをいう。
|
| 2 救急外来を受診 |
当該医療施設の救急外来窓口を経由して受診したものをいう。
|
| 3 診療時間外の受診 |
当該医療施設が表示する診療時間以外に受診したものをいう。 |
病床の種別
|
精神病床 |
|
医療法第7条第2項に規定する精神病床。
|
老人性痴呆
疾患療養病棟 |
精神病床のうち、精神症状や問題行動を有し慢性期に至った老人性痴呆疾患(認知症)患者に対し長期的に治療を行う病棟で、「厚生労働大臣が定める施設基準」に適合しているものとして都道府県知事に届け出られたもの。
|
| 感染症病床 |
医療法第7条第2項に規定する感染症病床。
|
| 結核病床 |
医療法第7条第2項に規定する結核病床。
|
| 老人病床 |
医療法に定める「経過的旧その他の病床」のうち、「特例許可老人病床」または「特例許可以外の老人病床」。
|
療養病床
(療養型病床群を含む)
|
医療法第7条第2項に規定する「療養病床」および「経過的旧療養型病床群」。
|
| 一般病床 |
医療法に定める「一般病床」および「経過的旧その他の病床」(「経過的旧療養型病床群」および「老人病床」を除いたもの。)。
|
| 経過的旧その他の病床 |
旧医療法第7条第2項に規定する「その他の病床」であって、「医療法等の一部を改正する法律」の施行後、「療養病床」または「一般病床」のいずれかに移行する届出をしていない病床(平成15年8月までの経過措置)。
|
| 経過的旧療養型病床群 |
「経過的旧その他の病床」のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための一群の病床(平成15年8月までの経過措置)。 |
入院の状況
| 1 |
|
生命の危険は少ないが入院治療、手術を要する
|
|
退院が決定している患者を含む。
|
| 2 |
生命の危険がある |
生命の危険がある重篤な患者をいう。
|
| 3 |
受け入れ条件が整えば退院可能 |
退院は決まってないが退院可能な状態にある患者をいう。
|
| 4 |
検査入院 |
検査のために入院した患者をいい、健康な者に対する一般的検査のための入院患者も含む。
|
| 5 |
その他 |
上記「1〜4」以外の場合をいう。 |
心身の状況
自分でできる能力があるかではなく、調査日当日の状況で把握されたもの。
老人性痴呆疾患療養病棟、療養病床(療養型病床群を含む)、老人病床の患者のみ調査項目とした。
(一般診療所については、療養病床の患者のみ調査項目とした。)
(1) 移乗
| 1 |
自立 |
|
這って動いても、移乗が自分でできる場合も含まれる。 |
| 2 |
見守りが必要
(介護側の指示を含む) |
直接介助する必要はないが、事故等がないように常時または時々見守る場合、移乗の際そばにいて確認する場合等をいう。 |
| 3 |
一部介助が必要 |
自分では移乗はできないが、介護者が手を添える、運ぶ等の介助によって移乗ができる場合をいう。 |
| 4 |
全介助が必要 |
自分では移乗が全くできないために、介助者が抱える、運ぶ等の介助によって移乗ができる場合をいう。 |
(2) 食事摂取
| 1 |
自立 |
|
介助や見守りなしで食事をしている場合をいう。 |
| 2 |
見守りが必要
(介護側の指示を含む) |
介助なしに食事をしているが、見守りや指示が必要な場合をいう。 |
| 3 |
一部介助が必要 |
食事の際に(食卓で)、小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等、食べやすくするために何らかの介助が必要な場合をいう。 |
| 4 |
全介助が必要 |
自立して食事をしていない、スプーンフィーディング(食べ物を口に運んで食べさせる)、中心静脈栄養(IVH)、胃瘻や経管栄養の場合も含まれる。 |
(3) 嚥下
| 1 |
できる |
|
常時、自然に飲み込める場合をいう。 |
| 2 |
見守りが必要
(介護側の指示を含む) |
飲み込む際に見守りや声かけが必要な場合をいう。 |
| 3 |
できない |
常時、飲み込むことができない場合をいう。
中心静脈栄養(IVH)、胃瘻や経管栄養の場合も含まれる。 |
(4) 排便の後始末
| 1 |
自立 |
|
自分1人で排便後の後始末ができる場合をいう。 |
| 2 |
見守りが必要
(介護側の指示を含む) |
介護者が紙の用意をしたり、排便後にトイレを汚した時に便器まわりの掃除をする等の間接的援助が必要である場合をいう。 |
| 3 |
一部介助が必要 |
排便後に身体の汚れたところを介護者に拭いてもらう、自分でも拭くが不十分なため介護者がきれいにしなければならない等の直接的援助が必要な場合をいう。 |
| 4 |
全介助が必要 |
オムツ等を使用している場合や、身体の汚れた部分を拭くことを含め、排便にかかわるすべての動作を介護者が行う必要がある場合をいう。 |
|
表章記号の規約
| 計数のない場合 | − |
| 計数不明または係数を表章することが不適当な場合 |
… |
| 統計項目のあり得ない場合 | ・ |
|
|
○傷病分類の年次比較について
昭和59年〜平成5年と平成8年〜14年調査の結果の比較を行う場合、平成5年以前のデータをICD-10のコードを用いて同じ分類で比較する必要がある。
しかし、平成5年以前の傷病分類別データはICD-9の傷病コードに変換したものしか存在しないため、ICD-9コードをICD-10コードへ変換しなければならない。
その場合、次のような問題が生じる。
| (例) |
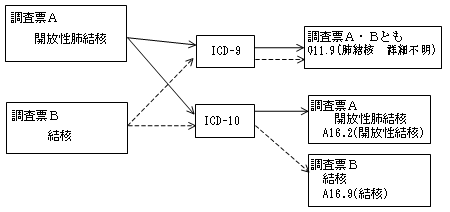 |
上記の例は、調査票に記載されている傷病名は異なるが、ICD-9を用いてコード付けすると同じ傷病コード(011.9)が付くが、ICD-10では、(A16.2)と(A16.9)と別々の傷病コードが付くことを示している。
このような場合、ICD-9コード(011.9)だけに着目すると、A16.2とA16.9のどちらのコードに変換すべきか判断できないため、事実上コード変換は不可能であり、年次比較はできないことになる。
これに該当する傷病は12頁以降の「傷病別年次推移の目次」で一覧できるようになっており、21頁以降の「傷病別年次推移表」では傷病名の左側に「×」を付してあるので注意して利用されたい。
|