| 厚生労働省発表 平成18年6月 |
|
労働経済動向調査(平成18年5月)結果の概況
| I | 調査の概要 この調査は、生産、販売活動及びそれに伴う雇用、労働時間などの現状と今後の短期的見通しなどを把握するため、日本標準産業分類の建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業及びサービス業(他に分類されないもの)に属する事業所規模30人以上の全国の民営事業所5,408事業所を対象として、年4回実施(通信調査方式)しているもので、本概況は平成18年5月1日現在の調査結果である(回答事業所数2,732、回答率50.5%)。 |
| II | 結果の要旨 |
| 1 | 生産・売上、所定外労働時間、雇用 |
| (1) | 生産・売上《三産業の実績でプラス》 生産・売上判断D.I.(平成18年1〜3月期実績)は、製造業で9ポイント、卸売・小売業で7ポイント、サービス業ではプラスに転じ4ポイントとなり、三産業でプラスとなった。先行きは、18年4〜6月期実績見込は製造業、卸売・小売業でプラス、サービス業でマイナス、18年7〜9月期見込では、三産業でプラスとなっている。(表1、第1図) |
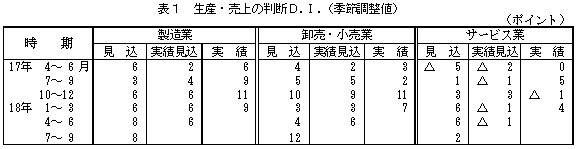
| (2) | 所定外労働時間《三産業の実績でプラス》 所定外労働時間判断D.I.(18年1〜3月期実績)は、製造業で6ポイント、卸売・小売業で4ポイント、サービス業で2ポイントとなり、三産業でプラスとなっている。先行きは、18年4〜6月期実績見込は製造業で0ポイント、卸売・小売業、サービス業でマイナス、18年7〜9月期見込は製造業、卸売・小売業でプラス、サービス業で0ポイントとなっている。(表2、第2図) |
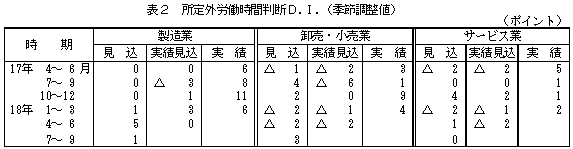
| (3) | 常用雇用《製造業の実績でプラス幅が拡大、サービス業でプラスに転じた》 常用雇用判断D.I.(18年1〜3月期実績)は、製造業で7ポイント、卸売・小売業でマイナス5ポイント、サービス業で1ポイントとなり、製造業でプラス幅が拡大し、卸売・小売業でマイナス幅が縮小し、サービス業でプラスに転じた。先行きは、18年4〜6月期実績見込、18年7〜9月期見込とも三産業でプラスとなっている。(表3、第3図) |
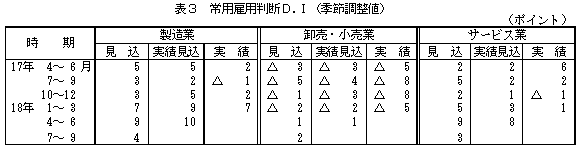
| (4) | パートタイム雇用《製造業の実績でプラスに転じ、サービス業でプラス幅やや拡大》 パートタイム雇用判断D.I.(18年1〜3月期実績)は、製造業で3ポイント、卸売・小売業でマイナス1ポイント、サービス業で2ポイントとなり、製造業でプラスに転じ、サービス業でプラス幅がやや拡大した。先行きは、18年4〜6月期実績見込で、製造業、サービス業でプラス、卸売・小売業でマイナス、18年7〜9月期見込は製造業で0ポイント、卸売・小売業でプラス、サービス業でマイナスとなっている。(表4、第4図) |
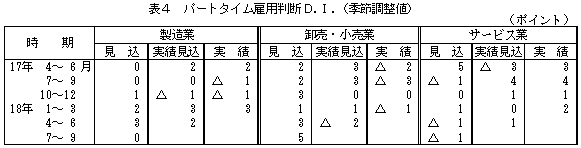
- 付属統計表 第1表
| 2 | 労働者の過不足状況 |
| (1) | 常用労働者《不足感続く》 5月現在の常用労働者過不足判断D.I.により、雇用過不足感の動向をみると、調査産業計で21ポイントとなり前期より不足感、不足超過幅ともにやや縮小したものの、依然として不足超過幅が大きい。 産業別にみると、運輸業、卸売・小売業、不動産業、飲食店,宿泊業で不足超過幅が前期より拡大している。(表5、第5図) |
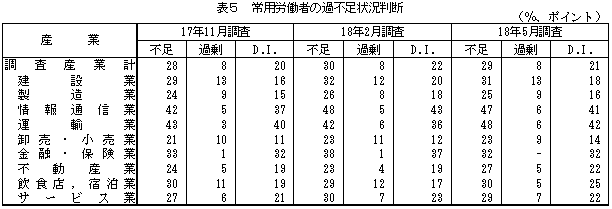
| (2) | パートタイム労働者《不足超過幅がやや拡大》 5月現在のパートタイム労働者過不足判断D.I.により、雇用過不足感の動向をみると、調査産業計では23ポイントの不足超過で超過幅は前期(22ポイント)よりもやや拡大している。 産業別にみると、製造業、情報通信業、運輸業、飲食店,宿泊業、サービス業で不足超過幅が前期に比べ拡大し、特に飲食店,宿泊業で不足超過幅が大きい。(表6、第5図) |
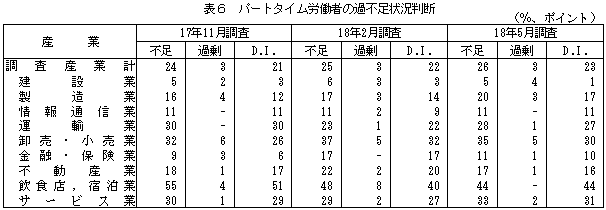
| 3 | 雇用調整 |
| (1) | 実施割合 雇用調整を実施した事業所の割合(18年1〜3月期実績)は、調査産業計で12%と前期(11%)と比べるとやや高くなっている(表7、第7図)。 |
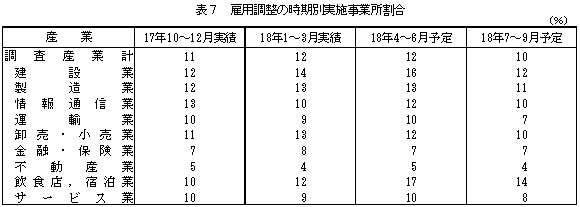
| (2) | 実施方法 雇用調整の実施方法は、調査産業計では残業規制(5%)の割合が高く、次いで配置転換(4%)の順となっている(表8、第8図)。 |
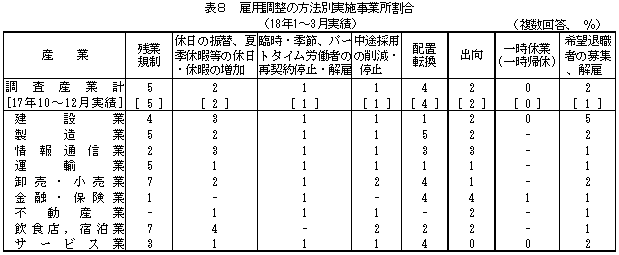
- 付属統計表 第4表
| 4 | 中途採用《上昇している》 「中途採用あり」とした事業所割合(18年1〜3月期実績)は、調査産業計で56%と前年同期(17年1〜3月期実績)と比べると上昇している。産業別にみると、運輸業及び不動産業を除いて上昇しており、特に飲食店,宿泊業での上昇幅が大きい。(表9) |
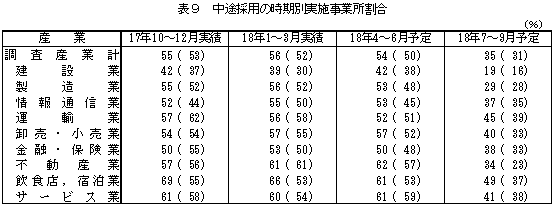
|
- 付属統計表 第5表
| 5 | 平成19年新規学卒者の採用計画等 |
| (1) | 採用計画《増加事業所割合がすべての学歴で前年を上回る》 平成19年新規学卒者の採用予定者数を18年の採用者数と比べると、増加事業所割合がすべての学歴で前年を上回っている(表10、第9図)。 |
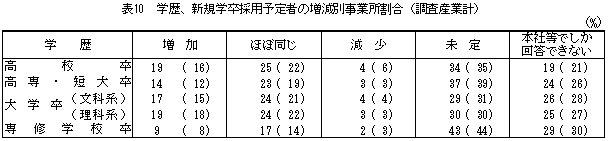
| 注:1) | ( )は前年5月調査の数値である。 |
| 2) | 数値は「平成18年、19年ともに採用しない」事業所を除いた集計事業所に対する割合である。 |
| 3) | 大学卒(文科系及び理科系)には大学院卒を含む(以下同じ)。 |
| (2) | 採用予定者の増加理由 平成19年新規学卒者の採用予定者数を「増加」とする理由(複数回答)を学歴別にみると、高校卒、高専・短大卒で「年齢等人員構成の適正化」、大学卒(文科系)、専修学校卒で「経営状態の好転・既存事業の拡大」、大学卒(理科系)で「技術革新への対応・研究開発体制の充実」の割合が最も高くなっている(表11)。 |
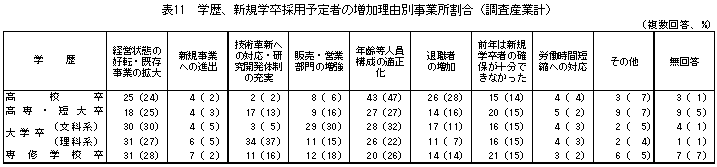
|
- 付属統計表 第6表
主な用語の説明
| 〔労働者〕 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 〔職種〕 |
|
| (注)1 | この調査で「サービス業」とは、「サービス業(他に分類されないもの)」を指している。 |
| 1 | 「生産・売上判断D.I.」、「所定外労働時間判断D.I.」及び「雇用判断D.I.」とは、前期と比べて増加と回答した事業所の割合から減少と回答した事業所の割合を差し引いた値である。 |
| 3 | 上記判断D.I.の季節調整は、センサス局法X-12-ARIMAのなかのX-11デフォルトによる。また、今回、発表の季節調整値は平成18年2月調査までの結果に基づき過去に遡って改訂したので前回発表の数値と異なっている部分がある。 |
| 4 | 「労働者過不足判断D.I.」とは、不足と回答した事業所の割合から過剰と回答した事業所の割合を差し引いた値である。 |
| 5 | 統計表に用いている数値は、「0」は単位未満の割合を示し、「−」は調査客体がないものを示す。 |
| 6 | 調査の結果は、厚生労働省のwebページ(https://www.mhlw.go.jp/)に掲載されている。 「統計調査結果」→「最近公表の統計資料」→「月報で公表・提供しているもの」→「労働経済動向調査(平成18年5月)結果の概況」 |