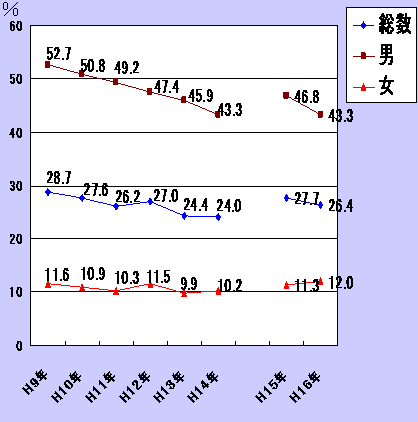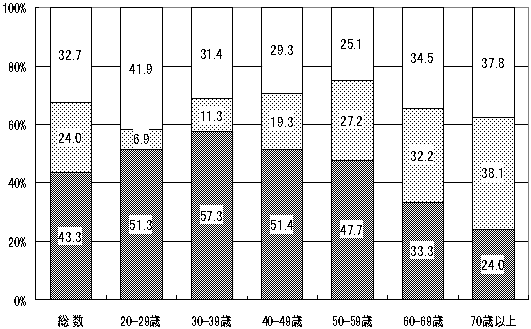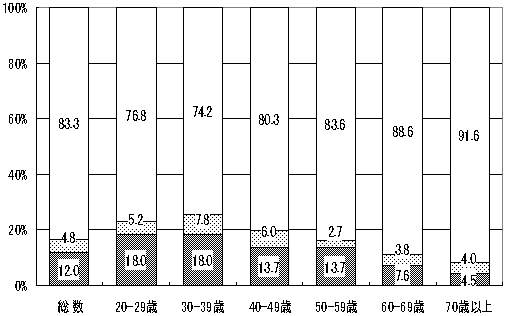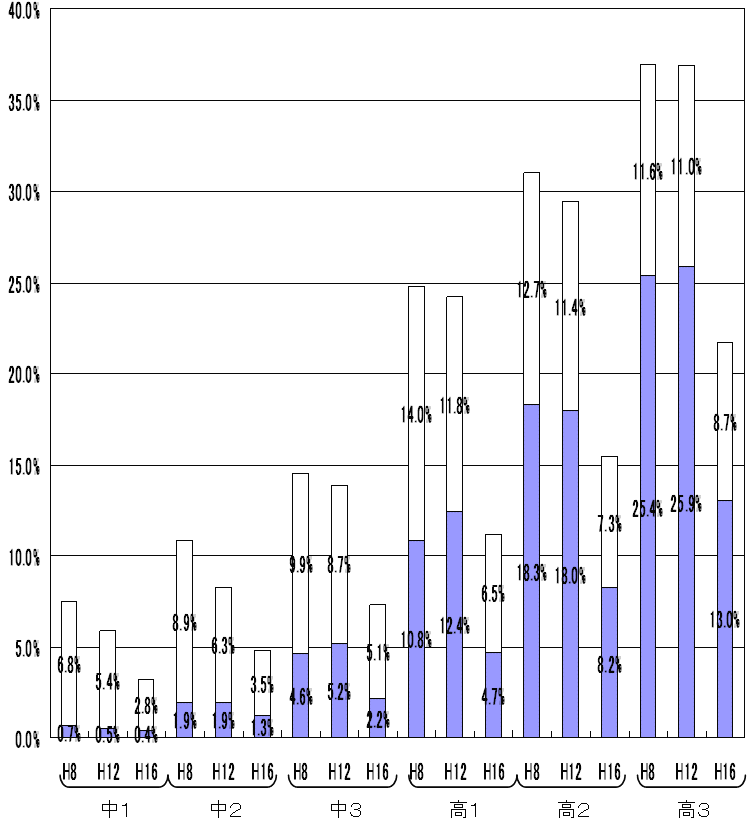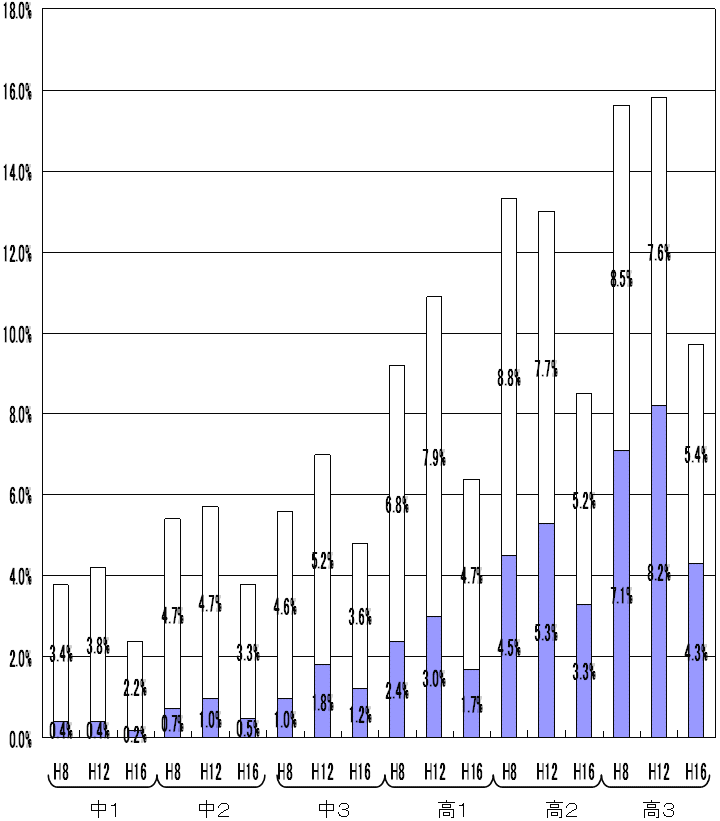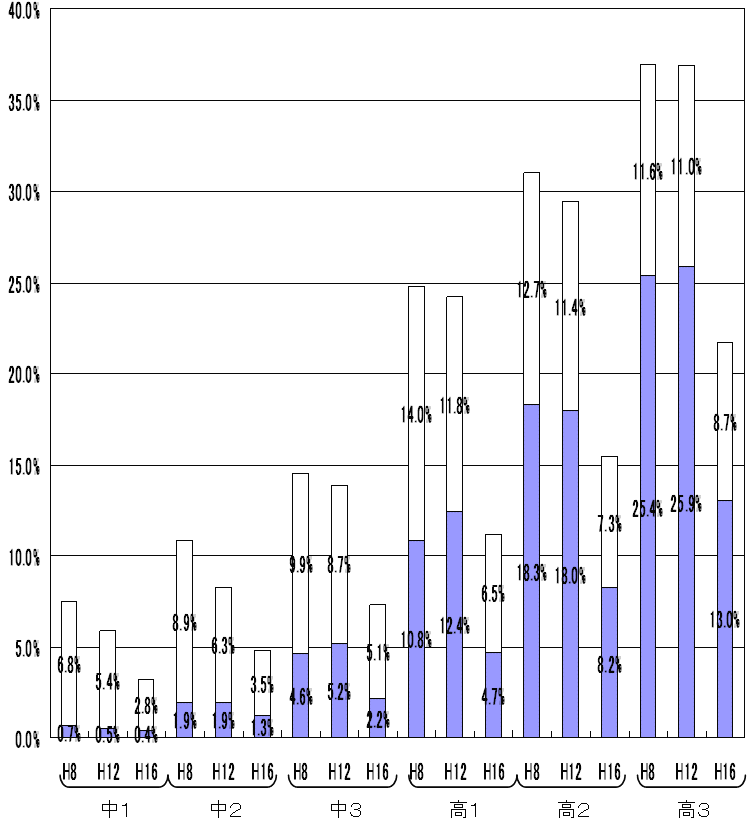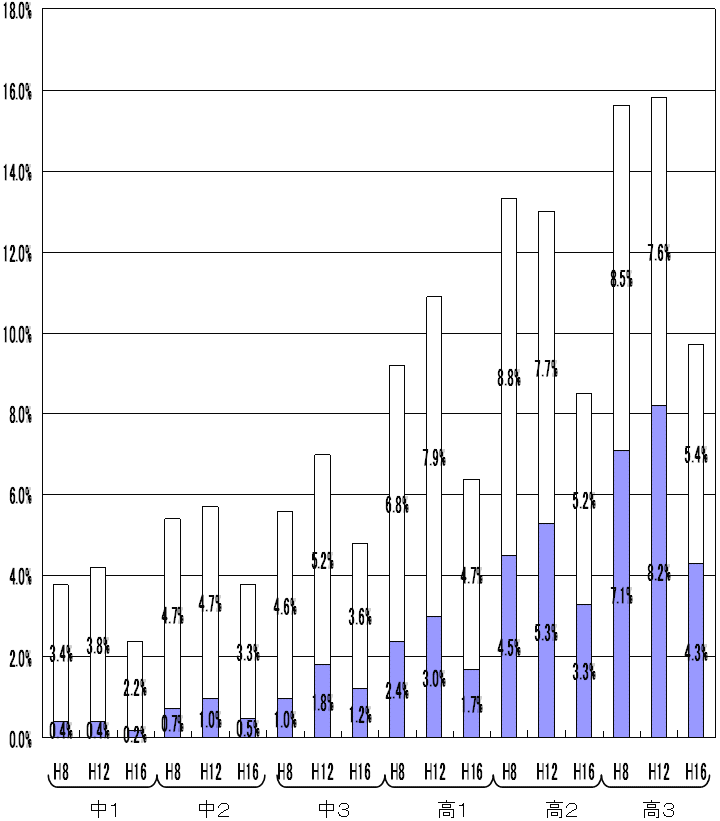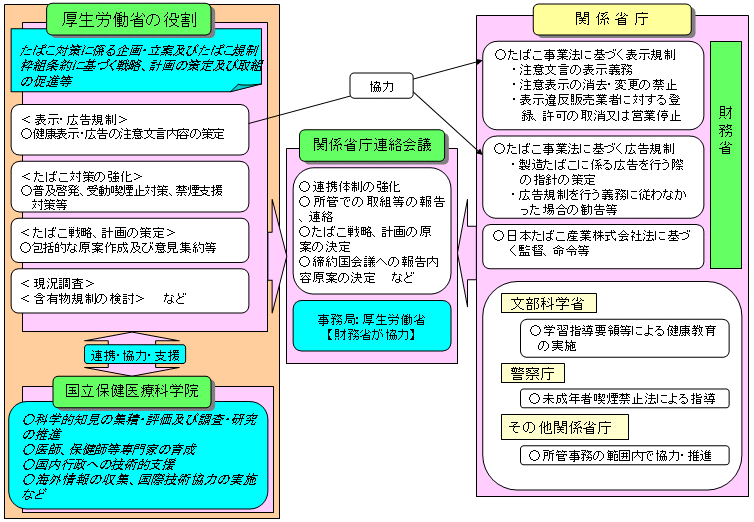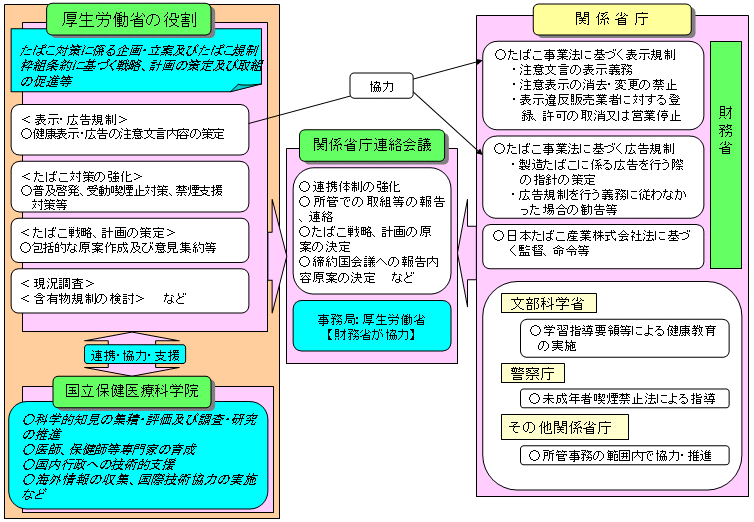たばこ規制枠組条約と
今後のたばこ対策
厚生労働省
喫煙率の状況について
我が国の喫煙率
| 出典: |
平成14年までは国民栄養調査。平成15年は国民健康・栄養調査
| ※ |
国民栄養調査と国民健康・栄養調査では、喫煙の定義及び調査方法が異なるため、その単純比較は困難である。 |
|
諸外国の喫煙率
(%)
| 国名 |
男性 |
女性 |
| 日本 |
43.3 |
10.2 |
| ドイツ |
39.0 |
31.0 |
| フランス |
38.6 |
30.3 |
| オランダ |
37.0 |
29.0 |
| イタリア |
32.4 |
17.3 |
| イギリス |
27.0 |
26.0 |
| カナダ |
27.0 |
23.0 |
| 米国 |
25.7 |
21.5 |
| オーストラリア |
21.1 |
18.0 |
| スウェーデン |
19.0 |
19.0 |
|
| 出典: |
WHO Tobacco ATLAS (2002)
(日本の数値は国民栄養調査) |
| 1. |
たばこに関する情報提供について
|
| 2. |
未成年者の喫煙防止対策について
|
| 3. |
受動喫煙からの非喫煙者の保護について
|
| 4. |
禁煙を希望する者に対する禁煙支援について
|
| 5. |
たばこ対策に係る研究等について |
| |
世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」と定め、シンポジウムの開催やポスターの配布等により普及啓発を行っている。 |
| |
ホームページを活用して、たばこに関する情報を国民に提供している。 |
| |
「健康日本21」の策定を踏まえ、専門家による検討を行い、たばこと健康問題に関する最新の科学的知見を集積した報告書が取りまとめられた。(平成13年12月) |
| |
平成15年11月たばこ事業法施行規則を改正し、JT及び特定販売業者が17年7月以降出荷する全てのたばこ製品について新たな8種類の注意文言の表示を義務付けた。
(たばこ包装の主要な面の面積の30%以上) |
| |
平成15年3月たばこ事業法第40条に基づく「製造たばこに係る広告を行う際の指針」を改正し、たばこ広告の規制を強化した。 |
| |
未成年者の喫煙禁止、未成年者にたばこを販売した者に対する罰則等を規定している。 |
| |
喫煙している未成年者に対する補導や、未成年者やその保護者に対する広報啓発活動を推進している。 |
| |
未成年の段階から喫煙をしないという態度を育てることを目的として、保健体育など学校教育全体を通じて、喫煙防止に関する指導を行っている。 |
| |
平成16年10月「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」を改正し、自動販売機の設置場所の店舗併設の取扱を明確化した。(平成16年12月1日以降の申請から適用)
| (例) |
特定販売業(劇場、旅館など閉鎖性のある店舗での販売)の許可に当たっては、施設の従業員や管理者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所に設置する場合には許可しない。 |
|
| 未成年者喫煙防止のための適切なたばこの販売方法の取組みについて |
| |
年齢確認の徹底、たばこ自動販売機の適正な管理の徹底等、未成年者喫煙防止のための適切なたばこの販売について、警察庁、財務省及び厚生労働省より関係業界宛に通知を発出。(平成16年6月28日3省庁局長連名通知)
|
<参考>成人識別機能付たばこ自動販売機の設置
日本たばこ協会、日本自動販売機工業会及び全国たばこ販売協同組合連合会が、平成20年からの全国一斉稼働を目指し、現在、試験を実施している。 |
| |
関係府省庁(内閣府、警察庁、財務省、文部科学省、厚生労働省)の密接な連携の下、未成年者の喫煙防止対策を促進するため、たばこ対策関係省庁連絡会議幹事会の下に設置し、(1)未成年者への喫煙防止教育、(2)たばこの入手方法に応じた喫煙防止、(3)喫煙習慣者への禁煙指導等について検討を行っている。 |
| |
都道府県における、未成年者や子どもへの影響の大きい父母等に対する喫煙防止対策に取り組むこと等に重点をおいた施策を支援し、地域におけるたばこ対策の推進を図ることとしている。 |
未成年者の喫煙について
男子中学生、高校生喫煙率比較(平成8年、12年、16年)
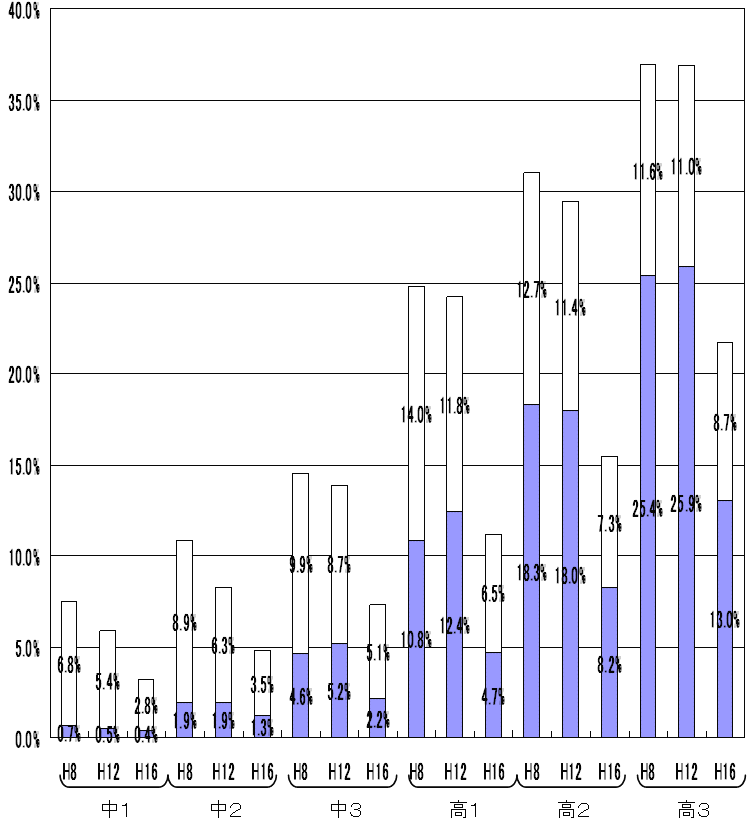 女子中学生、高校生喫煙率比較(平成8年、12年、16年)
女子中学生、高校生喫煙率比較(平成8年、12年、16年)
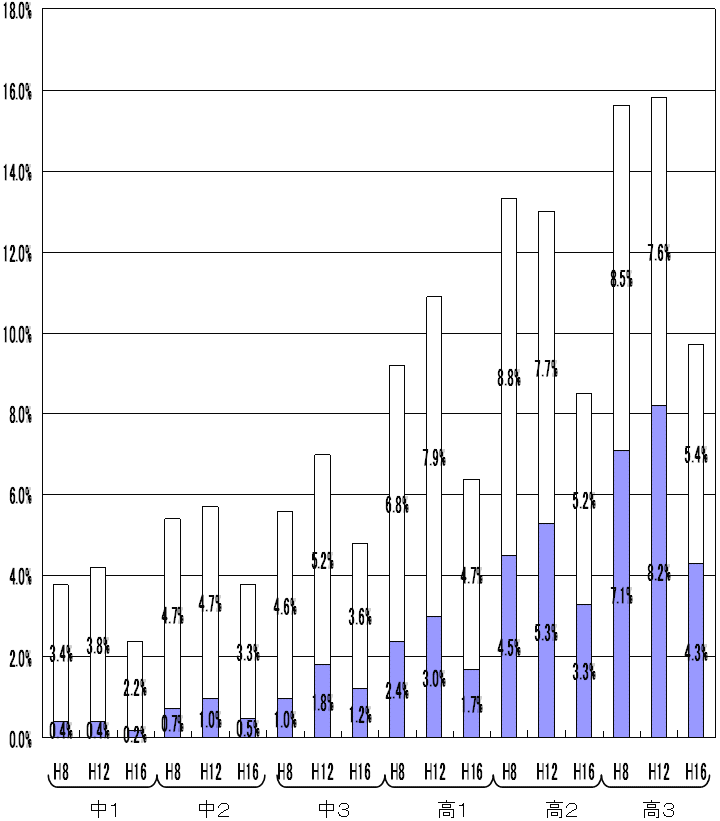
 |
月喫煙者(この30日間に1日でも喫煙した者) |
 |
毎日喫煙者(この30日間に毎日喫煙した者) |
| 出典: |
厚生労働科学研究費補助金健康科学総合研究費業「未成年者の喫煙実態状況に関する調査研究」等 |
| |
健康増進法の施行に併せ、適切な受動喫煙防止対策を推進するよう都道府県等に対して、通知を発出。(平成15年4月30日健康局長通知)
関係省庁においても、職場や学校等における受動喫煙防止対策に努めるよう関係方面への周知を行った。 |
| |
労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図る観点から、喫煙対策の充実を図ることとし、新ガイドラインを策定し、これに沿った喫煙対策の円滑な実施に向け、事業場に対し、個別支援(指導)、研修会、シンポジウム等の普及啓発を行っている。 |
| |
都道府県における、受動喫煙防止対策が遅れている施設等を対象とした禁煙・分煙指導の強化を図ること等に重点をおいた施策を支援し、地域におけるたばこ対策の推進を図ることとしている。 |
| |
地方自治体のたばこ対策担当者並びに医療保険者の保健事業実施担当者及び労働安全衛生法における安全衛生担当者を対象に、効果的なたばこ対策の推進に必要な最新の動向や知識の習得を図るために講習会を実施している。 |
| |
すべての市町村で禁煙支援が実施され、地域での保健指導や禁煙指導の充実を図るために、必要な基礎知識、指導方法等について、まとめた禁煙支援マニュアルを作成したところ。今後、地方公共団体、医療関係者等に対し、その普及を図り、禁煙支援を推進する。 |
| 平成18年度診療報酬改定におけるニコチン依存症管理料の新設 |
| |
ニコチン依存症について、疾病であるとの位置付けが確立されたことを踏まえ、ニコチン依存症と診断された患者のうち禁煙の希望がある者に対する一定期間の禁煙指導について、新たに診療報酬上の評価を行う。
ニコチン依存症の管理に伴う場合、禁煙補助剤(ニコチンパッチ)を診療報酬の対象とする。
ニコチン依存症管理料
| ・ |
「禁煙治療のための標準手順書」に沿って外来で禁煙治療 |
| ・ |
12週間にわたり計5回 |
| ・ |
対象患者
| ・ |
スクリーニングテストでニコチン依存症と診断 |
| ・ |
1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じた数が200以上 |
| ・ |
直ちに禁煙していることを希望し、文書により同意 |
|
ニコチン依存症管理料に関する施設基準
| ・ |
禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること |
| ・ |
呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること |
| ・ |
医療機関の敷地内が禁煙であること |
|
| |
国内外の喫煙の実態、喫煙の習慣の改善に関する研究、未成年者の喫煙防止に関する研究等、健康影響と喫煙対策の動向に関する研究を実施している。 |
| |
厚生労働省において、たばこ対策専門官を設置したほか、国立保健医療科学院の研究情報センターにたばこ政策情報室を設け、たばこに関する情報政策の収集に努めている。 |
| |
たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の内容を踏まえ、関係省庁の密接な連携の下にたばこ対策を推進するため、たばこ対策関係省庁連絡会議を設置し、対策の充実強化に向けた体制整備を行っている。また、同会議の幹事会の下に、未成年者喫煙防止対策ワーキンググループを設置し、未成年者の喫煙防止対策の促進を図っている。 |
<参考>たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約
たばこの使用及びたばこの煙にさらされることの広がりを継続的かつ実質的に減少させるため、締約国が自国において並びに地域的及び国際的に実施するたばこの規制のための措置についての枠組みを提供することにより、たばこの消費及びたばこの煙にさらされることが健康、社会、環境及び経済に及ぼす破壊的な影響から現在及び将来の世代を保護することを目的とする。 |
| ・平成15年5月 |
第56回WHO総会
条約案が全会一致により採択された。 |
| ・ |
平成16年6月 8日 |
条約批准(閣議決定→受諾書を寄託) |
| ・ |
平成16年6月15日 |
たばこ対策関係省庁連絡会議設置 |
| ・ |
平成17年1月18日 |
第一回たばこ対策関係省庁連絡会議 |
|
| 平成17年2月27日 条約発効
署名168か国、批准128か国 |
↓
第1回締約国会議(平成18年2月6日〜17日)
<主要議題>
| ・ |
事務局の設置及び機能の確定 |
| ・ |
手続規則、財政規則、予算案の採択 |
| ・ |
締約国会議への報告、価格操作以外の喫煙抑制措置 |
| ・ |
含有物規制の実施に係るガイドラインについて |
| ・ |
広告、販売促進及び後援に関する議定書について |
|
たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約
第1回締約国会議(概要) |
| ・ |
2006年2月6日〜17日までジュネーブの国際会議場にて開催 |
| ・ |
締約国110カ国(含むEC。なお会議開催中に3カ国増加)が参加
| |
その他、米を含む非締約国が49カ国、国連機関、国際機関、NGO等がオブザーバーとして参加。 |
|
|
| ・ |
オブザーバーの発言・参加を認める公開会合 |
| ・ |
要すれば締約国のみによる限定参加会合も開催 |
| ・ |
予算・財政事項はコンセンサス |
| ・ |
その他もコンセンサス形成に努める |
| ・ |
非締約国、地域経済統合体、政府間組織、締約国会議の承認を受けたNGOが、投票権はないが発言権を有するオブザーバーとして規定。 |
|
| (イ) |
条約事務局をWHO本部内に設置 |
| (ロ) |
条約事務局の説明責任 |
| ・ |
条約事務局は、締約国会議に対し、条約実施上の事項、技術的事項につき報告し、WHO事務局長に対し、技術的事項及び行政事項につき報告。 |
| ・ |
WHO部局(特にタバコ・フリー・イニシアティブ部)との作業の重複を避け、透明性を確保し、費用対効果を高めるべくWHOとの協力関係を構築。 |
|
| ・ |
801万ドルを承認(含:第2回締約国会議開催費用、各国報告書提出のための技術的支援、取りまとめ、たばこ規制関連ガイドライン作成等)。
|
| ・ |
第2回締約国会議にて予算の中間レビューを実施。 |
|
| ・ |
特定の基金等新たな資金メカニズム立ち上げは見送られた |
| ・ |
各国の提出する報告書にたばこ規制関連の援助の実施実績及び要請実績を含め、条約事務局が取りまとめる |
| ・ |
先進国、国際機関等に対し、途上国の要請に基づき、資源を振り向ける(channel resources)ことを求める |
|
| ・ |
初回報告の項目を決定した |
| ・ |
2回目以降の報告については別途再検討 |
| ・ |
報告頻度は各国における条約発効後2年、5年、8年に報告を提出 |
| ・ |
2回目以降の統計データについては、変更があった事項につき報告。 |
|
| ・ |
第8条(たばこの煙にさらされることからの保護)及び第9条(たばこ製品の含有物の測定)に関し優先的に作成 |
| ・ |
ガイドライン案を第2回締約国会議に提出 |
|
| ・ |
「国境を越える広告規制措置」及び「不法取引」に関する議定書策定に向け作業 |
| ・ |
検討状況につき第2回締約国会議に報告 |
|
| (5) |
経済的に実行可能な代替活動に対する支援に関する研究 |
| ・ |
関心国による代替活動に関する研究グループの設立が合意され、第2回締約国会議に報告書が提出される予定。 |
|
| ・ |
2007年前半に1週間開催。
開催場所については、希望国が第1回締約国会議終了後60日以内に主催の意思を条約事務局に伝達。 |
|
たばこ対策に係る国内体制について
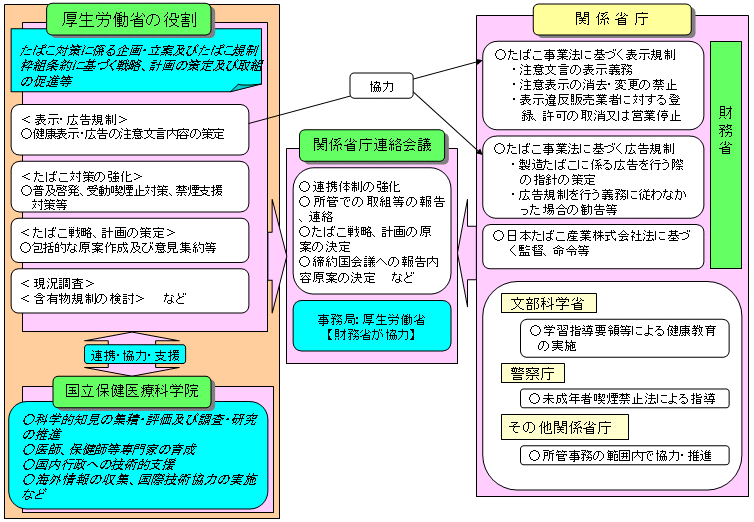
厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会
「中間とりまとめ」より抜粋
〜たばこ対策に係る部会意見要旨〜
| (1) |
|
喫煙率低下についての数値目標の設定 |
| (2) |
|
未成年者喫煙防止対策として自動販売機規制の大幅強化 |
| (3) |
|
受動喫煙防止対策の取組が遅れている施設について積極的対策の推進 |
| (4) |
|
公共の場の禁煙・分煙状況に関する調査の推進 |
| (5) |
|
たばこの価格又は税を引き上げ、その財源を生活習慣病予防対策に充当することへの検討 |