|
 |
関係各位
介護保険制度は、老後生活の最大の不安である介護を社会全体で支え、高齢者の自立を支援することを目的とした制度でありますが、この制度が定着していくためには、質の高い介護サービスが提供され、利用者と事業者の間に信頼関係が醸成されることが重要です。
その中で、身体拘束の問題は、これからの高齢者介護を見据える中で、関係者一丸となって取り組むべき喫緊の課題であると同時に、単に身体拘束をゼロにすることだけにとどまらず、「よりよいケアのあり方、ケアの本質とは何か」を自ら問いかけ、高齢者介護の内容を見直し、更なるサービスの向上へ向けてのスタートではないかと考えます。
このため、身体拘束ゼロ作戦推進会議が設置され、今年の3月には、介護の現場の方々の参考となるような「身体拘束ゼロへの手引き」が身体拘束ゼロ作戦推進会議においてとりまとめられました。また、身体拘束ゼロを支える福祉用具や居住環境の改善という観点から、同会議にハード改善分科会を設置し、昨年度3回にわたり開催し、活発な議論を行うことができました。また、本年5月には、身体拘束ゼロに役立つという観点に加え、今後の福祉用具や居住環境の在り方というやや広い観点に立った議論の機会も設けました。
今般、ハード改善分科会として、この「身体拘束ゼロに役立つ福祉用具・居住環境の工夫」を取りまとめました。身体拘束ゼロと福祉用具・居住環境との関わりには、直接的なものもあれば、間接的なものもあり、また、ここに盛り込まれたもの以外にも多種多様な工夫があろうかと思います。
ハード面の改善だけで万事解決すると考える人はいないとい思います。基本は「介護の心」です。しかし用具や環境を改善し、よりよく利用することも重要です。実務者の方々の努力をお願いいたします。
ハード面の改善のためには、単に用具や環境の設計を改良するだけでなく、供給面や知識の普及など広い範囲の改善が必要です。今後この報告書に書かれた提言等について、厚生労働省をはじめ関係者の方々に、積極的に実施し、あるいは研究を開始して、よりよいケアに向けて、息の長い取組みをお願いいたします。
ハード改善分科会としてのこの報告書については、身体拘束ゼロ作戦推進会議に報告する予定です。ここに盛り込まれた内容が、これからの福祉用具や居住環境の在り方を考える際の一助となれれば幸いです。
平成13年8月
身体拘束ゼロ作戦推進会議ハード改善分科会長
斎藤 正男
| 石崎 征義(前東京都福祉機器総合センター所長) | |
| 加島 守(武蔵野市立高齢者総合センター) | |
| 木村 哲彦(日本医科大学医療管理学教室教授) | |
| ◎ | 斎藤 正男(東京電機大学工学部教授) |
| 齊藤 正身(霞ヶ関南病院病院長) | |
| 相良 二朗(神戸芸術工科大学工業デザイン学科助教授) | |
| 園田 知弘((株)環境デザイン研究所副社長) | |
| 武内 寛(パラマウントベッド(株)技術本部統括室室長) | |
| 鳥海 房枝(特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘副施設長) | |
| 時田智恵子(湘南ベルサイド施設長) | |
| 外山 義(京都大学大学院教授) | |
| 畠山 卓朗(横浜市総合リハビリテーションセンター企画研究開発室研究員) | |
| 早川 京子(京都市介護実習・普及センター) | |
| 松永 茂之((株)松永製作所代表取締役) | |
| 光野 有次((株)無限工房代表取締役) | |
| 光益 康夫(北九州福祉用具研究開発センター副所長) | |
| 森山 由香((社福)三條会介護老人保健施設「ひうな荘」) | |
| 山内 繁(国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所長) |
2.身体拘束廃止におけるハード改善の基本的な考え方
3.福祉用具について
4.施設の居住環境について
|
平成13年6月 身体拘束ゼロ作戦推進会議 ハード改善分科会 |
| 身体拘束のない介護を実現するためには、施設の責任者やスタッフが一丸となって、身体拘束をしないという決意に基づいてケアに取り組むことだでなく、そうした取組みを支え、あるいは容易にしたり、負担を軽減したするための福祉用具や施設の居住環境といった、いわば「ハード」面での善を進めることが極めて重要である。 |
<身体拘束ゼロへ>
老後の生活の最大の不安要因となっている介護を社会全体で支え、高齢者の自立を支援することを目的とした介護保険制度が、平成12年4月から実施されたところである。それに伴い、介護保険の適用を受ける介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等では身体拘束が原則禁止されることとなった。
これまで介護の現場では、寝たきりゼロを目指し、ベッドから車いす等への日常生活の移行の努力がなされてきた過程において、転倒・転落事故の防止、介助者の不足、点滴や経管栄養等の治療の完全遂行、他人への迷惑行為の防止などの理由により身体拘束が行われてきたが、そうした身体拘束は、拘束される高齢者の心身両面での尊厳を著しく損なうのみでなく、その状態を一層悪化させる危険性がある。身体拘束を許容する考え方を問い直し、介護に関わる全ての者が、介護を受ける高齢者の立場に立って、ケアの在り方を見直すことが求められている。
<身体拘束ゼロへ向けてのハード改善>
身体拘束のない介護を実現するためには、高齢者施設の責任者やスタッフが一丸となって、身体拘束をしないという決意に基づいてケアに取り組むことに加え、そうした取組みを支え、あるいは容易にしたり、負担を軽減したりするための福祉用具や施設の居住環境といった、いわば「ハード」面での改善を進めることが極めて重要である。すなわち、ケアの在り方を見直す過程では、高齢者を取り巻く物理的環境を見直すことも求められる。
高齢者にとって安全で快適な物理的環境についての明確な検証は十分にされていないが、危険を少なくするための具体的取組みは始まってきている。
|
|
|
|
といった効果がある。
| 身体拘束に当たる具体的な行為の中には、福祉用具の利用に伴う事故を防止するという理由で行われているものがあるが、高齢者の身体状況や生活的に合致したケアの提供という観点から福祉用具の改善を行うことによりこうした身体拘束を回避することが可能となる。 |
|
<福祉用具の活用の改善−3つのポイント> (1) 身体状況に適合しやすく、使いやすい福祉用具 福祉用具が身体状況に不適合であるために事故が発生する場合、福祉用具の改善によって適合を可能とし、事故の発生を低減させることが可能である。また、現場における事故発生を防止するためには、高齢者と介護者の両者にとって使いやすいものであるとともに、施設環境に調和しやすいものであることが望ましい。 (2) 身体・精神状況に応じて福祉用具を適合、活用する技術・知識
構造や機能の改善だけでは身体的・精神的要因により発生するあらゆる事故に対応することはできない。また、加齢とともに変化する高齢者の身体・精神機能に現場で対応し得るためには、変化に対応して再適合が容易なものであるとともに、現場で容易に活用できる適合技術・知識が必要となる。 (3) 福祉用具の使用に関する意識 使用しようとする福祉用具本来の用途以外に、身体拘束の理由となる事故を発生させる可能性について十分に検討し、必要に応じて高齢者や介護者に意識を喚起することが必要である。また、痴呆性高齢者による使用も想定し、想定しなかった使用法による場合にも事故を発生させることのないよう配慮することも必要である。 |
|
| ○ 高齢者施設においては、確かに日中ベッドで寝たきりになっている高齢者はかつてに比べて激減したが、一方で車いすに座りきりという生活をしている高齢者がよく見られる。そして、そうした高齢者が座っている車いすは、座面と背面がシートでできた折りたたみ式(右図)のものであることが多い。 こうした車いすは、短時間の移動が目的であればともかく、長く座る場所としては不適当であることから、立ち上がり能力の減退や座位保持能力の低下により、転倒、ずり落ち等の事故が発生する可能性が高くなり、結果的にそれを回避するために身体拘束につながりかねない。 |
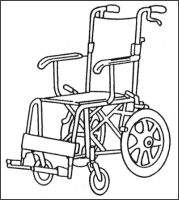 |
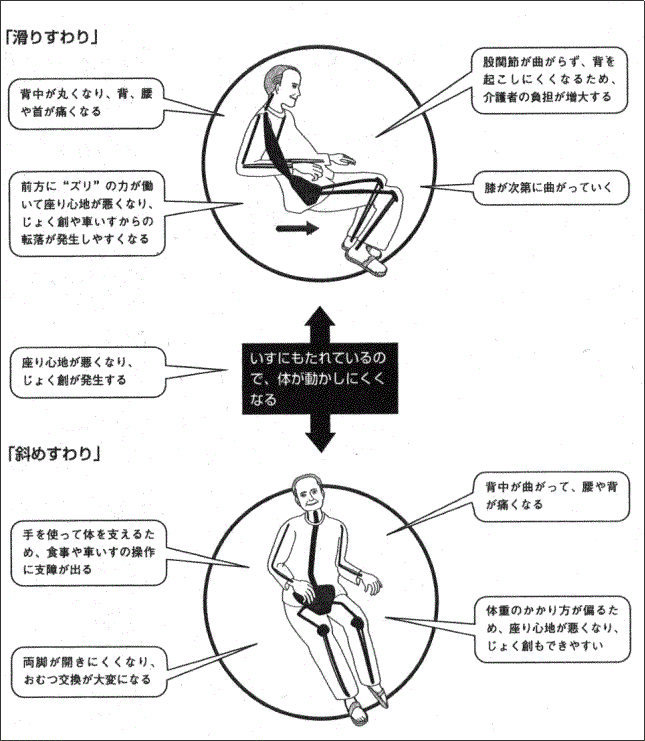
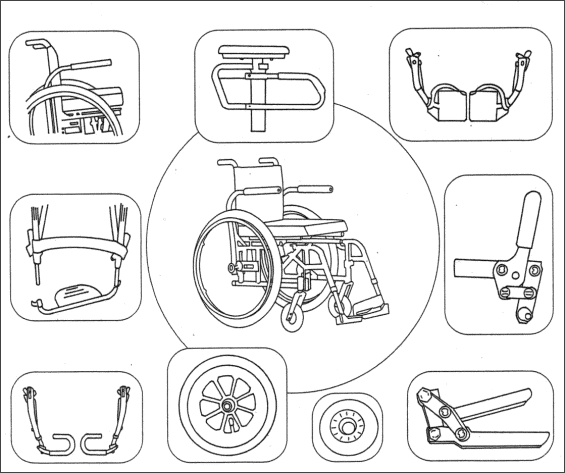
| 解説<ティルト機能>
ある肢位を維持したまま、全体として角度を変えることができる機能。全体の角度が変わると、(1)臀部にかかっていた力を背中で受けるなど、当たる位置がかわる、(2)姿勢が重力でつぶれない、(3)身体を戻したとき、身体のずれが少ないなどの利点がある。 |
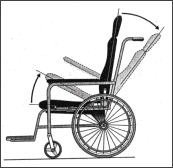 |
| 解説<リクライニング機能>
背面(バックレスト)が後方へ傾き、座面との間の角度を変えることができる機能。これにより食事をとるときやテーブルで作業を行うときは、背面を起こして使い、休養するときには背面を倒すことができる。また、移動時に安定した座位を確保する必要がある場合などにも役立つ機能である。 |
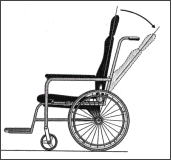 |
|
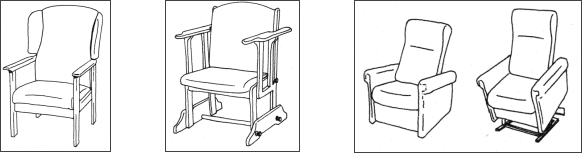
|
左:ゆったり過ごせる背もたれが比較的高いいす 中:身体に合わせて調節できる安定したいす 右2つ:立ち上がりを助ける電動いす |
| ○ また、いすとあわせてテーブルの高さ等も重要である。高齢者施設によっては、テーブルの高さを、車いすの肘掛けがテーブルの下に入る高さに設定している場合がみられるが、座高の低い人は首しか出ず、これでは食事や作業をすることが困難となる(右図)。これは、いす又は車いすとテーブルによって、実質的な身体拘束を行っていると言うことができる。 | 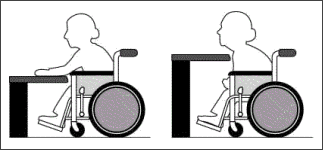 |
|
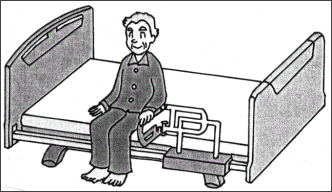 |
端座位(安定してベッドの横に座った姿勢)をとるためには、足底を床につけ、マットレスにしっかりと腰をおろせる高さにベッドを調節することが重要である。また、立ち上がりをより容易にするためベッド用手すりを使用するなど、ベッドの付属品を適切に利用することが重要である。なお、端座位がとれる高さであれば、誤って落ちた場合の衝撃も少ない。 |
| ○ 一方で、転落時の衝撃緩和のためベッドを低くすることと、介護職員の腰痛を予防するためにベッドを高くすることは相反するとの意見がある。確かに、利用者に提供する医療・介護サービスの内容によっては一定の高さがあった方が適当であることもあるものの、多くの利用者については、低いベッドを利用する場合でも、介護職員がベッドに膝をついておむつ交換(上図参照)などを行うことにより負担を少なくすることは可能であり、介護の方法についても改めて検証してみる必要がある。 また、サービスを提供する時には高く、就寝するときには低くすることができるベッドを導入することにより、サービス提供時の必要な高さの確保と転落等の事故の減少の両立を図ることが可能である。 |
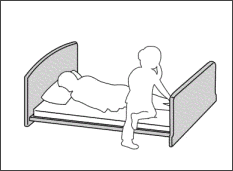 |
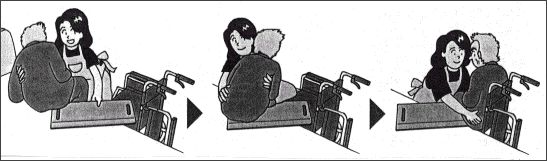
|
|
といったように、福祉用具を人に合わせるという姿勢が求められる。
| 身体拘束と高齢者施設の居住環境は一見結びつきにくいが、「居住環境の貧しさが心理的不安定につながり問題行動を起こし、結果として身体拘束至る」という意味では、身体拘束の遠因となるという関係にあり、居住環の改善により、問題行動の発生を低減し、身体拘束に至ってしまう原因のつを取り除くことが可能となる。なお、ここで取り上げた居住環境の改善の工夫は、あくまで考え方の一例であってマニュアルではない。実際、既存の施設において大規模な改修をなくても、ちょっとした工夫により居住環境の改善について成果を上げてる。このため、こうした事例の収集等を通じて研究を進めていくことも必である。 |
|
●物理的環境がもたらすもの
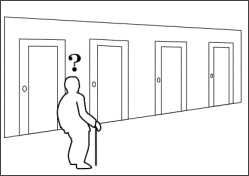 |
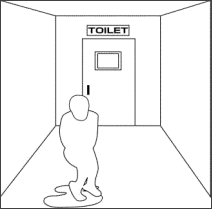 | |
| 同じパターンの繰り返しによる混乱 | トイレがトイレと認識できない |
上記のように、痴呆性高齢者が混乱して問題行動を起こすことがないように、心理的な安定が得られるような居住環境を整えることで、問題行動の発生を低減させて身体拘束を回避したり、あるいは、不幸にして転倒等の事故が起こった場合でもそれによる衝撃を緩和できるような居住環境を整えることで事故防止のための身体拘束を回避したりすることも可能である。そうした観点から考えられる工夫の例を以下に掲げる。
|
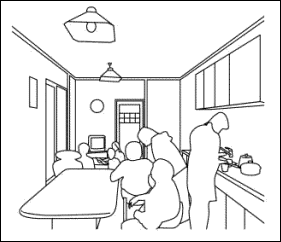
|
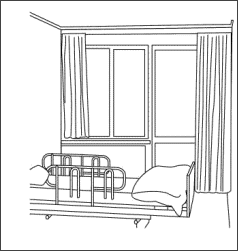 |
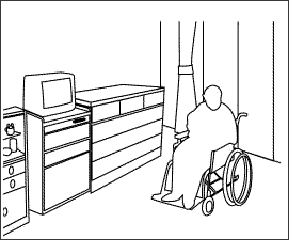 |
|
| 一人部屋(ベッドのみ) | 個室(使い慣れた家具などがある) |
本研究で、一人ひとりの入居者のタイムスタディをとったところ、多床室において、同室者同士の会話はほとんどなく、お互い背を向け合って、お互いが存在しないかのように生活しているという実態が浮かび上がった。すなわち、多床室の同室者の間でトラブルも起こりうるし、ストレスも生じてしまい、交流がかえって損なわれることもあるということである。また、このタイムスタディにおいては、同室者同士のトラブルの回避のために払われる職員の介護上の配慮やケアは相当な量に上っており、一概に多床室が効率的とはいえないことがわかった。
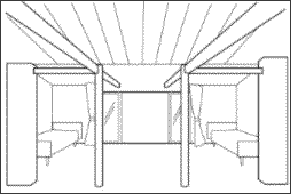 |
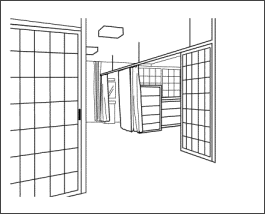 |
|
| 丸太柱、梁などによる個室風空間の例 | 障子、板戸等による個室風空間の例 | |
| さらに、個々に、のれん、家具等を用いて施設らしくない雑多で個性的な空間に | ||
|
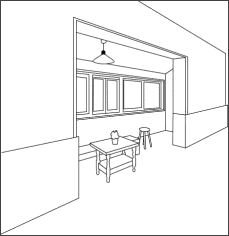 |
たまり空間 隣近所の気心知れた仲間が小人数で集うにはちょうどよい広さの談話コーナー。 |
● 従来の高齢者施設の生活スペースは、主として居室(プライベートゾーン)とホール状の共用空間(セミパブリックゾーン)のみからなり、この二つの領域を二拍子のリズムで行き来しながら生活が構成されている、という趣があった。共用空間の中にも、一方的に職員が主導権を握って集団で活動が展開されるセミパブリックゾーンだけではなく、気の合う入居者同士が数人で自発的に時間を過ごすことのできる、セミプライベートゾーンの存在が重要であり、さらに施設内であっても地域住民に開放され、外部社会に開かれた場(パブリックゾーン)の存在も極めて重要である。
●自分の生活の拠点であるプライベートゾーンをベースにしながら、次第に馴染みの関係が培われつつある入居者同士での自発的な場を持ち、共用空間の中にも、気に入った居場所を次第に獲得してゆくことができれば、やがて、個々の入居者にとって、プライベートからパブリックに至る段階的な領域を貫いて、様々な空間を生活の場として編み上げる、安定的な生活シナリオが、それぞれに定着してゆくことだろう。
| 定義 | 主な利用者 | |
| プライベートゾーン | 入居者個人の所有物を持ち込み管理する領域。一般には個室を指す。 | 入居者 |
| セミプライベートゾーン | プライベートゾーンの外側にあって複数の入居者により利用される領域。居室前の廊下部分なども含まれる。 | 複数の入居者 |
| セミパブリックゾーン | 基本的には食事やリハビリ、レクリエーションなどの集団行為が行われる領域(プログラム間の空白時間には自発的行為も行われる)。 | 職員(寮母) |
| パブリックゾーン | 入居者と地域住民、外部社会の双方に開かれた領域 | 職員 地域住民 |
|
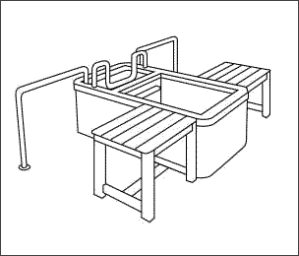 |
個別浴槽 できるだけ自力で入浴できるようにするための腰掛けや手すりなどの工夫がなされた例。また、浴室内は、目隠壁やカーテンなどで個々に区切られ、プライバシーを確保している。 |
|
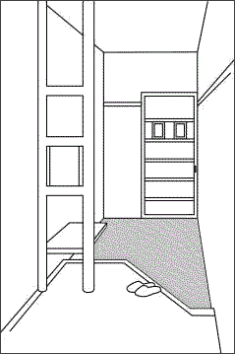 |
(下図)小上がりと囲炉裏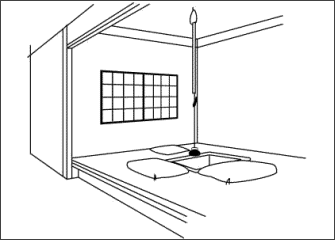 |
| (上図)トイレと舞良戸 トイレがトイレであることを形態により理解できるようにするため昔利用した舞良戸を用いた例 |
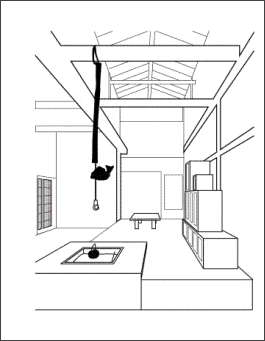 |
| (右図)囲炉裏 いすや車いすでも利用できる高さ。家具もなじみのある形態、材質を考慮し選定 |
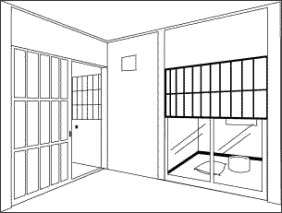 |
格子戸 個室の前に格子戸のついた前室を設けることで、居室内のプライバシーを守るとともに、前室を玄関に見立てることにより、「住まい」として認知できるよう意図。 |
|
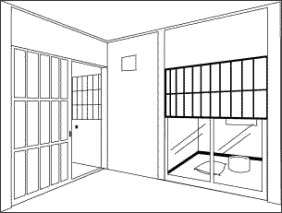
|
|
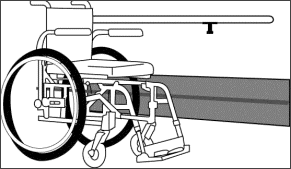 |
巾木(キックプレート) |
|
| 新築・改築 | 改造(リフォーム) | |
| 空間レベル | 高齢者に快適なスケール たまり空間 個室化、ユニット化 |
建物の小分節化→ユニットの概念 (小スケール化、たまり空間等) 個人領域の確保(個室風) |
| 素材・設備レベル | 家庭で使われるような設備 トイレの分散配置、居室に近い位置への配置、必要な便房数の確保 個別浴槽等の工夫 |
|
| 転倒時にできるだけ衝撃が少ない床材の利用 危険な段差の解消、突起物などの防護 手すりの取付け (ただし、過剰な安全保護対策は住宅らしさを失い逆効果) |
||
| 演出レベル | 高齢者に馴染みのあるしつらえ、家具、調度品、サインの工夫 | |
|
|
まとめ
|
参考文献
| 1. | 「縛らない看護」吉岡充、田中とも江 編 (医学書院1999) |
| 2. | 「車「いす」について考えてみましょう」廣瀬秀行、木之瀬隆、清宮清美、佐藤真理子 ((財)テクノエイド協会1999) |
| 3. | 「高齢者の車いす座位能力分類と座位保持機能」木之瀬隆、廣瀬秀行(Rehabulitation Engineering 13(2) 4-12 1998) |
| 4. | 「Wheelchair Needs of the Disabled,Therapeautic Consideratipns for the Elderly」Susan C.H(Churchill Livingstone,1989) |
| 5. | 「Positioning for Function」Adrienne F.B.(Valhalla Rehabilitation Publication,1990) |
| 6. | 「重度高齢障害者の車いすの評価」廣瀬秀行、木之瀬隆、浅海奈津美、佐藤真理子、清宮清 美(第13回リハ工学カンファレンス1998) |
| 7. | 「Principles of Seating The Disabled」R.Mervyn Letts(CRC Press,1991) |
| 8. | 「テーブルの高さが高齢者の作業速度に及ぼす影響」木之瀬隆、廣瀬秀行、相原みどり(東 京都立医療技術短期大学紀要、9、1997) |
| 9. | 「車椅子を使用している高齢障害者の座位能力と座位保持装置」相原みどり、木之瀬隆、廣 瀬秀行(国リハ研究紀要、16、1995) |
| 10. | 「Biomechanics and the wheelchair」McLaurin,C.A.& Brubaker C.E.(Prosthetics and Othotics International,15,24-37,1991) |
| 11. | 「高齢者のための車椅子の改良−座位保持装置を中心に−」廣瀬秀行(老人ケア研究、5、 1996) |
| 12. | 「高齢者の作業時の車いすおよびその座面の影響について」廣瀬秀行、相原みどり、木之瀬 隆(国リハ研紀18、19-24、1997) |
| 13. | 「ケアマネージャーのための住宅改修テキスト」(品川区、2000.3) |
| 14. | 「老後のマイルーム」相良二朗 (社団法人 家の光協会 1999.9) |
| 15. | 「福祉用具のよりよい活用システムを求めて」(医療法人財団健和会 2000.3) |
| 16. | 「ケアマネジャーのための在宅ケアハンドブック vol2,3」(パラマウントベッド株式会社 編集協力 窪田静、河添竜志郎 2000.7, 2000.10) |
| 17. | 「寝たきり起こし そのメカニズムとモノ選び((1)〜(17))」窪田静、河添竜志郎(月刊「訪問看護と介護」連載1999.1〜2000.12 医学書院) |
| 18. | 「特集 高齢者のための地域福祉施設「自宅でない在宅」を提案する」(ディテール第146号株式会社彰国社 2000年秋号) |
| 19. | 「特集 グループホームの家らしさとは」(日経アーキテクチャ2000.5.29号 日経BP社) |
| 20. | 「個室は究極の居住環境か」外山義(月刊総合ケア2000年8月号 医歯薬出版株式会社) |
| 21. | 「医療・高齢者施設の計画法規ハンドブック」(社団法人 日本医療福祉建築協会 1998) |
| 22. | 「特別養護老人ホームの個室化に関する研究」(全国社会福祉協議会 1996.3) |
| 23. | 「高齢者・障害者の心身機能の向上と木材利用」(全国社会福祉協議会 1998.3) |
| 24. | 「痴呆性高齢者の住まいのかたち」大原一興、オーヴェ・オールンド(株式会社ワールドプ ランニング 2000.10) |
| 25. | 「ユニットケア施設の空間設計と運営管理」(総合ユニコム株式会社 2001.2) |
イラストの提供
P9:「福祉用具を活用したケアプラン(社)日本福祉用具供給協会」より引用
P10、P12:「身体拘束ゼロへの手引き(身体拘束ゼロ作戦会議)」より引用
P11:「福祉用具解説書〜移動機器編(テクノエイド協会)」より引用
P14上:参考文献13より引用
P15、P17:参考文献16より引用
P16、P37:(財)高齢者住宅財団がイラストを作成
P25:参考文献19を参考に(財)高齢者住宅財団がイラストを作成
P14下、P27〜P35:参考文献18を参考に(財)高齢者住宅財団がイラストを作成
照会先 老健局振興課福祉用具係 TEL 03(5253)1111 内線3985