| 課題 |
| ○ | 介護保険施行後見えてきた課題
|
|||
| ○ | 制度の持続可能性の確保(課題解決の前提) |
| 目標 |
高齢者の尊厳を支えるケアの確立
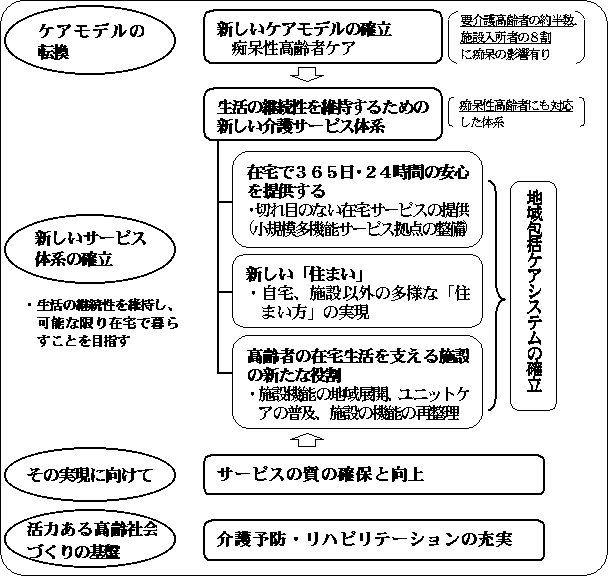
|
|
||||||||
|
高齢者の尊厳を支えるケアの確立 |
||||||||
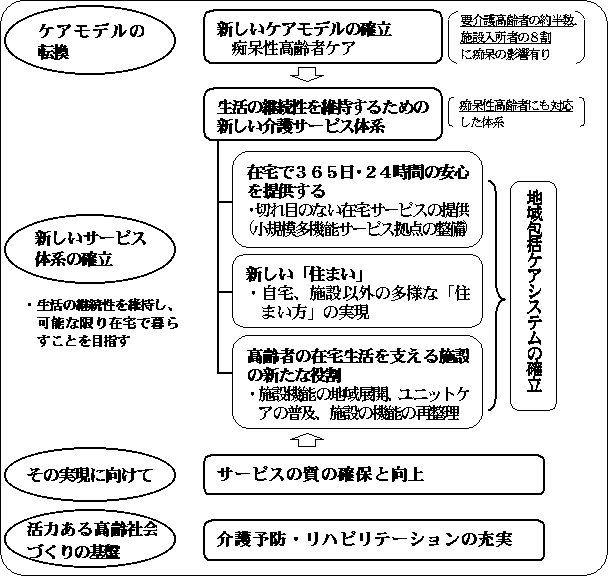 |
|||||||||
|
早急に着手し、2015年までに着実に実施 (戦後のベビーブーム世代が高齢期に達する2015年までに実現) |
| 要介護認定者の増加・軽度の者の増加 |
| ・ | 軽度の要介護者の出現率に大きな都道府県格差が存在。その要因について詳細な検証が必要。 |
| ・ | 要支援者への予防給付が、要介護状態の改善につながっていない。 |
| 在宅サービスの脆弱性 |
| ・ | 特別養護老人ホームの入所申込者の急増 |
| ・ | 重度の要介護認定者の半数は施設サービスを利用。在宅生活を希望する高齢者が在宅生活を続けられない状況にある。 |
| 居住型サービスの伸び |
| ・ | 特定施設の利用が増加。居住型サービスへの関心が高まっている。 |
| 施設サービスでの個別ケアへの取組 |
| ・ | ユニットケアの取組が進展。個人の生活、暮らし方を尊重した介護が広がりを見せている。 |
| ケアマネジメントの現状 |
| ・ | ケアマネジメントについては、アセスメントなど、当然行われるべき業務が必ずしも行われていない。 |
| 求められる痴呆性高齢者ケア |
| ・ | 要介護高齢者のほぼ半数は痴呆の影響が認められる者であるにもかかわらず、痴呆性高齢者ケアは未だ発展途上、ケアの標準化、方法論の確立にはさらに時間が必要。 |
| 介護サービスの現状 |
| ・ | 事業者を選択するために必要な情報が十分に提供されていない。 |
| ・ | サービスの質に関する苦情が多い。従事者の質の向上、人材育成が課題。 |
| ・ | 劣悪な事業者を市場から排除する効果的手段が不十分。 |
|
| ↓ | 身体ケアのみでなく、痴呆性高齢者に対応したケアを高齢者介護の標準とするべき |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介護(要支援)認定者における痴呆性高齢者の推計
| ○ 所在と痴呆性老人自立度 | 単位 万人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 2002年9月末についての推計。 「その他の施設」:医療機関、グループホーム、ケアハウス等。 カッコ内は、運動能力の低下していない痴呆性高齢者の再掲。(痴呆自立度「III」、「IV」又は「M」かつ、障害自立度「自立」、「J」又は「A」)。 |
| ○ 将来推計 | 単位 万人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | カッコ内は65歳以上人口比(%)。 |
| → |
|
痴呆ケアモデルの構築
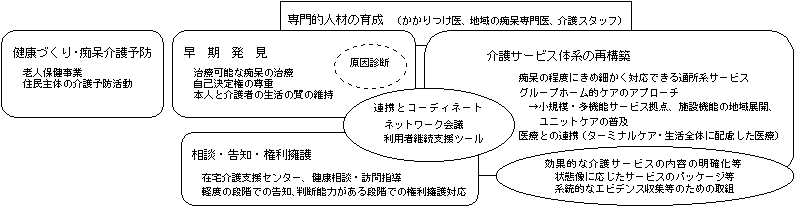
痴呆ケアモデルの存立基盤
| 家族・地域住民の痴呆についての正しい知識と理解、痴呆性高齢者との適切な関わり →「時として痴呆性高齢者を追いつめてしまう存在」から「痴呆性高齢者を地域で支援する担い手」へ転換 |
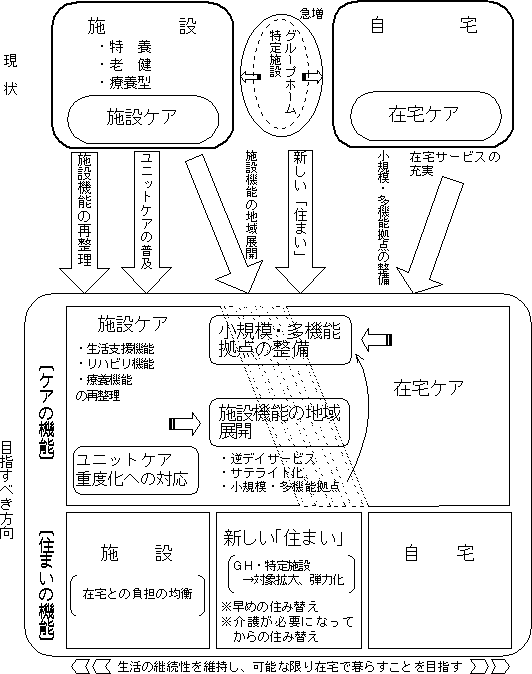
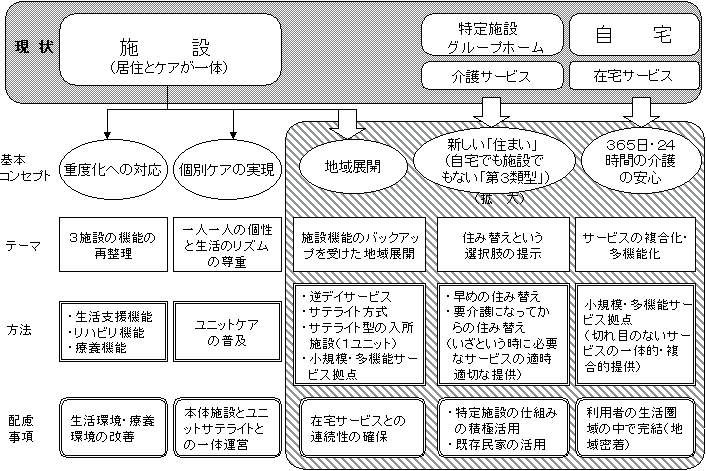
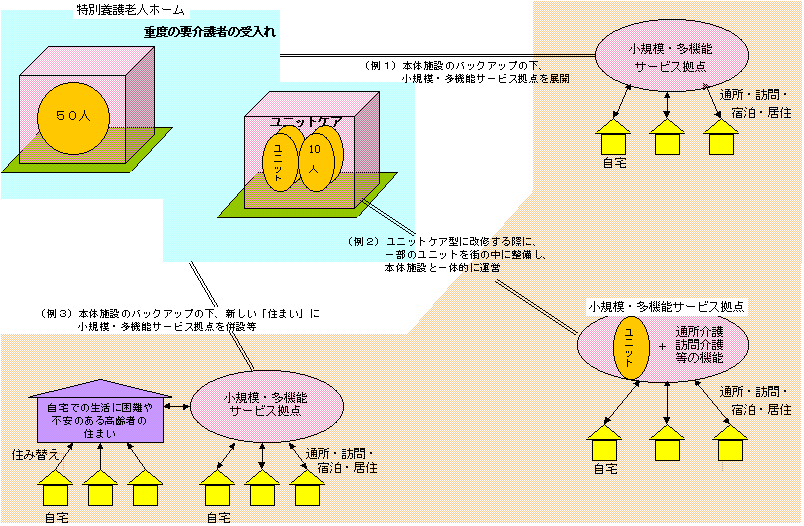
| 個々の高齢者の状況やその変化に応じて、介護サービスを中核とした様々な支援が継続的かつ包括的に提供される仕組み |
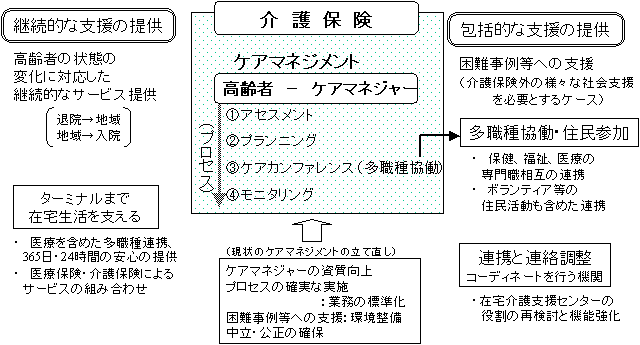
| ※ケアマネジメント: | 高齢者の状態を踏まえた総合的な援助方針の下に必要なサービスを計画的に提供していく仕組み |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
| 介護予防・リハビリテーションの充実 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|