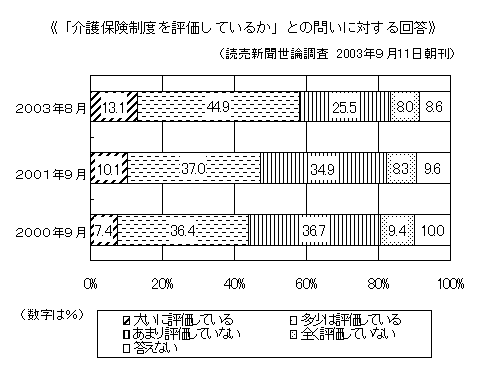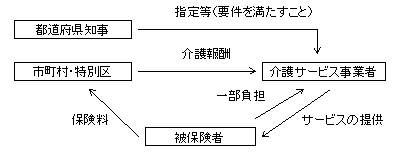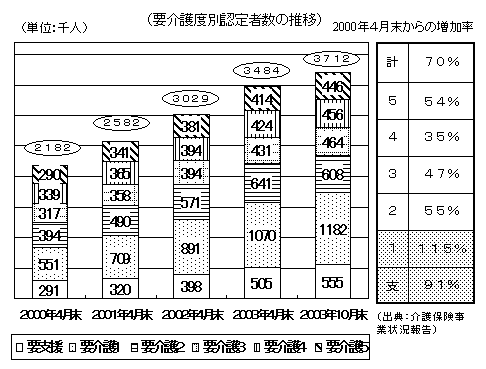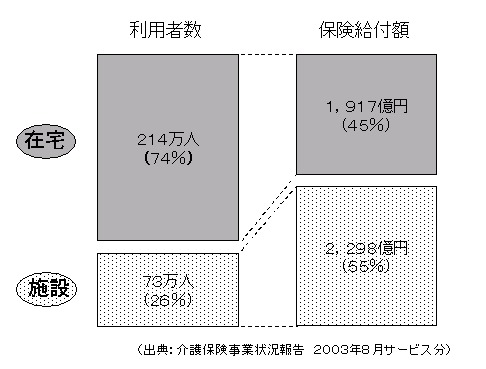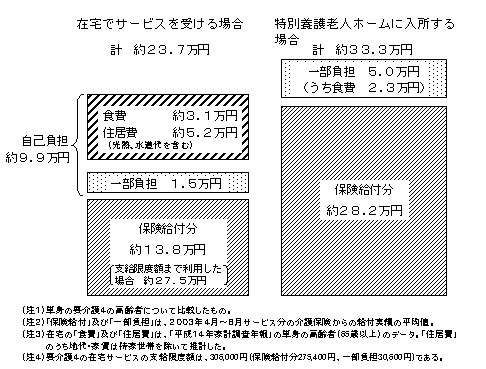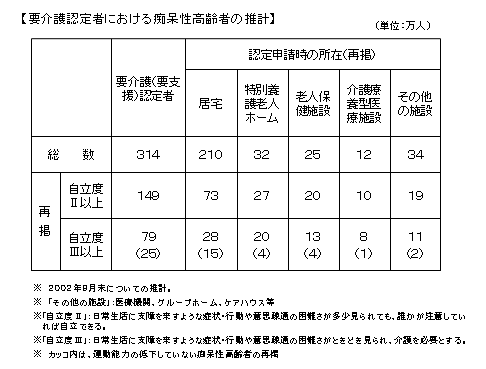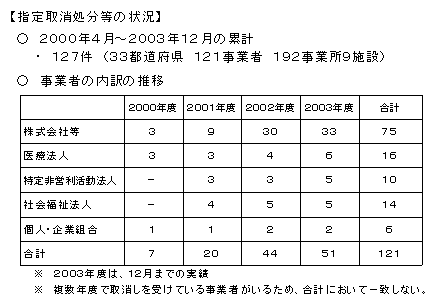| 2000年4月末 | 2003年10月末 | |
| 第1号被保険者数 | 2,165万人 | 2,420万人(12%増) |
| 要介護認定者数 | 218万人 | 371万人(70%増) |
【利用者数の推移】
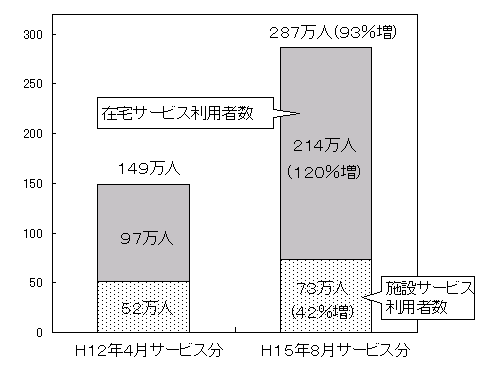 |
【介護保険の総費用及び給付費の推移】
| 2000年度 (実績) |
2001年度 (実績) |
2002年度 (実績) |
2003年度 (補正後) |
2004年度 (予算案) |
|
| 総費用 | 3.6兆円 | 4.6兆円 | 5.2兆円 | 5.7兆円 | 6.1兆円 |
| 給付費 | 3.2兆円 | 4.1兆円 | 4.7兆円 | 5.1兆円 | 5.5兆円 |
| ※ | 2000年度は11ヶ月分。 |
| ※ | 2003年度は補正後予算案ベース。2004年度は予算案ベース。 |