○ 入院基本料に係る保険給付の範囲を見直す。
| (1) 難病患者等 長期にわたる 療養が必要な者 |
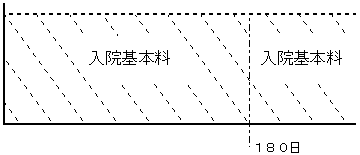 |
| (2) 入院医療の必要性が低い者 |
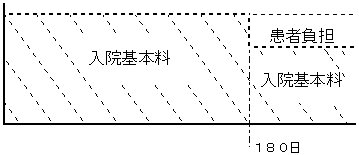 |
I.次期事業運営期間に向けた保険者の取組について
(1)次期事業運営期間に向けた基本的な考え方
ア 平成14年度における取組の重要性について
平成15年度からの第2期事業運営期間を控え、本年度は、各市町村において、市町村介護保険事業計画の策定及び平成15年度から17年度までの第1号被保険者の保険料の改定に向けた作業を行うこととなる。
これは、単に保険料改定等の作業を行うというのみならず、地域におけるあるべき給付と負担の水準を真摯に検討するという点で、極めて重要な期間であると考えている。わがまちの将来像を地域で考えていくという姿勢で取り組んでいただきたい。
イ 各自治体における取組状況について
本年4月、5月の各都道府県、市町村の取組をみると、残念ながら進捗状況に大きな相違がみられる。課題分析が行われ、具体的な施策を検討している自治体がみられる一方で、介護険事業計画作成委員会等が未だ開催されていない、あるいは給付分析が十分に行われていないといった市町村がみられる。後者の自治体におかれては、今後、取組を加速していただきたい。
その際、圏域ごとや状況が類似している自治体同士で、勉強会を開催するなどにより、効果的・効率的に計画策定を進めている自治体も多くみられるので、参考にされたい。また、都道府県におかれては、こうした勉強会への呼びかけや場の設定のほか、単独ではきめの細かい取組が困難な町村に対する支援について、特に御配慮願いたい。
ウ 介護保険制度の考え方と住民参加について
介護保険制度においては、利用者が増加し、あるいは各人の利用サービス量が増加するにつれ、それだけ保険料負担が必要になるものであり、次期保険料は引上げとなる市町村も相当程度生じることが予想される。
しかしながら、給付に見合った負担をいただくという介護保険制度の趣旨を踏まえれば、保険料の引上げは必要となるものであり、それに当たって、
といった点に留意することが特に重要である。このため、計画策定に当たっては、地域住民に対して介護保険制度の考え方について周知、啓発を行い、加えて地域の給付状況や保険料の見込みに関する情報公開を進め、住民参加型の計画作りを目指していくことが重要である。
なお、こうした介護保険制度の仕組みから、保険料の設定に当たって給付実勢に見合わない低い額とすることは適当ではなく、また、保険料の引上げを抑えるために、一般財源を繰り入れることは許されないということに十分に留意する必要がある。
(2)事業計画策定に向けた留意点
ア 在宅サービスの重視
介護保険制度は、在宅サービスを基本としている。このため、事業計画の策定を契機として、在宅サービスの利用が少ない地域では、その利用促進を検討するとともに、計画策定に当たっては、在宅重視という制度の基本的な考え方からの検証を行い、参酌標準も踏まえ、適切な施設利用者数の見込みを立てることが必要である。
イ 給付の適正化
一方、これまでの間に給付が過大となっている一部の自治体においては、給付の適正化に着手していくことも重要である。
具体的には、地域の給付状況についてサービス毎の分析・評価を十分に行った上で、給付が増大している状況について積極的に情報を公開していくとともに、必要に応じ、居宅介護支援の関係連絡会などにおけるケアプランの分析や介護予防の更なる推進などについて、検討されたい。
(3)長期入院に係る保険給付の見直しについて
ア 今般、180日を超えて入院する患者に対する保険給付が特定療養費化され、医療機関に支払われる診療報酬が基本的な報酬額の85%(14年度は経過措置により95%)となる一方、これに相当する額を患者が支払うこととされている(別添参照)。この措置の実施により、入院患者のうち退院される方も生じることが予想され、介護サービスを必要とする者については、介護保険においても一定の受け皿整備が求められるものと考えられる。
イ 各市町村において、施設等の利用者見込みを立てるに当たっては、参酌標準の考え方を踏まえ、また高齢者の状態像にふさわしいサービスを適切に用意するという観点から、地域のあるべきサービスの姿を検討することが求められる。
ウ また、各都道府県においては、長期入院患者の動向にも留意し、施設の指定に当たっては、地元市町村の意見も参考にするなどの対応も考えられたい。
(4)「介護サービス量等の見込み(中間値)」について
「介護サービス量等の見込み(中間値)」については、既に各自治体に調査をお願いしているところである。
この介護サービス量等の見込み値は、現時点における中間値という扱いであり、ある程度粗いものになると考えているが、厚生労働省においては、この結果も勘案して平成15年度予算の概算要求を行う予定であることから、各市町村におかれては、可能な限り、給付実績を踏まえた推計を行っていただくとともに、各都道府県におかれては、管内市町村の取りまとめに当たり、エラーチェック(※)や報告値の確認などに特段のご配慮をお願いする。
なお、今回、ご報告いただく介護サービス量等の見込み(中間値)の集計結果の公表項目については、基本的に現行計画の策定時におけるものを想定している。具体的には、全国の加重平均や分布等を公表することを予定しており、自治体が特定される数値の公表は原則として行わない予定である。
また、この報告に引き続き、各市町村においては、最終報告に向けて、介護サービス量等を適切に見込んでいただくようお願いしたい。
※エラーチェック項目例
要介護認定者数が65歳以上人口を超えている。
標準的居宅サービス対象者数が要介護認定者数を超えている。
居宅における要支援・要介護者数(標準的居宅サービス利用者数)が標準的居宅サービス対象者数を超えている。
居宅介護支援の利用人数が居宅における要支援・要介護者数を超えている。
訪問介護〜短期入所サービスの供給率が全て100%を超えている。
要介護者全員のサービス利用量が区分支給限度基準額を超えている。
所得段階別被保険者数の合計が65歳以上人口と一致していない。
(5)保険料算定に当たって必要な諸係数について
次期保険料の算定に当たって必要となる諸係数については、以下のとおり、10月に予定されている「介護サービス量等の見込み量(最終見込み値)」の調査に間に合うよう、可能なものから速やかに、遅くとも8月を目途として設定する予定である。
なお、審査支払手数料については、年末の予算編成時に最終決定する予定である。
ア 第2号被保険者負担率(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
(平成10年政令第413号。以下「算定政令」という。)第5条)
第2号被保険者負担率については、現在配布されているワークシートに示されている32%とする予定である。
イ その他
(1) 財政安定化基金拠出率(介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成11年厚生省令第43号。以下「納付金省令」という第4条)
財政安定化基金拠出率については、算定政令第12条第3項により、次期事業運営期間における交付金及び貸付金の見込額の合算額から借入金の償還見込額を控除して得た額や標準給付費額の見込額の総額等を勘案して定めることとされており、現行の0.5%から引き下げることになると考えているが、具体的には、今後、第1期事業運営期間における貸付・交付実績見込額等を踏まえて設定する予定である。
(2) 保険料の収納下限率(納付金省令において新規に設定する予定。)
保険料の収納下限率については、算定政令第6条第3項により、各市町村の第1号被保険者の数等の区分に応じて設定することとされており、介護保険事業状況報告の年報を基に、通常期待できる徴収努力を勘案の上、設定する予定である。
(3) 基準所得金額(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号) 第143条)
基準所得金額については、平成14年5月14日付事務連絡「基準所得金額の設定に関する調査について(追加の状況提供)」にあるとおり、集計でき次第、速やかに省令改正に取りかかる予定であるので、改めて調査への御理解と御協力をお願いする。
(4) 後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数に係る数値(介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成12年厚生省令第26号)第5条及び第6条)
(3)の調査や介護保険事業状況報告の実績等を踏まえ、平成15年度から平成17年度までの見込値として設定する予定である。
(6)保険料収納の適正化等について
ア 適切な保険料の設定等について
保険料の改定に際し、以下の点にご留意いただく必要があると考えている。
(1) 6段階制の導入等による適切な保険料設定について
第1号被保険者の保険料については、5段階設定のほか、6段階による設定や基準額に対する割合の変更及び基準所得金額(境界所得)の変更といった弾力的な設定が可能である。
これらの弾力化は政令上認められたものであり、特に次期保険料が引上げとなる市町村においては、低所得者に対する配慮として考えられる有効な方策である。このため、特に低所得者への配慮を行う場合には、まずはこうした法令上認められた方法による対応を検討することが求められる。
なお、6段階方式については、そのメリットや具体的な設定方法に関し、平成13年5月28日の全国介護保険担当課長会議資料(P.40、46〜)に記載されているほか、先般配布した保険料推計のワークシートにおいても「6段階の設定」を選択し、各段階別被保険者数や基準額に対する負担割合を入力することにより、簡便に保険料推計を行うことが可能となっている。
(2) 保険料の単独減免の場合の三原則の遵守について
保険料の単独減免については、いわゆる三原則を遵守している市町村が増えている。介護保険制度は、介護を国民皆で支え合おうとするものであり、保険料を支払った者に対して必要な給付を行うものであることから、
については適当でないので、引き続き市町村が適切に対応するよう努められたい。
(参考)
〔 〕内は前回調査時点からの増加数 |
(3) 保険料の徴収に関する総務省行政評価局の勧告について
上記(1)、(2)の事項については、今般、以下のとおり総務省行政評価局の勧告においても指摘されているところであり、適切な実施をお願いしたい。
|
総務省行政評価局勧告(抜粋) 低所得者について、三原則の趣旨を踏まえずに保険料減免を行っている市町村に対しては、6段階制の導入や料率の変更の検討も含め、保険料の減免の適正化を図るよう技術的助言を行うこと。 |
イ 保険料収納率の向上について
(1) 保険料徴収が平成12年10月より開始されたが、各市町村における収納努力により、平成12年度の収納率が98.6%(うち普通徴収が93.0%)、定点市町村における平成13年10月分の収納率も98.9%と高い水準を維持しており、制度や保険料負担について全体的には理解が得られていると考えている。
(2) 保険料の徴収については、引き続き住民に対する制度の趣旨、内容等の周知や保険料の納付相談の実施並びに口座振替の促進等により普通徴収の収納率の向上に努めていただくよう市町村に対しご指導願いたい。
(3) 保険料収納率の向上については、上記の趣旨が以下のとおり総務省行政評価局より勧告されているところである。
|
総務省行政評価局勧告(抜粋) 保険料の普通徴収について、納付相談の実施や口座振替の推進により収納率向上を図るよう、市町村に技術的助言を行うこと。 |
ウ 給付減額措置に関するQ&Aについて
本年10月末以降には時効により保険料徴収権が消滅し、保険料滞納者(2年以上)に対する給付減額措置(介護保険法第69条)の対象となる者が生じ得ることとなる。引き続き、滞納者に対しては納付の督促を続ける必要があるが、やむを得ず当該給付減額措置を講じることとなる場合には、別紙のQ&Aを参考に適切に対応されたい。
また、こうした取扱いに関し、サービス事業者や国民健康保険団体連合会への周知につき、特段のご配慮をお願いしたい。
エ 特別徴収の年金保険者への正確な通知の徹底について
特別徴収の運用については、昨年度、年金保険者に対する依頼通知に一部誤りがあり、年金保険者において特例的な処理を行わざるを得ない事例がみられた(平成14年2月12日全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議資料32頁参照)ので、本年度の介護特別徴収依頼の通知に当たっては、年金保険者への通知が正確に行われるよう、年金保険者へのデータ回付前に抽出検査を行うなど、適切な事務処理の実施について改めて市町村に対し周知徹底をお願いしたい。
また、特別徴収対象被保険者が特別徴収の資格を喪失した場合には、介護保険法第138条及び介護保険法施行規則第155条の規定により、特別徴収義務者(年金保険者)に通知することとされており、当該通知については、毎月20日までに磁気媒体により通知していただいているところであるが、資格喪失の事由を設定する「各種区分」欄に「02(転出)」等の場合であっても「01(死亡)」と誤って設定されている事例が発生しているので、「介護保険料の年金からの特別徴収における情報交換媒体作成仕様書」に基づき、適正な情報を収録のうえ通知されるよう、管内市町村に対し周知願いたい。
オ 介護報酬の請求に係る消滅時効について
介護報酬の請求に係る消滅時効については、平成13年9月19日付事務連絡(「介護給付費請求書等の保管について」)及び平成14年3月1日付事務連絡(「介護報酬の請求に係る消滅時効の起算日について」)において、2年の消滅時効であり、その起算日はサービス提供日の属する月の翌々々月の1日としているところである。
制度施行当初の平成12年4月のサービスに係る時効期限が本年6月末に近づいているところから、各都道府県におかれては、管内市町村や事業者等への周知徹底について特段のご配慮をお願いしたい。
カ その他
次期介護報酬の見直しについては、現在、社会保障審議会介護給付費分科会において審議中であるが、その結果によっては各都道府県の「事業者台帳システム」の修正が必要になる可能性もあるものと考えている。このような場合を想定し、国としても14年度予算において、システム改修に対する補助金の交付を考えているところであり、都道府県におかれても、予算等の環境整備方よろしくお願いしたい。
<保険料滞納者に対する保険給付の制限等に係るQ&A vol.3>
1.保険給付の制限等について
保険料を滞納している第1号被保険者に係る保険給付の制限については、介護 保険法の規定により、
(1) 1年以上滞納の場合は、給付の償還払い化
(2) 1年半以上滞納の場合は、保険給付の支払の一時差し止め(控除)
(3) 2年以上滞納の場合は、保険給付の減額(9割→7割)、高額介護サービス費の不支給
という3段階の措置が実施されることになっているところである。
2.給付減額に係るQ&Aについて
保険料の徴収を開始して2年が経過することに伴い、本年10月末以降、保険料徴収権の消滅時効が完成し、各市町村においては給付額減額等の事務が生じてくることが想定されるが、その際の具体的な事務処理について、以下のとおりQ&Aを作成したので、事務の参考とされたい。
また、本件については、各サービス事業者の請求や国民健康保険団体連合会の審査支払にも影響を及ぼすものであるので、これらに対する周知方お願い申し上げる。
(公費負担医療との関係について)
| (問1)公費負担医療等の受給者(生活保護の被保護者を除く。)も給付額減額措置の対象となるが、介護保険の給付減額分は公費が負担することとなるのか。 |
(回答)
貴見のとおり。
(ホームヘルプサービス3%軽減措置と社会福祉法人の利用料軽減について)
| (問2)ホームヘルプサービスの利用料3%軽減や社会福祉法人の利用料軽減の対象者が給付額減額措置に該当する場合は、どのように取り扱うこととなるのか。 |
(回答)
給付額減額措置の対象者に対するホームヘルプサービスの利用者負担軽減の適用については、10%負担を3%負担とする軽減割合に鑑み、利用者負担は9%(30%×3/10)とする。また、社会福祉法人による利用料軽減の適用についても、基本的に利用者負担を2分のに軽減(30%→15%)することとなる。
なお、当該措置の対象となる被保険者の「訪問介護利用者負担額減額認定証」の「減額内容」欄には、「91/100」と記載することが適当である。
(住宅改修費及び福祉用具購入費について)
| (問3)給付額減額措置の対象者については、住宅改修費や福祉用具購入費の給付額も減額されることとなり、こうしたサービスを受領委任契約により現物給付化している場合には、減額して支払うことについてサービス提供事業者との間でトラブルが起きかねないと思われるが、その対応如何。 |
(回答)
サービス提供事業者と締結する受領委任契約の中に、被保険者証を確認すべきことを盛り込むことなどにより対応していただきたい。
(境界層措置について)
| (問4)生活保護との関係によりいわゆる境界層に既に該当し、保険料、食費負担又は高額介護サービス費について減額措置を受けている者が、給付額の減額措置の対象となった場合、既存の境界層該当証明書により、給付額減額措置の対象外としてよいか。 |
(回答)
より低い負担とすれば生活保護の対象とならない場合に当該より低い負担を適用するいわゆる境界層措置については、(1)給付額減額等、(2)食費負担、(3)高額介護サービス費、(4)保険料の順に優先して適用するとされているところである。
このため、御質問の事例では、明らかに境界層に該当する場合には新たな証明書は要せず、給付減額措置の対象外となると解されるが、それまでサービスを利用していなかった者の場合には、サービス利用により境界層該当ではなく、生活保護の要保護者となる可能性があるので、改めて福祉事務所に相談をさせる必要がある。
(市町村特別給付について)
| (問5)給付額減額措置の対象となるサービスには、市町村特別給付が含まれていない。市町村特別給付の給付割合が9割の場合、給付額減額措置の対象者について、9割の給付を実施してもよいのか。 |
(回答)
市町村特別給付は、その内容について法律上の規定はなく、条例に委ねられているところであり、給付額減額措置の趣旨を踏まえて、各市町村において判断すべきものである。
(記載日について)
| (問6)法第69条第3項に「当該記載(給付額減額等)を受けた日」とあるが、これは具体的にどの日となるのか。 |
(回答)
償還払い化の措置と同様、要介護認定等の申請があった際に交付する資格者証の有効期限の翌日とすることが適当と考えられる(平成13年7月30日付事務連絡問7参照)。
(月途中で消除要件に合致することとなった場合について)
| (問7)被保険者が介護保険法(以下「法」という。)第69条第2項に定める特別の事情に該当することが、月途中で明らかになった場合には、給付額減額措置は月途中で消除されることとなるのか。 |
(回答)
特別の事情に該当することになった月の初日に遡って(該当することになった日が月の初日であれば、その月から)給付減額等の記載を消除することが適当である。
なお、この場合、消除決定日(月の途中)以降月末までの当該者のサービス利用予定を市町村において確認することとし、決定日後サービスを利用しない場合には、事業者が給付額減額措置の記載が消除された被保険者証を確認できないため、7割分を請求する可能性が高いものであり、その場合には市町村において2割分を被保険者に償還して差し支えない。
(保険料軽減の場合について)
| (問8)保険料財源による市町村の単独減免により、軽減された保険料額を賦課されていた場合、納付すべき保険料額は、当該軽減された額により算定するのか。 |
(回答)
現金給付の形式など、実質的に負担を軽減するが保険料額自体を変えないものを除き、軽減された後の保険料額にて算定すべきものである。
(減額期間が1ヶ月未満となり、措置の対象とならなかった場合について)
| (問9)給付額減額期間を算定したところ、減額期間が1か月未満となり、当該措置の対象とはならなかった者について、その後、要介護更新認定(要介護区分状態の変更の認定等を含む)を行う際には、前回の算定に用いた徴収権消滅期間を算定対象としてよいか。 |
(回答)
介護保険法施行規則(以下「規則」という。)第111条第2項及び第3項において、過去に給付額減額の記載がなされた場合には、その際に算定した期間は算定の対象とされないこととされている。逆に、給付額減額の記載がなされなかった場合には、次の給付額減額期間の算定の対象となるものである。
(自立となった者の場合について)
| (問10)給付額減額期間中に自立となった者が、その減額期間中に再び要介護認定を受けるときは、残りの減額期間が終了するまでは、新たな給付額減額期間を計算しないことでよいか。 |
(回答)
規則第111条第1項において、既に給付額減額等の記載を受けており、要介護認定等の時点で給付額減額期間が経過していない要介護被保険者等について要介護認定等を行う場合には、給付額減額期間の再計算を行わないこととされていることから、自立であった者についても新たな減額期間は計算しないこととすることが適当であると解される。
(年度をまたぐ賦課について)
| (問11)ある年度分の保険料を翌年度に賦課された(調定日から納期限までの間に年度をまたぐ)場合、給付額減額期間の算定に当たって、当該保険料は、どちらの年度に納付する保険料とすべきか。 |
(回答)
納期限が属する年度に納付する保険料とすべきである。
(納付猶予と算定期間の関係について)
| (問12)徴収権消滅期間や保険料納付済期間の算定に当たっては、納期が到来してから10年以上経過したものは算定の対象としないとしているが、納付猶予により納期を延長した場合は、延長後の納期から10年を算定することでよいか。 |
(回答)
貴見のとおり。
(督促状の発出について)
| (問13)保険料の延滞に係る督促状の発出は、時効の中断の効力を有するが、時効の進行はいつから再開するのか。また、督促状を送る際に、期日を記載して発出するが、納期到来から10年間以内か否かを確認するときは、ここに記載された期日から起算すると解してよいか。 |
(回答)
督促状が被保険者に届いた日の翌日から進行することとなる。また、督促状に記載された期日は、納期限を猶予したものではないので、本来の納期限から起算して10年間に該当するかを判断すべきである。
(滞納保険料の一部支払いについて)
| (問14)滞納保険料の一部を支払った場合、支払った時点で消滅時効が中断すると解してよいか。また、その年度のすべての保険料について時効が中断するのか。 |
(回答)
滞納保険料の一部を支払うことは、納付の意思表示であり、民法第147条第3号に規定する「承認」であると解釈されることから、納付があった時点で、支払った一部保険料の納期分に係る保険料については、時効が中断する。なお、納付日の翌日から、時効は再度進行することとなる。
(賦課権の期間制限について)
| (問15)保険料の賦課権の期間制限は2年と解してよいか。また、賦課権の期間が2年であれば、2年以上遡って資格取得を行った場合には、2年以上前の保険料は賦課することができないが、給付額減額期間の算定の対象とはならないのか。 |
(回答)
保険料の徴収権は、2年の消滅時効が適用されるのに対し、徴収の前段階である賦課決定や更正については、法律上、期間についての定めがなされていないが、賦課権についても、消滅時効の期間等に鑑み、2年の期間制限によるものと解される。
したがって、賦課期日現在に被保険者である場合には第1納期日の翌日から、賦課期日時点で被保険者資格を取得していない場合には保険料を賦課することができるようになった日の翌日から、それぞれ2年以上経過した後は、当該年度の保険料についての賦課権が存在しないため、そもそも保険料徴収権が発生しておらず、給付額減額期間の算定の対象とはならない。
長期入院患者に係る給付の見直し
1 基本的な考え方
○ 長期療養患者への医療の確保を図りつつ、入院医療の必要性が低いが、患者側の事情により長期にわたり入院している患者への対応として、特定療養費制度を活用して給付の在り方を見直す。
2 具体的な仕組み
(ア)対象者
○ 療養病床等に6ヶ月を超えて入院している者
※ ただし、難病患者、精神疾患患者、結核患者などを除く。
(イ)入院基本料の特定療養費化
○ 入院基本料に係る保険給付の範囲を見直す。
| (1) 難病患者等 長期にわたる 療養が必要な者 |
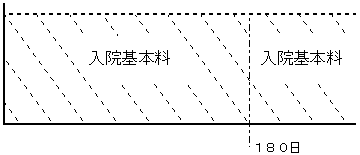 |
| (2) 入院医療の必要性が低い者 |
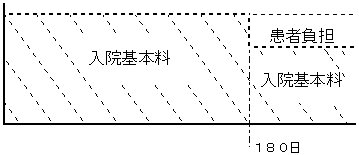 |
入院基本料の特定療養費化に関する経過措置
(1)平成14年3月31日に入院している患者
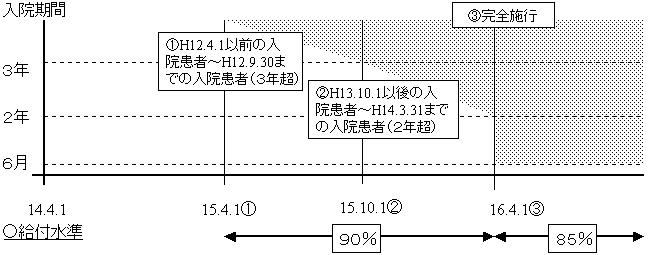
(2)平成14年4月1日以降に入院した患者(180日以上)
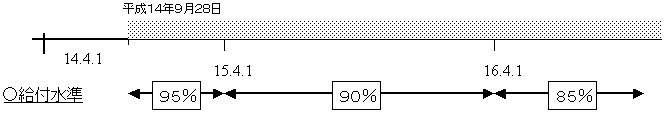
○ 特定療養費の対象外となる患者
平成14年3月18日 保医発第0318001号
『「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の制定に伴う実施上の留意事項について』第3の11(抄)
| 状態等 | 診療報酬点数 | 実施の期間等 |
| 1 難病患者等入院診療加算を算定する患者 | 難病患者等入院診療加算 | 当該加算を算定している期間 |
| 2 重症者等療養環境特別加算を算定する患者 | 重症者等療養環境特別加算 | 当該加算を算定している期間 |
| 3 重度の肢体不自由者、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等 (注1参照) |
左欄の状態にある期間 | |
| 4 悪性新生物に対する腫瘍用薬(重篤な副作用を有するものに限る。)を投与している状態 (注2参照) |
動脈注射 | 左欄治療により、集中的な入院加療を要する期間 |
| 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入 | ||
| 点滴注射 | ||
| 中心静脈注射 | ||
| 骨髄内注射 | ||
| 5 悪性新生物に対する放射線治療を実施している状態 | 放射線治療 (エックス線表在治療又は血液照射を除く。) |
|
| 6 ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態 (注3参照) |
ドレーン法(ドレナージ) | 当該月において2週以上実施していること |
| 胸腔穿刺 | ||
| 腹腔穿刺 | ||
| 7 人工呼吸器を使用している状態 | 間歇的陽圧吸入法 | 当該月において1週間以上使用していること |
| 人工呼吸 | ||
| 8 人工腎臓又は血漿交換療法を実施している状態 | 人工腎臓 | 各週2日以上実施していること(注4) |
| 血漿交換療法 | 当該月において2日以上実施していること | |
| 9 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し、当該疾病に係る治療を継続している状態 (当該手術を実施した日から起算して30日までの間に限る。) |
脊椎麻酔 | |
| 開放点滴式全身麻酔 | ||
| マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 |
| 注 | 1 |
3の左欄に掲げる状態等にある患者は具体的には以下のような状態等にあるものをいうものであること。 a 重度の肢体不自由者、脊髄損傷等の重度障害者及び重度の意識障害者 b 以下の疾患に罹患している患者 筋ジストロフィー、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン舞踏病、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上でかつ生活機能症度II度又はIII度のものに限る。)、シャイ・ドレーガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病及び亜急性硬化性全脳炎 c 重度の肢体不自由者については、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日老健第102−2号)においてランクB以上に該当するものが対象となるものであり、ランクB以上に該当する旨を診療報酬明細書に記載すること。 |
| 2 | 4の「重篤な副作用を有するもの」とは、肝障害、間質性肺炎、骨髄抑制、心筋障害等の生命予後に影響を与えうる臓器障害を有する腫瘍用薬であること。 | |
| 3 | 6に係る胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した場合は、当該胸腔穿刺又は腹腔穿刺に関し洗浄を行った旨を診療報酬明細書に記載すること。 | |
| 4 | 8の「人工腎臓を実施している状態」にある患者については、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日老健第102−2号)においてランクB以上に該当するものが対象となるものであり、ランクB以上に該当する旨を診療報酬明細書に記載すること。 | |
| 5 | 医薬品等告示第4号ルに規定する「ロからヌまでに掲げる状態に準ずる状態にある患者」に関する事項は、入院医療の必要性についての医学的な判断基準という観点から検討の上、別途通知する。 |
財政安定化基金貸付金の状況
| (金額の単位:百万円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険事業状況報告からみた
都道府県別の給付状況(平成13年11月分)
※ 以下のグラフは、事業状況報告月報の暫定版より作成したものであり、全体の傾向をみるものとして作成。
1−(1) 第一号被保険者1人あたり支給額
○ 居宅支給額にはばらつきがあり、施設支給額の高い都道府県が全体で上位になっている。
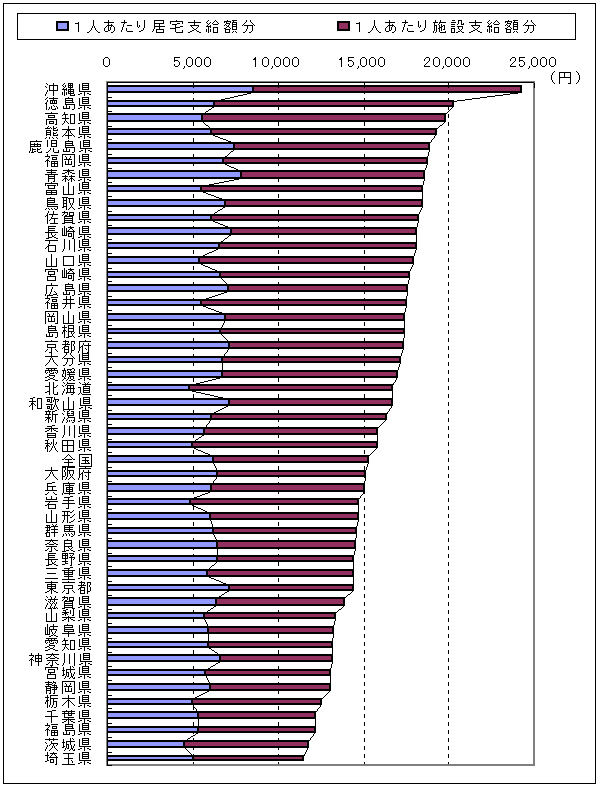
1−(2) 第1号被保険者に対する受給者割合と受給者1人あたり支給額
○ 支給額の高い都道府県には、受給者割合の高いものと1人あたり支給額の高いものがある。
|
第一号被保険者に対する受給者割合
|
受給者1人あたり支給額
|
1−(3) 受給者割合と1人あたり支給額の関係
○ 支給額の高い都道府県には、一人あたり支給額の高いもの(高知、富山)、受給者割合の高いもの(徳島、青森、鹿児島)、両方の傾向があるもの(沖縄)がある。
|
第一号被保険者に対する受給者割合と受給者1人あたり支給額との関係
|
2−(1) 認定者と受給者の割合
○ 認定者の割合が高いところは、概して受給者の割合が高く、また、居宅受給者の割合も高い。
|
第一号被保険者に対する認定者と受給者割合
|
2−(2) 認定者割合と受給者割合の関係
○ 認定済み未利用者の割合にはばらつきが少ない。
|
第一号被保険者に対する認定者割合と受給者割合の関係
|
3.高齢化の状況と認定者割合
○ 高齢化の状況と認定者割合は相関が低い。
|
第一号被保険者に対する認定者と後期高齢者加入率との関係
前期と後期高齢者の認定者割合の関係
|
4.要介護度別の出現率
○ 重度の要介護度の分布は一定であり、認定者が多い都道府県では軽度の要介護者が多くなっている。
|
第一号被保険者に対する要介護度別出現率
|
第一号被保険者に対する要介護度別出現率
|
(注)上記は認定者割合全体の高い順である。
5−(1) 1人あたり居宅支給額と施設支給額
○ 受給者1人あたり支給額の高い都道府県は、施設支給額の高いところが多い。
|
受給者1人あたり支給額
|
5−(2) 受給者1人あたり支給額と施設受給者割合
○ 施設受給者割合の高い都道府県では受給者1人あたり支給額が高くなっている。
|
受給者1人あたり支給額と施設受給者割合との関係
|
被保険者1人当たり給付費(各都道府県と全国との比較2001年11月分)
○以下は、各国保連の支払実績、及び事業状況報告(月報)から、各都道府県別・サービス別の給付状況(全国平均を100とした場合の指数)を示したものである。
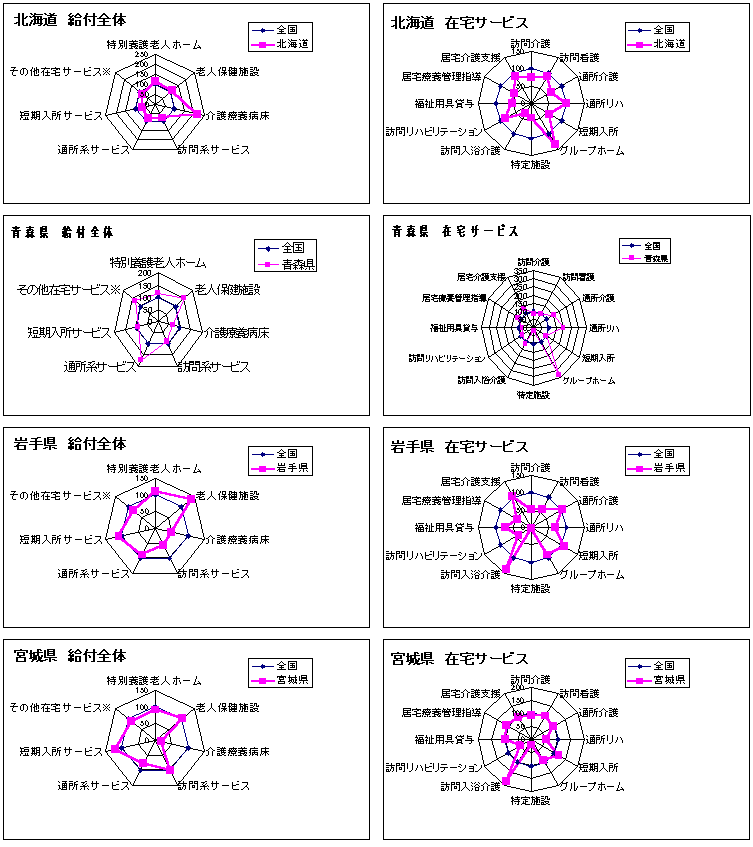
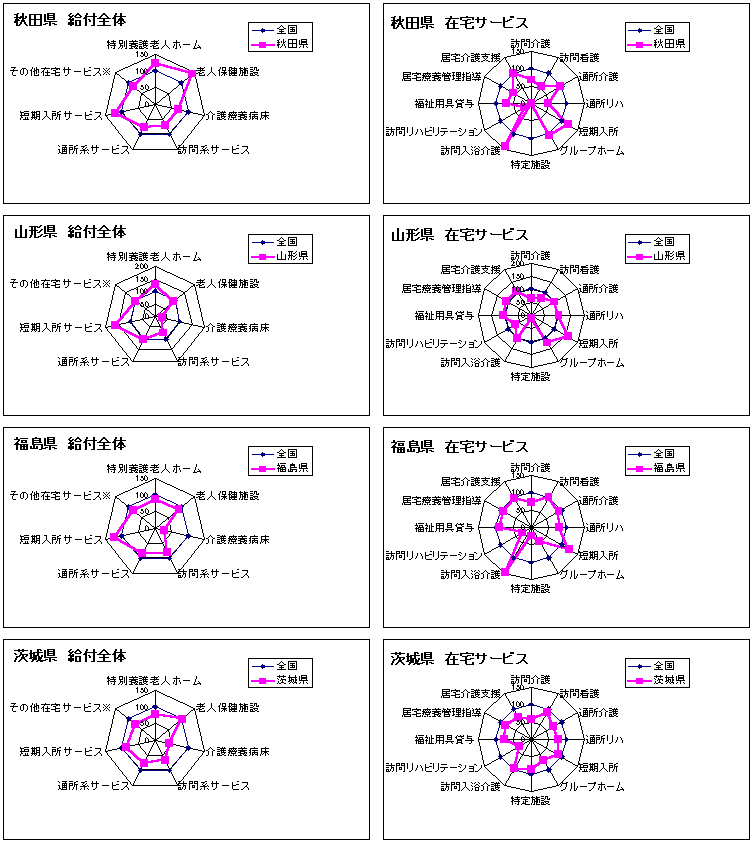
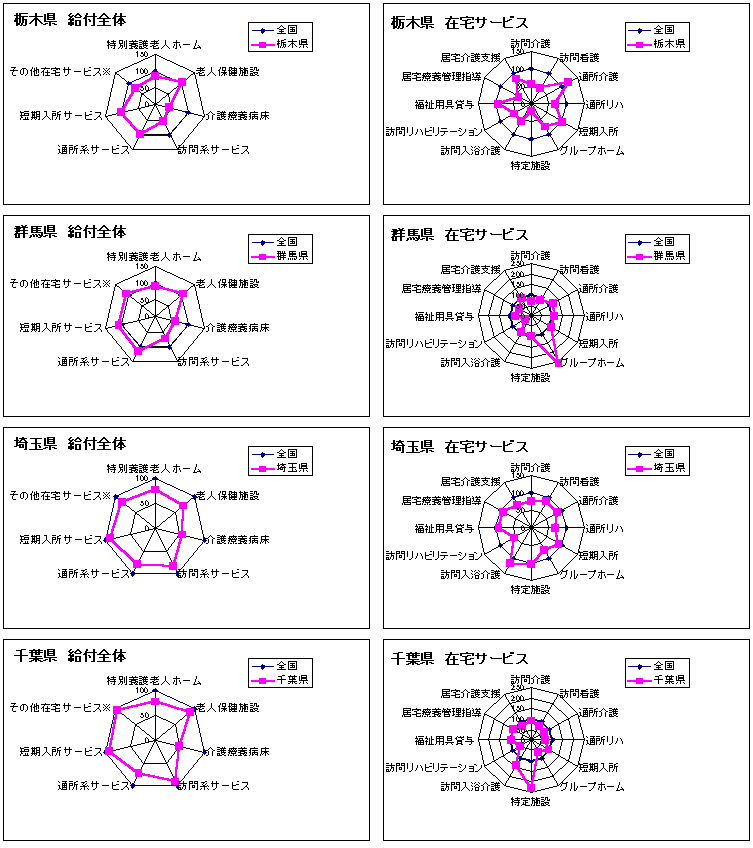
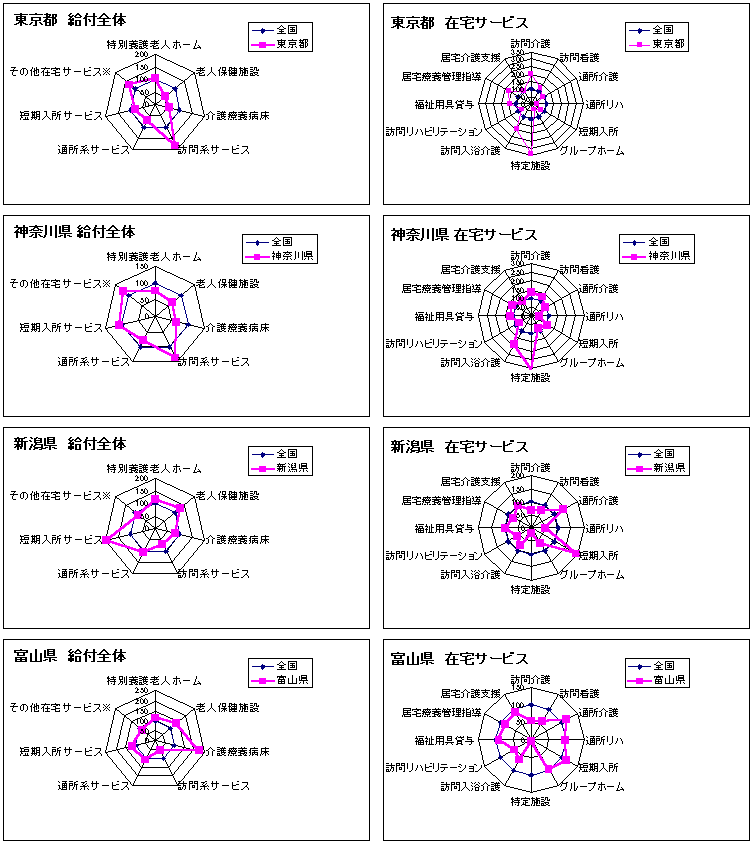
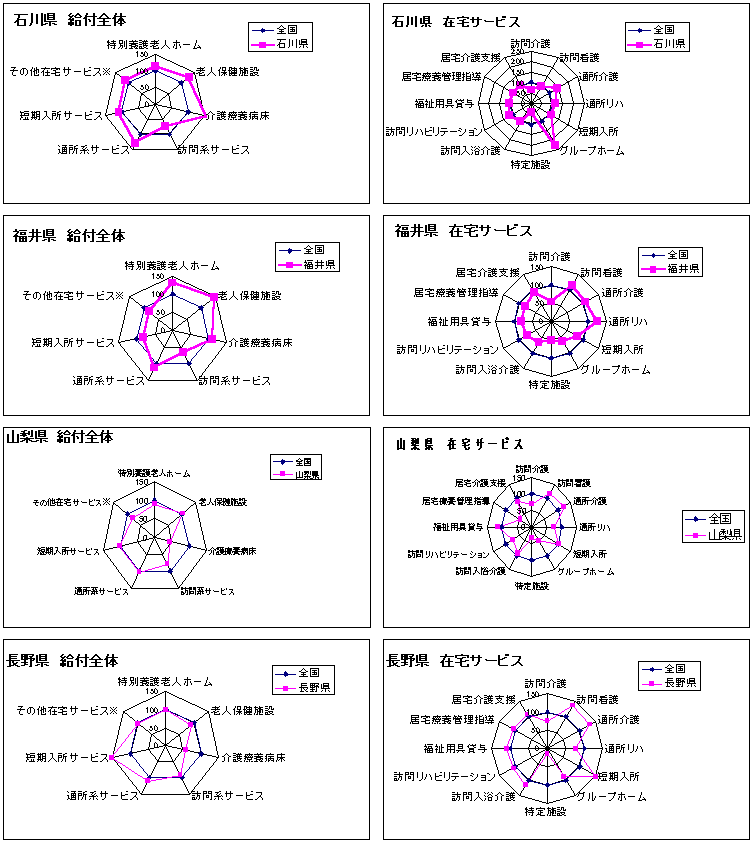
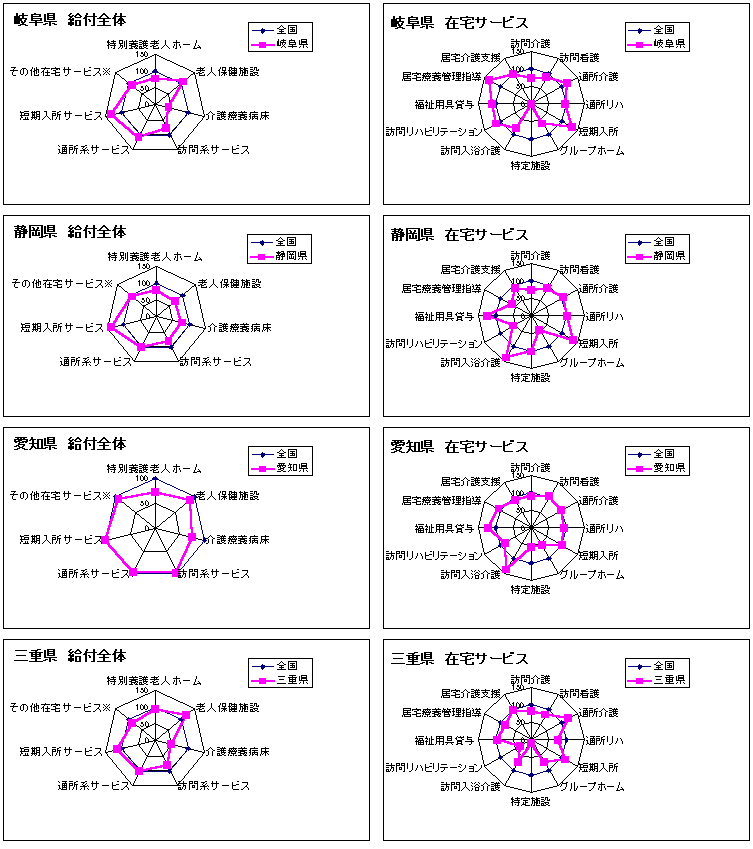
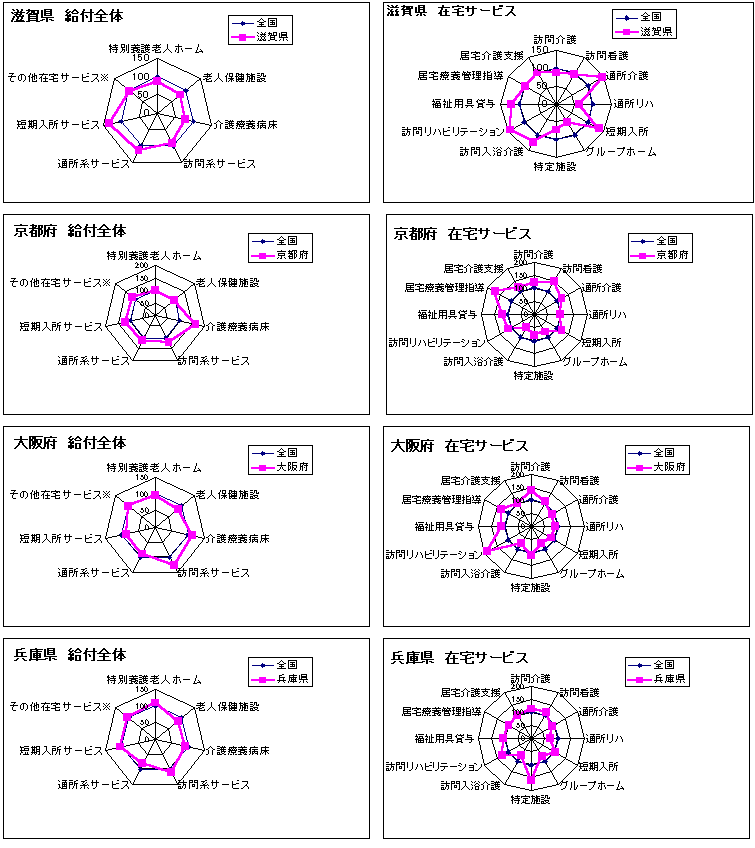
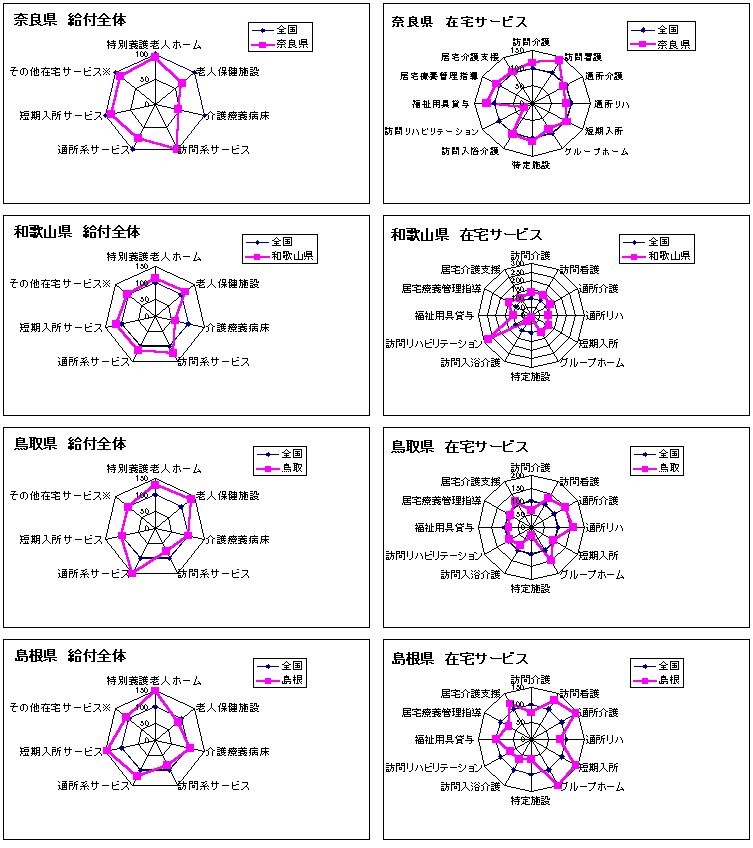
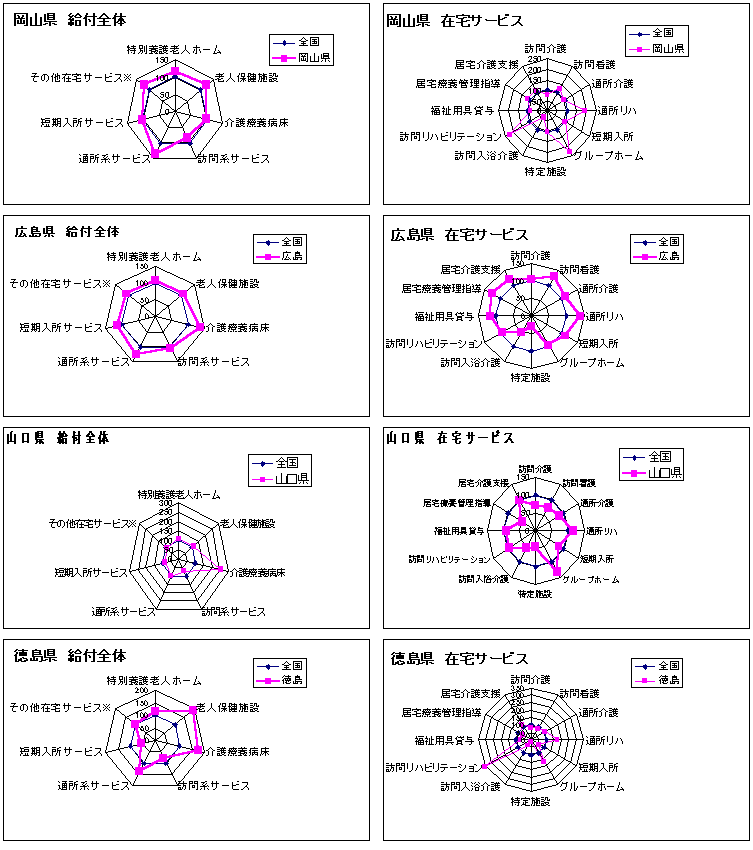
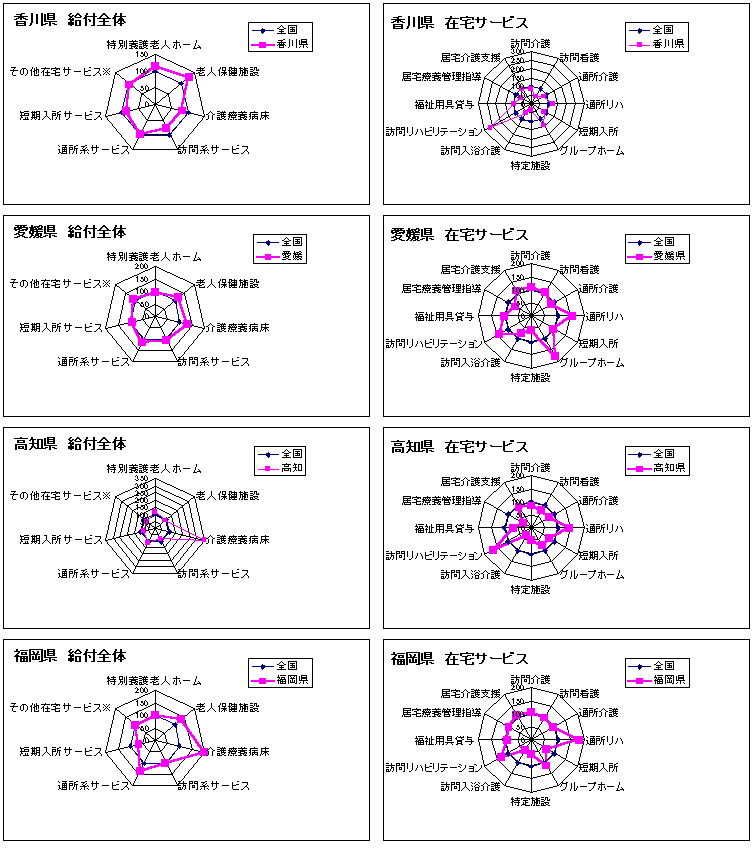
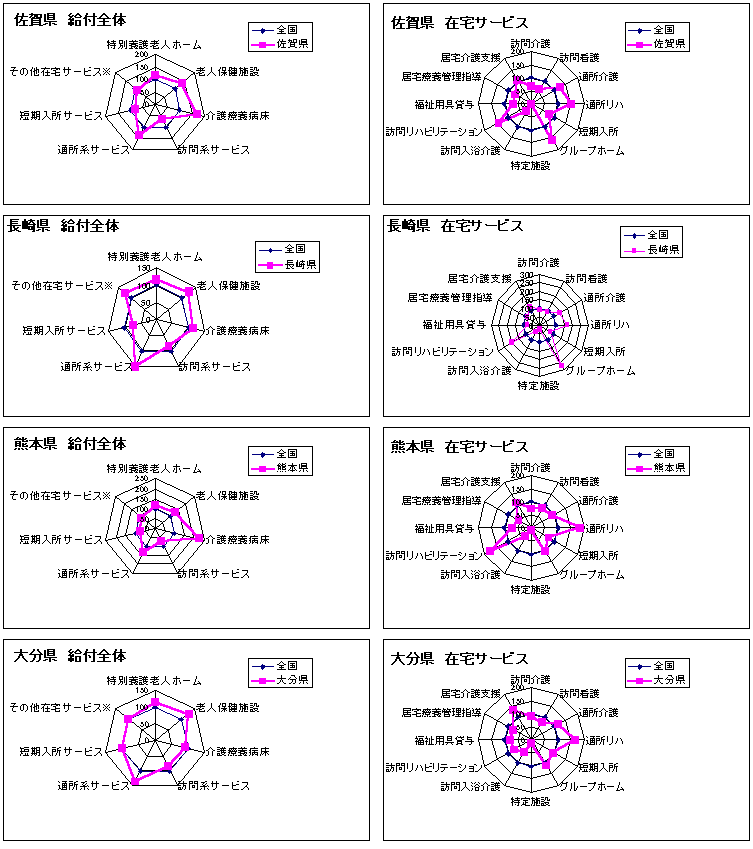
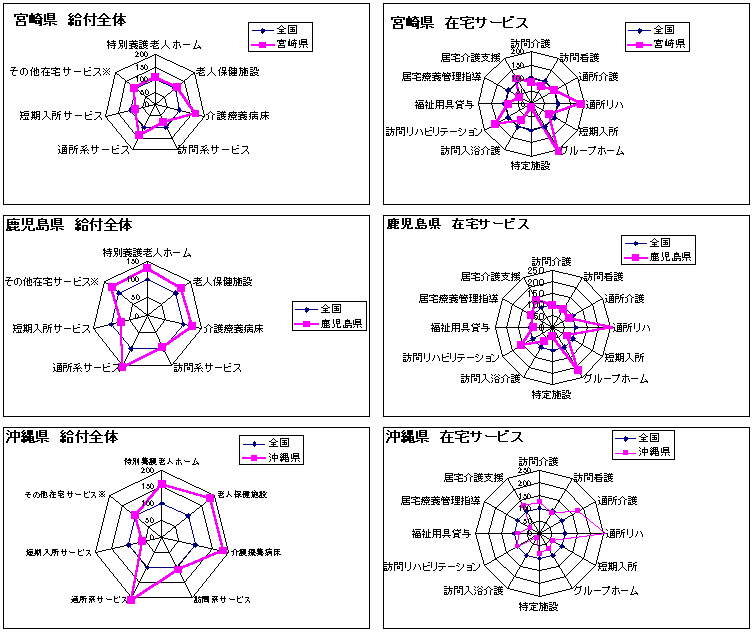
※「その他在宅サービス」福祉用具貸与、居宅療養管理、グループホーム、特定施設、居宅介護支援
市町村における実施状況(平成14年4月1日現在)
| 調査時点:平成14年4月1日現在 調査対象:全国3,241市町村(回答率100%) |
1.保険料
○保険料を「6段階」で設定している市町村は11市町
(千葉県流山市、神奈川県横浜市、京都府亀岡市・京北町・園部町・丹波町・ 日吉町・瑞穂町・和知町、大宮町、和歌山県南部町)
○低所得者に対する単独減免の実施状況
低所得者への単独減免を実施している市町村数は431(全体の13.3%)であり、このうち「個別申請により判定」「減額のみ」「保険料財源」といういわゆる3原則の範囲内で行っている市町村数は314。
昨年10月1日現在(309市町村が実施)からの増加数は、122市町村であるが3原則遵守の増加数は123市町村と多くなっている。
(参考)
| 調査時点 | 単独減免実施市町村数 (A) |
うち3原則遵守市町村 (B) |
B/A |
| 12年10月1日現在 | 72市町村 | 4市町村 | 5.6% |
| 13年4月1日現在 | 139市町村 | 43市町村 | 30.9% |
| 13年10月1日現在 | 309市町村 | 191市町村 | 61.8% |
| 14年4月1日現在 | 431市町村 〔122(100%)〕 |
314市町村 〔123(100.8%)〕 |
72.9% |
2.給付
(1)市町村特別給付[%は全市町村に対する割合(以下の項目について同様)]
| 実施市町村数 76(2.3%) | ||
| 内訳 (重複あり) |
寝具乾燥サービス | 10 |
| 移送サービス | 16 | |
| 配食サービス | 10 | |
| おむつの支給 | 47 | |
| その他 | 30 ※ | |
※「その他」の中には、訪問理美容等がある。
(2)基準該当居宅サービス
| 実施市町村数 477(14.7%) | ||
| 内訳 (重複あり) |
居宅介護支援 | 165(5.1%) |
| 訪問介護 | 241(7.4%) | |
| 訪問入浴 | 97(3.0%) | |
| 通所介護 | 167(5.2%) | |
| 福祉用具貸与 | 105(3.2%) | |
| 短期入所生活介護 | 98(3.0%) | |
| 同居家族へのヘルパー派遣 | 32(1.0%) | |
(3)相当サービス
| 実施市町村数 | 19(0.6%) |
相当サービス:離島等地域における通所介護など
(4)保健福祉事業
| 実施市町村数 317(9.8%) | ||
| 内訳 (重複あり) |
高額介護サービス貸付 | 242 |
| 介護予防教室 | 55 | |
| その他 | 61 | |
※「その他」の中には、住宅改修費の貸付等がある。
(5)バウチャー
| 実施市町村数 | 9(0.3%) |
バウチャー方式による住宅改修費、福祉用具購入費等の支給。
(6)受領委任方式
| 採用市町村数 532(16.4%) | ||
| 内訳 (重複あり) |
高額介護サービス費(施設) | 284 |
| 福祉用具購入 | 234 | |
| 住宅改修 | 279 | |
| その他 | 59 | |
※「その他」の中には、特例居宅介護サービス費等がある。
3.利用者負担の軽減施策
| 高齢ヘルパー利用者の軽減措置 | 3,213(99.1%) | |
| 障害ヘルパー利用者の軽減措置 | 2,487(76.7%) | |
| 社会福祉法人の軽減措置 | 2,376(73.3%) | |
| 対象者拡大(注1)を実施 | 763(23.5%)注2 | |
| 離島等地域における減額措置 | 295( 9.1%) | |
| 市町村単独の軽減措置 | 825(25.5%) | |
| (参考) | 社会福祉法人の軽減措置については、平成13年4月1日時点で2,235(68.8%) |
| 注1 | 平成12年末、本措置の対象者を第1号被保険者の2%程度から1割程度に拡大。 |
| 注2 | 社会福祉法人の軽減措置を実施している市町村に対する割合は32.1% |
4.市町村独自の施策
(1)支給限度基準額の上乗せ
| 実施市町村数 19(0.6%) | ||
| 内訳 (重複あり) |
居宅サービス区分 | 13 |
| 福祉用具購入 | 0 | |
| 住宅改修 | 8 | |
(2)種類支給限度基準額
| 実施市町村数 7(0.2%) | ||
| 内訳 (重複あり) |
訪問介護 | 3 |
| 訪問入浴介護 | 1 | |
| 訪問看護 | 0 | |
| 訪問リハビリ | 0 | |
| 通所介護 | 2 | |
| 通所リハビリ | 0 | |
| 短期入所生活介護 | 3 | |
| 短期入所療養介護 | 1 | |
| 福祉用具貸与 | 1 | |
5.介護予防・生活支援事業
(1)高齢者等の生活支援事業
| 事業名・実施市町村数 | ||
| 配食サービス | 2,516(77.6%) | |
| 外出支援サービス | 1,815(56.0%) | |
| 寝具類洗濯等サービス | 1,622(50.0%) | |
| 軽度生活援助事業 | 2,273(70.1%) | |
| 住宅改修支援事業 | 2,485(76.7%) | |
| 住宅改修理由書作成の委託助成 | 2,508(77.4%) | |
| 訪問理美容サービス事業 | 844(26.0%) | |
| 高齢者共同生活支援事業 | 41( 1.3%) | |
(2)介護予防・生きがい活動支援事業
| 事業名・実施市町村数 | ||
| 介護予防事業 | 1,771(54.6%) | |
| 転倒骨折予防教室 | 1,532(47.3%) | |
| 痴呆予防・介護事業 | 912(28.1%) | |
| IADL訓練事業 | 537(16.6%) | |
| 地域住民グループ支援事業 | 464(14.3%) | |
| その他事業 | 108( 3.3%) | |
| 高齢者食生活改善事業 | 860(26.5%) | |
| 運動指導事業 | 372(11.5%) | |
| 生きがい活動支援通所事業 | 2,811(86.7%) | |
| 生活管理指導事業 | 1,821(56.2%) | |
| 生活管理指導員派遣事業 | 1,261(38.9%) | |
| 生活管理指導短期宿泊事業 | 1,634(50.4%) | |
| 食の自立支援事業 | 115( 3.5%) | |
(3)家族介護支援事業
| 事業名・実施市町村数 | |
| 痴呆高齢者家族やすらぎ支援事業 | 37( 1.1%) |
| 家族介護教室 | 1,442(44.5%) |
| 介護用品の支給 | 2,238(69.1%) |
| 家族介護者交流事業 | 1,194(36.8%) |
| 家族介護者ヘルパー受講支援事業 | 440(13.6%) |
| 徘徊高齢者家族支援サービス事業 | 381(11.8%) |
| 家族介護慰労事業 | 2,006(61.9%) |
(4)緊急通報体制等整備事業
| 事業名・実施市町村数 | |
| 緊急通報体制等整備事業 | 2,670(82.4%) |
(5)成年後見制度利用支援事業
| 事業名・実施市町村数 | |
| 成年後見制度利用支援事業 | 342(10.6%) |