精神障害者の退院促進
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課
我が国の精神病床数の状況
○ 我が国の精神病床数は、約35万床。精神病床入院患者数は、約32万人。
○ 人口当たりの精神病床数は、諸外国においてはここ数十年で病床削減・地域生活支援強化等の施策を通じて減少 しているのに対し、我が国では、概ね横ばい状態であり、かつ、諸外国を大幅に上回っている。
【人口当たり精神病床数(OECD)】
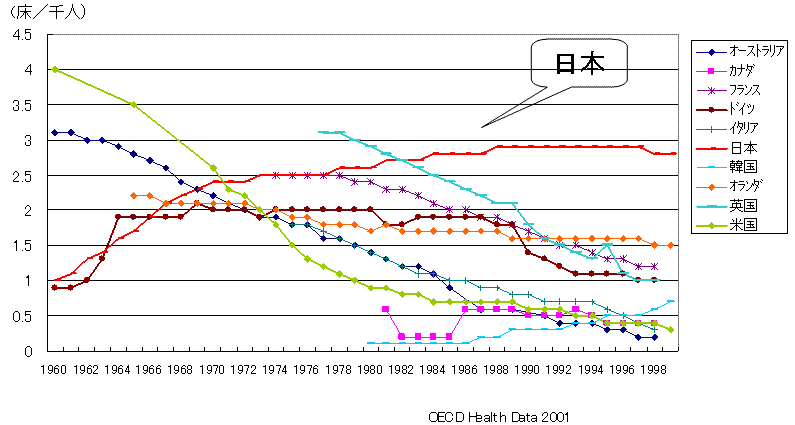
受入条件が整えば退院可能な入院期間別患者数
受入条件が整えば退院可能な精神入院患者は約7万人であるが、入院期間から見ると、その約半数は入院3年未満(この傾向は、ここ数年ほぼ変化なし)
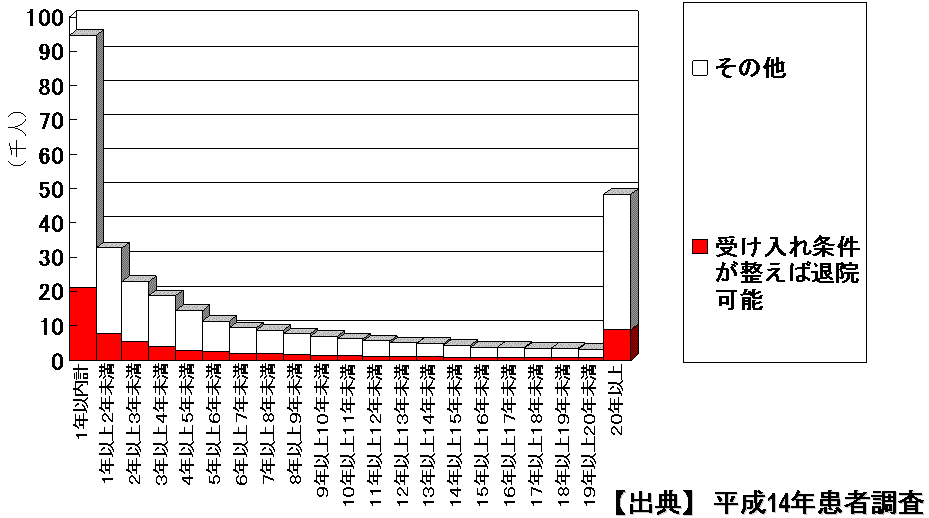
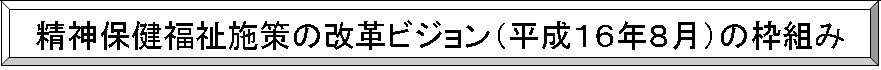
| 精神保健福祉施策について、「入院医療中心から地域生活中心へ」改革を進めるため、 [1]国民の理解の深化、[2]精神医療の改革、[3]地域生活支援の強化を今後10年間で進める。 |
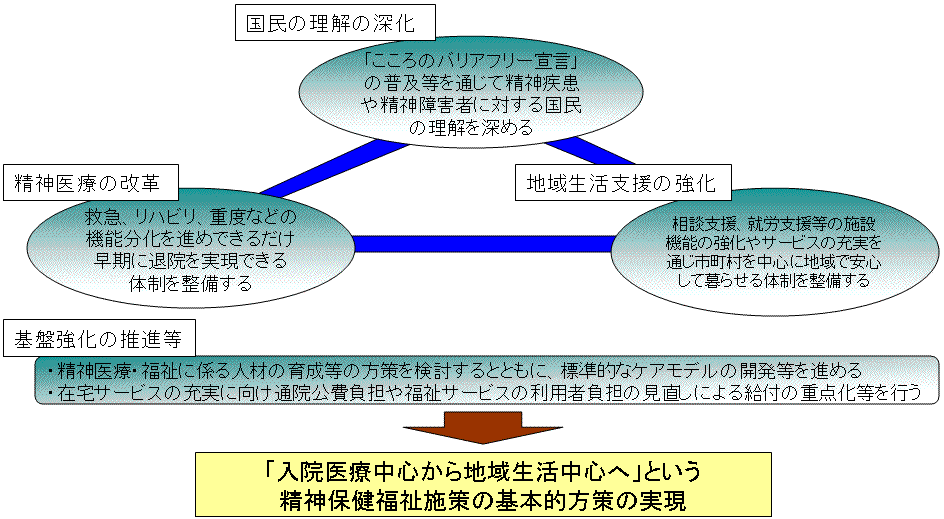
※上記により、今後10年間で必要な精神病床数の約7万床減少を促す
精神保健医療福祉の改革ビジョンと障害者自立支援法
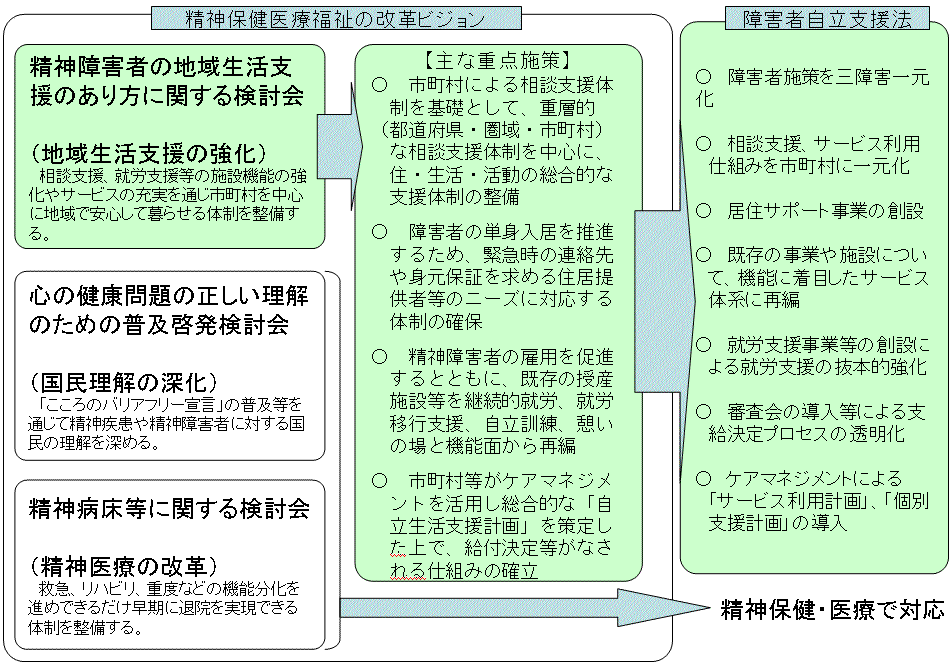
相談支援事業とサービス利用について
障害者のニーズに応じて、支援を効果的に実施するための仕組み(ケアマネジメント)を制度化。
(1)一人一人の利用者が、必要に応じて支援を受けられるよう、市町村の必須事業(地域生活支援事業)として相談支援事業を位置付け、これを相談支援事業者に委託できるようにする。
(2)特に計画的な支援を必要とする者を対象として、サービス利用のあっせん・調整などを行うための給付(サービス利用計画作成費)を制度化。
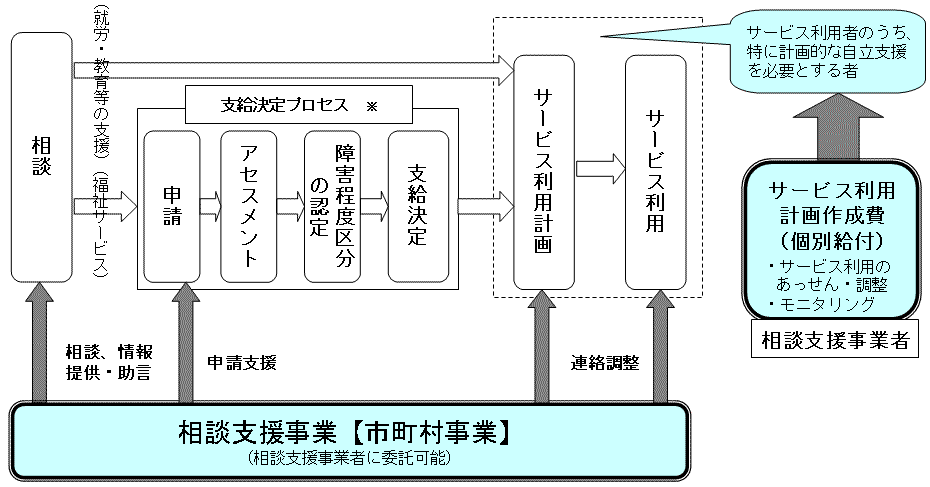
※支給決定事務の一部(アセスメント等)について、市町村から相談支援事業者へ委託可能。
相談支援体制の整備について(イメージ)
○ 新制度において、相談支援事業を市町村に一元化することとしているが、直ちに、市町村では十分な体制を確保できない場合も想定されることから、次のとおり、都道府県が積極的に支援を行う。
- 相談支援に係る専門的職員を市町村に配置
- アドバイザーの派遣を通じ、圏域ごとのネットワークづくり、困難ケースへの対応等を支援
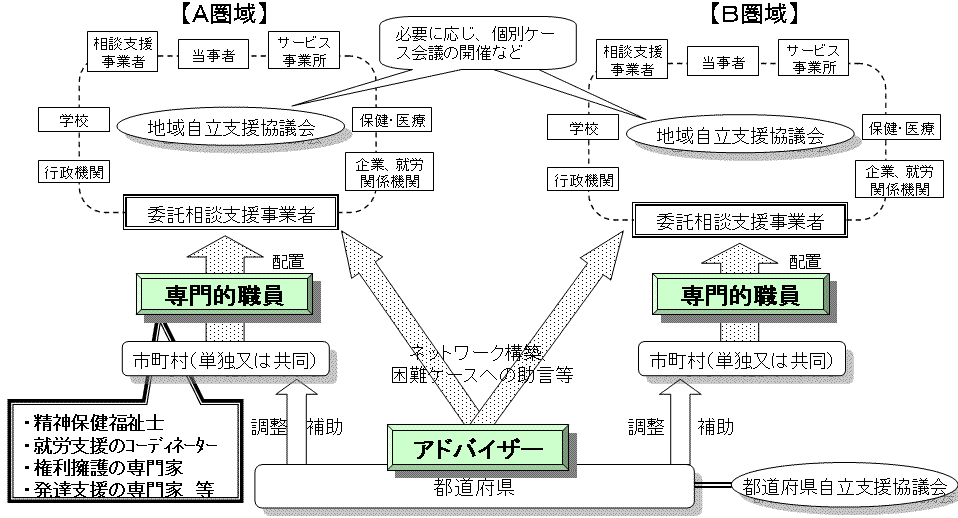
地域自立支援協議会
【概要】
市町村が、相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関し、中核的役割を果たす協議の場として設置する。[交付税]
【実施主体】
市町村(複数市町村による共同実施可)
【構成メンバー】
相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療、学校、企業、高齢者介護等の関係機関、障害当事者団体、権利擁護関係者、地域ケアに関する学識経験者 等
【主な機能】
[1] 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
[2] 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
[3] 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保(事業評価)
[4] その他(市町村障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議など)
【地域の実情に応じた運営】
- 権利擁護等の分野別のサブ協議会(部会等)を設置するなど、地域の実情に応じた多様なかたちで実施
- 運営を指定相談支援事業者に委託
都道府県自立支援協議会
【概要】
都道府県全体における相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関し、主導的役割を果たす協議の場として設置する。[交付税]
【実施主体】
都道府県
【構成メンバー】
相談支援事業者、学識経験者、市町村 等
【主な機能】
[1] 都道府県内の市町村又は圏域(地域自立支援協議会単位)ごとの相談支援体制の状況を把握・評価し、整備方策等を助言
[2] 相談支援従事者の研修のあり方を協議
[3] 専門的分野における支援方策について情報や知見を共有、普及
[4] その他(都道府県障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議など)
都道府県相談支援体制整備事業
(アドバイザー派遣)
【概要】
都道府県に、相談支援に関する広域的支援を行うアドバイザーを配置する。[補助金]
【実施主体】
都道府県
【事業の具体的内容】
- 地域のネットワーク構築に向けた指導、調整
- 地域では対応困難な事例に係る助言
- 地域における専門的支援システムの立ち上げ援助
(例:権利擁護、就労支援などの専門部会) - 広域的課題・複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援
- 地域の相談支援従事者のスキルアップに向けた指導
- 地域の社会資源(インフォーマルなものを含む)の点検、開発に関する援助 等
【アドバイザーの担い手】
- 地域における相談支援体制整備について実績を有する者
- 相談支援事業に従事した相当期間の経験を有する者
- 障害者支援に関する高い識見を有する者
【都道府県自立支援協議会との関係】
配置するアドバイザーの職種や人員等について協議
精神障害者社会復帰施設の新体系サービスへの移行について
○ 地域生活支援センター、福祉ホーム(A型)については、平成18年10月から新体系へ移行。
○ 上記以外の精神障害者社会復帰施設については、現在の利用者の状況、人員配置等の基準等に照らし、新体系に直ちに移行することが困難と思われることから、経過措置の対象とする。
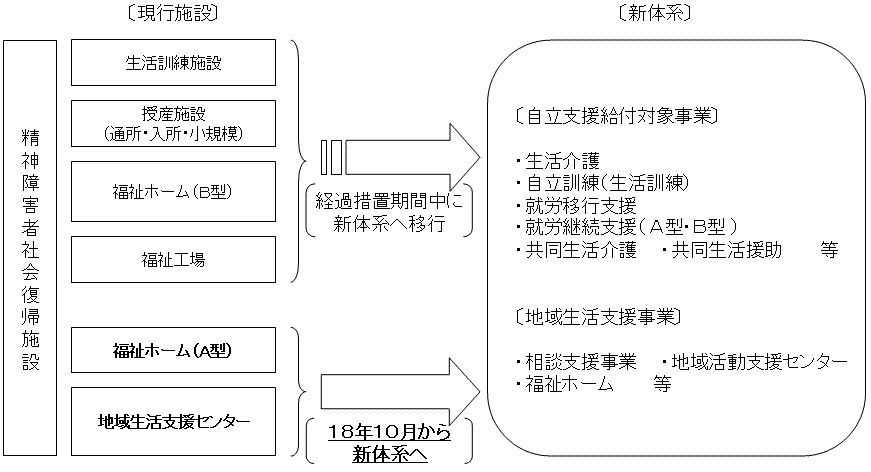
精神障害者地域生活支援センターの移行
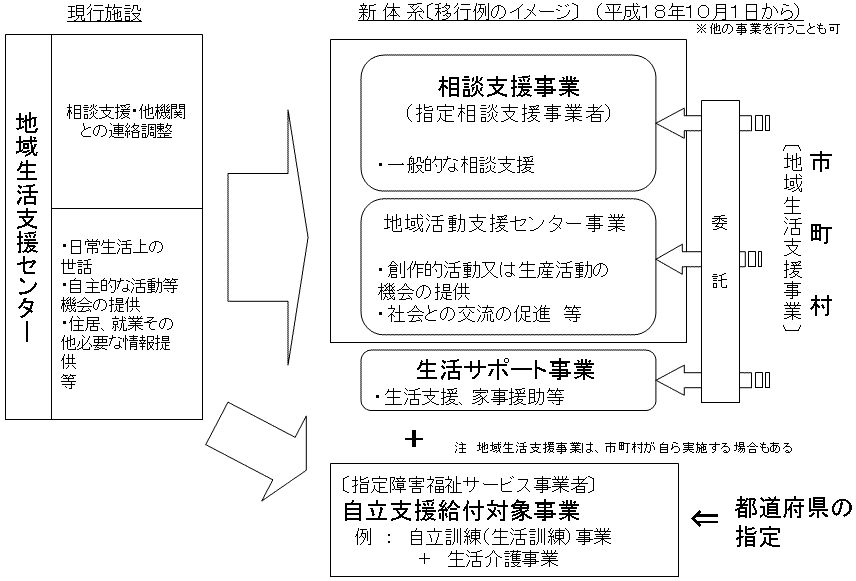
精神障害者福祉ホーム(A型)の移行
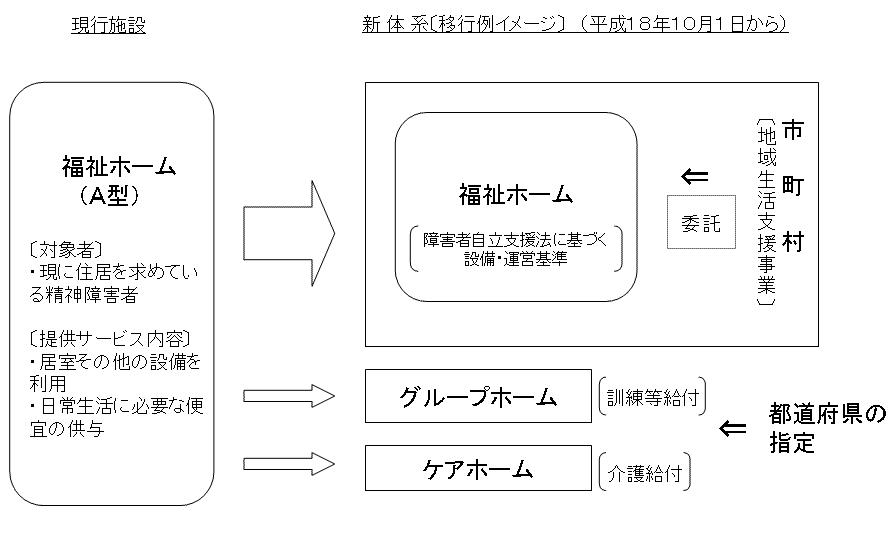
社会復帰施設の新体系(個別給付サービス)への移行について
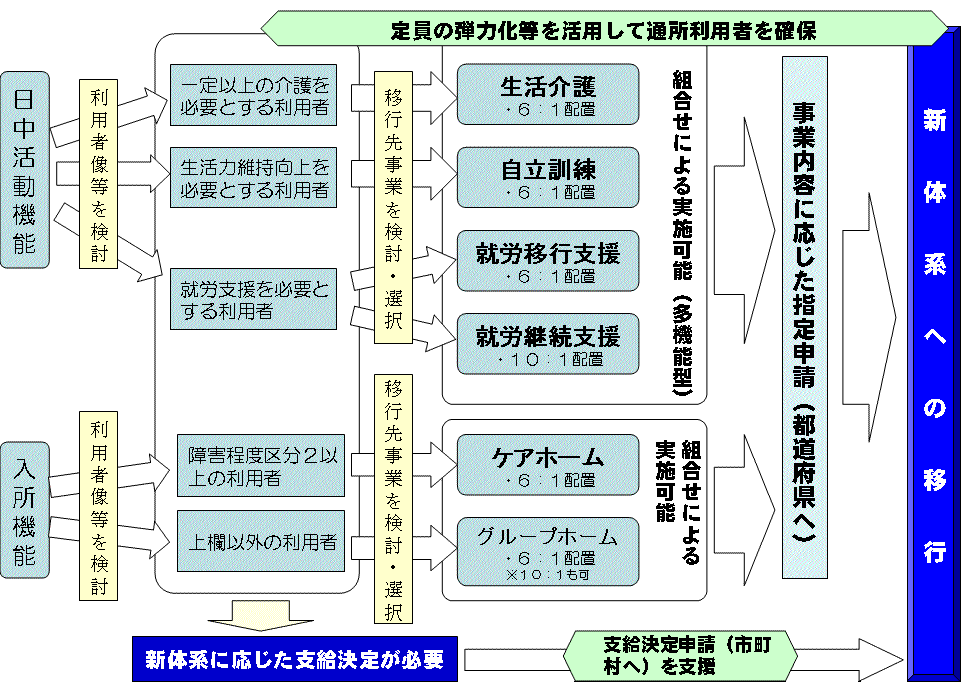
精神障害者退院支援施設について
【ポイント】
[1] 精神病床の削減(定員と同数の病床数を削減)[2] 入院治療が不要な者の明確化
[3] 地域移行に向けた適切な支援と開かれた施設運営
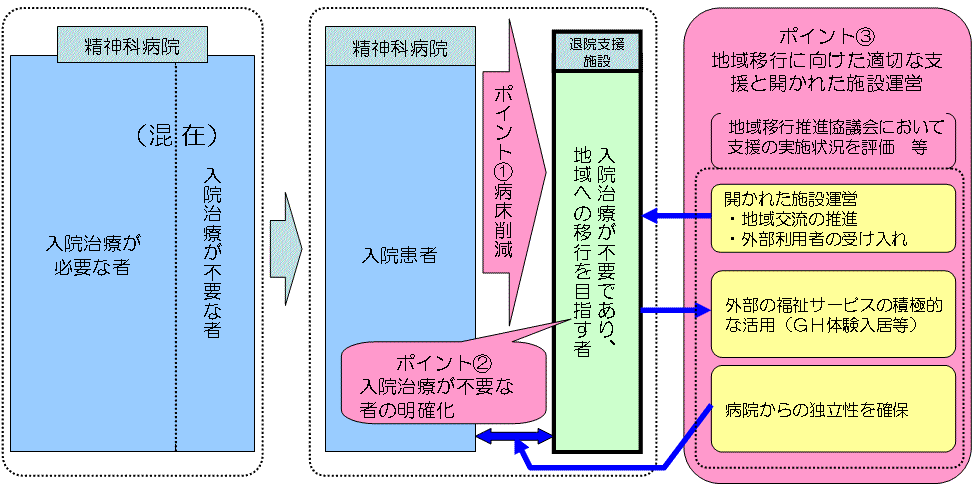
精神障害者退院支援施設の概要(案)
| 精 神 障 害 者 退 院 支 援 施 設 | ||
| 病棟設備を転用する場合 | 外で設置する場合 | |
| 法律位置付け | 自立訓練(生活訓練)、就労移行支援の加算事項 | |
| 定員規模 | 20人以上60人以下 | 20人から30人程度 |
| 居 室 | ○1室当たり4人以下 ○1人当たり床面積 : 6m2以上 |
○原則として個室 ○1人当たり床面積 : 8m2以上 |
| 設 備 | 食堂、浴室、洗面設備、便所等 | |
| 人 員 配 置 |
【生活訓練の場合】 ○生活支援員 6:1以上 【就労移行支援の場合】 ○職業指導員・生活支援員 6:1以上 ○就労支援員 15:1以上 【共通事項】 ○サービス管理責任者 1人 ○夜間の生活支援員 1人以上 |
|
| 報 酬 基 準 (日単位) |
<定員40人以下の場合> ○生活訓練 : 639単位 → 1月(22日)分 : 14,058単位 ○就労移行支援 : 736単位 → 1月(22日)分 : 16,192単位 ○精神障害者退院支援施設加算 〈宿直体制〉 115単位 → 1月(30日)分 : 3,450単位 〈夜勤体制〉 180単位 → 1月(30日)分 : 5,400単位 |
|
| 備 考 |
○2年乃至3年の標準利用期間(日中の自立訓練、就労移行支援に夜間が付属) ○精神病棟転換によって設置(病棟設備の転用又は病棟建物外での設置) |
|
地域生活支援事業と精神障害者支援
○地域の実情に応じて、柔軟に実施されることが好ましい各般の事業について、地域生活支援事業として法定化。国は、予算の範囲内において、市町村及び都道府県の実施する地域生活支援事業の実施に要する費用の2分の1以内(都道府県は市町村に4分の1以内)を補助。
○精神障害者のニーズを踏まえ、居住サポート事業や退院促進支援事業を市町村、都道府県の事業として位置づけ。
○障害者相談支援事業〈地方交付税〉
地域の障害者等の福祉に関する相談に応じて、必要な情報の提供や助言などを行う。
○市町村相談支援機能強化事業〈国庫補助〉
相談支援事業の機能強化のため、保健師、精神保健福祉士、社会福祉士等の専門的職員を配置する。
○成年後見制度利用支援事業〈国庫補助〉
知的障害者、精神障害者のうち判断能力が不十分な者について、成年後見制度の利用を支援する。
○住宅入居等支援事業(居住サポート事業)〈国庫補助〉
賃貸住宅への入所を希望しているが保証人不在等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等の支援や、家主等への相談・助言等を行う。
○地域活動支援センター事業〈国庫補助〉
障害者等に対し、通所で、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流促進などを、地域の実情に応じて実施。
○精神障害者退院促進支援事業〈国庫補助〉
受入条件が整えば退院可能である精神障害者に対し、退院に向けた支援を行う。
障害者相談支援事業のイメージ
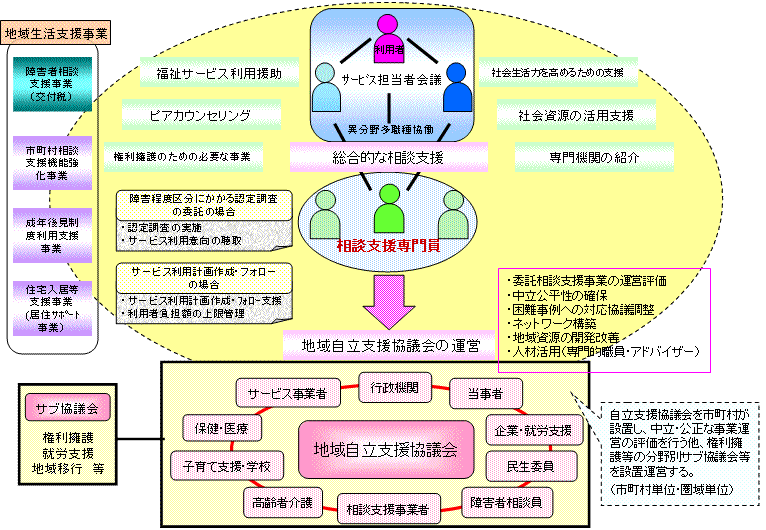
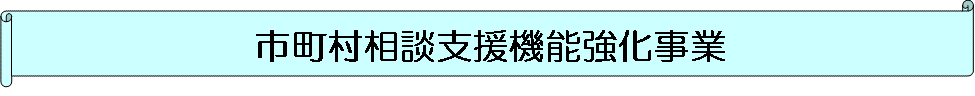
【目的】
市町村における相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を市町村等に配置することにより、相談支援機能を強化することを目的とする。
【事業内容】
(ア)専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応
(イ)地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等
【専門的職員】
社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市町村の相談支援機能を強化するために必要と認められる者
【留意事項】
| (ア) | 地域自立支援協議会を設置する市町村又は圏域等を単位として実施すること |
| (イ) | 地域自立支援協議会において、市町村内の相談支援体制の整備状況やニーズ等を勘案し、本事業によって配置する専門的職員について協議し、事業実施計画を作成すること。 |
| (ウ) | 都道府県自立支援協議会に、事業実施計画に係る助言を求めるほか、概ね2年ごとに事業の見直しに向けた評価・助言を求めるなど、事業の適切な実施に努めること。 |
市町村相談支援機能強化事業
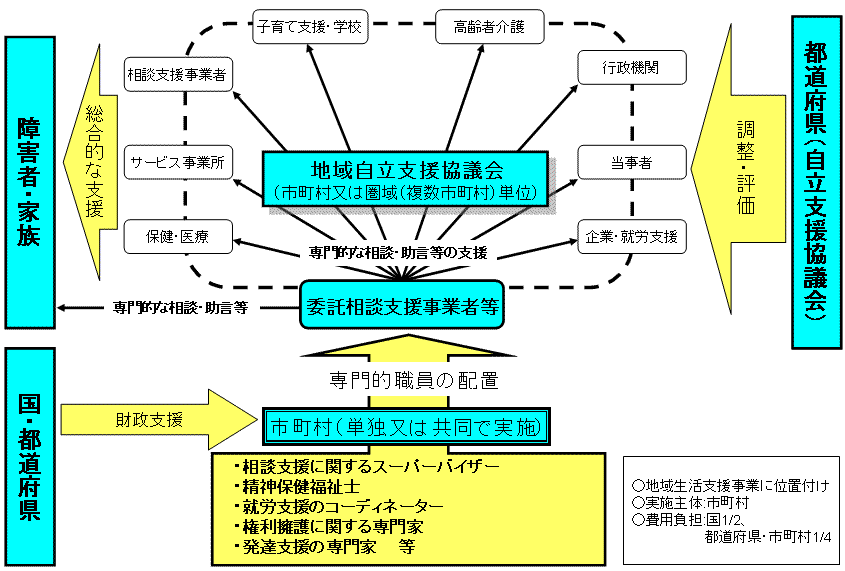
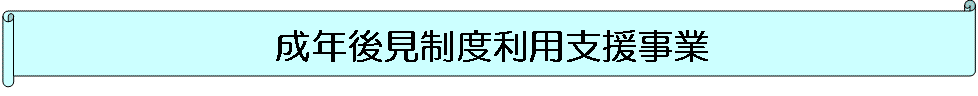
【目的】
障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。
【事業内容】
成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する。
【対象者】
次のいずれにも該当する者
| (ア) | 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする身寄りのない重度の知的障害者又は精神障害者 |
| (イ) | 市町村が、知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に基づき、民法第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認める者 |
| (ウ) | 後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者 |
成年後見制度利用支援事業
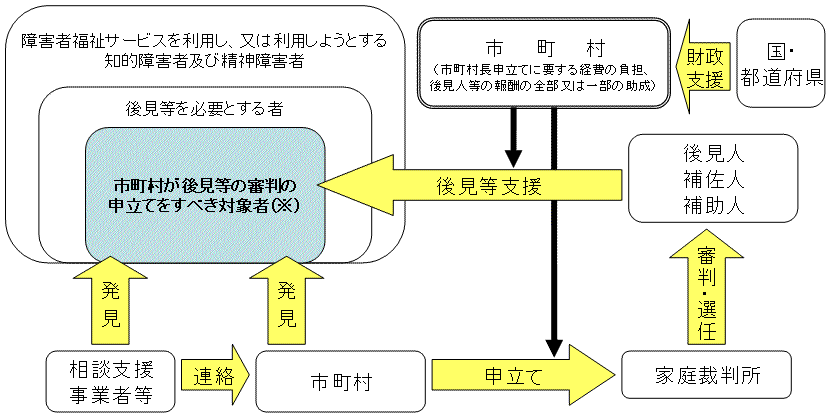
|
○地域生活支援事業に位置付け ○実施主体:市町村 ○費用負担:国1/2、 都道府県・市町村1/4 |
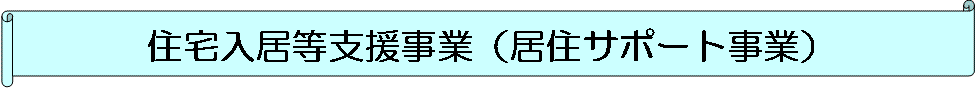
【概要】
賃貸契約による一般住宅(※)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する。
※「一般住宅」とは、公営住宅及び民間の賃貸住宅(アパート、マンション、一戸建て)のことをいう。
【実施主体】
市町村(共同実施も可能)
(指定相談支援事業者へ委託することができる。)
【対象となる障害者】
知的障害者又は精神障害者(住居の確保により退院・退所できることとなる者を含む)であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者。
ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。
【事業の具体的内容】
賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者について、不動産業者に対する一般住宅のあっせん依頼、障害者と家主等との入居契約手続きにかかる支援、保証人が必要となる場合における調整、家主等に対する相談・助言、入居後の緊急時における対応等を行う。
| (1) | 入居支援(不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援) ※地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じその利用支援を行う。 |
| (2) | 24時間支援(夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等、必要な支援を行う。) |
| (3) | 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整 利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。 |
住宅入居等支援事業(居住サポート事業)(イメージ図)
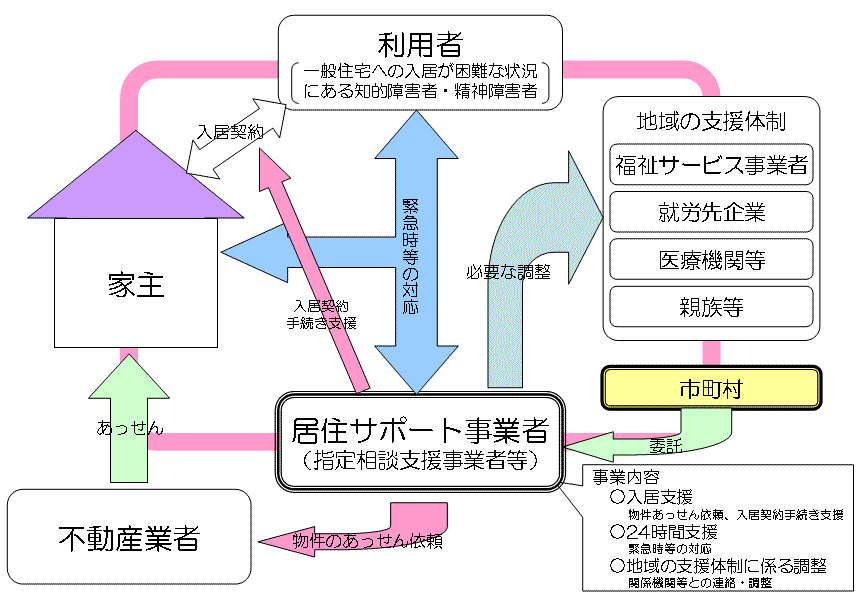
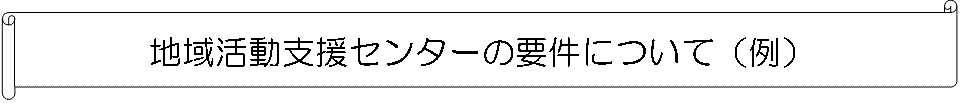
地域活動支援センターは、地域生活支援事業として位置づけられたものであり、実際の委託や助成の内容については、市町村が地域の実情に応じて設定。
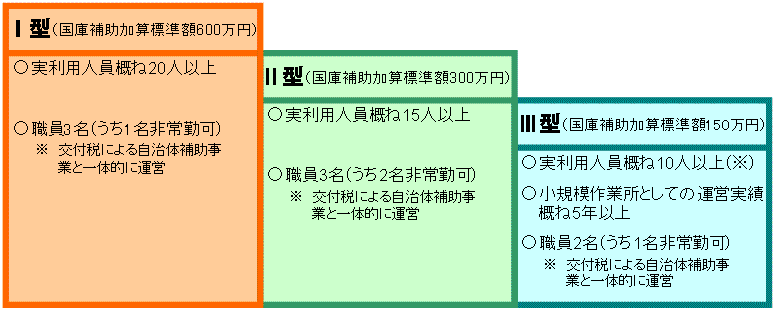 |
|||
|
|||
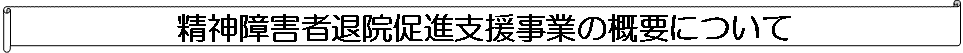
【概要】
精神病院に入院している精神障害者のうち、受入条件が整えば退院可能である者に対し、円滑な地域移行を図るための支援を行う。
【事業の具体的内容】
対象者の個別支援等に当たる自立支援員を指定相談支援事業者等に配置し、精神病院の精神保健福祉士等と連携を図りつつ退院に向けての支援を行い、精神障害者の円滑な地域移行の促進を図る。
(主な支援内容)
- 精神病院内における利用対象者に対する退院への啓発活動。
- 退院に向けた個別の支援計画の作成。
- 院外活動(福祉サービス体験利用、保健所グループワーク参加等)にかかる同行支援等
- 対象者、家族に対する地域生活移行に関する相談・助言
- 退院後の生活に係る関係機関との連絡・調整
【自立支援員の要件】
精神保健福祉士又はこれと同等程度の知識を有する者
【留意事項】
(関係機関への周知)
管内市町村、精神病院及び福祉サービス事業者等の関係機関に対して広く周知し、本事業の実施に係る対象者の申請、協力施設の拡充及び支援体制の充実等、事業の円滑な実施を図ること。
(対象者の選定等)
実施主体、市町村、精神病院医師、福祉サービス事業者等で構成する協議会等を設置し、客観的な視点に立って対象者の選定を行うこと。
(関係機関との連携)
対象者の円滑な地域移行を図る観点から、相談支援事業者、その他福祉サービス提供者、保健医療サービス事業者等と連携を図ること。
(事業の評価)
地域における支援体制等に関する課題が明らかになった場合には、地域自立支援協議会に報告するなど、課題解消に向けた方策を検討するよう努めること。
精神障害者退院促進支援事業(イメージ図)
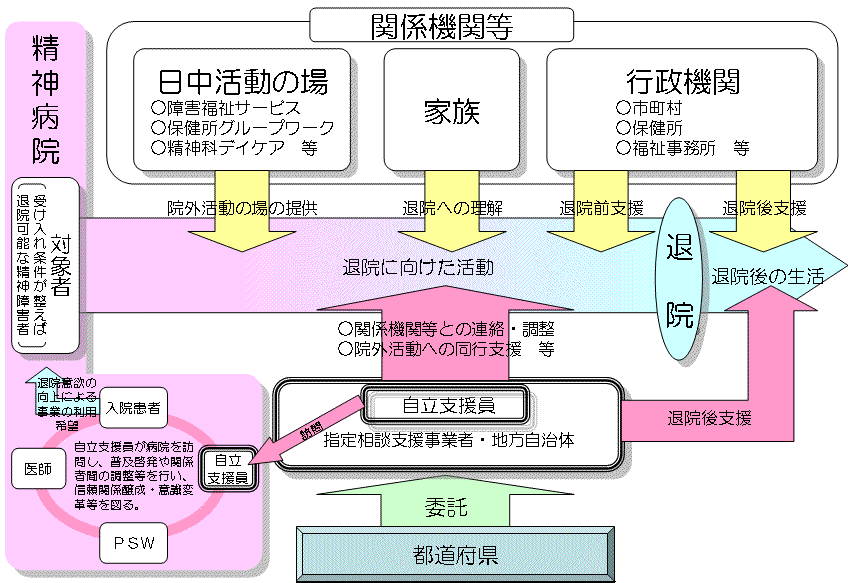
障害関係サービスの計画的整備
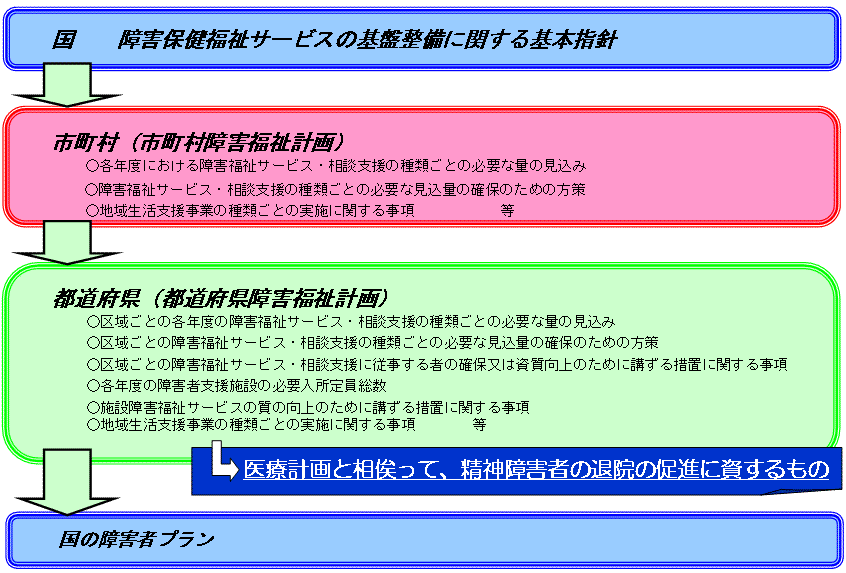
障害福祉計画の「基本指針」について |
○ 「基本指針」は、下記の事項を内容とするものであるが、具体的には、障害福祉計画作成に当たって基本となる理念、サービス見込量の算定の考え方、計画的な基盤整備を進めるための取組みなど、定めるものとする
- 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本事項
- 市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成に関する事項
- その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項
○ 市町村及び都道府県は、「基本指針」を踏まえ、平成23年度までの新サービス体系への移行を念頭に置きながら数値目標を設定し、平成18年度中に平成20年度までを第1期とする障害福祉計画を策定するものとする
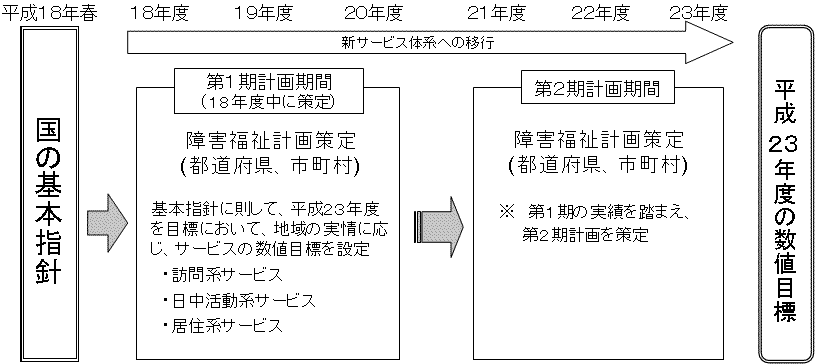
地方障害福祉計画における障害福祉サービス見込量の算定のポイント
<2月9日社会保障審議会障害者部会資料より抜粋>
ポイント1
○ 訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービスのそれぞれについて、現在の利用者数を基礎としつつ、障害者のニーズ、近年の利用者の伸び、今後新たに利用が見込まれる精神障害者や小規模作業所利用者の移行などを見込んだ上で、必要なサービス量を具体的に見込むものとする。
ポイント2
○ 特に、地域生活や一般就労への移行を進める観点から、下記の数値目標を設定するとともに、この目標を達成するために必要なサービス見込量の設定を行う。
1 平成23年度末までに、現在の入所施設の入所者の1割以上が地域生活に移行することをめざす
⇒ これにあわせて、平成23年度末時点の施設入所者数を7%以上削減することを基本としつつ、地域の実情に応じて目標を設定する
2 平成24年度までに、精神科病院の入院患者のうち「受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者」(以下「退院可能精神障害者」という。平成14年患者調査で約7万人)の解消をめざす
⇒ これにあわせて、平成23年度における退院可能精神障害者数の減少目標値を設定するとともに、医療計画における基準病床数の見直しを進める
3 平成23年度中に福祉施設から一般就労に移行する者を現在の4倍以上とすることをめざす
⇒ これにあわせて、福祉サイドにおける就労支援を強化する観点から、就労継続支援利用者のうち、3割は雇用型をめざす
ポイント3
○ 地域生活支援事業についても、地域の実情に応じ、数値目標を設定し、その事業量の確保のための措置を明記するものとする。
サービス利用者の将来見通し
推計結果のポイント
○新制度の障害福祉サービスについて、以下の3つに区分して推計
- 訪問系サービス(ホームヘルプサービス)
- 日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センター等)
- 居住系サービス(施設入所、グループホーム・ケアホーム)
○ 訪問系サービスについては、近年の動向を踏まえ、現在、利用率が低い地域を中心に利用者が増え、平成23年度には現在の1.8倍(約16万人)に増加
○ 日中活動系サービスについては、旧体系サービスから新体系サービスへの段階的移行を見込むとともに、小規模作業所利用者の法定サービスへの移行や精神入院患者の退院促進により、平成23年度には利用者が現在の1.6倍(約47万人)に増加
○ 居住系サービスについては、地域における居住の場としてのグループホーム・ケアホームの充実を図るとともに、自立訓練事業等の実施に伴う入所施設定員数の減少とグループホーム等への転換、一般住宅等への移行を進めることにより、平成23年度には、グループホーム・ケアホームの入居者が現在の3倍(約9万人)に増加。結果として、施設入所者及び退院可能な精神入院患者のうち約6万人が地域生活に移行する見通し
○ 障害者の就労については、就労移行支援事業等の推進により、平成23年度には、福祉施設から一般就労への毎年度の移行者が現在の4倍(約0.8万人)に、福祉施設における就労の場が現在の10倍(約3.6万人)に増加
推計結果の概要 |
| 訪問系サービスの利用者数 | 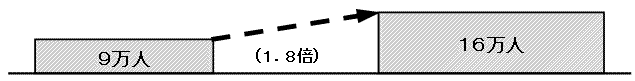 |
| 日中活動系サービスの利用者数 | 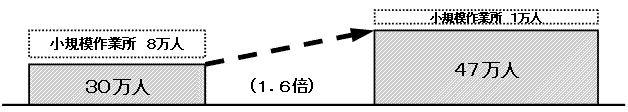 |
| 居住系サービスの利用者数 | 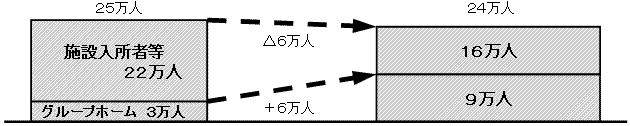 |
| 一般就労への移行者数 |  |
| 福祉施設における雇用の場 |  |
障害福祉計画策定と精神障害者支援に係る主な視点
○個別給付サービスの見込みへの精神障害関連サービスの反映
介護給付、訓練等給付に係るサービスの見込みに当たっては、以下のような観点を踏まえつつ、精神障害者に係る必要量を反映したものとすることが必要。
- 従来の制度下における精神障害者のサービス利用の伸び
- 受入条件が整えば退院可能な精神障害者(約7万人)の解消に向けて、通常の伸びに加え特に必要と見込まれるサービス利用の伸び
- 精神障害者社会復帰施設から新サービス体系への移行促進 など
※ 介護給付、訓練等給付の実施主体は、原則として入院・入所前に居住していた市町村。
○地域生活支援事業の活用による精神障害者支援
介護給付、訓練等給付に係るサービス以外にも、地域生活支援事業による支援を検討し、取組方針を計画に記載することが必要。
〈市町村〉居住サポート事業、成年後見制度利用支援事業、地域活動支援センター事業による支援 など〈都道府県〉精神障害者退院促進支援事業による退院支援、就業・生活支援センター事業による支援 など
○精神障害者に係る相談支援体制の構築
障害者に係る一般的な相談支援は、障害種別を超えて横断的に市町村に一元化されることから、精神障害者に係る相談支援体制について、必要に応じて広域での共同実施等を視野に入れつつ整備することが必要。
- 精神障害者に係るケアマネジメント体制
- 医療と福祉の連携による退院時・後の支援など、関係機関・関係者の連携強化
- 人材育成、広域調整など、都道府県による専門的、技術的支援 など
○精神障害に関する正しい理解の促進
障害種別を超えて福祉サービスの提供制度が一元化されることを踏まえ、他の障害と併せ、知識の普及啓発や交流等を通じて、精神障害に関する正しい理解の促進に資するための取組が重要。
新しい仕組みと精神障害福祉への期待
○ 精神障害福祉サービスの普遍化
身体障害、知的障害と並んで、市町村で一元的に提供。未実施地域でのスタートなど、精神障害福祉がキャッチアップするチャンス。
○ 退院患者の受け入れ体制の整備
障害福祉計画によって、精神障害者の地域生活、社会復帰のためのサービス基盤を計画的に整備。また、在宅精神障害者も含め、地域のニーズとしての気づきの機会。
○ 福祉サービス財源の安定化
従来は、社会復帰施設、精神障害在宅サービスとも裁量的経費。新制度では、国、都道府県の財政負担義務を強化。
○ 医療と福祉の連携強化
相談支援事業の実施、多様な主体による事業参入等を通じ、精神障害者の特性に応じて、医療と福祉が連携しつつ支援を展開。
○ 仕組みは共通、支援は個別
目的に応じたサービス体系の再編、空き店舗等の活用を可能とする規制見直し、複数種類のサービス組合せ(多機能型)など、精神障害者のニーズに応じたサービス提供体制づくりと、相談支援、個別支援計画等を通じて個々のニーズに応じた支援。 等々
精神障害者の地域生活、社会復帰の推進
「医療だけが資源」の地域から「医療も資源」の地域づくり
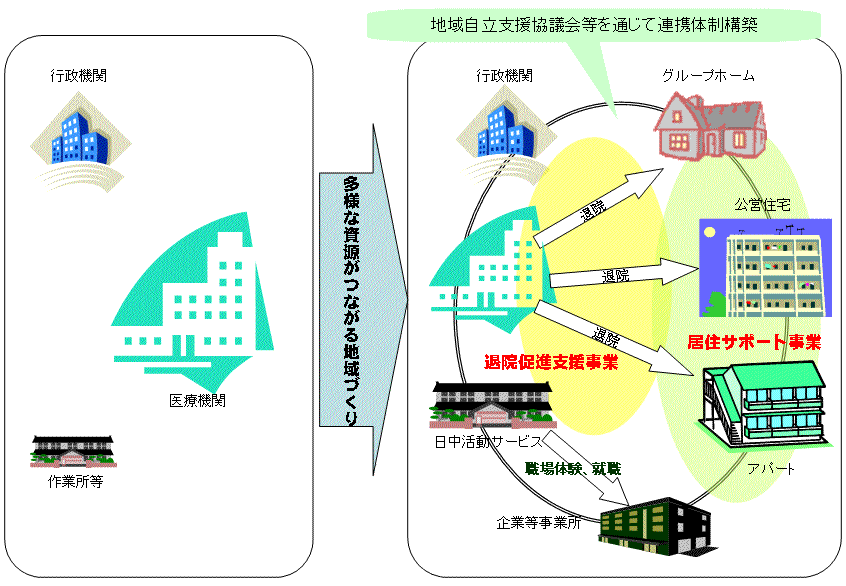
|
平成18年12月26日障害保健福祉関係 |
障害者自立支援対策臨時特例交付金に
よる特別対策事業の実施方法について
(精神障害者の地域生活支援関連事業抜粋)
※ 本資料は現時点での案であり、今後、変更があり得るものである。
目 次
1. |
事業者に対する激変緩和措置 |
[1] 事業運営円滑化事業 |
|
[2] 通所サービス利用促進事業 |
|
2. |
新法への移行等のための緊急的な経過措置 |
(1)新法に移行するまでの経過的な支援 |
|
[3] 小規模作業所緊急支援事業 |
|
[4] デイサービス事業等緊急移行支援事業 |
|
(2)新法への移行のための支援 |
|
[5] 障害者自立支援基盤整備事業 |
|
[6] 移行等支援事業 |
|
[7] 地域移行・就労支援推進強化事業 |
|
(3)制度改正に伴う緊急的な支援 |
|
[8] 相談支援体制整備特別支援事業 |
|
[9] 障害児を育てる地域の支援体制整備事業 |
|
[10] 障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業 |
|
[11] 就労意欲促進事業 |
|
[12] その他法施行に伴い緊急に必要な事業 |
|
1 事業者に対する激変緩和措置
[2] 通所サービス利用促進事業
1 事業の目的
今般の制度改正の激変緩和措置の一環として、新体系の日中活動サービス事業所及び旧体系の通所施設における送迎サービスの実施を促進し、利用者がサービスを利用しやすくするとともに、送迎サービスの利用に係る利用者負担の軽減を図ることを目的とする。
2 事業の内容
| (1) | 実施主体 市町村 |
| (2) | 事業の内容 次のいずれかに該当する事業所が、当該事業所において行われる通所サービスの利用につき、利用者の送迎を行った場合(外部の事業者へ送迎を委託する場合も含む。)であって、申請時における直近1月間の送迎の実績が週3回(1回の送迎の利用者が一定程度以上である場合に限る。)以上であるものにつき、当該送迎に要する費用を助成する。 [1] 通所による生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(障害者支援施設が行う場合も含む。) [2] 旧身体障害者通所授産施設、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設又は各入所施設の通所部 |
| (3) | 補助単価 1事業所あたり3,000千円以内 |
3 補助割合 1/2
4 実施年度 19年度〜20年度
5 その他
利用者負担については、徴収は不可とする(ただし、生活介護を除き、燃料費に係る実費相当額については、徴収可)。
6 事業担当課室・係 障害福祉課 居住支援係
2 新法への移行等のための緊急的な経過措置
(1) 新法に移行するまでの経過的な支援
[3] 小規模作業所緊急支援事業
1 事業の目的
個別給付(生活介護、就労継続支援等)や地域活動支援センターなど新たなサービスへの移行が直ちにできない小規模作業所が、新たなサービスへ円滑に移行できるよう、経過的な措置として定額を助成する。
2 事業の内容
| (1) | 実施主体 都道府県(障害者団体への補助) |
| (2) | 事業の内容 新たなサービスへの移行に向けて調整段階にあり、直ちに新たなサービスへの移行が困難である小規模作業所について、以下の要件を満たす場合に補助対象とする。 [1] 利用定員が概ね5名以上であり、原則として週4日以上利用できる小規模作業所 [2] 地域活動支援センター又は個別給付への移行計画(実利用人員の増加など地域活動支援センター等の要件を満たすための移行計画)を作成した小規模作業所 |
| (3) | 補助単価 1作業所あたり1,100千円以内 |
3 補助割合 定額(10/10)
4 実施年度 18年度〜20年度
5 その他
事業の実施にあたっては、以下の点に留意すること。
| (1) | 従来、民間団体を通じて国庫補助を行っていた小規模作業所に対する経過的な措置であることから、小規模作業所に精通した障害者団体を通じて協議・申請をさせる等の方法により実施すること。 |
| (2) | 新たなサービスへの移行時期は、平成20年度末までとすること。 |
| (3) | 移行計画の記入様式は、都道府県において任意に定めるものとすること。 |
6 事業担当課室・係 地域生活支援室 地域生活支援事業係
交付の仕組み(小規模作業所緊急移行支援事業)
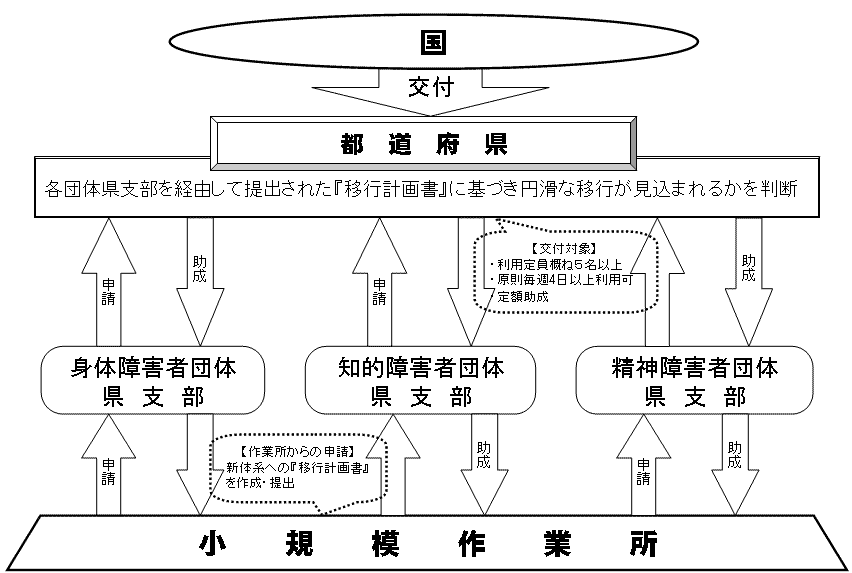
[4] デイサービス事業等緊急移行支援事業
1 事業の目的
新たなサービスへの移行が直ちにできないデイサービス事業及び精神障害者地域生活支援センター等が、新たなサービスへ円滑に移行できるよう、経過的な措置として運営費を助成する。
2 事業の内容
| (1) | 実施主体 市町村 |
| (2) | 内容 新たなサービスへの移行に向けて調整段階であり、直ちに新たなサービスへの移行が困難であるデイサービス事業所等が地域活動支援センター又は個別給付への移行計画(実利用人員の増加など地域活動支援センター等の要件を満たすための移行計画)を作成した場合に必要となる運営費及び体制整備(補助員雇上費、備品等更新費、改修費等)に係る経費を助成する。 |
| (3) | 補助単価 デイサービス緊急移行支援事業 1事業所あたり1,500千円以内 精神障害者地域生活支援センター緊急移行支援事業 1事業所あたり3,000千円以内 |
3 補助割合 定額(10/10)
4 実施年度 19年度〜20年度
5 その他
(2)移行計画の記入様式は、都道府県において任意に定めるものとする。
| 旧事業体系 | 地域生活支援事業 | 緊急移行支援事業 | 想定される事業 |
| 身体障害者デイサービス事業 知的障害者デイサービス事業 |
経過的デイサービス事業 | デイサービス緊急移行支援事業 | 地域活動支援センター、生活介護、 自立訓練 |
| 精神障害者地域生活支援センター | 経過的精神障害者地域生活支援 センター事業 |
精神障害者地域生活支援セン ター緊急移行支援事業 |
地域活動支援センター、生活介護、 相談支援事業 |
6 事業担当課室・係 地域生活支援室 地域生活支援事業係
2 新法への移行等のための緊急的な経過措置
(2) 新法への移行のための支援
[5] 障害者自立支援基盤整備事業
1 事業の目的
既存施設等が新体系に移行する場合等に必要となる、施設の改修等の経費に対し助成を行うことにより、新体系におけるサービスの基盤整備を図ることを目的とする。
2 事業の内容
| (1) | 実施主体 都道府県 |
| (2) | 事業の内容 事業の具体例としては、以下のとおりである。なお、既存の補助制度で対象としている事業については対象外とする。 |
【 改 修 】
[1] 小規模作業所を新体系の設備基準に適合させるための改修工事
[2] ケアホーム等を実施するアパート等のバリアフリー化等に必要な改修工事
[3] 居宅介護事業及び相談支援事業を行うために必要な既存建物の改修工事
[4] その他基盤整備対策に資する改修工事
【 増 築 】
[1] 生産事業等のための作業スペースの設置
[2] 新体系事業を行うにあたって必要となる厨房等の拡張工事
[3] その他基盤整備対策に資する増築工事
(ただし、【改修】の[2]は、2,000千円以内、改修の[3]は5,000千円以内)
3 補助割合 定額(10/10)
4 実施年度 18年度〜20年度
5 事業担当課室・係 障害福祉課 福祉財政係(施設整備担当)
[6] 移行等支援事業
1 事業の目的
新たなサービスへ移行できていない小規模作業所、デイサービス事業、精神障害者地域生活支援センター、その他旧体系サービス事業者(以下、「小規模作業所等」という。)が、個別給付や地域活動支援センターなど新たなサービスへ円滑に移行できるようにするための事業を実施する。
2 事業の内容
| (1) | 実施主体 都道府県(社会福祉法人等への委託可) |
| (2) | 内容[1] 移行推進コンサルタント派遣事業小規模作業所等にコンサルタントを派遣し、移行のための体制づくり、事業内容の充実等、新体系に円滑に移行できるよう支援する。 [2] 移行推進研修会開催事業複数の小規模作業所等の経営者等に対して、経理事務(財務、会計の処理等)、法人格の取得のための支援などを図るための研修会を継続的に実施する。 |
| (3) | 補助単価 1都道府県あたり16,000千円 |
3 補助割合 定額(10/10)
4 実施年度 18年度〜20年度
5 その他
新たなサービスへの移行計画を作成した小規模作業所等を優先して実施すること。
また、地域活動支援センターについても、より安定した事業運営が図られるよう、積極的に個別給付への移行を促進すること。
6 事業担当課室・係 地域生活支援室 地域生活支援事業係
[7] 地域移行・就労支援推進強化事業
1 事業の目的
新たなサービスへの円滑な移行に向けて、関連する各施策を強化するための各種の事業を、緊急的かつ集中的に実施することにより、地域への移行、就労支援等をより一層推進することを目的とする。
2 事業の内容
地域移行、退院促進及び就労支援等のための関係機関のネットワーク強化、グループホーム等の借り上げのための初度経費の助成、就労支援のための実習受入先の開拓や重度訪問介護に関する基盤整備等を行う。
(1)精神障害者退院促進強化事業([7]別紙1のとおり)
(2)グループホーム・ケアホーム整備推進事業([7]別紙2のとおり)
(3)就労支援事業移行初期支援強化事業([7]別紙3のとおり)
(4)在宅重度障害者地域生活支援基盤整備事業([7]別紙4のとおり)
[7](別紙1)精神障害者退院促進強化事業
1 事業の目的
いわゆる社会的入院者の退院促進を図ることは急務であり、従来より退院促進支援事業を実施してきたところであるが、こうした取り組みを各都道府県が全域的に展開していくためには、退院促進に関する知識・技術を有した者を一定程度確保することが非常に重要である。
このため、地域において指導的役割を果たす退院促進に関する専門家を養成するとともに、地域における受入基盤の拡充を図ることにより、退院促進支援事業の円滑かつ効果的な実施を図ることを目的とする。
2 事業の内容
| (1) | 実施主体 都道府県 |
| (2) | 事業の内容[1] 退院支援に関する専門家の養成研修
【対象者】都道府県職員等
【研修内容】長期入院者への支援に必要な知識・技術の習得、退院促進先進地区における実習 等 [2] 退院支援に関する理解促進のための基礎研修
【対象者】市町村職員、地域住民等
【研修内容】精神障害者の特性の理解、元社会的入院者の体験談、病院見学 等 |
| (3) | 補助単価 研修企画:1都道府県あたり610千円以内 研修実施:1障害福祉圏域あたり2,000千円以内 |
3 補助割合 定額(10/10)
4 実施年度 18年度〜20年度
5 事業担当課室・係 障害福祉課 通所サービス係
[7](別紙2)グループホーム・ケアホーム整備推進事業
1 事業の目的
アパートや一般住宅等を借り上げてグループホーム・ケアホームを実施するに当たり、借上に伴う初度経費 (敷金・礼金)の負担を軽減し、障害者が地域で暮らせるように支援することを目的とする。
2 事業の内容
(1) |
実施主体 都道府県 |
(2) |
事業の内容 グループホーム等を実施するに当たり、アパート等の借り上げに伴い、初度に係る敷金・礼金に対し助成を行う。 |
(3) |
補助単価 入居者1人あたり133千円以内 |
3 補助割合 定額(10/10)
4 実施年度 18年度〜20年度
5 事業担当課室・係 障害福祉課 居住支援係
[7](別紙3)就労支援事業移行初期支援強化事業
【障害者職場実習設備等整備事業】
1 事業の目的
職場実習は、事業所内での作業等以外の作業体験が可能であり、就労支援利用者等が、作業能率の向上や、現場感覚を習得できるなど、一般就労への移行に有効なものである。
このため、就労移行支援、就労継続支援事業者等から職場実習を受け入れる企業が、受入のために企業内の設備の更新等を実施した場合にその費用を助成することとし、もって職場実習の受入先の確保を促進することを目的とする。
2 事業の内容
| (1) | 実施主体 都道府県 |
| (2) | 事業の内容[1] 実施方法職場実習を受け入れる予定の企業は、[1]実習内容、[2]これまでの実習の実績、[3]職場実習派遣元事業所(施設)名、[4]職場実習年間受入予定(可能)人数、及び[5]当該受入に際し必要な備品等の購入に要する額等を都道府県に対し申請し、都道府県はこれらの内容を審査した上で助成する。 なお、本事業費により職場実習環境を構築した企業は、都道府県が「職場実習受入企業」として広く公表し積極的な受入を促すこと等により、今後効果的かつ継続的な職場実習を図ることとする。 [2] 対象企業就労移行支援事業、就労継続支援(A型、B型)事業、授産施設(3障害、通所・入所・小規模)から職場実習を継続的に受け入れる民間企業 |
| (3) | 補助単価 1企業あたり5,000千円以内 |
3 補助割合 定額(10/10)
4 実施年度 18年度〜20年度
5 事業担当課室・係 障害福祉課 就労支援係
【就労支援ネットワーク構築事業】
1 事業の目的
障害者の就労支援を効果的に推進するためには、就労移行支援事業、就労継続支援事業の移行促進のみならず、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター及び養護学校等地域の社会資源と就労支援ネットワークを構築し、各機関が連携し、情報の共有化を図りながら適切な支援を実施することが重要である。
このため、障害保健福祉圏域等の地域における就労支援ネットワークの構築に必要な、情報の共有化を図るためのホームページの開設や各種研修会の開催等に要する費用を助成することとし、もって、地域における就労支援ネットワークの構築の促進を図ることを目的とする。
2 事業の内容
(1) |
実施主体 都道府県 |
(2) |
事業の内容 都道府県内の各障害保健福祉圏域における就労支援ネットワークの構築のために開催した会議、情報共有化を目的としたホームページの構築、研修会等に要する費用を助成する。 なお、これらの事業を各ネットワーク内の幹事事業者に委託することも可能。 |
(3) |
補助単価 1障害福祉圏域あたり1,000千円以内 |
3 補助割合 定額(10/10)
4 実施年度 18年度〜20年度
5 事業担当課室・係 障害福祉課 就労支援係
2 新法への移行等のための緊急的な経過措置
(3) 制度改正に伴う緊急的な支援
[8] 相談支援体制整備特別支援事業
1 事業の目的
障害者が地域で安心して生活するためには、地域自立支援協議会をはじめとする相談支援体制の構築が重要であり、本事業によりその体制整備や充実強化を促進し、早急に地域における相談支援体制を整備・確立することを目的とする。
2 事業の内容
(1) 実施主体 都道府県
(2) 事業の内容
○ 先進地のスーパーバイザーや学識経験者等2〜3名を特別アドバイザーとして招聘し、チームで都道府県内の相談支援体制の整備や充実強化に向けて、評価、指導等を実施する。
○ 特別アドバイザーは、毎月1回程度(集中的に何日間か実施することも可)都道府県を訪問し、都 道府県の担当職員及び当該県のアドバイザーと十分連携しながら、以下の事業を行う。
- 都道府県自立支援協議会の設立・充実強化の支援
- 県内を巡回するなどして、市町村(圏域)ごとの相談支援体制や地域自立支援協議会の立ち上げ・運営等についての具体的で丁寧な支援
(例) 小規模市町村が圏域単位で相談支援体制を共同で実施する場合のアドバイス
地域自立支援協議会に参加して、会議の持ち方や運営方法等について具体的にアドバイス 等 - 県内の相談支援関係者を対象とした連絡会議・研修会の開催による人材育成支援
相談支援事業(市町村が社会福祉法人等に委託して実施する場合を含む。)立ち上げ等に当たり、必要な設備整備等について支援する。
市町村(市町村が相談支援事業者等に委託して実施する場合を含む。)が障害者を対象として、地域交流や自己啓発などの社会参加に資する事業(障害当事者が障害者の活動をサポートする形態とする。)を実施する場合に、必要な設備整備等について支援する。
例えば、パソコン教室(障害者と同数程度の同一障害の当事者がサポート)を開催し、障害者が仲間づくりや地域に関わる手段を身につけることにより障害者の地域生活のきっかけづくりのための支援を行うために必要な設備整備等。
(3) |
補助単価 |
(2)[1]:1都道府県あたり2年間で14,000千円以内 | |
| (2)[2]:1か所あたり1,000千円以内 | |||
| (2)[3]:1障害福祉圏域あたり1,950千円以内 |
3 補助割合 定額(10/10)
4 実施年度 18年度〜20年度
5 事業担当課・係 障害福祉課 相談支援係
[11] 就労意欲促進事業
1 事業の目的
入所施設で工賃を得て働く者のうち一定の要件を満たすものに対し、これまでの食費負担等にも配慮した給付金を支給し、もって施設に入所する障害者の就労意欲の向上と就労を通じた自立を一層促進することを目的とする。
2 事業の内容
(1) 実施主体 市町村
(2) 事業の内容
平成18年度において入所施設(指定障害者支援施設及び入所に係る特定旧法指定施設(旧知的障害者通勤寮を除く。)をいう。)で生産活動に従事していた低所得者(所得区分が「低所得1」又は「低所得2」の者に限る。)に対し、更なる就労意欲の向上と就労を通じた自立を一層促進する観点から、工賃額に応じた給付金を支給する。
| (3) 補助単価 | 平成18年12月26日付事務連絡「就労意欲促進事業の取扱いについて」に従って算定された額 |
3 補助割合 1/2
4 実施年度 18年度(又は19年度)
5 事業担当課室・係 障害福祉課 企画法令係
[12] その他法施行に伴い緊急に必要な事業
1 事業の目的
これまでに掲げた事業のほか、障害者自立支援法の施行に伴い緊急に対応する必要がある事業を実施する。
2 事業の内容
(1) 事業者コスト対策([12]別紙1のとおり)
(2) 進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置([12]別紙2のとおり)
(3) オストメイト(人工肛門・人工膀胱造設者)対応トイレ設備緊急整備事業([12]別紙3のとおり)
(4) 視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業([12]別紙4のとおり)
[12](別紙1)事業者コスト対策
1 事業の目的
障害者自立支援法の施行時に伴い、制度の移行期に特有の事由から、会計処理システムの改修や報酬等請求事務処理のための関連経費の増加等により各事業者のコストが著しく増加していることから、事業者コストの一部を助成することにより、円滑な障害者自立支援法の施行と各事業者の新体系への移行を図ることを目的とする。
2 事業の内容
(1) 実施主体 都道府県
(2) 事業の内容
障害者自立支援法の施行に伴う制度の移行期に特有の事由から、会計処理システムの改良費や報酬等請求のための関連経費など、通常では発生しないコストの増加分を助成する。
<助成額の考え方>
助成する額としては、18年度中の制度移行期に発生した事業者コストの移行に伴う増加分であり、その中には、18年度の社会経済情勢の変化に伴うコストの増加分(原油高騰対策など)について含めることも可能とする。