(作成:平成18年5月31日)
(最終更新日:平成28年11月9日)
ビブリオ・バルニフィカスに関するQ&A
ビブリオ・バルニフィカスによる重篤な感染症についての研究結果が取りまとめられたことから、正しい知識と予防策等について理解を深めていただきたく、厚生労働省において、Q&Aを作成しました。
今後、ビブリオ・バルニフィカスに関する知見の進展等に対応して、逐次、本Q&Aを更新していくこととしています。
なお、海産魚介類の生食によるビブリオ・バルニフィカスの感染について、健康な方は過敏になる必要がありません。海産魚介類は一般に人の健康に有益ですので、以下の注意事項が海産魚介類の摂食の減少につながらないよう、正確なご理解をお願いします。
<目次>
<肝臓疾患、免疫力の低下などを基礎疾患として持つ方や貧血の治療で鉄剤を内服している方へ>
| Q1 | ビブリオ・バルニフィカスとは何ですか? |
| Q2 | どのようにして感染するのですか? |
| Q3 | 肝臓疾患、免疫力の低下などの基礎疾患のある人や貧血の治療で鉄剤を内服している人に注意が必要なのはなぜですか? |
| Q4 | どのようなことに注意すればよいですか? |
<一般の方へ>
| Q5 | 肝臓疾患や免疫力の低下などの基礎疾患や鉄剤による治療中の貧血を持たない人も注意が必要ですか? |
| Q6 | 日本での発生状況は? |
| Q7 | 諸外国での発生状況は? |
<専門家の方へ>
| Q8 | 診断方法は? |
| Q9 | 治療方法は? |
<肝臓疾患、免疫力の低下などを基礎疾患として持つ方や貧血の治療で鉄剤を内服している方へ>
| Q1 | ビブリオ・バルニフィカスとは何ですか? |
| A1 | ビブリオ・バルニフィカスは食中毒菌である腸炎ビブリオやコレラ菌と同様にビブリオ属に分類される菌の名前です。ビブリオ属の菌は一般に塩分濃度が2〜8%でよく発育しますが、ビブリオ・バルニフィカスはそれより低い1%程度の塩分濃度でも発育しますので、特に、河口域で海水(塩分濃度は約3.5%)と真水が交わる汽水域に生存しています。また、海水温度が20℃を超えると検出される傾向がみられます。 |
| Q2 | どのようにして感染するのですか? |
| A2 | 海産魚介類、特に汽水域(海水と淡水が混じり合う区域)でとれる甲殻類(エビなど)や河口域でとれる海産魚介類に付着し、刺身や加熱不足の料理を食べて感染する場合(経口感染)と皮膚に傷のある人が河口近くの海(汽水海水)に入って傷から感染する場合があります。人から人への感染の報告はありません。 |
| Q3 | 肝臓疾患、免疫力の低下などの基礎疾患のある人や貧血の治療で鉄剤を内服している人に注意が必要なのはなぜですか? |
| A3 | 肝臓疾患、免疫力の低下などを基礎疾患として持つ方や貧血の治療で鉄剤を内服している方は、重篤化することがあるため、注意が必要となります。この場合の初発症状は発熱と激しい痛みで、ほとんどの患者に皮疹が認められます。その皮疹は多彩で、紅斑、紫斑、水疱、血疱、潰瘍などが混在し、また短時間で皮疹が変化します(写真)。このような症状が認められた場合には、直ちに医療機関を受診してください。 なお、肝硬変などの肝臓に基礎疾患のある患者では、敗血症を引き起こすことがあり、この場合、死亡率は高く、50%〜80%であったと報告されています。
 |
| Q4 | どのようなことに注意すればよいですか? |
| A4 | 肝臓疾患、免疫力の低下などを基礎疾患として持つ方や貧血の治療で鉄剤を内服している方は、特に夏場における海産魚介類の生食は避け、適切に加熱調理したものを摂取することが重要です。なお、ビブリオ・バルニフィカスは、通常の調理温度(腸管出血性大腸菌O157:H7を殺す温度)である食品の中心温度が70℃で1分間(100℃であれば数秒間)加熱すれば死滅します。 また、手足に傷のある人は6月〜10月に海水に入らないことにより予防することが可能です。 |
<一般の方へ>
| Q5 | 肝臓疾患、免疫力の低下などの基礎疾患や鉄剤による治療中の貧血を持たない人も注意が必要ですか? |
| A5 | 健康な方では、軽度の胃腸炎を起こすことがあります。しかし、重症になることはほとんどなく、過敏になる必要はありません。この感染症は肝臓疾患、免疫力の低下などを基礎疾患として持つ方や貧血の治療で鉄剤を内服している方が、夏場の海産魚介類の生食により発症しやすい感染症です。 ただし、健康な人でも、足などに傷がある場合には、海水に接触することなどによりまれに感染し発症する可能性がありますので注意してください。 |
| Q6 | 日本での発生状況は? |
| A6 | 日本におけるビブリオ・バルニフィカス感染症は1976年に長崎で第1例が報告されて以来、約200例が確認されています。 1999〜2003年の調査によると創傷感染を含め、年間19〜27例発生し、合計107例が確認されました。このうち患者の基礎疾患が明らかとなった83例の内訳としては、肝硬変が50例(60%)であり、肝癌の合併も9例ありました。これに慢性肝炎19例を加えると83例中69例(83%)の患者が肝疾患を有していました。 発生地域は熊本県が24例と最も多く福岡、佐賀、長崎を加えた北部九州地域で全体の50%以上を占めています。その他に、山口から岡山にかけての瀬戸内海沿岸と東京、千葉の東京湾沿岸における患者発生が目立ちました。 発生時期は6〜10月で冬季の発生はありませんでした。 ただし、冬も暖かい奄美大島では2004年1月にビブリオ・バルニフィカス感染症が疑われる症例が1例見つかっています。
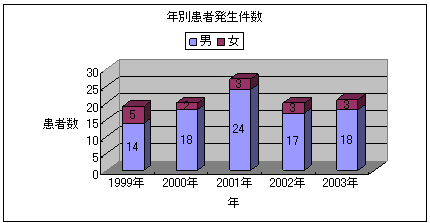
|
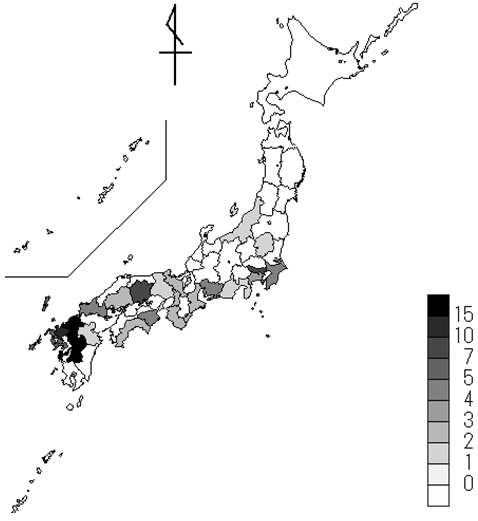
| Q7 | 諸外国での発生状況は? |
| A7 | 米国では1980年代より、韓国でも近年、いずれも年間30〜40例の発症が確認されています。 |
<専門家の方へ>
| Q8 | 診断方法は? |
| A8 | 細菌学的な検査が重要ですが、一般的な血液寒天培地を用いた培養法では他のグラム陰性桿菌との区別がつかない事があります。そのため、皮疹を見た場合にはA3を参考にし、ビブリオ・バルニフィカスを疑って検査を進める必要があります。 |
| Q9 | 治療方法は? |
| A9 | ビブリオ・バルニフィカスに対しては、早期の診断と治療が重要です。 一般的な治療としては、イミペネム、パニペネムなどのカルバペネム系抗生物質の安全に使用できる最大量の投与にミノサイクリン投与を併用します。 |
<参考文献&リンク>
国立感染症研究所感染症情報センター
http://idsc.nih.go.jp/disease/vulnificus/index.html
食品安全委員会
https://www.fsc.go.jp/sonota/hazard/H21_18.pdf
農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/f_encyclopedia/vibrio.vulnificus.html
米国 CDC
http://www.cdc.gov/disasters/vibriovulnificus.html
<Q&Aを作成するにあたって御協力を頂いた専門家>(50音順)
荒川 英二 先生(国立感染症研究所細菌第一部主任研究官)
井上 雄二 先生(熊本大学医学部付属病院講師)
岡部 信彦 先生(国立感染症研究所感染症情報センター長)
山本 茂貴 先生(国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部長)
渡辺 治雄 先生(国立感染症研究所副所長)
| このページに関する照会先 生活衛生・食品安全部 監視安全課 水産安全係 (内線2491、4238) |