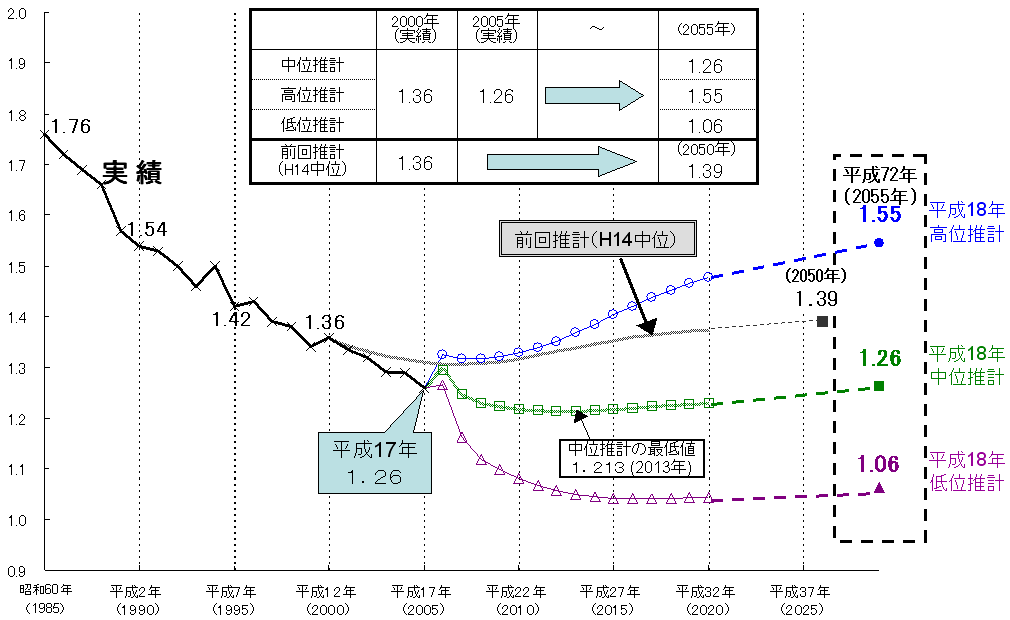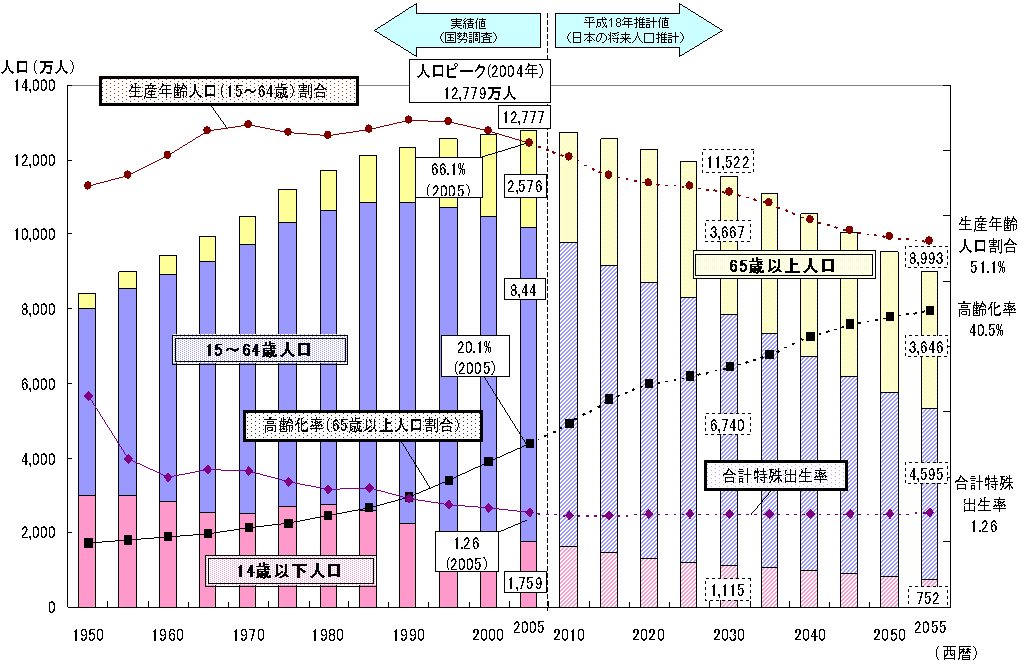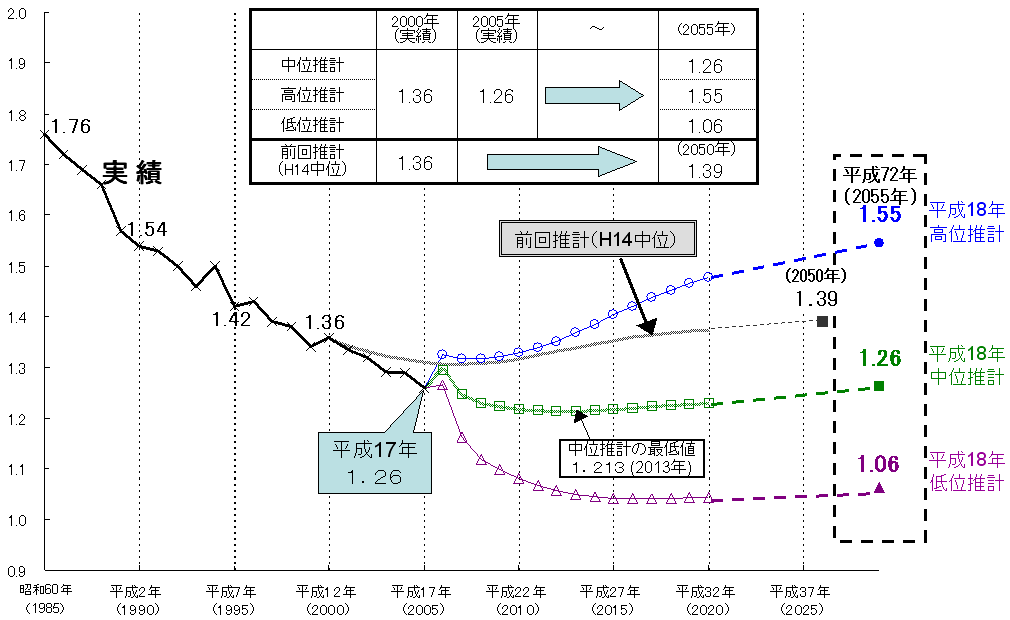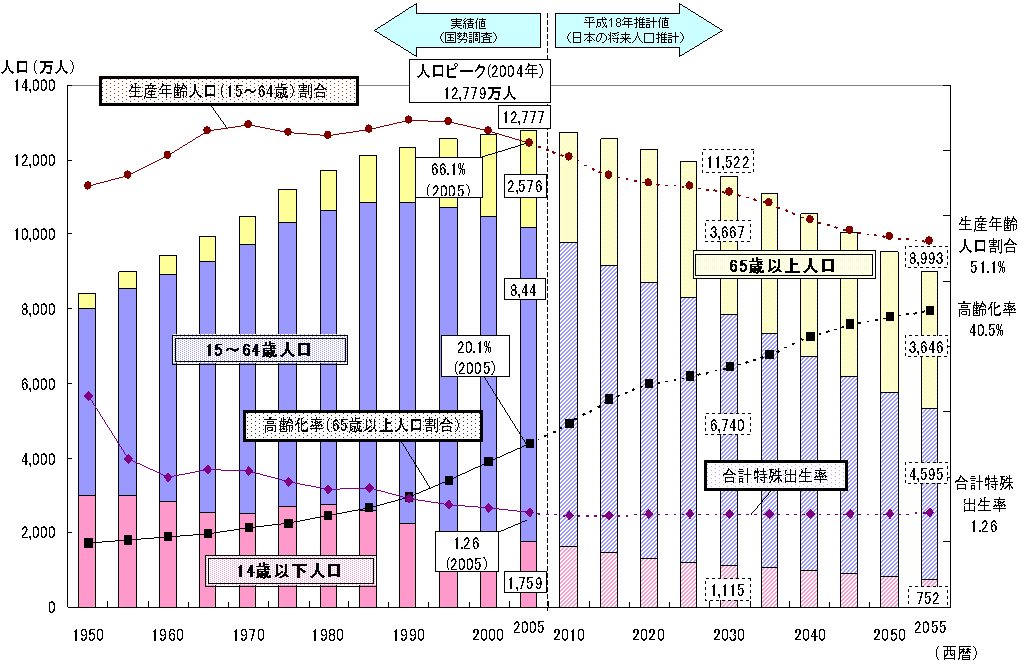| ○ |
将来推計人口は、社会保障・人口問題研究所が、国勢調査等の客観的データに基づき、概ね5年ごとに将来の人口を推計。
|
| ○ |
今回の推計は平成17年国勢調査結果に基づき、2055年までの日本の人口を推計。
(参考推計として、2105年まで推計) |
| (2005) |
|
(2055) |
| 1.26 |
 |
高位 1.55 <1.63>
中位 1.26 <1.39>
低位 1.06 <1.10> |
| |
※ < >内は前回推計(H14)の2050年の仮定値 |
| 非婚化、晩婚化の進行により、合計特殊出生率は、前回推計の仮定より低下。 |
| (2005) |
|
(2055) |
男 78.53歳
女 85.49歳 |
 |
中位 |
男 83.67 <80.95>
女 90.34 <89.22> |
| |
※ < >内は前回推計(H14)の2050年の仮定値 |
|
|
| 日本の総人口 |
2005年
1億2,777万人 |
→ |
2055年
8,993万人 |
| 老年人口(65歳以上) |
2,576万人
[20.2%] |
→ |
3,646万人
[40.5%] |
| 生産年齢人口(15〜64歳) |
8,442万人
[66.1%] |
→ |
4,595万人
[51.1%] |
| 年少人口(0〜14歳) |
1,759万人
[13.8%] |
→ |
752万人
[8.4%] |
| 日本の総人口 |
2000年
1億2,693万人 |
→ |
2050年
1億 59万人 |
| 老年人口(65歳以上) |
| 2,204万人[17.4%] |
→ |
3,586万人[35.7%] |
| 生産年齢人口(15〜64歳) |
| 8,638万人[68.1%] |
→ |
5,389万人[53.6%] |
| 年少人口(0〜14歳) |
| 1,851万人[14.6%] |
→ |
1,084万人[10.8%] |
|
|
合計特殊出生率の推移と将来人口推計(平成18年推計)における仮定値 |
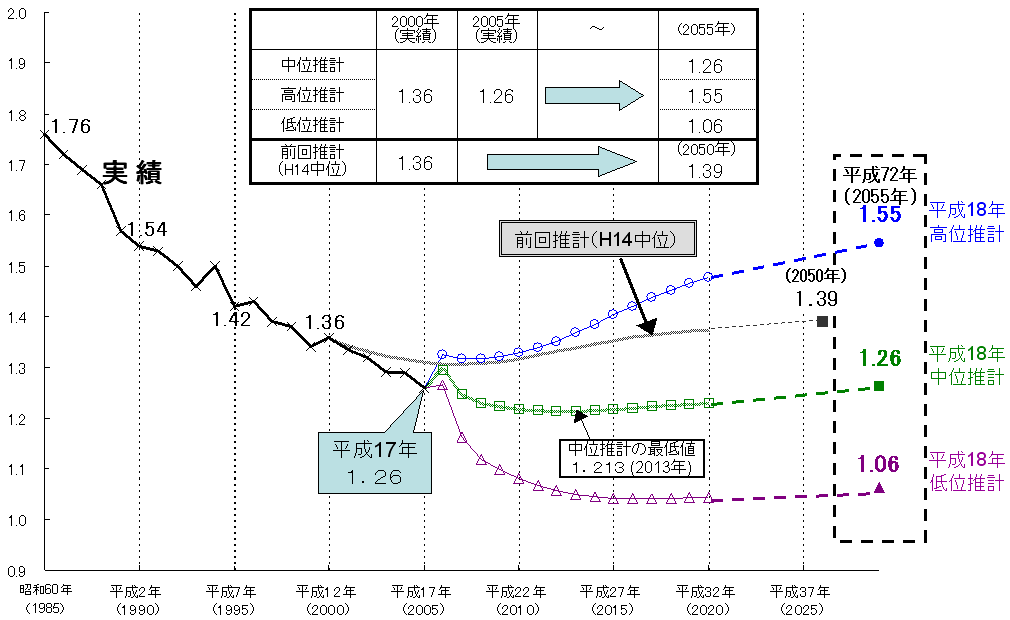
我が国の人口の推移
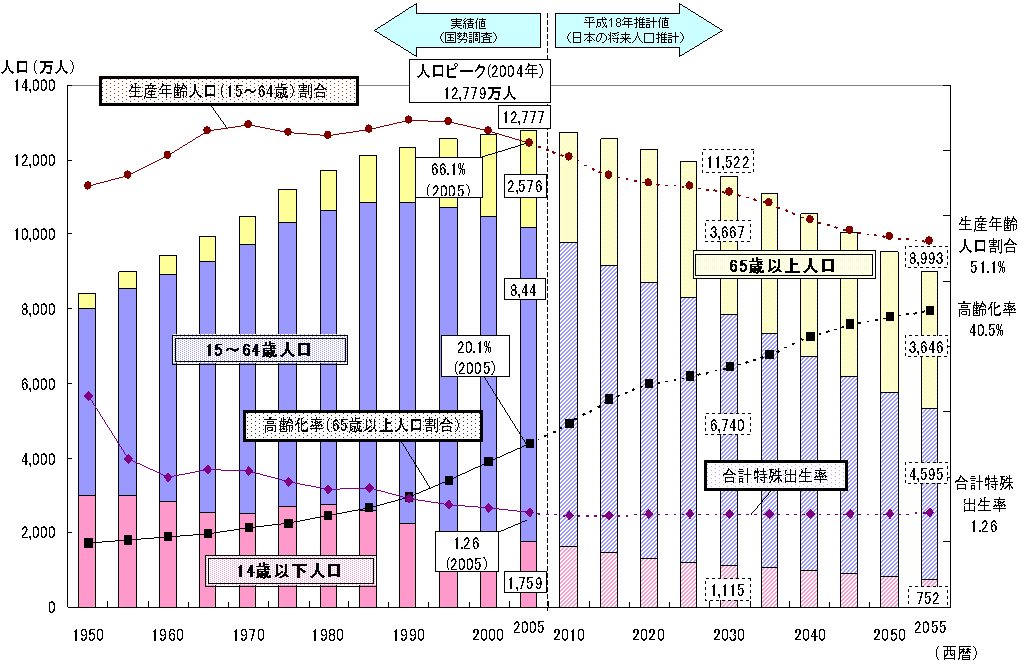
資料:2005年までは総務省統計局「国勢調査」、2010年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成18年12月推計)中位推計」
| ○ |
近年の少子化傾向は、結婚や出生等に係る意識調査を見る限り、必ずしも国民が望んだ結果ではないことから、仮に各種障壁が取り除かれ、国民の希望が一定程度叶った場合の将来の人口の姿について、仮定的に試算する。
(公表は1月下旬目途) |
|
| ○ |
2030年までの生産年齢人口は既にほぼ確定。現状のままでは労働力人口は減少。 |
| |
| 人口減少の影響を技術革新等でカバーする一方で、高齢者や女性等の就労支援等によって労働力率を向上させ、良質な労働力を確保していくことが重要。 |
|
| ○ |
更に高齢化が進む2030年以降は、これから生まれる世代が社会経済の支え手となる。 |
| |
| 今から効果的な少子化対策に取り組み、2030年以降の支え手減少を緩和することが急務。 |
|
|
| ○ |
人口推計が厳しいものとなることは予測されていたことから、19年度予算案では最大限効果的な対応を図ったところ。 |
| ○ |
更に、特別部会の議論や仮定人口試算を踏まえ、結婚や出産に係る国民の希望と実態との乖離を縮めるための効果的な施策の展開を図っていく。 |
|
| ○ |
社会保障審議会年金部会において、厚年法等の規定に基づき、財政検証議論を開始。
(平成21年までに検証結果とりまとめ予定) |
| ○ |
その議論の際の資料の一つとして、将来の人口の見通しの変化や近年の経済動向などを踏まえた財政影響に関する暫定的な試算を速やかに実施したい。
(公表は1月末目途) |
|