参考資料2
「特定健康診査及び特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(案)」より
1 重要事項に関する規程
1-1 運営についての重要事項に関する規程
(1)健診・保健指導機関による情報公開の必要性
医療保険者が健診・保健指導を委託できる機関の基準が告示により定められていることから、医療保険者が委託先を探すにあたって、委託基準を満たしている機関であるか否かを判別できるよう、健診・保健指導機関は基準の遵守状況について情報を公開する必要がある。
(2)規程として予め定めておくべき項目
省令及び告示に運営等に関する基準を示しているが、この中において、規程として定めておくべき7項目(保健指導は8項目)を挙げている。
<特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第○条の規定に基づき厚生労働大臣が定める者>(抜粋)
五 運営等に関する基準
6(※保健指導は7) 次に掲げる事項の運営についての重要事項に関する規程を定め、当該規程の概要を、医療保険者及び受診者が容易に確認できる方法(ホームページ上での掲載等)を通じて、幅広く周知すること。また、規程の概要を周知するに当たっては、指定の様式により行うこと。
・事業の目的及び運営の方針
・統括者の氏名及び職種(※保健指導のみ)
・従業者の職種、員数及び職務の内容
・特定健康診査(特定保健指導)の実施日及び実施時間
・特定健康診査(特定保健指導)の内容及び価格その他の費用の額
・事業の実施地域
・緊急時における対応
・その他運営に関する重要事項
1-2 規程の概要
(1)健診・保健指導機関による情報公開の必要性
医療保険者が健診・保健指導を委託できる機関の基準が告示により定められていることから、医療保険者が委託先を探すにあたって、委託基準を満たしている機関であるか否かを判別できるよう、健診・保健指導機関は基準の遵守状況について情報を公開する必要がある。
(2)概要の必要性
規程は詳細を記述するものであることから、量的にも相当なもの(イメージとしては金融商品等の約款のようなものになる可能性が高い)になるため、即座に理解・把握することは難しいことが想像される(十分に読みこむ必要がある可能性が高い)。
医療保険者が委託先を探す際は、まずはアウトラインをつかんで比較検討により絞り込み、その上で詳細な情報が必要となる。そのため規程そのものの周知は必要ではないが、その概要がわかるものについては周知が必要である。
(3)概要に記載すべき事項
規程の概要は、(1)(2)に述べたように、医療保険者が委託先を探すための情報であることから、各機関独自の表記方法で公開された場合、比較検討が困難になる。
そのため、共通の様式を用いて記載することとしている(様式については本書巻末の付属資料を参照のこと)。
なお、様式は一部の項目を除き必須記載項目となっていることから、必須記載項目は全て記載すること、また一部の項目については選んだ選択肢によっては委託基準を満たさなくなること(例えば「受診者に対するプライバシーの保護」の項目で「無」を選んだ場合は基準を満たさない機関となる)に注意が必要である。
図表1:重要事項に関する規程の概要(健診機関用)の様式イメージ
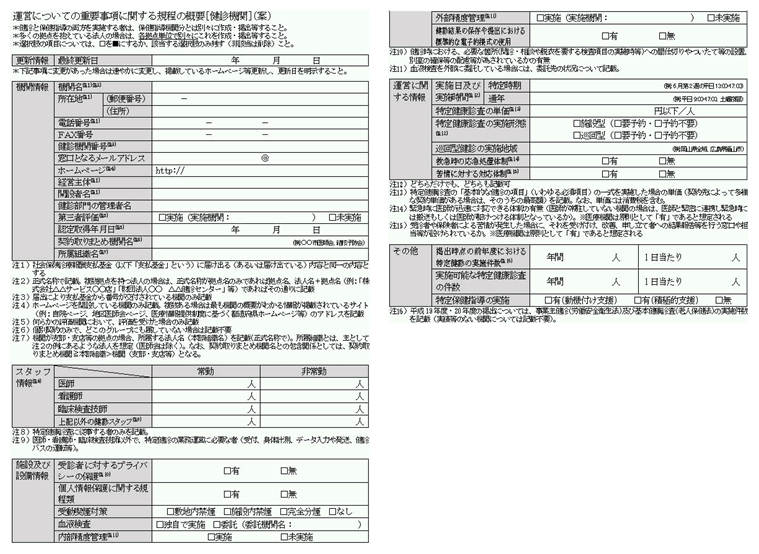
(4)概要の作成単位
規程の概要は、人員配置基準や施設基準、実施時間を明記することから、複数の実施拠点を抱える機関が、機関単位で作成した場合、医療保険者にとって当該機関が基準を満たしているか否かが分かりにくい(拠点によっては満たしていない基準があるかもしれないが、それが判別できない)だけでなく、拠点によって実施時間が異なる場合に、受診者にとってもわかりにくい。
以上を踏まえ、運営についての重要事項に関する規程の概要(ホームページ等)は、実施拠点単位で作成することになっている。
1-3 概要の公開・更新
(1)公開する場
医療保険者並びに受診者(利用者)が健診・保健指導機関に関する情報を容易に確認できることが重要である。
また、健診・保健指導機関にとっても多くの医療保険者・受診者(利用者)の目に触れる場に情報を公開することが顧客獲得上重要であるとも言える。
以上を踏まえると、基本としてはホームページという形式で公開することがポイントになるが、掲載場所(サイト)をどこにするかが双方にとって重要である。
基本的には、どこのサイトに掲載しても構わない。自機関のサイトが基本になると考えられるが、所属する団体やグループ等のサイトや、よく閲覧される有名サイト(掲載料が高額である可能性があるが多くの人の目に触れる効果を優先する場合)に掲載することも一つの考え方である。
また、どこにも掲載先がないという機関は、国立保健医療科学院に無料の掲載場所(健診・保健指導機関データベース)が設けられる(平成19年7月中旬以降)ことから、その場を借りて公開することも考えられる。
(2)情報の更新
公開している規程の概要の内容に変更があった場合は、医療保険者が公開情報で確認している内容と実際の状況に差異が生じた状態となったままであると、公開情報を元に委託先を決めていたならば特にトラブルの元になることから、速やかに掲載している情報を更新する必要がある(紙での掲示では再配布・変更通知等の手間が生じることから、変更した情報が即座に公開される点もホームページでの公開の利点がある。)。
共通の様式には、上述のようなトラブルの発生を未然に防ぐ一助となるよう、いつ時点の情報であるかを明確にするために、最終更新日の欄を設けている。更新の都度、この欄の日付を更新しておくことが重要である。
加えて、可能な範囲で、更新した箇所がわかるような配慮があることが望ましい(例えば、太字にする、書体やフォントサイズを変える、色を変える等)。
2 健診・保健指導機関番号
2-1 番号とは
(1)健診・保健指導機関番号の必要性
健診・保健指導の結果は、電子データの形で標準的に定められたファイル形式に基づきやり取りされることになっている。データのやり取りは、健診・保健指導機関から代行機関や医療保険者(その逆も)、代行機関から医療保険者(その逆も)、医療保険者間(他の医療保険者に実施を委託している場合や、医療保険者間の異動による加入者のデータの授受)医療保険者から支払基金(国への実績報告)等、さまざまな主体の間で為される予定である。
ファイルのやり取りに当たっては、発信者や送付先、送付内容(医療保険者への納品なのか、国への実績報告なのか等)がファイルに明示されていないと、正しい送付先に正しい内容のものが送られているかを判別できないため、標準的なファイル形式においては、健診・保健指導の結果データや請求データだけではなく、これらの情報を記載する領域が設けられている。
この時、発信者や送付先を機関名で記載した場合、さまざまな記載方法が発生する可能性がある(例えば、国への実績報告時の送付先に、「国」「厚労省」「厚生労働省」等記載者によってさまざまな記載の可能性がある)ことから、誰もが同じ記載方法となるよう、番号での記載に統一することとした。
(2)基本的な付番ルール
医療保険者には保険者番号(8桁)が、医療機関には保険医療機関番号(10桁)が、それぞれ既にあることから、医療機関でない健診・保健指導機関や代行機関に新たに番号を用意することとした。
既に保険医療機関番号を保有する機関は、新たな番号を持つよりも既存の番号を利用する方が合理的であること、またそうなると既存の保険医療機関番号に準じた付番ルールが適当なことから、付番ルールは次のようにした。
| 桁数 | 区分 | 内容 |
|---|---|---|
| 2 | 都道府県コード | 機関所在の都道府県番号(0〜47) |
| 1 | 機関区分コード | 保険医療機関(医科)=1 |
| 1及び3〜0以外の健診・保健指導機関=2 | ||
| 6 | 機関コード | 原則として、届出順に付番 |
| 1 | チェックデジット | 健診・指導機関番号の先頭から9桁を使用し、モジュラス10ウェイト2・1分割(M10W21)方式により設定。 (1)=チェックデジットを除いた部分の末尾桁を起点として、各数に順次2、1、2、1の繰り返しで乗じる。 (2)=(1)で算出した積の和を求める(但し、積が2桁になる場合は1桁目と2桁目の数字の和とする)。 (3)=10と(2)で算出した数字の下1桁の数との差を求め、これをチェックデジットとする(但し、1の位の数が0の場合はチェックデジットを0とする)。 |
(3)付番ルールにおける留意事項
国保ベースの集合契約(詳細は6-2参照)において、国保が市町村の一般衛生部門に健診・保健指導の実施を委託する場合、集合契約における委託先が市町村の一般衛生部門となる。そのため、受託する市町村は健診・保健指導機関として番号の取得が必要となる。
また、特に保健指導実施後の評価における委託との区別をつける上で、医療保険者自身が実施する場合(他の医療保険者から受託しない場合に限る。受託する場合は健診・保健指導機関としての届出が必要)の番号も設けておく必要がある。
| 桁数 | 区分 | 市町村一般衛生部門が健診・保健指導機関として登録する場合 | 医療保険者自身が実施する場合 |
|---|---|---|---|
| 2 | 都道府県コード | (通常と同じ) | 55 |
| 1 | 機関区分コード | 2 | 2 |
| 6 | 機関コード | 999(自治体を示す)+現行市町村番号(3桁) | 111111 |
| 1 | チェックデジット | (通常と同じ) | 1 |
2-2 番号取得申請
(1)番号の一元管理
健診・保健指導機関番号は、各機関が独自に番号を設定するのではなく、一意に定まっているよう、一元的に発番および失効情報等の管理を行う必要がある。
そのためには、付番センターのような機能が必要となるが、あくまで健診・保健指導の委託は、医療保険者の自由意志による契約に基づくものであることから、健診・保健指導機関が委託基準を満たしているか否かの認定と同様、国で管理することは適当ではなく、民間が共同でそのような機能を持つことが理想である。
しかし、制度施行までにそのような機能の提供が民間で整わない可能性が高いため、以下の理由から支払基金にて一元管理を行っていくこととなった。
○番号を用いての処理が最も必要となるのは代行機関であり、その中でも支払基金は国保ベースの集合契約における代行処理を取り扱う全国規模の最大手となること
○加えて、支払基金は、代行機関としてだけでなく、国への実績報告も受け付ける等健診・保健指導データの処理が集中すること
○支払基金には都道府県支部があり、レセプト処理業務において医療保険者や医療機関との長年の関係がある(突如出現したよくわからない組織ではなく一定の信頼に足ること)等、全国の健診・保健指導機関からの付番申請に対応できる規模・体制があること
(2)申請方法
医療保険者から健診・保健指導の委託を受けようと考えている機関は、機関の立地する都道府県の支払基金の支部に、届出を行う。
届出は、支払基金所定の様式(保険医療機関番号の取得とほぼ同様)に必要事項を記入し提出することにより行う。
平成19年9月頃から受付を開始する予定。
図表4:健診・保健指導機関番号の申請様式
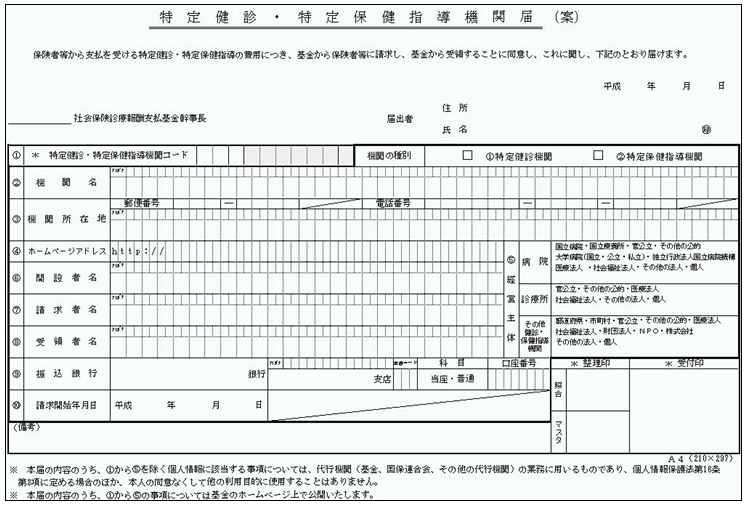
(3)申請に当たっての留意事項
届出様式には、に示した「運営についての重要事項に関する規程の概要」を公開しているホームページのURLを記載する欄があることから、申請前に「運営についての重要事項に関する規程の概要」を作成・公開しておくことが前提となる。これは、支払基金のホームページにおいて市町村別に健診・保健指導機関のリストを公開する際に、リストに掲載されている機関が委託基準を満たしていることを確認できるよう、リンク先として表示するためである。
既に保険医療機関番号を保有している医療機関についても、新たな番号取得の必要はないが、申請が必要となる。これは、保険医療機関の全てが健診・保健指導を受託する訳ではないため、支払基金ホームページの健診・保健指導機関リストに委託基準を満たした機関として掲載される必要があるためである。同様に、医療保険者が他の医療保険者から受託する場合も、保険者番号があるため新たな番号取得の必要はないが、健診・保健指導機関としての届出が必要となる。
医療保険者が事業主の産業医・保健師等に委託する場合、当該事業主が、加入する医療保険者からの受託に限る(他の医療保険者から幅広く受託しない)場合は、必ずしも番号の取得は必要ない(医療保険者自身が実施する場合と同様に見做せるため)。但し、その場合でも委託基準の遵守や「運営についての重要事項に関する規程の概要」の公開(この場合は医療保険者への提示)は必須である。