| 3 | 生活保護制度について(保護課、指導監査室) |
| (1) | 平成18年度生活保護基準の改定 |
| ア | 生活扶助基準の改定 生活扶助基準については、一般国民の消費水準との均衡が図られるよう、政府経済見通しにおける民間最終消費支出の伸びを基礎とし、国民の消費動向や社会経済情勢を総合的に勘案して改定しているが、平成18年度においては、改定を据え置くこととしたものである。 |
標準3人世帯(33歳・29歳・4歳)の生活扶助基準額
| 平成17年度 | 平成18年度 | |
| 1級地−1 | 162,170円 | 162,170円 |
| 3級地−2 | 125,680円 | 125,680円 |
| イ | 生活保護基準の見直しについて 生活保護基準については、平成15年から16年にかけて開催された「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」の報告を踏まえ、平成16年度から順次見直しを行っているところであるが、平成18年度における見直しの内容については以下のとおりであるので、改正の趣旨や支給額の変更等について管内の福祉事務所及び被保護世帯への周知方についてよろしくお願いしたい。 |
| (ア) | 母子加算の見直し(2年目) 平成17年度において、母子加算の子どもの年齢要件を見直し、16〜18歳の子どものみを養育するひとり親世帯について、母子加算を廃止することとしたが、当該母子世帯の生活水準が急激に低下することのないよう、3年かけて段階的に廃止していくこととしている。
なお、15歳以下の子どもを養育するひとり親世帯(子どもを2人以上養育している場合で末子の年齢が15歳以下の場合も含む)に係る母子加算については、平成19年度以降、自立支援プログラムの定着度合等を見据えつつ、支給要件、支給金額等を見直すこととしているので、ご承知願いたい。 |
| (イ) | 多人数世帯の生活扶助基準額の適正化(2年目) 多人数(4人以上)世帯の生活扶助基準については、世帯人員が増すにつれて第1類費の比重が高くなり、スケールメリット効果が薄れるため、一般低所得世帯の消費実態と比べて割高となるとの指摘がなされている。このため、一般低所得世帯の消費実態、消費構造を踏まえ、世帯規模の経済性を反映した水準となるよう、平成17年度から3年計画で、第1類費算定において逓減率を導入しているところである。 具体的には、多人数世帯の第1類費の算定に際し、以下の逓減率を乗じて算定することとしている。 |
| 17年度 | 18年度 | 19年度 | |
| 4人世帯 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
| 5人以上世帯 | 0.96 | 0.93 | 0.90 |
| (ウ) | 老齢加算の段階的廃止(3年目) 老齢加算については、平成16年度から3年計画で段階的に廃止することとしているものであり、平成18年度において全廃することとしている。
|
| (エ) | 障害者福祉制度見直しへの対応 「障害者自立支援法」が平成18年度から施行されることに伴い、障害者施設入所者について食費等の実費負担が生じることとなるが、被保護者についても同様に実費負担が生じるため、障害者施策からの補足給付で賄えない実費負担分を基準生活費の特例として設定し、給付することとしている。 |
障害施設入所者の基準額(基準生活費の特例)
| 20歳以上 | 18,19歳 | 18歳未満 | |
| 基準額 | 22,000円以内 | 10,000円以内 | 1,000円以内 |
| ウ | その他の改定 重度障害者他人介護料、出産扶助(施設分娩)、生業扶助の技能修得費(高等学校等就学費を除く)、葬祭扶助基準については、それぞれの扶助の性格を踏まえ、費用の実態等を勘案し、所要の改定を図ることとしている。 |
| (2) | 生活保護の動向 |
| ア | 近年の保護動向 最近の保護動向は、被保護人員が最低であった平成7年度と比較すると、人員、世帯共に急激に増加している。 |
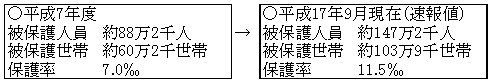
| イ | 近年の保護動向の特徴 |
| (ア) | 世帯類型別世帯数の状況 (1)高齢化の進展を受けて高齢者世帯が増加している一方、近年の景気の影響を受けて、(2)稼働能力がある者を多く含む母子世帯やその他世帯の伸びも顕著である。 |
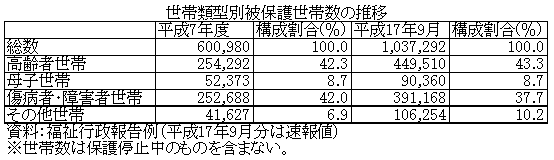
| (イ) | 世帯の状況 世帯の単身化が進んでおり、現在被保護単身世帯の割合は73.7%となっている。特に高齢者世帯においては9割を占めている。 |
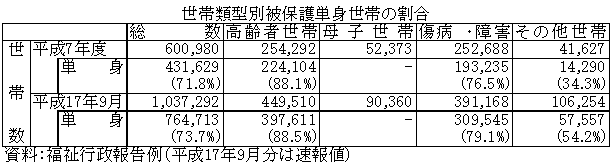
| (ウ) | 生活保護の開始及び廃止状況 保護の開始世帯数については、平成16年度において減少に転じたものの、廃止世帯数は微増に止まっているため、被保護人員、世帯共に増加する結果となっている。 |
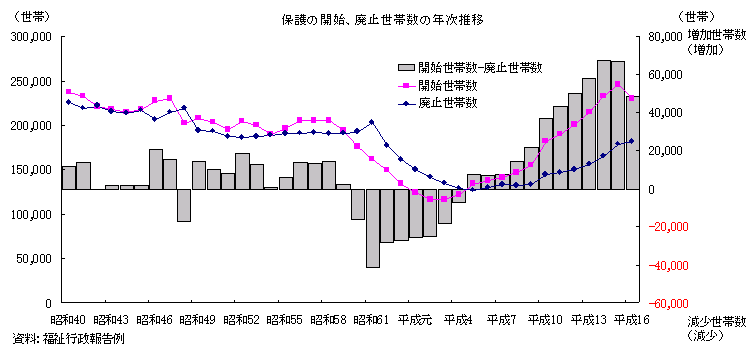
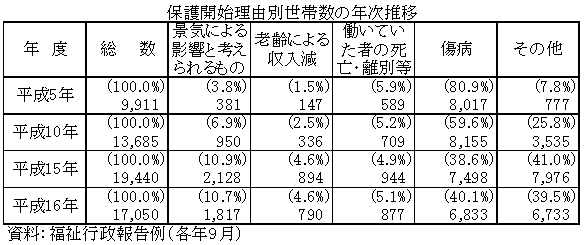
| ウ | 今後の保護動向 最近の社会経済情勢をみると、人口の高齢化に伴い高齢者数が増加していることや、引き続き完全失業率が高い水準で推移していることから、今後とも被保護人員及び被保護世帯数の増加傾向は続くものと考えられる。 しかしながら、完全失業率が平成16年平均で4.7%あったものが、平成17年9月には4.2%と改善の傾向がみられ、また、有効求人倍率も平成16年平均で0.83倍であったものが、平成17年9月には0.97倍に改善している。 こうした雇用情勢の改善傾向等を受けて、被保護人員の増加の伸びは平成16年平均の5.9%から、平成17年9月には3.6%と鈍化する傾向にある。 |
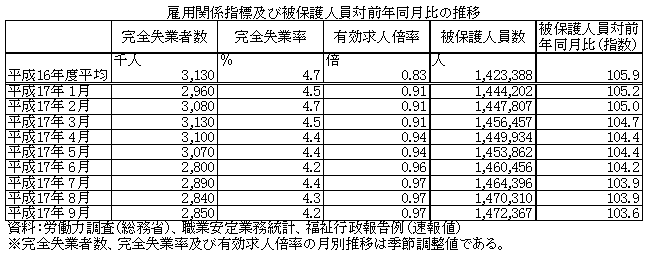
| エ | 積極的な保護動向の把握 稼働能力のある者を多く含む母子世帯やその他世帯等が増加していることから、自立に向けた一層の取組が求められるところである。 このため、各都道府県におかれては、管内各自治体の保護動向について、年齢階級や世帯類型等様々な角度から積極的に分析を行い、地域の特徴に即した保護の適切な運営が図られるようお願いしたい。 |
| (3) | 生活保護の適切な運営 生活保護は、国民生活の最後の拠り所となる制度であり、国民の理解と信頼を得られるよう、次の点に留意し、適切な保護の決定実施を行う体制の整備が講じられるようお願いしたい。 |
| ア | 自立支援プログラムの推進について |
| (ア) | 生活保護制度について、経済的な給付に加え、組織的に被保護世帯の自立を支援する制度に転換するため、その基本的な手段として、平成17年度から自立支援プログラムの導入を推進している。 厚生労働省としては、
地方自治体におかれては、自立支援プログラムの定着に向けて、実施機関がより多くの自立支援の経験を積むことが必要であることから、まずはできる限り多くの被保護者が個別支援プログラムに参加することを目標とし、管内の被保護者の状況やその自立阻害要因の状況を踏まえ、優先的に対応が必要とされる事項、あるいは地域の社会資源に照らして早期に実施可能な事項から順に、簡便な支援策も含め、被保護者の抱える課題にできるだけ幅広く対応する個別支援プログラムを積極的に整備されたい。 |
| (イ) | 生活保護受給者等の就労支援について 平成17年度よりハローワークが中心となって福祉事務所と連携して、就労・自立の意欲が一定程度以上ある生活保護受給者及び児童扶養手当受給者に対して、個々の対象者の態様、ニーズ等に応じてきめ細やかな就職支援を行う生活保護受給者等就労支援事業を実施し、一定の成果をあげているところである。(当省職業安定局及び職業能力開発局予算) 平成18年度においては、地方自治体の自立支援プログラムの導入をさらに推進するため、生活保護受給者については支援対象者数を拡充するとともに、児童扶養手当受給者についてはモデル事業として一部地域(東京都、大阪府、14の指定都市)で実施していた事業について全国展開するため、ハローワークに配置される就労支援コーディネーター及び就職支援ナビゲーターを増員することとしているので、ハローワークとの連携の強化を図るとともに、本事業を一層活用し、生活保護受給者の就労支援に積極的に取り組まれたい。
|
| (ウ) | 組織的な対応の確立について 各実施機関における保護の実施体制については、担当職員の配置数の不足や経験不足が見られるとともに、組織としての支援が十分でないために、担当職員の負担が過重となっている現状があることから、担当職員の確保や質の向上に努めるとともに、組織的な対応により業務を実施する体制を確立していく必要がある。 特に、自立支援プログラムは、組織としてシステム的に業務を実施する体制の確立を目指すものでもあるので、各実施機関において積極的に取り組まれるよう必要な支援及び指導をお願いしたい。 |
| イ | 保護の相談における窓口対応について 生活困窮者の発見及び適切な保護のために生活困窮者に関する情報が福祉事務所の窓口につながるよう、住民に対する生活保護制度の周知、保健福祉関係部局や社会保険・水道・住宅担当部局等の関係機関との連絡・連携を図るとともに、要保護者に対するきめ細かな面接相談、申請の意思のある方への申請手続の援助指導を行うよう努められたい。 |
| ウ | 医療扶助の適正運営 被保護者の適切な処遇の確保並びに生活保護費の適正支出を図る上で、医療扶助の適正運営は重要な課題であることから、各都道府県市においては、下記の事項に留意の上、長期入院患者の退院促進や頻回受診者に対する適正受診指導など、医療扶助の適正化対策について、地域の実情に応じた積極的な取組をお願いしたい。 |
| (ア) | 診療報酬請求書(レセプト)点検の徹底 診療報酬請求書(レセプト)の点検は、医療扶助受給者の病状把握や医療扶助費の適正な支出を図るために必要不可欠なものであることから、全てのレセプトについて点検を行うとともに、適宜点検効果の検証を行い、効果が不十分と思われる場合は点検方法の見直し(外部委託等)を行うなど、より効率的かつ効果的な点検を実施する。 |
| (イ) | いわゆる社会的入院の解消 いわゆる社会的入院患者に対しては、適切な受入先の確保を図るとともに、個々の退院阻害要因の解消や退院に向けた指導援助を行うため、精神保健福祉施策等他法他施策の活用を含めた自立支援プログラムの導入やセーフティネット支援対策等事業費補助金の活用による退院促進個別援助事業の実施など支援体制の充実を図る。 |
| エ | 介護扶助の適正運営 介護扶助受給者は着実に増加している一方、介護報酬の不正請求等不適切な事例も見受けられることから、指定介護機関に対して生活保護制度の周知等指導を徹底するとともに、介護保険担当部局等との連携体制の充実を図ることとされたい。 また、セーフティネット支援対策等事業費補助金の活用による居宅介護支援計画(ケアプラン)点検強化事業を実施するなど介護扶助の適正実施に努められたい。 平成18年4月の介護保険制度の改正に伴う介護扶助の対応については、内容が決まり次第お知らせするが、介護保険担当部局との連携を図り、実施につき遺漏のないように留意されたい。 なお、介護予防事業等を行う指定介護機関の指定については、指定申請手続き及び様式に関して生活保護法施行規則の改正を行う予定であり、また、介護保険における介護予防サービスの実施に合わせて、介護保険の被保険者以外の者について、要介護認定の見直しが必要となる者があるので、留意されたい。 |
| (4) | 保護施設の整備及び運営 |
| ア | 保護施設の整備 平成17年度補正予算(案)において、吹付けアスベスト(石綿)除去等に要する経費及び老朽施設の耐震化を図るための経費について所要額を計上したところであるが、平成18年度においても吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する施設のばく露の状況、及び耐震化整備の必要性について的確に把握し、整備に取り組まれたい。 なお、公立施設に係る施設整備費の税源移譲に伴い、平成18年度から公立施設は補助対象外となったところであるが、私立の施設整備については、従前どおり補助対象として実施することとしている。 |
| イ | 保護施設の運営 |
| (ア) | 入所者に対する居宅生活への移行支援等 救護施設及び更生施設については、生活扶助を行う機能に加え、入所者の地域生活への移行の支援や居宅生活を送る被保護者に対する生活訓練の実施の場として活用されることが期待されている。 このようなことから、保護施設通所事業、救護施設居宅生活訓練事業及び救護施設居宅生活者ショートステイ事業に積極的に取り組み、入所者の居宅生活への移行が促進されるよう、救護施設、更生施設及び実施機関への働きかけを行われたい。 |
| (イ) | 保護施設への適切な入所 保護施設については、常に入所者一人一人の状況把握に努め、居宅での保護や他法の専門的施設での受入が可能な者についてはこれを優先するなど、当該施設への入所が適切か否かを検討し、必要に応じ入所先の変更を行うなど、より適切な処遇が確保されるよう、管内福祉事務所を指導されたい。 |
| (5) | 生活保護及び保護施設の指導監査 |
| ア | 生活保護法施行事務監査関係 被保護世帯の増加にもかかわらず必要な現業員、査察指導員の確保がされず、また、査察指導員のケース審査と業務進行管理等査察指導機能が十分確立されていない等のために、保護の要件の確認、生活実態の把握、自立への支援等適切な保護の決定実施上の基本的事項に問題が認められる福祉事務所が少なからず見受けられる。 こうした観点から、都道府県本庁の生活保護法施行事務監査においては、特に、必要な現業員の充足及び査察指導体制の充実・整備、不正受給防止等の観点からの関係先調査や課税調査等各種調査の徹底等について指導し、併せて管内福祉事務所ごとの課題に応じた具体的な助言・指導を行うようお願いしたい。 また、福祉事務所長等幹部職員に対しては、常に管内の保護動向、福祉事務所全体の生活保護の運営状況、問題点を十分把握・分析の上、必要に応じて業務量の把握や業務分担の見直し、関係機関との連携確保、査察指導機能の強化、円滑な制度運営確保のための体制整備等に努めるよう指導し、組織的な運営管理の推進が図られるようお願いしたい。 (参考)
|
| イ | 保護施設監査関係 保護施設においても、健全で安定した運営の下に、入所者個々の特性に合った適切な入所者処遇が確保されるためには、施設に対する都道府県、指定都市及び中核市の指導監査の果たす役割が改めて重要となっている。 平成18年度の監査に当たっては、適切な入所者処遇の確保及び施設の適正な運営管理体制の確立とともに、施設の衛生管理や感染症予防にも重点を置き、適切な施設運営が図られるよう、引き続き厳正な指導監査の実施をお願いしたい。 |