| 4. | 介護給付の適正化等について |
| (1) | 介護給付適正化の取組みについて |
| 介護保険制度の施行状況をみると、サービス利用は急速に拡大しており、老後を支える基礎的な社会システムとして着実に定着している一方で、提供される介護サービスが真に所期の効果をあげているかとの観点、不適正・不正な介護サービスはないかとの観点から改善の余地があるものと考えている。 介護保険制度において、介護給付の適正化は喫緊の課題であり、常に提供された介護サービスが要介護者の「自立支援」に繋がるものとなっているか否かという視点から、介護給付の適正化を考えていく必要がある。このような状況を踏まえ、平成16年10月から全保険者を対象とした「介護給付費適正化推進運動」を実施することとしたところであり、平成18年度においても、保険者をはじめ、国・都道府県・国民健康保険団体連合会が連携を強化しながら、より一層積極的に取り組んでいくことが必要である。 |
| ア | 現状の把握、分析等 |
| 介護給付の適正化に取り組むための前提として、それぞれの地域における介護保険の財政状況の分析や介護給付の動向等的確な把握が不可欠である。各保険者において、第2・3期介護保険事業計画における見込みと実際のサービス給付状況に乖離が生じていないかについて、継続的に把握するとともに、要介護度別、サービス種類毎の介護給付に関する動向等の把握及び分析に努めるよう、各都道府県においても配慮されたい。 |
・PDF:562KB
第1号被保険者に対する認定者数(第1号被保険者)の割合
|
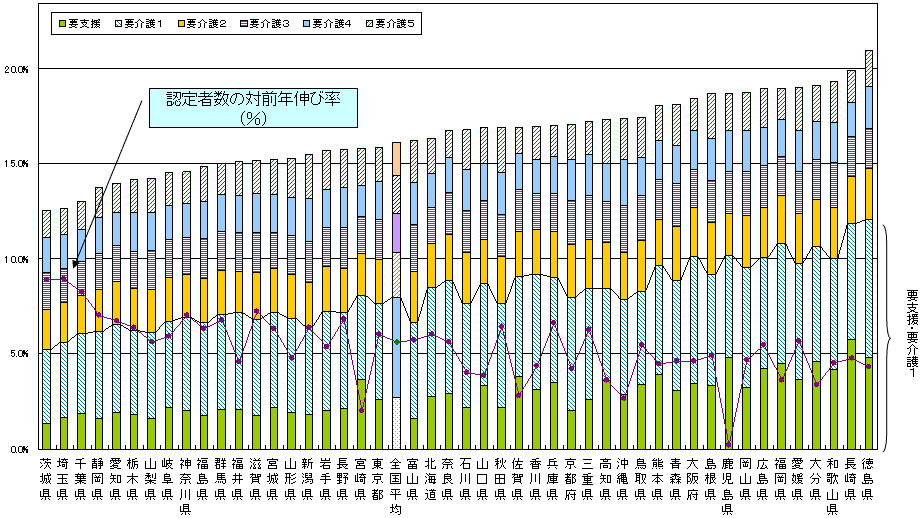 (出典:介護保険事業状況報告) |
| イ | 国民健康保険団体連合会との連携 |
| 各都道府県国民健康保険団体連合会(国保連)においては、保険者等が介護費用適正化対策のために活用できるよう、認定者や事業所の状況に関する各種情報を提供する体制が整備されているところである。 今後、このシステムについては、今制度改正による改修部分を含め、さらに充実強化することとしており、各都道府県におかれては、管下保険者がこの国保連のシステムを引き続き積極的に活用するよう、配慮されたい。 また、システムによる事業者情報の活用とともに、国保連が現在行っている苦情処理業務における苦情等に基づき、個々の事業者等に関する情報を収集し、都道府県や保険者に対し迅速に提供しており、都道府県や保険者の給付適正化の取り組みを支援しているところであり、今後とも、より一層、国保連との連携強化を図っていただきたい。 |
| ウ | 「介護給付適正化推進運動」の推進 |
| 介護給付費については、依然として10%近い伸びが続いている。 各保険者においては、介護給付の適正化に積極的に取り組んでいる保険者の効果的な事業実施例などを参考にしながら、地域の特性を踏まえ、ターゲットを絞り創意工夫を活かした「介護給付適正化推進運動」に、引き続き取り組んでいただきたい。 取組の状況については、都道府県において管下保険者の成果を含めて取りまとめていただくこととしており、昨年度同様平成18年度も別途、都道府県から厚生労働省がヒアリングを行うこととしている。 |
《具体的な取り組み》
|
介護給付適正化事業の主な実施例
(平成17年度厚生労働省における介護給付適正化推進運動ヒアリング結果より)
| 1. | 都道府県実施例 【独自システムの構築】
| ||||||||||||
| 2. | 市町村実施例 【アンケート調査を基にした事業者指導等の実施】
|
| (2) | 指定事業者等の指導の徹底について |
| ア. | 保険者(市町村)指導について |
| ○ | 平成16年10月から介護給付費の動向等を踏まえた「介護給付費適正化推進運動」を実施しているところであるが、平成18年度における保険者指導に当たっても、引き続き「(1)介護給付適正化の取組について」に掲げた事項に重点をおいた技術的助言をお願いしたい。 ついては、平成17年度における各保険者の介護給付費適正化推進運動の実施状況を把握した上、給付分析や適正化の取り組みが低調である保険者を対象に実地指導をお願いしたい。 |
| ○ | 低所得者の保険料に関し独自の施策を講じている保険者においては、(1)保険料の全額免除、(2)資産等を把握しないことによる一律の減免、(3)保険料減免に関する一般財源の繰り入れをしている保険者が一部みられる。 これらの方法による減免は、国民皆で制度を支える介護保険法の本旨に照らすと適切ではないので、保険者に対しては今後とも指導方お願いしたい。 また、利用料についても利用者の負担能力に関係なく全額免除又は一律に軽減している保険者が一部みられるが、利用者負担は、介護保険の負担の公平性や適切なコスト意識の喚起の観点から設けられたものであるので、制度の趣旨を踏まえ節度ある対応について指導方お願いしたい。 |
| イ. | 指定事業所に対する指導等について |
| (ア) | 平成18年度指導監査方針 平成12年4月の介護保険制度発足以降、介護サービス利用者の増大に伴い指定事業所(介護保険施設を含む)数が増加しているが、一方では運営基準等を遵守しない不適切なサービス提供や架空又は水増しといった不正な介護給付費の請求等を行ったため、指定取消処分を受ける事業所も増加していることは誠に遺憾である。 平成17年12月現在、指定取消処分の対象となった事業所は41都道府県で362カ所となっているが、これは氷山の一角であると危惧する向きもあることから、このような不正行為を行っている者が見逃されることがないよう、効果的な指導監査の実施が求められている。 また、指定取消には至らないものの、人員不足の際の介護報酬の減額算定等を行わないなど、過剰な請求を行っている事業所も増加しており、平成16年度においては、4,050事業所で約80億円の返還請求が行われているところである。 更に、会計検査院の「平成16年度決算検査報告」においても、介護療養型医療施設において特別な室料を徴している場合に療養環境減算が行われていない等の多くの指摘がなされているところであり、これは、平成13年度以降連続して指摘されているところである。 以上のことを踏まえ、平成18年度は次に掲げる事項に留意して指定事業所に対する指導監査に当たられたい。
|
||||||||||||||||||||||||||
| (イ) | 介護保険法改正関係
|
| ウ. | 指定取り消し事業者に対する介護報酬の返還について |
| 平成12年度から平成16年度までの5年間に313事業所の指定取り消しが行われており、そのうち245事業所については保険者において介護報酬の返還請求を行っているところであるが、その返還額は約4割となっている。 ついては、保険者に対しては次により介護報酬の不正請求に伴う徴収金の適正な債権管理を行うよう周知方お願いしたい。 |
| ○ | 保険者の徴収金債権の適正な管理について 介護報酬の不正請求に伴う徴収金については、指定取消を受けた事業者が指定期日までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税法の滞納処分の例により処分するなど、適正な債権管理を行うこと。 また、指定取消を受けた事業者の行方不明又は破産等の場合は、当該事業者の所在や財産の状況など必要な調査を行うとともに、差押えが可能な財産があるときは、徴収吏員により財産を差押え、換価し納付させるなどの処分を行うこと。 なお、当分の間、保険者における指定取消を受けた事業者に対する徴収金の納付(債権管理)状況を各年度末時点で把握することとしたので、別途お示しする様式により報告方お願いしたい。 |
| ○ | 国保連による指定取消事業者に対する介護報酬支払いの留保について 保険者の申し出による国保連の事業者に対する介護報酬の支払いの留保は現在でも一定の場合に可能となっているが、今後においては、都道府県、関係保険者及び国保連の連携により、事業所の指定取消と同時に国保連の介護報酬の支払いを留保するなど適切な対応を図られたい。 |