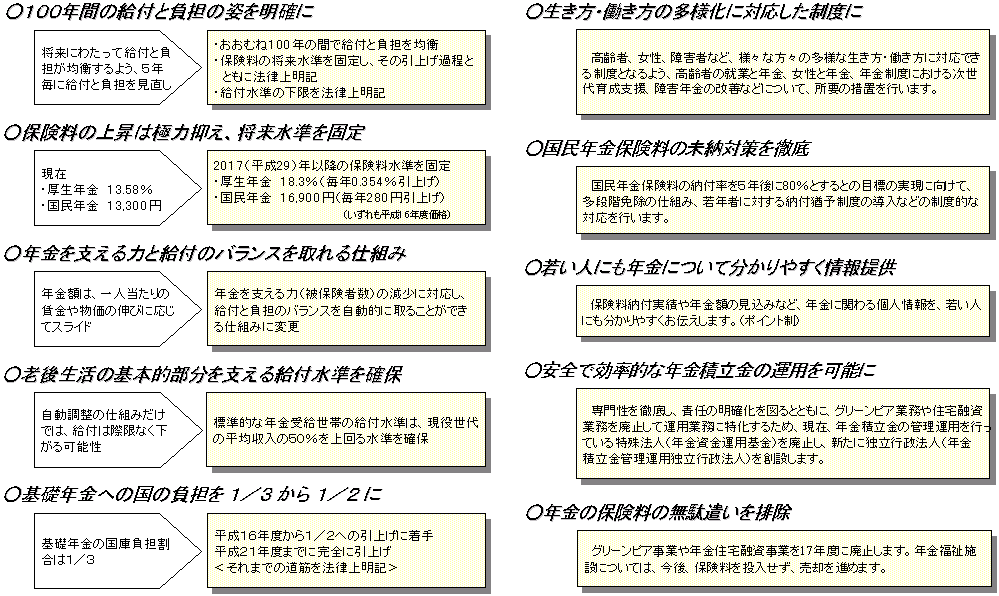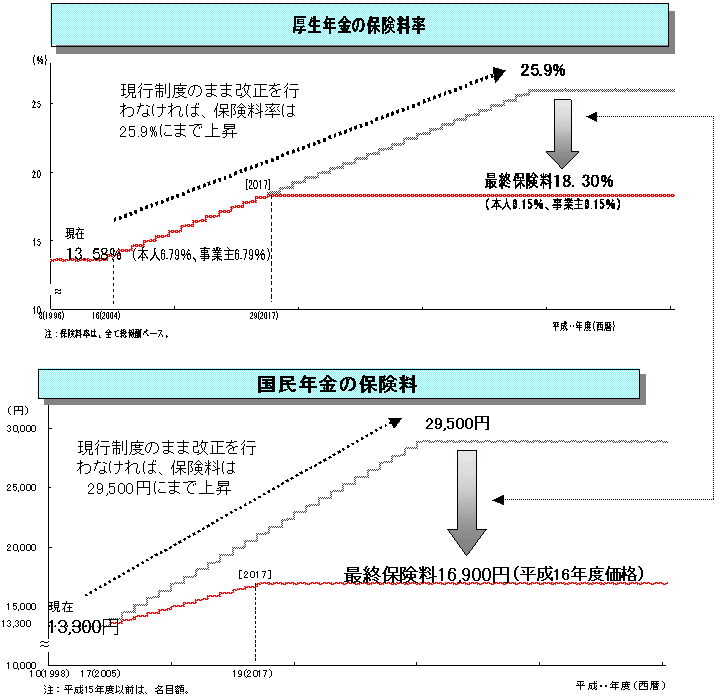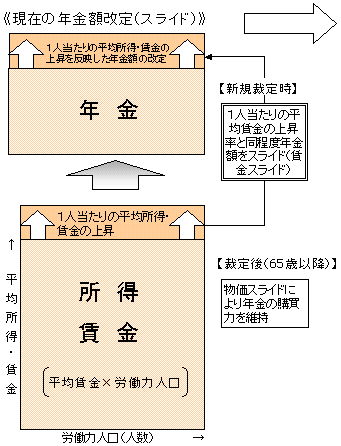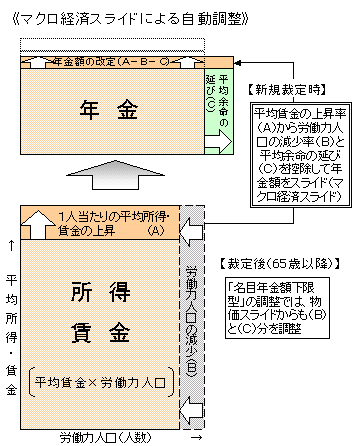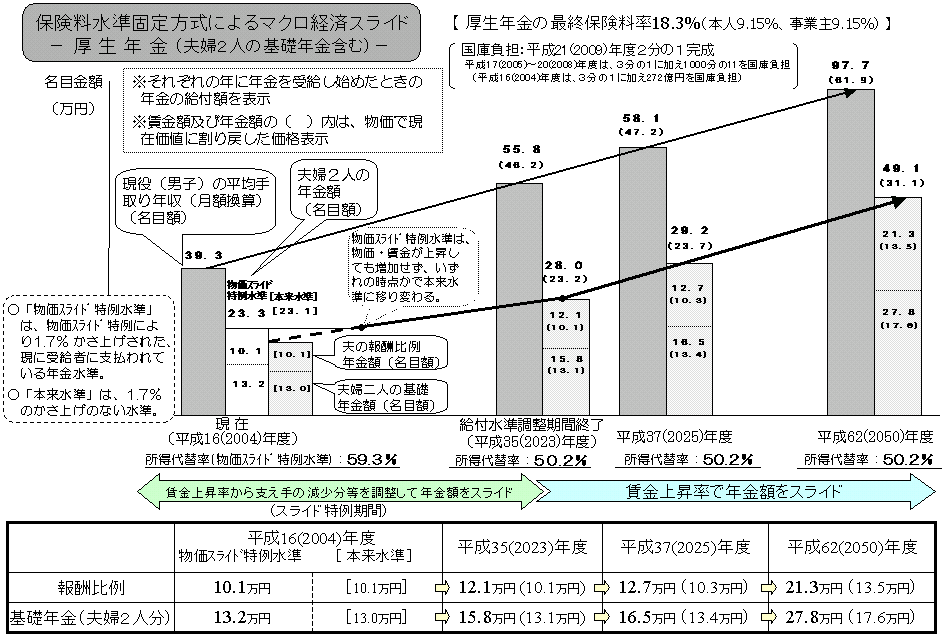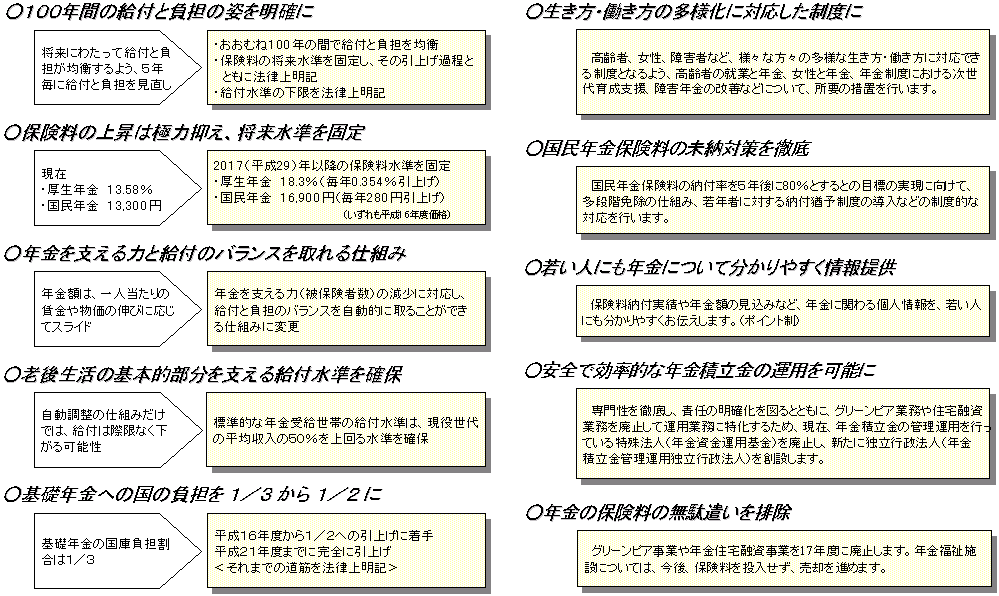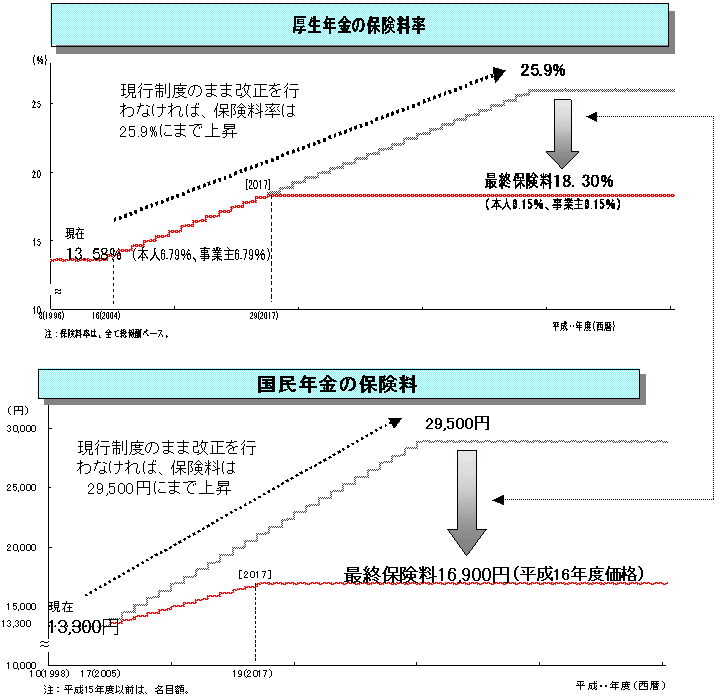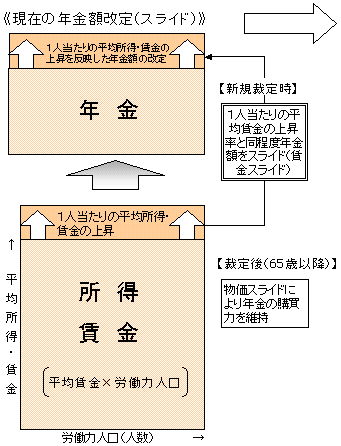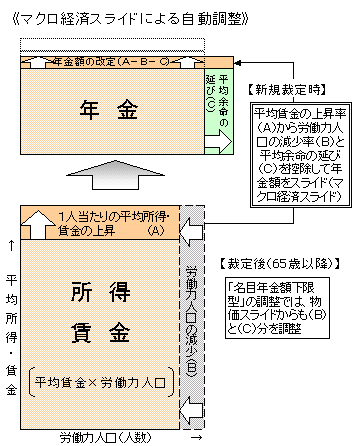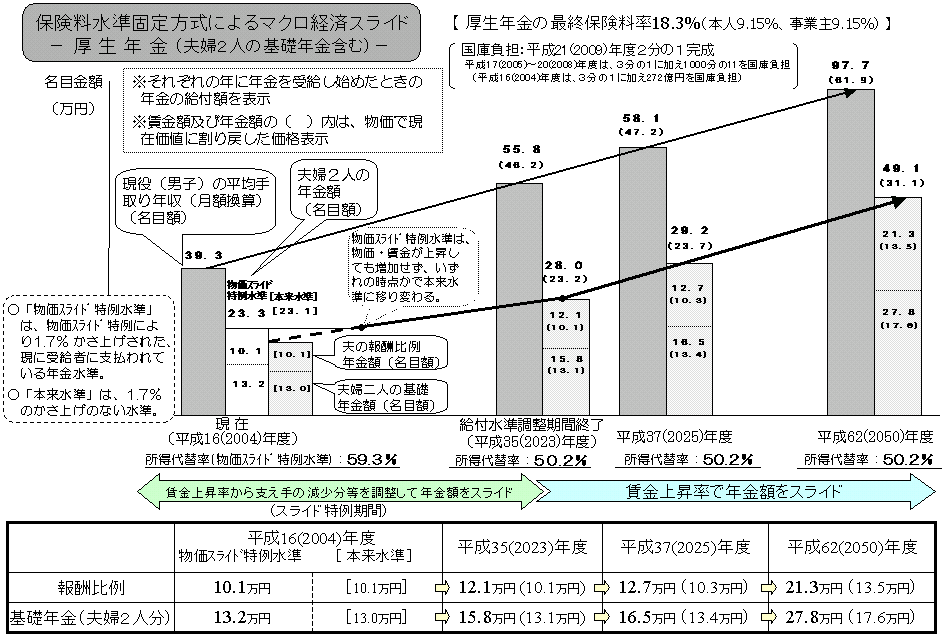今後の少子化の中でも、
標準的な年金の給付水準は、
年金を受給し始める時点(65歳)で
現役サラリーマン世帯の平均的所得の
50%を上回るものとする。 |
┌
│
│
│
└ |
現在の59.3%から、現役世代の
人口減少とともに水準を調整。
ただし、もらっている年金額は
下げない。 |
┐
│
│
│
┘ |
┌
│
│
│
│
│
│
│
└ |
年金をもらい始めた年以降
の年金額(名目額)は物価の
上昇に応じて増加するが、
通常は物価上昇率よりも
賃金上昇率の方が大きいため、
そのときどきの現役世代の
所得に対する比率は
下がっていくこととなる。 |
┐
│
│
│
│
│
│
│
┘ |
|
|
| 改正前 |
厚生年金:13.58%
(本人6.79%)
国民年金:13,300円 |
|
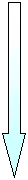 |
(厚生年金)
・平成16(2004)年10月から毎年0.354%(本人0.177%)の増
※平均的勤労者(月収36.0万円、ボーナス3.6ヶ月分)本人
各月650円
ボーナス1回1,150円(年2回)
(国民年金)
・平成17(2005)年4月から毎年月額280円の増(平成16年度価格) |
|
平成29(2017)年度以降
厚生年金:18.30%
(事業主9.15%)
国民年金:16,900円
(平成16年度価格※) |
| ※ |
「平成16年度価格」・・・16年度の賃金水準を基準として価格表示したもの。実際に賦課される保険料額は、16年度価格の額に、賦課される時点までの賃金上昇率を乗じて定められる。したがって、その額は今後の賃金の上昇の状況に応じて変化する。 |
|
|
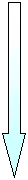 |
財源:年金課税の見直し(公的年金等控除の見直し、老年者控除の廃止)
┌
│
│
│
│
│
│
│
└ |
増収約2,400億円のうち
地方交付税分を除く
約1,600億円を
基礎年金に充当
| ※ |
平成17年の所得から
適用なので
16年度の充当分は
その1/6(272億円) |
|
┐
│
│
│
│
│
│
│
┘ |
|
平成17(2005)年度・18(2006)年度:
適切な水準にまで引上げ |
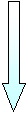 |
財源:【平成15年12月与党税制改革大綱】
個人所得課税の抜本的見直し |
| ← |
平成19(2007)年度を目途
【平成15年12月与党税制改革大綱】
消費税を含む抜本的税制改革を実現 |
|
|
平成21(2009)年度まで:
2分の1への引上げ完了 |
|
|