地域生活支援事業について
地域生活支援事業について
【事業の概要】
| ○ | 目的 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 |
| ○ | 性格 |
| (1) | 地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効率的・効果的な事業実施が可能である事業
|
| (2) | 地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業 |
| (3) | 生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも想定できる事業
|
| (4) | 障害者保健福祉サービスに関する普及啓発等の事業 |
| ○ | 内容 |
| (1) | 市町村地域生活支援事業 障害者、障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供等を行う事業、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付又は貸与、障害者等の移動を支援する事業、障害者等を通わせ創作的活動等の提供を行う事業(地域活動支援センター)等 |
| (2) | 都道府県地域生活支援事業 特に専門性の高い相談支援事業、広域的な対応が必要な事業、その他サービスの質の向上のための養成研修等 |
| ※ | 事業の内容は、P7「地域生活支援事業の内容(現行事業との比較)」参照 |
【実施主体】
| ○ | 市町村地域生活支援事業:市町村(指定都市、中核市を含む。) ただし、複数の市町村が連携し広域的に実施することや、事業の全部又は一部を団体等に委託し実施することが可能。 また、都道府県が地域の実情を勘案して、市町村に代わって地域生活支援事業を行うことができる。 |
| ○ | 都道府県地域生活支援事業:都道府県 |
| ※ | 指定都市や中核市は都道府県との取り扱いとしない。(いわゆる大都市特例は設けない。) ただし、これまでの経緯、事業の実施体制等を踏まえ、指定都市や中核市で都道府県事業を実施した方が適切に事業を実施できると考えられるものについては、都道府県と指定都市や中核市の間で調整のうえ、都道府県の事業としつつ、指定都市等に実施を委託することも可能。 |
【利用者負担】
| 地域の実情に応じて柔軟な実施が期待されていることから、利用者負担の方についても、基本的には事業の実施主体の判断による。 |
| ┌ │ │ │ └ |
従来の利用者負担の状況(その手法や額等)や、他の障害者サービス(個別給付の手法、低所得者への配慮)等を考慮し、実施主体として適切な利用者負担を求めることは考えられる。 | ┐ │ │ │ ┘ |
【18年度予算額】
| 地域生活支援事業の施行に必要な経費として、200億円(事業の施行は、平成18年10月であり、半年分を計上)を確保。 |
【国庫補助の方法】
| ○ | 実施主体と負担割合 |
| 市町村 | 国1/2 | 都道府県1/4 | 市町村1/4 |
| 都道府県 | 国1/2 | 都道府県1/2 | |
| ※ | 大都市特例の適用なし。 ただし、発達障害者支援センターは、大都市特例を適用。 |
| ○ | 国庫補助の配分について |
| ア | 基本的な考え方 |
| (1) | 統合補助金であることから、個別事業の所要額に基づく配分は行わない。 |
| (2) | 事業を行っていない市町村等については、全国水準並みに事業を実施するよう底上げを図る必要があること。また、現行の実施水準を反映する。 |
| (3) | 以上の観点から、次の組み合わせで配分額を決定する。
|
| イ | 配分の枠組み(案) |
| (1) | 市町村が実施する事業と都道府県が実施する事業の配分比率を以下のとおりとする。
|
| (2) | 事業実績割分と人口割分の配分比率を以下のとおりとする。 なお、19年度以降、人口割分に対する配分比率を高めることとする。
|
| (3) | 個々の市町村等への具体的な配分については、別途、必須事業(相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具、移動支援、地域活動支援センター)に係る事業評価の指標の実績を聴取したうえで、以下の考え方により決定する。
|
| ○ | 各市町村への具体的な配分の考え方 |
| ア | 事業実績割分の配分額 |
| 全国分の事業実績割分 | × |
|
| イ | 人口割分の配分額 |
| 全国分の人口割分 | × |
|
| ウ | A市合計配分額(ア+イ) |
| ○ | 各都道府県への具体的配分な配分の考え方 |
| 都道府県分の配分額 | × |
| =A県配分額 |
| ○ | 地域生活支援事業の内容(現行事業との比較) |
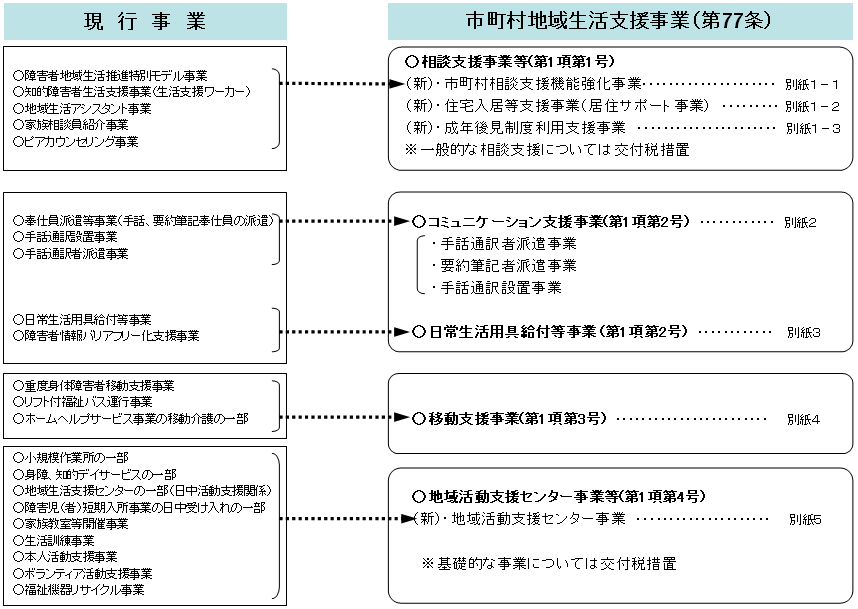
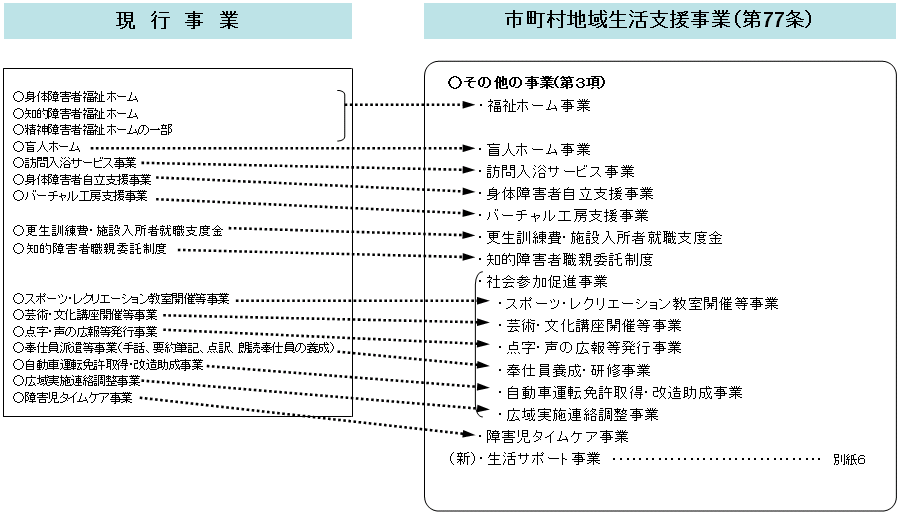
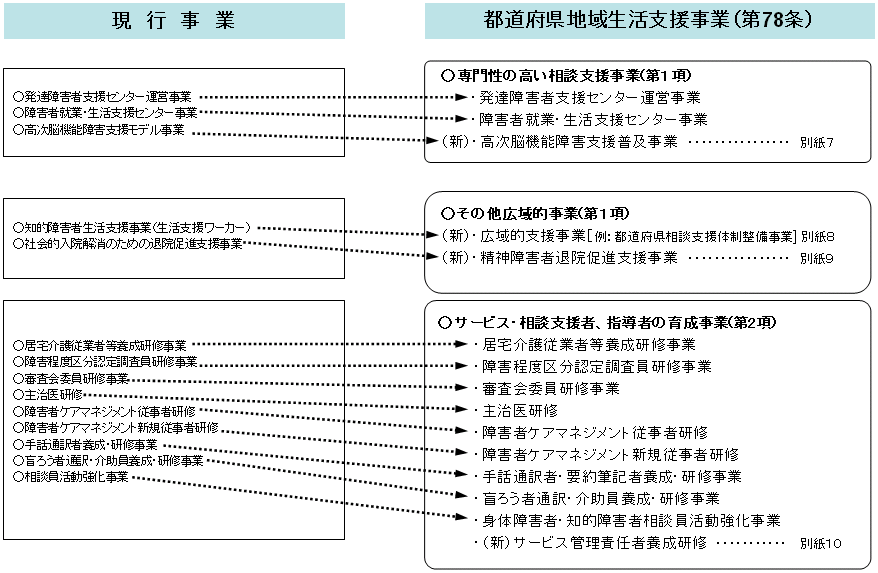
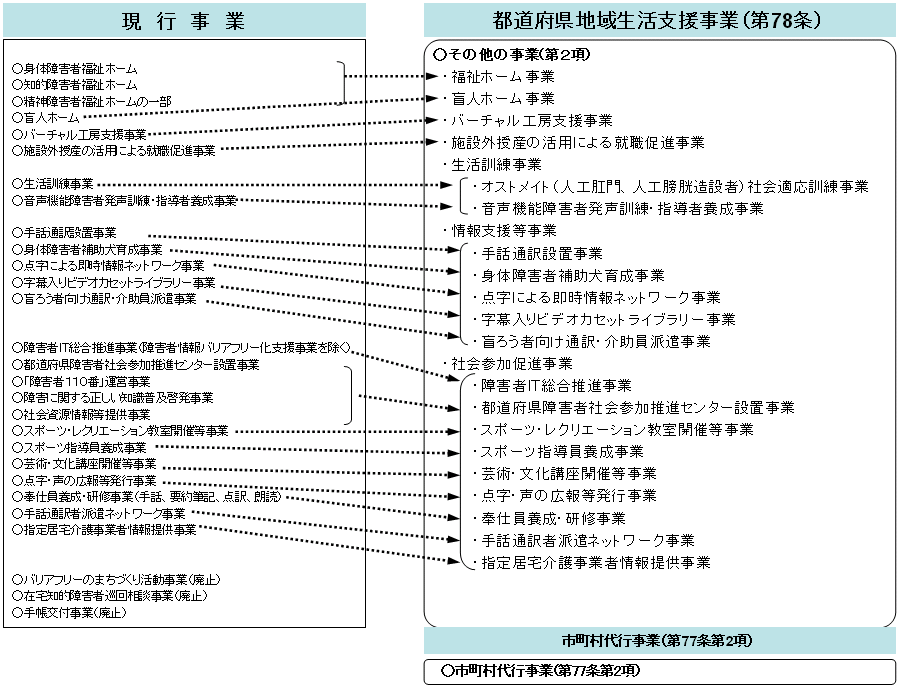
(別紙1−1)
| 市町村相談支援機能強化事業の概要について |
【概要】
| 市町村の相談支援事業の機能を強化するため、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を市町村等に配置する。 |
【事業の具体的内容】
| ・ | 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応 |
| ・ | 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等 |
【専門的職員の例】
| 社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市町村の相談支援事業の機能を強化するために必要と認められる者 |
【地域自立支援協議会等との関係】
| ○ | 地域自立支援協議会において、市町村内の相談支援体制の整備状況やニーズ等を勘案し、本事業によって配置する専門的職員について協議し、事業実施計画を作成 | ||||
| ○ | 都道府県自立支援協議会
|
【留意事項】
| 地域自立支援協議会を設置する市町村又は圏域等を単位として実施 |
(別紙1−2)
| 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の概要について |
【概要】
賃貸契約による一般住宅(※)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する。
|
【対象となる障害者】
|
知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者。 ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。 |
【事業の具体的内容】
| 賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者について、不動産業者に対する一般住宅のあっせん依頼、障害者と家主等との入居契約手続きにかかる支援、保証人が必要となる場合における調整、家主等に対する相談・助言、入居後の緊急時における対応等を行う。 |
| (1) | 入居支援(不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援) |
| ※ | 地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じその利用支援を行う。 |
| (2) | 24時間支援(夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等、必要な支援を行う。) |
| (3) | 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整 利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。 |
【留意事項】
| 共同実施も可能であり、指定相談支援事業者へ委託することができる。 |
(別紙1−3)
| 成年後見制度利用支援事業の概要について |
【概要】
| 知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な者について、障害者福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業に対して補助を行う。 |
【事業の具体的内容】
| 成年後見の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成 |
【対象者】
| 次のいずれにも該当する者 |
| ・ | 市町村が、知的障害者福祉法第27条の3又は精神保健福祉法第51条の11に基づく市町村長による後見等の開始の審判請求を行うことが必要と認める者 |
| ・ | 障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない(原則、2親等以内の親族がいない)重度の知的障害者又は精神障害者 |
| ・ | 所得状況等を勘案し、申立てに要する経費の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者 |
【対象経費】
| 成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部 |
(別紙2)
| コミュニケーション支援事業の概要について |
【概要】
| 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害(以下「聴覚障害者等」という。)のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行う。 |
【事業の具体的内容】
| 聴覚障害者等に手話通訳者等を派遣する事業、手話通訳者等を設置する事業など障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する事業 |
【対象者】
| 意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等 |
【留意事項】
| (1) | 派遣事業が円滑に行われるよう、手話通訳者等の派遣が適切に行われるための調整者の設置等について配慮すること。 |
| (2) | 派遣事業、設置事業等を行う手話通訳者等は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守り、信条等によって差別的取り扱いをしてはならないこと。 |
(別紙3)
| 日常生活用具給付等事業の概要について |
【概要】
| 本事業は重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。 |
【事業の具体的内容】
| 障害者自立支援法第77条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具の給付または貸与。 |
| 【新告示案のイメージ】 厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具とは、安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの。以上の三要件を満たす、次の6種の用具をいう。
|
【対象者】
| 重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者であって、当該用具を必要とするもの。 |
【留意事項】
| (1) | 給付にあたって実施主体は、必要性や価格、家庭環境等をよく調査し、真に必要な者に適正な用具をより低廉な価格で購入し給付すること。
|
||
| (2) | 公的給付にあたって、従来の手法等を参考にしつつ、同機能であればより廉価なものを給付すべき。
|
||
| (3) | 給付する種目及び製品を具体的に決定するにあたっては、別紙参考例等を参考とすること。 |
||
| (4) | 排泄管理支援用具においては、継続的な給付が必要なことから、年間の需要量を把握し、計画的な給付に努めること。 |
日常生活用具参考例(案)
| 種目 | 対象者 | |
| 介護 ・ 訓練支援用具 |
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害 |
| 特殊マット | ||
| 特殊尿器 | ||
| 入浴担架 | ||
| 体位変換器 | ||
| 移動用リフト | ||
| 訓練いす(児のみ) | ||
| 訓練用ベッド(児のみ) | ||
| 自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害 |
| 便器 | ||
| 頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害 | |
| T字状・棒状のつえ | ||
| 歩行支援用具→移動・移乗支援用具(名称変更) | ||
| 特殊便器 | 上肢障害 | |
| 火災警報機 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難 | |
| 自動消火器 | ||
| 電磁調理器 | 視覚障害 | |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | ||
| 聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害 | |
| 在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害等 |
| ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害等 | |
| 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害等 | |
| 酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法者 | |
| 盲人用体温計(音声式) | 視覚障害 | |
| 盲人用体重計 | ||
| 情報 ・ 意思疎通支援用具 |
携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害 |
| 情報・通信支援用具※ | 上肢機能障害又は視覚障害 | |
| 点字ディスプレイ | 盲ろう、視覚障害 | |
| 点字器 | 視覚障害 | |
| 点字タイプライター | ||
| 視覚障害者用ポータブルレコーダー | ||
| 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | ||
| 視覚障害者用拡大読書器 | ||
| 盲人用時計 | ||
| 聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害 | |
| 聴覚障害者用情報受信装置 | ||
| 人工喉頭 | 喉頭摘出者 | |
| 福祉電話(貸与) | 聴覚障害又は外出困難 | |
| ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難 | |
| 視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害 | |
| 点字図書 | ||
| 排泄管理支援用具 | ストーマ装具 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) 収尿器 |
ストーマ造設者 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 高度の排尿機能障害者 |
| 住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変 |
| ※ | 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。 |
(別紙4)
| 移動支援事業の概要について |
【概要】
| 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の介護を行う。 |
【事業の具体的内容】
| 移動支援事業の実際の運用は、各市町村の判断により地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態で実施することとしているが、具体的には下記のような利用形態が想定される。 |
| (1) | 個別支援型
|
||||
| (2) | グループ支援型
|
||||
| (3) | 車両移送型
|
【対象者】
| (1) | 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者・児、全身性障害者・児(※)、知的障害者・児(但し、重度訪問介護、行動援護対象者を除く)。 |
| ※ | 肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級に該当するものであって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者。 |
| (2) | 一人での外出に困難(漠然とした不安がある、妄想がある、公共機関等の利用に係る各種手続きを一人で行うのが困難など)のある精神障害者(但し、行動援護対象者を除く)。 |
【留意事項】
| (1) | 指定事業者への事業の委託 サービス提供体制の確保を図るため、市町村は、(1)新制度における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者や(2)これまで支援費制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者などを活用した事業委託に努める。例えば、市町村のつくった委託事業者リストの中から利用者が事業者を選択できるような仕組みとする。 |
| (2) | 突発的ニーズへの対応 急な用事ができた場合、電話等の簡便な方法での申し入れにより、臨機応変にサービス提供を行う。 |
| (3) | サービスを提供する者 サービスを提供するに相応しい者として市町村が認めた者とする。 |
| ※ | 今後、各自治体の取り組み(参考事例)の情報提供を行う予定。 |
| ※ | ガイドラインの詳細については、現在検討中であり、今後お示しする。 |
(別紙5)
| 地域活動支援センター事業の概要について |
【概要】
| 障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等地域の実情に応じ、市町村がその創意工夫により柔軟に事業を実施。 |
【事業の具体的内容】
| (1) | 「基礎的事業」として、創作的活動、生産活動、社会との交流の促進等の事業を実施。 | ||||||
| (2) | (1)に加え、事業の機能を強化するために下記の事業を実施する場合、その内容に応じI型〜III型までの類型を設定。
|
【留意事項】…補助額、補助方法について
| (1) | 基礎的事業の補助 地方交付税による、小規模作業所に対する自治体補助事業の一部を財源とする。 |
||||
| (2) | I型〜III型の補助 (1)に加え、「地域活動支援センター機能強化事業費」として国庫補助を実施。
|
(地域活動支援センター事業の各事業内容について)
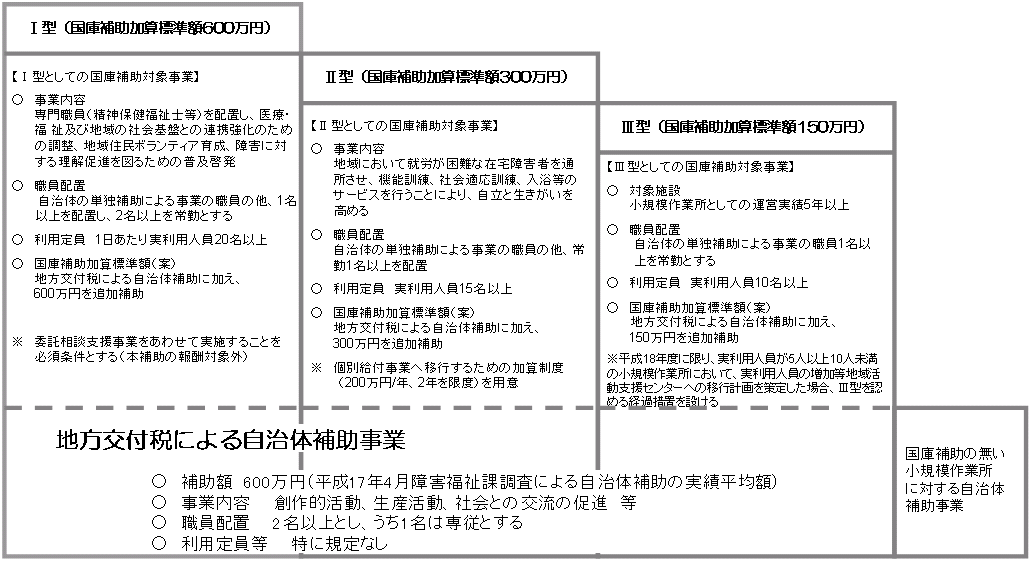
|
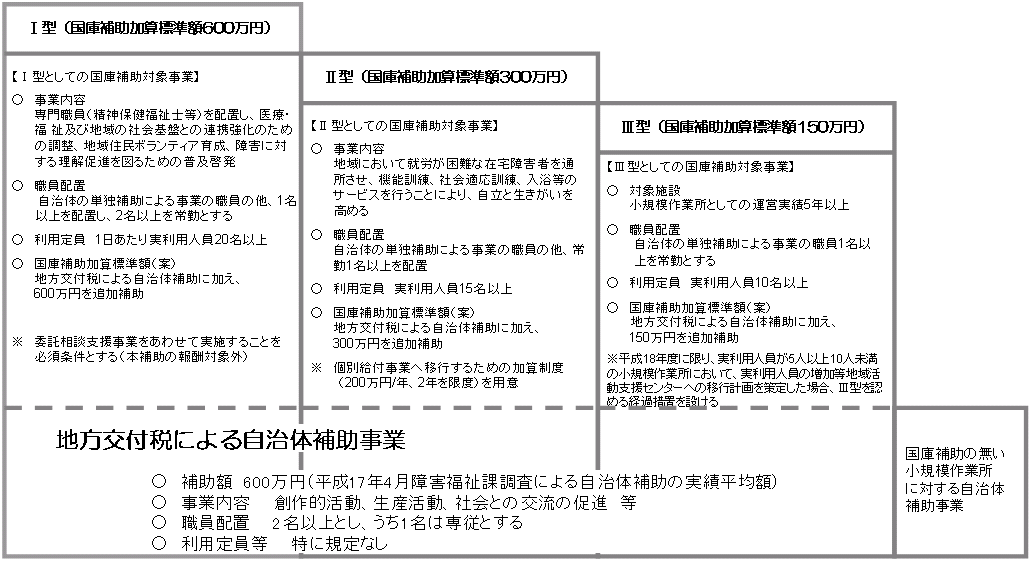
(小規模作業所から地域活動支援センター等への移行について)
|
(別紙6)
| 生活サポート事業の概要について |
【概要】
介護給付の対象外となる者であって、
|
【事業の具体的内容】
| ホームヘルパー等を居宅に派遣し、必要な支援(生活支援・家事援助等)を行う。 |
【対象者】
| 介護給付の対象外の者であって、サービス提供に相応しいと市町村が認めた者 |
【留意事項】
利用者の状態に応じ、障害程度区分認定を見直すなど、利用者の利便を図ること。
|
(別紙7)
| 高次脳機能障害支援普及事業の概要について |
【概要】
| 都道府県に高次脳機能障害者への支援拠点機関を置き、高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実、高次脳機能障害に関する研修等を行い高次脳機能障害者に対して適切な支援が提供される体制を整備する。 |
【事業の具体的内容】
| ・ | 支援拠点機関に相談支援コーディネーターを配置し、専門的な相談支援、関係機関との連携、調整を行う |
| ・ | 自治体職員、福祉事業者等を対象に高次脳機能障害支援に関する研修を行い、地域での高次脳機能障害支援の普及を図る |
【支援拠点機関の例】
| リハビリテーションセンター、大学病院、県立病院 等 |
【相談支援コーディネーターの例】
| 社会福祉士、保健師、作業療法士等、高次脳機能障害者に対する専門的相談支援を行うのに適切な者 |
【留意事項】
| 他の地方公共団体等への委託可 |
(別紙8)
| 広域的支援事業(例:都道府県相談支援体制整備事業)の概要について |
【概要】
| 都道府県に、相談支援に関する広域的支援を行うアドバイザーを配置する。 |
【事業の具体的内容】
| ・ | 地域のネットワーク構築に向けた指導、調整 |
| ・ | 地域では対応困難な事例に係る助言等 |
| ・ | 地域における専門的支援システムの立ち上げ援助 (例:権利擁護、就労支援などの専門部会) |
| ・ | 広域的課題、複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援 |
| ・ | 相談支援従事者のスキルアップに向けた指導 |
| ・ | 地域の社会資源(インフォーマルなものを含む)の点検、開発に関する援助 等 |
【アドバイザーの担い手】
| ・ | 地域における相談支援体制整備について実績を有する者 |
| ・ | 相談支援事業に従事した相当期間の経験を有する者 |
| ・ | 障害者支援に関する高い識見を有する者 |
【都道府県自立支援協議会との関係】
| 配置するアドバイザーの職種や人員等について協議 |
(別紙9)
| 精神障害者退院促進支援事業の概要について |
【概要】
| 精神病院に入院している精神障害者のうち、受入条件が整えば退院可能である者に対し、円滑な地域移行を図るための支援を行う。 |
【事業の具体的内容】
自立支援員を指定相談支援事業者等に配置し、精神病院の精神保健福祉士等と連携を図りつつ退院に向けての支援を行い、精神障害者の円滑な地域移行の促進を図る。
|
【自立支援員の要件】
| 精神保健福祉士又はこれと同等程度の知識を有する者 |
【留意事項】
| 指定相談支援事業者、他の地方公共団体への委託可 |
(別紙10)
| サービス管理責任者養成研修の概要について |
【概要】
| サービスの質を確保するため、事業者ごとに、個別支援計画の作成、サービス内容の評価等を行うサービス管理責任者を配置。 |
【事業の具体的内容】
| (1) | 実施主体 研修事業者
|
||||||||||
| (2) | 研修の期間等
|
||||||||||
| (3) | 費用負担
|
||||||||||
| (4) | 研修に係る経過措置
|
【対象者】
| 障害福祉サービスにおいて個別支援計画の作成に従事した経験など、一定の実務経験を有している者 |