障害福祉サービス事務処理システムについて
平成17年12月26日(月)
平成17年12月26日(月)
| ※ | 今後の検討により、内容等に変更が生じることがありうる。 |
| 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害保健福祉改革推進室 |
19年10月稼動の国民健康保険団体連合会の支払システムについて
全国統一の国保連合会支払システム
| ・ | 障害福祉サービス費について、市町村はサービス事業者からの請求に基づき、内容を審査のうえ支払うこととされているが、この審査支払事務の効率化と平準化を図るため、国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に支払事務の委託を進めることとしている。 |
| ・ | 国保連合会の支払事務は、障害福祉サービス費について全国共通の支払システム(以下「支払システム」という。)を導入することにより、サービス事業者からの請求受付から支払まで一連の事務のシステム化を図り、障害福祉サービス費の請求、審査、支払等の事務の効率化と平準化を図るものである。 |
支援費制度、自立支援制度【19年9月まで】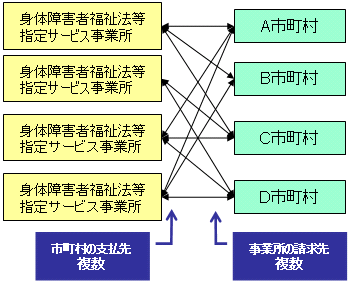
市町村により審査水準が異なることがある |
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ |
自立支援制度【19年10月以降】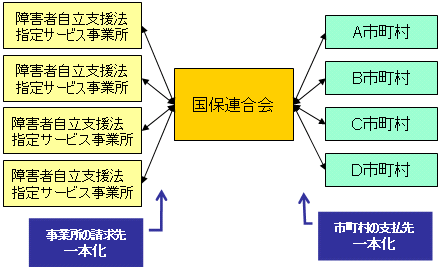
システム導入により審査水準の平準化を図る |
19年10月以降の障害福祉サービス費の事業所の請求から審査・支払までの流れ
19年10月以降、サービス事業所の障害福祉サービス費の請求先は各市町村から事業所の所在する国保連合会に移行する。
|
|
|
||
│ │ │ ↓ |
|
|
||
│ ↓ |
|
|
||
│ │ ↓ |
|
|
||
|
|
|
障害福祉サービス費支払システムでの使用回線について
19年10月以降の国保連合会の支払システム稼動後は、障害福祉サービス費の請求・審査・支払事務の迅速化を図るため、都道府県、市町村、サービス事業者、国保連合会の関係機関を回線で結合させたネットワークシステムを形成する必要があるが、各関係機関との結合回線は下記の回線の使用の検討を進めている。
障害者自立支援システム(19年10月以降)
参考 介護保険システム
|
関係機関から国保連合会に提供する必要のある情報
国保連合会の支払システム稼動後は、関係機関より定期的に審査支払に必要なデータの提供が必要となる。
| ・ 都道府県より | 指定事業所に関するデータ | |
| ・ 市町村より | 支給決定に関するデータ | |
| ・ 事業所より | 契約・請求に関するデータ |
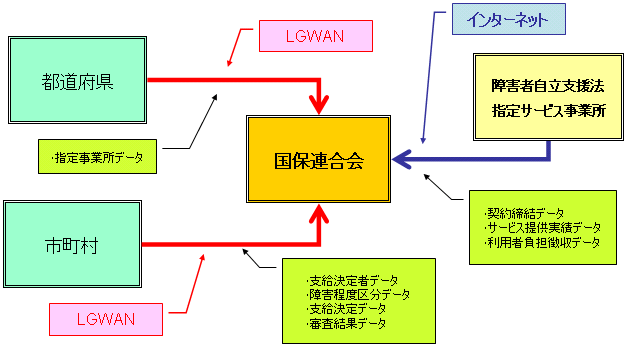
|
国保連合会と地方自治体との結合イメージ
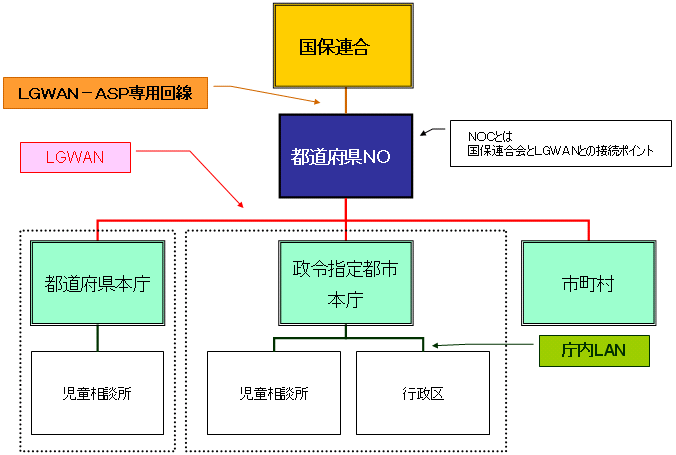
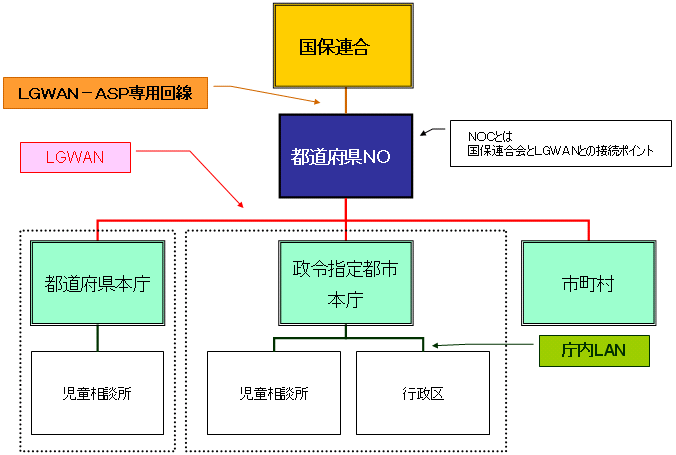
現時点で市町村で予測されるランニングコスト
|
なお、LGWAN回線は、全地方自治体に敷設されており、通常、障害保健福祉部局で回線使用の費用はないものと思われる。
現時点でサービス事業所で予測されるランニングコスト
|
障害者自立支援法施行後の受給者(証)番号の取り扱いについて
受給者(証)番号の取り扱いについて
市町村は、障害者自立支援法の支給決定の際、利用者に受給者証一枚だけを交付し、サービス種別ごとに受給者証を発行しない。 受給者(証)番号は、証一枚につき、一つの番号を使用すること。 |
平成18年10月以降は、障害福祉サービスの利用者が所持する受給者証は一枚となり、結果、支給決定者一人に一つの受給者(証)番号の取り扱いとするものである。
18年4月から9月までの間は、
この取り扱いは、18年10月支給決定分より完全実施として、それまでの間は、対応できる自治体より順次実施していくこととする。 |
受給者番号の付番ルールは支援費制度時と同様とする。
支援費制度、自立支援制度受給者番号の付番ルール
|
障害福祉サービスにかかる受給者番号の取り扱いについて
| 18年3月まで | ||||||||||||
|
┐ │ │ ├ │ │ ┘ |
5種類の受給者証が存在
|
||||||||||
18年4月から9月まで |
||||||||||||
|
┐ │ ├ │ ┘ |
3種類の受給者証が存在
|
||||||||||
18年10月以降 |
||||||||||||
|
┐ ├ ┘ |
1種類の受給者証が存在
|
||||||||||
支給決定の移行図
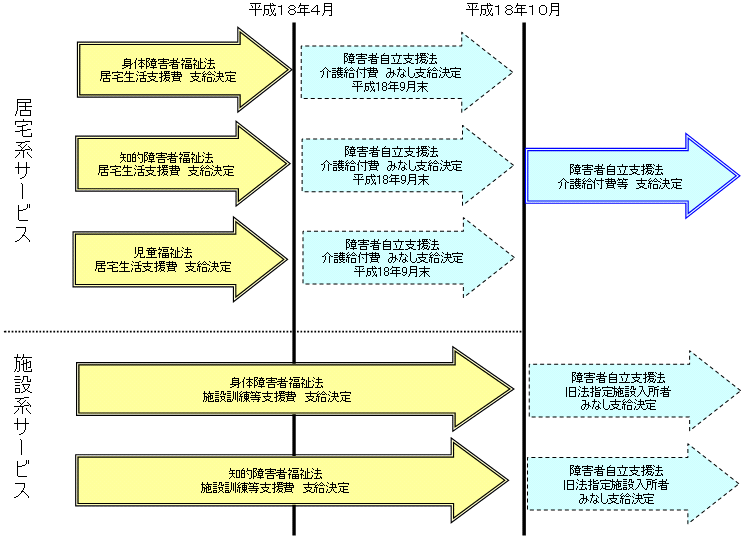
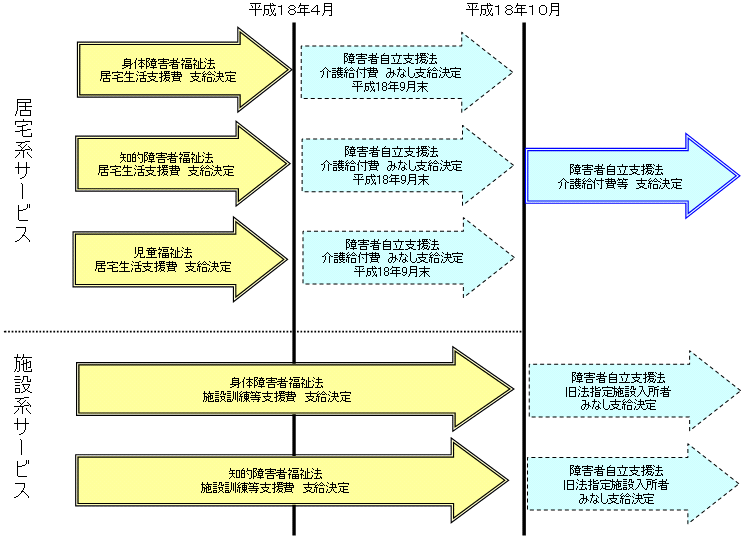
受給者証の移行図
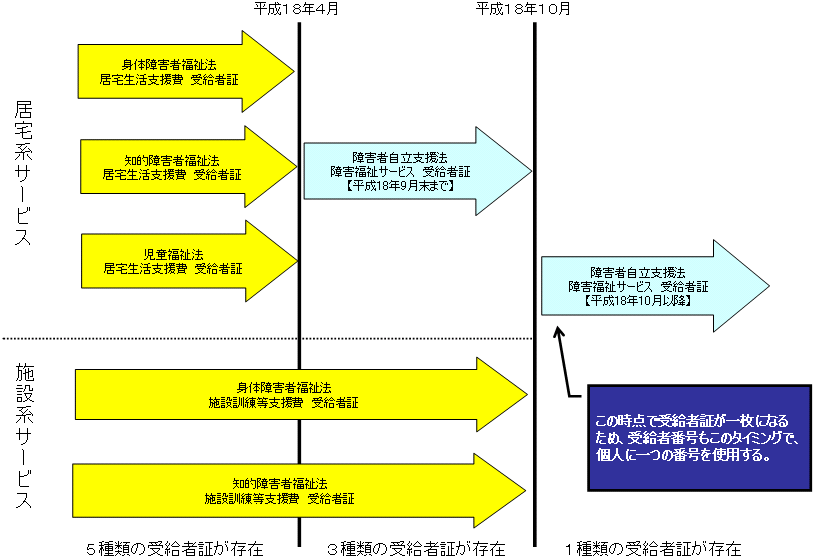
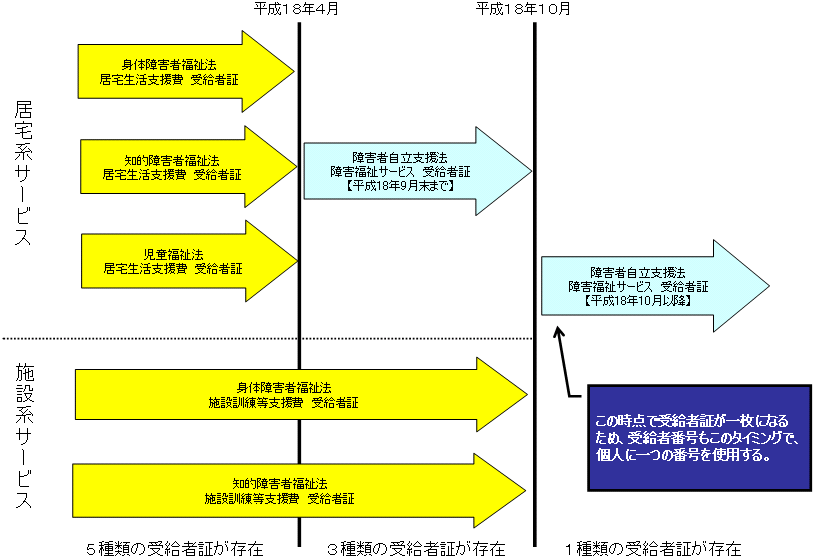
障害者自立支援法施行後のサービス事業所番号の取り扱いについて
障害者自立支援法及び児童福祉法の指定事業所等の設定について(案)
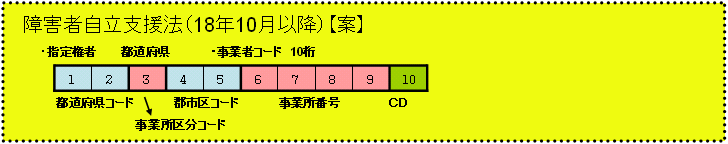
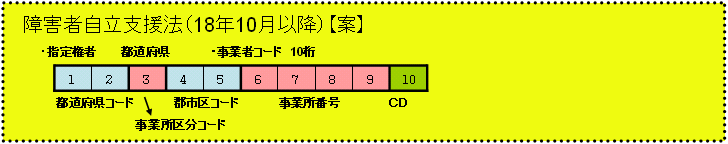
|
サービス事業所の事業所番号の移行図
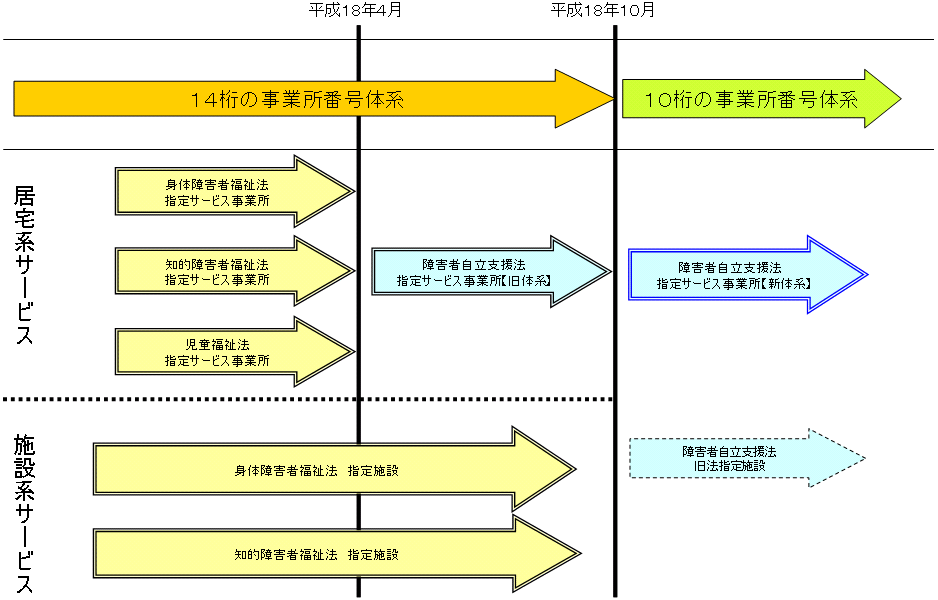
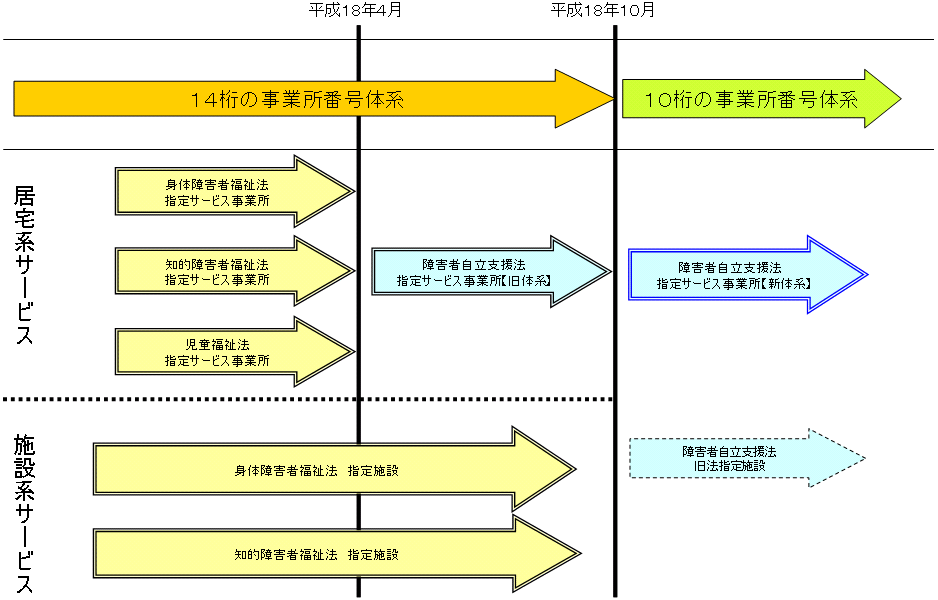
18年4月から9月までの自立支援制度の事業所番号について
自立支援法の事業所番号体系は18年10月に大きな変更を予定しているため、18年9月までの間は、現在の支援費制度の事業所番号体系を原則踏襲したものとする。
変更点
| ・ | 「法区分コード」を「請求区分コード」へ定義変更する。 |
| ・ | サービス種別「15 行動援護」、「16 外出介護」を新設 |
指定事業所番号は、「サービス種別」単位に付番されるが、指定申請時に確認された「主たる障害種別」をもとに請求区分コード分の事業所番号を付番する。
サービス事業者に、指定申請時に当該事業者がサービスを提供する「主たる障害種別の対象者」を明記させる予定である。(みなし指定の場合、事業者の意向確認は、2月中に完了)
| 障害者自立支援法上の指定サービス事業者であるが、事業所番号は複数付番される。 |
サービス事業者は障害福祉サービス費を請求する際に、受給者証に記載された各サービス種別ごとの障害種別を基に請求を行うが、請求の際には、その障害種別にあわせてた請求区分コードの事業所番号を請求書等に記載する。
NPO法人○○事業者▲▲営業所
⇒事業者番号は4つ付番(用意)される。 |
┌ │ │ ┤ └ |
|
18年4月から9月までの自立支援制度における指定事業所番号
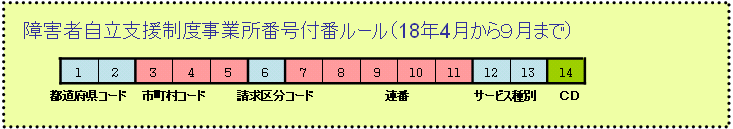
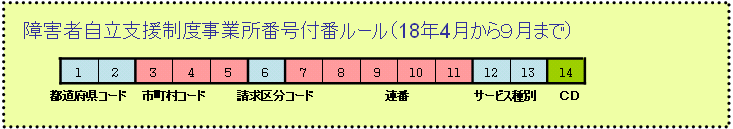
| 請求区分コード 指定事業者
|
サービス種別コード
|
事業所番号は、「サービス種別」を単位として、主たる障害種別「請求区分コード」分の番号を付番する。
| ⇒ | 障害者自立支援法上の指定事業者であるが、事業所番号は最大4番号を所有する。 |
| 例示は、いずれも、ひとつの事業者で申請時に確認した障害種別で事業所番号を付番した場合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年4月から9月までの支援費制度における指定事業所番号
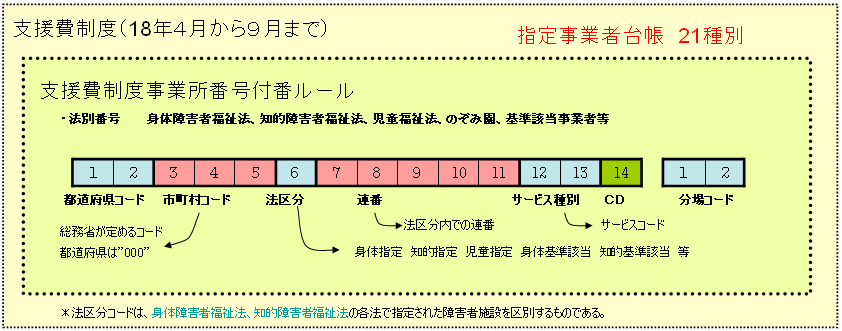
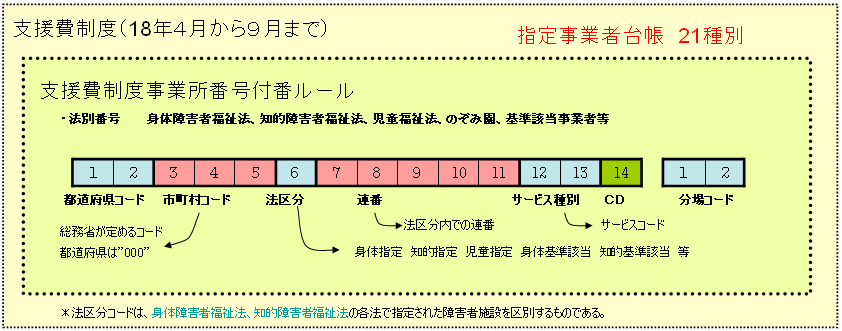
法区分コード
|
サービス種別コード【現行のまま】 (法区分+サービス種別) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独立行政法人福祉医療機構〈WAMNET〉への情報提供について
都道府県、指定都市、中核市においては、従来同様に引き続き、事業所を指定した際には、定期的にWAMNETに情報を提供していただきたい。
みなし指定事業所【平成18年3月までの指定事業所】
| 都道府県等は、該当する事業所に18年4月以降のサービス提供意向を確認した後に、「支援費制度」の事業所データを「自立支援制度」の事業所データに移行させた後に、WAMNETにみなし事業所として、事業所データを提供することとなるが、新データ等の情報提供時期については、別途WAMNETより提示を予定。 |
なお、WAMNETの指定事業所の台帳機能を使用している都道府県等については、みなし指定に伴うデータ移行のうち定型的な部分についてはWAMNET側で行うことで調整中である。後日、WAMNETよりこの作業等についての説明を予定している。
| (データ移行の例)13 000 2 00001 11 CD → | 13 000 2 00001 11 CD(居宅介護) 13 000 2 00001 15 CD(行動援護) 13 000 2 00001 16 CD(外出介護) |
| (ただし、精神のみなし事業所については新規入力が必要) | |
詳細内容等はインタフェース等を含めて、後日、福祉医療機構より、別途提示を予定。