�[��Ô�Ə����ɒ��ځ[
�@��Ô�݂̂ɒ��ڂ������S�i���_�j�Ə����ɂ̂ݒ��ڂ������S�i�X���E�琬�j���A���̊ϓ_����A�u��Ô�Ə����̑o���ɒ��ڂ������S�v�̎d�g�݂ɓ�������B
|
��Õی��� ���S��� �i72,300�~���j |
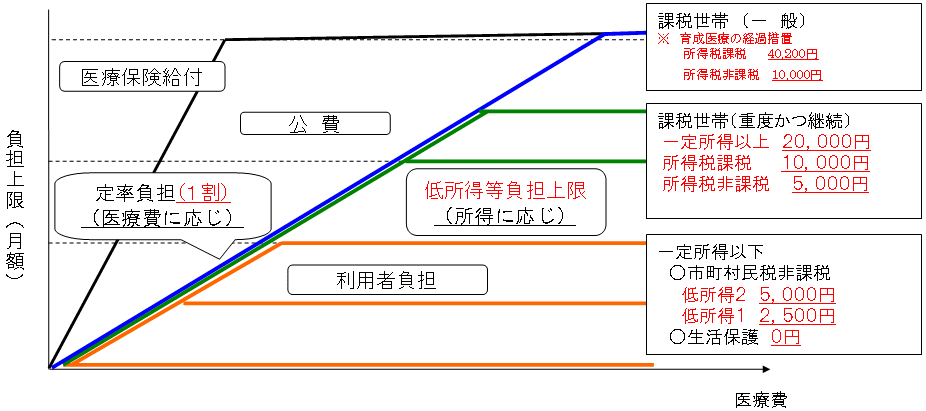
|
| �琬��Ái���ԏ����w�j�ɌW��o�ߑ[�u�̌����� |
�y�������āz
|
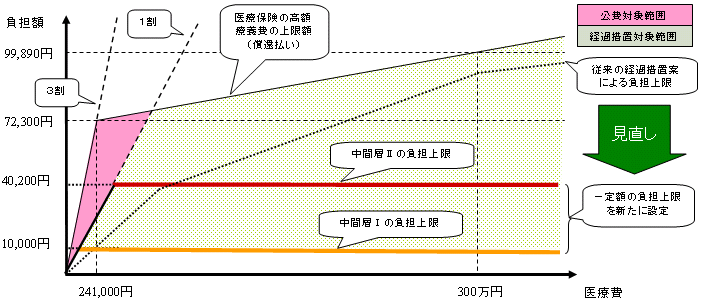
| �@�{���K�p�����ׂ�����z��K�p����ΐ����ی��K�v�Ƃ��邪�A���ɁA���Ⴂ����z��K�p����ΐ����ی��K�v�Ƃ��Ȃ���ԂɂȂ�҂ɂ��ẮA�{���K�p�����ׂ�����z���Ⴂ���S����z��K�p����B |
| ��Q�����T�[�r�X�̏ꍇ | �@ | �����x����Â̏ꍇ | |
|
|
||
| �� ���Ⴂ����z��K�p �� |
�� ���Ⴂ����z��K�p �� |
||
|
|
||
| �� ���Ⴂ����z��K�p �� |
�� ���Ⴂ����z��K�p �� |
||
|
|
||
| �@ | �� �ڍs�h�~�K�v�z�܂Ō��z �� |
||
| �@ |
|
|
| �@�i�P�j | �x���F�莖���̗���i���s���x�Ƃ̔�r�j |
| �@�@(1) | �琬��� |
|
||||||||||||||||||||||||||
| �@ |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| �@ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| �@�@(2) | �X����� |
|
||||||||||||||||
| �@ |
|
|
|
�@ | ||||||||||||
|
������������������ ������������������ |
|
���������� ���������� |
|
||||||||||||
| �@ |
|
�@ |
|
�@ | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
| �@ |
|
|
|
�@ | ||||||||||||
|
������������������ ������������������ |
|
���������� ���������� |
|
||||||||||||
| �@ |
|
�@ |
|
�@ | ||||||||||||
| �@�@(3) | ���_�ʉ@��� |
|
||||||||||||||||||||||
| �@ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
�������������� �������������� |
|
���������� ���������� |
|
||||||||||||||||||
| �@ |
|
|
|
�@ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| �@ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
�������������� �������������� |
|
���������� ���������� |
|
||||||||||||||||||
| �@ |
|
|
|
�@ | ||||||||||||||||||
| �@�i�Q�j | �x���F��̂��߂̎葱�� |
|
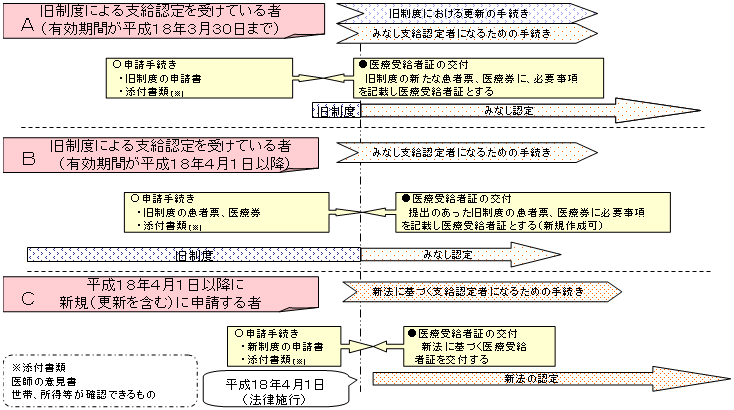
|
|
�@�x���F��ɂ��ẮA��o���ꂽ�����Ɋ�Â��A�ȉ��̗���ŔF�肷��
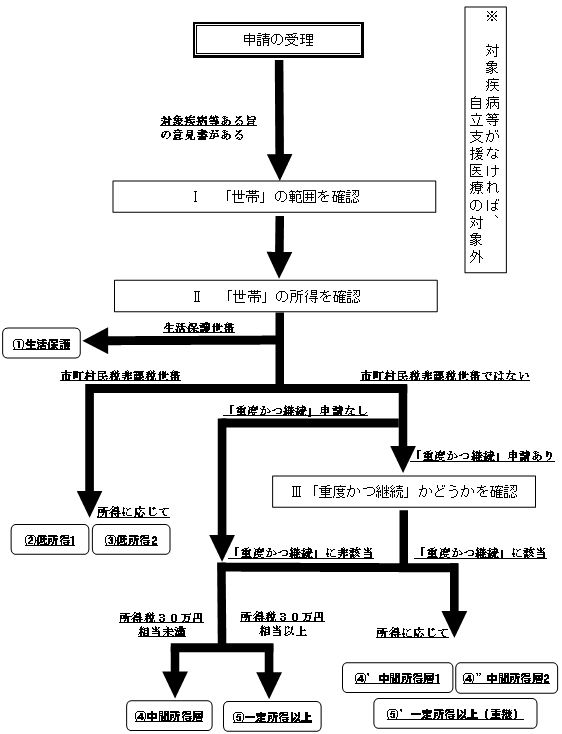
| �P�D��f�� | �F | �]���̍X����ÁA�琬��ÁA���_�ʉ@����̑Ώێҁi�Ώێ��a�́A�]���̑Ώێ��a�͈̔͂ǂ���j |
| �Q�D���t���� | �F | ���ȕ��S�ɂ��Ă͂P�����S�i �܂��A���@���̐H��i�W�����S�z�j�ɂ��Ă͎��ȕ��S�B |
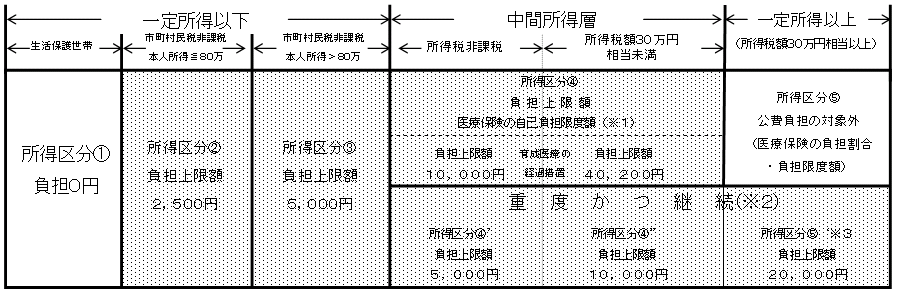
| �@�@���P | �@(1) | �@ | �琬��Ái�Ⴂ���сj�ɂ����镉�S�̌��ϊɘa�̌o�ߑ[�u�����{����B | ||
| �@(2) | �ĔF���F�߂�ꍇ�⋑�ۂ���ꍇ�̗v���ɂ��ẮA����A���ؓI�Ȍ������ʂɊ�Â��A���x�{�s��T�˂P�N�ȓ��ɖ��m�ɂ���B | ||||
| �@�@���Q | �@(1) | �@ | ���ʂ̏d�x���p���͈̔� | ||
| �E | ���a�A�Ǐ���ΏۂƂȂ��
|
||||
| �E | ���a���Ɋւ�炸�A���z�Ȕ�p���S���p�����邱�Ƃ���ΏۂƂȂ��
|
||||
| �@(2) | �d�x���p���̑Ώۂɂ��ẮA���ؓI�Ȍ������ʂ܂��A�����������A�Ώۂ̖��m����}��B | ||||
| �@�@���R | �@�u��菊���ȏ�v���u�d�x���p���v�̎ҁi�����敪(5)�f�j�ɑ���o�ߑ[�u�́A�{�s��R�N���o���i�K�ň�Î��ԓ��܂��Č������B | ||||
|
�u���сv�̏����́A���Y�u���сv�ɂ������Õی��̕ی����̎Z��ΏۂƂȂ��Ă���҂̏������m�F |
|
�� �� �� �� �� �� �� �� |
|
||||||||||||||||||
| ���N�ی��ȂǍ������N�ی��ȊO�̈�Õی��Ȃ��ی��҂̏��� | �@ | �������N�ی��Ȃ�u���сv���̔�ی��ґS���̏��� |
| �� | �����x����Â���҂��A��ی��҂ł����Ă���}�{�҂ł����Ă���L�����͕ς��Ȃ��B |
| �@�i�P�j | �Ώێ҂͈̔� |
|
||||||||||||||||||||||
| �@�i�Q�j | �L�������̐ݒ� |
| �@ | ���s | �����x���@ | �o�ߑ[�u | ||||||||||||||||
| ���_�ʉ@��� |
|
|
|
||||||||||||||||
| �X����� |
|
||||||||||||||||||
| �琬��� |
|
| �� |
|
| �����x����Â̎x���F��i�{���x���F���j�̗L�����ԁi�@��T�T���j���P�N�ȓ��A�܂��A�@������P�R���݂̂Ȃ��F��̗L�����Ԃ��P�N�ȓ��Ƃ���\��i�ȗ߂ŋK��\��j�ł��邪�A�����P�X�N�R�����Ɋe�����̂ɖ{���x���F�莖�����W�����邨���ꂪ���邱�Ƃ���A�e�F��̗L�����ԓ��ɂ��Ă͖{�����Ɋ�Â���舵�����Ƃ��ł�����̂Ƃ���B |
| I | �@�݂Ȃ��F��ɌW�錴�� |
�@�݂Ȃ��F��̗L�����Ԃ͂P�N�ȓ��ł��邱�Ƃ���A
|
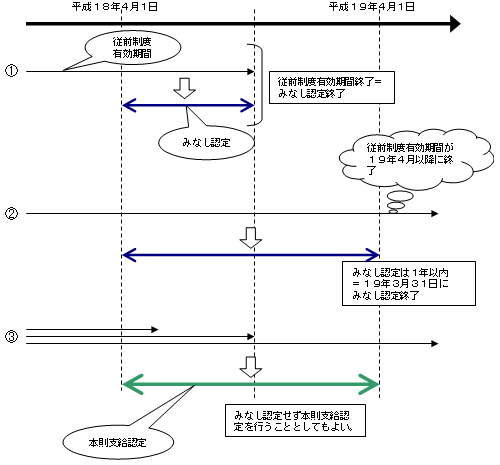
| II | �@��O���[���` |
| �@ | �����P�W�N�R���R�P���܂��́A�݂Ȃ��F��Ɠ����ɁA�݂Ȃ��F��I����i���]�O���x�L�����ԏI����j�̖{���x���F����s�����Ƃ��ł�����̂Ƃ���B
���̏ꍇ�A�u�݂Ȃ��F��̎ҏv�Ɓu�{���x���F��̎ҏv�̂Q���s���邱�ƂƂ���B �������A�e�����̂̔��f�ŁA�{���x���F��̎ҏ͕����P�W�N�R���i�K�ł͌�t�����A�K�X�̎����ɗX���E������n�����̕��@�ɂ���t���邱�Ƃ������x���Ȃ��B |
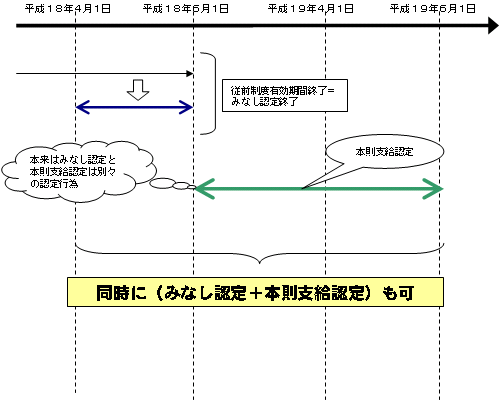
| III | �@��O���[���a |
| �@ |
�݂Ȃ��F��ɌW�錴����(2)�ɊY������ꍇ�ɂ��ẮA
���̏ꍇ�A�u�݂Ȃ��F��̎ҏv�Ɓu�{���x���F��̎ҏv�̂Q���s���邱�ƂƂ���B �������A�e�����̂̔��f�ŁA�{���x���F��̎ҏ͕����P�W�N�R���i�K�ł͌�t�����A�K�X�̎����ɗX���E������n�����̕��@�ɂ���t���邱�Ƃ������x���Ȃ��B
|
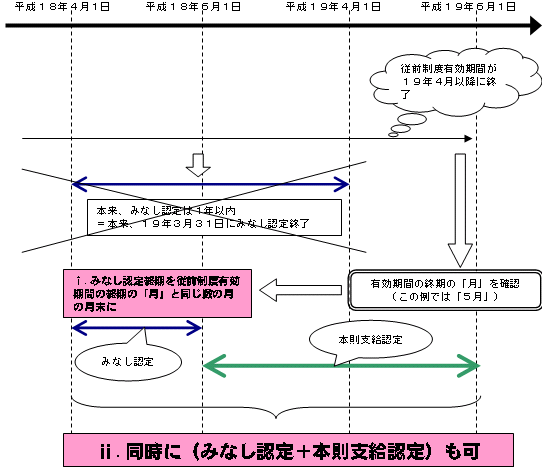
| III | �@��O���[���b |
| �@ |
�����P�W�N�S���P�����畽���P�W�N�P�O���R�P���܂ł̊Ԃ��n���Ƃ���V���Ȗ{���x���F��i�݂Ȃ��F��Ɠ����ɍs����{���x���F��������j���s���ꍇ�Ɍ����A�e�����̂ɂ�����{���x���F��E�݂Ȃ��F��̎����̒��x�����Ă��A�e�����̂̔��f�ɂ���āA�L���������Œ��łP�N�U�����ȓ��̊Ԃ̓K�X�̊��ԂƂ��邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ����B
|
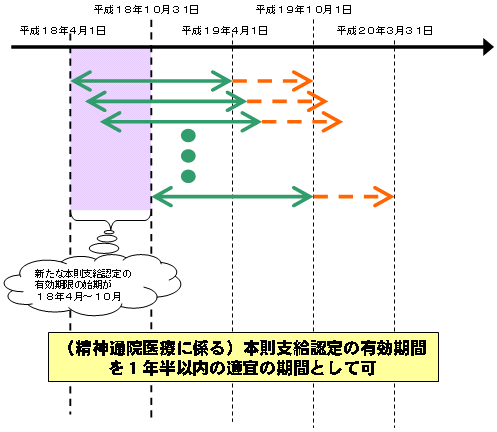
| �@�i�R�j | �҂���̕ύX�̓͏o���K�v�ȏꍇ |
| �@ | �@��Q�Ҏ����x���@��75���Ɋ�Â���߂鐭�߂ɂ����āA�҂Ɉ��̎��R���������ꍇ�ɂ́A�����x����Â̎��{��̂ł���s�������ւ̓͏o�����߂邱�ƂƂ��Ă���B�����_�ōl���Ă���͏o���R��͈ȉ��̒ʂ�B |
| �@�@�� | �@�����̕ύX�i��G�����A�����A�{�q���g�A�����A�����j
|
||||||
| �@�@�� | �@������{��̂̋��ɂ�����Z���̕ύX
|
||||||
| �@�@�� | �@���i�r��
|
||||||
| �@�@�� | �@���������Õی��̕ύX
|
| �@�i�S�j | �҂���̕ύX�\�����K�v�ȏꍇ |
| �@�@�� | �@���S����z�̕ύX
|
||
| �@�@�� | �@�w�莩���x����Ë@�ւ̕ύX
|
| �@�i�T�j | �w�莩���x����Ë@�ւ̑I�� |
| �@�@�P | �@�w�莩���x����Ë@�ւ̑I��̈Ӌ`
|
||||||||||||
| �@�@�Q | �@�I��̎��{���@
|
||||||||||||
| �@�@�R | �@�I�肳�ꂽ�w�莩���x����Ë@�ւ̕ύX
|
||||||||||||
| �@�@�S | �@���̑��w�莩���x����Ë@�ւ̑I��ɌW�闯�ӎ���
|
| �@�i�U�j | ��Îҏ̔��s |
| �@�@�� | �@�݂Ȃ��x���F��҂ɑ����Îҏ̔��s �@�݂Ȃ��x���F��҂ɑ����Îҏ̔��s�́A�����O�̊e�@�ɂ��ʉ@��Ô����S���ҕ[�A�X����Ì����͈琬��Ì����ő�����p����Ȃǎ����ʂ̌y����}����̂Ƃ���B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�@�� | �@�����O�̊e�@�ɂ�銳�ҕ[�y�ш�Ì��̎��
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�@�� | �@�݂Ȃ��x���F�肵����Ì��� �@�]�����͗��ʂ��g���Ď��̂悤�ȕ\�������邱�Ƃɂ�莩���x����ÎҏƂ���B �@�i�������]���◠�ʂ��Ȃ��ꍇ���A�V�����ҏɍ����ւ��邱�Ƃ��K�Ɣ��f�����ꍇ�ɂ͂��̌���ł͂Ȃ��B�j �@�ʉ@��Ô����S���ҕ[�ɂ����Ă͖�ǖ��A�K��Ō쎖�ƎҖ���\��������̂Ƃ���B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�i�V�j | ���S����z�̊Ǘ� |
| �@ |
�@�����x����Î҂̒��ɂ́A���a�E�ǏA�����ɂ�茎�X�̕��S����z�̔F����Ă���҂�����A�a�@�A��Ǔ��Q�����ȏ�̎w�莩���x����Ë@�ւ̑I����Ă��鎩���x����Î҂ɌW�镉�S����z�̊Ǘ����s���K�v������B �@�u���ȕ��S����z�Ǘ��[�v�i�l���Ă͕ʓY�j����t���A��f�����ƂɎw�莩���x����Ë@�ւŒ��������z���L�����A���S����z���Ǘ����� |
|
| �@�i�P�j | ���m�̕��@�� |
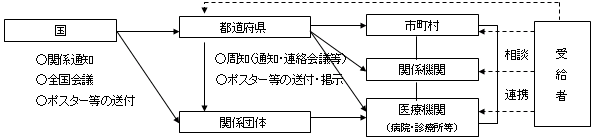
| �@�@�@�� | �@�W�c�̂Ƃ͓��{��t��A���{���_�ȕa�@����A���{���_�_�o�Ȑf�Ï���������x����Â�S�������Ë@�֓����W����c�́A�W�@�ւƂ͕ی����A���_�ی������Z���^�[�A�X�����k���������x����ÂɊւ��鎖���A���k�����s���@�ւ������B |
| �@�i�Q�j | ���m�̓��e |
| �@�@�� | �@�̎{�s�W�E�E�E�E���x�̊T�v |
| �@�@�� | ���葱���̊W�E�E�E�e�\�����葱���i�����A�K�v���ށj |