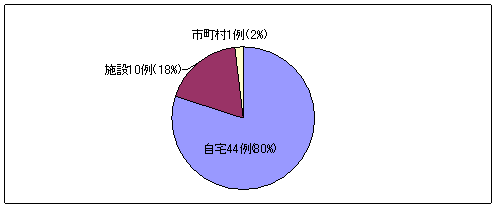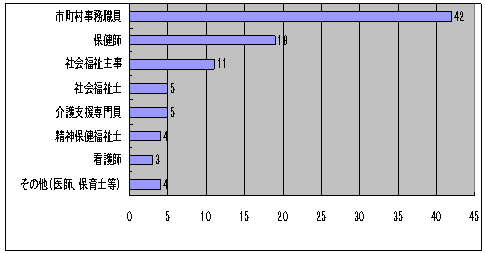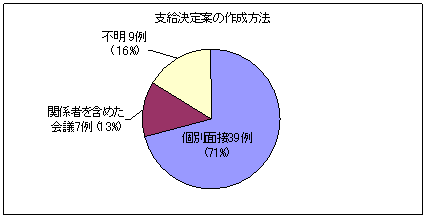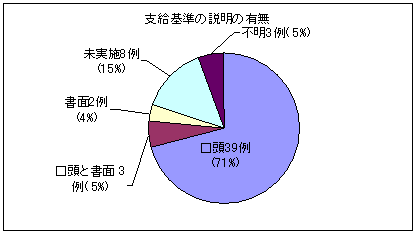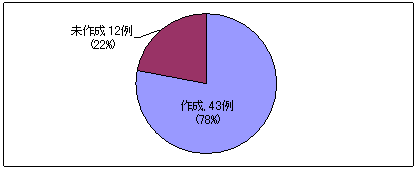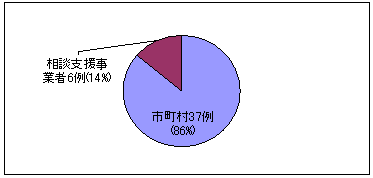(速報)
| I | 障害程度区分関係 |
| 1 | 経緯 |
| ○ | 平成16年度、障害者の介護ニーズを判定する指標に関する調査研究として、介護保険の要介護認定基準の有効性の評価を行ったところ |
| ・ | 現行の要介護認定基準は、「介護給付」に相当するサービスの必要度を測定する上では、障害者においても有効と考えられた。 |
| ・ | ただし、障害者に対する支援は、機能訓練や生活訓練、就労支援等も重要であり、これらの支援の必要度の判定には、「介護給付」に相当するサービスの判定に用いられるロジックとは別のロジックが必要と考えられた。 |
| ○ | 平成17年度は、こうした研究結果を踏まえ、厚生労働科学研究事業「新たな障害程度区分の開発と評価等に関する研究」の一環として、介護保険における要介護認定の認定調査項目(79項目)に、(1)多動やこだわりなど行動面に関する項目、(2)話がまとまらない、働きかけに応じず動かないでいるなど精神面に関する項目及び(3)調理や買い物ができるかどうかなど日常生活面に関する項目(計 27項目)を追加した106項目の調査項目を設定し、試行事業を実施 |
| 2 | 事業の内容 |
| (1) | 実施市町村 |
| 全国60市町村(各都道府県1カ所(熊本県を除く)及び指定都市) |
| (2) | 調査対象者 |
| (1) | 調査対象者は、現在既に居宅サービスを利用している身体障害者・知的障害者・精神障害者各10名、合計30名 | ||||||||
| (2) | 調査対象者の選定 居宅サービス利用者の中から、無作為抽出により選定 選定は、障害種別ごとに、
|
| (3) | 実施内容 |
| (1) | 要介護認定の認定調査項目(79項目)によって一次判定(コンピューター判定)を実施 |
| (2) | 審査会(有識者5名程度で構成)で二次判定を実施 (1)新たに追加された27項目、(2)106項目の調査項目に特記された事項(特記事項)、(3)医師の意見書を基に、介護の必要性に関する障害程度について、介護保険の要介護状態区分(要支援〜要介護5)で判定 |
| 3 | 結果 |
| (1) | 調査対象者の基本属性 |
|
障害種別
| 計 | 身体障害者 | 知的障害者 | 精神障害者 |
| 1790人 | 600人 | 593人 | 597人 |
年齢
| 計 | 20歳未満 | 20歳以上 40歳未満 |
40歳以上 65歳未満 |
65歳以上 |
| 1790人 | 46人 | 612人 | 1052人 | 80人 |
| 100.0% | 2.6% | 34.2% | 58.8% | 4.5% |
| (2) | 判定結果 |
|
最終結果
| 計 | 要介護5 | 要介護4 | 要介護3 | 要介護2 | 要介護1 | 要支援 | 非該当 | ||
| 全障害者 | 1790 | 239 | 139 | 197 | 258 | 478 | 414 | 65 | |
| 100.0% | 13.4% | 7.8% | 11.0% | 14.4% | 26.7% | 23.1% | 3.6% | ||
| 身体障害者 | 600 | 170 | 69 | 57 | 70 | 110 | 105 | 19 | |
| 100.0% | 28.3% | 11.5% | 9.5% | 11.7% | 18.3% | 17.5% | 3.2% | ||
| 知的障害者 | 593 | 69 | 64 | 110 | 98 | 133 | 105 | 14 | |
| 100.0% | 11.6% | 10.8% | 18.5% | 16.5% | 22.4% | 17.7% | 2.4% | ||
| 精神障害者 | 597 | 0 | 6 | 30 | 90 | 235 | 204 | 32 | |
| 100.0% | 0.0% | 1.0% | 5.0% | 15.1% | 39.4% | 34.2% | 5.4% | ||
(参考)一次判定結果
| 計 | 要介護5 | 要介護4 | 要介護3 | 要介護2 | 要介護1 | 要支援 | 非該当 | ||
| 全障害者 | 1790 | 176 | 109 | 116 | 147 | 456 | 445 | 341 | |
| 100.0% | 9.8% | 6.1% | 6.5% | 8.2% | 25.5% | 24.9% | 19.1% | ||
| 身体障害者 | 600 | 135 | 78 | 59 | 47 | 130 | 75 | 76 | |
| 100.0% | 22.5% | 13.0% | 9.8% | 7.8% | 21.7% | 12.5% | 12.7% | ||
| 知的障害者 | 593 | 41 | 31 | 57 | 91 | 167 | 139 | 67 | |
| 100.0% | 6.9% | 5.2% | 9.6% | 15.3% | 28.2% | 23.4% | 11.3% | ||
| 精神障害者 | 597 | 0 | 0 | 0 | 9 | 159 | 231 | 198 | |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 26.6% | 38.7% | 33.2% | ||
| (3) | 認定調査員・審査会委員の状況 |
|
認定調査員の職種
|
審査会委員の職種
|
| 4 | 今後の検討について |
| (1) | 障害程度区分の開発に当たっての基本的考え方 |
| (1) | 障害程度区分の開発に当たっては、透明で公平な支給決定を実現する観点から、以下の点を踏まえて行う。
|
||||||
| (2) | 介護給付、訓練等給付でそれぞれサービス内容が異なることから、それぞれの給付ごとに設定する。
|
(参考)
| 1 | 障害程度区分は、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため障害者の心身の状態を総合的に示す区分 |
| 2 | 新制度における支給決定は、障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、(1)障害者の心身の状態(障害程度区分)に加えて、(2)社会活動や介護者、居住等の状況、(3)サービスの利用意向、(4)訓練、就労に関する評価といった諸事項を総合的に勘案して行われることとなっている |
| (2) | 今後の検討の進め方と検討課題 |
| 今後、以下の検討課題について、試行事業の結果の分析とあわせて、有識者、関係者からのヒアリングを実施し、検討を進める。 |
| (1) | 介護給付に係る障害程度区分について |
| ・ | 要介護認定の調査項目(79項目)以外の項目を一次判定(コンピューター判定)でどのような形で反映するか |
| ・ | 審査会における二次判定の判定基準をどうするか など |
| (2) | 訓練等給付に係る障害程度区分について |
| ・ | 支給決定時の優先度の判定に用いるスコア(点数)をどうするか など |
| (3) | 認定調査や市町村審査会の運営のあり方について |
| 介護給付における障害程度区分のプロセス |
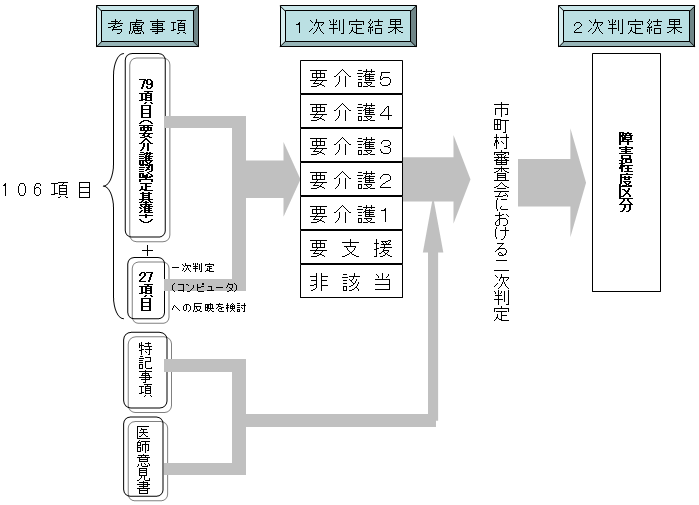
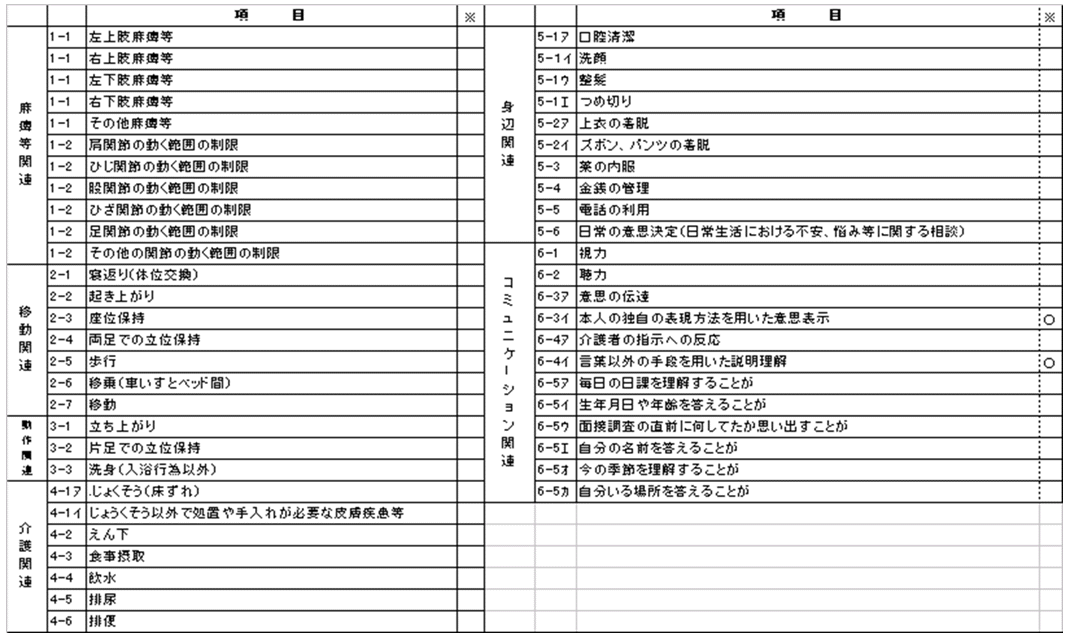
| ※ | ○=要介護認定基準の認定調査項目以外の項目(27項目) |
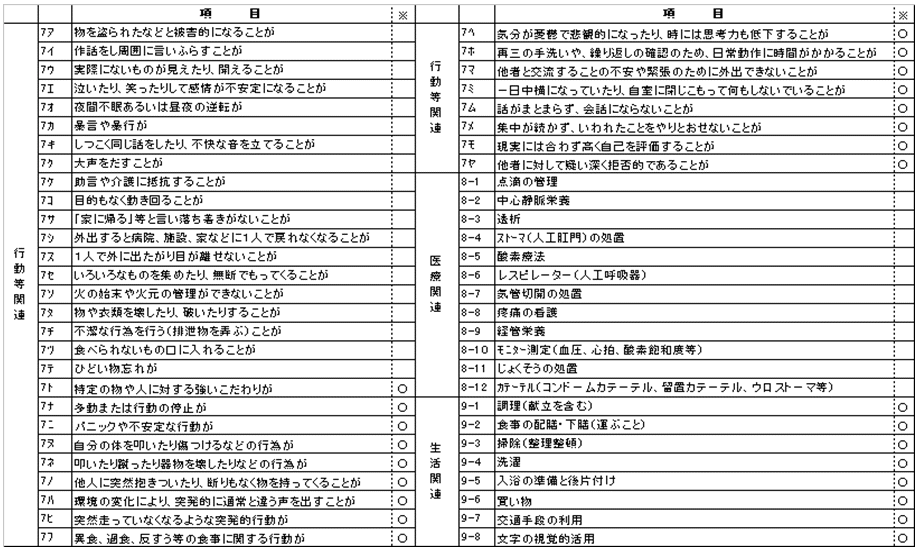
| ※ | ○=要介護認定基準の認定調査項目以外の項目(27項目) |
| II | 支給決定プロセス調査関係 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
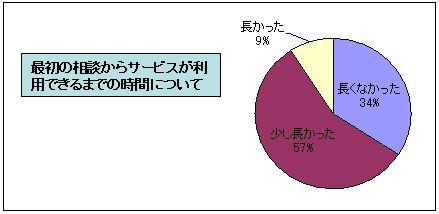 |
|
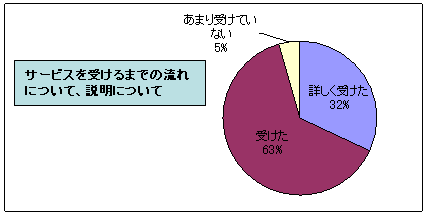 |
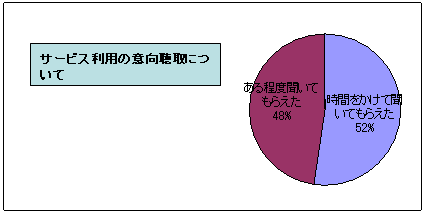 |
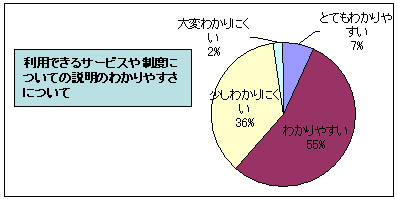 |
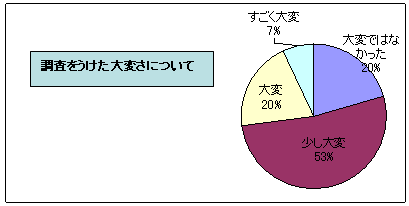
|
| 障害程度区分判定等試行事業の概要 |
【参考資料1】
| ○ | 支給決定に関する調査(アセスメント)や障害程度区分素案の試行を通じ、障害者等の心身の状態等に関するデータを収集し、障害程度区分の開発を行うとともに、新制度における新支給決定手続き実施の際の実務上の課題を把握することを目的として実施 |
↓
|
||||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ※ | 調査対象者の中で、今回の試行事業の期間中に、新たに支給決定を行ったか、あるいは支給決定の変更を行った者を対象に、障害程度区分の判定以降、支給決定までのプロセスを調査 |
【参考資料2】
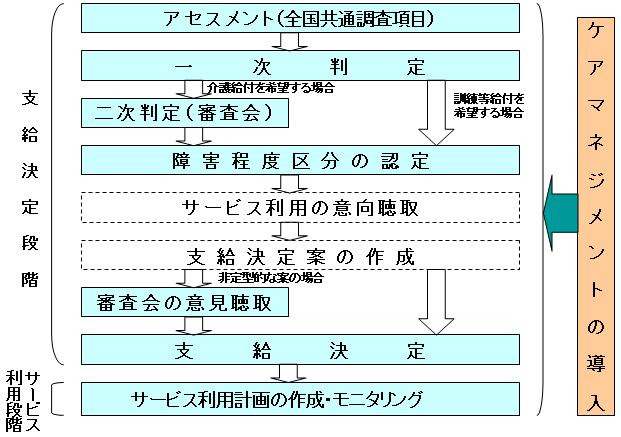
| (※) | 一定数以上のサービス利用が必要な者や長期入所・入院から地域生活へ移行する者などのうち、計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者を対象 |