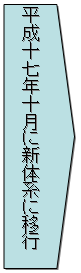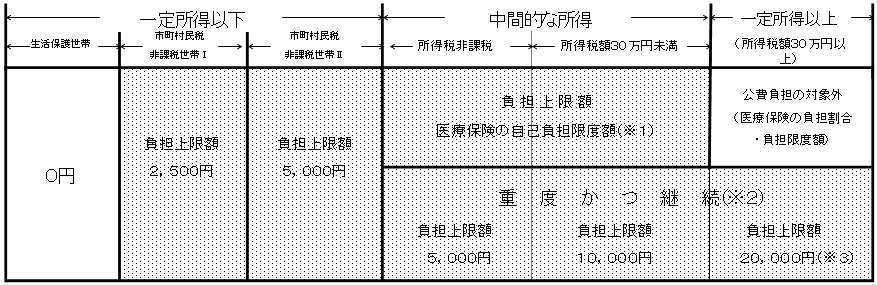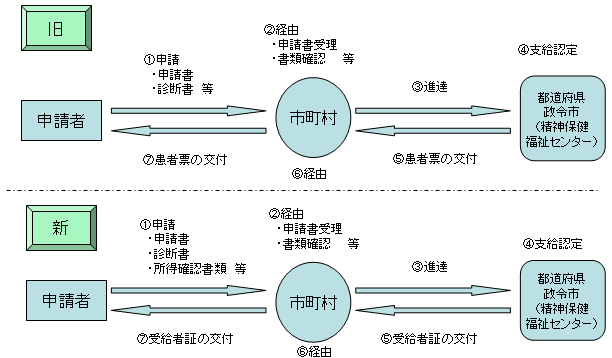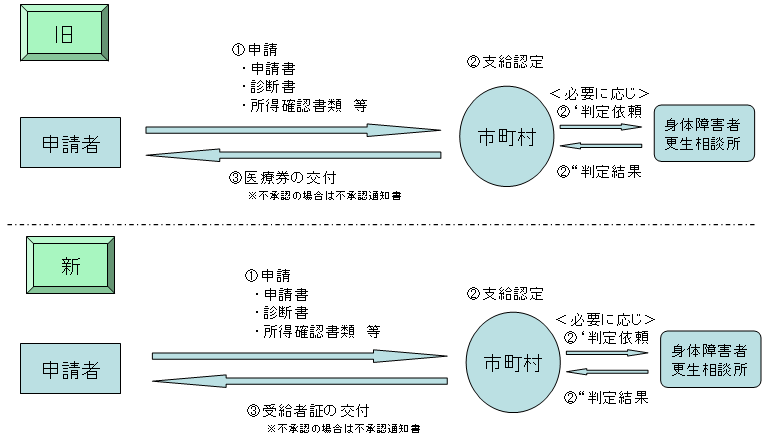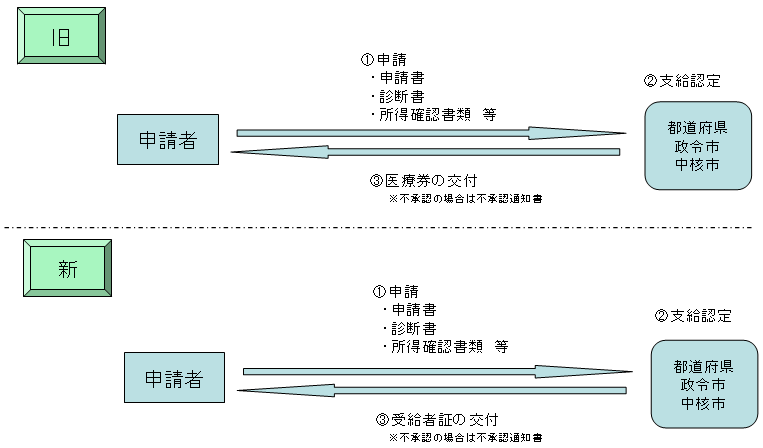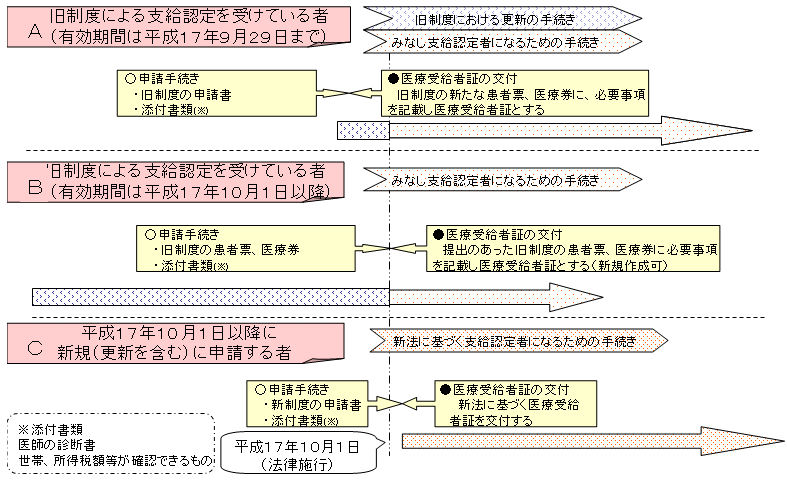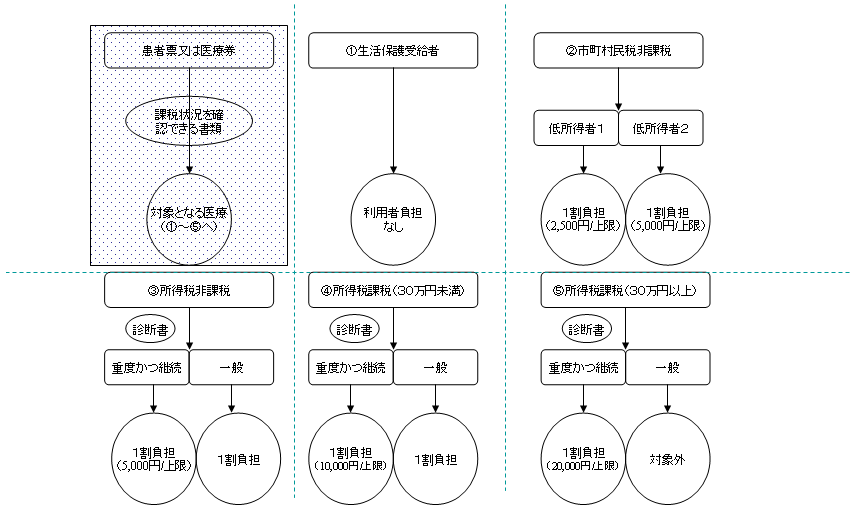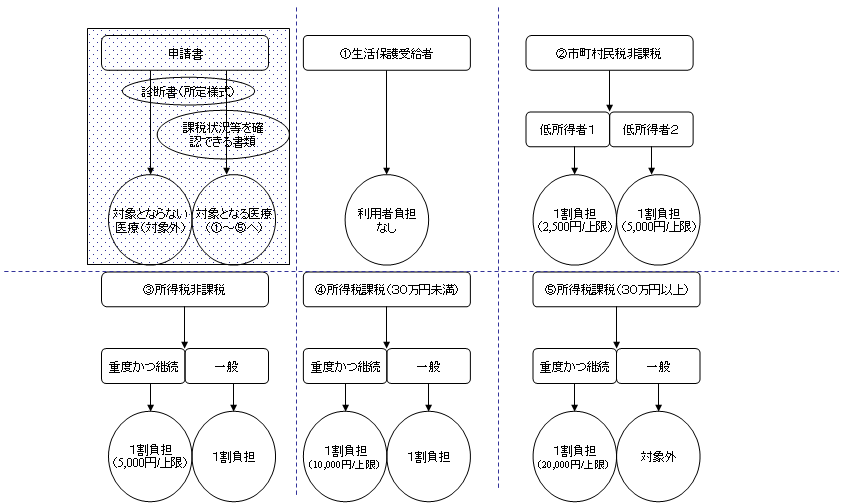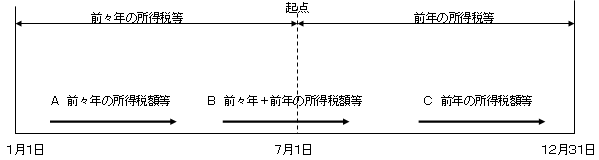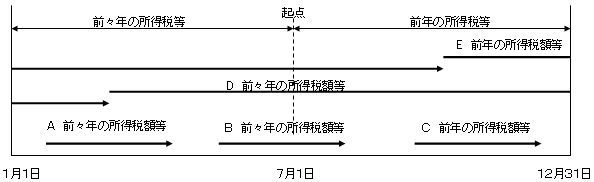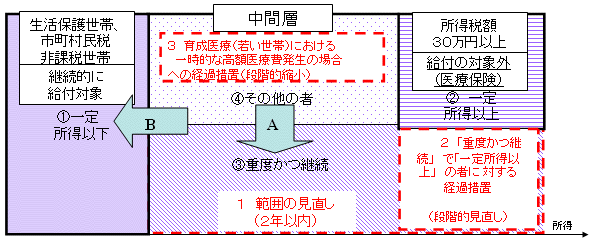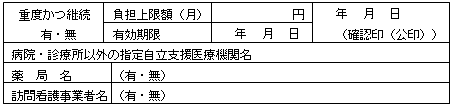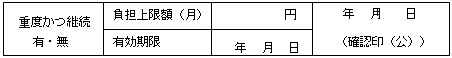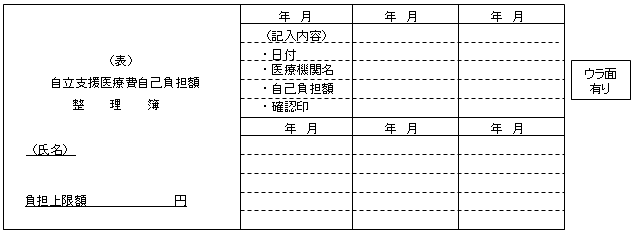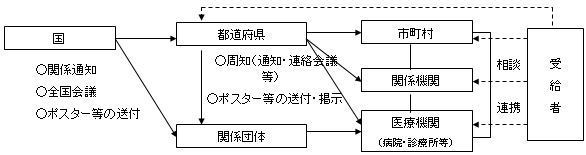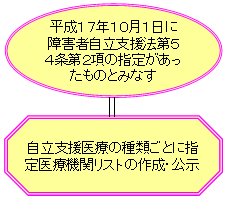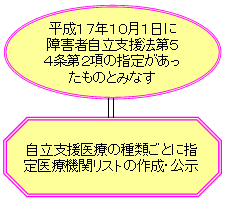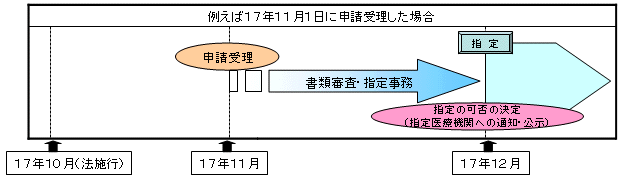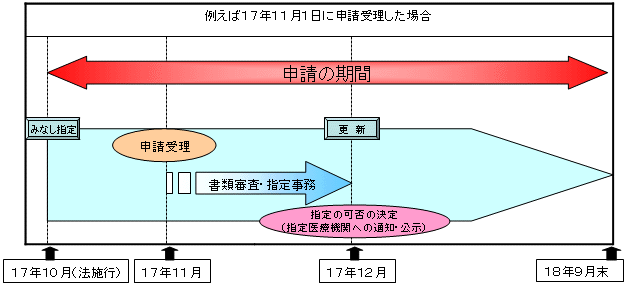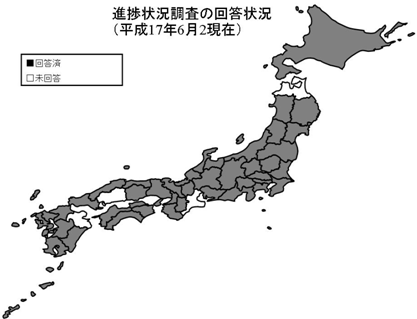自立支援医療について
今回の改正のポイント
〜よく聞かれる御質問と正確な情報をお伝えするために〜
【ポイント】
| ○ |
更生医療、育成医療、精神通院医療は、それぞれの現行根拠法から、自立支援医療として障害者自立支援法案にその根拠を移すのであって、廃止されるわけではありません。
|
| ○ |
自立支援医療においては、
| ・ |
一律5%負担の精神通院医療、所得に応じた負担の更生医療・育成医療という、制度間の不均衡を解消し、医療費と所得の双方に着目した自己負担の仕組みとして障害者の負担の公平を図り、 |
| ・ |
制度の持続可能性を高めるため、障害者を含め、費用を皆で支え合う仕組みとして、制度の効率性、安定性を確保して、持続可能性を高めることを図る、 |
ことを目的としています。
|
| ○ |
自立支援医療の対象となる疾病の範囲は、これまでの制度と同じです。
|
| ○ |
自己負担は、原則として1割負担ですが、負担水準への配慮として、
| ・ |
低所得世帯に属する方については、月当たりの負担額に上限を設定 |
| ・ |
一定の負担能力がある方であっても、「重度かつ継続」に該当する場合には、継続的に相当額の医療費負担が発生することから、月当たりの負担額に上限を設定 |
などの仕組みを組み込んでいます。
|
| (1) |
精神保健福祉法第32条の精神通院医療は、廃止になるのですか? |
|
(答)
| ○ |
精神通院医療は、廃止されるのではなく、自立支援医療の一種類として引き続き実施されます。
|
| ○ |
今般、精神通院医療を含む障害者に関する公費負担医療制度について、利用者負担の仕組みの共通化等を図るために「自立支援医療制度」として再編し、また、増大する費用を皆で支え合う仕組みとするために利用者負担の見直しなどを行うこととしています。
|
| ○ |
この「自立支援医療制度」は新しい障害者自立支援法案に基づいて実施することになりますので、精神通院医療についても、従来の精神保健福祉法ではなく、この障害者自立支援法案に基づいて実施されることとなり、廃止されるのではありません。
|
| (2) |
更生医療、育成医療、精神通院医療の3つの公費負担医療制度について、自立支援医療への移行に伴い、対象となる疾病の範囲が狭くなると聞きましたが? |
|
(答)
| ○ |
自立支援医療制度の対象となる疾病の範囲については、現在の3つの公費負担医療制度と同じです。 |
| (3) |
「重度かつ継続」とはどういう目的の制度なのでしょうか? |
|
(答)
| ○ |
自立支援医療においては、対象となる疾病については現在の公費負担医療制度と同じとしながら、医療保険制度の3割負担部分について負担割合を1割に軽減し、負担額の上昇が医療保険よりも緩やかになるようにした上で、低所得の方については、一月当たりの負担額に上限(以下「月額負担上限」と言います。)を設けることとしています。
|
| ○ |
さらに、「重度かつ継続」に該当する方については、継続的に相当額の医療費負担が発生する方であるため、一定の負担能力がある場合においても、医療費の家計に与える影響を考慮して、月額負担上限を設けることとしています。
|
| ○ |
このように、「重度かつ継続」は、自立支援医療の対象疾病の範囲を決めるものではなく、「継続的に相当額の医療費負担が発生する」ことへの配慮として月額負担上限の対象となるかどうかに関わるものですが、その対象とする疾病の範囲については様々な意見があることから、実証的研究に基づき更に検討を行い、結論を得たものから順次対応することとしています。 |
| (4) 「重度かつ継続」の疾病に該当する人しか自立支援医療の対象にならないのでしょうか? |
|
(答)
| ○ |
自立支援医療の対象となる疾病の範囲は現行と同様ですので、「重度かつ継続」に該当しない方についても、自立支援医療の対象になり、医療費の自己負担が1割負担になりますし、低所得世帯に属する方であれば月額負担上限の対象になります。
|
| ○ |
その中で、一定の負担能力がある方については、原則として負担の上限は医療保険制度とおりとなりますが、「重度かつ継続」に該当する場合には、月額負担上限が5,000円又は10,000円になります。
|
| ○ |
ただし、「所得税額が30万円以上の世帯」に属する方については、原則として自立支援医療の対象外(医療保険制度とおりの負担)となり、「重度かつ継続」に該当する場合に限り、自立支援医療の対象になり、月額負担上限が20,000円になります。 |
| (5) |
低所得(市町村民税非課税)世帯に属する人でも、「重度かつ継続」に該当しない場合には、2,500円又は5,000円の月額負担上限の対象にはならないのでしょうか? |
|
(答)
| ○ |
低所得世帯に属する方の場合には、「重度かつ継続」に該当するかどうかに関わりなく、申請の際に確認された所得に基づいて、2,500円又は5,000円といった月額負担上限の対象になります。 |
| (6) |
低所得の方や「重度かつ継続」の方は、毎月、2,500円、5,000円、10,000円といったそれぞれの月額負担上限の金額を、医療費と関係なく、支払わなければならないのでしょうか? |
|
(答)
| ○ |
自立支援医療における月額負担上限は、ある月において、1割負担をしていただきながら、その合計額がその方の月額負担上限に達した後は、その月の間は、それ以上の負担をしていただく必要はないというものです。
|
| ○ |
つまり、月額負担上限とは、定額で毎月負担していただくというものではなく、ある月の1割負担の合計額が月額負担上限未満であった場合には、その合計額を負担いただければよいということです。 |
| (7) |
「重度かつ継続」に該当しない人は、1年で自立支援医療が打ち切りになるのでしょうか? |
|
(答)
| ○ |
自立支援医療の支給認定については、1年の範囲内で、有効期限を設定することとしています。
|
| ○ |
この有効期限が経過した後の再認定については、一定所得(市町村民税非課税世帯)以下の方、「重度かつ継続」に該当する方のほかに、その他の対象となる場合についても、実証的研究に基づき、明確化を制度実施後1年以内に行うこととしています。
|
| ○ |
従って、具体的な範囲は今後検討を進めますが、「重度かつ継続」に該当しない方が一律に1年で打ち切りになるのではありません。 |
| (8) |
自立支援医療では、食費の標準負担額を負担しなければならないと聞きましたが、精神科デイケアの昼食代も自己負担になるのでしょうか? |
|
(答)
| ○ |
食費の標準負担額を負担していただくのは入院の時のみですので、精神科デイケアの場合には負担していただく必要はありません。 |
障害に係る公費負担医療制度の再編
| <現行> |
|
<見直し後> |
|
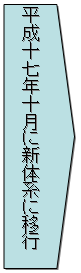
|
|
|
| ・ |
支給認定の手続を共通化
|
| ・ |
利用者負担の仕組みを共通化
|
| ・ |
指定医療機関制度の導入 |
|
|
| ・ |
医療の内容や、支給認定の実施主体(※)については、現行どおり |
|
|
|
|
自立支援医療の対象者、自己負担の概要
| 1. |
対象者 |
: |
従来の更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者であって一定所得未満の者(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり) |
| 2. |
給付水準 |
: |
自己負担については1割負担( 部分)。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費(標準負担額)
については自己負担。 部分)。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費(標準負担額)
については自己負担。 |
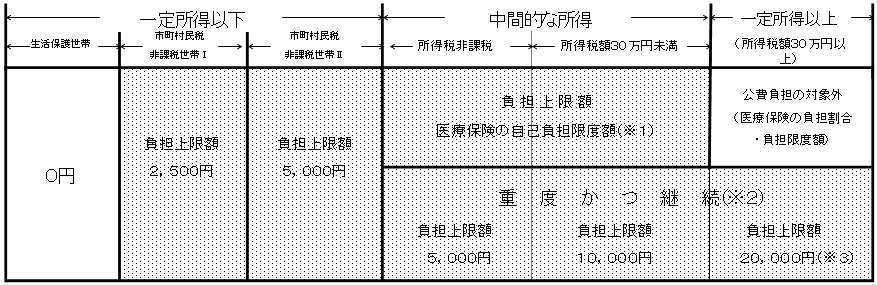
| ※1 |
(1) |
育成医療(若い世帯)における一時的な高額医療費発生の場合への経過措置(段階的縮小)を実施する。
(施行後3年を経た段階で、医療費の分布、平均負担率等を踏まえ見直す。) |
| (2) |
再認定を認める場合や拒否する場合の要件については、今後、実証的な研究結果に基づき、制度施行後概ね1年以内に明確にする。 |
| ※2 |
(1) |
当面の重度かつ継続の範囲 |
| ・ |
疾病、症状等から対象となる者
| 精神 |
・・・・・・・・ |
統合失調症、躁うつ病(狭義)、難治性てんかん |
| 更生・育成 |
・・・・・・・・ |
腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害 |
|
| ・ |
疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
|
| (2) |
重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。 |
| ※3 |
「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。 |
自立支援医療の支給認定に関する事務
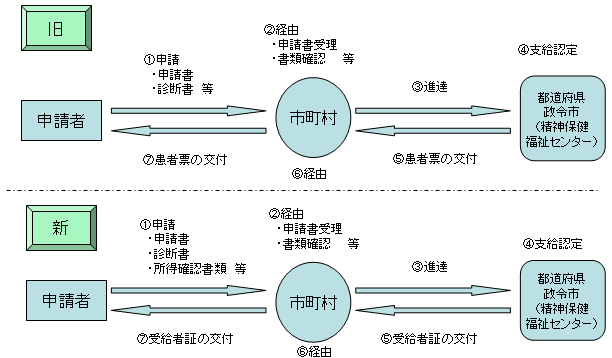
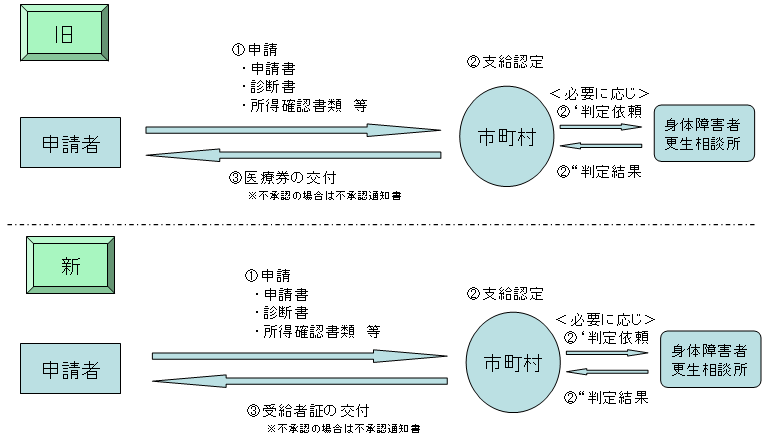
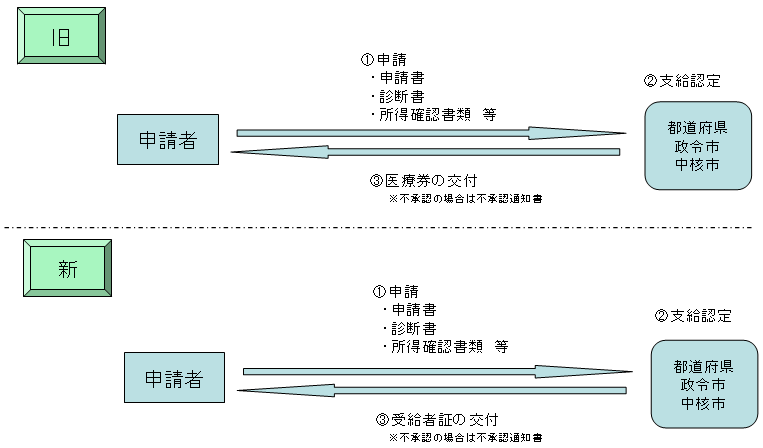
| A. |
旧制度による支給認定を受けている者(平成17年9月29日までに有効期限が終了する者で更新する者) |
| ○ |
旧制度における更新の申請(新たな有効期限が平成17年10月1日を超える者の場合)手続きと
みなし支給認定者になるための手続きを同時に行う。
| (1) |
旧制度による申請書 |
| (2) |
添付書類(医師の診断書(所定の様式による。以下同じ。)及び世帯、所得税額等が確認できるもの) |
|
| ● |
医療受給者証の交付
旧制度の患者票等に必要事項を追加記載して交付する。 |
|
| ※ |
毎年6月に実施している旧更生・育成医療の所得の再認定は行わないものとする。 |
| B. |
旧制度による支給認定を受けている者(平成17年10月1日を超えた有効期限の者 |
| ○ |
みなし支給認定者になるための手続き
| (1) |
旧制度における通院医療費公費負担患者票、更生医療券、育成医療券 |
| (2) |
添付書類(医師の診断書(「重度かつ継続」に係る申請の場合に限る。この場合については、簡便な様式とする方向で検討。) 及び世帯、所得税額等が確認できるもの)
|
提出のあった旧制度の患者票等に必要事項を追加記載して交付する。(新たな患者票等を交付しても差し支えない) |
|
| ※ |
毎年6月に実施している旧更生・育成医療の所得の再認定は行わないものとする。 |
| ※ |
有効期限が平成17年9月30日の者の更新手続きは下記Cによる。 |
<新法による支給認定のための手続き>
| C. |
平成17年10月1日以降に新規(更新を含む)に申請する者 |
| ○ |
新法による申請の手続き
| (1) |
新制度による申請書 |
| (2) |
添付書類(医師の診断書及び世帯、所得税額等が確認できるもの) |
|
| ● |
医療受給者証の交付
新法に基づく医療受給者証を交付(様式は検討のうえ別途提示)する。 |
|
支給認定の手続き
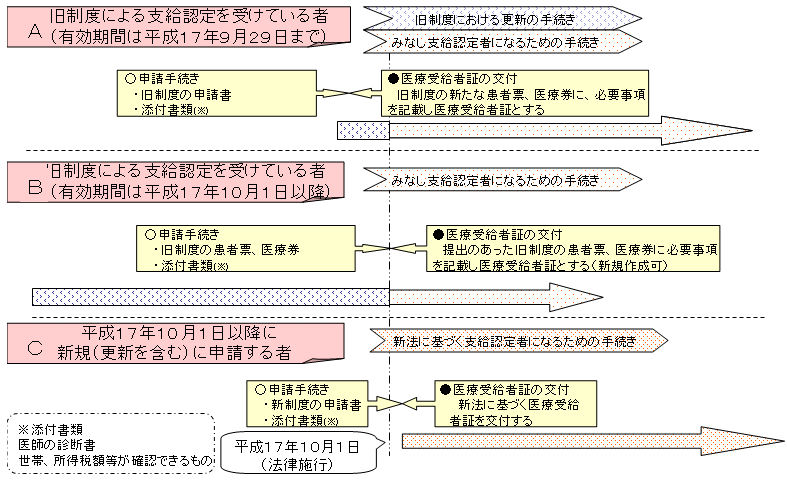
| ※ |
旧制度による支給認定者が多数のため、窓口の混乱を防ぐとともに事務量の軽減を図る工夫が必要であることから、例えば次のような申請期間を分散する方法が考えられる。 |
| B |
: |
旧制度による支給認定を受けている者(平成17年10月1日
を超えた有効期限の者)の手続き分散(案) |
|
↓
| 有効期限 |
申請期間 |
| ○ |
17年10月〜18年3月 |
| ○ |
18年4月〜18年9月 |
| ○ |
18年10月以降 |
|
17年7月下旬〜8月上旬
17年8月中旬〜8月下旬
17年9月上旬〜9月中旬 |
|
〈支給認定事務フロー図(みなし支給認定)〉
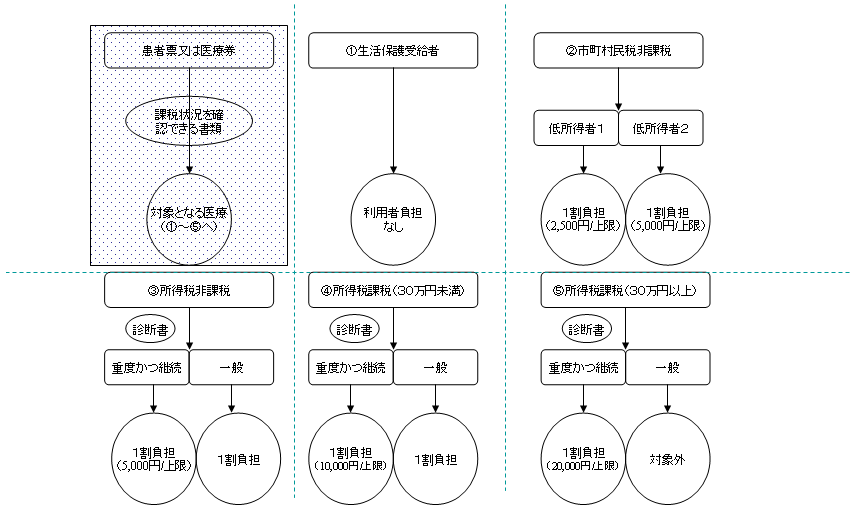 〈支給認定事務フロー図(新規支給認定)〉
〈支給認定事務フロー図(新規支給認定)〉
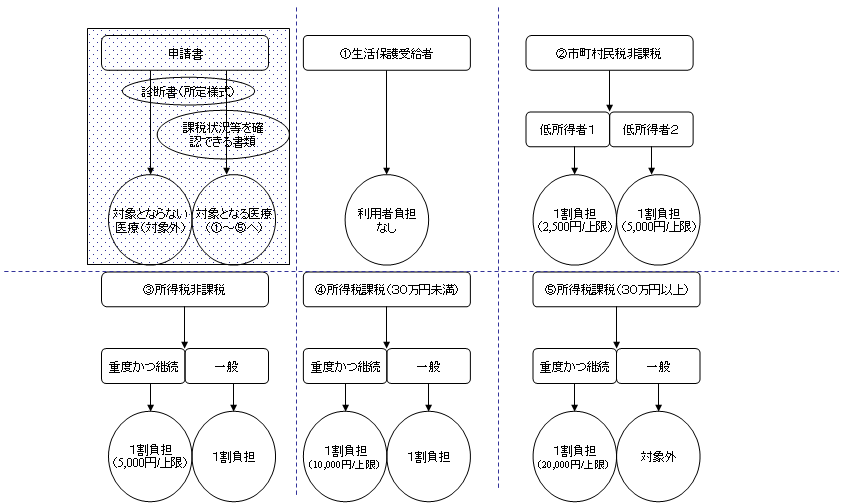 重度でかつ継続的に医療費負担が発生する者のモデル的な利用者負担の変化
重度でかつ継続的に医療費負担が発生する者のモデル的な利用者負担の変化
| モデル1 |
旧)精神通院:統合失調症 デイケア等を利用 月額医療費約15万円 |
| |
旧制度 |
新制度(1割負担)(注1) |
| 生活保護 |
0円(0%)※7.5千円を医療扶助 |
0円 |
| 低所得1 |
7.5千円 |
2.5千円 |
| 低所得2 |
5千円 |
所得税非課税
(市町村民税は課税) |
5千円 |
| 所得税課税 |
1万円 |
| 一定所得以上 |
2万円(経過措置) |
| モデル2 |
旧)更生医療:腎疾患 通院で人工透析を実施 月額医療費約28万円 |
| |
旧制度 |
新制度(1割負担)(注1) |
| 生活保護 |
0円 |
0円 |
| 低所得1 |
0円 |
2.5千円 |
| 低所得2 |
0円 |
5千円 |
所得税非課税
(市町村民税は課税) |
2.3千円〜3千円 |
5千円 |
| 所得税課税 |
3.5千円〜1万円 |
1万円 |
| 一定所得以上 |
1万円(注2) |
1万円(注2) |
| (注1) |
新制度における上記数値は月の負担額の上限である。 |
| (注2) |
人工透析の月額上限額は1万円である。 |
| (1) |
給付の対象(旧制度と同じ)
| ○ |
精神通院医療
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症(精神分裂病)、精神作用物質による急性中毒又は、その依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるもの。
|
| ○ |
更生医療
更生のために、医療が必要な身体障害者手帳所持者で、治療によって確実なる治療効果が期待できるもの。
|
| ○ |
育成医療
身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、治療によって確実なる治療効果が期待できるもの。 |
|
| (2) |
(1)のうち自立支援医療における重度かつ継続(重度でかつ継続的に医療費負担が発生する者)の対象
| ○ |
精神通院医療 |
・・・・・・ |
統合失調症、躁うつ病(狭義)、難治性てんかん |
| ○ |
更生・育成医療 |
・・・・・・ |
腎臓機能、免疫機能、小腸機能障害 |
| ○ |
上記のほか医療保険の多数該当に該当する者 |
|
| ・ |
申請者氏名、性別、年齢、住所及び電話番号 |
| ・ |
保護者又は扶養義務者の氏名、住所及び電話番号、本人との関係 |
| ・ |
被保険者証の記号及び番号、保険者名 |
| ・ |
障害者手帳番号及び手帳交付年月日(申請の対象となる障害者手帳の交付を受けている場合) |
| ・ |
希望する指定自立支援医療機関名及び所在地 など |
| |
旧制度(更生医療・育成医療)においては、毎年7月1日を起点として世帯の所得税額等に応じた自己負担額を認定し、徴収している(起点をまたがる場合は、再認定を実施)が、障害者自立支援法の運用にあたっては、新たに精神通院医療に係る当該事務等が加わることを勘案して、起点をまたがる場合であっても、所得税額等の再確認は行わないものとする。
なお、所得税額等の確認については、自治体の事務として一定時期等において行うことは差し支えない。
| * |
世帯の範囲
世帯の範囲については「生計を一にする者」を考えているが、具体的な範囲や基準については他制度との整合性を図りつつ決定することとしている。
|
| * |
所得の確認
所得の確認のための申請書添付書類については、市町村民税非課税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控えなどが考えられるが、世帯の範囲とも関連するので、追ってお示しする。 |
|
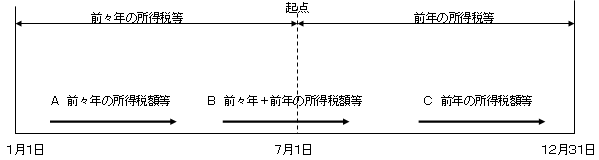
| ※ |
A,C |
: |
所得の再確認なし |
| ※ |
B |
: |
所得の再確認あり |
|
| ○ |
自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療) |
| |
現行 |
自立支援法 |
経過措置 |
| 精神通院医療 |
|
| ○ |
再認定の対象 |
| (1) |
一定所得以下
再認定あり |
| (2) |
重度かつ継続
再認定あり |
| (3) |
(1)(2)以外の者 |
再認定を認める場合や拒否する場合の要件については今後、臨床実態に関する実証的研究に基づき、制度施行後概ね1年以内に明確化。 |
| ・ |
みなし支給認定を受けた者の有効期限は、改正前の各法による承認期間の残存期間とし1年以内の省令で定める期間とする。 |
|
| 更生医療 |
| ○ |
有効期限 |
| ・ |
運用上概ね3ヵ月、疾病によっては最長1年以内 |
| ○ |
更新の場合 |
| ・ |
医師の診断書がない場合には原則、2週間以内かつ1回に限る |
| ・ |
医師の診断書がある場合には、運用上最長1年以内 |
|
| 育成医療 |
| ○ |
有効期限 |
| ・ |
運用上最長1年以内 |
| ○ |
更新の場合 |
| ・ |
運用上最長1年以内 |
| ・ |
医師の診断書 |
|
| |
障害者自立支援法案第75条に基づき定める政令において、受給者に一定の事由が生じた場合には、自立支援医療の実施主体である市町村等への届出を求めることとしている。現時点で考えている届出事由例は以下の通り。 |
| ○ |
氏名の変更(例;結婚、離婚、養子縁組、改姓、改名)
| ・ |
届出書記載事項;新旧氏名、受給者番号、変更年月日 |
| ・ |
添付書類;受給者証、氏名の変更を証明するもの
|
|
| ○ |
同一実施主体の区域における住所の変更
| ・ |
届出書記載事項;氏名、新旧住所、受給者番号、変更年月日 |
| ・ |
添付書類;受給者証、住民票等新住所を証明するもの
| ※ |
市町村合併等による地名の変更に伴う住所の変更の場合は不要とする。
|
|
|
| ○ |
資格喪失
| ・ |
届出書記載事項;氏名、受給者番号、資格喪失の年月日及びその理由 |
| ・ |
添付書類;受給者証住所の変更が理由である場合は新旧住所、事由を証明するもの
|
|
| ○ |
加入する医療保険の変更
| ・ |
届出書記載事項;氏名、受給者番号、変更の年月日 |
| ・ |
添付書類;受給者証、変更後の医療保険の書類が分かるもの |
|
| |
支給認定障害者等から次の事項について申請があった場合は支給認定の変更を行う。
| A |
「その他の者」として認定された受給者が支給認定期間中に「重度かつ継続」となった場合。 |
| B |
災害等のやむを得ない事情により経済的な状況が大幅に変わった等、一定所得以下に相当すると市町村等が個別に認定した場合。 |
|
なお、新たな申請者であっても、Bの取り扱いを行っても差し支えないものとする。
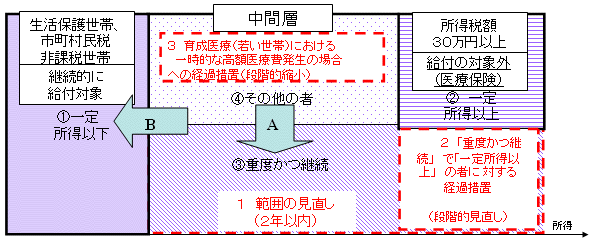
指定自立支援医療機関選定後に医療機関を変更する場合には事前に申請の上、支給認定の変更の認定を受ける必要がある。
| 1 |
指定自立支援医療機関の選定の意義
| ○ |
医療機関との適切な治療関係の構築や、質の高い医療の継続的な提供といった観点から、市町村等は、支給認定を行った際に、支給認定を受けた障害者等が自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関を選定することとされている。(法第54条第2項) |
| ○ |
自立支援医療は、あらかじめ予定された医療であり、原則として選定された医療機関以外の医療機関での受診は認められないものである。 |
|
| 2 |
選定の実施方法
| ○ |
更生・育成医療については、更生医療券や育成医療券に記載された病院又は診療所、薬局等を17年10月1日時点でそのまま選定する。(患者にとっては変更なし) |
| ○ |
他方、精神通院公費については、通院医療費公費負担患者票には病院又は診療所の記載しかないことから、薬局等については、施行前に所得等の資料を提出する際に、併せて薬局等に関する事項を記載した書面を提出させることとする。(※1) |
| (2) |
新法による支給認定の対象となる者(17年10月1日以後に新たに申請を行う者又は更新の申請を行う者)
申請時に、自立支援医療を受けるべき病院又は診療所、薬局等の名称等に関する事項を記載した書面を提出させる。
| ※1 |
法施行日以後に精神通院公費の新規又は更新の申請を行う場合には、病院又は診療所に加え、薬局等に関する事項についても記載させるようにする。 |
| ※2 |
支給認定を行う自治体以外の自治体に所在地のある医療機関を選定することも差し支えないこととする。 |
|
|
| 3 |
選定された指定自立支援医療機関の変更
| ○ |
選定後に医療機関を変更する場合には事前に申請の上、支給認定の変更の認定を受ける必要がある。
(法第56条第1項) |
|
| 4 |
その他指定自立支援医療機関の選定に係る留意事項
| ○ |
選定する指定自立支援医療機関のうち、病院及び診療所については、原則としては単独の医療機関を選定することとなるが、単独の医療機関では必要な自立支援医療をカバーできないような合理的な理由がある場合に、複数の医療機関を選定する場合があり得ると考えられる。 |
|
| ○ |
みなし支給認定者に対する医療受給者証の発行
みなし支給認定者に対する医療受給者証の発行は、改正前の各法による通院医療費公費負担患者票、更生医療券又は育成医療券を最大限活用するなど事務量の軽減を図るものとする。 |
| ○ |
改正前の各法による患者票及び医療券の種類
| イ |
通院医療費公費負担患者票 |
病院・診療所用 |
| ロ |
更生医療券、育成医療券 |
病院・診療所用、薬局用、訪問看護事業者用 |
|
|
| ○ |
みなし支給認定した医療券等
余白又は裏面を使って次のような表示をすることにより自立支援医療受給者証とする。
(ただし余白や裏面がない場合等、新しい受給者証に差し替えることが適切と判断される場合にはこの限りではない。)
通院医療費公費負担患者票にあっては薬局名、訪問看護事業者名を表示するものとする。
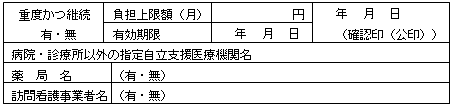
| ロ |
更生医療券、育成医療券 (病院・診療所用、薬局用、訪問看護事業者用) |
|
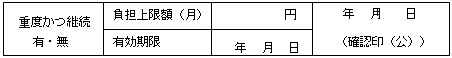
|
| ※ |
新たに自立支援医療受給者の認定を受けた者の医療受給者証は、別途検討の上提示する予定である。 |
| |
自立支援医療受給者の中には、疾病・症状等、所得により月々の負担上限額の認定を受けている者がおり、病院、薬局等2か所以上の指定自立支援医療機関の選定を受けている自立支援医療受給者に係る負担上限額の管理を行う必要がある。
その管理方法については例を示すが、当方で示した例の他により良い方法を実施している又は考えられる方法があれば情報提供していただきたい。
いただいた情報、ご意見を参照のうえ、おって管理方法をお示しいたします。 |
方式1)
| |
「自立支援医療費自己負担額整理簿(仮称)」を交付し、受診等ごとに指定自立支援医療機関で徴収した額を記入し、負担上限額を管理する方式
| (留意点) |
受給者が「自立支援医療費自己負担額整理簿(仮称)」を忘れた際の対応。 |
|
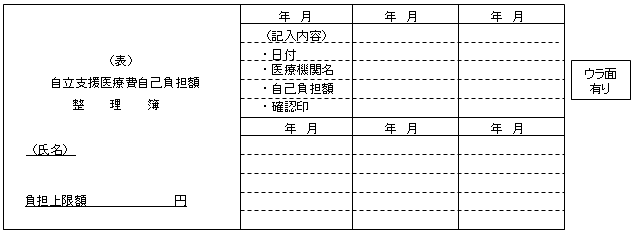
方式2)
| |
受診している医療機関において月末毎に一括して自己負担額を徴収する方式
| (留意点) |
当該医療機関では最大で当該医療機関に係る総医療費の1割しか徴収できないため、それを上回る負担上限額が認定されている場合、薬局等で残額を徴収することとなるため、医療機関等間の連携が必要である。 |
| ※ |
医療保険の多数該当の負担上限額の管理についての取り扱いについては検討中。 |
|
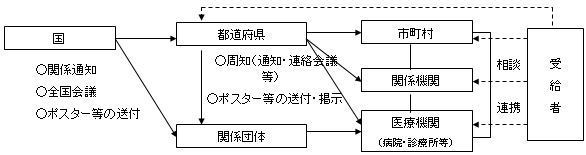
| ※ |
関係団体とは日本医師会、日本精神科病院協会、日本精神神経科診療所協会等自立支援医療を担当する医療機
関等が関係する団体、関係機関とは保健所、精神保健福祉センター、更生相談所等自立支援医療に関する事務、相談等を行う機関を言う。 |
| (2) |
周知の内容
| ○ |
法の施行関係 |
・・・・ |
制度の概要 |
| ○ |
諸手続きの関係 |
・・・・ |
各申請等手続き(時期、必要書類) |
|
指定自立支援医療機関の指定に関する事項
| ・ |
病院、診療所、薬局等の開設者の申請により、自立支援医療の種類(精神、更生、育成)ごとに都道府県知事が行う。(指定は6年間の有期。健康保険法と同様、別段の申出がないときに指定更新の申請があったものと見なす仕組みを導入) |
| ・ |
申請者が保険医療機関等でないとき、自立支援医療費の支給に関して重ねて勧告等を受けているとき、役員・職員が禁固・罰金を受けてから5年を経過していないとき等には、都道府県知事は指定をしないことができる。 |
| ・ |
指定自立支援医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定自立支援医療機関は、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。 |
| ・ |
都道府県知事は、必要があると認めるときは、医療機関の開設者等に対し報告や帳簿書類等の提出を命じ、出頭を求め、又は職員に関係者に対し質問させ、設備や診療録等につき検査させることができる。 |
| ・ |
診療方針等に沿って良質かつ適切な自立支援医療を実施していないと認めるときは、期限を定めて勧告することができ、勧告に従わない場合に公表、命令することができる。 |
| ・ |
診療方針等に違反したとき、自立支援医療費の不正請求を行ったとき、命令に違反したとき等において、都道府県知事は指定を取り消すことができる。 |
|
| ・ |
指定があったものと見なす医療機関
| |
障害者自立支援法附則第5条の規定に基づく、自立支援医療機関に関する事項の施行日(平成17年10月1日)に指定があったものと見なす医療機関は次のとおりである。 |
|
| 1. |
平成17年10月1日において現に改正前の身体障害者福祉法第19条の2第1項の規定の指定を受けている医療機関 |
|
平成17年10月1日現在指定を受けている医療機関
|
|
+ |
都道府県知事等の指定
(国が開設者以外の医療機関) |
|
|
|
→ |
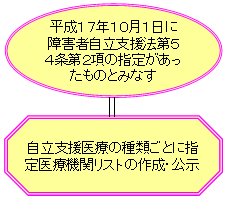 |
| 2. |
改正前の精神保健福祉法第32条第1項の医療を担当しているものとして厚生労働省令で定める基準に該当する医療機関 |
|
平成17年10月1日現在医療を担当している医療機関
2月〜4月の診療状況を基に当該医療機関リストを作成
(関係団体と調整中) |
|
+ |
7月〜9月の間の新たな受給認定者に係る当該医療機関リストを作成
(都道府県において作成) |
|
|
| ※ |
国が作成した医療機関リストは7月中に都道府県に配布予定。 |
|
→ |
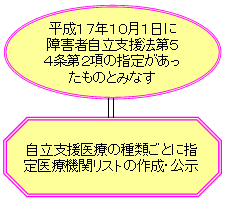 |
障害者自立支援法附則第5条の規定による指定があったものとみなされた医療機関は、平成17年10月1日から1年以内にあって厚生労働省令で定める期間内に同法第59条第1項の申請をしないときは、当該期間の経過によって、指定の効力を失う。
| ・ |
施行後における指定
| |
法施行後における指定自立支援医療機関の指定は、施行後において新たに自立支援医療を担当する医療機関の場合と同法附則第5条の規定による指定があったものとみなされた医療機関の更新とがあるが、その指定の手順は次のとおりである。
なお、人員配置等指定自立支援医療機関の運営方針、指定申請書の審査事務、指定自立支援医療機関の指導監督等については、別途お示しする予定である。 |
|
指定申請書受理から概ね1ヶ月後までに指定の可否を決定し、申請者に通知するとともに、指定を決定した場合は速やかに公示する。
公示の場合は、医療機関の名称、開設者、所在地等を予定している。
指定自立医療機関の指定について
【指定の対象機関】
指定自立支援医療機関の指定対象となるのは、障害者自立支援法案に規定する病院、診療所、薬局のほか、政令において、訪問看護事業所を規定することとしている。
【指定の事務主体】
指定自立支援医療機関の指定は、自立支援医療の種類ごとに行うこととされており、具体的な指定事務の実施主体は政令で規定することとなるが、現時点においては、
| ・ |
更生医療、育成医療については、都道府県、政令指定都市、中核市 |
| ・ |
精神通院医療については、都道府県、政令指定都市 |
における事務とする予定。
この場合において、更生医療、育成医療については、現行制度において更生医療の指定医療機関が同時に育成医療の提供機関となっていることを踏まえ、新たな制度においても指定申請書の共通化等を図りつつ一括して指定を行うことを原則とする方向で検討中。 |
同法附則第5条の規定による指定があったものとみなされた医療機関は、平成17年10月1日から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内に更新の申請を行うこととなっている。
| ○ |
指定に係る医療機関の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更
|
| ○ |
指定の辞退
| → |
医療機関は、一月以上の予告期間を設けて指定の辞退をする
|
|
| ○ |
指定の取消
| → |
医療機関が保険医療機関等でないとき、不正請求を行ったとき、
法63条及び67条に基づく指導勧告等に従わないとき等 |
|
|
↓
| ・ |
指定自立支援医療機関
| 1. |
良質かつ適切な自立支援医療を行うこと(法61条) |
| 2. |
診療方針は、健康保険の診療方針の例によること(法62条) |
|
| ・ |
医師の経験等の遵守事項
具体的な自立支援医療機関の遵守事項は、現在検討中。 |
|
診療科目別医療施設数(精神保健福祉課調:平成14年医療施設調査より)
| |
重複計上 |
| |
一般病院 |
精神病院 |
一般診療所 |
| 精神科 |
1,430 |
1,068 |
4,352 |
| 神経科 |
679 |
898 |
2,590 |
| 神経内科 |
1,637 |
81 |
2,109 |
| 心療内科 |
435 |
167 |
2,317 |
| 内科 |
7,379 |
681 |
61,917 |
| 小児科 |
3,359 |
33 |
25,862 |
| 脳神経外科 |
2,365 |
7 |
1,212 |
| 総数 |
8,116 |
1,069 |
94,819 |
| |
主たる診療科目 |
| |
一般病院 |
精神病院 |
一般診療所 |
| 精神科 |
|
|
1,695 |
| 神経科 |
|
|
200 |
| 神経内科 |
|
|
180 |
| 心療内科 |
|
|
279 |
| 内科 |
|
|
36,324 |
| 小児科 |
|
|
2,991 |
| 脳神経外科 |
|
|
509 |
| |
単科 |
| |
一般病院 |
精神病院 |
一般診療所 |
| 精神科 |
|
|
183 |
| 神経科 |
|
|
17 |
| 神経内科 |
|
|
22 |
| 心療内科 |
|
|
21 |
| 内科 |
|
|
12,222 |
| 小児科 |
|
|
2,285 |
| 脳神経外科 |
|
|
59 |
更生医療指定医療機関の指定状況(平成15年度末)
| 区分 |
医療機関数 |
区分 |
医療機関数 |
区分 |
医療機関数 |
| 眼科 |
590 |
中枢神経 |
174 |
小腸 |
193 |
| 耳鼻咽喉科 |
515 |
脳神経外科 |
326 |
歯科矯正 |
1,065 |
| 口腔 |
226 |
心臓脈管外科 |
759 |
免疫 |
353 |
| 整形外科 |
1,727 |
腎臓 |
2,456 |
薬局 |
14,600 |
| 形成外科 |
262 |
腎移植 |
156 |
訪問看護ステ-ション |
844 |
|
公費負担医療の見直しのスケジュール(案)
| |
国 |
都道府県等 |
市町村 |
17年3月
:
:
:
:
5月 |
| ○ |
全国会議の開催(3月18日・4月28日) |
| ・ |
支給認定の方法(所得の認定等) |
| ・ |
指定自立支援医療機関の指定の手順 |
| ・ |
周知の方法(全国会議、ポスター等(医療機関・自治体向け))他 |
|
| ○ |
市町村への伝達会議の開催
(施行に向けた準備開始) |
|
(同左) |
6月
:
:
:
:
:
:
7月 |
| ○ |
法案成立後に政省令等公布、関係通知発出 |
| ○ |
「みなし指定」の対象となる医療機関リストの提示 |
| ○ |
申請書、受給者証様式の確定、提示 |
| ○ |
都道府県等からの意見を踏まえた施行事務要領の提示(「みなし認定」の際の必要書類内容の整理を含む。) |
|
| ○ |
市町村、医療機関関係者等への説明会等の開催 |
| ○ |
指定医療機関の指定(経過措置) |
| ○ |
各種様式の準備 |
|
(同左) |
| ○ |
周知用ポスター等の提示 |
| ○ |
負担上限額の管理方法(アイデア募集) |
|
| ○ |
ポスター等による周知(施行時まで継続的に) |
| ○ |
現行受給者への通知(7月下旬〜) |
|
8月
:
:
:
:
9月 |
|
| ○ |
「みなし認定」、新制度による認定の実施
| ・ |
所得区分や「重度かつ継続」の確認 |
| ・ |
新受給者証の発行・交付(「みなし認定」
対象者については現行の患者票、医療券も活用) |
|
|
(同左) |
| 10月 |
|
(同左) |
(同左) |
「医療計画と精神障害者の退院促進についての進捗状況調査」結果報告
本年3月18日に配布した医療計画等についての資料に関する標記調査にご協力いただきまして誠に有り難うございました。集計及び分析結果については下記の通りですので、ご報告いたします。
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課
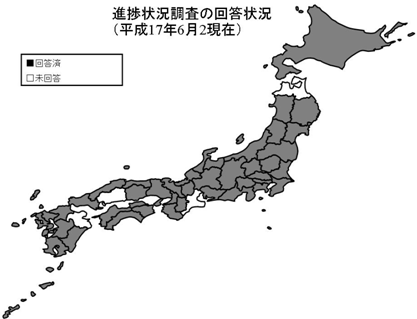
<コメント>
情報提供未了の都道府県においても「近日中に行う予定」という回答が多く、本件についてはほぼ円滑に情報提供がなされているものと考えられる。
他方、医療計画関係と精神保健関係とを同じ部署が担当している都道府県は1〜2県のみであり、今後も各自治体内における関係部署間の連携協力体制が重要と考える。
| ◎ |
医療計画資料についての理解度
| 完全 |
: |
0 |
/ |
概ね |
: |
11 |
/ |
多少 |
: |
23 |
/ |
よく分からず |
: |
8 |
/ |
全く分からず |
: |
0 |
|
| ◎ |
新しい算定式の内容についての理解度
| 完全 |
: |
0 |
/ |
概ね |
: |
12 |
/ |
多少 |
: |
21 |
/ |
よく分からず |
: |
8 |
/ |
全く分からず |
: |
0 |
|
<コメント>
概ね理解を得た都道府県は全体の半分に満たなかった。特に「具体的な数値がないとイメージができない」という意見が目立った。この結果については今後周知を図る上で十分に考慮したい。
基準病床数を算定するための数値については医療法施行規則等で定めることとしており、都道府県で把握可能かどうかも含め精査の上、国で示す数値の範囲等を確定させた後に公布する予定である。
| ◎ |
医療計画の次回見直し時期
| 平成17年(現在見直し中) |
: |
2 |
/ |
平成18年予定 |
: |
7 |
/ |
平成19年予定 |
: |
17 |
/ |
| 平成20年予定 |
: |
9 |
/ |
平成21年予定 |
: |
4 |
/ |
未定 |
: |
3 |
|
<コメント>
具体的な計算を行った都道府県はないものの、試算をしたという回答が一部に見られた。
医療計画の見直し時期については都道府県ごとにばらつきが大きく、基準病床数の計算もそれに併せて行うこととしている都道府県が多かった。
各都道府県において医療計画の見直しや基準病床数の計算が行われるに当たり、今後とも必要に応じ技術的支援等を行うこととしたい。
<コメント>
退院促進の目標数値を設定している都道府県は少ないものの、退院促進のための取り組みは一部の都道府県で既に行われている。その内容としては退院促進支援事業が多く、具体的な目標設定を行っている県も見られた。今後はそれらの成果検証を含め、より具体的な数値目標の達成を目指しての取り組みをお願いしたい。