精神保健福祉施策の改革と医療計画の見直しについて
厚生労働省障害保健福祉部
精神保健福祉課
精神保健福祉施策の改革の枠組み
| 精神保健福祉施策について、「入院医療中心から地域生活中心へ」改革を進めるため、(1)国民の理解の深化、(2)精神医療の改革、(3)地域生活支援の強化を今後10年間で進める。 |
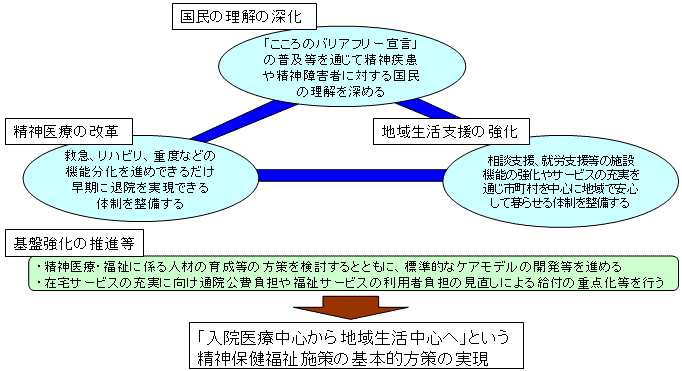
| ※ |
上記により、今後10年間で必要な精神病床数は約7万床減少 |
精神医療の改革の方向性
| 1 |
精神病床の機能分化と地域医療体制の整備 |
| 2 |
精神病床に係る基準病床数の算定式の見直し |
| 3 |
入院形態ごとの適切な処遇の確保と精神医療の透明性の向上 |
|
| ○ |
精神病床を急性期、社会復帰リハビリ、重度療養等に診療報酬上区分し、入院患者の病状に応じた医療体制を整備する。 |
| ○ |
精神科救急について、現行の一般救急システムと同様に、中核的なセンター機能を持つ救急医療施設の整備を進める。 |
| ○ |
都道府県が作成する医療計画において、精神科救急医療体制の整備に関する事項や精神入院患者の退院促進に関する方策に関する事項を記載する。 |
| ○ |
精神保健福祉法の改正により、病院等に対する指導監督の強化や地域医療体制の確保を図る。(障害者自立支援法の一部として、法案を国会に提出ずみ) |
|
精神保健福祉施策の見直しと医療計画との関係
| 1. |
基準病床算定式の見直しを通じた精神病床に関する目標値の設定 |
|
| ○ |
精神病床の基準病床数に係る算定式について、平均残存率、退院率等の目標値がパラメータとして含まれるような算定式へと見直す。(平成17年5月見直し予定) |
| ○ |
都道府県ごとの目標値については、新たな算定式に基づき、各都道府県の医療審議会等で検討して設定する。 |
| ※ |
平均残存率等は、将来的には疾病別の入院動態を踏まえた設定方式へと見直す。 |
|
| 2. |
精神入院患者の退院促進に向けた障害福祉計画と医療計画との連携 |
|
| ○ |
目標値を達成するための方策(精神科救急医療体制の整備等)について、医療計画において規定する方向で社会保障審議会医療部会にて検討中。 |
| ※ |
障害者自立支援法第89条第4項においては、都道府県障害福祉計画は、医療計画と相まって、精神病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない旨規定 |
|
算定式の見直しの視点
良質な医療を効率的に提供し退院を促進する体制づくりに向け
| 1 |
比較的短期で退院する群と、歴史的に長期に入院している群等が存在することを前提とした計算式へと見直す。
|
| 2 |
現状追認的なものから、退院率等の将来目標を設定し、段階的に地域差の解消を促す算定式へと見直す。
|
| 3 |
都道府県の実態に応じて、各都道府県が目標設定等について、一定の自由度を確保する算定式へと見直す。
|
| 4 |
各医療機関の病床利用の目標設定等、他の目的に活用できる普遍的なものへと見直す。 |
精神病床の新たな算定式(案)
(計算式)
基準病床数=(一年未満群)+(一年以上群)+(加算部分)
| ・ |
一年未満群=(ΣAB+C−D)×F/E1
| ※ |
A |
: |
各歳別人口(将来推計、4区分) |
| B |
: |
各歳別新規入院率(実績、4区分) |
| C |
: |
流入患者数 |
| D |
: |
流出患者数 |
| E1 |
: |
病床利用率(95%) |
| F |
: |
平均残存率(目標値) |
|
| ・ |
一年以上群=【ΣG(1−H)+I−J】/E2
| ※ |
G |
: |
各歳別一年以上在院者数(実績、4区分) |
| H |
: |
一年以上在院者各歳別年間退院率(目標値、4区分) |
| I |
: |
新規一年以上在院者数(一年未満群からの計算値) |
| J |
: |
長期入院者退院促進目標数(目標値)
(病床数が多く(対人口)、かつ退院率(1年以上群)が低い地域が設定) |
| E2 |
: |
病床利用率(95%) |
|
| ・ |
加算部分≦(D/E)/3
| ※ |
現行通り。居住入院患者数(当該区域に所在する病院の入院患者のうち当該区域に住所を有する者の数)がΣABより少ない場合、都道府県知事は上記の計算式で得た数を上限として適当と認める数を加えることができる。
|
|
| ・ |
数値:都道府県ごとの数値を用いる。 |
| ○ |
今後5年間の平均残存率等の目標値については、都道府県ごとに定められる10年後の達成目標と当該都道府県の現状値の中間値を基本とする。 |
|
新たな精神病床算定式と精神医療改革
−平成16年度厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業)「新たな精神病床算定式に基づく、早期退院と社会復帰促進のための精神保健福祉システムに関する研究」をもとに−
国立精神・神経センター精神保健研究所
精神保健計画部長
竹島正
平均残存率(一年未満群)の推計値
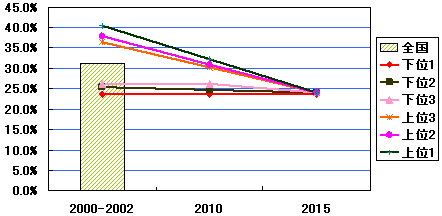
上位、下位県は2000-2002年の合計に基づく
退院率(一年以上群)の推計値
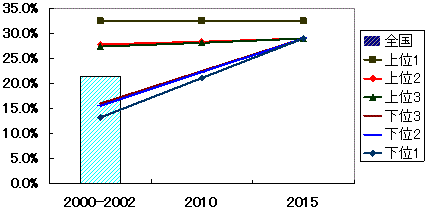
上位、下位県は2000-2002年の合計に基づく
基準病床数(人口万対)
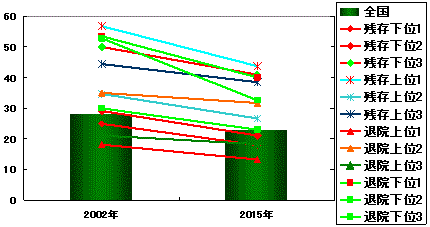
2002年から2015年までに、約7万床の減少となる
検討・分析した事項
| ・ |
入院患者の平均残存率及び退院率に影響する要因について |
| ・ |
都道府県において平均残存率の差を生じる要因の聞き取り調査 |
| ・ |
社会復帰施設等の整備と平均残存率及び退院率との関連について |
| ・ |
平均残存率及び退院率からみた各都道府県の傾向分析 |
入院患者の平均残存率及び退院率に影響する要因について
| ・ |
平均残存率と退院率について、厚生労働省患者調査を用いて性別、年齢、診断などの患者特性との関係を総合的に検討した。 |
| ・ |
長期在院化予備群が多くを占める「1年以上5年未満」の在院患者の特徴として、継続在院期間1年未満と比較して、年齢がやや高い、統合失調症等および認知症の割合が高く、九州の割合が高かった。 |
| ・ |
入院後1年までの残存率の推移から、認知症、知的障害および統合失調症等では病院に長く残存する傾向が見られた。 |
| ・ |
入院後の継続在院期間長期化に伴い、著しく退院可能性が低下していた。急性期に適切な対応ができる体制整備が退院促進に不可欠である。 |
| ・ |
入院後1年未満と1年以降のそれぞれにおいて、性別、年齢、病名により退院可能性が異なることが示唆された。 |
都道府県において平均残存率の差を生じる要因の聞き取り調査
| |
P県 |
Q県 |
|
人口万対病床数 |
25.0床 |
26.2床 |
| 病床利用率 |
90.9% |
91.3% |
|
平均在院日数 |
264.6日 |
513.3日 |
| 平均残存率(一年未満群) |
23.7% |
36.2% |
| 退院率(一年以上群) |
18.7% |
16.4% |
| ・ |
診療応需体制:P県は各々のブロックで医療ニーズをほぼ満たすことができる。個々の精神科病院は自院の患者は休日夜間でも診療することが基本。Q県の精神科救急事業は、受診までのプロセスが複雑である。 |
| ・ |
地域ブロックの大きさ:P県における人口60万程度の地域ブロックは、Q県の人口100万程度の地域ブロックよりも精神科救急として機能的である可能性がある。 |
| ・ |
歴史的経緯・精神科医師等の交流:P県では歴史的に医師間、病院間の交流が積み上げられてきた。そのことが病院間の協力と機能分化につながり、平均残存率が低いことに反映されていった可能性がある。 |
社会復帰施設等の整備と平均残存率及び退院率との関連について
| ・ |
社会復帰施設等の整備状況と,各地域における平均残存率や,退院率との関連について検討した。 |
| ・ |
平均残存率および退院率と,入所型社会復帰施設等の数,人口当たり定員数および実利用人数の関連では、平成10年生活訓練施設数が、平成14年退院率と統計学的に弱い相関関係を示した。 |
| ・ |
通所施設では、平成10、14年度、いずれの施設のどの指標とも、有意な相関は認められなかった。 |
(参考イメージ:「精神障害者の地域生活支援のありかたに関する検討会」より)
平均残存率及び退院率からみた各都道府県の傾向分析
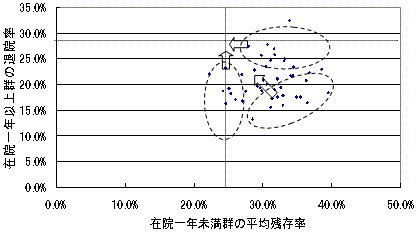
(参考イメージ:「精神病床等に関する検討会」より)
| ・ |
平成14年平均残存率及び退院率に基づくクラスタ分析により、3つのクラスタが得られた。平均残存率が高く退院率が低い群では、入所施設数と全社会復帰施設数で、他の2群を下回っていたが、統計的に有意な差はなかった。 |
| ・ |
平均残存率や退院率は直接には社会復帰施設数や人口当たりの定員数、実利用人数と関連しておらず、退院の促進には単純に施設の増設だけではなく、さらなる課題があることが示唆された。 |
| ・ |
退院率と平均残存率の両方に課題を抱えた県では、施設数そのものが不足している可能性もあり、地域特性を検討したより詳細な検討が必要である。 |
精神保健福祉施策における今後の方向性
厚生労働省障害保健福祉部
精神保健福祉課
目指すべき方向性
<その1>急性期等の医療の充実等
| → |
直接的には早期退院の実現 |
| → |
さらに、新規の長期入院の発生のできる限りの防止効果も |
| ○ |
病床の機能分化(強化)等
| ・ |
急性期、社会復帰リハ等の枠組みの整備(報酬体系等) |
| ・ |
救急医療体制の強化等、都道府県単位での分化を進める枠組み |
| ・ |
各病院における急性期等への人員の再配置 |
|
| ○ |
入院形態別の退院促進
| ・ |
措置入院等を受け入れる病院の基準見直し |
| ・ |
都道府県における実地検査等の体制強化 |
|
<その2>社会復帰リハの強化と地域体制強化
| ○ |
病床の機能分化(強化)等
| ・ |
急性期、社会復帰リハ等の枠組みの整備(報酬体系等) |
| ・ |
高齢者の増加等を念頭に置いた介護力を強化した病床の枠組み |
| ・ |
個々の医療施設等の長所を活かすための連携 |
|
| ○ |
地域における体制づくり
| ・ |
住、活動、生活等の支援体系の再編と充実(障害者自立支援法案) |
| ・ |
都道府県、市町村における地域サービスの具体的な数値目標等を定める計画的な行政の推進 |
| ・ |
各病院における精神分野のノウハウを活かせる他分野への人員の再配置 |
|
医療計画と障害福祉計画の関係(精神部分)[イメージ]
![医療計画と障害福祉計画の関係(精神部分)[イメージ]図](images/04g.gif)
今後のスケジュール(案)
<病床算定式関係>
| ・ |
17年5月 医療法施行規則の改正・公布 |
| ・ |
17年度中 各都道府県において、
| − |
新たな算定式に基づく各都道府県の基準病床数の算定(達成目標の設定を含む) |
| − |
目標値を達成するための方策に関する検討(退院促進事業等) |
|
| ・ |
18年4月 新病床算定式の施行 |
<医療計画関係>
| ・ |
18年冬 医療法の改正法案を国会に提出 |
| ・ |
18年度以降 各都道府県において、障害福祉計画とも調和を図りつつ、随時医療計画の改定を実施(精神科救急医療体制の整備に関する事項や、精神長期入院患者の退院の促進に関する事項を規定する予定) |
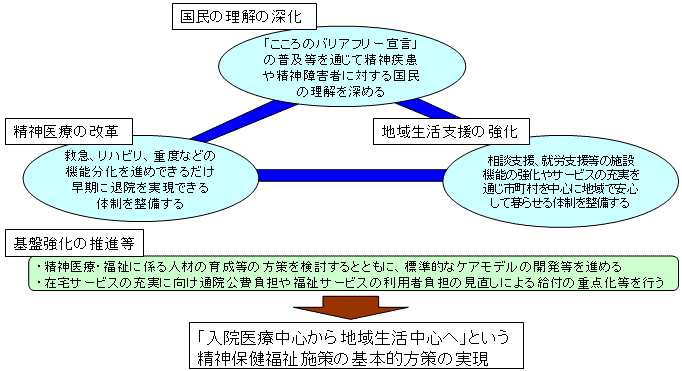
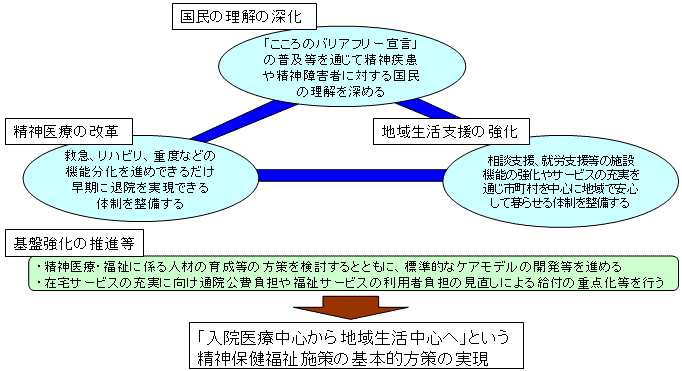
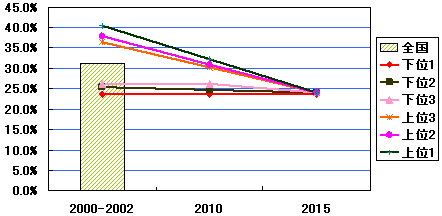
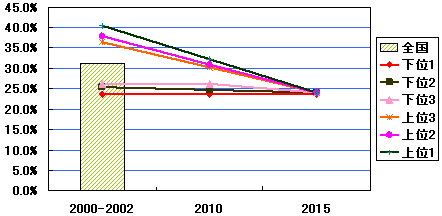
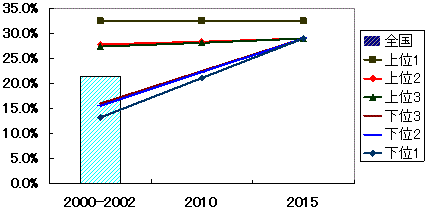
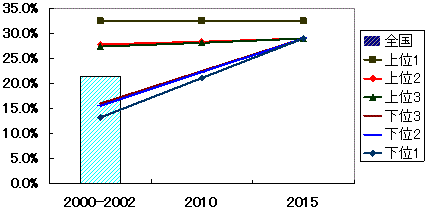
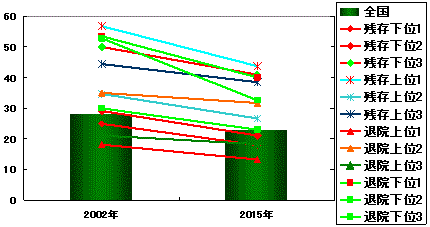
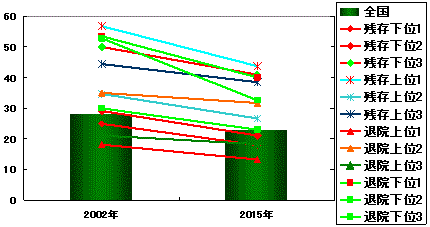
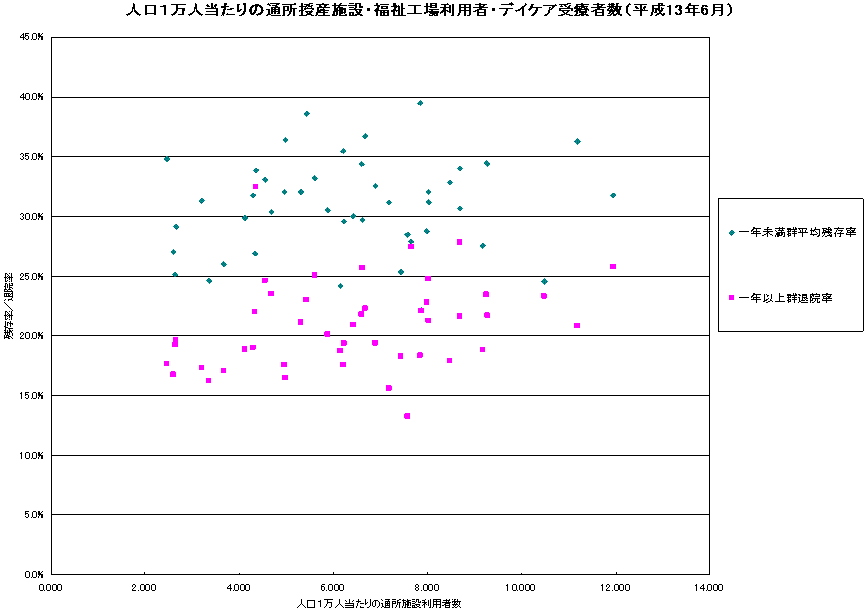
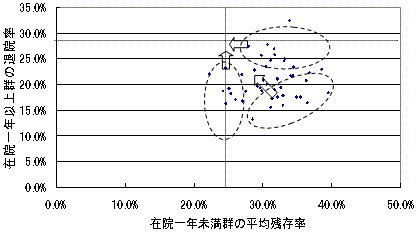
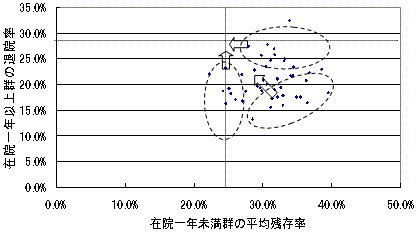
![医療計画と障害福祉計画の関係(精神部分)[イメージ]図](images/04g.gif)
![医療計画と障害福祉計画の関係(精神部分)[イメージ]図](images/04g.gif)