障害者自立支援法案における支給決定・サービス利用プロセスについて
現行制度の課題と新制度における対応について
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
→ |
|
← |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
← |
支給決定・サービス利用のプロセス(全体像)
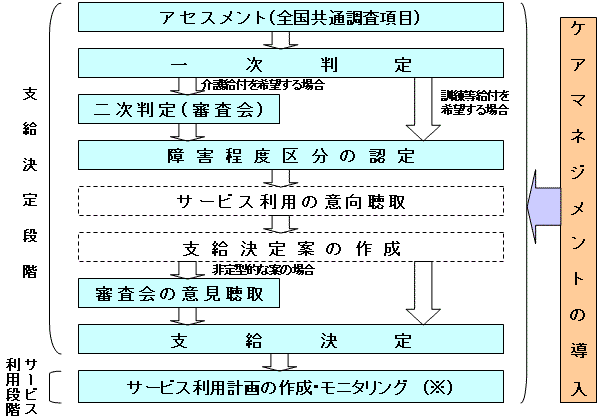
| (※) | 一定数以上のサービス利用が必要な者や長期入所・入院から地域生活へ移行する者などのうち、計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者を対象 |
(介護給付・訓練等給付の利用手続き)
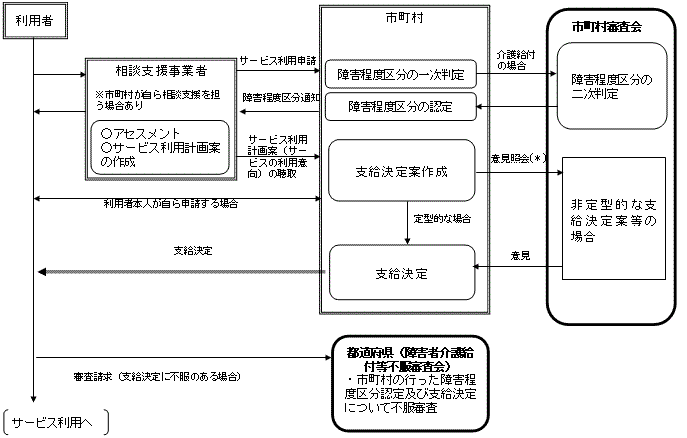
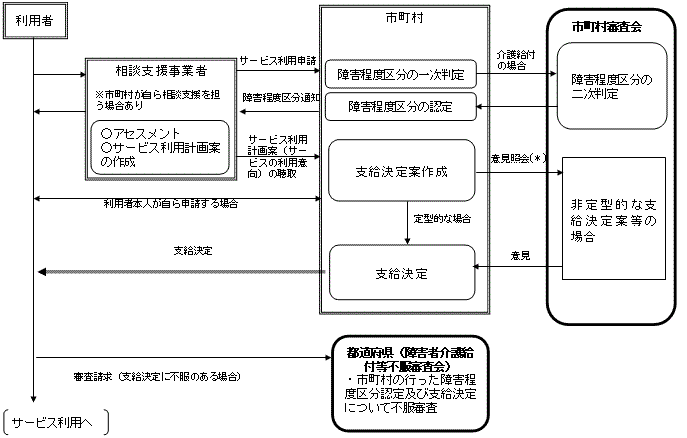
| (*) | より専門的な判断を要する場合には、更生相談所等に意見照会 |
支給決定後のサービス利用の流れ
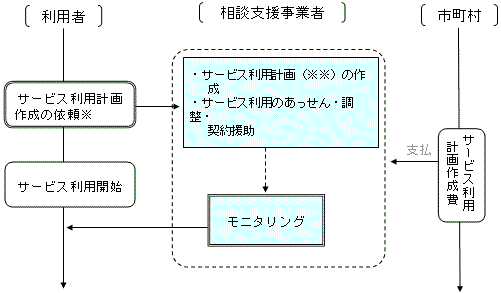
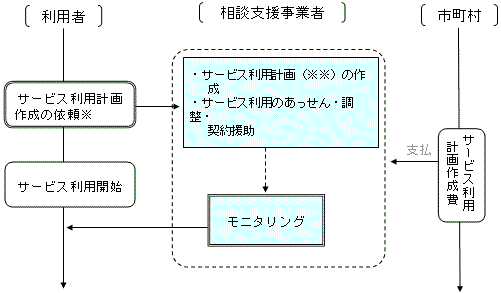
|
支給決定について
| 障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、(1)障害者の心身の状況(障害程度区分)、(2)社会活動や介護者、居住等の状況、(3)サービスの利用意向、(4)訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。 |
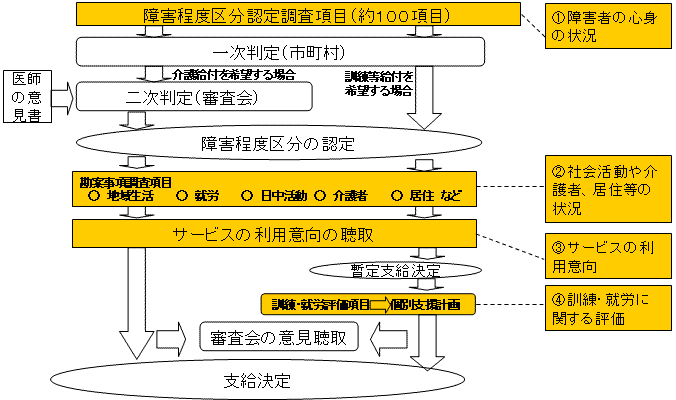
支給決定時のアセスメント項目(案)
| 障害程度区分 | 勘案事項調査 | 訓練・就労評価 | ||||||||||||
| 領域 | 例 | 領域 | 例 | |||||||||||
| 生活関連 | 調理 | 地域生活関連 | 外出の頻度・状況 |
|
||||||||||
| 掃除、洗濯 | ||||||||||||||
| 買い物 | 社会活動の参加の状況 | |||||||||||||
| 交通手段の利用 | ||||||||||||||
| コミュニケーション関連 | 視力 | 入所・入院歴、入所・入院期間 | ||||||||||||
| 聴力 | ||||||||||||||
| 説明の理解 | 就労関連 | 就労状況、過去の就労経験 | ||||||||||||
| 意思の伝達 | ||||||||||||||
| 行動関連 | 夜間不眠あるいは昼夜の逆転 | 就労希望の有無 | ||||||||||||
| 多動または行動の停止 | ||||||||||||||
| パニックや不安定な行動 | 日中活動関連 | 日中活動の主な場所 | ||||||||||||
| 身辺関連 | 整髪 | |||||||||||||
| 上衣の着脱 | ||||||||||||||
| 金銭の管理 | ||||||||||||||
| 薬の内服 | 介護者関連 | 介護者の有無 | ||||||||||||
| 排尿 | ||||||||||||||
| 移動・動作関連 | 寝返り | 介護者の健康状況等 | ||||||||||||
| 移動 | ||||||||||||||
| 洗身 | 居住関連 | 生活の場所 | ||||||||||||
| 麻痺等関連 | 下肢麻痺 | |||||||||||||
| 関節の動く範囲の制限 | 他のサービスの利用状況 | 受けているサービスの内容 | ||||||||||||
| 医療関連 | じょくそうの処置 | |||||||||||||
| レスピレーター | ||||||||||||||
| 透析 | ||||||||||||||
障害程度区分のイメージ(案)
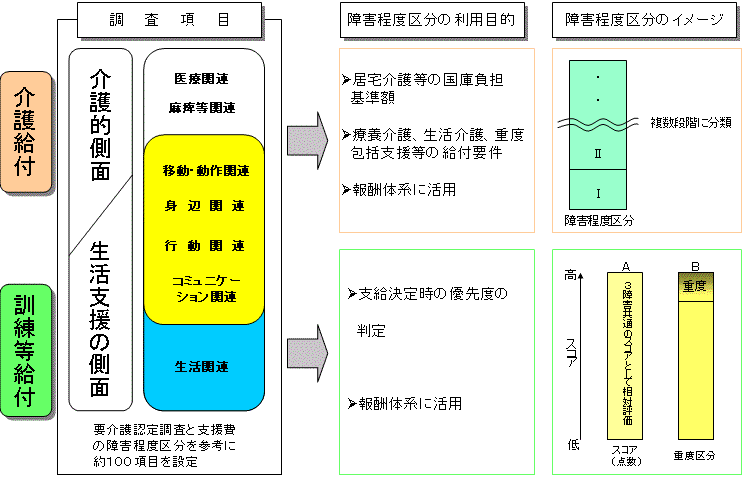
訓練等給付に関する支給決定(案)
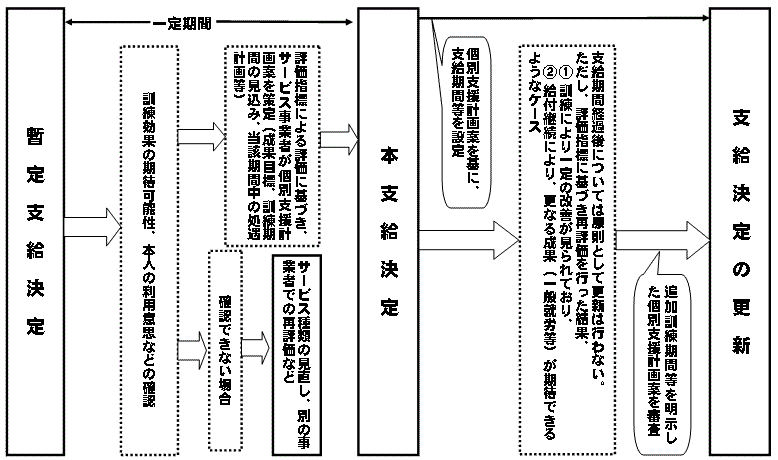
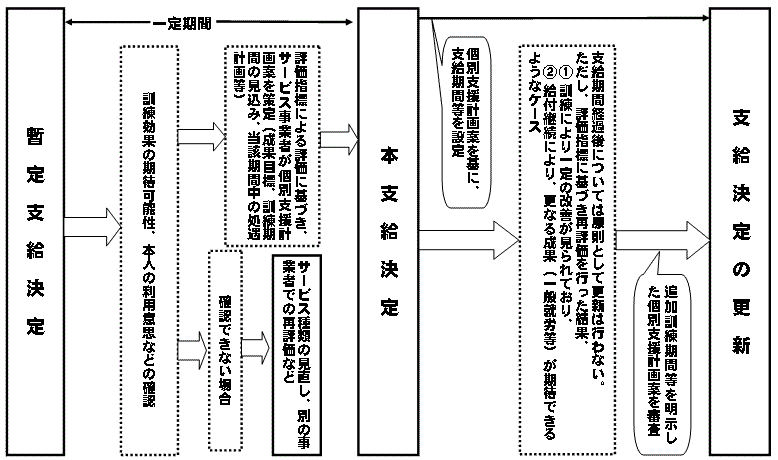
障害程度区分判定等試行事業(概要)
| ○ | 支給決定に関する調査(アセスメント)や障害程度区分素案の試行を通じ、障害者等の心身の状態等に関するデータを収集し、障害程度区分の開発を行うとともに、新制度における新支給決定手続き実施の際の実務上の課題を把握することを目的として実施 |
| ○ | 全国61市町村(各都道府県1カ所、14指定都市)で5月〜7月にかけて実施 |
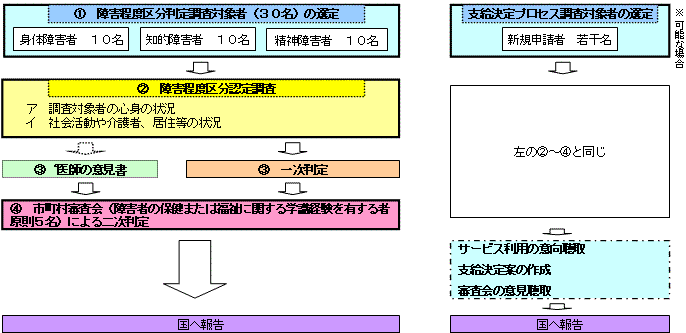
障害程度区分認定モデル事業対象自治体(案)
17.4.13
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 人口規模については、平成15年度版「全国市町村要覧」による |
| ※ | 北海道帯広市と京丹後市についてはホームページより確認した(2005/4/5) |
障害程度区分判定等試行事業実施要綱(案)
1.事業の目的
本事業は、支給決定に関する調査(アセスメント)や障害程度区分素案の試行を通じ、障害者等の心身の状態等に関するデータを収集し、障害程度区分の開発を行うとともに、新制度における新支給決定手続き実施の際の実務上の課題を把握することを目的とする。
2.事業内容
| (1) | 事業実施市町村 全国61市町村(各都道府県1カ所及び指定都市) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 調査対象者の選定
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 障害程度区分認定調査について
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 市町村審査会の設置及び施行
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 支給決定プロセスに係る試行 上記事業に加えて、実施可能な市町村は、試行事業実施期間中に在宅サービス(身体障害者又は知的障害者の居宅生活支援費、精神障害者居宅生活支援事業等)の支給申請を行った障害者若干名を対象に、(3)及び(4)を実施するとともに、別紙プロセスを参考にケアマネジメントの手法を活用しつつ、当該障害者からサービス利用の意向聴取、支給決定案の作成、審査会の意見聴取を試行する。 その際、支給決定案の作成は、現行の当該市町村の支給基準又は現行の当該市町村の支給決定の考え方を用いて行う。 なお、当該市町村が、障害の程度の判定に関し、既に独自のアセスメント項目を設定している場合には、当該アセスメント項目に基づき判定し、支給決定案を作成して差し支えない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 国への報告 報告は、次の2回に分けて報告を行う。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 事業実施における留意事項 本事業においては、障害程度区分認定調査や市町村審査会の実施上、使用する資料等から調査対象者個人が特定されないようにする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 経費の支出について 本事業の実施に係る経費については、別に定めるところにより事業実施自治体に対し、50万円程度を交付することとする。 |
試行事業における支給決定・サービス利用のプロセス(全体像)
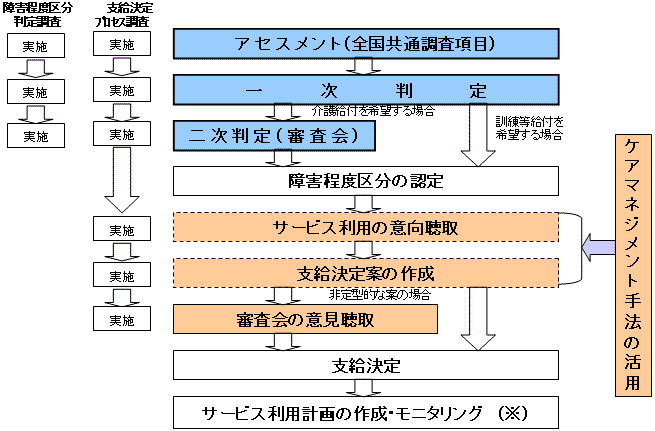
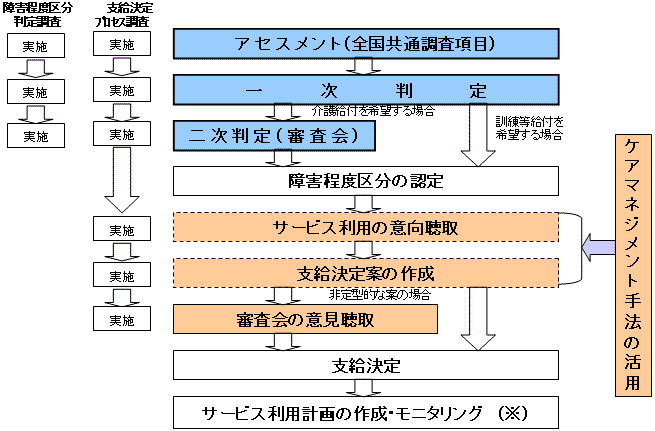
| (※) | 一定数以上のサービス利用が必要な者や長期入所・入院から地域生活へ移行する者などのうち、計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者を対象 |
障害程度区分判定等試行事業の流れ
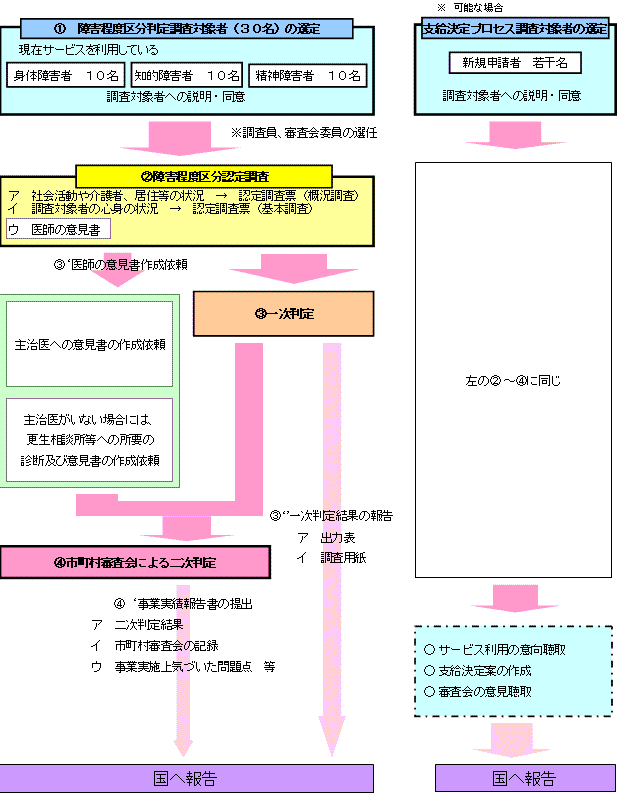
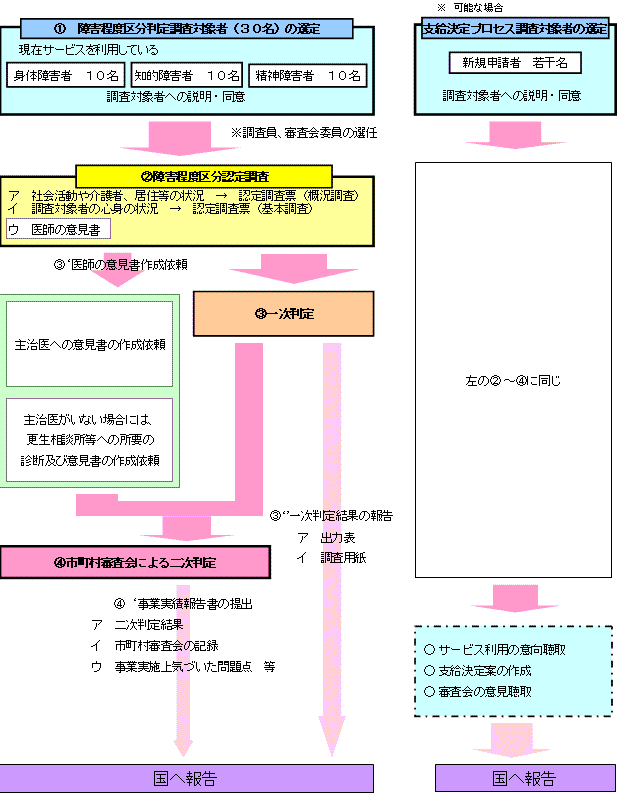
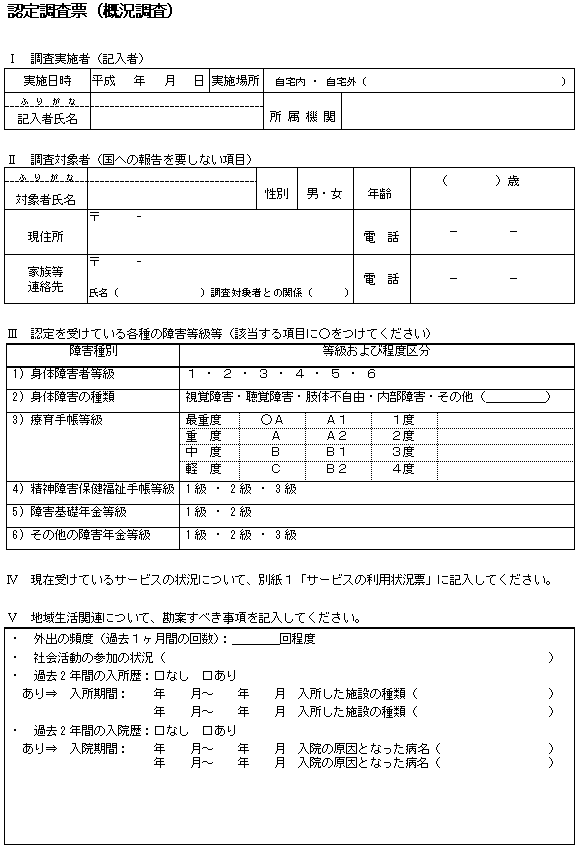
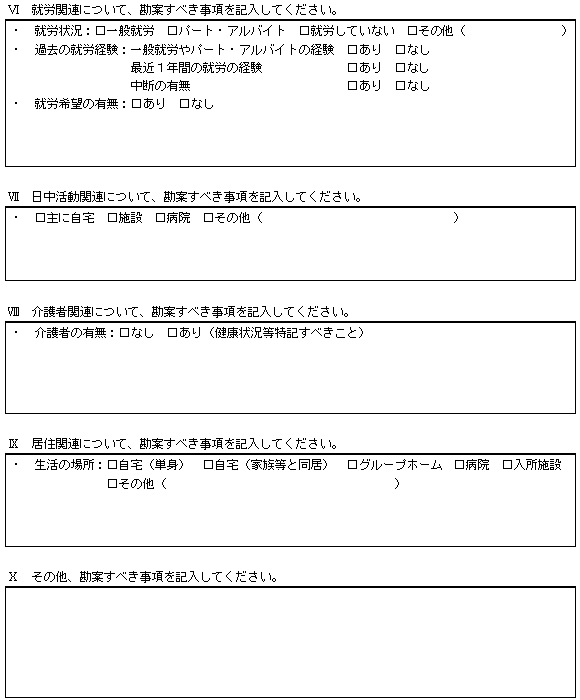
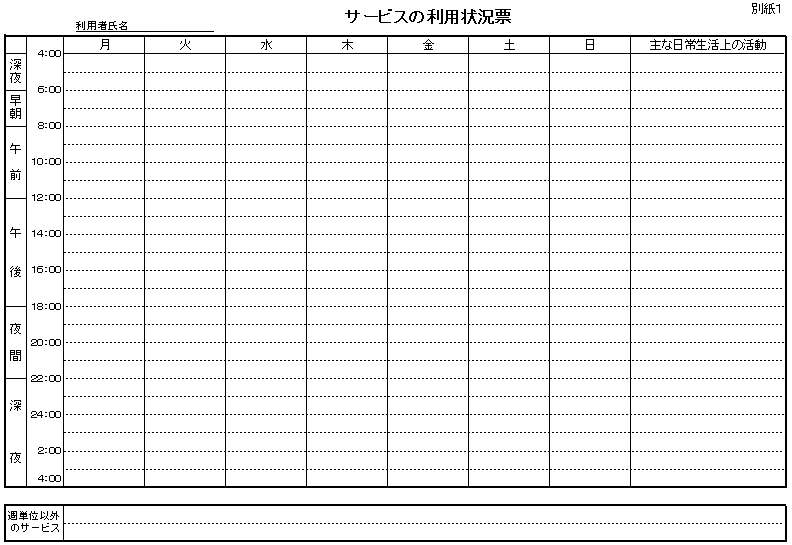
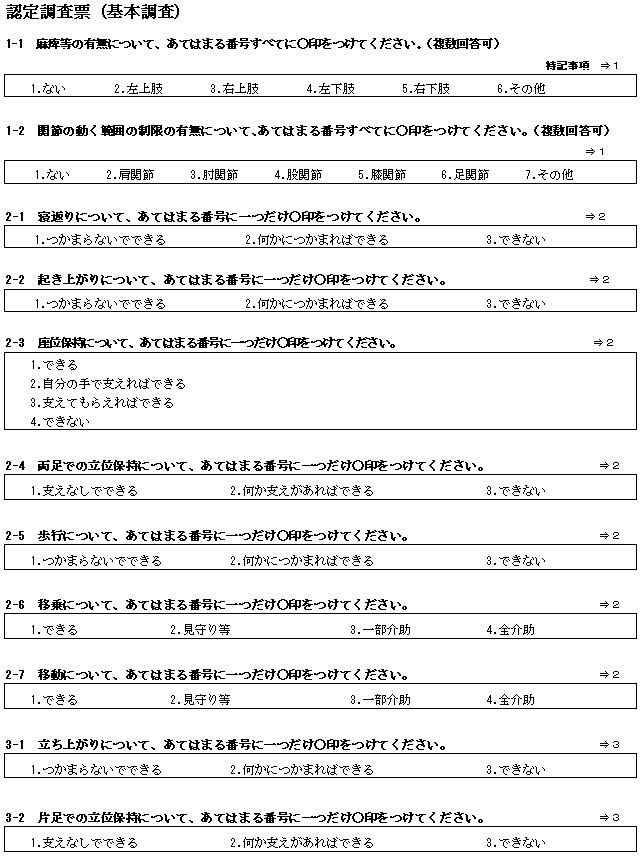
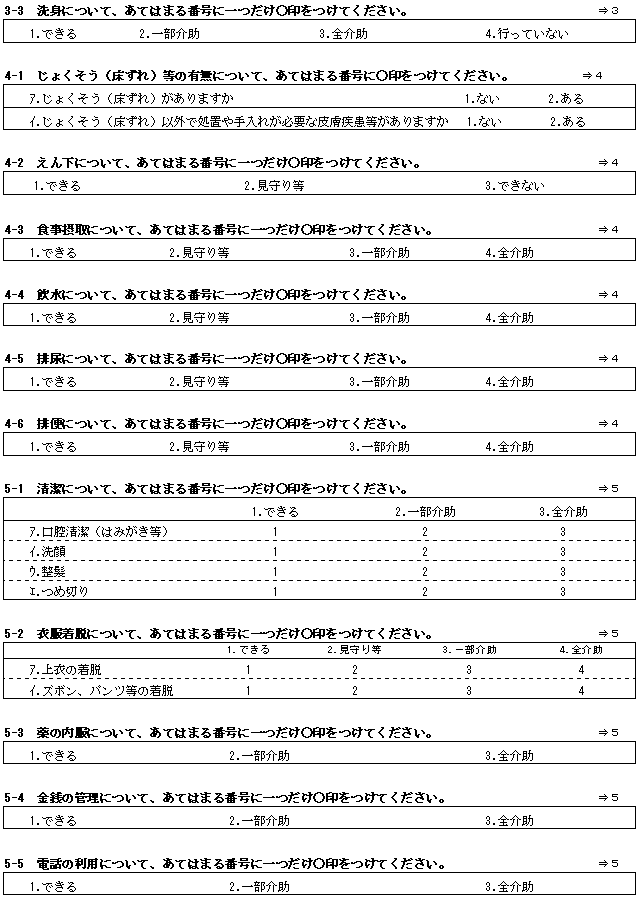
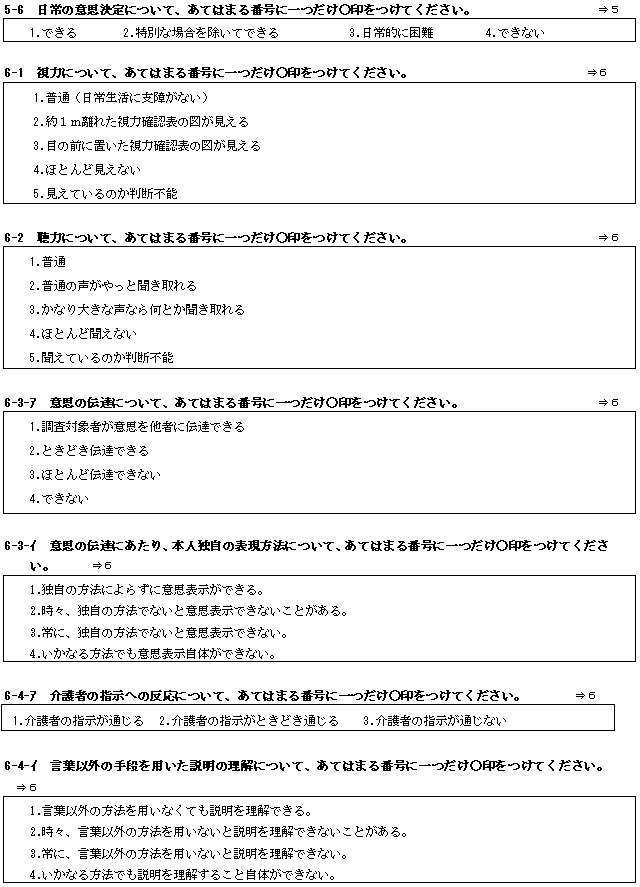
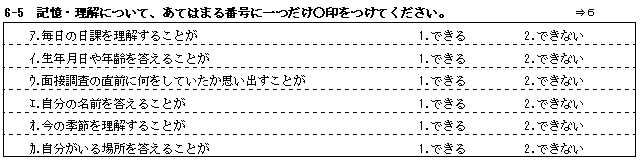
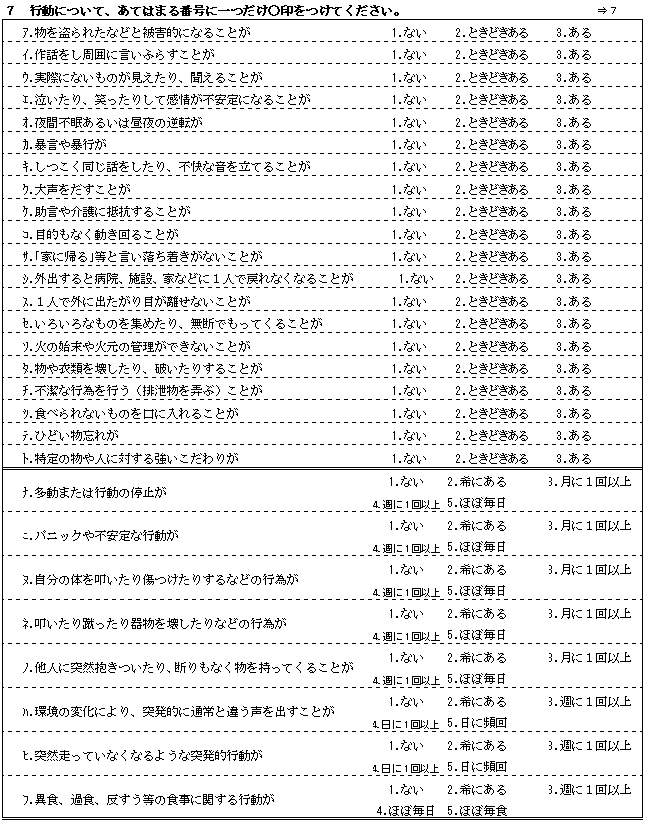
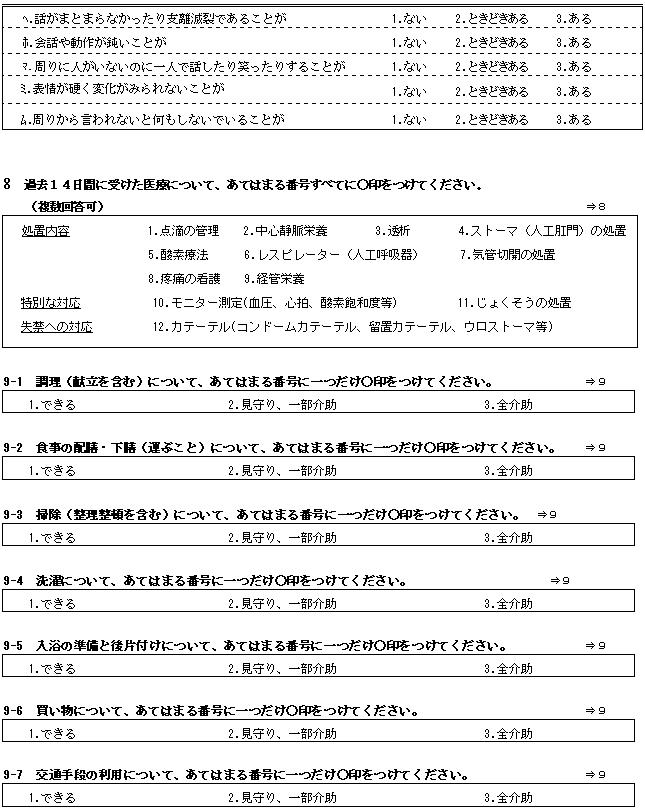
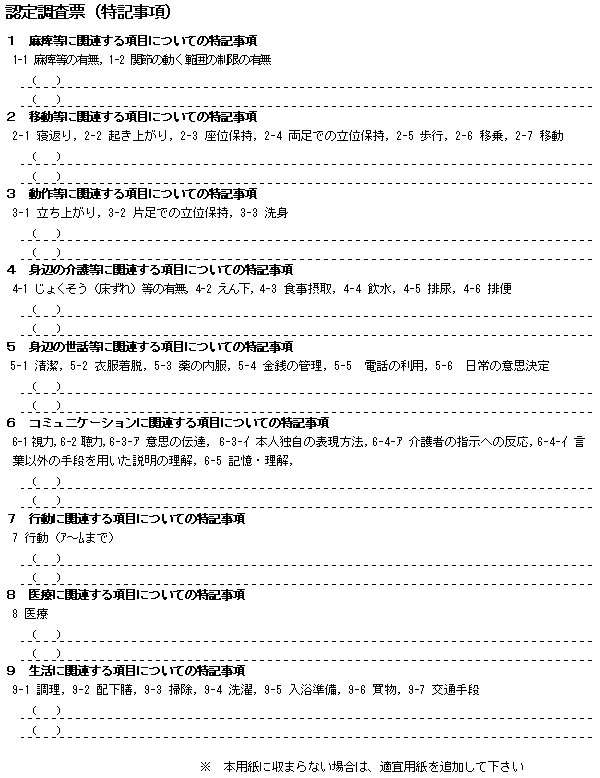
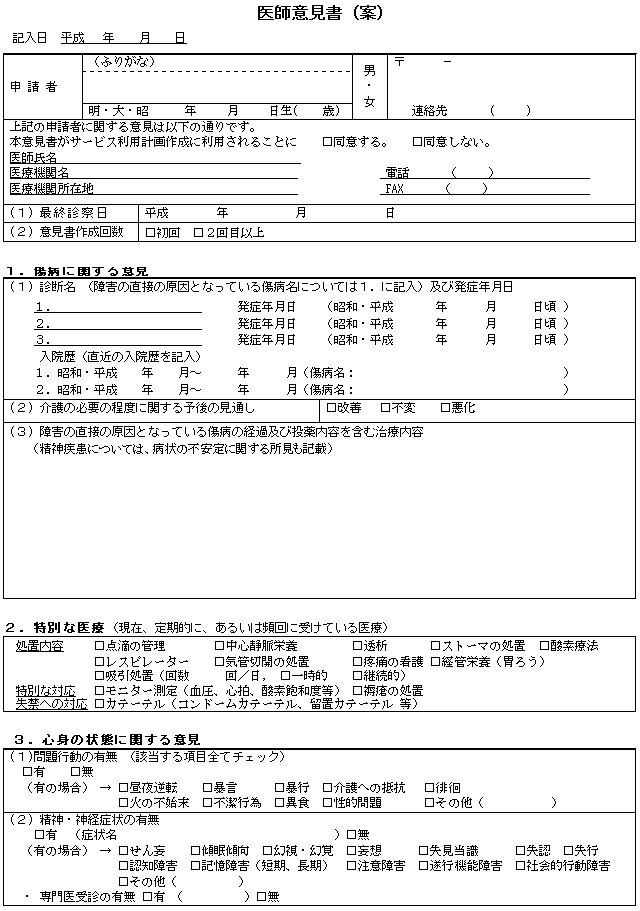
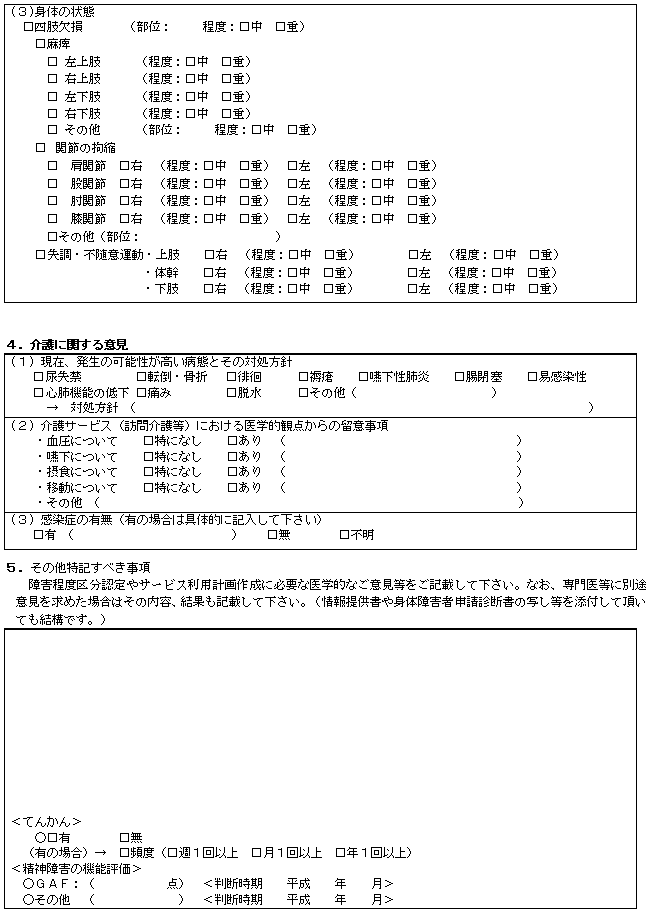
障害者に対する要介護認定基準の有効性について(概要)
【目的】
障害者の介護ニーズを判定するための指標として、現行の要介護認定基準の有効性を評価するため、福祉サービスを利用している障害者(2,468人)を対象に認定基準調査を実施
【結果】
(身体障害者)
| ○ | 身体障害者については、要介護認定における一次判定結果と、障害程度区分(生活関連動作支援項目)、介護支援専門員からみた要介護度との間に高い相関を示した。 |
| ※ | ホームヘルプ利用者・身体障害者療護施設入所者(119人)中、117人が要介護状態ないし要支援状態と判定 |
(知的障害者)
| ○ | 知的障害者については、要介護認定における一次判定結果と、障害程度区分(生活関連動作支援項目)、HoNOS、介護支援専門員からみた要介護度との間に比較的高い相関が認められた。 |
| ※ | ホームヘルプ利用者(30人)中、29人が要介護状態ないし要支援状態と判定 |
(精神障害者)
| ○ | 精神障害者については、他の障害と比較して、要介護認定の一次判定結果と、その他の指標との間にあまり高い相関は得られなかった。 |
| ※ | ホームヘルプ利用者(8人)中、2人が要介護状態ないし要支援状態と判定 |
| ○ | 一次判定結果が「要支援」以上であった群は、「非該当」であった群との比較において、障害程度区分、GAF、IADL、ケア必要度等他の指標の多くにおいて、重度またはケアの必要性が有意に高かった。 |
↓
【結論】
| ○ | 現行要介護認定基準は、身体介護等の介護サービスに相当するサービス、グランドデザインで言うところの「介護給付」に相当するサービスの必要度を測定する上では、障害者においても有効と考えられた。 |
| ○ | ただし、障害者に対する支援においては、自立を目的とした機能訓練や生活訓練、就労支援等も重要であり、これらの支援の必要度の判定には、「介護給付」に相当するサービスの判定に用いられるロジックとは別のロジックが必要と考えられた。 |
障害者に対する要介護認定基準の有効性について
| 1 | 目的 障害者の介護ニーズを判定する指標として、現行の要介護認定基準の有効性を評価する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 方法
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 結果 [身体障害者]
[知的障害者]
[精神障害者]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 考察 [現行要介護認定基準の適用可能性] 現在、客観的な指標に基づき介護の必要度を判定するものとして、我が国で制度的に用いられているものは、介護保険における要介護認定基準しか存在しない。 現行の要介護認定基準は、高齢者の加齢による介護ニーズに対し、身体介護等の介護サービスの必要度を予測する指標として開発されたものであるが、今回の調査において、身体障害者及び知的障害者の身体介護を中心とした介護サービスの必要度を測定する上でも有効であることが認められた。 一方、精神障害者については、「非該当」と判定された群と「要支援以上」と判定された群の2群間の比較では、GAF等他の指標の大半において、「要支援以上」の群が「非該当」の群と比べて重度またはケアの必要性が高いという有意差が認められ、要介護認定基準が精神障害者においても身体介護等の介護サービスの必要度を反映していることが示唆された。 精神障害者について、今回のデータでは、要介護認定の一次判定結果と、介護支援専門員が判断した要介護度、障害程度区分、GAF、BPRS等他の指標との高い相関は得られなかったが、これは、(1)調査対象者の半数について「要支援」又は「要介護1」が大半であり、残りの半数も「非該当」という結果であったこと、(2)介護支援専門員の判断する要介護状態区分が比較的低いレベルに分布していること、(3)障害程度区分(日常生活支援項目)の点数も低いレベルに分布していること、から統計的な相関が高くは得られなかったと考えられる。 なお、精神障害者が実際に利用しているサービスは、その大半が、グランドデザインでいうところの「訓練等給付」に相当する授産施設等のサービスであり、「介護給付」に相当するサービスとは異なっているが、これは、精神障害者では身体障害者や知的障害者と比べて身体介護等の支援を必要とする者が、相対的に少ないという実態を反映しているものと考えられた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 結論 現行要介護認定基準は、身体介護等の介護サービス、グランドデザインで言うところの「介護給付」に相当するサービスの必要度を測定する上では、障害者においても有効と考えられた。 ただし、障害者に対する支援においては、自立を目的とした機能訓練や生活訓練、就労支援等も重要であり、これらの支援の必要度の判定には、「介護給付」に相当するサービスの判定に用いられるロジックとは別のロジックが必要と考えられた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 今後の研究方針 今回の調査結果では、障害者に対しても、「介護給付」に相当するサービスの必要度を判定する指標として、介護保険制度で用いられている要介護認定基準は有効性をもつことが認められたが、今後、これを出発点として、より精確で加齢による要介護状態、障害による要介護状態双方により有効な指標の開発を進めていくことが必要である。そのためには、介護保険の要介護認定基準策定の際に行われたようなタイムスタディの実施が不可欠であり、平成18年度にも実施できるよう、障害福祉サービスにおけるケアコードの開発等の準備を行う必要がある。 なお、障害者に対する支援は、精神障害に関する今回の調査結果からも明らかなように、訓練、就労支援など身体介護以外のサービスが必要であり、こうしたサービスの必要度を判定するための指標の開発をあわせて進めていくことが必要と考える。 |
居宅サービスに係る支給決定の有効期間について
1 平成18年1月1日以降
| (1) | 平成18年1月1日以前に支給決定を受けている者 平成18年1月1日時点で新法の支給決定を受けたものとみなされる。 なお、居宅サービスに係るみなし支給決定の有効期間については、平成18年10月1日に新サービス体系に切り替わることから、平成18年9月30日までとする。 |
||||||
| (2) | 平成18年1月1日以降に新たに支給決定を受ける者
|
2 平成18年10月1日以降
| ○ | 居宅サービスに係るみなし支給決定等を受けている者 居宅サービスに係るみなし支給決定等は、平成18年9月30日で有効期間が終了するため、平成18年10月1日までに平成18年10月以降の支給決定を受ける必要がある。 |
| ※ | 精神障害者の居宅サービスについても上記と同様の取扱いとする。なお、具体的な事務手続きについては別途通知する。 |