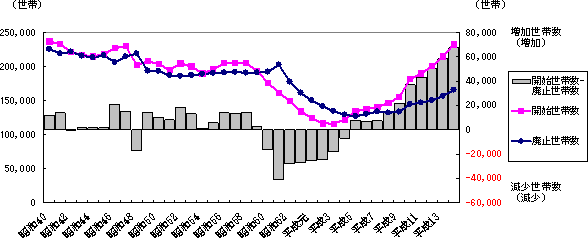
| (1 | )生活保護制度の在り方の検討
|
| (2 | )平成16年度生活保護基準の改定
|
| (3 | )生活保護の動向 最近の保護動向は、平成7年度を底に被保護人員、保護率共に急激に増加している。
|
保護の開始、廃止世帯数の年次推移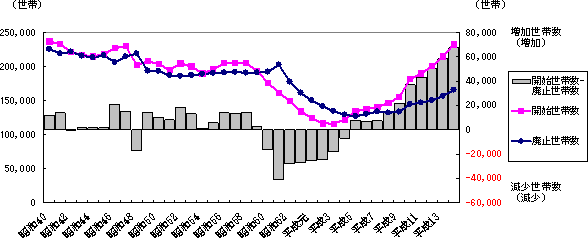 |
|
| (4 | )生活保護の適切な運営 生活保護は、国民生活の最後の拠り所となる制度であり、国民の理解と信頼を得られるよう、次の点に留意し、適切な保護の決定実施を行う体制の整備が講じられるようお願いしたい。
|
| 生活保護費補助金の概要 |
| 1 | 生活保護適正実施推進事業 16年度予算(案) : 60億円(補助率10/10) 生活保護適正実施推進事業の見直しを行い、実効性のある事業に重点化する。 (事業例)
|
| 2 | 自立・就労支援等事業(仮称)の創設 16年度予算(案) : 20億円(補助率1/2) 自治体における民間の活力も活用した自立・就労支援の取組みを新たに推進する補助事業を創設。 (事業例(案))
|
| (5 | )保護施設の整備及び運営
|
| 1 | 目的 近年、精神疾患に係る入院患者の退院後の受入先等として、救護施設のニーズが高まっていることに鑑み、敷地が狭い等の理由により、増築が困難な救護施設等について小規模な施設(サテライト型救護施設)を設置できるものとし、地域の実情に応じた救護施設の整備を促進する。 |
| 2 | 設置経営主体 サテライト型施設の設置経営主体は、本体となる救護施設(以下「中心施設」という。)を設置経営する地方公共団体若しくは社会福祉法人とする。 |
| (1 | )中心施設は生活保護法第38条に規定する救護施設とする。 |
| (2 | )中心施設とサテライト型施設をもって、単一の施設とする。 なお、サテライト型施設は複数設置できるものとする。 |
| 4 | 定員 入所定員は、原則、サテライト型施設1か所当たり5名以上20名以下とする。 |
| 5 | 職員 サテライト型施設には、、実務上の責任者(サテライト型施設担当責任者)の他、必要な職員を配置すること。 |
| 6 | 運営 中心施設の施設長の管理の下に中心施設と一体的に施設運営が行われるものとする。 |
| 7 | 建物の構造及び設備 建物の構造及び設備については、「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準」(昭和41年7月1日厚生省令第18号)によるものとする。 ただし、入所者の処遇に支障がないときは、本体施設との兼用等により、事務室、集会室等を設けないことができる。 |
| 8 | 土地及び建物についての取扱い サテライト型施設に係る土地及び建物については、本体施設と同様の取扱いとすること。 |
| 9 | サテライト型施設設置の手続き |
| (1 | )都道府県は、中心施設と同様、生活保護法第40条第1項に基づき、サテライト型施設を設置することができる。 |
| (2 | )サテライト型施設を設置しようとする市町村は、中心施設と同様、生活保護法第40条第2項に基づき、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 |
| (3 | )サテライト型施設を設置しようとする社会福祉法人は、中心施設と同様、生活保護法第41条に基づき、都道府県知事の認可を受けなければならない。 |
| 10 | 施設整備費 サテライト型施設の施設整備費については「社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費の国庫負担(補助)について」(平成3年11月25日厚生省社第409号)に規定する救護施設の基準により行うものとする。 |
| ※ | 今後、内容について変更があり得る。 |
| 1 | 目的 救護施設に入所している被保護者がスムーズに居宅生活に移行できるようにするため、施設において、居宅生活に向けた生活訓練を行うとともに、居宅生活に移行可能な対象者の訓練用住居(アパート、借家等)を確保し、より居宅生活に近い環境で実体験的に生活訓練を行うことにより、社会的自立を図る。 |
| 2 | 対象者 本事業の対象者は、生活保護法第38条に規定する救護施設に入所している者であって、6か月間の個別訓練を行うことにより、居宅において生活を送ることが可能であると認められる者のうちから、当該施設長により選定された者とする。 また、事前に選定された対象者に対し、本事業の目的及び内容を十分説明し、その実施について了解を得ること。 なお、事業終了後、居宅生活を送ることが可能となった者については、その居住地を所管する保護の実施機関が保護の実施責任を負うこととなるので、十分な連絡調整を図ること。 |
| 3 | 実施施設の指定 本事業は、次により指定された救護施設において実施するものとする。 |
| (1 | )本事業を実施しようとする施設は、毎年度、事業に係る申請書を都道府県に提出し、その指定を受けること。 |
| (2 | )都道府県知事は、実施施設の指定を行う場合には、毎年度、厚生労働大臣に協議すること。 |
| 4 | 対象者の居住場所及び設備 訓練用住居は、当該施設の近隣に確保し、通常の生活に必要な設備を有すること。 なお、緊急時等の対応のため、電話設備を設けること。 |
| 5 | 訓練期間・対象人員 訓練期間は、原則6か月間(前期:4月〜9月、後期:10月〜3月の2期間)とし、対象人員は1期3〜5人とする。 |
| 6 | 職員の実施体制 本事業の実施に当たっては、原則として、2名以上の職員を配置することとし、本事業についての実務上の責任者(居宅生活訓練事業担当責任者)を専任職員として1名配置すること。 また、本事業は、当該施設入所者の処遇の一環として実施するものなので、本体施設と十分、連携協力体制をとり、実施すること。 |
| 7 | 事業の実施 本事業の実施に当たっては、居宅生活訓練事業担当責任者を中心に、事業対象者の状況に応じ、あらかじめ6か月間の訓練計画を定め、効果的に行うこと。 |
| 8 | その他留意事項 本事業の実施期間中は、衛生管理、健康管理について十分配慮すること。 本事業の実施に当たっては事故の防止について十分留意すること。 特に夜間においては、火災等に備えて最前の注意を払うこと。 |
| ※ | 今後、内容について、変更があり得る。 |
| (6 | )生活保護及び保護施設の指導監査
|