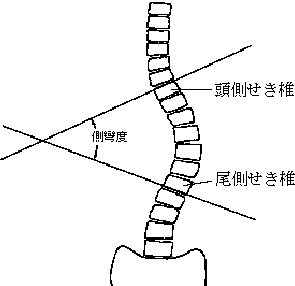| (1) | せき柱の障害認定の原則 せき柱のうち、頸椎(頸部)と胸腰椎(胸腰部)とでは主たる機能が異なっている(頸椎は主として頭部の支持機能を、また、胸腰椎は主として体幹の支持機能を担っている。)ことから、障害等級の認定に当たっては、原則として頸椎と胸腰椎は異なる部位として取り扱い、それぞれの部位ごとに等級を認定すること。 |
| ア | せき柱の変形障害については、「せき柱に著しい変形を残すもの」、「せき柱に変形を残すもの」に加え、新たに第8級に準ずる障害として取り扱う「せき柱に中程度の変形を残すもの」の3段階で認定すること。 |
| イ | 「せき柱に著しい変形を残すもの」及び「せき柱に中程度の変形を残すもの」は、せき柱の後彎又は側彎の程度等により等級を認定すること。この場合、せき柱の後彎の程度は、せき椎圧迫骨折、脱臼等(以下、「せき椎圧迫骨折等」という。)により前方椎体高が減少した場合に、減少した前方椎体高と当該椎体の後方椎体高の高さを比較することにより判定すること。また、せき柱の側彎は、コブ法による側彎度で判定すること。 なお、後彎又は側彎が頸椎から胸腰部にまたがって生じている場合には、上記(1)にかかわらず、後彎については、前方椎体高が減少したすべてのせき椎の前方椎体高の減少の程度により、また、側彎については、その全体の角度により判定すること。 |
| ┌ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └ |
|
┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
| ウ | 「せき柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像(以下「エックス線写真等」という。)により、せき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいう。 |
| (ア) | せき椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの。この場合、「前方椎体高が著しく減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいうこと。 |
| ┌ │ │ │ └ |
|
┐ │ │ │ ┘ |
| (イ) | せき椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。この場合、「前方椎体高が減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいうこと。 |
| ┌ │ │ │ │ └ |
|
┐ │ │ │ │ ┘ |
| エ | 「せき柱に中程度の変形を残すもの」とは、エックス線写真等によりせき椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいう。 |
| (ア) | 上記ウの(イ)に該当する後彎が生じているもの |
| (イ) | コブ法による側彎度が50度以上であるもの |
| (ウ) | 環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む。)により、次のいずれかに該当するもの。このうち、a及びbについては、軸椎以下のせき柱を可動させずに(当該被災者にとっての自然な肢位で)、回旋位又は屈曲・伸展位の角度を測定すること。 |
| a | 60度以上の回旋位となっているもの |
| b | 50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの |
| c | 側屈位となっており、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの |
| ┌ │ │ │ │ │ │ └ |
|
┐ │ │ │ │ │ │ ┘ |
| オ | 「せき柱に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
| (ア) | せき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの |
| (イ) | せき椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかのせき椎に吸収されたものを除く。) |
| (ウ) | 3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの |
| ア | エックス線写真等では、せき椎圧迫骨折等又はせき椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に、疼痛のために運動障害を残すものは、局部の神経症状として等級を認定すること。 |
| イ | 「せき柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直したものをいう。 |
| (ア) | 頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの |
| (イ) | 頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの |
| (ウ) | 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの |
| ウ | 「せき柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 |
| (ア) | 次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの |
| a | 頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの |
| b | 頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの |
| c | 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの |
| (イ) | 頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの |
| (1) | 「鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形障害を残すもの」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいう。 したがって、その変形がエックス線写真によって、はじめて発見し得る程度のものは、これに該当しないものであること。 |
| (2) | ろく骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、ろく骨全体を一括して1つの障害として取り扱うこととし、ろく軟骨についても、ろく骨に準じて取り扱うこと。 また、骨盤骨には、仙骨を含め、尾骨は除くものと取り扱うこと。 |