酸化チタン光触媒による光誘起分解反応、光誘起親水化反応を発見。多様な効果を示す材料の開発、実用化に成功。
東京大学教授 橋本 和仁 東京大学教授
(元東陶機器(株)研究所主幹、事業部次長) 渡部 俊哉
東京大学名誉教授 藤嶋 昭
 外付けブラインドに適用し、 ビル冷却効果を実証 |
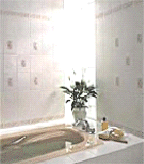 セルフクリーニング機能 を利用したタイル |
生体内のアミノ酸や糖類などの代謝物を一斉に測定する技術の実用化。
慶應義塾大学助教授
(ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株)取締役) 曽我 朋義
慶應義塾大学先端生命科学研究所長
(ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株)取締役) 冨田 勝
慶應義塾大学知的資産センター所長 清水 啓助
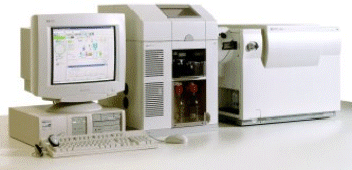
CE-MS装置
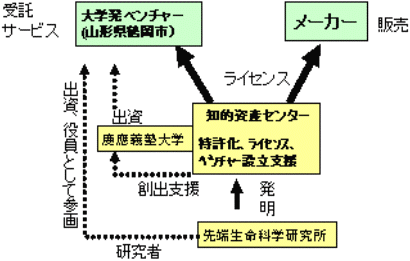
血圧正常化効果などがあるアミノ酸ギャバが、コメに大量に富化される条件を発見し新規食材を開発・特許化。製品化にも努め新規市場を創出。
(独)農業・生物系特定産業技術研究機構 近畿中国四国農業研究センター
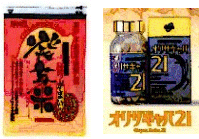
福井県の地元中小企業の若手経営者により設立された協同組合が、大学等との共同研究を通じて、環境に調和した風力発電機を開発
協同組合プロード代表理事 西村 琢磨
福井大学教授 山本 富士夫
福井県工業技術センター

各都道府県の計66箇所のアクセスポイントをギガビットクラスの回線で結んだ超高速テストベッドネットワークを整備。
次世代インターネット技術に関する研究開発等を全国規模で促進。
通信・放送機構(現:独立行政法人情報通信研究機構)
ギガビットネットワーク研究開発プロジェクト
プロジェクトリーダー 齊藤 忠夫(東京大学名誉教授)
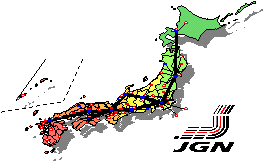
シリコン基板上などに微細加工技術マイクロマシニングを用いて立体的な構造を製作し光・機械・材料などを組み合わせた、MEMS(微小電気機械システム)と呼ばれる技術の産業展開に貢献
東北大学教授 江刺 正喜
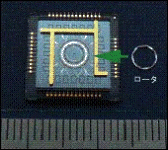
プレス成形過程で生じるスプリングバック現象を解析する立体構造予測手法を開発し、実用化に成功。
理化学研究所プログラムディレクター 牧野内 昭武
(株)先端力学シミュレーション研究所代表取締役社長 大崎 俊彦
(株)先端力学シミュレーション研究所主査研究員 吹春 寛
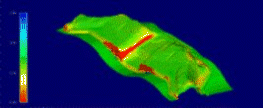 |
シミュレーションソフトを用いた、われ危険部位の解析 |
C型肝炎のインターフェロン療法の効果を事前に予測するDNAチップを開発
金沢大学教授 金子 周一
(株)ジェー・ジー・エス代表取締役社長 窪田 規一
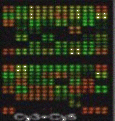 |
DNAチップによる解析 |
コバルト系ガラスのレーザー照射による屈折率変化メカニズムに関する研究を基にした、次世代DVD用集光機能膜の開発。
京都大学 工学研究科 教授 平尾 一之
独立行政法人産業技術総合研究所 光技術研究部門
ガラス材料技術グループ グループリーダー 西井 準治
社団法人ニューガラスフォーラム 研究開発部長 田中 修平
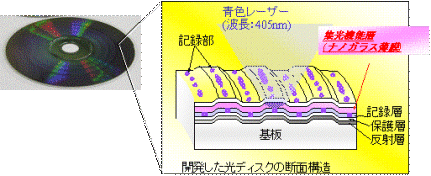
「日本一創業しやすい街」づくりを掲げ、ベンチャー企業が次々と誕生。また、九州シリコンクラスター計画(九州経済産業局)、シリコンシーベルト構想(福岡県)及び知的クラスター創成事業(文部科学省)と協働・連携し、具体的成果を生み出すイノベーションサイクルを構築し、クラスターのモデル地域を形成している。
飯塚市長 江頭 貞元(えとう さだもと)
九州工業大学長 下村 輝夫
近畿大学産業理工学部長 菊川 清

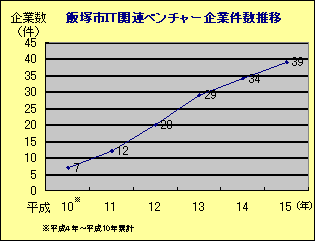
超微量の液滴を高精度に配列できることから、高精密のプリント基板を描画可能。電子部品の高密度化と、それによる電子機器の高機能化、高品質化をもたらすとともに製造過程の資源消費、環境負荷を軽減するものとしても期待される技術。
独立行政法人産業技術総合研究所ナノテクノロジー研究部門 スーパーインクジェット連携研究体
| 複雑図形の描画例[導電性高分子]:線幅3μm、格子部分のピッチ10μm) | 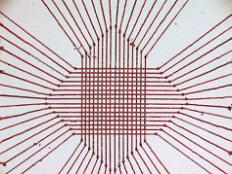 |
自己の細胞を用いて、実際に移植可能な表皮、軟骨を大量に培養する技術を確立。
名古屋大学教授 上田 実
広島大学教授 越智 光夫
(株)ジャパンティッシュエンジニアリング代表取締役 小澤 秀雄
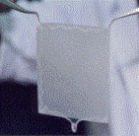 培養表皮 |
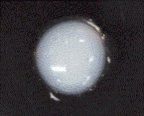 培養軟骨 |
臨床ニーズに基づいて複数のブレークスルー技術の開発と結集により、治療用医療機器である高性能人工肺を開発し、製品化と普及に成功。新しい治療分野への応用可能性も高い。
国立循環器病センター
人工臓器部長 妙中義之
東洋紡績株式会社
医療用具製造センター部長 佐藤正喜
大日本インキ化学工業株式会社
メンブレン本部本部長 酒井一成
