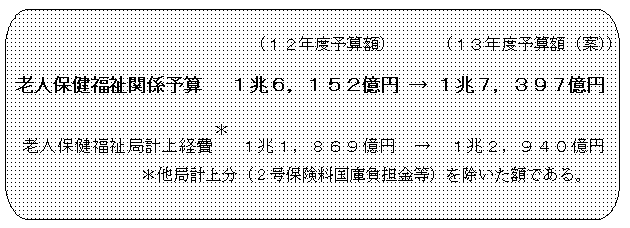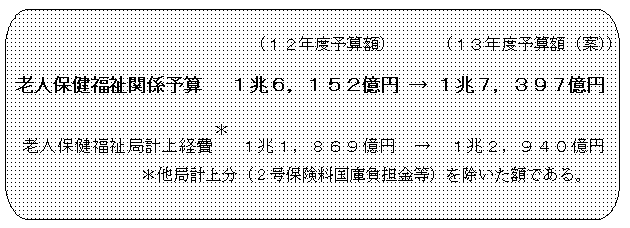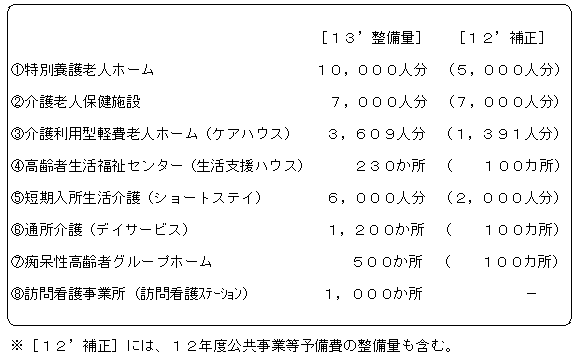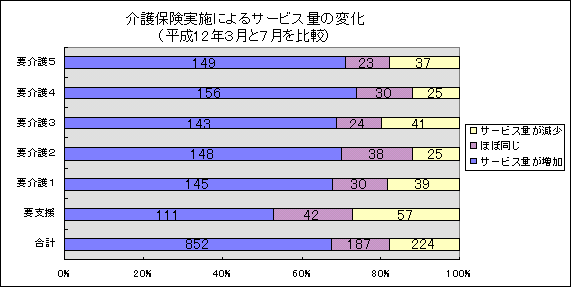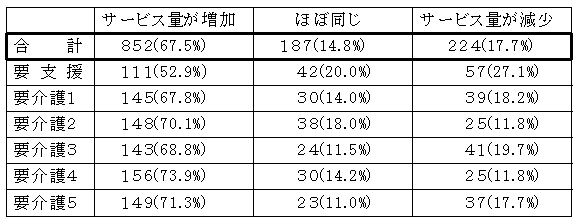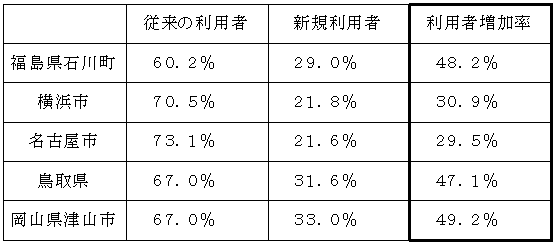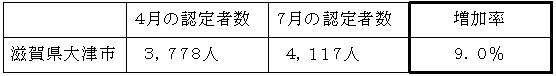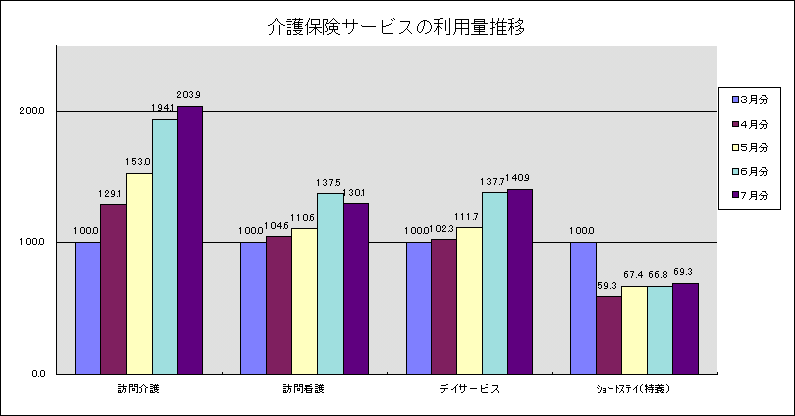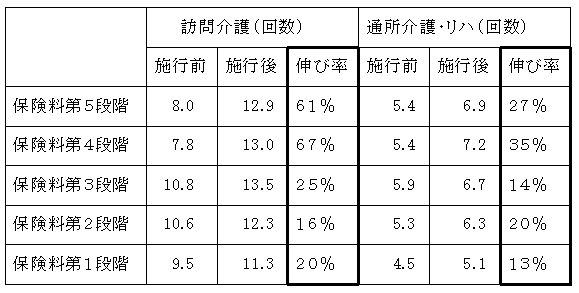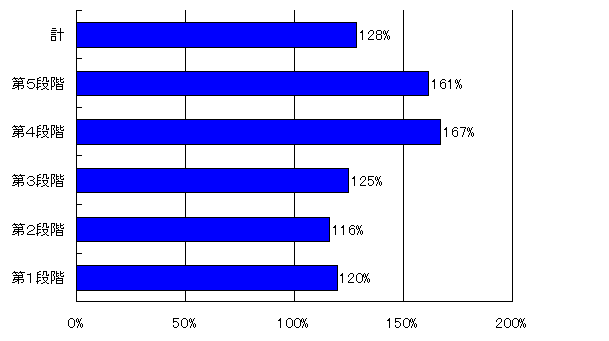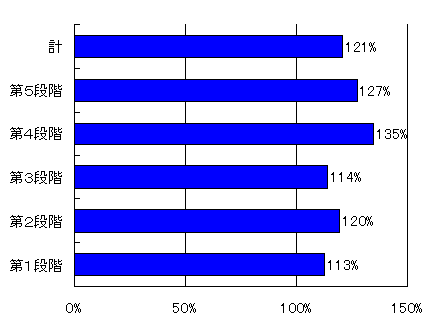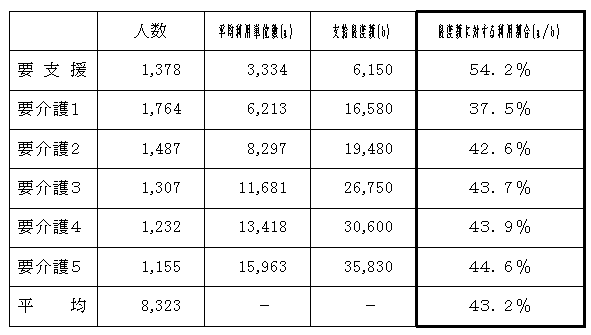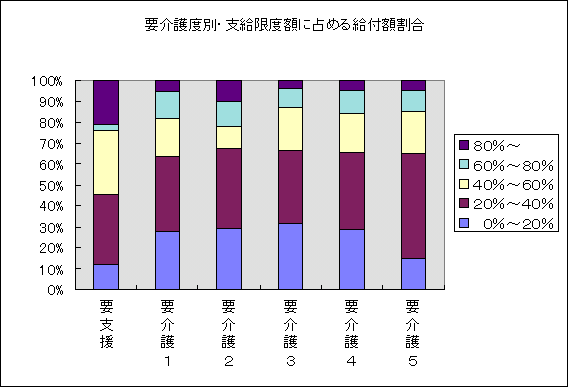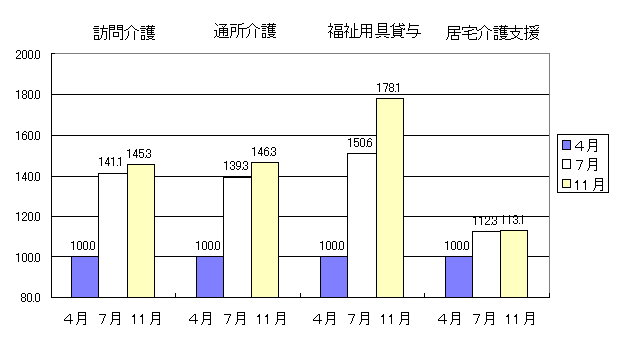会議資料目次
トピックス
厚生労働省ホームページ
全国厚生労働関係部局長会議資料
老健局
平成13年度老人保健福祉関係予算(案)の概要
平成12年12月24日
−老人保健福祉局−
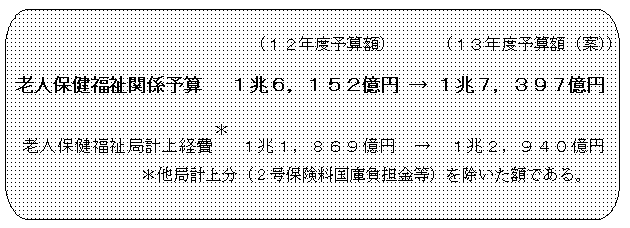
【主要事項】
| I 介護給付に対する国の負担等 |
(13’予算額(案))
1兆4,152億円 |
|
1. 介護給付費負担金
各市町村における介護給付及び予防給付に要する費用の20%を負担。
2. 調整交付金
全市町村における介護給付及び予防給付に要する費用の5%を負担。
(各市町村間の後期高齢者割合等に応じて調整)
3. 財政安定化基金負担金
都道府県が設置する財政安定化基金に対し、国がその3分の1を負担。
4. 要介護認定事務費交付金
市町村が行う要介護認定・要支援認定の事務処理に要する費用を交付。
| II 介護保険制度の着実な実施 |
(13’予算額(案))
2,462億円 |
|
1.ゴールドプラン21による介護サービス基盤の整備
(1)特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、痴呆性高齢者グループホーム等の整備
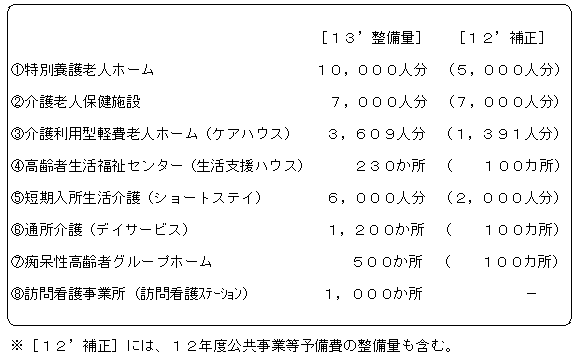
(2)施設整備費補助内容の改善による整備促進【事項要求】
- ・ 特別養護老人ホーム等の連携や地域との交流が確保された単 独型のグループホームに対し補助。
- ・ 新たに一定の要件を満たすNPO法人等の設置するグループ ホームについて、所在地の市町村が助成する事業に対し補助。
- ・ 民家改修型デイサービスが、地域における介護予防事業を併 せ実施する場合に初度設備費を補助。
- ・ 高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)の併設要件を緩 和(介護老人保健施設との併設・隣接及びデイサービスとの隣 接についても対象)。
(3)離島等の介護サービスの確保対策
- (1)離島等サービス確保対策事業
離島等における介護サービスの確保を推進するため、事業者説明会の開催や参入に必要な情報の提供などにより、事業者の参入を推進。
- (2)離島等における訪問介護員養成事業
訪問介護員の供給が困難な離島等における人材確保のための研修を実施。
(4) 在宅福祉事業等の推進
- (1)在宅介護支援センター運営事業
介護予防プランの作成など、介護予防・痴呆介護の拠点としての機能を充実。
- (2)高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業
高齢者の自立した在宅生活を支援するため、高齢者の生活に配慮した設備、構造を有する公営・公団住宅(シルバーハウジング)及び民間の高齢者向け優良賃貸住宅への生活援助員の派遣等を実施。
2.介護サービスの質の向上
(1)身体拘束ゼロ作戦の推進
都道府県においてサービス提供者、利用者代表、行政関係者などをメンバーとする身体拘束ゼロ作戦推進会議を開催するとともに、身体拘束相談窓口を設置。
(2)痴呆介護技術等に関する研究と指導者の養成
- (1)高齢者痴呆介護研究センター運営事業
全国3か所の高齢者痴呆介護研究センターにおいて、痴呆性高齢者の介護技術等に関する研究を推進し、その成果を全国に普及。
- (2)痴呆介護指導者養成事業
痴呆介護技術等の向上を図るため、高齢者痴呆介護研究センターにおける痴呆介護の指導者養成及び都道府県における実務者研修を実施。
(3)介護支援専門員(ケアマネジャー)に対する支援策の充実
- (1)介護支援専門員活動支援モデル事業
介護支援専門員が行う介護サービス計画(ケアプラン)の作成等の業務を支援するため、介護サービス計画の事例の研究、インターネットの活用等による必要な情報の提供を実施。
- (2)介護支援専門員実務研修及び現任研修事業
介護支援専門員の新規養成研修及び現任者の資質向上を目的とした現任研修を実施。
(4)訪問介護サービスの適正な提供等に対する対策
- (1)訪問介護員養成研修円滑化事業等【日本新生特別枠(留保枠)】
利用者のニーズに応じた良質な訪問介護サービスを提供するため、訪問介護員の養成研修における実習の円滑な実施の支援や、訪問介護の適正な実施を図るためのサービス提供責任者に対する研修を実施。
- (2)訪問介護員資質向上事業
現に訪問介護員として活動している3級課程修了者が、適切に身体介護業務に対応できるようにするための資質向上を目的とした2級課程研修を実施。
3.より良い介護保険制度の実現に向けた取組み
(1)高齢者ITケアネットワーク支援事業【日本新生特別枠】
痴呆性高齢者が徘徊した場合に、位置検索から保護までの対応を広域的、一体的に行えるシステムの構築など、市町村のIT化への取組みに対し支援。
(2)要介護認定の仕組みの検討のための事業
一次判定のあり方の検討を行い、要介護認定に係るモデル事業を実施し、その結果を検証。
| III 介護予防・生活支援の推進 |
(13’予算額(案))
596億円 |
|
1.介護予防・生活支援事業の推進
高齢者ができる限り寝たきりなどの要介護状態にならずに自立した生活を送ることができるよう、転倒骨折予防教室、配食サービスなどの介護予防・生活支援策や、家族介護教室などの家族への支援策を総合的に推進。
13年度より新たに、成年後見制度の利用支援や介護予防事業の指導者養成などを実施。
2.高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)の整備の推進(再掲)
常時の介護は必要としないが在宅での一人暮らしが困難な高齢者などが生活する施設として、高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)の整備を推進。
| IV 保健事業の推進 |
(13’予算額(案))
283億円 |
|
1.保健事業第4次計画の着実な推進
生活習慣病などの疾病の予防、早期発見、早期治療を図り、要介護状態になることを防止するため、健康教育、健康相談、健康診査等の保健事業を推進。
2.個別健康教育の充実【日本新生特別枠】
「高血圧」「高脂血症」「糖尿病」「喫煙」の4分野について、老人保健事業の個別健康教育において指導的役割を果たす保健婦等に対する研修を実施。
(参考)
ゴールドプラン21の推進
ゴールドプラン21により、介護保険施設等を計画的に整備
今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)に基づく平成16年度における介護サービス提供量を確保できるよう計画的に整備を行うため、平成13年度においても所要の整備量の確保を図る。
| 区分 |
平成13年度
整備量 |
(参考)
平成16年度
見込量 |
| 特別養護老人ホーム |
10,000人分 |
36万人分 |
| 介護老人保健施設 |
7,000人分 |
29.7万人分 |
痴呆対応型共同生活介護
(痴呆性高齢者グループホーム) |
500か所 |
3,200か所 |
短期入所生活介護/
短期入所療養介護 |
−
6,000人分
(ショートステイ専用床) |
4,785千週
9.6万人分
(短期入所生活介護専用床) |
通所介護(デイサービス)/
通所リハビリテーション(デイ・ケア) |
−
1,200か所 |
105百万回
(2.6万か所)※ |
訪問看護
訪問看護ステーション |
−
1,000か所 |
44百万時間
(9,900か所) |
介護利用型軽費老人ホーム
(ケアハウス) |
3,609人分 |
10.5万人分 |
高齢者生活福祉センター
(生活支援ハウス) |
230か所 |
1,800か所 |
注:平成16年度( )※の数値については、一定の前提条件の下で試算した参考値である。
2 介護保険を巡る最近の動きについて
(1)制度のこれまでの実施状況について
ア 介護保険による在宅サービス利用量の変化
(ア) 制度導入前後におけるサービス利用量の変化
定点市町村(全国108保険者)の1,263人に対する平成12年3月と7月とのサービス量の変化の状況(厚生省実施)
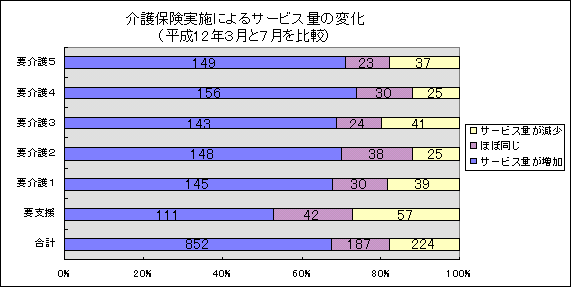
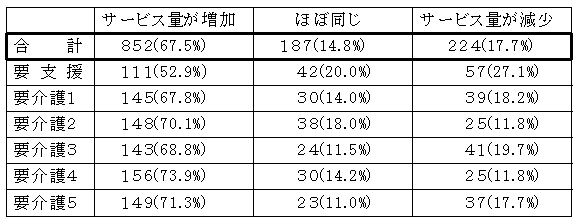
全体の7割近く(67.5%)の人がサービス量が増えており、介護保険の実施によりサービス利用が伸びていることが伺われる。
また、要介護度別にみると、要支援の方にサービス量を減らした方が相対的に多くなっているが、これは、介護保険の実施により、介護の必要度に応じて給付がなされることとなった結果と考えられる。
(参考)介護サービス量が減った理由
(「減った」と回答した224人についての調査:複数回答あり:単位(人))
| 理由 |
人数 |
割合 |
全体割合 |
| (1) これまで受けていたサービスが現在の利用限度額を超えていたため |
25 |
11.0% |
2.0% |
| (2) 短期入所を緊急時のための取っておくため |
11 |
4.9% |
0.9% |
| (3) サービス事業者が予約でいっぱいだったため |
2 |
0.9% |
0.2% |
| (4) 家族との同居等により、これまでほどはサービスが必要でないため |
10 |
4.5% |
0.8% |
| (5) 利用者負担を支払うのが困難だったため |
32 |
14.3% |
2.5% |
| (6) 利用者負担は支払えるが、従来受けていたサービスが必ずしもすべて真に必要なサービスではないと考えたため |
35 |
15.6% |
2.8% |
| (7) その他(本人の状態の回復、入院のためなど) |
40 |
17.9% |
3.2% |
| (8) 回答なし |
81 |
36.2% |
6.4% |
(注)「割合」はサービスが減った人に対する割合、「全体割合」は調査対象全体に対する割合
調査対象(1,263人)のうち、「利用料負担を支払うのが困難だったため」と回答した方は32人(2.5%)と少なくなっている。
(イ)介護保険実施による新たな利用者の増加状況
各自治体が実施した調査によれば、介護保険の実施により、新たな利用者が3割から5割程度増加しているとの結果が出ており、サービス利用の裾野がかなり拡がっていることが伺われる。
(利用者の内訳)
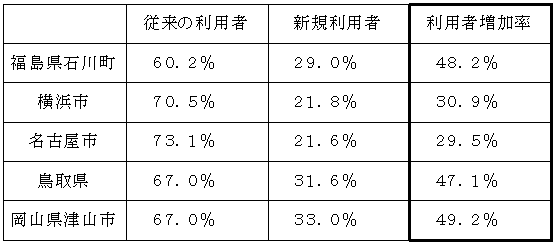
また、介護保険実施後も要介護・要支援認定者数の伸びが見られる。
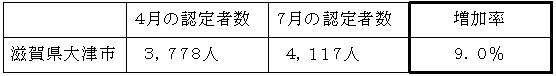
(ウ) サービス利用量の伸びの状況
各自治体が実施したサービス利用量の調査によれば、介護保険の実施により、サービスの利用量は、かなり伸びていることが伺われる。
また、制度実施後も、制度内容が利用者の間に浸透するに伴い、サービス利用量の増加が見られる。
a.兵庫県神戸市の調査
平成12年3月から7月までの月毎のサービス利用量の推移
| |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
| 訪問介護(利用時間) |
65,155 |
84,114 |
99,711 |
126,436 |
132,866 |
| 訪問看護(利用回数) |
10,976 |
11,486 |
12,143 |
15,094 |
14,285 |
| 通所介護(利用回数) |
23,620 |
24,161 |
26,390 |
32,531 |
33,291 |
| 短期入所生活介護(利用日数) |
18,250 |
10,818 |
12,294 |
12,183 |
12,641 |
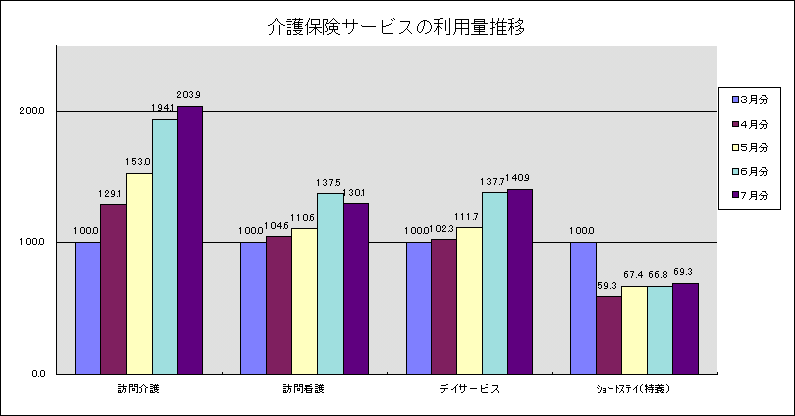
(注)3月を100とした場合のサービス利用量の状況
b.千葉県の調査
介護保険の導入前後による利用回数の比較
| |
介護保険導入前 |
介護保険導入後 |
| 訪問介護(利用回数) |
100 |
167.7 |
| 訪問看護(利用回数) |
100 |
171.9 |
| 通所介護(利用回数) |
100 |
150.9 |
| 通所リハビリ(利用回数) |
100 |
155.8 |
(注)千葉県内市町村における要介護者948人抽出による週当たり利用回数調査。
c.山形県の調査
前年同期比では、短期入所サービスを除いて利用が順調に増加しており、また、4月以降は、短期入所サービスも含めて利用が増加してきている。
(サービス利用の増加率)
| |
平成12年4月から7月までと
平成11年(同期)との比較 |
平成12年4月と7月との比較 |
| 訪問介護(利用回数) |
140.5% |
117.6% |
| 訪問入浴(利用回数) |
118.1% |
109.1% |
| 訪問看護(利用回数) |
105.3% |
102.2% |
| 通所介護(利用延人数) |
131.4% |
111.7% |
| 通所リハビリ(利用延人数) |
111.6% |
109.8% |
| 短期入所生活介護(利用延人数) |
73.2% |
126.4% |
| 短期入所療養介護(利用延人数) |
48.8% |
118.9% |
| 福祉用具貸与(件数) |
− |
137.8% |
(注)山形県内の238事業者を対象とした調査。
d.岩手県の調査(保険料段階別)
制度施行前と平成12年7月とサービス利用量の比較(月当たり利用回数)
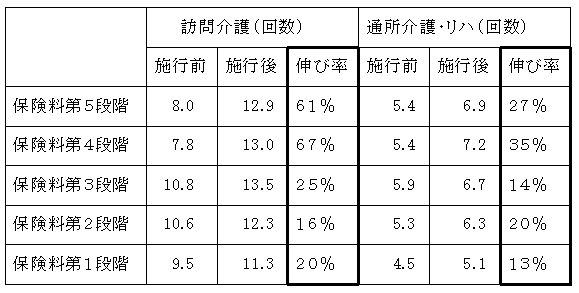
(注)岩手県内の訪問介護(545人)、通所介護・リハ(939人)に対する調査
サービス利用料の伸びを保険料の所得段階別にみた場合には、所得段階に 関係なく全体的に伸びているが、従来措置制度の下でサービスをほとんど利用していなかった所得が相対的に高い層のサービスの伸びが大きくなっている。
〇 訪問介護の利用回数の伸び率
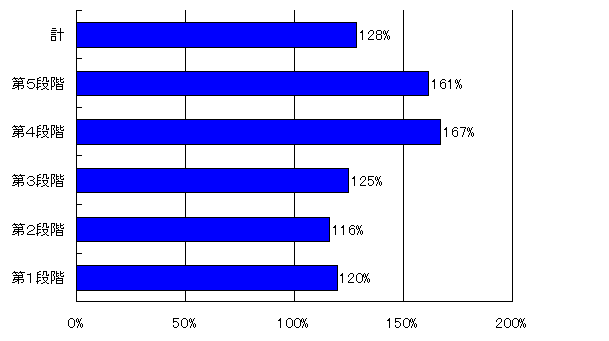
〇 通所介護・通所リハビリの利用回数の伸び率
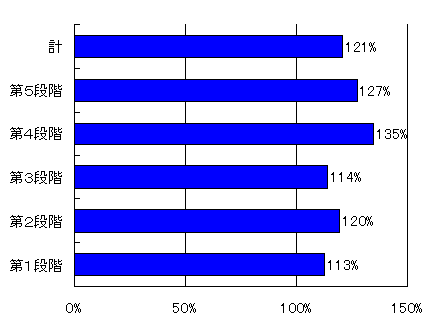
※ 第1段階から第5段階は第1号保険料の賦課区分
イ 在宅サービスの利用状況(支給限度額に対する利用割合)
(ア) 定点市町村を対象とした支給限度額に対する利用状況調査
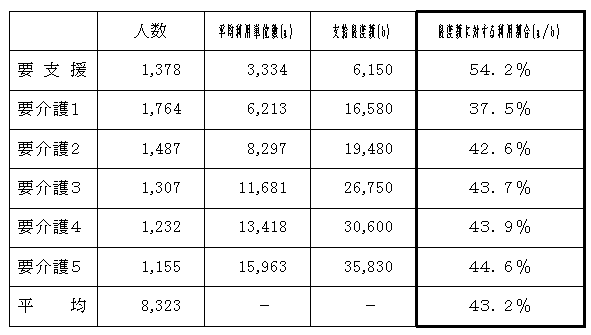
| 注1 |
106保険者(定点市町村)8,323人についての調査
(ケアプラン無作為抽出方式。原則として平成12年7月サービス分の調査) |
| 注2 |
「平均利用単位数」は、訪問通所サービスと短期入所サービスの合計の平均 |
(考え方)
- a.在宅サービスの支給限度額は、在宅重視を基本理念として、現在のサービス水準をかなり上回る水準で設定(ドイツの介護保険よりも高い水準のサービスレベルを保障)。
- b.実際の利用割合は、本人の希望やサービスの供給量によって決まり、今後の制度の定着状況やサービス供給量の増加により、将来的に増加することが予想される。
- c.平成12年度予算の在宅サービスの利用見込みは、サービスを全く利用しない人を含め支給限度額に対する利用割合を約33%と設定。上記43.2%はサービスを利用する人の数値であり、それらを勘案すれば、在宅サービスの利用割合は当初の見込みどおり増加しているものと推定。
(イ) 家族構成と支給限度額に対する利用割合の関係(山形県調査)
家族構成で見ると、一人暮らし、老人夫婦世帯、子ども同居等の順に利用率が高くなっている。
| 世帯構成 |
限度額に対する利用割合 |
| 一人暮らし |
50.1% |
| 老人夫婦世帯 |
44.1% |
| 子ども同居等 |
36.9% |
| 平均 |
39.5% |
(注)山形県内の742名を対象とした調査(本年6月サービス利用分)。
(ウ) 要介護度分布と支給限度額に対する利用割合の関係
a.滋賀県大津市調査
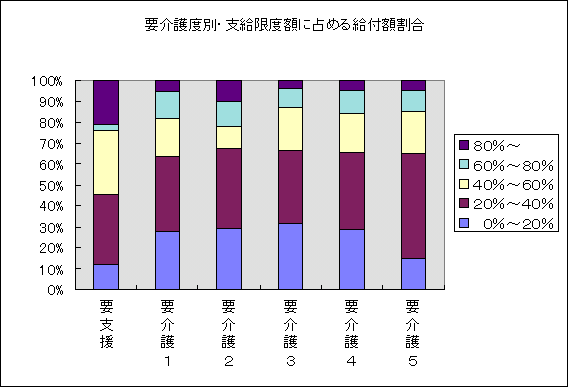
| |
要支援 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
| 80%〜 |
7人 |
3 |
6 |
2 |
2 |
1 |
| 60%〜80% |
1 |
7 |
7 |
5 |
4 |
2 |
| 40%〜60% |
10 |
10 |
6 |
11 |
7 |
4 |
| 20%〜40% |
11 |
20 |
22 |
19 |
14 |
10 |
| 0%〜20% |
4 |
15 |
17 |
17 |
11 |
3 |
| 合計 |
33 |
55 |
58 |
54 |
38 |
20 |
b.岩手県調査(平成12年9月)
| 限度額に対する利用割合 |
利用者の割合 |
| 0%から25%まで |
50% |
| 25%から50%まで |
33% |
| 50%から75%まで |
10% |
| 75%以上 |
7% |
c.鳥取県調査(平成12年8月)
- (a) 利用限度額に対するサービス利用の割合
| 限度額に対する利用割合 |
構成比 |
| 7割以上 |
19.4% |
| 5割以上7割未満 |
9.9% |
| 5割未満 |
34.8% |
| わからない |
25.2% |
| 無回答 |
10.7% |
- (b) 利用限度額に対する利用額の割合が7割未満の場合の理由
| 理 由 |
構成比 |
| 必要がない |
60.3% |
| 利用料が高い |
11.6% |
| 利用したいサービスがない |
6.0% |
| その他 |
11.7% |
| 無回答 |
10.4% |
(エ)介護保険導入による在宅サービス利用者・家族の状況の変化
a.要介護者本人の効果
- (a)「要介護者に意欲が出てきた」と回答している人の割合
| 札幌市 |
群馬県 |
相模原市 |
>伊丹市 |
>熊本市 |
| 16.0% |
17.2% |
11.9% |
18.1% |
27.0% |
- (b)「引き続き在宅生活を送れるようになった」と回答している人の割合
| 群馬県 |
相模原市 |
伊丹市 |
| 24.9% |
15.6% |
22.9% |
b.家族への効果
「介護者が楽になった(介護負担が減った)」と回答している人の割合
| 札幌市 |
群馬県 |
相模原市 |
伊丹市 |
熊本市 |
| 42.6% |
49.0% |
37.2% |
42.2% |
41.0% |
(オ)利用者と事業者の関係
a.利用者が事業者を選ぶ基準
現時点では、「制度前からサービスを受けていたところに頼んだ」とする者が多い。
- (a)熊本市の調査(複数回答あり)
| 制度前からサービスを受けていたところに頼んだ |
71.8% |
| ケアマネジャーの意見を参考にした |
19.6% |
| かかりつけ医の意見を参考にした |
15.0% |
| 知人の評判を参考にした |
6.0% |
| いくつかの事業者から話を聞いてみた |
1.7% |
| 新聞やテレビの広告を参考にした |
0.6% |
| その他 |
12.0% |
- (b)滋賀県草津市の調査(複数回答あり)
| サービスの内容 |
15.9% |
| 事業者の知名度 |
6.1% |
| 事業者の信用 |
11.8% |
| 利用者の評判 |
6.4% |
| サービス事業所の場所 |
15.8% |
| 職員の技術や訓練の程度 |
6.3% |
| 職員の態度 |
13.3% |
| 利用者負担額 |
4.6% |
| 今まで利用していた事業所 |
18.1% |
| その他 |
1.5% |
b.サービスの苦情・要望の言い易さなど
熊本市の調査によれば、不満や要望を介護サービス事業者に直接言えるかどうかについては、「言えると思う」、「少しは言えると思う」と回答した者が全体の約3/4を占めている。
| 言えると思う |
55.7% |
| 少しは言えると思う |
18.5% |
| どちらとも言えない |
4.7% |
| あまり言えないと思う |
12.2% |
| 言えないと思う |
7.3% |
| その他 |
1.6% |
ウ 介護サービス事業者の参入状況
在宅サービス事業者の参入は4月以降も進んでおり、全国的にみたサービス事業所の総数は増加している。
一部の民間事業者にサービス拠点を削減する動きがあるが、従来から地域に密着して利用者との信頼関係を築いてきた事業者は、着実に事業を実施している。
| |
12年4月 |
12年7月 |
12年11月 |
| 訪問介護 |
9,185件 |
12,960件 |
13,349件 |
| 通所介護 |
5,621件 |
7,832件 |
8,221件 |
| 福祉用具貸与 |
2,585件 |
3,894件 |
4,604件 |
| 居宅介護支援 |
19,466件 |
21,852件 |
22,015件 |
(注)WAM−NET掲載ベースの4月1日、7月1日及び11月4日の比較
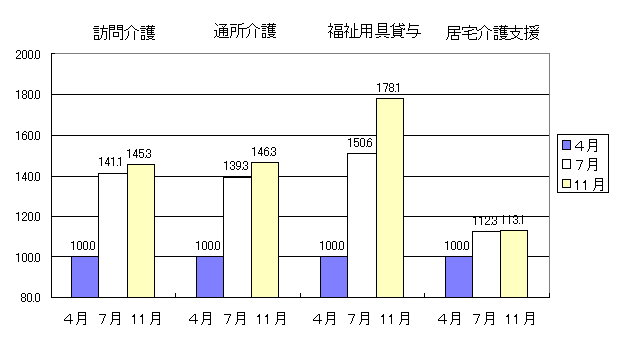
4月を100とした場合の指定事業者数の伸び率
エ 介護給付費の支払状況(暫定集計値)
(単位:億円)
| サービス提供月 |
4月分 |
5月分 |
6月分 |
7月分 |
8月分 |
| 在宅サービス |
600 |
820 |
960 |
1,000 |
1,020 |
| 施設サービス |
1,540 |
1,900 |
1,980 |
1,970 |
2,030 |
| 合計 |
2,140 |
2,720 |
2,940 |
2,970 |
3,050 |
(注1)
各国保連の支払実績として1割の利用者負担を除く介護給付費(9割分)を集計したもの。
(注2)
福祉用具購入費、住宅改修費などの市町村が直接支払う費用を除く。
(1) 請求・支払状況が安定してきた6月から8月分の給付実績を平成12年度予算上の1月当たりの単純平均と比較すると、9割弱の水準。
(在宅サービス約8割、施設サービス9割強)
(2) 制度施行後、在宅サービスの給付費は着実に伸びており、施設サービスもやや増加傾向。
(3) 給付実績の推移などからすると、今後、年度全体では平成12年度の予算の見込みにかなり近づく見通し。
(2)当面の課題への対応について
ア 高齢者保険料の減免問題
- (1) 一部の市町村において、災害などの特殊な事情の場合以外に、低所得者である高齢者(第一号被保険者)の保険料を単独で減免する動きがある。(平成12年10月1日現在で保険料の単独減免を実施している市町村数は72)
- (2) 介護保険制度は、介護を国民皆で支え合おうとするものであり、保険料を支払った者に対して必要な給付を行うものであることから、
- (ア)保険料の全額免除
- (イ)資産状況等を把握しない一律の減免
- (ウ)保険料減免分に対する一般財源の繰入れ
- は、適当でないと考えている。
なお、保険料の単独減免を行った市町村については、財政安定化基金の交付の対象とはしていないが、貸付の対象としているところである。
イ 利用者負担の低所得者対策
低所得者の利用者負担については、既に、負担月額の上限についての特例措置や、訪問介護利用者の経過的措置などを実施するほか、社会福祉法人が利用者負担を減免する措置が講じられているが、この措置が全国的に十分に浸透していない状況にあることから、以下の取り組みを実施したところであり、この減免措置の市町村における積極的な取り組みにご配慮願いたい。
- (1) 全国的な実施の推進(社会福祉法人への協力要請を含む。)
- (2) 対象となる低所得者の範囲を被保険者の(2%から)1割程度へ拡大
ウ 訪問介護の家事援助の取扱い
訪問介護の家事援助の取扱いについては、平成12年9月に与党より保険給付として適切な範囲を逸脱した家事援助の是正についての方策が示され、これを受けて国としても(1)リーフレットの作成・配布による周知徹底(2)ケアプランへの家事援助の必要性の記載(3)ケアマネジャーへの研修等、引き続きその改善方策を推進することとしているので、各都道府県においても、訪問介護の適正な取扱いについて、各市町村、居宅介護支援事業者、訪問介護事業者及び要介護者等に対して引き続き周知徹底が図られるようお願いする。特に今般国において作成したリーフレットについて、要介護者、要支援者や居宅介護支援事業者、訪問介護事業者への配布に格別の御協力をお願いするとともに、必要に応じて個々の事業者による家事援助や、身体介護等のサービス提供の状況について実態把握を行ってその情報を提供するなどによって、訪問介護の適正な利用や、利用者の状態の改善につながるようなサービス提供に資するようご配慮をお願いする。
なお、平成13年度において、訪問介護サービスの適正な提供を確保する観点から、訪問介護計画の作成などの重要な役割を担うサービス提供責任者を対象とした研修事業に対する補助を行うこととしているので、本事業の実施についてもご配慮願いたい。
あわせて、訪問介護員の養成研修についても、実習受入れ部分が必ずしも円滑に行われていない現状に鑑み、平成13年度予算において新たに「訪問介護養成研修円滑化事業」を行うこととしている。具体的には、各都道府県において、実習受け入れ施設・同行訪問受け入れ事業者を把握の上、リストを作成し、公示を行うことにより適切かつ円滑な研修事業の実施を推進し、適正な訪問介護員の確保を図ることとしている。
エ いわゆる介護タクシーの取扱い
介護保険制度において、訪問介護の指定を受けたタクシー会社が、通院介助等を行った場合には、
- ・自宅の部屋からタクシーまでの間、と
- ・目的地(病院等)到着後タクシー降車から院内等への付添い
までは、介護保険の給付対象(身体介護中心型)となるが、
- ・自宅から目的地(病院等)までの運送中
は、運転に専念することになり、また、運転は訪問介護に該当しないため、介護保険の給付対象とならない取扱いをしているところである。
介護保険制度上、移送は介護保険の給付対象となっていないので、運転中を介護報酬の対象とすることはできない。他方、運転中の運賃をとるかどうかは道路運送法の問題であるが、厚生労働省としては、介護タクシーには、
- (1) 介護タクシーによって提供されるサービスは、タクシーへの乗降の手伝いにとどまらず、それのみを切り離して、介護サービスとして独立に評価し得るようなものかどうか、
- (2) 訪問介護は、入浴、排せつ、食事など様々な日常生活上の世話を提供すること を前提としているにもかかわらず、もっぱらタクシーの乗降時の移動介助に事実 上特化しているとみられ、訪問介護事業の在り方として適切といえるのか、
- (3) また、ほとんど乗降時の移動介助しか行われていない場合の単価としては、介 護報酬の水準が高すぎるのではないか、
などといった問題があると考えている。
このような問題意識から、10カ所の都道府県において、介護保険の指定を受けたタクシー会社による介護サービス提供の実態把握を行っていただいたところであるが、今後、この実態把握の結果を踏まえて必要な対応を検討した上で、対処方針をお示ししたいと考えているので、ご留意願いたい。
オ 訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化
- (1) 短期入所サービス(ショートステイ)が利用しにくいとの指摘があり、これについては、昨年3月に講じた振替措置及びその受領委任化により、相当程度解決したが、利用者の利便性や選択性を向上する観点から、両サービスの支給限度額について一本化を図り、同じ支給限度額の中でいずれのサービスも利用できる措置とすることを決定したところである。
実施時期については、市町村等の準備期間等を考慮し平成14年1月としており、その準備について特段のご配慮をお願いしたい。
- (2) 平成14年1月までの間についても、本年1月から、上記振替措置における限度日数(1月当たり2週間)を、訪問通所サービスの利用枠の範囲内で30日まで拡大したところであり、市町村における取り組みを促していただくようご配慮願いたい。
カ 介護サービスの質の向上
- a 身体拘束廃止に向けての取り組み
- 介護保険法の施行に伴い、身体拘束が原則として禁止され、また、ゴールドプラン21においても、これを踏まえた質の高い介護サービスを実現することとされたが、その趣旨を徹底し、実効をあげていくためには、現場において身体拘束を廃止するための努力を重ねるととともに、それを関係者が支援していくことが重要である。
このため、身体拘束の廃止を実現するための幅広い取り組みを「身体拘束ゼロ作戦」として取りまとめ、関係者の協力の下で推進しているところであり、厚生労働省としては、昨年6月に第1回身体拘束ゼロ作戦推進会議を開催したほか、現在、当該会議に分科会を置き、介護現場用及び都道府県における指導用のマニュアルの作成や車いすなどのハード面の改善についての検討を進めているところである。マニュアルについては、作成後、幅広く情報提供する予定であるので、介護保険施設等の現場関係者や行政担当者等への普及や周知徹底について特段のご配慮をお願いしたい。
また、各都道府県においては、平成12年度はモデル的に18都道府県で開催する推進会議を来年度は全県で開催していただくほか、介護の専門家などが施設等の介護担当者や利用者(家族)の相談に応じ、身体拘束を廃止していくためのケアの工夫等について具体的な助言・指導を行う「相談窓口」の設置や、介護相談員や在宅介護支援センターの職員等を対象とする研修の実施等により、現場における取り組みを積極的に支援していただきたい。
- b 介護サービス評価についての取り組み
- 利用者による事業所の選択に役立つような評価の手法等を検討することを目的として、「介護保険サービス選択のための評価の在り方に関する検討会」を開催しており、平成12年11月2日に第1回、12月18日に第2回を開催したところである。
検討会においては、本年度は、訪問介護及び訪問看護を中心として、利用者がサービスを選択する際にどのような情報がポイントであるのかを整理し、事業者からの情報提供や自他のサービス利用を通じて得た情報を材料に、主として利用者自身が活用するための「チェックリスト」の作成を検討しており、今後、第3回検討会(2月下旬を目途に開催)において、チェックリストの原案をもとに議論を行う予定である。
チェックリストの性格としては、これを参考に、地方自治体、事業者団体等が独自に項目を工夫したり、利用者以外の者が活用したりすることも当然可能であり、また、今後のサービス利用の状況等に応じて適宜見直しを行うものという位置付けとする方向であるが、いずれにしても、地方自治体、事業者団体等における独自の取組みを妨げるものではないのでご承知願いたい。
- c 介護相談員の推進に向けた取り組み
- 介護保険法の施行に伴い、高齢者における介護サービスの利用は、従来の措置を中心としたサービス利用から、契約によるサービス利用へと大きく変わった。この新たな仕組みが「利用者本位」の仕組みとして定着するためには、高齢者が自分自身のニーズに合ったサービスを適切に選択し、利用できるような環境を整備することが重要である。
介護相談員派遣等事業は、上記の目的から平成12年度に創設されたものであり、介護相談員が現場を定期又は随時に訪問し、気軽な雰囲気の中で介護サービス利用者の介護サービス等に関する疑問や不満に対してきめ細かに応じることにより、苦情に至る事態を未然に防ぐとともに、介護相談員が市民の目を通してサービスの実態等を把握し、市町村に提言を行うことなどにより、介護サービスの質の向上や市町村の介護保険行政の円滑な運営、さらに介護問題にとどまらない「地域づくり」にもつながる効果が期待されるものである。
本年度は、全国160の市町村で実施されることとなっているが、平成13年度予算(案)においても所要の経費を計上し、本事業を実施する市町村に対する支援に万全を期すこととしているので、各都道府県においても積極的な対応をお願いしたい。
キ 介護支援専門員(ケアマネジャー)に対する支援策
介護保険制度の要である介護支援専門員に対する支援体制の整備は喫緊の課題であり、厚生労働省においても、引き続き各般の支援施策に取り組んでまいるので、各都道府県においても、資質向上を目的とした現任研修の実施や支援会議の開催、あるいは各市町村に対し、介護予防・生活支援事業による短期入所振替利用援助事業や住宅改修の理由書作成に係る補助の活用を促すなど、所要の支援施策について積極的に取り組んでいただくようお願いする。
国としても、ケアプランの成功例を収集してお示ししたいと考えているので、これらについてもご活用をお願いしたい。
また、平成13年度予算において、介護支援専門員が行う介護サービス計画(ケアプラン)の作成、関係者との連携等介護支援専門員の業務を円滑かつ効果的に行うため、介護サービス計画事例研究等の先駆的な取組みを行う都道府県に対して、2年間のモデル事業(「介護支援専門員活動支援モデル事業」)を新たに行うこととしているが、本事業の採択については個別にヒアリングを実施する予定であるのでご承知願いたい。
なお、第4回実務研修受講試験については、平成13年11月11日(日)を予定しているが、各都道府県においては会場確保等の所要の準備について適切かつ滞りなく努められたい。
ク 介護保険施設における保険外負担について
介護保険施設等における保険外負担については、先般、「介護保険施設における日常生活費等の受領について」(平成12年11月16日老振第75号、老健第122号)において、保険外負担の受領に係る同意については、保険外負担サービスの内容及び費用の額を明示した文書に利用者等の署名を受けることなどをお示したところであるが、その取扱いにつき、適正な実施が図られるよう一層指導を徹底されたい。
なお、平成12年11月16日の全国都道府県担当課長会議でもご紹介したように、一部の市町村において、地域のサービス事業者の保険外負担の内容、金額を調査し、当該情報をパンフレット等により紹介し、利用者の選択に役立てている事例もあり、このような取組みについても参考にされたい。
ケ 要介護認定のあり方の検討
- (ア)要介護認定調査検討会について
- 要介護認定における一次判定については、(1)痴呆性高齢者が低く評価されているのではないか、(2)在宅における介護の状況を十分に反映していないのではないか、などの指摘があることから、昨年8月に「要介護認定調査検討会」を設置し、一次判定の仕組みについて専門的・技術的な検討を行っている。
本検討会での議論を踏まえ、本年2月〜3月に全国で「高齢者介護実態調査」を行うこととしているので、協力をお願いしたい。
なお、本調査の結果をもとに、さらに本検討会でご検討いただいた上で、来年度には自治体の協力をいただきながらモデル調査を行うなど、具体的な検討を行っていく予定である。
- (イ)要介護認定二次判定変更事例集について
- 要介護認定における最終判定は二次判定であることから、その重要性に鑑み、全国の都道府県の協力を得て、二次判定において一次判定の結果を変更した事例をとりまとめ、要介護認定二次判定変更事例集を作成した。
これは、要介護度の変更にいたる検討過程や変更理由を可能な限り明らかにして全国の関係者間で共有することにより、今後の審査判定の運用の一層の明確化をはかるための参考資料を提供しようとするものである。
さらに、事例の取りまとめに際し、要介護認定において留意すべき事項をまとめたので、今後ともより適正な要介護認定業務を実施されたい。
- (ウ)更新認定における有効期間について
- 更新認定における有効期間については、原則6月間としながらも、市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合には、3月間〜12月間の範囲内で有効期間の延長又は短縮を可能としているが、延長・短縮を行った事例を収集し提示した。
申請者の状態が安定して継続すると判断できる場合には、有効期間の延長について事務局から認定審査会に対して意見を求めるなど、延長の是非について検討されたい。
- (エ)認定調査員等研修事業について
- 認定調査員等研修事業については、都道府県において実施しているところであるが、例えば、痴呆性高齢者の要介護度が適正に評価されるためには、(1)一次判定の基礎となる調査票の記入に際し、痴呆症状に随伴する身体の状況等に関し適切な記入が行われること、(2)問題行動等、介護の度合いに影響を及ぼす事項に関しては、認定調査時のみならず、日頃の介護の状況が反映されるよう特記事項として記入することも重要であることなど、当研修事業等により一層指導を徹底されたい。
コ 福祉用具及び住宅改修の取扱い
福祉用具は、要介護者自身にとって役立つというだけでなく、腰痛予防等介護者の負担軽減も図られるなど、介護を支えていく上で極めて重要な役割を果たし得るものである。また、在宅生活を継続したり、福祉用具を効果的に活用したりするためには、住宅のバリアフリー化等の住環境の整備を行う必要もあることから、福祉用具の活用と住宅改修は有機的に関連づける必要がある。
ついては、福祉用具及び住宅改修の普及について、下記の点に留意し、積極的な取組みを願いたい。
あわせて、福祉用具や住宅改修に関する利用者への適切な助言やそれらの活用を促進することを目的に、介護支援専門員等を対象とした研修を都道府県・指定都市が行えるよう、新たに「介護サービス適正実施指導事業」の「福祉用具・住宅改修研修事業」として計上したので、その円滑な実施についてご配慮を願いたい。
- a 福祉用具について
- 介護保険制度においては、利用者が自ら選択して福祉用具の貸与を受け、又は購入をすることとなったところであるが、利用者が福祉用具を選択するためには、実際に見たり、触れたりすることや住環境の整備について考慮する必要がある。こうしたことから、介護実習・普及センターや在宅介護支援センターにおける福祉用具の展示や相談等を通じ、情報提供を積極的に行う必要があるので、各市町村への助言及び援助を引き続き積極的に行われたい。
また、法施行当初は、車いす及び特殊寝台の付属品については、本体と一体的に貸与される場合に限って貸与が可能であったが、平成12年12月以降、付属品単独での貸与も可能となったので、引き続き市町村、利用者等に対し周知方お願いする。
なお、福祉用具に関する情報収集や企業情報の提供等については、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」に基づく国の指定法人である(財)テクノエイド協会においても行われているので、積極的に活用されるようお願いする。
- b 住宅改修について
- 介護保険制度においては、可能な限り在宅で自立した日常生活が営めるよう、手すりの取付け等住宅改修を在宅サービスとして位置づけたところである。
法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修費の支給が可能となったので、引き続き市町村、利用者等に対し周知方お願いする。
(3)介護保険事業(支援)計画及び老人保健福祉計画の見直しについて
ア 見直しの基本方針について
- (1) 計画の見直しの時期等
- 介護保険事業(支援)計画は、5年を1期とするものであるが、その見直しについては、3年ごとに行うこととされており、各自治体におかれては、見直し後の第2次介護保険事業(支援)計画(平成15年度〜平成19年度)については、平成14年度中に作成を完了させるとともに、介護保険事業(支援)計画と調和が保たれるよう老人保健福祉計画の見直しについても併せて行うことになる。
また、見直しの過程において、前回の計画策定時と同様に、介護サービス量等の見込量に係る中間集計を平成14年度の一定時点において国にご報告いただくことを予定としているので、別途指示する報告時期及び報告事項等に基づく報告について御協力願いたい。
- (2) 計画の見直しに係る基本的な考え方等
- 平成12年から介護保険制度が開始され、今回初めての見直しの時期に当たることから、今後、計画の見直しに係る基本的な考え方等について幅広い観点から検討を進めることとしており、その中で、各自治体の意見を求めていきたいと考えているので、御協力願いたい。
イ 高齢者保健福祉計画行政情報システムについて
- (1) 老人保健福祉サービス利用状況地図(老人保健福祉マップ)数値表の終了
- 平成元年より実施してきた老人保健福祉マップについては、新ゴールドプランの終了とともに、その役割を果たしたことから平成12年版(平成11年度実績)の作成をもって終了することとする。
- (2) 高齢者保健福祉計画行政情報システムの構築
- 平成12年度からは、介護保険制度が開始されたことにより、各自治体において介護保険事業(支援)計画及び老人保健福祉計画を策定し、当該計画に基づき各自治体において介護サービスの提供を行っているところである。
今後は、介護保険制度開始以降の老人保健福祉計画及び介護保険事業(支援)計画の進捗状況や一定の仮説を前提にした介護保険事業による事業の効果及び介護サービス量の見込量の推計などを行うことができる「高齢者保健福祉計画行政情報システム」を構築し、各自治体における老人保健福祉計画及び介護保険事業(支援)計画の見直しに係る支援を行うこととしている。
- (3) 老人保健福祉計画等統計調査の変更
- 平成13年度に構築する「高齢者保健福祉計画行政情報システム」において必要となる情報については、既存の各種統計調査等における情報からの流用の外、平成6年度より実施している「老人保健福祉計画等統計調査」の調査項目を大幅に見直した上で、調査を依頼することとしている。
当該調査における調査項目は、各自治体の老人保健福祉計画及び介護保険事業(支援)計画の分析や検証にも必要であると考えられる部分も多くあるものと認識していることから、調査の実施に当たっては、各都道府県はもちろんのこと管下市町村等の御協力が必要不可欠であることから、情報の収集・集約にご協力いただきたい。
(参考資料)
高齢者保健福祉に係る基盤整備等の状況
(4)介護保険に関する今後の広報について
ア 国における広報活動
昨年4月に施行された介護保険制度も1年が経ち、さらに国民各層に対して制度の積極的なPRを推進するため、介護保険シンポジウムを開催するほか、新聞・雑誌等の活用による広報活動を実施することとしている。
介護保険シンポジウムの開催について(案)
| (1)趣旨: |
介護保険を1周年を契機に、介護保険の1年を振り返るとともに、今後を展望し、介護保険に対する理解を促進する。 |
| (2)主催: |
(財)長寿社会開発センター |
| (3)日時: |
平成13年3月23日(金) |
| (4)場所: |
新高輪プリンスホテル |
| (5)内容 |
(演題は予定・出演者未定) |
-
| 10:30〜12:30 |
パネルディスカッション(120分)
「介護保険の1年を振り返る」 |
| 13:30〜14:30 |
特別講演(60分) |
| 14:45〜16:45 |
分科会(120分)
○第1分科会
「質の高い介護サービスを目指して」
○第2分科会
「介護予防と地域の取り組み」
○第3分科会
「痴呆性高齢者とこれからの介護のあり方」
○第4分科会
「介護保険と地方分権」 |
|
イ 都道府県・指定都市における広報活動
本年10月から第1号被保険者の保険料が本来額の徴収となることなどを踏まえ、各都道府県及び市区町村においても、さらに介護保険制度に対する住民の理解促進が図られるよう積極的な広報活動を実施していただきたい。
3.介護保険施設等に対する指導等について
1.介護保険施設等の適正な運営の確保
介護保険施設等に対する指導・監査は、介護保険施設等が介護を要する高齢者にその心身の状況等に応じた適切な介護サービスの提供を行うとともに、その能力に応じて自立した生活を営むことができるよう支援することを目指すものであることから、その目的に沿った適正な運営が行われるよう、適切かつ効果的に行っていく必要がある。
しかしながら、平成12年4月の制度発足以降、適切な介護サービスの提供に積極的に取り組むとともに、適正な介護給付の請求に努めている介護保険施設等がある一方、施設整備に絡む不正、不適切な介護サービスの提供、不正な介護給付費の請求など、極めて憂慮すべき不祥事が起きており、そのうち全国で3件の指定取消が12月末までに行われたところである。
このため、特に次の点に留意して今後の指導・監査を実施されるよう特にお願いしたい。
ア 都道府県・保健所政令市等における指導体制の確立
各都道府県・保健所政令市等にあっては、介護保険施設等に対して、より実効のある指導・監査ができるような本庁の指導・監査体制の確立に努めるとともに、介護保険サービスの質の確保、介護給付の適正な確保の観点から、関連する社会福祉法人監査担当部門、老人福祉監査担当部門、医療監視担当部門、医療保険監査担当部門等との連携を緊密に図ること。
また、指導・監査にかかる事務を福祉事務所等本庁以外の機関に委任又は委任を予定している都道府県・保健所政令市等にあっては、指導方針、指導内容等について各担当者が共通認識のもとに統一的な実施が図られ指導に差異が生じないよう十分留意するとともに、当該実施機関による指導結果等についても的確な把握に努め、その内容を十分精査分析した上で、必要に応じ当該実施機関に対し十分な指導を行うこと。
さらに、指定等事務部門と指導・監査担当部門が異なる都道府県及び保健所政令市にあっては、指定事業者について是正改善の指導を行う場合には、当該都道府県の指定等部門と十分な連携を図ること。
(2)適切な指導・監査の実施
介護保険施設等の指導・監査に当たっては、利用者保護の観点から適正な運営の確保について万全を期する必要があるが、不正請求、不当なサービス提供が疑われる介護保険施設等や指導に基づく是正改善事項について改善措置が講じられない介護保険施設等に対しては、介護保険法に基づく厳正な監査を実施し、悪質な不正等の事実が認められる場合には、不適切な事業者を排除する観点から、指定取消など厳正な対処を行うこと。
なお、制度発足後間もないこともあり、また、全国的に整合性のとれた指導・監査の実施を確保する観点から、指定取り消し等の介護保険法に基づく行政処分の必要性が考えられる場合には、速やかに介護保険法第197条第2項の規定に基づく報告を当室あてに行うようお願いしたい。
2.国における指導体制について
本年1月6日付けで厚生労働省の地方支分部局として全国7カ所の地方厚生局が発足したところから、平成12年5月12日付老人保健福祉局長通知において示した指導指針に基づく国の各都道府県・保健所設置市等との合同指導にあっては、別紙のとおり、本省及び地方厚生局において業務の役割を分担し、実施することとしたので留意されるとともに今後ともそれぞれの部署と十分な連携と協力をお願いしたい。
なお、13年度から本格的に合同指導を実施することとしているが、その詳細な時期、方法等については、2月に開かれる課長会議において示す予定としているので了知されたい。
本省・地方厚生局の業務分担
| 事項 |
本省 |
地方厚生局 |
介
護
保
険
指
導 |
介護保険の都道府県本庁に対する指導
地方自治法第245条の4
…助言・勧告、資料の提出の要求
地方自治法第245条の5
…是正の要求 |
・本庁における介護保険事務(指定事務及び指導監査事務を除く)の実施状況について指導を実施 |
・実施しない |
介護保険の市町村(保険者)に対する指導
介護保険法第197条第1項
…報告の徴収
地方自治法第245条の4
…助言・勧告、資料の提出の要求
地方自治法第245条の5
…是正の要求 |
○合同指導
・政令指定都市を対象に指導を実施 |
○合同指導
・中核市、保健所政令市、特別区(23区)、広域連合等を対象に指導を実施
・保険料収納率が悪化している市町村(保険者)等を対象に指導を実施 |
介
護
サ
|
ビ
ス
指
導 |
都道府県知事に対する介護保険の指定事務等に関する指導
介護保険法第197条第2項
地方自治法第245条の4,5 |
・本庁における指定事務及び指導監査事務の実施状況にについて指導を実施 |
・実施しない |
介護サービス事業者等に対する指導、被保険者に対する質問、指導
介護保険法第24条第1項、第2項 |
○特別合同指導
| 全国的に影響の大きいと考えられる広範囲で活動を行うサービス事業者等又は特に重点指導を必要とするサービス事業者等について行うもの |
(1)全国的に広範囲で活動を行うサービス事業者等を対象に実地指導を実施
(2)その他特に特別合同指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実地指導を実施 |
○合同指導
| 厚生省及び都道府県が合同で行うもの(特別合同指導を除く) |
(1)複数の都道府県で指定を受けているサービス事業者等を対象に実地指導を実施
(2)その他特に合同指導が必要と認められるサービス事業者等を対象に実地指導を実施 |
緊
急
時
指
導 |
緊急時の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設に対する監査
老人福祉法第34条の2
介護保険法第203条の2 |
・国民の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認める場合に実施 |
・必要に応じ本省と連携し実施 |
老
人
福
祉
指
導 |
老人福祉法による福祉の措置の実施及び老人福祉施設に対する指導監査状況に関する指導
地方自治法第245条の4,5 |
・本庁における措置に関する指導事務及び老人福祉施設の指導監査事務の実施状況について指導を実施 |
・実施しない。 |
法
人
指
導 |
社会福祉法人に対する指導監督
※老人福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする法人
社会福祉法第56条
地方自治法第245条の4,7,8 |
・地方厚生局をまたがって事業所等を有する国所管の社会福祉法人を対象に指導を実施 |
・各地方厚生局管内の国所管の社会福祉法人を対象に指導を実施 |
4.介護予防・生活支援対策について
今後、介護保険制度の適切な運営に併せ、高齢者ができる限り寝たきりなどの要介護状態に陥ったり、要介護状態がさらに悪化することがないようにすること(介護予防)や、自立した生活を確保するために必要な支援を行うこと(生活支援)がますます重要な課題であり、そのため、平成13年度予算(案)において、「介護予防・生活支援事業」の拡充を図ることとしたところである。これにより、より効率的・効果的に、要介護になるおそれのある高齢者に対する介護予防事業を適切に実施できるよう支援することとしているので、その重要性を十分認識の上、市町村に対し適切な助言やご指導をお願いしたい。
特に、各市町村において、介護予防事業を適切に実施できるよう、その人材の育成に力を入れていく必要があると考えており、そのため、本事業のメニューの一つとして、「介護予防指導者養成事業」を位置づけたところである。都道府県においては、本事業の積極的な取り組みをお願いしたい。
(1)介護予防・生活支援事業について
平成13年度予算(案)においては、「介護予防・生活支援事業」の予算額の増を図るとともに、事業メニューの追加を行い、内容改善を図ることとしている。また、平成13年度より、「家族介護支援特別事業」を本事業に統合し、各地方自治体において補助金が弾力的に執行できるよう配慮することとしているところであるので、より一層の本事業への取り組みをお願いしたい。
〈平成13年度予算(案)における主な改善事項〉
ア 予算額の増
| 367億円 |
→ |
500億円
(家族介護支援特別事業の100億円を含む) |
イ メニューの追加等
○ 市町村事業
- ・ 成年後見制度利用支援事業
・ 高齢者地域支援体制整備・評価事業
・ 家族介護健康教育、健康相談など
○ 都道府県事業
- ・ 介護予防指導者養成事業
・ 高齢者訪問支援活動推進事業
・ 高齢者に関する介護知識・技術等普及促進事業
・ 高齢者地域支援体制整備・評価事業
(2)介護予防の人材育成について
介護予防事業に対する関心が高まる中で、この事業を推進する専門的な体制の確保・充実が大きな課題となっている。このため、介護予防に関する指導者等専門的な人材を養成し、介護予防事業の効果的・効率的な実施を図ることが求められている。
こうした状況を踏まえ、「介護予防指導者養成事業」として、都道府県が市町村担当者等を対象とする介護予防指導者研修を実施する場合に補助を行うこととしている。
現在、各都道府県における本事業の実施のために必要となるテキストの作成を行っているところであり、年度末までを目途にお示しする予定であるので、その有効活用を図り、本事業への積極的なお取り組みをお願いする。
(3)在宅介護支援センター運営事業について
介護保険制度が施行され、指定居宅介護支援事業所が運営されていることにかんがみ、今後の在宅介護支援センターの運営に当たっては、特に介護予防に力点をおき、高齢者が要支援、要介護の状態にならないような施策を展開し、住民の意識を変革していくことが各市町村に求められる。
このことが、高齢者の生活の質の維持向上につながるものであり、結果として、介護保険財政の健全化にも資するものとなることを十分念頭におく必要がある。
そこで、平成13年度予算(案)においては、介護予防プランの作成に要する経費を計上するなど、介護予防拠点としての機能の拡充を図ることとしているので、各都道府県においては、その趣旨を踏まえ、今後の市町村における事業展開に対するご指導、ご支援をお願いしたい。
〈平成13年度予算(案)における主な改善事項〉
○ 補助基準単価の改善
ア 基幹型
- ・通常型 14,985千円
- ・小規模型 9,678千円
- ・ケアプラン作成指導事業加算【新規】 年額 300千円
イ 地域型
- ・基本事業 2,890千円
- ・実態把握加算 1件あたり 2,700円
- ・福祉用具展示紹介業務加算 796千円
- ・介護予防サービス計画費加算【新規】 1件あたり 2,000円
- (介護予防プランの作成)
- ・痴呆相談事業加算【新規】 1件あたり 30,000円
- (痴呆高齢者の介護を含む家族介護の方法等の相談、家族介護サービスの 利用に関する相談、痴呆研修、痴呆予防教室の開催)
- ・住宅改修プラン・福祉用具購入プラン(意見書)作成加算【新規】 1件あたり 2,000円
- ・介護予防教室、転倒骨折予防教室加算【新規】 1回あたり 30,000円
- ・サービスマップ作成事業、適正契約普及事業加算【新規】 年額 1,700千円
※ 基幹型における「ケアプラン作成指導事業加算」、地域型における「サービスマップ作成事業、適正契約普及事業加算」については、「介護サービス適正実施指導事業」の委託を、地域型における「介護予防教室、転倒骨折予防教室加算」については、「介護予防・生活支援事業」の委託を、別途、市町村から受け、その補助金を活用して実施。
5.介護関連施設の整備・運営について
(1)介護関連施設の整備について
ア 基本的な考え方について
- (ア)平成12年度、13年度の介護サービス基盤整備
- ○ 介護サービス基盤整備については、ゴールドプラン21に掲げられた平成16年度における介護サービス提供見込量を踏まえた整備が必要である。国としても、各市町村が策定した介護保険事業計画に基づく介護サービスの提供量の確保に向け、毎年度必要な整備量を確保するためできる限り支援することとしているので、各市町村における整備状況及び整備計画を十分把握し、調整を図られたい。
- ○ 介護関連施設を含む社会福祉施設及び保健衛生施設については、昨年度と同様に、平成12年度末から平成13年度にかけて、切れ目のない予算執行を行う方針である。
このため、平成13年1月中旬から平成12年度補正予算に係る整備と併せて平成13年度に係る整備について協議を受けているものである。
なお、国庫補助協議にあたっては事業内容等の徹底した審査を求めているところであるが、平成12年度では国庫補助協議後の事業内容の変更等の事例がみられた。
今後は、執行段階での予期せぬ事由による計画変更を除き、このような事態が生じないよう、協議対象施設の審査にあたっては、一層厳密に行うようお願いしたい。
- ○ 平成13年度予算(案)においては、後述のとおり必要な整備量を確保したところであるので、各市町村において基盤整備が適切に行われるよう、指導をお願いしたい。
なお、平成12年度補正予算においては、介護サービス基盤の整備拡充を図るため、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の整備量の更なる確保を行うとともに、単独型のグループホームの整備を補助対象として追加した他、介護保険施設からの退所者で生活支援を要する高齢者の受け皿として需要が増大することが見込まれる高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)について、通所リハビリテーション等を行う介護老人保健施設に併設、隣接して整備する場合等に対しても補助を行うこととしたところであり、積極的な活用をお願いしたい。
- ○ さらに、介護関連施設の立地条件については、利用者である高齢者が長期間にわたり介護を受けながら生活する場でもあることから、一般住民が生活している区域から遠距離のところに孤立していることは望ましいこととは言えないので、都市計画の区域区分や住宅街からの距離・交通網、今後の近隣の開発計画等を総合的に勘案し、利用者の心情に配慮した地域に整備する事業について支援することとしている。
特に痴呆性高齢者グループホームの立地については都市計画の計画区域内であること等住宅地への建設を促進することとしているので留意されたい。
- ○ なお、これらに係る施設整備のヒアリングについては1月中旬から行っているところであるが、補正予算に伴う整備にあたっては、国庫補助に伴う都道府県市のいわゆる裏負担分に対して地方債の起債措置が講じられることとされていることから、財政担当部局とも十分協議の上、今年度事業への前倒しを積極的に検討されたい。
- (イ)今後の介護サービス基盤整備の基本方向
平成13年度以降、介護サービス基盤の整備を進めるにあたっては、次に掲げるような点を基本方向として対応することが望まれる。
- a 質・量両面にわたる基盤整備
- 介護サービス基盤の整備にあたっては、要介護高齢者の需要に応じた整備を計画的に進めることが求められる。この介護サービス基盤の整備においては、量的な面における整備の推進はもちろんのこと、質的な面での取り組みが重要となっているところである。
介護サービスは要介護高齢者を対象とする「対人サービス」であり、その良し悪しはサービスを担う人材の個人的な資質に依存する面が強い。具体的には、(1)高齢者や家族の状態を的確に把握し、適切なサービス提供ができる「知識技術」と、(2)他の職種を含め多様な社会資源と協調し、それらと一体となって問題解決に取り組む「協調性」を有するとともに、(3)高齢者や家族の心情を理解する「やさしさ」と個人のプライバシーに深くかかわってくることから「高い倫理観」を兼ね備えている人材が求められている。そうした人材の養成確保は、今後の基盤整備の重要な柱となるものである。
- b 地域の特性に応じた基盤整備
- 市町村や都道府県によって高齢化の度合い、人口規模等には大きな差異があり、高齢者を取り巻く社会資源も様々であることから、介護サービス基盤の整備にあたってはそうした地域特性を踏まえた取り組みが求められる。このため地方公共団体においては、それぞれの特性を踏まえ地域に最も適した介護サービス体制を構築するため、介護保険事業(支援)計画を定め、計画的に取り組んでいるところであり、今後とも介護サービスの確保のための基盤整備については計画的に推進されたい。
また、計画の推進にあたっては、高齢者に対する介護の面や老人保健福祉の分野にとどまらず、住宅整備や街づくり、生涯学習等幅広い分野との連携等を図りながら、高齢者の生活全般にわたる支援に対する取り組みとして推進されたい。
- c 効率性の視点を踏まえた基盤整備
- 介護保険においては給付と高齢者等の介護保険料の負担が連動しており、介護サービス基盤の整備は介護保険料をはじめとする介護保険財政に直接結びつくこととなる。それだけに、今後の基盤整備にあたっては、介護保険財政の安定等にも配慮した整備を行われたい。
イ 施設整備業務の適正化について
○ 本来の工事費を水増しした虚偽の契約書をもとに実績報告を行い、整備費補助金を過大に受給するなどの事件が、今年度においても散見されている。
これらの事件のほとんどは、平成9年度以降に施設整備業務改善方策を示す以前の整備ではあるが、今後とも同様の事件の再発防止を図るため、管内市区町村及び社会福祉法人等に対し、引き続き各種改善通知の趣旨に沿った指導の徹底に努められたい。
○ また、施設整備等を行う社会福祉法人がその施設の建設工事請負業者等から多額の寄付を受けることについては、いわゆる水増契約をして請負業者等からのリベートであるとの疑惑をもたれる恐れがある。
建設費の相当部分が公費や社会福祉・医療事業団からの公的融資により賄われる事業であることにかんがみ、寄付金相当額を値引きとして控除した後の額をもって工事請負金額とすることが妥当な方法と考えられる。
ついては、このような社会通念に照らし、発注者と受注者間における資金環流ではないかと疑惑をもたれるおそれがある寄付金に関して、基本的な考え方をお示ししたいと考えているのでご了知願いたい。
○ さらに、各種全国会議等で再三申し上げてきたことではあるが、不正受給の事実が発覚した場合には、補助金を返還させることはもとより、不正に関与していた者についての告発を行うなど、厳正な対処をお願いする。
○ なお、このほか、本年度、会計検査院の実地検査において、特別養護老人ホーム等を設置する際のスプリンクラー設備に係る補助について、設置者である市町村や社会福祉法人が、補助の仕組みを十分理解せず、誤って、同一の補助対象経費を二重に算入する又は補助対象外経費を補助対象に含めることにより、結果として補助金を過大に受給している事例が指摘されている。
今後、施設を設置する予定の管内市町村や社会福祉法人等に対し、適切な補助 の取扱いについて周知徹底するとともに、国庫補助協議時、交付申請時、実績報 告時の書類審査を厳格に行なうよう努めること。
ウ 平成13年度介護関連施設関係予算(案)について
平成13年度予算(案)において、介護関連施設整備分については、約1,228億円を計上したところである。
また、平成12年度補正予算において、介護関連施設整備分として、約315億円を確保している。
これにより、「ゴールドプラン21」に掲げられた平成16年度における介護サービス提供量を踏まえた計画的な整備を進めるために必要となる経費を確保できたものと考えている。
(参考)介護関連施設の整備量
| |
(12年度補正予算) |
(13年度予算(案)) |
| ○特別養護老人ホーム |
5,000人分 |
10,000人分 |
| ○介護老人保健施設 |
7,000人分 |
7,000人分 |
| ○ショートステイ |
2,000人分 |
6,000人分 |
| ○ケアハウス |
1,391人分 |
3,609人分 |
| ○高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス) |
100か所 |
230か所 |
| ○老人デイサービスセンター |
100か所 |
1,200か所 |
| ○痴呆性高齢者グループホーム |
100か所 |
500か所 |
| ○訪問看護ステーション |
− |
1,000か所 |
※(12年度補正予算)には、12年度公共事業等予備費の整備量も含む。
エ 平成13年度における整備方針について
- (ア)特別養護老人ホーム等社会福祉施設の整備方針
- a 基本的整備方針
- ○ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、ケアハウス等「ゴールドプラン21」において平成16年度における介護サービス提供量が示された介護関連施設については、その介護サービス提供量策定の基礎である各地方公共団体の介護保険事業(支援)計画等における介護サービス見込量に基づき、計画的な整備を行うものを推進する。
- ○ また、特別養護老人ホーム及び養護老人ホームにおいて、大部屋として整備されているものや老朽化が激しいものについては、サービスの質の向上を図る観点から平成13年度においても優先的に整備を行う方針である。
- ○ 介護保険制度下での特別養護老人ホームについては、地域における今後の状況等を踏まえつつ、より良質で効果的な介護サービスを安定的、効率的に提供できるような運営基盤の確保が求められていることから、施設整備に関しては、特に次の3点に留意されたい。
- (a)多機能化(痴呆性高齢者グループホーム、デイサービス、ショートステイ、ホームヘルパーステーション、ケアハウス、高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)等の機能を併せ持つこと)、
- (b)適正な規模の確保(介護保険制度下での施設の経営状況や地域での需要を勘案して、適切な規模とすること、また、既存施設で健全な運営を図っている小規模な施設については、定員増を図ること)、
- (c)グループケアユニット型(いくつかの居室や共用スペースを一つの生活単位として整備し、家庭的な環境の中で、少人数ごとに処遇する形態)の整備
- これら将来に向けての取組みが重要になると考えられることから、今後の老朽改築整備や増改築・新築整備に当たっては、このような視点に立った整備計画を優先採択する方針である。
- ○ なお、特にケアハウスやショートステイ床については、単に介護保険事業(支援)計画等において不足が生じていることをもってではなく、現下、当該地域において真に需要があるものの整備を推進するよう取り計らい願いたい。
- b 平成13年度予算(案)における内容改善事項
- (a)NPO法人等が設置する痴呆性高齢者グループホームに対して市町村が助成する事業についての補助の創設
- 一定の条件を満たしたNPO法人等がグループホームを設置する事業に対し、所在地の市町村が助成する場合について施設整備費補助の対象とする。
なお、補助を受ける際の法人の条件や補助方式の詳細については、追って補助金交付要綱等でお示しすることとするが、当該事業の間接補助先は市町村であり、あくまで所在地の市町村が非営利法人に助成する場合に限って補助対象とするものであることから管内市町村とは十分に連携を図られたい。
- (b)老人デイサービスセンター・在宅介護支援センターの補助基準額の定額化
- 補助金執行効率化の観点から、老人デイサービスセンター及び在宅介護支援センターの補助方式を従来の社会福祉法人に対する痴呆性高齢者グループホームに対する補助方式と同様の簡素なものとする。
- (c)ケアハウスのスプリンクラー設備補助要件の緩和
- ケアハウスのスプリンクラー設備に係る施設整備費について、要介護等の入所者のために防災対策を強化する観点に立ち特別養護老人ホーム並に補助要件を緩和する。
- (イ)介護老人保健施設等保健衛生施設の整備方針
- a 基本的整備方針
- ○ 介護老人保健施設、痴呆性高齢者グループホーム、訪問看護ステーション等ゴールドプラン21において平成16年度における介護サービス提供見込量が掲げられている介護関連施設については、地方公共団体が策定している介護保険事業(支援)計画に基づく計画的な整備について支援することとしている。
- ○ 介護保険制度下における介護老人保健施設については、地域における今後の状況等を踏まえつつ、より良質で効果的な介護サービスを安定的、効率的に提供できるような運営基盤の確保が求められていることから、施設整備に関しては、地域における需要の把握等に留意されたい。
- b 平成13年度予算(案)における内容改善事項等
- (a)介護老人保健施設整備における加算の見直し
- 介護老人保健施設の施設整備に対する国庫補助は、基本整備額に地域加算等の各種加算を加えた額を定額補助しているが、平成13年度からは加算事項等の見直しを行うこととしている。
- 【加算見直しの内容】
- 《加算の創設》
- ・グループケアユニット型加算
- 複数の療養室を一グループとして、そのグループ毎に食堂、談話スペース等の設備を備えた形態の整備に対し加算を行う。
- 《加算対象の見直し》
- ・大都市加算
- 指定都市に整備する場合にあっては、原則として都市計画法に定める計画区域内に整備する場合についてのみを加算の対象とする。
- 《加算の廃止》
- ・痴呆性老人処遇加算
- ・回廊式廊下等加算(平成13年度に限り加算額を減額して対象とする)
・療養環境整備加算
- (b)痴呆性高齢者グループホームの補助対象者の変更
- 従来、保健衛生施設等施設整備費補助金から行う痴呆性高齢者グループホームの国庫補助対象は、「『医療法人その他厚生大臣が認めた者』が行う施設整備事業に対する都道府県市の補助事業」としてきたところであるが、平成13年度からは「『医療法人』が行う施設整備事業に対する都道府県市の補助事業」に対し国庫補助を行うこととする予定であるので留意願いたい。
なお、従来補助対象としていた医療法人以外の者への補助事業については、平成13年度からは社会福祉施設等施設整備費補助金の補助対象とする予定である。
(2)介護関連施設の運営について
ア 運営費の主な改善内容
平成13年度予算(案)においては、労働基準法の改正を踏まえ、常勤職員について、年休代替要員費を更に2日分上乗せし、合計20日分とすることとしている。また、社会福祉法第65条において、社会福祉施設の設備の規模及び構造等に加え、利用者等からの苦情への対応についても最低基準に定めることが新たに規定されたことに伴い、苦情解決に要する経費を計上することとしている。
イ 高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)運営事業について
介護保険制度導入に伴い、現在、介護保険施設に入所している者のうち、要介護認定の結果、自立又は要支援と認定された者については、生活の場を確保して、円滑に退所できるようにする必要がある。
このため、平成13年度予算(案)において、高齢者生活福祉センターの名称を新たに「生活支援ハウス」として、その位置づけを明確化するとともに、生活支援ハウスの運営に必要な経費を計上しているところである。
各都道府県においては、この趣旨を管内市町村に周知するとともに、介護保険施設退所者の受け皿対策として、引き続き、積極的に本事業に取り組むようご指導、ご助言をお願いしたい。
ウ 感染症対策の適正な実施について
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の施設内におけるインフルエンザ、結核等感染症対策については、従来からご指導いただいているところであるが、「今冬のインフルエンザ総合対策について(平成12年度版)」をはじめ、既に通知しているレジオネラ症予防対策等各種の感染症対策等を踏まえ、引き続き施設内における感染症対策について特段の注意を払うよう管内介護関連施設に対する指導をお願いしたい。
エ 老人福祉施設の適正な運営及び老人保護費の適正な執行
養護老人ホーム等老人福祉施設の適正な運営については従来よりご指導いただいているところであるが、なお、施設の運営や建設をめぐる不祥事が見られる。
ついては、平成9年3月以降に出した適正化への指導通知等を踏まえ、管内老人福祉施設に対し、適正な運営について強力に指導をお願いしたい。
また、老人保護費の執行については、本年度の会計検査院の実地検査において、平成10年度の費用徴収に関する被措置者の対象収入の算定及び扶養義務者の認定の誤りなどにより、38市区町で総額約5,969万円の国庫補助金の過大な精算がなされていた、との指摘がなされたところである。
費用徴収事務の適正の確保については、昨年度も指摘されており、厳正な執行が求められるところであるので、管内の措置の実施機関等に対し、改めて適正な取扱いがなされるよう周知徹底を図るとともに、費用徴収額等の決定に当たって十分な審査を行い、適正を期すよう指導をお願いしたい。
6.痴呆性高齢者支援対策について
今後、急速に増加することが見込まれる痴呆性高齢者に対する取組みは、これからの 重要課題であり、「ゴールドプラン21」においても重要な柱の一つとして位置づけられており、各自治体においてもこの課題に今まで以上に積極的に対応していく必要がある。
ついては、平成13年度において下記の点に留意し、各都道府県・指定都市(以下「都道府県等」という。)においても、当該事業が効果的に実施できるよう特段のご支援と御協力をお願いする。
(1)痴呆介護研修事業について
痴呆性高齢者の介護に関する研修事業については、平成11年度までは都道府県等において「痴呆性老人処遇技術研修」を実施してきたところであるが、平成12年度より痴呆性高齢者の介護に携わる者に対し痴呆介護技術のさらなる向上を図る観点から新たに「痴呆介護研修」を創設したところである。
「痴呆介護研修」は、全国に3か所設置している高齢者痴呆介護研究センターにおいて都道府県等で高齢者介護の指導的立場にある者に対して実施される「指導者養成研修」と都道府県等において介護実務者に対して実施される「痴呆介護実務者研修」から構成されているところである。
「痴呆介護研修」を実効あるものとするには、指導者の確保が極めて重要な要素であることにかんがみ、各都道府県等においては、平成13年度から年間を通じて本格的に実施される「指導者養成研修」に研修受講者を積極的に派遣願うと同時に、各施設・事業所等において痴呆介護に携わる者に対する「痴呆介護実務者研修」に積極的に取り組んでいただきたい。
(2)高齢者痴呆介護研究センターについて
高齢者痴呆介護研究センターは、我が国における痴呆性高齢者の介護に関する研究の中核的機関として位置づけており、痴呆性高齢者の介護の専門性を高めるとともに、質の高い介護技術を理論化することを目的として、実践的なテーマを中心に大学や研究機関等と連携を図りながら学際的な共同研究を推進していくこととしている。
センターでは、この成果を踏まえ、都道府県等で指導的な立場にある者に対し、痴呆介護に関する専門的な知識及び技術並びに高齢者介護実務者に対する研修プログラム作成方法及び教育技術修得のための研修を実施し痴呆介護の専門職員の育成と確保に努めることとしている。
当センターは、現在、全国3か所(東京都杉並区、愛知県大府市、宮城県仙台市)で整備が進められているが、本年3月に都道府県等の職員を対象とした「痴呆介護行政推進担当者研修」を実施し、4月以降本格的な指導者養成研修を行うこととしている。来年度については、各センターで正味30日間の指導者養成研修をそれぞれ3回行うこととしており、具体的な日程や研修プログラムについては、現在検討を進めているところである。
さらに、平成12年度補正予算において痴呆介護情報ネットワーク体制整備費を確保したところであるが、このネットワークシステムは、(1)3センター間の情報の共有化やセンターで研究した成果を一般に広く情報提供していくシステム及び(2)各都道府県等における研修施設の設備整備及び3センターから各都道府県等の研修拠点に対する痴呆介護の研修情報提供システムから構築されるものである。(1)については現在システムの開発に取り組んでおり、(2)については各都道府県等からの整備費の協議手続きをすすめているところである。このシステムにより高齢者痴呆介護研究センターを中心とした情報ネットワークを構築し、痴呆介護に関する効率的な情報の収集・提供に取り組むこととしている。
(3)痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について
痴呆性高齢者支援対策の柱である痴呆性高齢者グループホームについては、平成16年度までに3,200か所の整備を見込んでいるところであり、地域のニーズを踏まえたさらなる整備の推進が期待されている。
今後、その適正な普及を図る観点から単独型グループホーム及びNPO法人等への施設整備費の補助拡大、住宅地への建設の促進、管理者・スタッフに対する研修の義務づけ、サービス評価の義務づけ、情報公開の推進、市町村との連携強化等を実施することとしている。
(4)徘徊高齢者保護システムの整備について
痴呆性高齢者が徘徊行動により所在不明となった場合に高齢者を安全・迅速に保護することは痴呆性高齢者支援対策の重要な課題である。
このため、平成13年度予算(案)において、高齢者ITケアネットワーク支援事業として、痴呆性高齢者保護システムの整備を図るための予算を計上したところである。
各都道府県においては、事業推進のための会議を設置し、管下市町村における徘徊高齢者保護体制の整備及び家族からの保護の依頼により最寄りの保護機関への連絡を行う広域保護情報センターを整備していただくこととなるが、これらの具体的方策及び補助金の執行方針については現在検討中であり、まとまり次第お示しすることとしている。
7.老人保健事業等について
(1)老人保健事業等について
ア 保健事業第4次計画について
- (ア)保健事業第4次計画の推進
- 老人保健法に基づく医療等以外の保健事業については、平成12年度より5か年の保健事業第4次計画を策定し、保健事業の一層の充実を図ることとしている。
第4次計画では、個別健康教育や健康度評価など新たな事業の取組みを行うこととしている。引き続き、その定着に向けて、市町村における実施体制等に留意しつつ、積極的な推進をお願いしたい。
平成13年度においても、保健事業第4次計画に基づき、所要の事業量を確保したところであるので、各事業のより一層の推進が図られるよう、引き続き各市町村に対する支援等をお願いしたい。また、これに必要な都道府県、市町村における財政措置についても配意をお願いしたい。
平成13年度においては、個別健康教育の各都道府県等における研修の際の指導者等を養成するための個別健康教育指導者養成研修を実施することを予定している
これは、個別健康教育の実施を支援するためのものであるので、研修参加者の派遣等については特段の配慮をお願いしたい。
なお、保健事業第4次計画の具体的な実施に際しては、高齢者の健康保持を効果的に推進する観点から、保健・医療・福祉の連携が重要であり、老人保健福祉計画や、健康日本21地方計画の実施と十分な連携を図るようお願いしたい。
- (イ)老人保健事業推進・評価委員会
- 平成12年12月に、老人保健事業推進・評価委員会を設置し、市町村が地域の実態に即して円滑に保健事業第4次計画における各種保健事業を推進できるよう、必要な検討を行うこととしたところである。今後、市町村等の第4次計画の実施状況等を踏まえながら検討を進めていく予定であるので、特段の配慮をお願いしたい
なお、検討の結果等については、適宜都道府県や市町村等に必要な情報提供を行っていくこととしている。
イ 支出科目の変更
「介護家族健康教育」「介護家族健康相談」「機能訓練B型」については、保健事業費等負担金により費用負担が行われてきたが、平成13年度より、「介護予防・生活支援事業」(在宅福祉事業費補助金)により費用を補助することとしているので、財政措置にあたっては十分了知されるとともに各市町村への周知方よろしくお願いしたい。なお、このことにより、保健事業第4次計画推進の必要性については何ら変更されるものではないので留意願いたい。
ウ 健康診査受診対象者の適正化
老人保健法第22条により、医療保険各法その他の法令に基づく事業のうち保健事業に相当するサービスを受けた場合又は受けることができる場合は、老人保健法の保健事業を行わないこととなっている。ついては、健康診査等の実施にあたってその主旨を踏まえ適正に運用されるよう引き続き周知に努められたい。
エ 地域リハビリテーション支援体制の推進
高齢者や障害を持つ者が、たとえ介護を必要とするようになっても、住み慣れた地域で生活が続けられることを基本理念とした地域リハビリテーションは、急性期から維持期にわたる適切なリハビリテーションの提供に加え、在宅ケアと施設ケアさらに住民参加等も含めたものである。このため、広い視野に立ったリハビリテーション連携指針の作成や、中核となる施設の選定、保健・医療・福祉関係諸機関への普及・啓発、患者の会等の自主活動の支援が総合的に推進されることが重要である。引き続き、積極的に推進されるよう配慮をお願いしたい。
なお、平成13年度においては、従前の地域リハビリ調整者養成研修を、地域リハビリテーション支援体制整備推進事業の中で一体的に実施していただくこととしているので、了知願いたい。
オ その他
平成10年度より実施してきた老人保健強化推進特別事業については、平成12年度をもって廃止されることとなったので、了知願いたい。
(2)高齢者の生きがい・健康づくりについて
ア 「介護予防・生活支援事業」への組み替え事業について
これまで、老人クラブを中心として行っていた「高齢者訪問支援活動推進員養成推進試行的事業」については、より効果的な事業実施を図るため、新たに「高齢者訪問支援活動推進事業」として介護予防・生活支援事業の「都道府県・指定都市事業」へ組替計上したものである。
事業内容の詳細については別途実施要綱でお示しする予定であるが、本事業は老人クラブが従来行っていた、在宅の高齢者に対して話し相手や日常生活上の援助などの訪問活動事業等を行う実践的指導者となるリーダー養成などの事業をもとに新たに構築したことから、事業の実施に当たっては老人クラブとの連携を密にするようご配慮願いたい。
また、介護実習・普及センター事業については、平成11年度において概ね全都道府県・指定都市に設置が完了したこと、介護保険制度が概ね順調に施行されたこと等から、平成13年度予算において介護実習・普及センターに対する補助金を見直すこととしたものである。
具体的には、人件費については一般財源化をすることとし、事業費については国民の介護に関する意識啓発や介護知識・介護技術の普及などの高齢者の生活の質の確保を図るとともに、高齢者を社会全体で支える地域づくりを目的とする事業が引き続き実施できるよう「高齢者に関する介護知識・技術等普及促進事業」として介護予防・生活支援事業の「都道府県・指定都市事業」へ組替計上したものである。
事業の詳細については別途実施要綱でお示しする予定であるが、当該事業の実施に当たっては、従来どおり介護実習・普及センターの活用を図り、事業の円滑な実施に向けた積極的な取組みを願いたい。
イ 全国健康福祉祭(ねんりんピック)について
高齢者を中心とする国民の健康保持・増進、社会参加、生きがいの高揚等を図り、ふれあいと活力ある長寿社会の形成を目的として開催されている全国健康福祉祭は、本年は広島県・広島市において開催することとしている。
本大会の趣旨である高齢者の社会参加及び地域間、世代間の交流を積極的に推進するため、都道府県明るい長寿社会づくり推進機構とも連携を図りながら、各イベントにおける参加者の裾野を広げるよう努めるとともに、本大会に対する選手等の派遣など十分な参加体制が確保されるようご配慮願いたい。
また、ねんりんピックの目的、理念を地域に浸透させ、健康増進、文化活動の推進を図る観点から、各地方自治体においても、地域の実情に応じた地方版ねんりんピックの開催など、引き続き積極的な取組みについてご配慮願いたい。
- a 第14回全国健康福祉祭広島大会(2001ねんりんピック広島)
-
| ・テーマ |
あなたの笑顔にあいたいけん |
| ・期日 |
平成13年10月6日(土)〜10月9日(火) |
| ・会場 |
広島市をはじめ14市町 |
- b 今後の開催予定
-
第15回(平成14年度) 福島県
第16回(平成15年度) 徳島県
第17回(平成16年度) 群馬県
第18回(平成17年度) 福岡県、北九州市、福岡市
第19回(平成18年度) 静岡県
第20回(平成19年度) 茨城県
第21回(平成20年度) 鹿児島県
(3)老人保健健康増進等事業について
本事業は、高齢者の介護、介護予防、生活支援、老人保健及び健康増進等に関わる先駆的、試行的な事業等に対し助成を行い、もって老人保健福祉サービスの一層の充実や介護保険制度の基盤の安定化に資することを目的として、平成13年度予算(案)においては、36億2,250万円を計上した。
本事業は、(1)先駆的・試行的な事業等で相当の効果が期待でき、その効果が施策等に反映できる具体性を持つ事業で、(2)他の補助金の対象でなく単年度事業のものを採択することとしている。国庫補助協議を行うに当たっては、事業内容の十分な精査と積極的な取り組みをお願いいたしたい。
また、本事業で交付した補助金について、会計経理区分や収支にかかる帳簿及び証拠書類の保管の不備など基本的な取扱いについて問題が見受けられたところである。
言うまでもなく補助金執行の基本であることからも、かかる事態が生じることのないよう管下市町村等に対し適正執行の指導をお願いいたしたい。
なお、会計検査院の実施検査においても指摘を受けたところであり、併せて適正な執行に努められたい。
トップへ
会議資料目次
トピックス
厚生労働省ホームページ