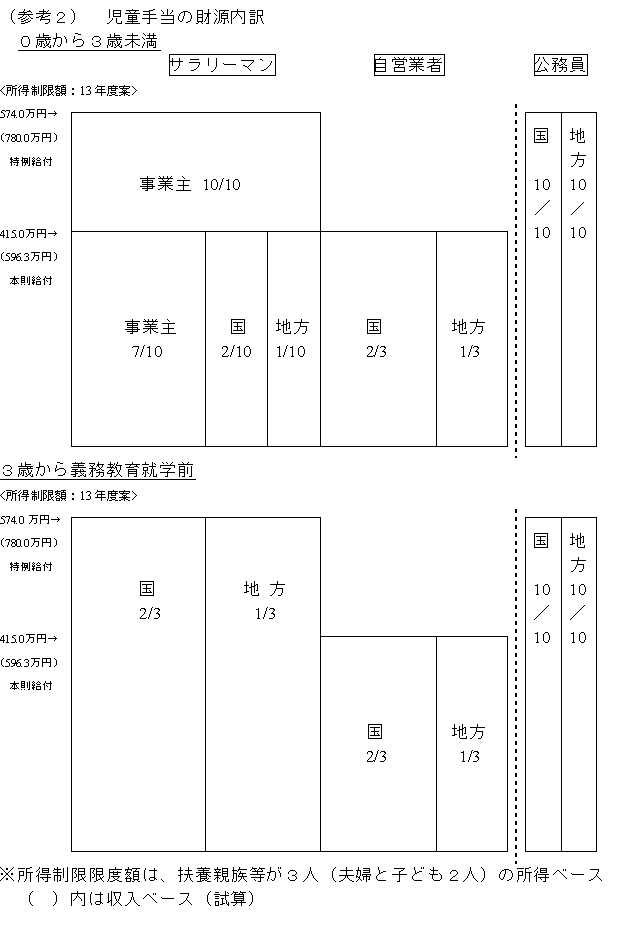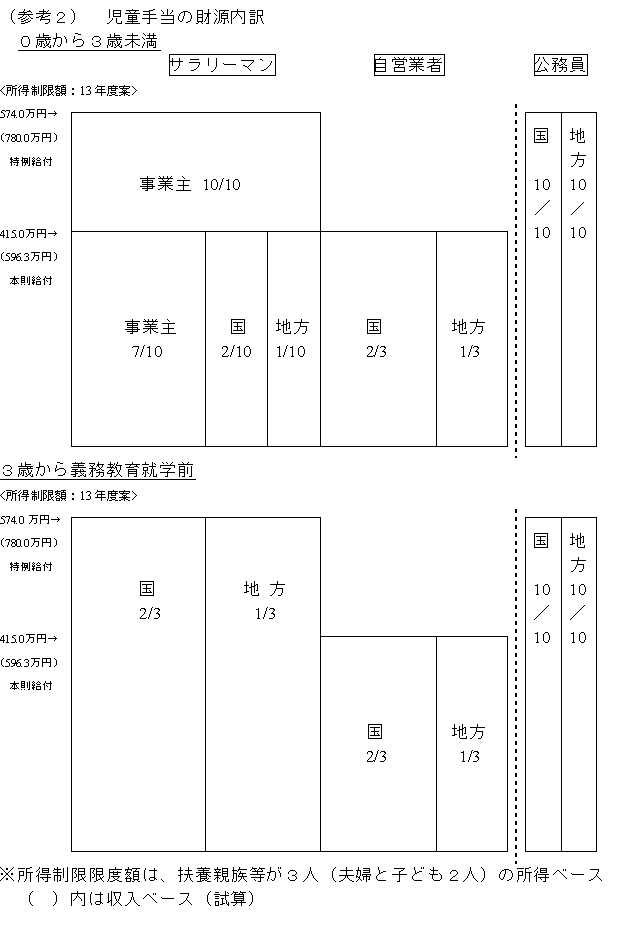
(1)少子化対策基本方針及び新エンゼルプランについて
少子化対策については、従来から様々な取組を行ってきたが、平成11年の合計特殊出生率は1.34と過去最低になるなど、少子化が進行しており、少子化対策の推進は引き続き重要な課題となっている。
(1)少子化対策基本方針
政府が一体となって、家庭や子育てに夢を持てる環境の整備を推進するため、中長期的に進める総合的な少子化対策の指針として、少子化対策推進関係閣僚会議において、平成11年12月17日に「少子化対策推進基本方針」を策定。
(2)新エンゼルプラン
「新エンゼルプラン」は、少子化対策推進基本方針に基づく重点施策の具体的実施計画として、平成6年12月に策定された「エンゼルプラン」及び「緊急保育対策等5か年事業」を見直し、働き方、保育サービス、相談・支援体制、母子保健、教育、住宅等について、大蔵、文部、厚生、労働、建設、自治の6大臣の合意により、平成11年12月19日に策定。
(新エンゼルプランの主な内容)
(3)地方版エンゼルプランの策定等
平成13年度予算案については、新エンゼルプランの目標達成に向けた保育対策、母子保健医療対策等の推進に必要な予算額を確保したところである。
このため、平成11年末に策定された「少子化対策基本方針」及び「新エンゼルプラン」に基づき、総合的な少子化対策を推進するとともに、内閣総理大臣の主催の下で「少子化への対応を推進する国民会議」を開催し、国民的な広がりのある少子化への取組を進めているところ。
当該方針は、仕事と子育ての両立や子育てのそのものに係る負担感を緩和・除去し、安心して子育てができるような様々な環境整備を進めることにより、21世紀の我が国を家庭や子育てに夢や希望を持つことができる社会にしようとするものであり、具体的には、
の6項目が掲げられている。
この「新エンゼルプラン」は、従来の「緊急保育対策等5か年事業」における保育対策のみならず、母子保健等の幅広い少子化対策の重点施策について、平成16年度の整備水準を示すなど具体的実施計画として策定したもの。
○保育関係
○子育て支援の推進
○母子保健医療体制の整備
また、少子化対策推進基本方針においても、「地方公共団体においては、本基本方針の策定趣旨、内容を踏まえ、少子化対策の計画的な推進を図るなど、地域の特性に応じた施策を推進するものとする」とされたところであり、少子化対策の重要性を踏まえ、地方版エンゼルプランの策定・見直しを含め、積極的な対策の推進をお願いしたい。
| 現行 | 改正後 | ||
| 児童手当 | 284.0万円 | → | 415.0万円 |
| (432.5万円) | → | (596.3万円) |
| 特例給付 | 475.0万円 | → | 574.0万円 |
| (670.0万円) | → | (780.0万円) |
| 全体 | 72.5% | → | 85.0% |
| 約 565万人 | → | 約 660万人 |
| 現行どおり | 第1子・第2子 第3子以降 | 月額 5,000円 月額 10,000円 |
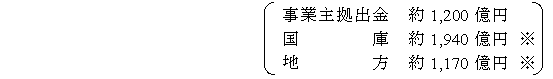
※公務員分の財源を含む。
(2) 広報等の実施について
(参考1) 「児童手当等に関する三党合意」(平成12年12月13日)
自由民主党・公明党・保守党の三党は、「3党連立政権合意」(平成12年4月5日)などを踏まえ、児童手当の拡充など子育て支援策について、鋭意、検討を続けてきた。
その結果、平成13年度予算編成にあたり、三党は次の点で合意に達した。
記
1.平成13年度当初予算においては、支給対象児童を養育する親等の所得制限を緩和し、概ね支給率を85%に引き上げることとする。