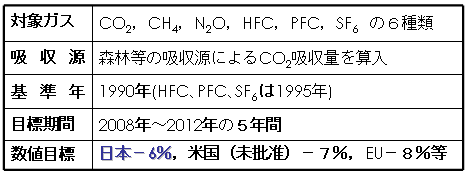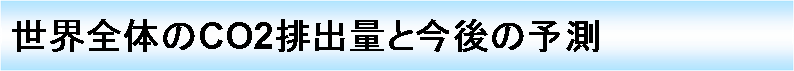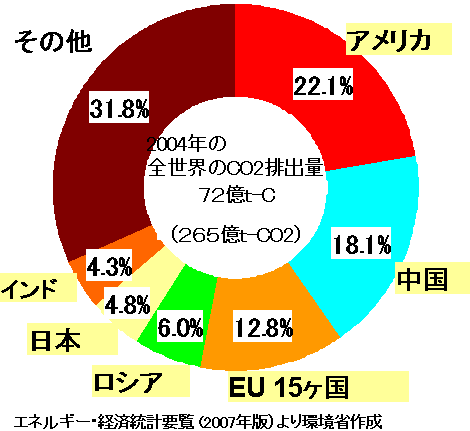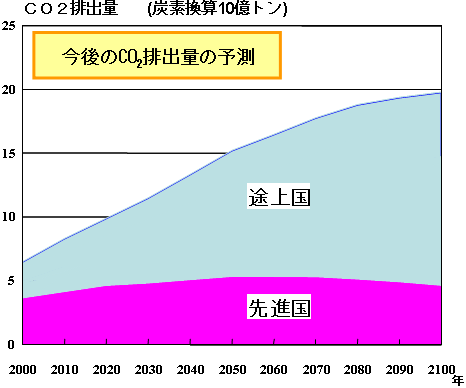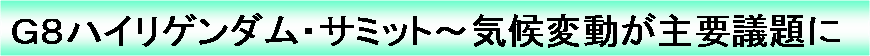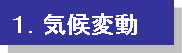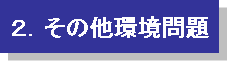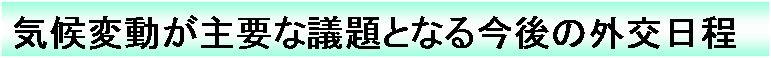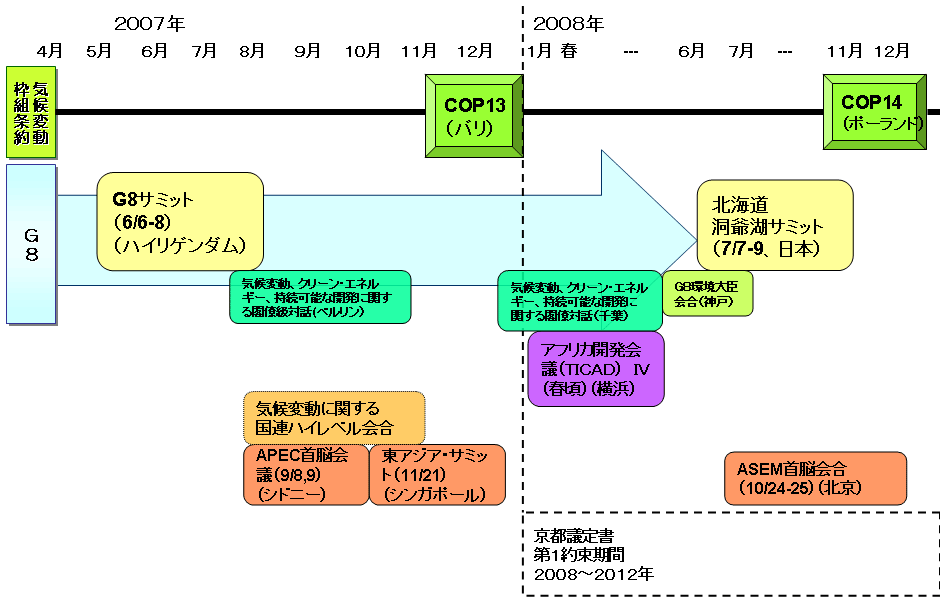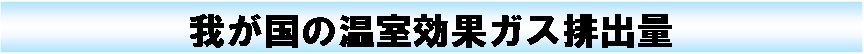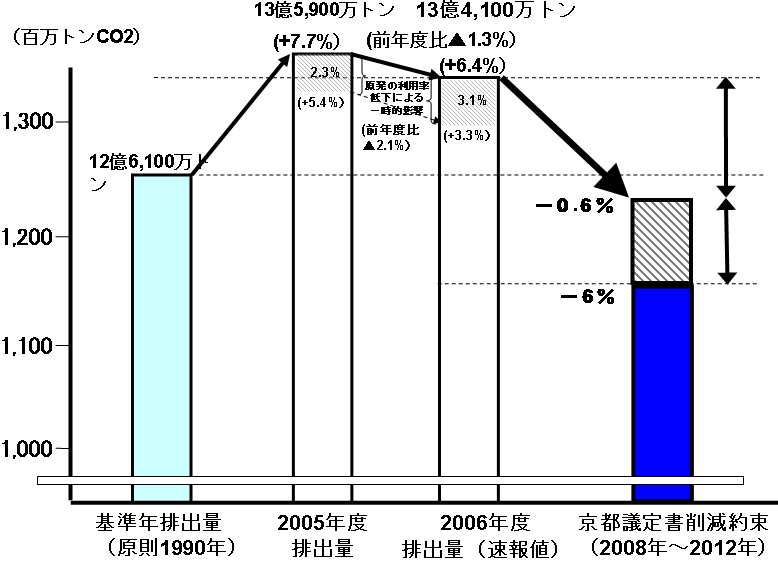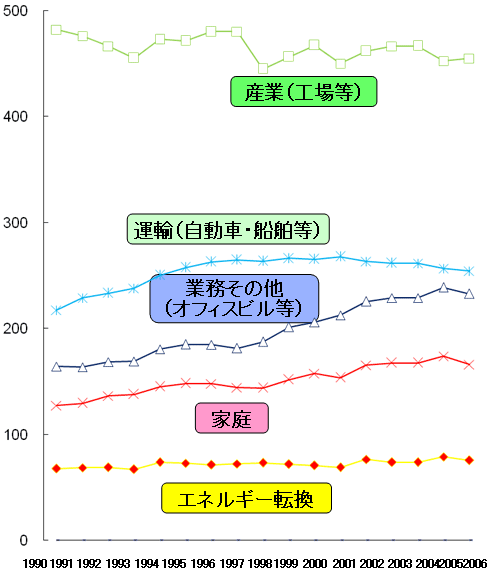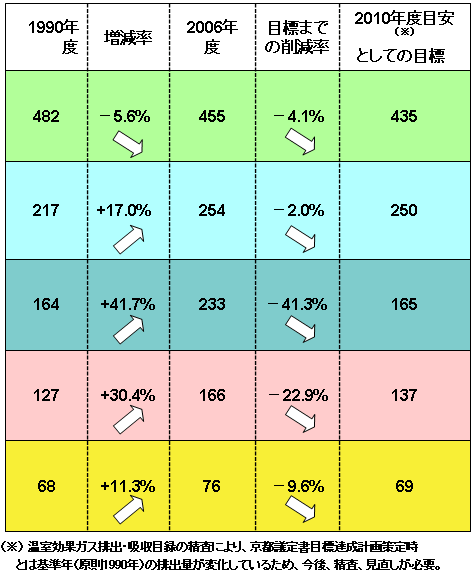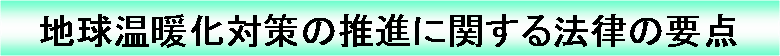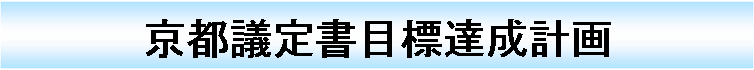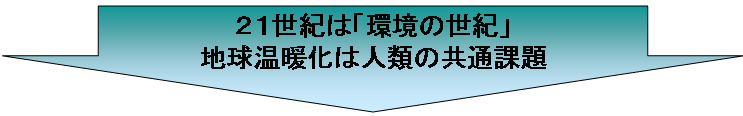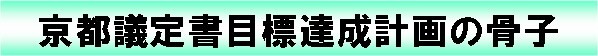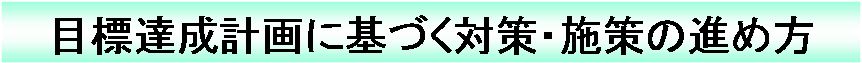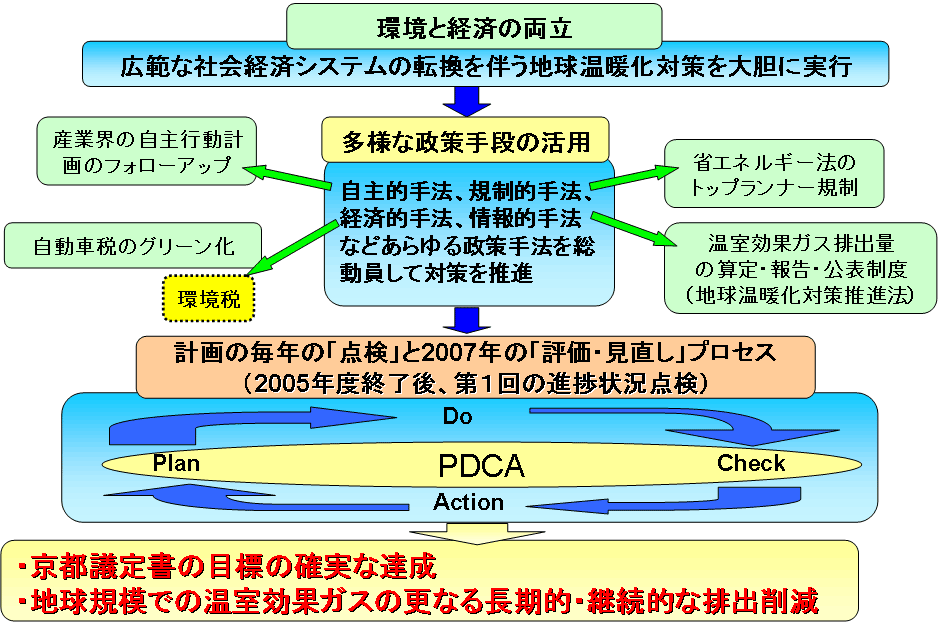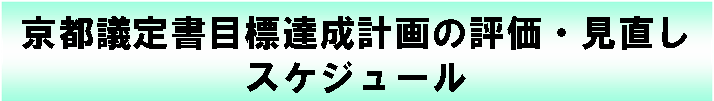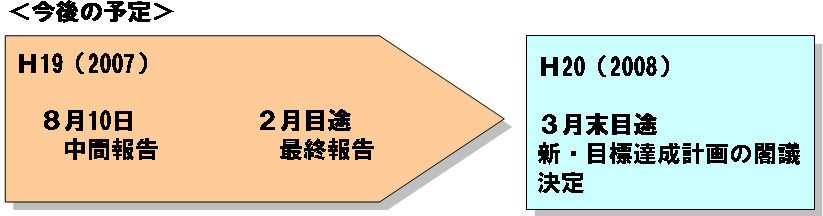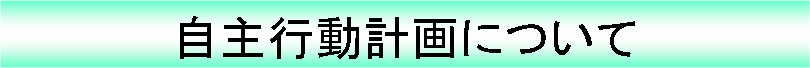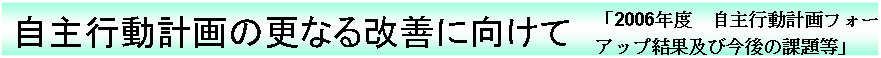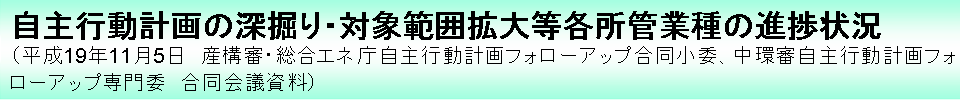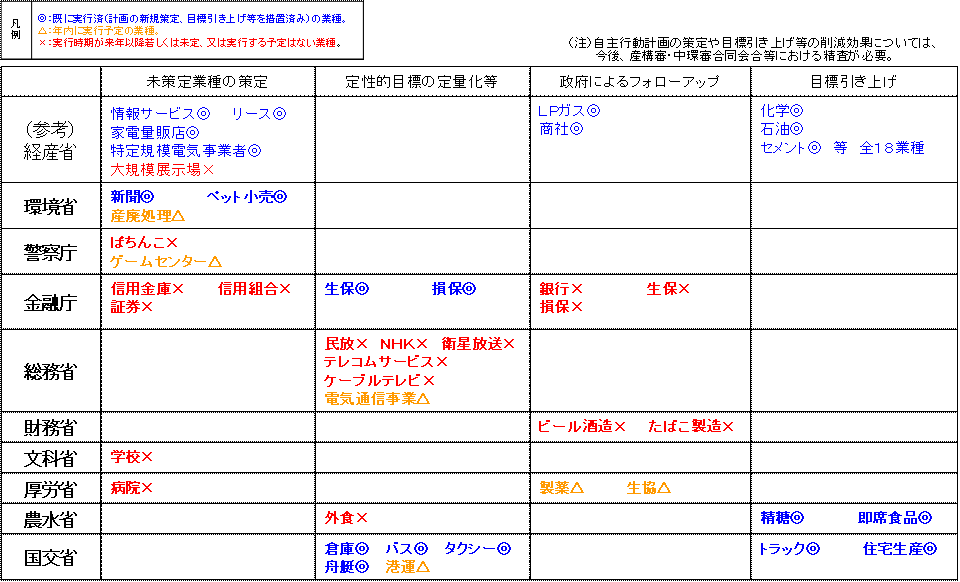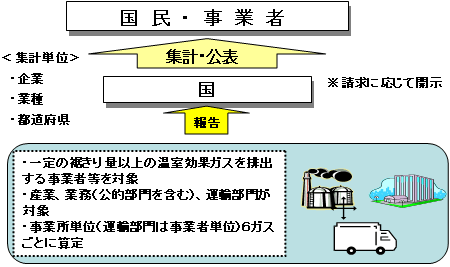気候変動枠組条約(UNFCCC、192ヵ国・地域) 1992年採択
究極目的: 温室効果ガス濃度を、気候システムに対して危険な人為的干渉を
及ぼすこととならない水準に安定化させる
原 則: 共通だが差異のある責任、及び各国の能力に従い、気候系を保護
全締約国の義務: 排出目録の作成、削減計画の立案等
先進国等の義務: 排出量を1990年の水準に戻すことを目的に削減活動を報告
先進国の途上国支援義務: 資金供与、技術移転、キャパシティ・ビルディング等
京都議定書(Kyoto Protocol、176ヵ国・地域) 1997年採択
「共通だが差異のある責任」 原則に基づき:
(1)先進国全体で1990年比で少なくとも5%の削減を目標。
(2)各国毎に法的拘束力のある数値目標設定(途上国は削減約束なし)
(3)柔軟性措置として、京都メカニズムを用意
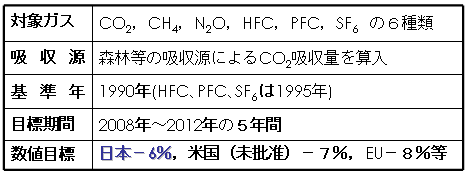
|
我が国は2002年6月4日
に締結し、議定書は
2005年2月16日に発効。
|
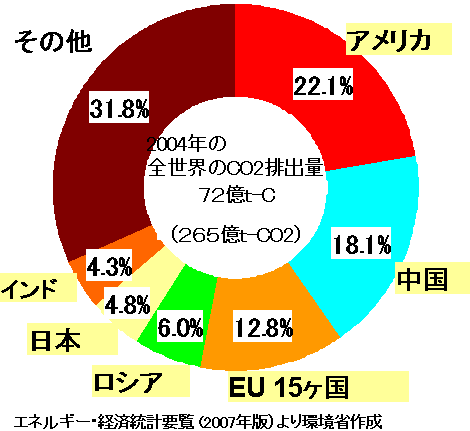
|
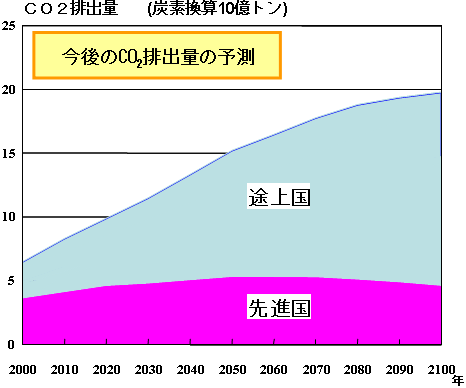
出典: Kainuma et al., 2002: Climate Policy Assessment,
Springer, p.64.
|
日程:2007年6月6〜8日
参加国:G8(日米加英独仏伊露)及び新興諸国(中国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカ)
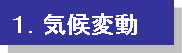
| 安倍総理の新提案「美しい星50」に基づき、各国に理解と協力を呼びかけた |
┌
|
|
|
|
└ |
☆2050年までに現状に比べ世界全体の排出量を半減、
☆ポスト京都議定書の3原則((1)主要排出国の参加、(2)柔軟で多様性のある枠組み、(3)経済と環境の
両立)、その実現のための新たな「資金メカニズム」、エネルギー効率向上など、
☆国民運動の展開
| ┐
|
|
|
|
┘ |
| 合意事項 |
(1)2050年までに世界全体の温室効果ガス排出量を
少なくとも半減することを真剣に検討
(2)主要排出国を含む2013年以降の包括的な合意達成に向け、
本年12月の国連気候変動会議への参加呼びかけ
(3)主要排出国による会合(少数国会合)を通じて、2008年末までに
新たなグローバルな枠組みのための具体的な貢献を行う
|
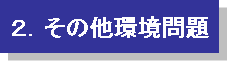
|
・・・気候変動とも密接に関連
|
●森林減少の抑制による排出の削減と持続可能な森林経営の促進
●生物多様性の保全と持続可能な利用の重要性
|
2006年度における我が国の排出量は、基準年比6.4%上回っており、
議定書の6%削減約束の達成には、7.0%の排出削減が必要。
|
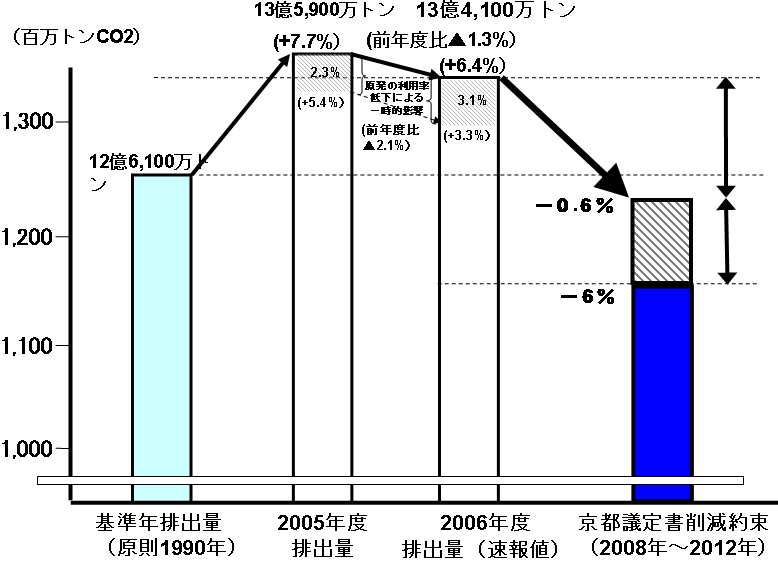
|
森林吸収源対策で3.8%
京都メカニズムで1.6%
の確保を目標
|
|
単位:百万トンCO2
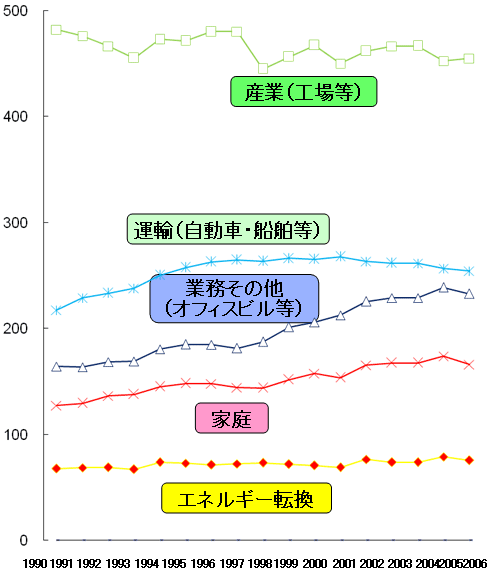
|
単位:百万トンCO2
|
|
・政府は、地球温暖化対策の推進に関する基本的方向、各主
体の講ずべき対策、事業者の計画等について定める京都議定
書目標達成計画を策定。
|
|
・地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣
総理大臣を本部長、環境大臣等を副本部長、全閣僚を本部員
とする地球温暖化対策推進本部を設置。
|
|
・国・都道府県・市町村が、それぞれの事務・事業に
伴い排出される温室効果ガスについて自らが率先
して削減努力を行う計画を策定
|
|  | |
|
|
・地方公共団体が、その区域の自然的社会的条件に応じて、温
室効果ガスの排出の削減等のための総合的かつ計画的な施策
を策定
|
|
|
<その他>
○京都メカニズムの推進・活用に向けた取組
(クレジット(算定割当量)を管理する割当量口座簿を整備)
○地球温暖化対策地域協議会の設置
○日本全体の総排出量の公表
○森林整備等による温室効果ガス吸収源対策の推進
|
| |
|
・地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、温
室効果ガスを一定量以上排出する者に温室効果ガスの排出
量を算定し、国に報告することを義務付け、国が報告された
データを集計・公表する制度。
|
(全国・都道府県)地球温暖化防止活動推進センター
地球温暖化防止活動推進員 |
|
(1)全国センター:地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこ
と等を目的として、環境大臣が設置。
(2)都道府県センター:地域における普及啓発を行うこと等を目
的として、都道府県知事が設置。
(3)推進員:温暖化対策の知見を有し普及啓発等の経験に富
む者が、都道府県知事の委嘱により住民への啓発や助言等
を行う。
|
|
|
6%削減約束を達成するために必要な対策・施策を盛り込んだ「京都議定書目
標達成計画」を2005年4月に閣議決定。
|
|
1. 京都議定書の6%削減約束の確実な達成
2. 地球規模での温室効果ガスの更なる
長期的・継続的な排出削減
|
|
我が国は、世界に冠たる環境先進国家として、地球
温暖化問題で世界をリードする役割を果たしていく
ことを目指す。
|
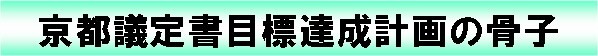 | (平成17年4月28日閣議決定、 平成18年7月11日一部変更)
|
|
○環境と経済の両立
○多様な政策手段の活用
|
○技術革新の促進
○評価・見直しプロセスの重視
|
○すべての主体の参加・連携の促進(国民運動、情報共有)
○国際的連携の確保
|
|
1-1. 温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策 |
|
(1) 温室効果ガスの排出削減対策・施策
[1]エネルギー起源CO2
・技術革新の成果を活用した「エネルギー関連機器
の対策」「事業所など施設・主体単位の対策」
・「都市・地域の構造や公共交通インフラを含む社
会経済システムを省CO2型に変革する対策」
[2]非エネルギー起源CO2
・混合セメントの利用拡大 等
(2) 温室効果ガス吸収源対策・施策
・健全な森林の整備、国民参加の森林づくり 等
|
[3]メタン
・廃棄物の最終処分量の削減 等
[4]一酸化二窒素
・下水汚泥焼却施設等における燃焼の高度化 等
[5]代替フロン等3ガス
・産業界の計画的な取組、代替物質等の開発 等
|
|
|
|
○排出量の算定・報告・公表制度 ○事業活動における環境への配慮の促進 ○国民運動の展開
| |
○公的機関の率先的取組 ○サマータイム ○ポリシーミックスの活用(※環境税等も検討)
|
|
|
|
○排出量・吸収量の算定体制の整備 ○技術開発、調査研究の推進 ○国際的連携の確保、国際協力の推進
|
|
|
| ○海外における排出削減等事業を推進 ○クレジット取得に関する取組 |
|
|
|
○毎年の施策の進捗状況等の点検、2007年度の計画の定量的な評価・見直し ○地球温暖化対策推進本部を中心とした計画の着実な推進
|
|
|
|
・中間報告(平成19年8月10日)で示された方向に従って、自主行動計画
の拡大強化や関連制度改革等の追加対策の具体化、削減効果の算定
・国民各層への働きかけを抜本的に強化すること等により、既存施策につ
いて見込み通りの効果の実現を図る。
|
9月以降、中環審・産構審合同審議会による審議
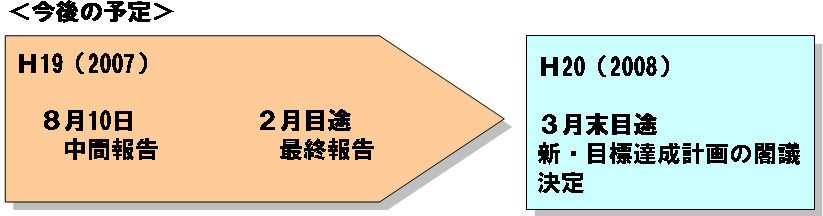
|
|
京都議定書目標達成計画においては、自主行動計画が、「産業・エネルギー
転換部門における対策の中心的役割を果たすもの」と位置付けられている。
|
産業・
エネルギー転換部門 |
日本経団連の環境自主行動計画の他、
51業種が策定。日本経団連加盟業種の
計画で、我が国の産業・エネルギー転換
部門の排出量の約8割をカバー。 |
| 民生業務部門 |
28団体・企業が策定 |
| 運輸部門 |
17団体・企業が策定 |
|
・業種ごとに定量的に目標を設定
・事業者の専門的知識や創意工夫をいかした、迅速かつ柔軟な対処が可能
・継続的な技術革新への誘因、関係者の環境意識の向上につながる
|
|
|
「京都議定書目標達成計画」(自主行動計画部分)
c.オフィス・店舗等の業務施設の省CO2化
○自主行動計画の着実な実施
自主行動計画の目標・内容についてはあくまで事業者の
自主性にゆだねられるべきものであることを踏まえつつ、社
会的要請にこたえ、その透明性・信頼性・目標達成の蓋然
性を向上していくことが極めて重要であり、関係審議会等に
おいて定期的にフォローアップを行う必要がある。
また、私立病院、私立学校等の未策定業種においても、
自主行動計画を策定し、特性に応じた有効な省CO2対策を
講ずることが期待される。
|
(1) 未策定業種に対する自主行動計画策定の働きかけ促進
自主行動計画の未策定業種(特に、サービス(非製造)分野など。私立病院・私立学校等を含む)に対し、
その策定を促すべき。
(2) 定性的目標の定量化等の促進
自主行動計画を策定していても、数値目標を持たない業種(経団連非加盟業種、特に業務・運輸部門)
に対し、目標の定量化を促すべき。
(3) 政府による厳格なフォローアップの実施
議事公開の下での審議会等プロセスの活用など、透明な手続きの下、厳格なフォローアップを実施すべ
き。また、毎年度の実施により、直近の正確な実態を把握すべき。
(4) 目標引き上げの促進
厳格なフォローアップにより、業務・運輸部門の業種も含め、目標の引き上げを促進すべき。その際、現
時点の実績水準以上の意欲的な新目標を設定すべき。
|
|
|
今後の対策内容とその効果(京都メカニズムの活用を含む。)を定量的・具体的に示すべき。
|
|
原単位を目標としている業種を含め、各業種はCO2排出量の削減を一層強く意識した積極的な取組を行うべ
き。原単位のみを目標指標としている業種は、CO2排出量についても併せて目標指標とすることを検討すべき。
|
|
4.業務部門、家庭部門及び運輸部門における取組の強化 |
民生・運輸部門への経団連等による業種横断的な取組を促すべき。具体的には、経団連加盟業種・会員企
業による(1)本社ビル等オフィスの削減目標設定や、(2)社員宅における環境家計簿の利用拡大。
|
|
|
「目達の評価・見直しに関する中間報告」
(19年9月中環審・産構審合同会合)
未策定業種に対する自主行動計画策定の働きかけ促進
【対象業種】ぱちんこ、ゲームセンター(警察庁)、信用組合、信用金庫、証
券(金融庁)、学校(文科省)、病院(厚労省)、情報サービス、リース、特
定規模電気事業者、家電量販店、大規模展示場(経産省)、産業廃棄
物処理、ペット小売り、新聞(環境省)
定性的目標の定量化等の促進
【対象業種】生保(金融庁)、通信、放送(総務省)、外食(農水省)、倉庫、バ
ス、タクシー、港運、舟艇(国交省)
政府による厳格なフォローアップの実施
【対象業種】銀行、生保、損保(金融庁)、ビール酒造、たばこ製造(財務省)、
製薬、生協(厚労省)、LPガス、商社(経産省)
目標引き上げの促進
【対象業種】食品製造(農水省)、化学、石油、セメント(経産省)、トラック、
住宅生産(国交省)
|