介護保険制度の被保険者・受給者範囲
に関する中間報告
介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議
平成19年5月21日
目 次
1 はじめに
2 被保険者・受給者の範囲についての議論の経緯等
(1)介護保険制度創設時の議論
(2)介護保険法改正(平成17年)時の議論
(3)社会保障制度全般の一体的見直し、障害者自立支援法の制定
(4)介護保険制度と障害者福祉制度の適用関係
(5)有識者調査及び関係団体ヒアリングの結果
3 「介護保険制度の普遍化」の意味
4 主要な論点
| (1) | 被保険者・受給者範囲の基本的方向 |
| (2) | 「介護保険制度の普遍化」の効果や「介護保険制度の普遍化」を目指す上で解決すべき課題 |
| (3) | 被保険者・受給者範囲を拡大するとした場合の制度設計の選択肢 |
5 今後の進め方
6 おわりに
1 はじめに
本有識者会議は、介護保険制度の被保険者・受給者の範囲の在り方に関する基本的課題等を検討するため、平成18年3月に設置され、これまで8回にわたって、精力的に審議を行ってきた。その審議過程においては、諸外国の制度調査、約2,900人を対象とした有識者調査、関係団体ヒアリングも行ってきた。
本有識者会議は、これまでの審議を踏まえ、中間的な意見を、以下のとおり取りまとめるものである。
2 被保険者・受給者の範囲についての議論の経緯等
(1)介護保険制度創設時の議論
| ○ | 介護保険制度の被保険者・受給者の範囲は、制度創設時にも大きな議論となった。高齢者介護・自立支援システム研究会報告(平成6年12月)は、「介護のリスクが高まる65歳以上の高齢者を被保険者かつ受給者とすることが基本と考えられるが、現役世代についても、世代間連帯や将来における受給者になるための資格取得要件として、被保険者として位置付けることも考えられる」とした。 |
| ○ | 老人保健福祉審議会の最終報告(平成8年4月)は、「高齢者介護問題が最大の課題となっていることから、65歳以上の高齢者を被保険者とし、保険料負担を求めることが適当である。この場合、高齢者介護の社会化は家族にとっても大きな受益であることなどから、社会的扶養や世代間連帯の考え方に立って、若年者にも負担を求めることが考えられる」、また、「若年世代の要介護状態については、公費による障害者福祉施策で対応するが、初老期痴呆などのような処遇上高齢者と同様の取扱いを行うことが適当なケースについては特例的に介護保険から給付すべきとの意見が有力であった」とした。 ただし、「介護サービスの必要性は年齢を問わないことや負担についての若年者の理解を得る観点から、若年者の介護サービスも社会保険化し、被保険者を20歳以上あるいは40歳以上とする意見」もあったとしている。 |
| ○ | 与党内での議論も経て老人保健福祉審議会に対して諮問された介護保険制度案大綱(平成8年6月)においては、「介護保険が対象とする老化に伴う介護ニーズは、高齢期のみならず中高年期においても生じ得ること、また、40歳以上になると一般に老親の介護が必要となり、家族という立場から介護保険による社会的支援という利益を受ける可能性が高まることから、40歳以上の者を被保険者とし、社会連帯によって介護費用を支え合うものとする」との最終的整理がなされた。 |
| ○ | 上記の最終的整理に基づき、介護保険の被保険者・受給者範囲は法定化されたが、平成9年に成立した介護保険法附則第2条は、施行後5年を目途として被保険者・受給者範囲を再検討すべき旨を規定した。 |
(2)介護保険法改正(平成17年)時の議論
| ○ | 平成17年の介護保険法改正の議論の際も、被保険者・受給者の範囲が大きな論点となり、障害者福祉施策をめぐる動向等も踏まえて、「対象年齢を引き下げるべきかどうか」が検討された。様々な角度からの審議の結果、社会保障審議会介護保険部会「被保険者・受給者の範囲」の拡大に関する意見(H16.12.10)では、「介護保険制度の将来的な在り方としては、要介護となった理由や年齢の如何に関わらず介護を必要とする全ての人にサービス給付を行い、併せて保険料を負担する層を拡大していくことにより、制度の普遍化の方向を目指すべきであるという意見が多数であった」とする一方、「被保険者・受給者の範囲の拡大については、極めて慎重に対処すべきであるという意見があった」とし、「その可否を含め国民的な合意形成や具体的な制度改革案についてできる限り速やかに検討を進め、結論を得ることが求められる」とした。 |
| ○ | その後、平成17年の介護保険法等の一部を改正する法律附則第2条第1項は、「政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成21年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。」と規定した。 |
(3)社会保障制度全般の一体的見直し、障害者自立支援法の制定
| ○ | 社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しを検討した「社会保障の在り方に関する懇談会」の報告書「今後の社会保障の在り方について」(平成18年5月26日)は、「介護保険制度の将来的な在り方としては、介護ニーズの普遍性の観点や、サービス提供の効率性、財政基盤の安定性等の観点から、年齢や要介護となった理由を問わず、すべての介護ニーズに対応する「制度の普遍化」を目指すことが方向として考えられる。他方で、これについては、若年層に負担を求めることについての納得感が得られるかどうか、保険料の滞納や未納が増加しないか、また、若年層の介護リスクを保険制度で支えることに理解が得られるかといった点にも留意する必要がある。このため、こうした個別の論点を精査し、プロセスと期限を明確化しつつ、関係者による更なる検討を進める必要がある。」とした。 |
| ○ | また、平成18年4月に施行された障害者自立支援法においては、3障害の制度格差の解消などが行われ、障害者福祉制度において多くの改革が行われた。 |
(4)介護保険制度と障害者福祉制度の適用関係
| ○ | ここで、介護保険制度と障害者福祉制度の適用関係について、改めて確認しておくと、現行制度においては、
という仕組みになっている。 実際に、既に65歳以上の高齢障害者については、こうした「組み合わせの仕組み」が適用されている。 |
[65歳以上の要介護状態にある障害者における介護保険制度と障害者福祉制度との関係]
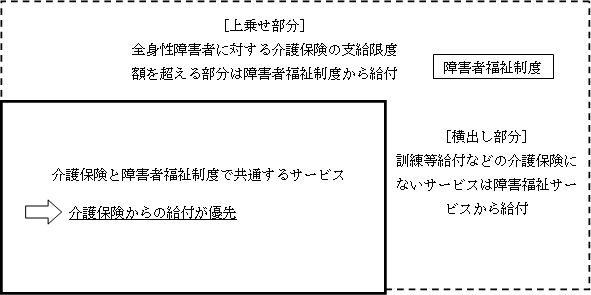
(5)有識者調査及び関係団体ヒアリングの結果
| ○ | 今回、実施された「介護保険制度の被保険者・受給者の範囲に関する有識者調査」(平成18年12月に約2,900人の有識者を対象に調査。約1,400人が回答。)において、「被保険者・受給者の範囲を将来的に拡大すべきかどうか」という質問に関しては、
という結果であった。 | ||||||||
| ○ | また、「被保険者(保険料負担者)と受給者の範囲は一致すべきかどうか」という質問に関しては、
という結果であった。 | ||||||||
| ○ | さらに、「仮に被保険者の範囲を拡大するとした場合、介護保険制度の受給の対象となる者の年齢をどのように考えるか」という質問に関しては、
という結果であった。 | ||||||||
| ○ | 「仮に被保険者の範囲を拡大するとした場合、保険料を負担する者の年齢をどのように考えるか」という質問に関しては、
という結果であった。 | ||||||||
| ○ | 本有識者会議で実施したサービス提供団体からのヒアリングでは、
| ||||||||
| ○ | 障害者関係団体からのヒアリングでは、
といった点が課題になるという意見や、「障害者の自己決定・自己選択を支える権利擁護システムの在り方を検討すべき」との意見もあった。 |
3 「介護保険制度の普遍化」の意味
| ○ | 「介護保険制度の普遍化」という用語は、平成17年の介護保険法改正の議論の際の社会保障審議会介護保険部会から使われ始め、これまでの議論においてもしばしば用いられてきたが、その概念は必ずしも明確となっていない。(後述の〔補論〕参照。)本有識者会議では、「介護保険制度の普遍化」とは、次のようなことを意味するものと理解した。 | ||||
| ○ | すなわち、「介護保険制度の普遍化」とは、現行制度を、「介護を必要とするすべての人が、年齢や要介護となった理由、障害種別の如何等を問わず、公平に介護サービスを利用できるような制度(「普遍的な制度」)に発展させること」を意味するものと理解する。 これを、さらに、給付と負担のそれぞれの面に着目して、捉え直すと、
介護保険制度という全国共通の社会保険システムを通じて、同時に実現しようとするのが「介護保険制度の普遍化」の意味するところと考える。 | ||||
| ○ | 負担面の普遍化により、現行40歳以上の被保険者の年齢区分が引き下げられ、収入のあるすべての者が社会連帯の精神で保険料を負担することになる。 ただし、その場合においても、低所得者層へ一定の配慮は必要である。 | ||||
| ○ | 給付面の普遍化の結果として、若年障害者等の介護ニーズに対しても高齢者の介護ニーズと共通する部分については、介護保険が適用されることとなる。 もちろん、「介護保険制度を普遍化」するとしても、これまでどおり「上乗せ」「横出し」部分については障害者福祉制度から給付されるものであり、障害者福祉制度の全体を介護保険制度に「統合」するということにはならない。 | ||||
| ○ | 以上、「介護保険制度の普遍化」の意味を明らかにしたが、「介護保険制度の普遍化」の理念に従って制度改正を行うとした場合の具体的時期や内容については、別途、十分な議論が必要である。 |
4 主要な論点
(1)被保険者・受給者範囲の基本的方向
| ○ | 現在の介護保険制度の枠組みは、40歳以上の者を被保険者としつつ、40歳から64歳までの者に対する給付については、「老化に起因する疾病」を理由とする場合に限定されており、実質的には「高齢者の介護保険」である。 | ||||||||||
| ○ | 被保険者・受給者範囲の基本的方向としては、現行の「高齢者の介護保険」の枠組みを維持するという考え方と、「介護保険制度の普遍化」を図るという考え方があり、どちらの方向を目指すかが大きな論点であるが、前回の改正時における議論においては、既述のとおり後者の意見が多数であった。 | ||||||||||
| ○ | これまでの議論において、「高齢者の介護保険」の枠組みを維持すべきとの立場から主張されている理由は、以下のとおりである。
| ||||||||||
| ○ | 一方、「介護保険制度の普遍化」の方向を目指すべきとの立場から主張されている理由は、以下のとおりである。
| ||||||||||
| ○ | また、今回実施した「介護保険制度の被保険者・受給者の範囲に関する有識者調査」や関係団体ヒアリングの結果は、2(5)で述べたとおりである。 |
(2)「介護保険制度の普遍化」の効果や「介護保険制度の普遍化」を目指す上で解決すべき課題
| ○ | 「介護保険制度の普遍化」の効果については、(1)において、「「介護保険制度の普遍化」の方向を目指すべきとの立場から主張されている理由」として挙げたとおりと考えられる。 | ||||||||
| ○ | 「介護保険制度の普遍化」を目指す上で解決すべき主な課題としては、
などが挙げられる。 | ||||||||
| ○ | 「介護保険制度の普遍化」によって達成される高齢者と障害者のサービスの相互利用(いわゆる「共生型サービス」)や相談窓口一本化については、
などから、サービス水準の低下を招かないよう配慮しつつ、その推進を積極的に図るべきである。 |
(3)被保険者・受給者範囲を拡大するとした場合の制度設計の選択肢
| ○ | 介護保険制度においては、被保険者としての負担と受給者としての給付は連動することが基本となること、また、有識者調査結果においても、「被保険者と受給者の範囲は原則として一致すべき」という意見が多かったこと等を踏まえると、被保険者・受給者の範囲を拡大した場合の制度設計の選択肢は、大別すると次の2類型に整理される。
| ||||
| ○ | 制度設計の具体化に当たっては、いずれの案についても、新たに保険料を負担する者の納得を得ることが重要な課題となるが、B類型については、(2)で述べた課題に加え、次のような点についても検討する必要がある。
| ||||
| ○ | その他、いずれの案についても、一括実施か段階実施かなど実施方法をどう考えるか、実施時期をどう考えるかという検討課題もある。 | ||||
| ○ | なお、A類型からB類型へと、順次、範囲拡大を図っていくという考え方もあり得る。 |
5 今後の進め方
| ○ | 「介護保険制度の被保険者・受給者範囲については、今後の社会保障制度全体(介護保険制度を含む。)の動向を考慮しつつ、将来の拡大を視野に入れ、その見直しを検討していくべきである」というのが、本有識者会議が到達した基本的考え方である。 また、被保険者・受給者範囲を拡大する場合の考え方としては、現行の「高齢者の介護保険」の枠組みを維持するという考え方(A類型)と、「介護保険制度の普遍化」を図るという考え方(B類型)があるが、本有識者会議においては、後者の「介護保険制度の普遍化」の方向性を目指すべきとの意見が多数であった。 |
| ○ | 一方、有識者調査の結果等をみると、障害者自立支援法や改正介護保険法の十分な定着を図る必要があること、介護保険給付の効率化を優先すべきであること、若年者の理解が得られず保険料徴収率が低下する可能性が高いこと、社会保障全体の給付・負担の動向を見極める必要があること等を理由として、将来的にはともかく、現時点においては被保険者・受給者範囲の拡大には慎重であるべきとの意見も依然として強い。また、当事者である障害者団体からも、被保険者・受給者範囲の拡大について、「介護保険制度の普遍化」の意味を含め、十分な理解が得られていない状況にある。 |
| ○ | したがって、平成17年の改正介護保険法附則の規定も念頭に置いて 制度設計の具体化に向けた検討作業を継続しつつ、当面、介護保険の被保険者・受給者範囲拡大に関する国民的合意形成に向けた取組に努める必要がある。 |
| ○ | いずれにせよ、いわゆる「制度の谷間」を含む現行制度の問題点について実態の把握に努めるとともに、介護保険の給付と負担に関する将来見通しや「介護保険制度の普遍化」の意味等について分かり易い資料を作成すること、直接語りかけ説明する機会をできるだけ多く設定すること等に留意すべきである。 |
| ○ | 上記のような取組と併せて、年齢に関係のない長期継続的な相談・支援を可能とするとともに、サービスの選択肢を拡大しアクセスを改善するため、高齢者と障害者のサービスの相互利用や相談窓口の一本化について、その推進を図るための具体的な措置をできるだけ早い時期に講ずるべきである。 |
6 おわりに
本有識者会議は、介護保険制度創設以来大きな課題である被保険者・受給者範囲の在り方について、精力的に議論を行ってきた。その結果として、これまで明確に定義されていなかった「介護保険制度の普遍化」の意味について概ね共通の理解を得るとともに、被保険者・受給者の範囲を拡大した場合の制度設計の類型について一定の整理を行うことができた。
今後、この中間報告を踏まえ、制度の普遍化に関するさらなる議論を深めつつ、介護保険制度の被保険者・受給者範囲の問題について、国民各層において幅広い議論が行われることを期待したい。
〔補論〕「介護保険制度の普遍化」に関連する議論の経緯について
| ○ | 高齢者介護・自立支援システム研究会報告(平成6年12月)は、「国民誰もが、身近に、必要な介護サービスがスムーズに手に入れられるようなシステムを構築していくことが強く求められている状況にある」として、「高齢者の自立支援を掲げ、そして、新たな基本理念の下で介護に関連する既存制度を再編成し、新介護システムの創設を目指すべき」ことを提言した。 その上で、新介護システムの在り方として、「介護のリスクが高まる65歳以上の高齢者を被保険者かつ受給者とすることが基本と考えられるが、現役世代についても、世代間連帯や将来における受給者になるための資格取得要件として、被保険者として位置付けることも考えられる」とした。 |
| ○ | 社会保障審議会障害者部会の「今後の障害保健福祉施策について(中間的な取りまとめ)」(平成16年7月)においては、「地域住民の視点からすると、誰しも障害の状態になりうるものであり、また、誰しも年老いていくものであることを考えると、障害種別、年齢、疾病等に関わりなく、同じ地域に住まう1人の住民として等しく安心して暮らせるように支え合うという地域福祉の考え方が重要になっている」とした。 その後、「今後の障害保健福祉策について(改革のグランドデザイン案)」(平成16年10月)において、「今後、障害者の福祉サービスについては、年齢、障害種別、疾病を超えて、市町村実施主体を一元化した上で、国、都道府県が効果的に支援しつつ市町村の創意と工夫により制度全体が効果的・効率的に運営される体系へと見直し、地域福祉の実現と全国的に均衡ある提供体制の確保の両立を図ることが必要である」とした。 |
| ○ | 社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成16年7月30日)では、「被保険者・受給者の対象年齢を引き下げる」ことについて審議を行った結果、積極的な考え方と慎重な考え方が出され、積極的な考え方として、「そもそも介護ニーズは高齢者に特有のものではなく、年齢や原因に関係なく生じうるものである。そうした介護ニーズの普遍性を考えれば、65歳や40歳といった年齢で制度を区分する合理性や必然性は見出しがたい。したがって、現行制度のように対象を老化に伴う介護ニーズに限定する考え方を改め、介護を必要とするすべての人が、年齢や原因、障害種別の如何や障害者手帳の有無を問わず、公平に介護サービスを利用できるような普遍的な制度への発展を目指すべきである。これにより、対象者の制限をなくし、全国民が連帯して全国民の介護問題を支える仕組みが実現され、国民の安心を支えるセーフティネットとしての役割を更に増すことになる」という考え方を示した。 その後、「被保険者・受給者の範囲」の拡大に関する意見(平成16年12月)では、「介護保険制度の将来的な在り方としては、要介護となった理由や年齢の如何に関わらず介護を必要とする全ての人にサービス給付を行い、併せて保険料を負担する層を拡大していくことにより、制度の普遍化の方向を目指すべきであるという意見が多数であった」とする一方、「被保険者・受給者の範囲の拡大については、極めて慎重に対処すべきであるという意見があった」とし、「その可否を含め国民的な合意形成や具体的な制度改革案についてできる限り速やかに検討を進め、結論を得ることが求められる」とした。 |
(参考1)
介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議メンバー
| 大島 伸一 | 国立長寿医療センター総長 | |
| ○ | 大森 彌 | 東京大学名誉教授 |
| 小方 浩 | 健康保険組合連合会副会長 | |
| 小島 茂 | 日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉局長 | |
| 貝塚 啓明 | 中央大学研究開発機構教授 | |
| 喜多 洋三 | 全国市長会介護保険対策特別委員会委員長(大阪府守口市長) | |
| ◎ | 京極 高宣 | 国立社会保障・人口問題研究所所長 |
| 紀陸 孝 | 日本経済団体連合会専務理事 | |
| 関 ふ佐子 | 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科准教授 | |
| 竹中 ナミ | 社会福祉法人プロップ・ステーション理事長 | |
| 堀 勝洋 | 上智大学法学部教授 | |
| 松下 正明 | 東京都立松沢病院顧問 | |
| 矢田 立郎 | 兵庫県国民健康保険団体連合会理事長(兵庫県神戸市長) | |
| 山本 文男 | 全国町村会会長(福岡県添田町長) |
(五十音順、敬称略)
◎は座長、○は座長代理
(参考2)
介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議
のこれまでの議論の経過
第1回(平成18年3月6日)
○ 被保険者・受給者の範囲をめぐる議論の経緯について
○ 今後の議論の進め方(案)について
第2回(平成18年5月31日)
○ 障害者自立支援法について
○ 障害者の雇用施策について
○ 社会保障の在り方に関する懇談会報告書について
第3回(平成18年7月25日)
○ 諸外国における介護と障害者施策について
○ 年齢や障害種別にかかわらないサービス提供の取組みについて
第4回(平成18年11月22日)
○ 関係者からのヒアリング(1)
サービス提供側8団体
第5回(平成19年2月5日)
○ 関係者からのヒアリング(2)
障害者関係団体8団体
第6回(平成19年3月7日)
○ 有識者調査及び外国調査の結果報告
第7回(平成19年4月10日)
○ とりまとめに向けた論点整理
第8回(平成19年5月21日)
○ 中間とりまとめ
(参考3)
有識者会議においてヒアリングを行った団体一覧
- 社団法人日本医師会
- 社団法人日本看護協会
- 特定非営利活動法人デイサービスこのゆびとーまれ
- 社会福祉法人南山城学園
- 社団法人全国老人福祉施設協議会
- 社団法人全国老人保健施設協会
- 社団法人日本介護福祉士会
- 社団法人日本社会福祉士会
- 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会
- 財団法人全日本ろうあ連盟
- 社団法人全国脊髄損傷者連合会
- 特定非営利活動法人DPI日本会議
- 日本障害者協議会
- 社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会
- 財団法人全国精神障害者家族会連合会
- 社会福祉法人日本盲人会連合
(ヒアリング順)