(資料4)
「配偶子・ヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントのあり方について」の検討にあたっての整理すべき事項
○生殖補助医療研究における提供医療機関と実施機関の例
(1)提供医療機関と研究実施機関が別々の場合 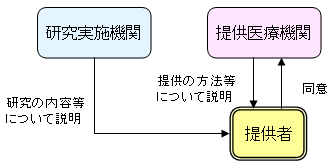 |
(2)提供医療機関と研究実施機関が同一の場合 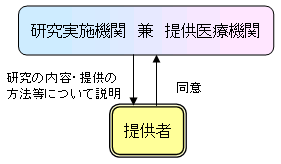 |
○主に整理すべき論点((2)の場合)
<インフォームド・コンセントの手続き(医療の過程で行われる場合)>
A.主治医と研究責任者が同一の場合
- 提供者へ圧力がかかる可能性が否定できないことから、主治医がインフォームド・コンセントを受けることを認めないこととするか。この場合、研究の内容や提供の方法についての説明は、提供又は研究に関与しない第三者(もしくは第三の機関)から行うこととするか。
- または、主治医がインフォームド・コンセントを受けることを認めることとするか。
B.主治医と研究責任者が異なる場合
- 提供者へ圧力がかかる可能性が否定できないことから、主治医がインフォームド・コンセントを受けることを認めないこととするか。この場合、研究の内容や提供の方法についての説明は、提供又は研究に関与しない第三者(もしくは第三の機関)から行うこととするか。
- または、主治医がインフォームド・コンセントを受けることを認めることとするか。
<機関内倫理審査委員会>
- 研究実施機関と提供医療機関が同一の場合、機関内倫理審査委員会のあり方はどのように考えるか。研究計画について審査するものと提供の妥当性について審査するものを個別に設けることとするか。
<個人情報保護>
- 個人情報保護の観点から、研究実施機関と提供医療機関を切り離す必要はあるか。
- 研究実施機関と提供医療機関が同一の場合、個人情報保護の枠組みをどのように考えるか。
(参考)「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成13年3月29日)における個人情報の取扱い
○ 機関の長は、研究において個人情報を取り扱う場合、その保護を図るため、個人情報管理者を置く。
○ 個人情報管理者は、試料等又は遺伝情報を匿名化し、その際作成した対応表等の管理、廃棄を適切に行い、個人情報を厳重に管理。
○ 個人情報管理者は、匿名化の際に取り除いた個人情報を外部の機関や研究部門に提供してはならない。