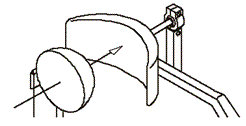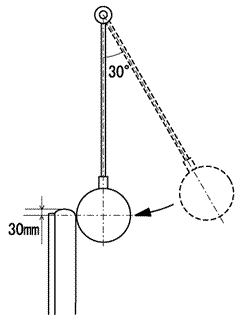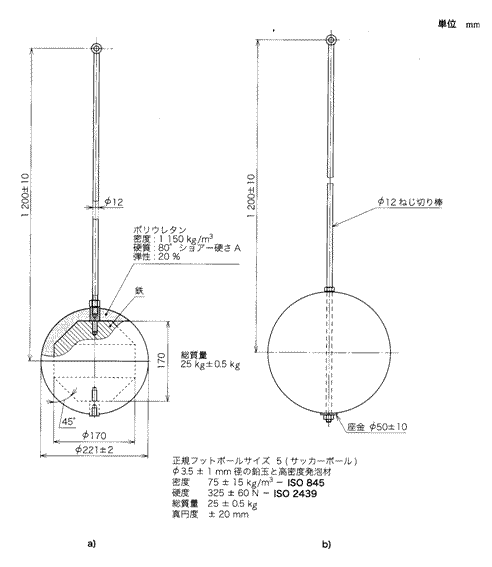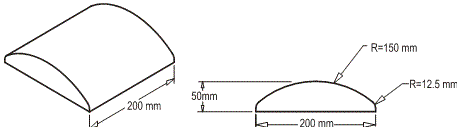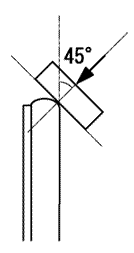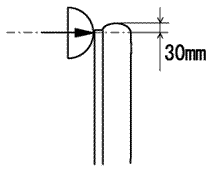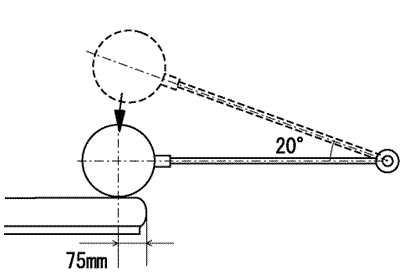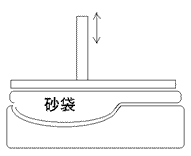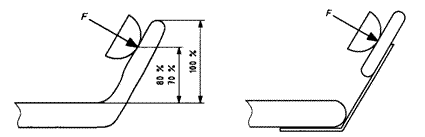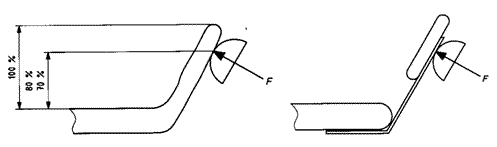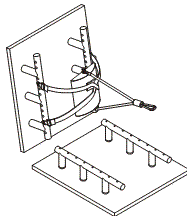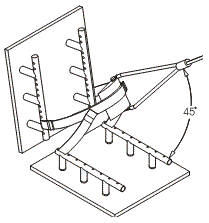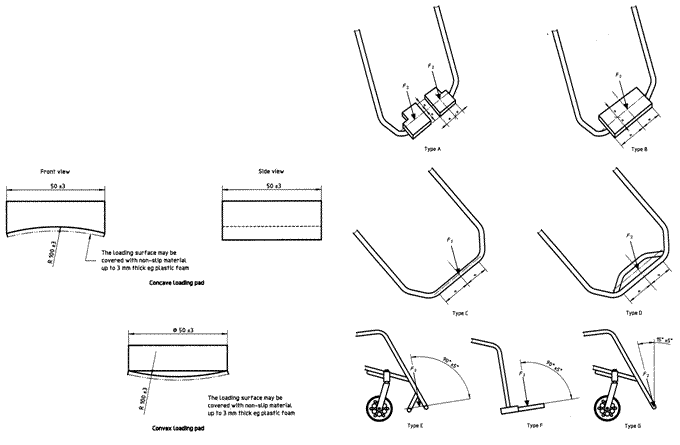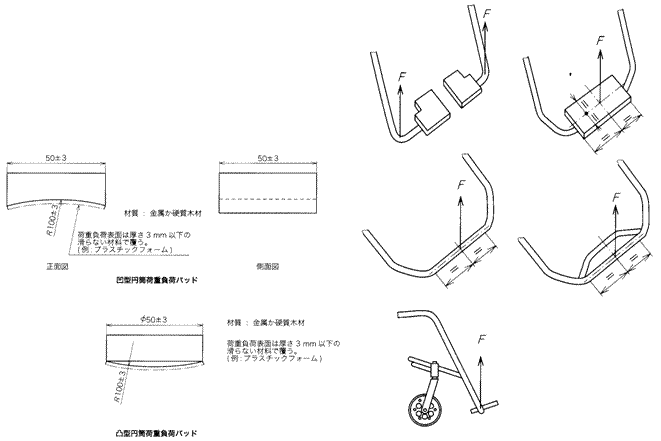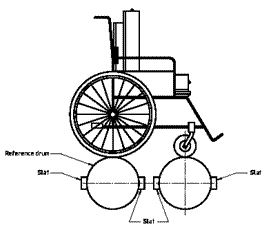平成18年度 第2回 補装具評価検討会 議事要旨
(別紙)
平成19年3月23日
座位保持装置部品の認定基準及び基準確認方法の策定について
厚生労働省では、障害者自立支援法に基づき補装具として給付している義肢、装具及び座位保持装置の製作に係る部品について、一定の工学的評価と臨床的評価を行い、安全性と有効性が確認されたものを完成用部品として指定しています。
平成18年11月に『補装具評価検討会』を設置し、座位保持装置に係る完成用部品として認定するための工学的評価基準とその確認方法の見直しについて検討してきたところですが、本検討会において「座位保持装置部品の認定基準及び基準確認方法(案)」がとりまとめられ、了承されましたので、情報提供致します。
社会・援護局障害保健福祉部
企画課地域生活支援室
| 担当 | 高木憲司 (内3089) 阿南尚登 (内3089) |
|
| 代表番号 03-5253-1111 | ||
座位保持装置部品の認定基準及び基準確認方法
1.基準の目的
この基準は、座位保持装置部品の安全性及び使用者が誤った使用をしないための必要事項を定め、座位保持装置を使用する者の身体に対する危害防止及び生命の安全を図ることを目的とする。
2.適用範囲
この基準は、主として補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準に新規に取り入れるために申請された座位保持装置の完成用部品について適用する。
3.引用規格
次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。
JIS T9201:2006 手動車いす
(初版は「JIS T9201:1998 手動車いす」を引用)
4.改訂履歴
・平成16年1月6日 初版
・平成19年4月2日 改訂版
(修正内容:一部の項目の修正と引用規格の改定による修正)
5.安全性品質
座位保持装置部品の安全性品質は、次のとおりとする。
| 項目 | 認定基準 | 基準確認方法 |
| 外観 及び 構造 |
座位保持装置部品の外観及び構造は次のとおりとする。 | |
| (1)仕上げは良好で、各部に変形、がた、亀裂、溶接不良などがなく、組み立てを含め、人体に触れる部分には、鋭い突起又は角部などがないこと。 | (1)目視及び触感により確認すること。 | |
| (2)表面処理をしている面には、素地の露出、はがれ、さびなどの不良がなく、安全性を損なわないこと。 | (2)目視及び触感により確認すること。 | |
| (3)調節機構を有するものにあっては調節が容易で、使用中容易に緩まない構造であること。 | (3)操作などにより確認すること。 | |
| (4)折りたたみ式のものにあっては、操作は容易で、使用中に容易に外れたり、折りたたまれない構造であること。 | (4)操作などにより確認すること。 | |
| (5)座面を有するものにあっては、使用中容易に外れたり折りたたまれない構造であること。 | (5)操作などにより確認すること。 | |
| (6)可動部や調節機構を有する部分などにおいて、指、手、足、頭などの体の一部が挟まれない構造になっていること。 | (6)目視及び操作などにより確認すること。 | |
| (7)ベルトとの取り付け部などは容易に外れないこと。 | (7)操作などにより確認すること。 | |
| (8)頭部側方パッドなど比較的小さなパッド類は容易に外れないこと。 | (8)操作などにより確認すること。 |
試験対象部品単体で試験することを原則とするが、必要に応じて固定用の各部品を組み合わせて以下に規定された試験を実施すること。試験用治具、試験機器については附属書を参照すること。
| 項目 | 認定基準 | 基準確認方法 | ||||||
| 頭部支持部 | ||||||||
| 後方静的 荷重試験 |
後方静的荷重試験を行った時、機能不全が起こらないこと。また、200Nまで破壊、機能不全が起こらない場合、破壊または機能不全状態まで荷重を増加して行い、その時、使用者の身体に損傷を与えるような鋭利な状態にならないこと。 |
|
||||||
| 衝撃試験 | 頭部支持部に衝撃試験を行い、機能不全が起こらないこと。 | 当面の間、頭部支持部、衝撃試験については適用を留保する。衝撃試験は実施しないが、後方静的荷重試験結果によりある程度はカバーできるため、後方静的荷重試験結果により判断するものとする。 | ||||||
| 背支持部 | ||||||||
| 後方衝撃 試験 |
背支持部に後方への衝撃試験を行い、機能不全が起こらないこと。 |
|
||||||
| 繰り返し 荷重試験 |
背支持部に後方への繰り返し荷重試験を行い、機能不全が起こらないこと。 |
|
||||||
| 後方静的 荷重試験 |
背支持部に後方への静的荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。 |
|
||||||
| 前方静的 荷重試験 |
背支持部に前方への静的荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。 |
|
||||||
| 座支持部 | ||||||||
| 衝撃試験 | 座支持部に対して座部衝撃試験実施し、機能不全が起こらないこと。 |
|
||||||
| 繰り返し 荷重試験 |
座支持部に対して繰り返し荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。 |
|
||||||
| 側方支持部(胸部、大腿外転・内転、下腿) | ||||||||
| 外側方向 負荷静的 荷重試験 と内側方 向負荷静 的荷重試 験 |
側方支持部品に対して、外側方向負荷静的荷重試験と内側方向負荷静的荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。 |
|
||||||
| 大腿内転防止支持部 | ||||||||
| 内側方向 静的荷重 試験 |
大腿内転防止支持部に内側方向静的荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。 | 大腿内転防止支持部に静的荷重を負荷する。負荷位置は膝支持部の中央±10mmの位置に内側方向へ負荷すること。子供用250N、大人用500Nで10秒間の負荷を10回繰り返すこと。 | ||||||
| 前方体幹支持部 | ||||||||
| 前方静的 荷重試験 |
前方体幹支持部品に対して、前方静的荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。 |
|
||||||
| 前方骨盤支持部 | ||||||||
| 前方静的 荷重試験 |
前方骨盤支持部品に対して、前方静的荷重試験を実施し、機能不全が起こらないこと。 |
|
||||||
| 足部支持部 | ||||||||
| 下方静的 荷重試験 |
下方静的荷重試験を行った時、機能不全が起こらないこと。 |
|
||||||
| 上方耐荷 重試験 |
上方耐荷重試験を行った時、機能不全が起こらないこと。目視、触感などで確認する。 |
|
||||||
| 構造フレーム(座背支持部がなければ、推奨する座背をつけて実施する) | ||||||||
| 構造フレームすべてに共通する項目試験 | ||||||||
| バックサ ポート斜 め耐衝撃 性試験 |
構造フレーム背支持部耐衝撃性試験は次のとおりとする。 バックサポート斜め耐衝撃性試験を行った後、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 |
JIS T9201に定めるバックサポート斜め耐衝撃性試験により確認すること。 ティルト・リクライニング機構がある場合も実施し、その時の背部角度は垂直またはそれに近い角度とすること。 |
||||||
| 静的安定 性試験 |
静的安定性は10度の斜面上で前方、後方及び左右方向に安定であること。 | JIS T9201に定める静的安定性試験により確認すること。 ティルト・リクライニング機構がある場合は、背部を後方に最も倒した状態と背部角度が垂直またはそれに近い角度の2条件で実施すること。 |
||||||
| 屋外車輪付構造フレーム | ||||||||
| 走行耐久 性試験 |
走行耐久性試験を行った後、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 |
|
||||||
| 静止力試 験 |
屋外構造用フレームは7度の斜面上に駐車用のブレーキをかけた状態で前方及び後方に安定であること。 | JIS T9201に定める静止力試験により確認すること。ただし子供用の場合は、33kgのおもりを座面の中央部分に載せて同様の試験を行うこと。 ティルト・リクライニング機構がある場合は、背部を後方に最も倒した状態と背部角度が垂直またはそれに近い角度の2条件で実施すること。 |
||||||
| 屋内車輪付構造フレーム | ||||||||
| 走行耐久 性試験 |
走行耐久試験を行った後、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 | JIS T9201に定める走行耐久試験により確認すること。ただし子供用の場合は、33kgのおもりを座面の中央部分に載せて同様の試験を行うこと。試験回数はJISの規定によらず、大人用、子供用とも10000回とすること。 ただし、車輪がすべてキャスターの構造フレームの場合は、対象外とすること。 ティルト・リクライニング機構がある場合、背支持部を水平から30度まで倒して実施すること。なお、30度まで倒れない場合は最大まで倒して実施すること。 |
||||||
| 構造フレームにティッピングレバー・グリップ・アームレストが装着している場合 | ||||||||
| ティッピングレバー | ||||||||
| ティッピ ングレバ ー耐荷重 試験 |
ティッピングレバー耐荷重試験を行った後、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 | JIS T9201に定めるティッピングレバー耐荷重試験により確認すること。ただし、負荷荷重を子供用330N、大人用750Nとする。 | ||||||
| グリップ | ||||||||
| 手押しハ ンドル上 方耐荷重 試験 |
手押しハンドル上方耐荷重試験を行った後、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 | JIS T9201に定める手押しハンドル上方耐荷重試験により確認すること。 | ||||||
| グリップ 耐離脱性 試験 |
グリップ耐離脱性試験を行った後、グリップが抜けないこと。 | JIS T9201に定めるグリップ耐離脱性試験により確認すること。ただし、負荷荷重を子供用330N、大人用750Nとする。 | ||||||
| アームレスト | ||||||||
| アームレ スト下方 耐荷重試 験 |
アームレスト下方耐荷重試験を行った後、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 | JIS T9201に定めるアームレスト下方耐荷重試験により確認すること。ただし、負荷荷重を子供用330N、大人用750Nとする。 | ||||||
| アームレ スト上方 耐荷重試 験 |
アームレスト上方耐荷重試験を行った後、各部に破損、外れ及び使用上支障のある変形がないこと。 | JIS T9201に定めるアームレスト上方耐荷重試験により確認すること。ただし、負荷荷重を子供用330N、大人用750Nとする。 | ||||||
| 支持部(座背クッション・ベルト) | ||||||||
| 生体適合 性 |
使用材料には、有害なものを含まないこと。 | |||||||
| 難燃性 | 難燃性の素材を使用していること。 | |||||||
附属書1 座位保持装置部品試験の詳細規定
1.座位保持装置部品の設置
構造フレームまたは車いすに装着するために座位保持装置製造者マニュアルに従い、規定された試験装置に座位保持装置や座位システムを固定すること。もし、取り付け具間隔が規定されていないなら背支持は150mmで、座は380mmで設置すること。
座位保持装置が製造者からのシステムとしての取り付け具が供給されているなら、ユニットとして取り付け具や支持面を組み立てる。装着機器での装着を意図した座位保持装置で、装着機器がない場合には、代用装着機器を使用すること。
フックやループなど多種な固定具は試験での座位保持装置の固定を補助するために使用されるが、試験手法を妨害しないようにすること。
すべての固定は製造者マニュアルに規定された方法で行うこと。取り付け位置が調節可能な場合は、最もよく使うであると思われる位置に取り付けて試験を行うこと。製造者マニュアルで規定されたすべての絞め金具は絞めること
試験された座位保持装置の取り付け状態は記録すること。
本基準内に治具などの寸法、形状などの規定がない場合は、適当なものを使用して良い。ただし、使用したものについて写真などで記録すること。
2.機能不全の定義
| SGでは使用上支障のある緩み、変形などがないことと規定されているが、本基準では以下のように規定する。 | ||||||||||||||
|
3.車輪付き構造フレームに各種機構がついた場合の走行耐久試験
機構を持っている場合、基本的にそれぞれの試験で最大の負荷がかかる位置で実施すること。
リクライニング機構がある場合
リクライニング機構がある場合は、最大に起こした状態と水平から30度に背フレームを保持したままの状態との2通りを試験する。ただし、そこまで角度が取れない場合は最大に後方へ倒した状態で試験を行う。
トランスファなどを考慮した前方への傾斜が可能な場合、水平から95度後方に背フレームを倒した状態で試験を実施すること。
ティルト機構がある場合
ティルト機構がある場合は、最大に起こした状態と水平から30度に背フレームを保持したままの状態との2通りを試験する。ただし、そこまで角度が取れない場合は最大に後方へ倒した状態で試験を行う。
トランスファなどを考慮した前方への傾斜が可能な場合、水平から95度後方に背フレームを倒した状態で試験を実施すること。
上下機構がある場合
上下機構がある場合は、最大高さで試験を実施する。
屋外用車輪付き構造フレーム
屋外用車輪付き構造フレームはJIS T9201の走行耐久試験の手法に準拠する。
屋内用車輪付き構造フレーム
屋内用車輪付き構造フレームはJIS T9201の走行耐久性試験の手法に準拠する。ただし、車輪がすべてキャスターの構造フレームであれば、試験の対象外とすること。
4.各種機構がついた構造フレームの傾斜での安定性と停止力試験
基本的にそれぞれの試験で最も安定性や停止力が落ちる状態で試験を実施すること。
リクライニング機構がある場合
リクライニング機構がある場合は、背部を後方に最も倒した状態と背部角度が垂直またはそれに近い角度の2条件で試験すること。
ティルト機構がある場合
ティルト機構がある場合は、背部を後方に最も倒した状態と背部角度が垂直またはそれに近い角度の2条件で試験すること。
上下機構がある場合
上下機構がある場合は、最大高さで試験を実施すること。
5.試験報告書
| 試験報告書は次の内容を含むこと ・試験種目の参照部 | ||||||||||||||||||||||||
|
6.試験が免除できる条件
| ・ | 同一タイプの部品―フック
|
||
| ・ | 同一負荷部位―頭部支持部
|
||
| ・ | 車いすフレーム装着に関する部品
|
7.試験方法
| ・ | 静的試験の圧子の速度は15mm/分以下とすること。 |
| ・ | 頭部支持部などの接合部を手で締めるタイプは概外観・構造の3)で規定する。なお、今回は調節部位を仮固定して試験を実施してよいが、次回より3)を遵守し、機能不全の状態に合わせる。 |
| ・ | 負荷時に使用する圧子はパッドの角でカバーなどを損傷しない位置で、基本は参考図のとおりとする。 |
附属書2 座位保持装置部品試験用治具
試験固定装置
試験中、座位保持装置を固定化させるために規定された手段である。長さ、幅、そして半径の計測の許容量は他に記述されていなければ寸法の±5%以内とする。
固定試験フレーム
座位保持装置を固定するための車いすフレームを類似させる手段であり、座位保持装置付属品の角度調整が最大に出来るようになっている。固定試験装置の例を図A1に示す。
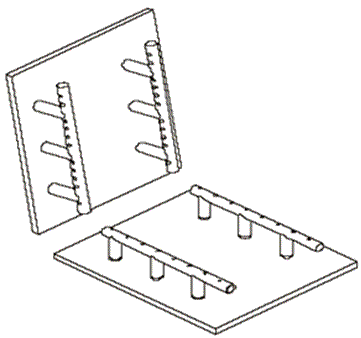 |
| 図A1 固定試験装置例 |
固定代用支持面
固定水平面での使用を意図した座位保持装置の付属品を安定化させる手段で、固定水平支持面以外には使用できない。代わりの固定支持面の例として図A2に示す。各種付属品のマウントに対応するために、穴を開けたり、他の物が使用できる。
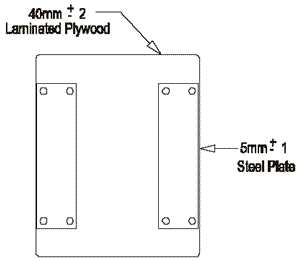 |
| 図A2 試験付属装置のための代わりの固定支持面の例 |
曲線固定面
スリングシートや背支持の固定材で曲面を模擬するための手段。スリング状態での使用を意図した座面、背面、または背支持クッションを固定するために使用される面。半径1000mm±100mmの曲線固定面の例が図A3に示される。
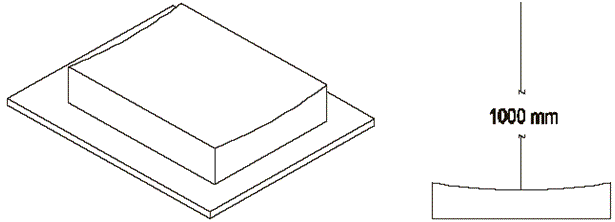 |
| 図A3 スリングシート面を模擬した半径1000mmの曲線固定面の例 |
固定水平面
固い材質で平らな座や背支持を模擬した手段。面は平らな支持面での使用を意図した座クッション、背クッション、背支持を安定化させるために使用される。
仮の装着品
装着部品の使用を意図した、しかし装着部品なしで供給された座位保持装置の固定のための手段。仮の装着部品は固定試験装置への座位保持装置の設置ができる。仮の装着部品の例を図A4に示す。
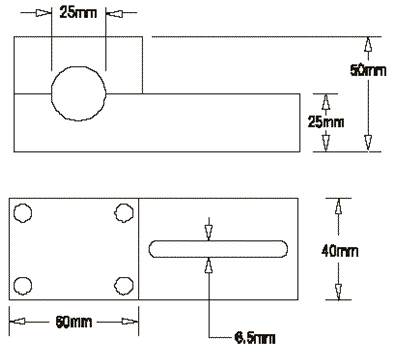 |
| 図A4 仮付属品の例 |
荷重パッド
座位保持装置への荷重の作用を規定した手段。
200mmx200mm凸荷重パッド
図A5に示すような金属または木の固定材質で作られた荷重パッド。
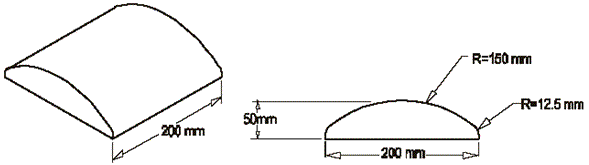 |
| 図A5 200mm×200mmの凸荷重パッドの例 |
200mmx100mmの凸荷重パッド
図A6で示された金属または木での固定材質で作られた荷重パッド。
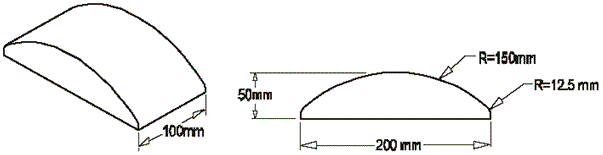 |
| 図A6 200mm×100mmの凸荷重パッドの例 |
Adjustable convex loading pad, 調整凸荷重パッド
図A7に示された凸面要素と調整幅を持った荷重パッド
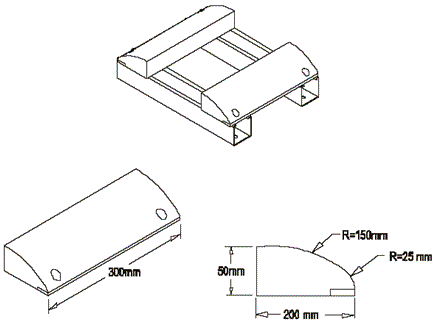 |
| 図A7 調整凸荷重パッド |
調整可能上部体幹荷重パッド
図A8に示す上部体幹を模擬した調整形状を持つ荷重パッド。
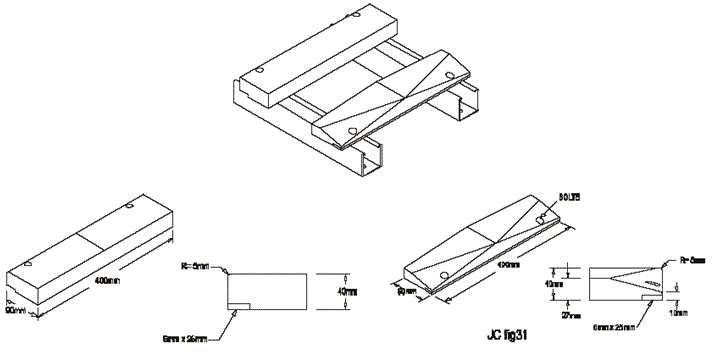 |
| 図A8 上部体幹荷重パッドの例 |
50mmx100mm凸荷重パッド
図A9に示された凸荷重パッド。金属または硬い木のような固体金属で作られた荷重パッド。
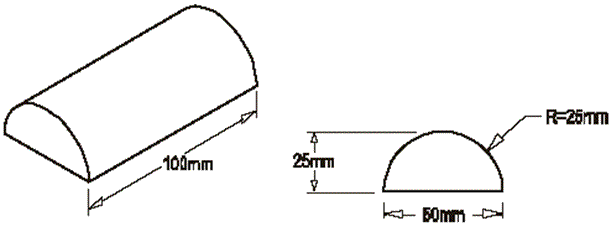 |
| 図A9 50 mm x 100 mm凸荷重パッドの例 |
凸荷重パッド
図A10に示された凸荷重パッド。金属または硬い木のような固体金属で作られた荷重パッド。
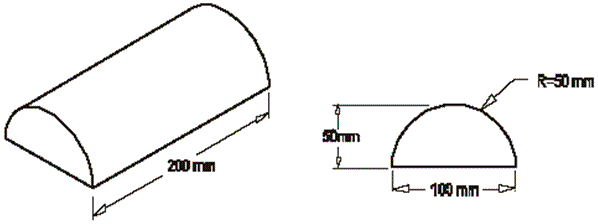 |
| 図A10 凸荷重パッド |
75mmx75mm凹荷重パッド
図A11に示された荷重パッド。金属または硬い木のような固体金属で作られた荷重パッド
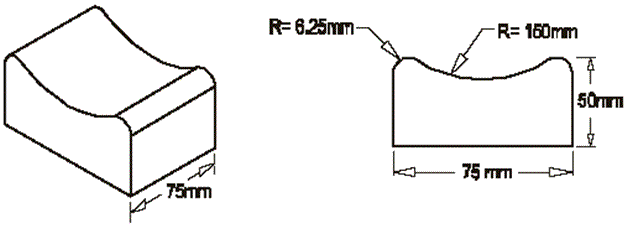 |
| 図A11 75mm×75mm凹荷重パッド |
75mm半球荷重パッド
図A12に示された金属または木のような硬質材で作られた荷重パッド。
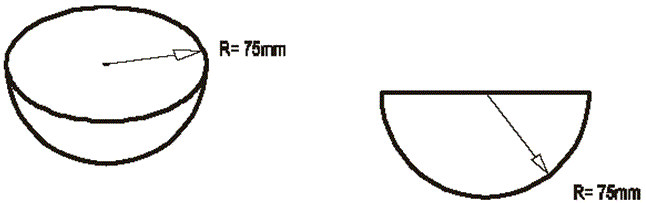 |
| 図A12 75mm半球荷重パッドの例 |