| 第3回 企業年金研究会 | 資料3 |
| 平成18年11月27日 |
| 確定拠出年金制度の現状認識と制度改善に向けての要望 |
| 2006年11月27日 特定非営利活動法人 確定拠出年金教育協会 代表 斎藤 順子 |
ご報告の概要(主として企業型確定拠出年金制度)
“ハード面(OS)の充実とともに、実効性を高めるソフト面の充実を”
| 1. | 企業担当者の制度改正要望の内訳
|
||
| 2. | 導入後の事業会社の状況
|
||
| 3. | 加入者の制度利用実態、運用実態
|
| 1. | 企業担当者の制度改正要望の内訳 |
| ■ | 2005年と2006年の比較 |
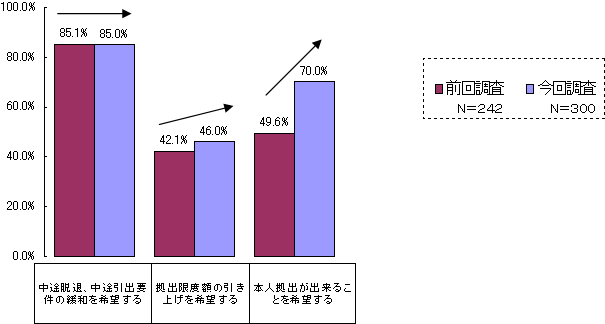
| 「貴社の確定拠出年金制度を充実させていくために制度改正を希望する事項」として、中途脱退、中途引出要件の緩和への希望が最も高く、大多数となっている。次いで、本人拠出が出来ることの希望が過半数を占め、前回の調査との比較でも比率が高くなり、制度進行に呼応して注目される改正事項として浮上してきている。 |
| ■ | 制度改正要望の理由はなにか? |
|
→ |
|
|||||
|
→ |
|
|||||
|
→ |
|
| 1. | 企業担当者の制度改正要望の内訳〜中途脱退〜 |
| ■ | 中途脱退、中途引出要件の緩和意向 全体 |
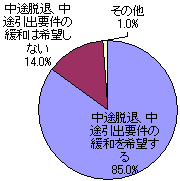
| ● | 従業員規模、制度導入時期別を問わず、中途脱退、中途引出要件の希望は高い。 若干、新規制度導入企業での希望が8割を下回る程度。 |
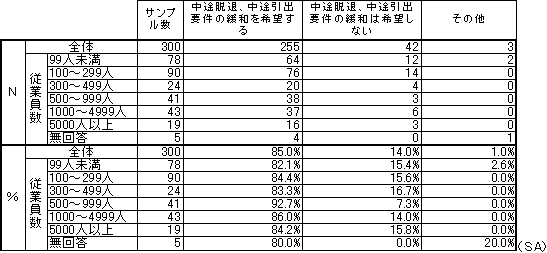 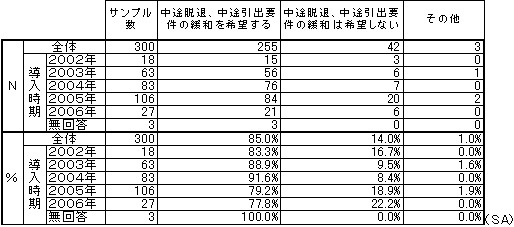 |
| 1. | 企業担当者の制度改正要望の内訳〜中途脱退・中途引出〜 |
| ■ | 中途脱退、中途引出要件の緩和の希望理由 |
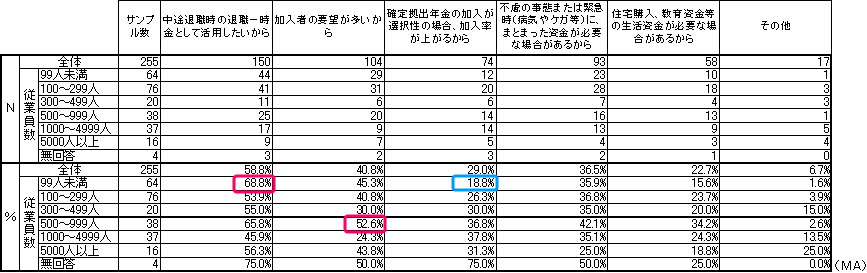 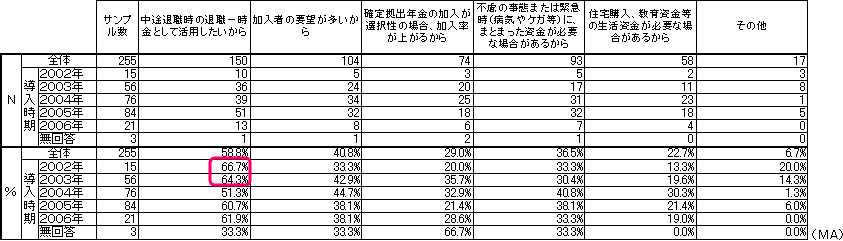 |
| ■ | 中途引出要件の緩和の容認水準 |
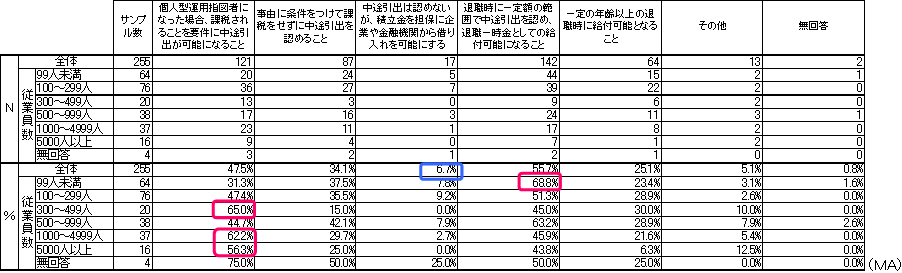 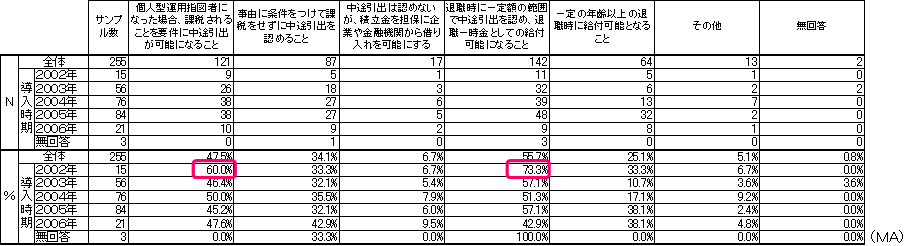 |
| 1. | 企業担当者の制度改正要望の内訳〜拠出限度額〜 |
| ■ | 拠出限度額の引き上げ意向 |
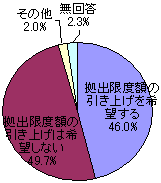
| ● | 500人以上の従業員規模の企業で、拠出限度額の引き上げ希望が高くなっている。企業規模が大きくなるほど、他の企業年金が多くあるため、確定拠出年金の割合に制約を受けることをうかがわせている。 |
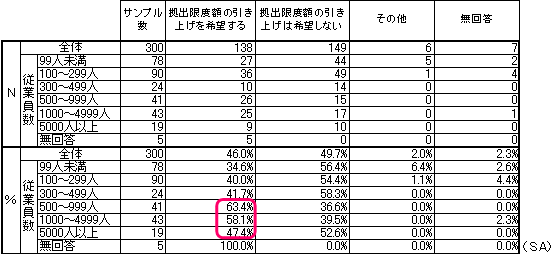 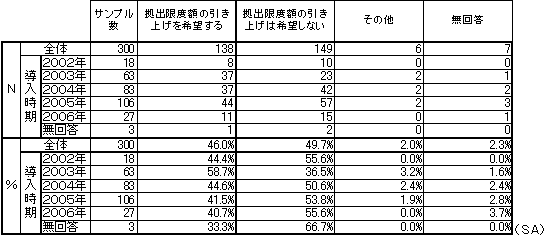 |
| ■ | 拠出限度額の引き上げの希望理由 |
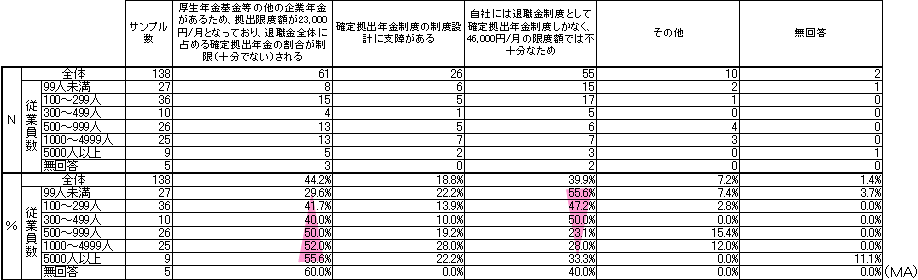 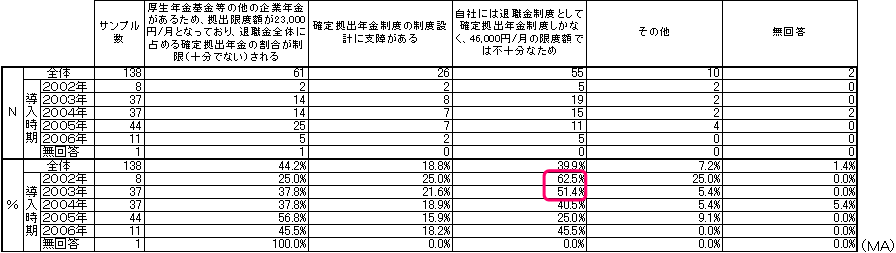 |
| 1. | 企業担当者の制度改正要望の内訳〜本人拠出〜 |
| ■ | 本人拠出の改正意向 |
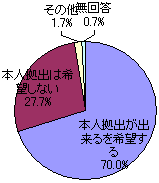
| ● | 早期導入企業で、本人拠出ができることを希望する傾向が高くなっている。 |
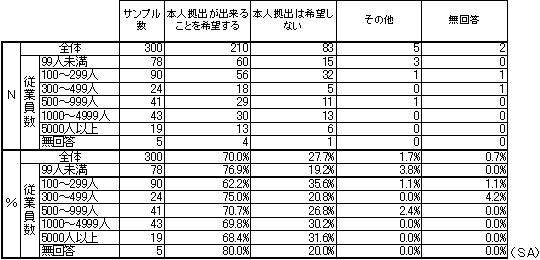 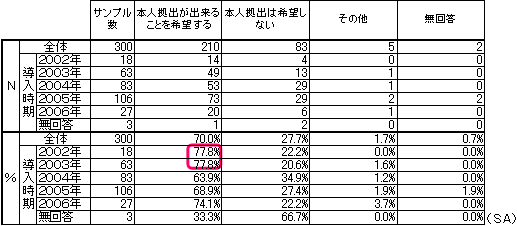 |
| ■ | 本人拠出の改正の希望理由 |
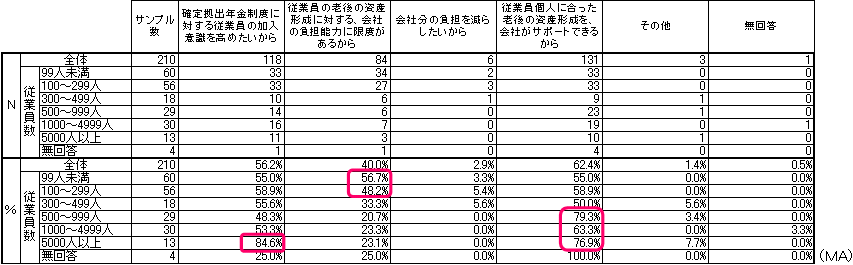 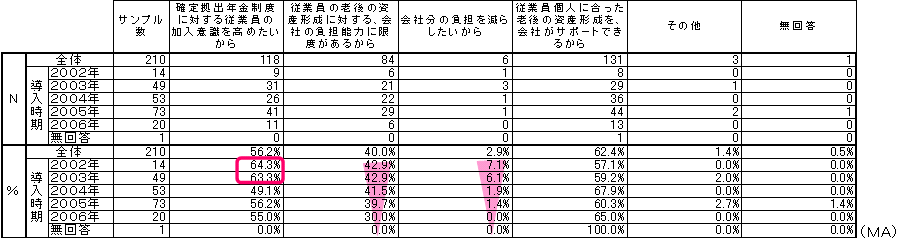 |
| 1. | 企業担当者の制度改正要望の内訳〜本人拠出と継続教育〜 |
| ■ | 本人拠出の希望と継続教育の実施有無 |
| ● | 過去に継続教育の実施経験のある企業で、本人拠出ができることを希望する比率が高くなっている。 |
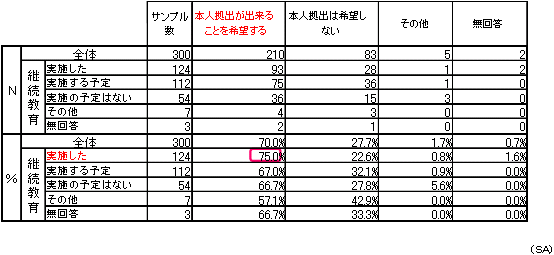
| 2. | 導入後の事業会社の状況〜現状評価〜 |
| ■ | 確定拠出年金導入後の現状評価 |
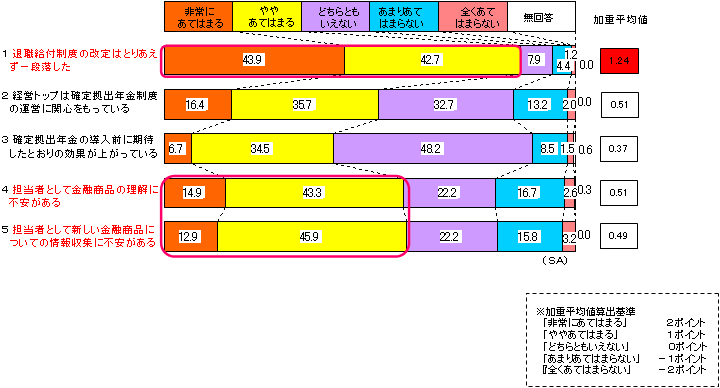
| ● | 肯定的な評価が最も高かった項目は、「退職給付制度の改正はとりあえずひと段落した」で、全体の8割以上が「あてはまる」との回答している。しかし、一方では、「金融商品の理解に不安がある」「新しい金融商品についての情報収集に不安がある」に「あてはまる」と不安材料として挙げている担当者も6割弱となっている。また、「確定拠出年金の導入前に期待したとおりの効果が上がっている」では、「あてはまる」との回答している担当者が4割強にとどまり、「どちらともいえない」が約半数となって、現状評価での反応は鈍いものとなっている。 |
| 2. | 導入後の事業会社の状況〜継続教育〜 |
| ■ | 継続教育に関する現状 |
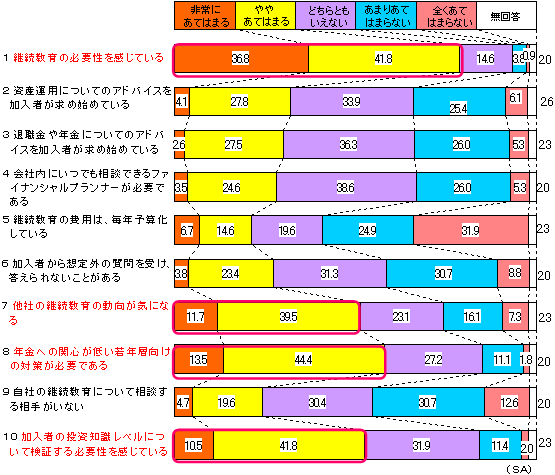
| ● | 継続教育に関する現状としては、8割弱の企業の担当者が「継続教育の必要性を感じている」と回答している。また、「年金への関心が低い若年層向けの対策が必要である」「加入者の投資知識レベルについて検証する必要性を感じている」「他社の継続教育の動向が気になる」でも過半数で肯定的な意向を示している。しかし、「継続教育の費用は、毎年予算化している」に該当する企業は、2割程度にとどまっている。 他項目に関しては、肯定と否定が2分化され、企業間での格差をうかがうことができる。 |
| ■ | 継続教育の実施理由 |
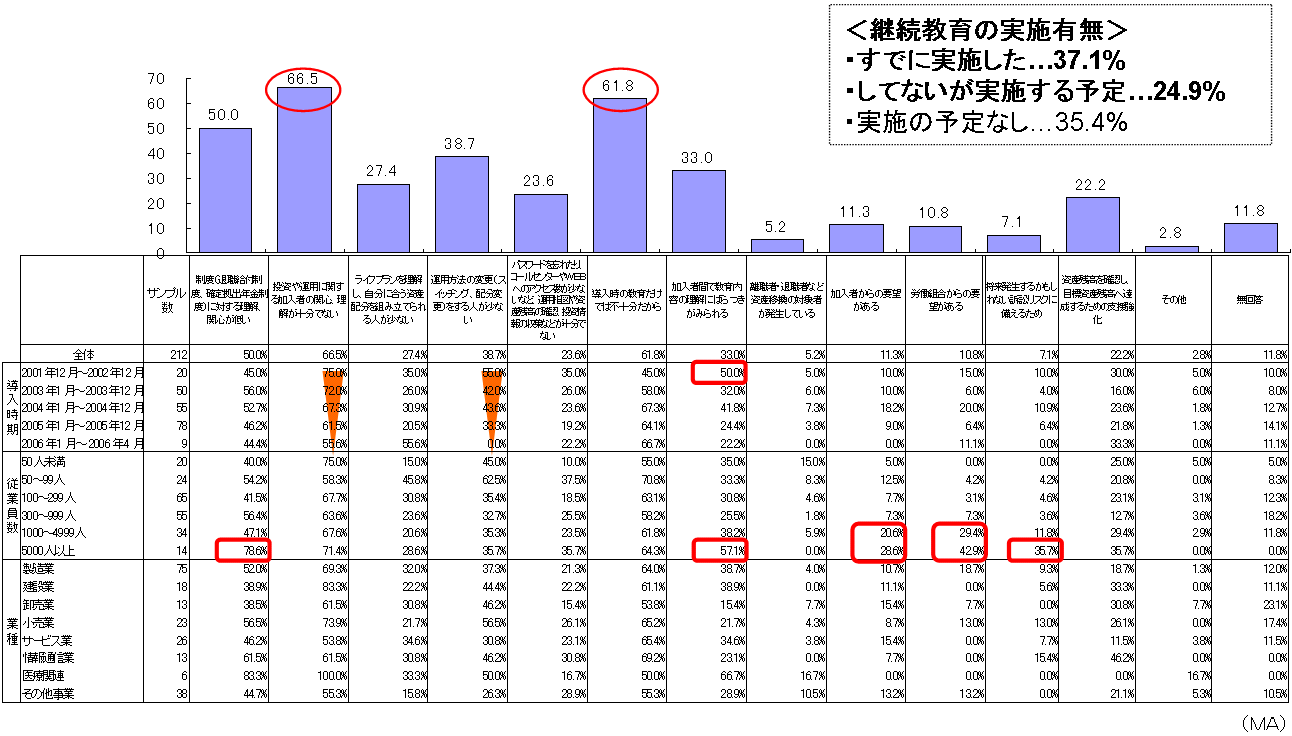
| ● | 継続教育の実施理由では、「投資や運用に関する加入者の関心、理解が十分でない」「導入時の教育だけでは不十分だから」の基本的な知識・理解促進に基づく実施ニーズが中心で6割強と多くなっている。次いで、同様に「制度(退職給付制度、確定拠出年金制度)に対する理解、関心が低い」が、5割で続いている。 |
| ● | 導入時期別の傾向を見ると、「投資や運用に関する加入者の関心、理解が十分でない」「運用方法の変更(スイッチング、配分変更)をする人が少ない」で早期導入企業であるほど比率が高くなる傾向にある。また、「加入者間で教育内容の理解にばらつきがみられる」は、2002年以前の導入企業で比率が高くなっている。 |
| 2. | 導入後の事業会社の状況〜従業員の商品選択理由の推測〜 |
| ■ | 元本確保型商品の選択理由 |
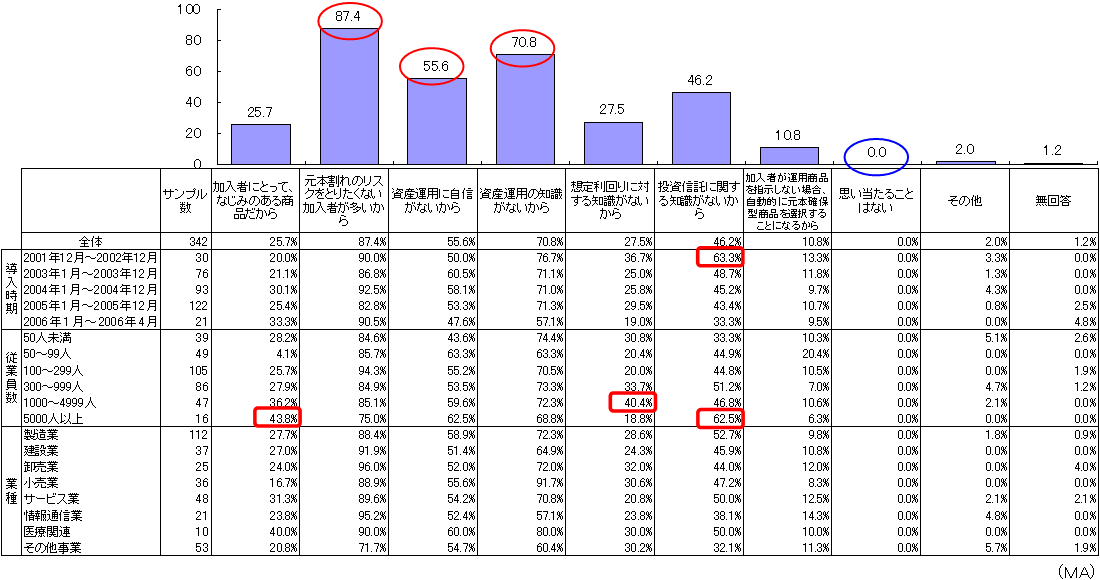
| ● | 元本確保型商品の選択理由としては、「元本割れのリスクをとりたくない加入者が多いから」が9割弱で最も多く、次いで、「資産運用の知識がないから」「資産運用に自信がないから」となり、資産運用における基本的な知識や理解不足から生ずる心理的な不安感をうかがわせている。「思いあたることがない」と回答した担当者は、皆無で現在の確定拠出年金制度における資産運用面での進展障害を浮き彫りとしたかたちになっている。 |
| ● | 「投資信託に関する知識がないから」が、早期導入企業で、また、5000人以上の企業で比率が高くなっていることからも上記結果を裏付けるものとなっている。 |
| 3. | 加入者の制度利用実態、運用実態 |
| ■ | 加入者の商品選択比率による分類 「元本確保派」VS.「投資信託派」 |
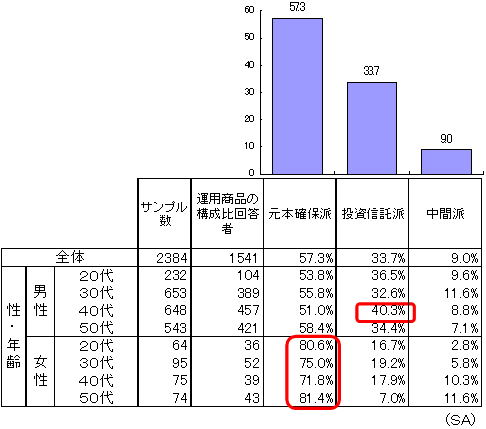
運用商品の構成比回答者(1541人)
|
|
| 元本確保派が全体で過半数を占め、投資信託派は、3人に1人にとどまっている。 性別では、女性の元本確保派の比率が高くななる傾向にあり、年齢別では、40代男性で投資信託派の比率が40%で若干高くなり、50代女性では投資信託派が10%以下となっている。 |
「元本確保派」VS.「投資信託派」(商品選択基準、必要情報)
| ● | 運用商品を選ぶ際の最も重視する項目 |
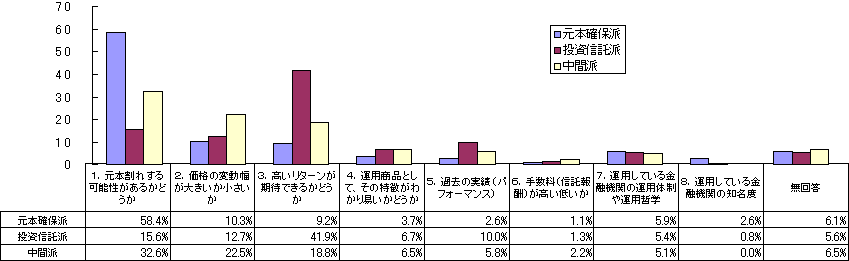
| ● | 今後知りたい情報内容 |
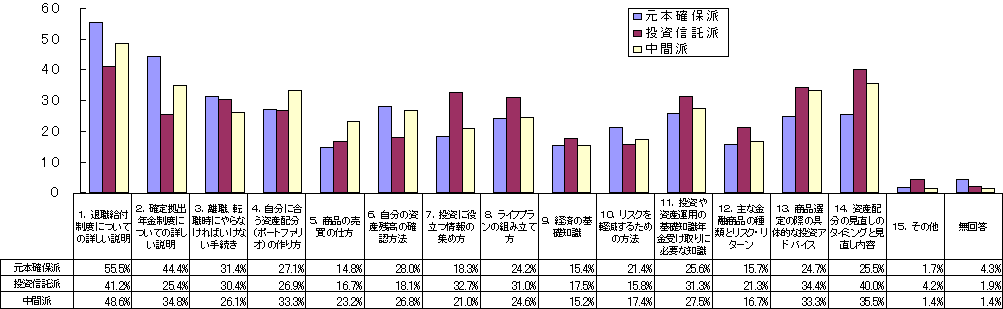
「元本確保派」VS.「投資信託派」(基本情報の認知)
| ● | 想定利回りの認知 |
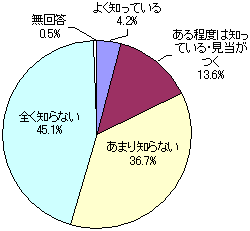
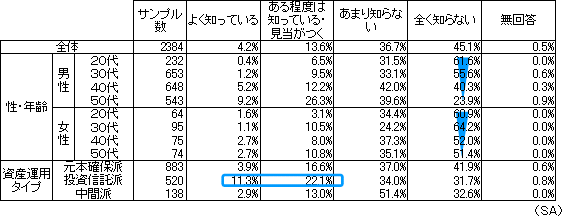
| ● | 掛金振込み額の認知 |
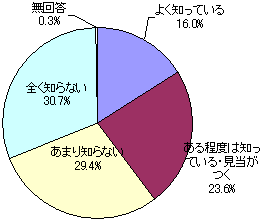
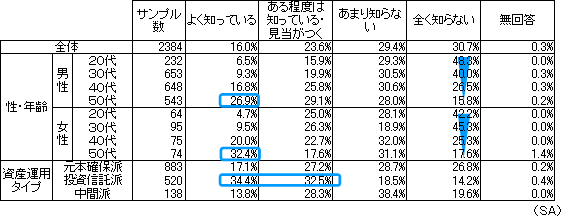
「元本確保派」VS.「投資信託派」(活用状況)
| ● | インターネット(Web)サービスの利用状況 |
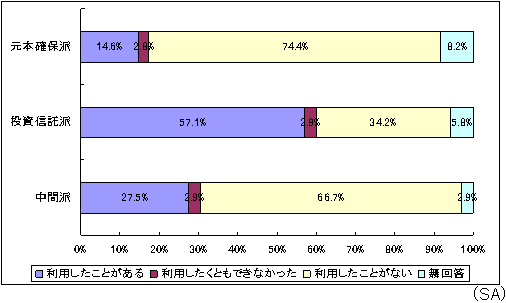
| ● | 「残高のお知らせ」の利用状況 |
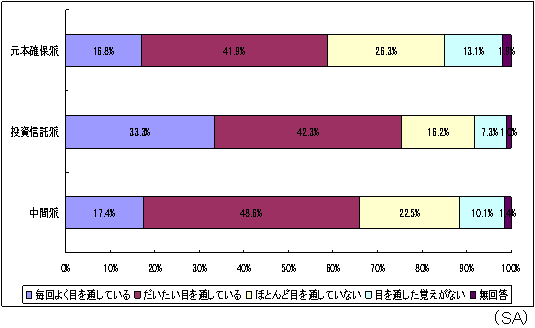
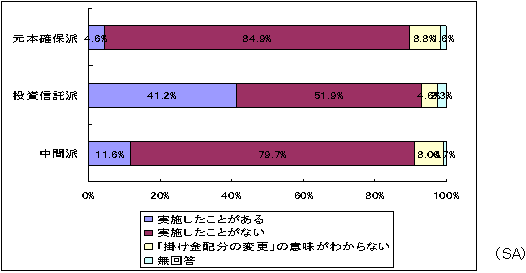
まとめ
“ハード面(OS)の充実とともに、実効性を高めるソフト面の充実を”
| 1. | 本人拠出の容認
|
||||
| 2. | 継続教育の義務化(投資家保護)
|
||||
| 3. | 教育実施状況の検証システム、報告の義務化
|
<データの出所>
| 1. | 企業担当者の制度改正要望の内訳 |
| 調査対象 | : | 確定拠出年金規約承認企業1729社(2006年2月28日現在)のうち、アンケート協力意向企業958社の確定拠出年金業務担当者 |
| 調査時期 | : | 2006年4月上旬〜5月中旬 |
| 調査方法 | : | FAX送付による自記入アンケート方式 |
| 回答者数 | : | 有効回答300名(制度担当者) 回収率31.3% |
| 調査主体 | : | NPO法人確定拠出年金教育協会、フィデリティ投信株式会社 |
| 2. | 導入後の事業会社の状況 |
| 調査対象 | : | 確定拠出年金規約承認企業1729社(2006年2月28日現在)の確定拠出年金業務担当者 |
| 調査時期 | : | 2006年7月上旬〜8月下旬 |
| 調査方法 | : | 郵送による自記入アンケート方式 |
| 回答者数 | : | 有効調査票回収数:342票(回収率19.8%) |
| 調査主体 | : | NPO法人確定拠出年金教育協会 |
| 3. | 加入者の制度利用実態、運用実態 |
| 調査対象 | : | 確定拠出年金制度導入後1年以上経過した事業会社5社の従業員 |
| 配布数 | 回収数 | 有効サンプル | 調査対象サンプル | |
| ・ 1000 | 909 | 896 | → | 600 |
| ・ 500 | 161 | 161 | → | 160 |
| ・ 1000 | 125 | 125 | → | 124 |
| ・ 6000 | 2568 | 2564 | → | 800 |
| ・ 2300 | 1263 | 1226 | → | 700 |
| ────────────────────────── | ||||
| 10800 | 5026 | 4972 | → | 2384名 |
| 調査時期 | : | 2005年10月下旬〜2006年3月下旬 |
| 調査方法 | : | 社内または自宅留置による自記入アンケート方式 |
| 調査主体 | : | NPO法人確定拠出年金教育協会 |