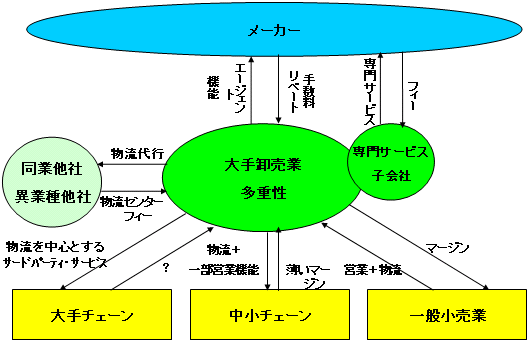| 最寄品の流通・取引問題から |
2006年9月21日(木)
拓殖大学 商学部 教授/(財)流通経済研究所 理事
根本 重之
最寄品メーカーの取引制度
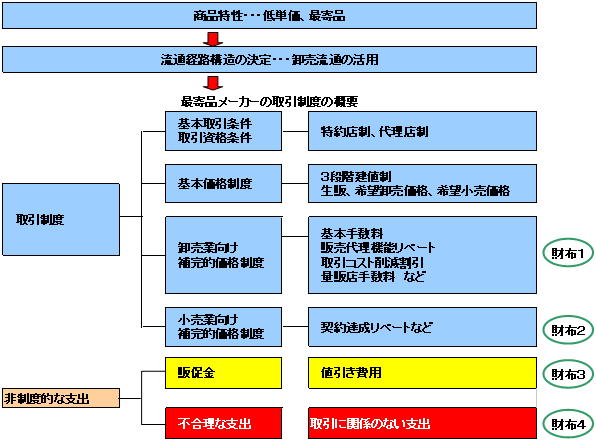
流通の変化→メーカー・機能分担関係と取引制度問題
| ● | 取引制度は、メーカー・取引先間の機能分担関係を定義するもの
|
||||||
| ● | だがメーカーは、競争上の理由などから、自前の営業組織を拡大することにより、卸売業、小売業の機能領域に進出してきた
|
メーカーが流通にでることにより卸売業の営業機能発揮領域を狭めてきた
|
商物分離・・・商流はすでに直接取引、物流のみ間接取引
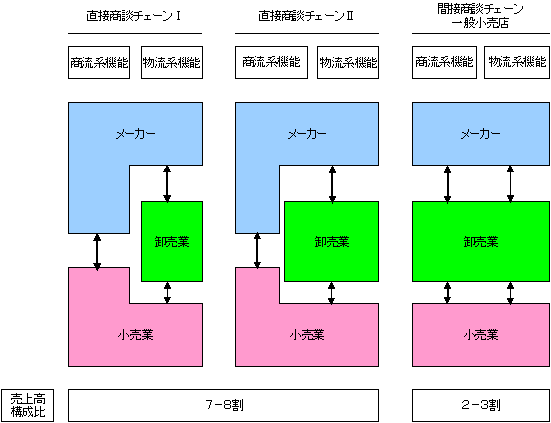
卸売業の変化1:実質3サードパーティ化
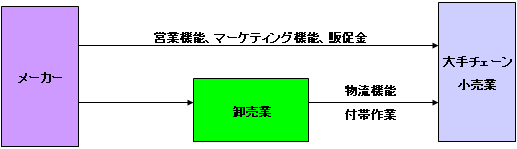
|
| ●大手卸売業の収益力の安定 ●収益力安定下での規模拡大 ●シェア上昇による影響力の強化 |
卸売業の変化2:環境変化に適応し、収益力を上昇
| ● | 1990年代の流通における戦いは、優秀な大手卸の勝ち。 |
| ● | 日本の大手卸は、「1/6モデル」、「1/5モデル」を構築し始めている。 |
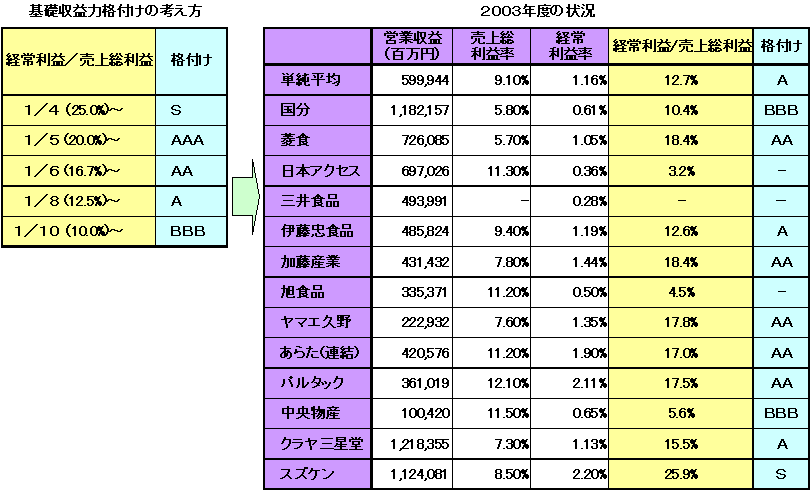
日本の卸売業の二重性、多重性
|
小売業による優越的地位の濫用問題
| ■ | 大規模小売業告示(新告示)施行(05/11/1) |
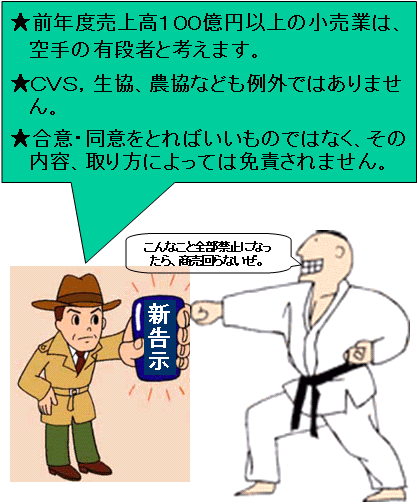
<運用基準に規定された10の禁止行為>
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
次の課題:卸売業が取引制度を作る
|
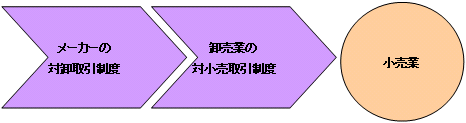
「卸売業が構築する小売業向け取引制度の内容として考えておくべきこと」
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
日本(SEJ)型流通システムと米国(ウォルマート)型流通システム
| A型 | B型 | |
| 初期条件 | ルーティーン業務をベンダーに転嫁可能 | ルーティン業務のコストは自己負担 |
| 初期ビジネスモデル特性 | 集約的(坪当り売上高が高いこと前提) | 粗放的(坪当り売上高が低いこと前提) |
| 品揃え方針 | バラエティー重視 | 代替品目の絞り込み |
| 基本的な考え方 | 単品・単フェイス管理 | カテゴリー・マネジメント・複数フェイス管理 |
| 発注ロット | ピース | ケース |
| リードタイム | 短縮前提 | 適正化可能 |
| 棚割り変更 | 固定的 売れなければアイテムカット、返品 |
弾力的 実績に応じてフェイス数を増減、返品を削減可能 |
| 価格政策 | 短期ハイ&ロー/ただしコンビニは価格維持 | EDLP+長期特売 |
| 補充作業の効率性 | 低い | 高い |
| 発注方法 | 人が仮説・検証:GOT、ST | 自動化:CAO→VMI |
| 構築した物流システム | カテゴリー別陳列順納品:過剰品質・高コスト | クロスドック・システム:適正品質・低コスト |
| 情報公開 | 情報は非公開(EOSさえ金をとる) | 情報公開してメーカーを活用(情報は無料) |
| デフレ、競争激化適正 | × | ○ |
| コラボレーション適正 | × | ○ |
宣伝:根本重之『新取引制度の構築』(白桃書房、2004年)、第1版第3刷(2006年5月26日)
| 〈第1部〉 | 取引制度の概要と基本的な問題点 |
| 第1章 | 取引制度の概要と検討の視点3 |
| 1. | 取引制度の基本機能と概要/3 |
| 2. | 最寄品メーカーの伝統的なチャネル構造と取引制度の概要7 |
| 3. | 取引制度問題を検討する視点/2 |
| 第2章 | 特約店制および建値制の概要とその前提の崩壊/21 |
| 1. | 特約店制の概要とその前提の崩壊/21 |
| 2. | 建値制の概要とその前提の崩壊/27 |
| 3. | 2次卸店の存在と「預り金」の発生/32 |
| 第3章 | 補完的価格制度に関する検討41 |
| 1. | 補完的価格制度の概要/41 |
| 2. | 補完的価格制度に関する考察/48 |
| 3. | 補完的価格制度と卸売業/53 |
| 〈第2部〉 | 1990年代前半の取引制度改定 |
| 第4章 | ライオン(1991年),桃屋(1992年)の取引制度改定69 |
| 1. | ライオンの取引制度改定(1991年)/70 |
| 2. | 桃屋の取引制度改定…新総合販売政策(1992年)/85 |
| 第5章 | カゴメの取引制度改定(1993年) 〜営業革新と取引制度改定の連動〜95 |
| 1. | 1980年代の多角化戦略による規模拡大と問題の累積/95 |
| 2. | 企業ドメイン再設定と営業戦略の革新/101 |
| 3. | 営業革新の一環としての取引制度改定/104 |
| 4. | 新取引制度導入の成果,限界と営業革新への展開/107 |
| 第6章 | 味の素の取引制度改定(1995年) 〜3段階建値制の廃止と仕切価格制の導入〜119 |
| 1. | 1960年代以降の事業多角化と取引制度の形成/整備/119 |
| 2. | 取引制度改定の背景/125 |
| 3. | 取引制度改定の概要……革新的な新取引制度の導入/128 |
| 4. | 取引制度改定の評価/133 |
| 第7章 | 1990年代前半の取引制度改定の成果と課題143 |
| 1. | 1990年代前半の取引制度改定の比較・検討/143 |
| 2. | 1990年代前半の取引制度改定が残した課題/151 |
| 〈第3部〉 | 流通の国際化,直接取引の発生を踏まえた取引制度改定1 |
| 第8章 | 欧米型直接取引モデルと日本型間接取引モデルの比較検討157 |
| 1. | 欧米の大手チェーン小売業の取引モデルと卸売業の状況およびメーカーの取引制度/158 |
| 2. | 日本の大手チェーン小売業の取引モデル/161 |
| 3. | 大手卸売業による流通システムの構築と日本の卸売段階の特徴/172 |
| 第9章 | P&Gの新取引制度(1999年) 〜直接取引への対応と取引基準,価格体系の明確化〜185 |
| 1. | P&Gの取引制度改定のレビュー/185 |
| 2. | P&Gの新取引制度の概要/191 |
| 3. | P&G新取引制度の評価/201 |
| 第10章 | 日本リーバの取引制度改定(2000年) 〜ネットプライス・オペレーションと卸機能活用型直接取引モデル〜 |
| 1. | 日本リーバの概要と事業戦略の転換/209 |
| 2. | ネットプライス・オペレーション,流通政策,取引制度/216 |
| 3. | 卸機能を活用した直取引のビジネスモデル/225 |
| 4. | 日本リーバの展開の成果と今後の課題/232 |
| 第11章 | ライオンの取引制度改定(2001年) 〜国内メーカーによる新たな取引制度の模索〜239 |
| 1. | 基本取引条件・取引基準と価格体系の変更/240 |
| 2. | 新たな補完的価格制度の概要/246 |
| 3. | 取引制度改定に関する評価/249 |
| 第12章 | カルビーの取引制度改定(2001年) 〜新たな事業モデル,流通モデルの構築と取引制度改定〜255 |
| 1. | カルビーの流通政策,営業政策のレビュー/255 |
| 2. | 新たな事業モデルの構築/263 |
| 3. | カルビーの旧取引制度とその問題点/268 |
| 4. | 取引制度改定の概要/271 |
| 5. | カルビーの取引制度改定の評価と第7期の展開/277 |
| 第13章 | 新取引制度構築の方向〜流通と営業の革新〜283 |
| 1. | 環境変化に関する明確な認識と上位戦略の明確化/283 |
| 2. | 特約店制および取引基準/288 |
| 3. | 基本価格体系/292 |
| 4. | 卸売業向け補完的価格制度/298 |
| 5. | 販売促進費/309 |
| ● | 市販価格:本体3,300円(税込み3,465円) | ||
| ● | 著者割引価格:税込み2,772円(税込み市販価格×0.8) | ||
| ● | 著者割引価格でのご注文方法 右記のようなご注文をメールあるいはファクシミリにて白桃書房販売部あてご送信下さい。前略のごく簡単なもので結構です。
|
||
| ● | 注文及び問い合せ先:株式会社白桃書房 販売部 eメール:hanbai@hakutou.co.jp TEL.03-3836-4781FAX.03-3836-9370 ***白桃書房販売部御中******** 著者の紹介により貴社発刊の根本重之著『新取引制度の構築』を( )冊注文します。 送付・請求先:(お会社名、ご住所、お名前、電話番号など、会社or個人明記)
|