| 資料3−6 |
平成18年6月19日
振動障害等の防止に係る作業管理のあり方検討会 第3回 資料
電動工具メーカーの振動表示及び振動測定
(騒音についても振動と類似していますが,ここでは振動について紹介します)
(騒音についても振動と類似していますが,ここでは振動について紹介します)
|
株式会社マキタ 技術研究部 畝山 常人 |
(1)動力工具の振動値表示
現在,EU加盟国内で販売されるすべての手持ち式及び/又は手誘導式動力工具は,その取扱説明書に振動値を記載することが規定されています。(EU加盟国以外では規定している国は無い)
これは,EU機械指令
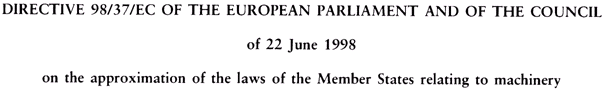
の 2.2 Portable hand-held and/or hand-guided machinery に essential health and safety requirements として下記が規定されているためです。
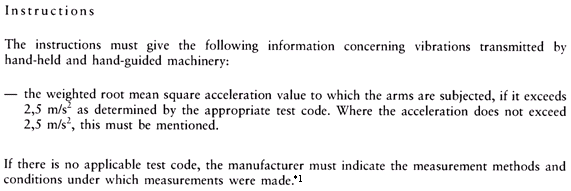
機械指令に規定されている事項を順守しなければ,CEマーキングを行うことは出来ず,それはEU加盟国での販売が出来ないことを意味します。
機械指令では,取扱説明書に適切な試験規定*2により得た機械の振動値が2.5m/s2を超えるものはその振動値を,2.5m/s2を超えないものはその旨を明記することが規定されています。振動値を取り扱い説明書のどの部分にどのように記載するかについては規定されていません。(CE適合宣言と共に記載する,又は機械仕様の一部として記載することが多いようです。)
次ページに振動値記載の例を示します。
日本では「ユーザーが取扱説明書を読むことはほとんど無い」と言われますが,欧州(特に英国)では,工具はハイヤー業者(レンタル業者)から借りるケースが多く,ハイヤーが自社のレンタル工具のカタログに取扱説明書から抽出した振動値を一覧で記載しユーザーの便を図っているケースが多くあります。
Makita の記載例(CE適合宣言とともに記載)
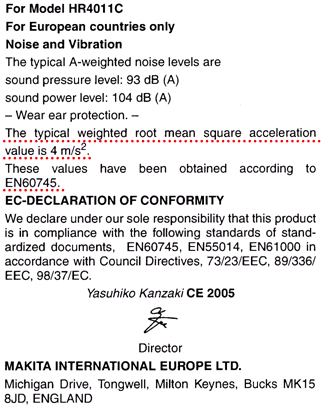
Boschの記載例(CE適合宣言とともに記載)
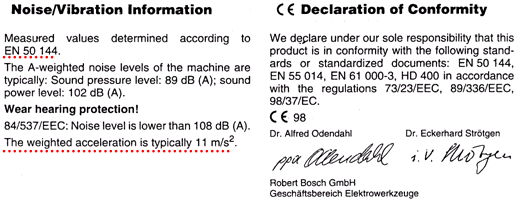
Hiltiの記載例(機械仕様表の一部として記載)
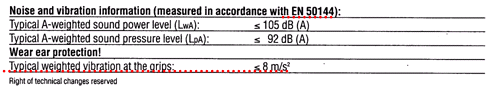
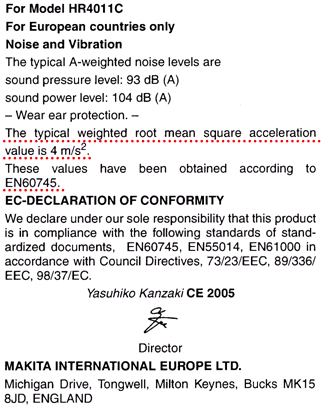
Boschの記載例(CE適合宣言とともに記載)
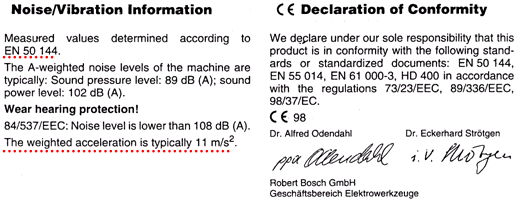
Hiltiの記載例(機械仕様表の一部として記載)
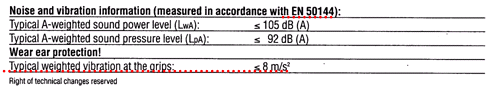
(2)振動の測定規格
| a) | 振動測定に関連する規格(代表的なもの) 動力工具の振動測定規格(規定)には,主なものとして次のようなものがあります。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | 適用する規格 EUでは,適用する試験規格[(1)の*2]優先順位を下記のように定めています。
マキタの製品は電動工具であるため,優先順位(1)の欧州規格であるEN 60745を適用することになります。(空圧・油圧工具であればISO 8662を,エンジンチェーンソー・刈払い機はISO 22867を適用します。 日本では,工具振動値の表示を規定した法令はなく,振動測定方法も評価方法も確定していないため,会社のデータとしてEN準拠の振動測定(3軸でおこなっています)を行いデータをプールしていますが,現状それを公開することはしておりません。(国内メーカの多くが同様と考えます) 実際の規格の適用は,該当工具がEN 60745に規定されておればEN 60745を,EN 60745に規定されていなければEN 50144を適用しています。 EN 60745は,3軸測定を規定するものですが,実際には3軸測定への改正は過渡期にあり,EN 50144の単軸測定を暫定的に個別工具群に適用しているものが多いのが実状です。 測定は3軸測定を行っていますが,CEに対応する宣言は各規格に規定するもの(単軸値又は3軸値)を記載しています。
<参考> ISO 8662,EN 50144,EN 60745で振動測定が規定されている工具群
<参考> 現在,手持ち式工具の動力源としては (1)油空圧 (2)電気(AC,DC)(3)内燃エンジンが主なものであり,電動工具が60%以上を占めていると言われている。 ISO 8662シリーズは,ISO/TC 118:Compressors, pneumatic tools and pneumatic machinesがIEC/TC 61:Safety of household and similar electrical applianceと共同で制定したものであるが,主に油空圧工具を対象としている。EN 50144はCENEREC TC 61F:Hand-held and transportable motor operated electric toolsにより電動工具を対象に制定されたものである。ISO 8662とEN 50144は測定方法において類似しているが,細部で異なっている点が多く,動力源が異なるだけの同種の工具で測定方法が異なり,結果として測定結果(振動値)が異なるという問題がある。 内燃エンジン工具については,主なものはチェーンソー及び刈払い機であり,エンジンという特殊性(アイドリングがある等)から,油空圧式及び電動式と異なる測定方法が規定される(ISO 22867:ISO/TC 23/SC 17 Tractors and machinery for agriculture and forestry, Manually portable forest machineryが作成)のはやむを得ないと考えられる。 ISO 5349の改正に伴い,EN 60745の制定・ISO 8662の改正作業が進められているが,EN 60745の制定はCENEREC TC 61Fが担当し,ISO 8662の改正はISO/TC 118/SC 3/WG 2とCEN/TC 231/WG 2の共同作業で進められている。ISO 5349に準拠するための3軸測定への変更がその大きな部分であるが,油空圧工具と電動工具の振動測定方法が統一されるという見込みは少ないと思われる。
|
(3) 株式会社マキタでの規格振動測定
| 3-1 | 測定装置 測定装置(機器)は,ISO 5439-1,ISO 8041(JIS B 7761-1)に適合するものが要求されます。 マキタで保有している測定装置(機器)は2006年5月現在下記です。
HVM100,VM-54はフィールド測定用に使用。 | ||||||||
| 3-2 | 測定室 マキタでは,EU指令で要求される振動値・騒音値を同時に測定しているため,測定はISO 3745(JIS Z 8732)に適合した半無響室(10.2×5.5×3m)にて測定を行っています。 | ||||||||
| 3-3 | 測定治具類 測定治具類は,ISO 8662,EN 50144,EN 60745に規定されるものを製作し保有しています。周辺機器も規格の要求に適合したものを使用しています。 | ||||||||
| 3-4 | 被削材 被削材・試験用コンクリートブロック等は,EN 50144,EN 60745に規定されるものを常備しています。 | ||||||||
| 3-5 | 試験者・測定者 規格測定においては,試験者・測定者の技量が大きな要素となります。 経験15年以上のベテランをはじめとし,十分な経験と技量を有する人員を配置しています(専用要員3名+試験者4名,他に試験が行えるもの数名)。これらの人員は,規格の詳細を熟知していると同時に“試験の勘どころ”を知り尽くしているメンバーです。 |
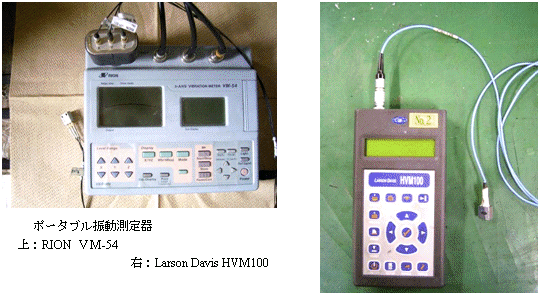
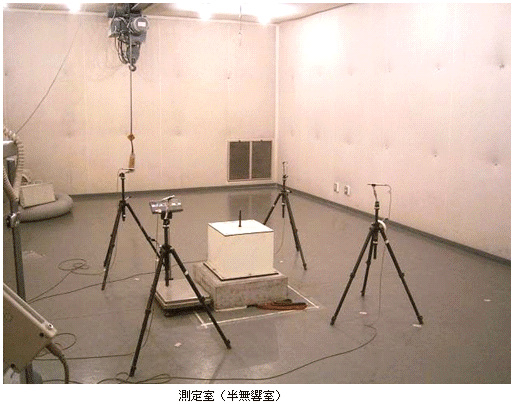 騒音は工具を中心とする半径2mの球面上の5本のマイクにて測定 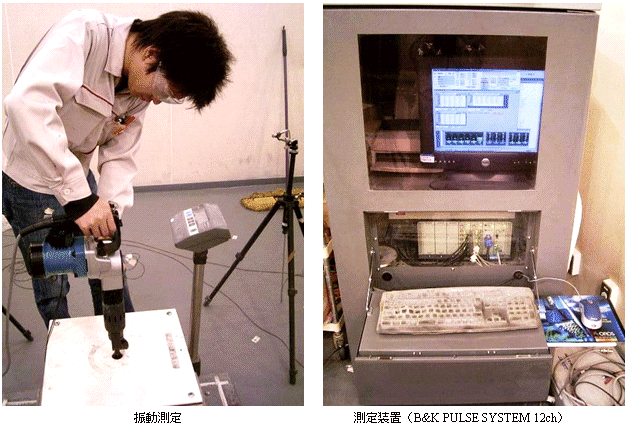
熟練作業者がはかりの上に乗って押付け力をモニタしながら作業する
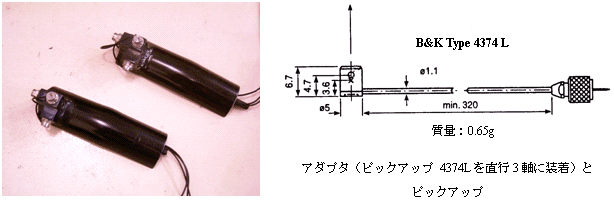
|
写真は,電動ハンマの測定の様子で,EN 60745-2-6に従って,騒音測定と振動測定を同時に行っているところを示します。
次ページに,EN 60745-2-6: Particular requirements for hammers の振動測定部分の抜粋を紹介します。 騒音値と振動値は同一試験条件で測定することになっており,ビットが回転しないハンマ(ブレーカなど)については,ISO 8662-2: Chipping hammers and riveting hammersなどと同様な負荷装置(エネルギー吸収装置:Figure Z104)を用いて,ビットが回転するハンマ(ロータリハンマ)は,Table Z102に規定するコンクリートブロックを用い,Table Z103に規定するドリルビット・Table Z104に規定する試験条件で測定を行うことを規定しています。
写真の試験はビットが回転しないハンマの試験であり,騒音測定のためエネルギー吸収装置は防音ボックスで覆われています。
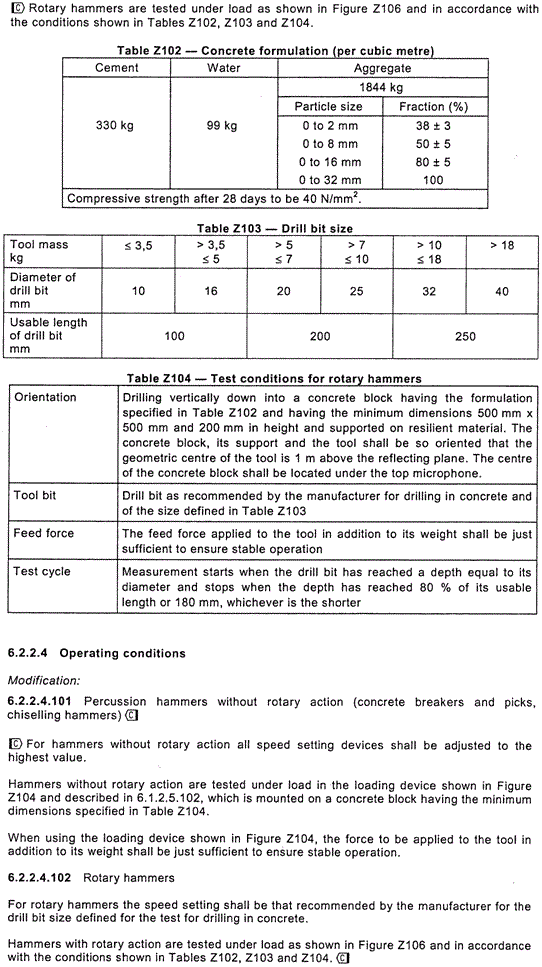
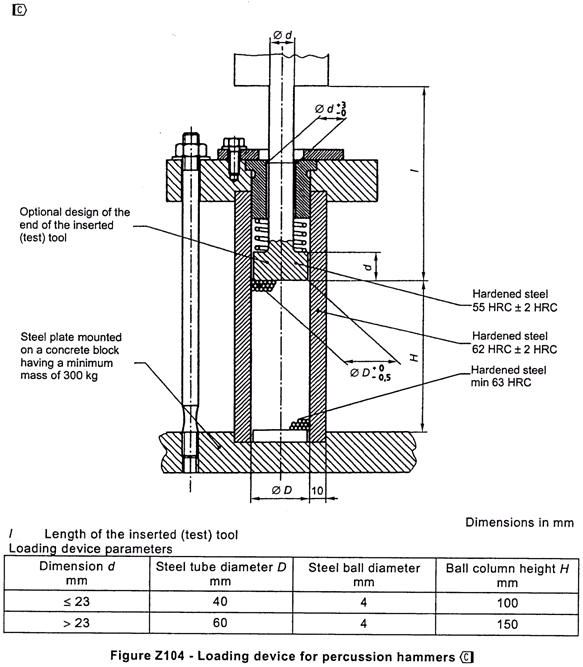
(4)規格試験による振動値と実作業で暴露される振動
「規格試験=形式試験」で得られる振動値は,実作業で暴露される振動と整合しているのか? ということがしばしば問題にされます。欧州でも,宣言値をそのままリスク評価に用いることが出来るのか? ということが大きな問題になっています。 規格試験は大きく分けて
| ・ | 模擬付加によるもの(グラインダ・インパクト工具・ハンマなど) |
| ・ | 実作業によるもの(ロータリハンマ・振動ドリル・サンダ・のこぎりなど) |
規格では“実際の作業環境における振動加速度と近い値となる(ISO 8662-3)”とされていますが,一方“異なる動力工具又は同じ種類の異なる形式の動力工具を比較するために用いることを目的にする”また“振動暴露の評価が必要な場合には実作業状態で測定することが必用となる(ISO 8662-4など)”とも明記されており,規格試験(形式試験)で得た振動値をそのまま人体への影響の評価に用いることが出来るかどうかには疑問があります。
規格試験は,「いつでもどこでも再現可能であること」が重要でありそのために詳細な測定方法を規定しているもので,その結果を「異なる動力工具又は同じ種類の異なる形式の動力工具を比較する」ために用いるときには信頼に足るデータとなりますが,実作業で人体が暴露される振動は規格試験に含まれない多くの要素が関係してきますので,規格試験で得た値をそのまま人体への評価に用いることには問題があると考えられます。
模擬負荷を使用する規格試験では,模擬負荷が実作業を代表する振動を発生するものであるかどうかが大きな問題点になります。
実負荷試験においても,負荷状態は厳密に規定されていますが,実作業で発生する振動は,
| ・ | 作業内容(例:同じグラインダを用いる作業でも,研削砥石を用いる研削・ダイアモンドホイールなどを用いる切削・カップブラシなどを用いる塗装剥がしなどで同じ工具を用いても発生する振動は大きく変化する) |
| ・ | 作業対象(例:同じグラインダに同じダイアモンドホイールを装着して切断作業を行う場合,被削材がコンクリート,石材,煉瓦,瓦など異なれば,発生する振動は大きく異なる。また砥石での研削作業でも砥石の粒度により振動値は異なる。) |
| ・ | 作業状況(例:同じ工具を用いても,重作業か軽作業かなどで振動値は異なる) |
| ・ | 作業者の技量(作業者の技量で振動値が大きく異なってくることは良く知られている) |
| ・ | 用いる先端工具の状況(例:コンクリートハツリ作業で,プルポイントが摩耗してくれば振動値は数倍に増大するケースもある) |
欧州では,規格試験で得た振動値から実作業時に暴露されるであろう振動値を推定するための係数を設定する試みもなされています(CEN TR15350)が,前田先生の調査ではその信頼性はあまり無いようです。
同じ工具を使用しても多種多様な条件により工具から発生する振動の大きさが大きく異なることはメーカーとしても承知しており,ある条件下での振動に対する問い合わせなどがある場合は,出来うる限りその条件を再現して振動測定を行う,又は作業現場へ伺い実作業での振動測定を行うことは実施していますが,工具振動値を公表する場合には,規定された試験方法に基づいた形式試験値を用いざるを得ないと考えています。
振動の人体への影響を評価する場合,実作業で暴露される振動を直接測定するのが最良ですが,
| ・ | 形式試験で得る値が可能な限り実作業で生じる振動に近づくよう試験規定を定める |
| ・ | 実作業を想定し,得た形式試験値を実際の値に換算するための係数を(作業条件に応じ複数)定める |
| ・ | 形式試験値から想定する実暴露振動値に安全率を持たせる |