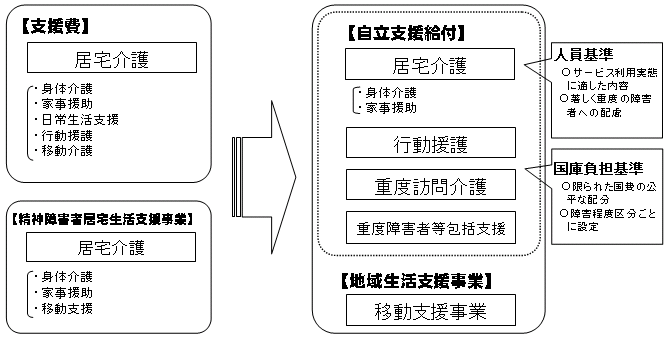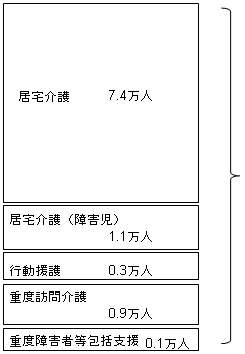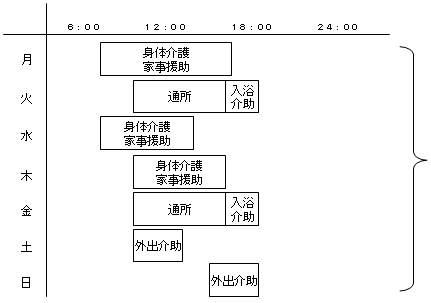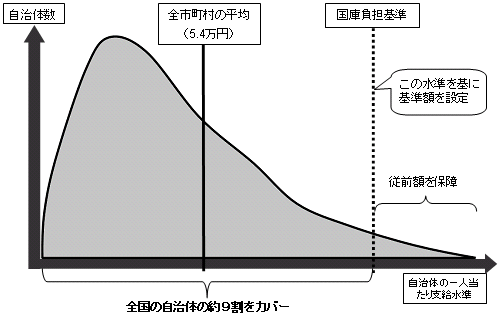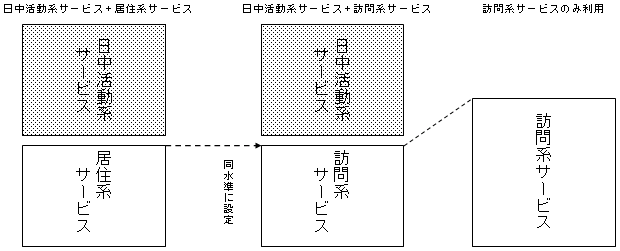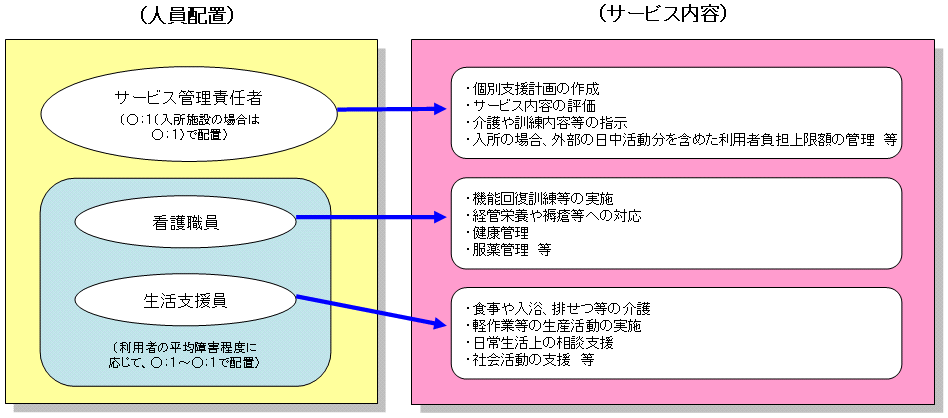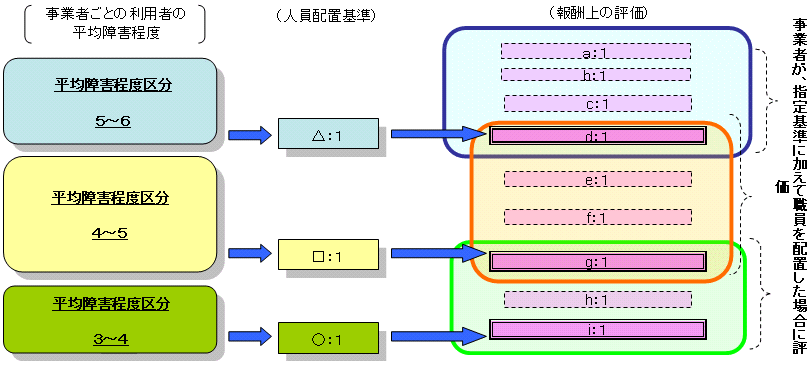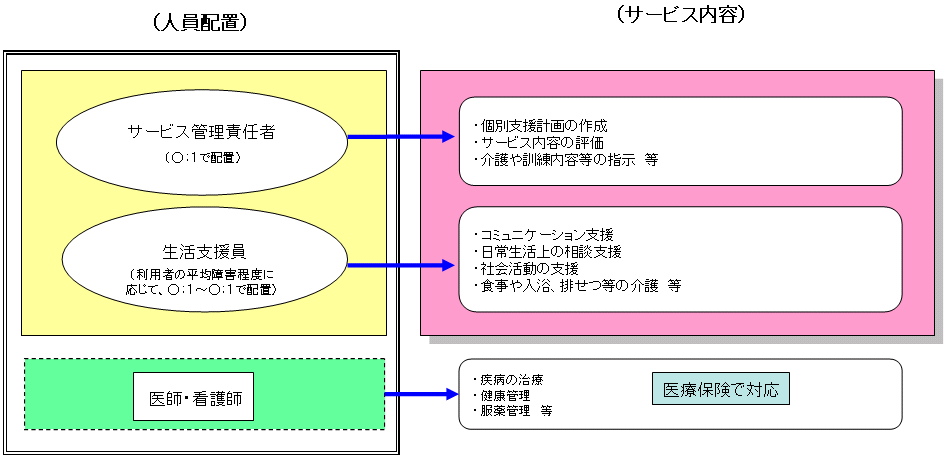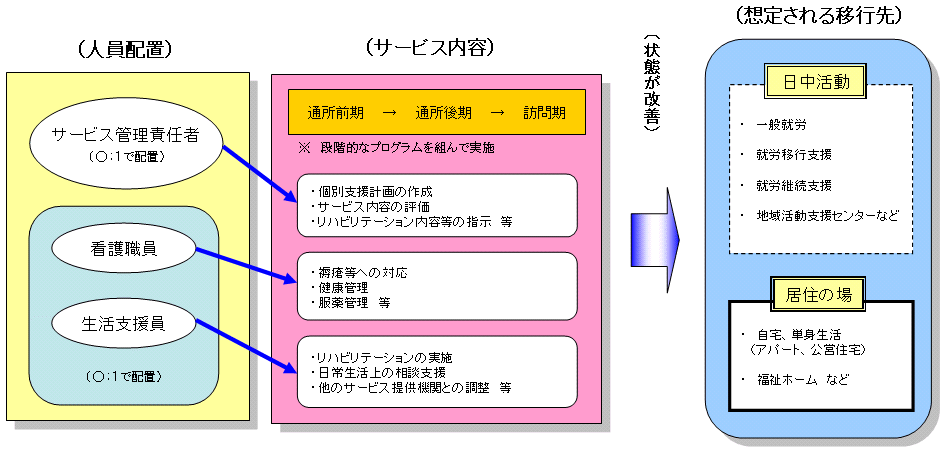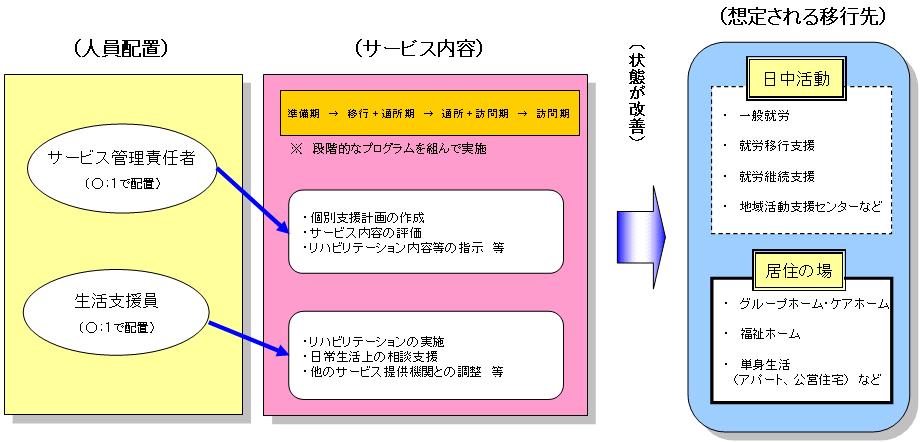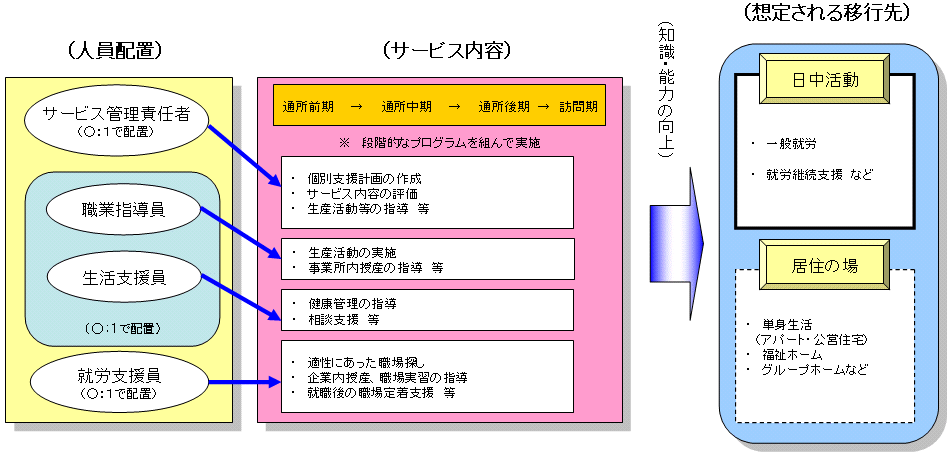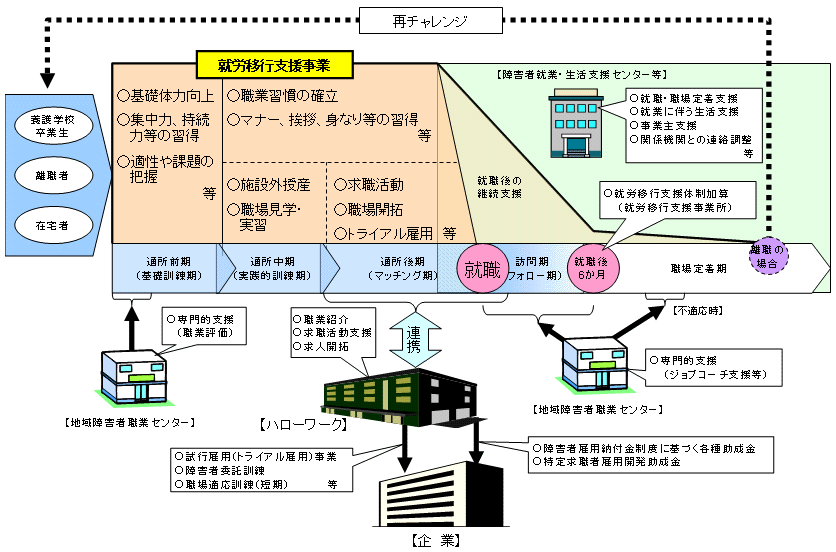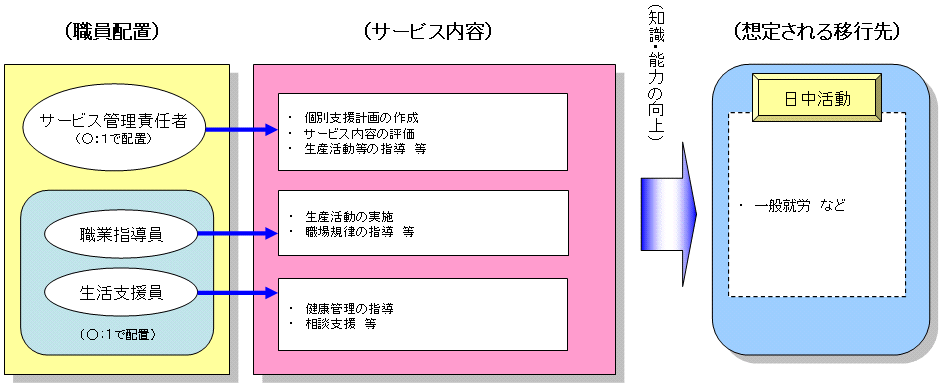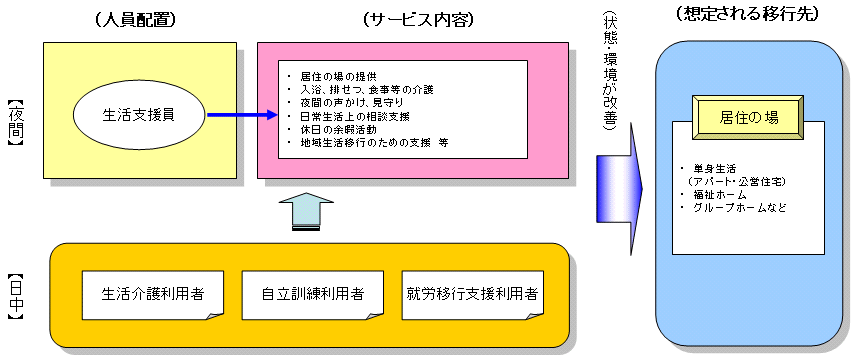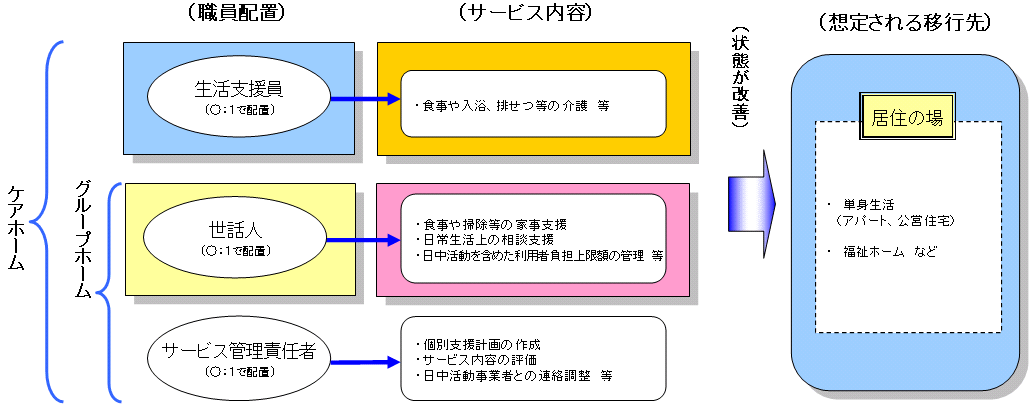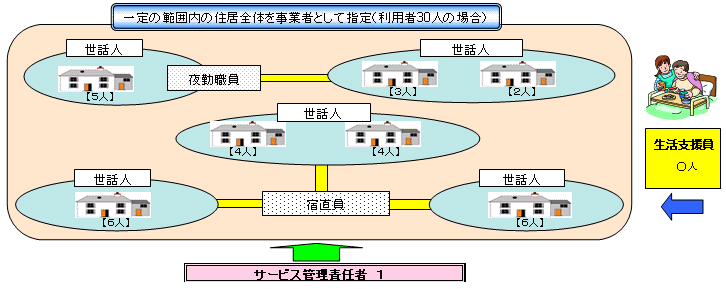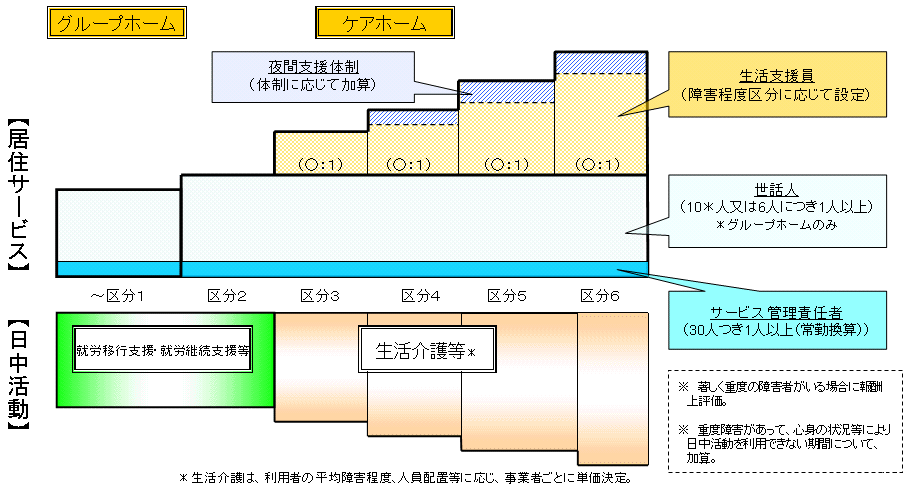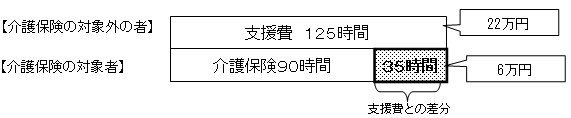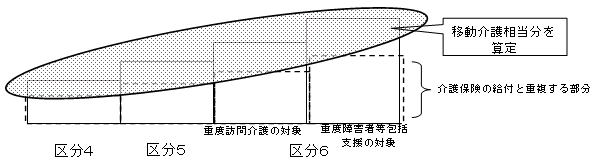新しいサービスに係る基準・報酬について
平成18年2月9日
基準・報酬の設定に関する考え方
| 地域生活移行や就労支援といった課題への対応、重度障害者への支援の充実等を図りつつ、質の高いサービスが、より低廉なコストで、できる限り多くの人に提供されるよう、利用者の状態像やサービス機能に即した基準・報酬を設定する。 |
| ○ |
最近の経済情勢等を踏まえ、報酬単価について、全体で△1.3%としつつ、地域生活移行や新事業体系への移行を促進する観点から、居宅系サービスや新体系サービスは△1.0%とする。なお、旧体系からの移行施設については、移行時支援措置を講ずる。
【平成18年度予算案における内訳】
| ・ |
訪問系サービス |
610億円 |
| ・ |
グループホーム・ケアホーム |
180億円 |
| ・ |
日中活動・居住サービス |
3,230億円 |
| ・ |
その他 |
110億円 |
| 計 4,130億円 |
|
| ○ |
地域生活を支える柱である訪問系サービスについて、利用者の状態やニーズに適したサービスが効果的・効率的に利用できるよう、短時間の集中的な提供と長時間滞在による提供といった実態に即した基準とするとともに、著しく重度の障害者に対する支援等を評価する。
|
| ○ |
入所施設や病院の中で完結するサービスや日常生活のあり方を見直し、地域社会と自然に交わりながら生活できるようにするため、日中活動と居住に係るサービスを区分し、それぞれについて、1人1人の状況やニーズに応じた支援を評価する。
|
| ○ |
地域生活を送る上で、特に計画的な支援を必要とする者について、地域の社会資源が最大限に活用され、1人1人の状況に即して適切な支援が組み合わせて提供されるよう、サービス利用のあっせん、調整、モニタリング等の相談支援を評価する。 |
| ○ |
これまで、施設の中に多様なニーズを有する利用者が混在し、必ずしも個々の状態に応じた適切なサービスが提供されておらず、結果として、地域生活や就労への移行が進んでいない状況があることから、事業ごとに利用者像や機能を明確化し、これに応じた体制を確保する。
| ・ |
事業ごとに、利用者像や標準的サービス内容に見合った人員配置とする。生活介護や療養介護については、事業者ごとに、利用者の平均障害程度区分に応じた人員配置基準を設定するとともに、これを超える手厚い配置を行った場合には、報酬上評価する。 |
| ・ |
事業者ごとに、個別支援計画の作成、サービス内容の継続的な評価等を行うサービス管理責任者を配置し、サービス提供に係る責任を明確化する。 |
|
| ○ |
重度の障害者について、適切な支援が行われるよう、障害者の状態やニーズ、サービス利用の実態に即した評価を行う仕組みとし、療養介護、生活介護等において、医療との連携を必要とする人工呼吸器を装着した者など、著しく重度の障害者への支援に配慮する。
|
| ○ |
研修体系を見直し、サービス管理責任者、相談支援専門員等が適切に業務を遂行できるよう、専門性の向上を図る。
|
| ○ |
複数の事業を組み合わせて行う多機能型を新たに位置付け、利用者のニーズに応じたサービスが身近な地域において提供される環境づくりを進める。 |
| ○ |
就労支援等を積極的に推進するため、客観的な指標により評価し得る事業運営上の成果について、報酬面に反映
する。
| ・ |
就労移行支援事業
事業の利用を通じて一般就労し、かつ、その職場で継続して就労する者が、利用者の一定割合に達する場合、これを報酬上評価する。 |
| ・ |
就労継続支援事業(非雇用型)
利用者の工賃水準の向上を図るため、指定基準として、工賃控除程度の水準を設定するとともに、事業者ごとの平均工賃が、地域の最低賃金に対して一定水準を上回った場合には報酬の加算を行う。 |
|
| ○ |
空き教室等地域の社会資源を最大限活用し、できる限り多くの利用者に対し効率的なサービス提供が可能となるよう、設備基準の見直し、食事提供に係る外部委託の要件の見直し、定員を超えた一定範囲内での利用者の受入れなど規制緩和を積極的に推進する。 |
| ○ |
サービス量に応じた利用者負担の導入等を踏まえ、日々の利用状況にかかわらず、毎日利用することを前提として定額の月額報酬が支払われる「月払方式」から、日々の利用実績に応じて報酬が支払われる「利用実績払い(日払い方式)」に転換する。
|
| ○ |
その際、(1)利用者が、心身の状況等により一時的にサービスを利用できなくなるケースを見込んで報酬を設定すること、(2)入所施設については、入院や外泊期間中の取扱いに配慮することなどの措置を講ずる。 |
| ○ |
事業ごとに、直接的なサービス提供に係る人件費を中心として評価することとし、事務費等の事業運営に係る間接的経費については、極力効率化を図る。
|
| ○ |
報酬単価については、利用者負担額の算定や地域差の反映を容易にするといった観点から、従来の円単位を改め、単位制を導入する。 |
| ○ |
現行施設・事業の基準・報酬について、新事業への円滑な移行の促進等の観点から、必要な見直しを行う。
|
| ○ |
現行の施設が新事業に移行する際、相当程度の事務作業やコストがかかることを踏まえ、移行時に一時的な加算を実施する。 |
| ○ |
新たに精神障害を個別に支給決定する仕組みに改めるとともに、「障害程度区分」の導入に合わせ、障害の状態やニーズに応じた支援が適切に行われるよう、訪問系サービスを再編する。
|
| ○ |
人員・運営基準や報酬基準については、短時間の集中的な利用と長時間の滞在による利用といったサービス利用の実態に適した内容とするとともに、著しく重度の障害者について配慮する。
|
| ○ |
国庫負担基準については、サービスの地域格差が大きい中で、限られた国費を公平に配分する観点から、市町村の給付実績等を踏まえつつ、サービスの種類ごとに、障害程度区分に応じて設定する。 |
|
| ○ |
各サービスごとに、障害程度区分判定等試行事業の結果等を踏まえつつ、利用者像を設定 |
| |
居宅介護 |
行動援護 |
重度訪問介護 |
重度障害者等包括支援 |
利
用
者
像 |
|
| ○ |
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を有する者 |
|
| ○ |
重度の肢体不自由者であって、常時介護を要する障害者 |
|
| ○ |
常時介護を有する障害者であって、その介護の必要の程度が著しく高い者 |
|
| ○ |
障害程度区分が区分1(要支援程度)以上である者 |
|
| ○ |
障害程度区分が区分3(要介護2程度)以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が10点以上である者 |
|
| ○ |
障害程度区分が区分4(要介護3程度)以上であって、下記のいずれにも該当する者
| ア) |
二肢以上に麻痺があること
|
| イ) |
障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること |
|
|
| ○ |
障害程度区分が区分6(要介護5程度)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下に掲げる者
| (1) |
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺があり、寝たきり状態にある障害者のうち、下記のいずれかに該当する者
| ア) |
気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
|
| イ) |
最重度知的障害者 |
|
| (2) |
障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が15点以上である者 |
|
|
【新しいサービス類型】
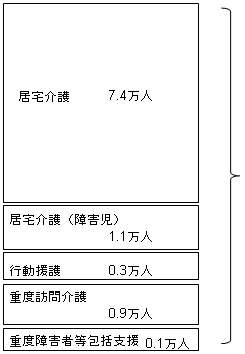
|
平成18年度の利用者数の見込
約10万人 |
| 訪問系サービスの人員・運営基準、報酬基準の基本的考え方 |
| ○ |
短時間での集中的なサービス提供(身体介護、家事援助)と長時間滞在してのサービス提供(重度訪問介護、重度障害者等包括支援)それぞれのサービス提供の実態に即した基準とするとともに、著しく重度の障害者について配慮する。 |
|
| ○ |
短時間での集中的なサービス提供にふさわしい基準とする観点から、30分単位のきめ細かな単価を設定するとともに、サービス提供に当たっては、一定の時間内(身体介護は3時間以内、家事援助は1.5時間以内)に集中してサービス提供を行うことを基本とした仕組みとする。
|
| ○ |
従事者の資格要件については、短時間に集中して専門的な支援を行うという業務内容を踏まえ、1級又は2級ヘルパーを基本とする。
なお、3級その他の者がサービス提供を行った場合には、減算を行う。 |
| ○ |
3時間を超えるサービス提供を基本とした上で、報酬単価については、同一箇所に長時間滞在しサービス提供を行うという形態を踏まえ、ホームヘルパーの1日当たり費用等を勘案しつつ、設定する。
|
| ○ |
また、人工呼吸器を装着したALS患者や重度心身障害者等の著しく重度の障害者であって、意思の疎通に著しい困難を有する者に対する支援について、一定の評価を行う。
|
| ○ |
従事者の資格要件については、利用者とのコミュニケーションなどの重要性を踏まえて、現在の日常生活支援の資格要件について、現場実習を中心とする内容に改めるとともに、広く従事者を確保する観点から研修時間数の緩和を行う。 |
| ○ |
スタートして間もないサービスであり、資格要件を満たす従事者を確保することが困難な事業者が多いことを踏まえ、研修の制度化を図った上で、経過的措置として、資格要件の緩和を行う。ただし、本来の要件を満たさない者がサービス提供を行った場合については、減算を行う。 |
| ○ |
基準該当事業者の場合、各種の規制を受ける指定事業者と比べ、管理コストを含めて柔軟な事業運営が可能であり、別途の報酬基準を設定する。 |
| ○ |
重度障害者等包括支援の報酬基準や運営基準については、
| (1) |
その対象者が最も重度の障害程度区分に該当するほか、意思の疎通に著しい困難を伴う者であること |
| (2) |
複数のサービスを長時間にわたり必要とする場合が多いこと |
| (3) |
体調の変化が大きく、しばしば緊急のニーズへの対応が必要となること |
といった特性を踏まえ、設定する。
|
| ○ |
意思の疎通に著しい困難が伴う重度の在宅の障害者を対象として、必要とする様々なサービスを包括的に提供するという本サービスの特性を踏まえ、サービスの質の確保について、十分な配慮を行う。 |
|
| ○ |
対象者の心身の状態、介護者の状況、居住の状況等を総合的に勘案して設定された標準的な個別支援計画に基づいて、必要な障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、ケアホーム、ショートステイ等)に要する時間(4時間1単位)を基本として、支給決定を行う。
|
| ○ |
報酬額は、訪問系サービスや日中活動系サービスの報酬水準を基礎として、1単位(4時間を想定)で設定する。ただし、ケアホーム、ショートステイについては、これらの報酬基準のうち最重度の者に適用される額を適用する。
|
| ○ |
重度障害者等包括支援の事業者は、下記の要件を満たすものとする。
| ・ |
重度訪問介護やケアホーム等何らかの障害福祉サービスの指定事業者であり、かつ、24時間、利用者からの連絡に対応できる体制となっていること |
| ・ |
相談支援専門員の資格を有するサービス管理責任者を配置していること |
| ・ |
週単位で個別支援計画を作成するとともに、定期的にサービス担当者会議を開催すること
| ※ |
市町村は、対象者に対し、定期的に、適切なサービスが報告どおり提供されているかどうか等について、実地で確認調査を行う。 |
| ※ |
重度障害者等包括支援は、これまでにない新たなサービスであることから、本年夏を目途に、各地の先進事例の収集・分析を行い、サービスの質の確保を含め具体的な事業運営の在り方についてのマニュアルを作成する。 |
|
|
【サービス利用計画】
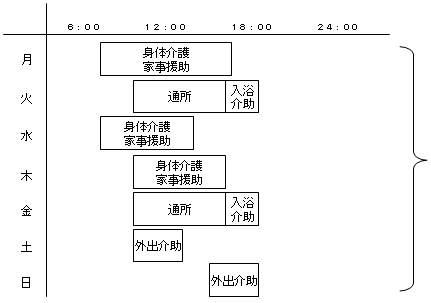
|
|
| 1. |
国庫負担基準について
| ○ |
国庫負担基準は、障害福祉サービスの地域格差が大きい中で、限られた国費を公平に配分する観点から設定するものであり、訪問系サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援)を対象に設定する。
| ⇒ |
日中活動系サービスを含めた設定については、全国統一の給付管理システムが導入された段階で検討。 |
| ※ |
なお、国庫負担基準は、「利用者一人当たりの支給上限額」でなく、市町村に対する国費配分の基準額であり、市町村は利用者の心身の状況や介護者の状況等を個別に勘案し、支給量(時間数や単位数)を決定することとなる。 |
|
|
| 2. |
基準額設定の考え方
| ○ |
現在の市町村の支給実績、支援費の国庫補助基準額等を勘案し、全国の9割程度の市町村の支給実績をカバーできるよう、サービスの種類に応じ、障害程度区分ごとに設定する。
|
| ○ |
なお、新たに制度化された重度障害者等包括支援の基準額については、著しく重度の障害者の給付実績、入所サービスの報酬水準等を勘案して設定する。
【参考】
| ◇ |
施設訓練等支援費(入所)の費用額/月
| 身体障害者療護施設 |
約32万円〜約45万円 |
(筋萎縮者側索硬化症者等加算を含む)
|
| 知的障害者更生施設 |
約35万円〜約40万円 |
(強度行動障害者特別支援加算を含む)
| (注) |
ともに、食費・光熱水費分を控除した平成17年度の区分A単価(丙地) |
|
|
| ◇ |
重度障害者等包括支援対象者の在宅サービス平均利用実績
| 約36万円 |
| (注) |
「障害程度区分判定等試行事業」における重度障害者等包括支援対象者のサービス利用実績 |
|
|
|
|
|
| 3. |
経過措置等
| ○ |
制度施行時点において、国庫負担基準を超える給付水準の自治体については、従前の補助実績に基づき、国庫負担を行う。
|
| ○ |
国庫負担基準の基礎となる障害程度区分は、新しい制度であり、各区分に該当する方々の分布状況等を見極める必要があることから、平成20年度までの3年間は、すべての訪問系サービスに係る障害程度区分の基準額を合算して適用する。
|
| ○ |
都道府県地域生活支援事業により、重度の障害者の割合が著しく高いために国庫負担基準を超過する小規模自治体等を対象に、一定の財政支援を行うことを可能とする。 |
|
|
| ○ |
国庫負担基準は、現在の支援費の国庫補助基準額を踏まえ、全国の9割程度の市町村の支給実績をカバーできるように設定する。 |
支援費制度の国庫補助基準額
| |
| 一般 |
移動介護利用 |
全身性障害者 |
| 69,370円 |
107,620円 |
216,940円 |
|
|
↓
障害者自立支援法における国庫負担基準額のイメージ
| (1) |
|
居宅介護対象者
| 区分1 |
区分2 |
区分3 |
区分4 |
区分5 |
区分6 |
|
障害児 |
| ○○単位 |
○○単位 |
○○単位 |
○○単位 |
○○単位 |
○○単位 |
○○単位 |
|
| (2) |
行動援護対象者
| 区分3 |
区分4 |
区分5 |
区分6 |
|
障害児 |
| ○○単位 |
○○単位 |
○○単位 |
○○単位 |
○○単位 |
|
| (3) |
重度訪問介護対象者
| 区分4 |
区分5 |
区分6 |
| ○○単位 |
○○単位 |
○○単位 |
|
| (4) |
重度障害者等包括支援対象者
|
| (注1) |
1単位当たりの単価は、地域区分別に定める |
| (注2) |
介護保険対象者、日中活動系サービス利用者については、介護保険や日中活動系サービスの利用を踏まえた別途の基準額とする。 |
|
|
| ○ |
障害者自立支援法では、現行の支援費制度同様、介護保険優先の規定が設けられており、介護保険対象者については、まずは介護保険のサービスを利用していただくこととなっている。
|
| ○ |
国庫負担基準についても、こうした観点から、介護保険対象者については、介護保険利用相当分を控除して設定するものとする。
| * |
なお、利用する介護保険のサービスの種類については、一律の制限は設けないこととする。 |
|
|
| ○ |
介護保険の対象となる場合、介護保険(要介護5)の月90時間相当分と、支援費の国庫補助基準時間である125時間との差分(6万円)を設定
|
| ○ |
重度訪問介護や重度障害者等包括支援の対象者について、介護保険では給付対象となっていない移動介護相当分等を算定する。
|
|
| ○ |
日中活動系サービスを加えた国庫負担基準の設定については、全国統一の給付管理システムの導入を待って検討することとしているが、通所サービス利用者と未利用者との間では訪問系サービスの利用の度合いが異なること、限られた国費をできるだけ公平に配分する必要があることを踏まえ、通所サービスを利用する者の訪問系サービスの国庫負担基準については、居住系サービスの報酬水準を基礎として算定する。 |
|
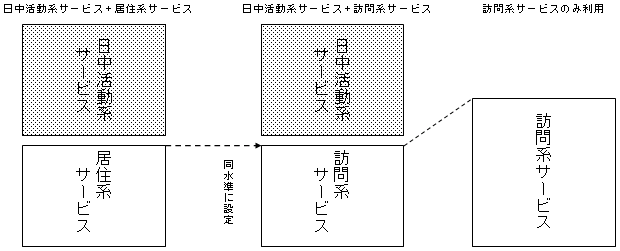
【参考】通所サービスの利用の有無でみた訪問系サービスの利用額
| 通所サービス利用者の場合 |
月57,000円 |
| 通所サービス未利用者の場合 |
月97,000円 |
〜障害程度区分判定等試行事業の結果から〜
|
|
生活介護事業
| ○ |
常時介護を要する者に対し、食事、入浴等の介護、生産活動や創作的活動の機会提供等を実施。 |
|
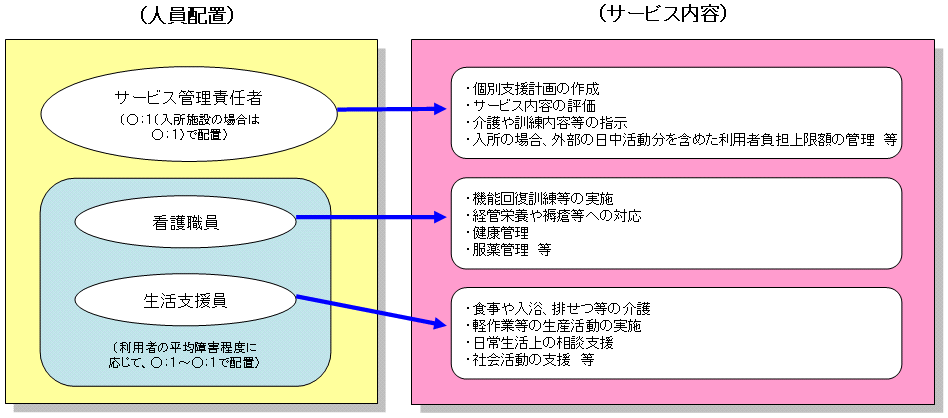
| ※1 |
居住の場として、夜間の介護等を行う「施設入所支援」を実施。 |
| ※2 |
利用期間の制限なし(利用者の状態に応じて地域移行を支援)。 |
|
【ポイント】
| 1. |
人員配置基準
| ○ |
障害種別等により、利用者の状態や支援のあり方が多様であることから、事業者ごとの利用者の平均的な障害程度に応じ、複数の人員配置基準を設定。
|
| ○ |
報酬については、個々の利用者の状態像に応じた単価とするのではなく、サービスの提供体制に応じた単価設定とし、事業者が、利用者の平均的な障害程度及び重度の障害者の人数に応じ、指定基準に加えて人員を加配した場合には、報酬上評価。 |
|
|
療養介護事業
| ○ |
病院等への長期入院による医療に加え、常時介護を要する者に対し、医学的管理の下における介護、日常生活上の支援等を実施。 |
|
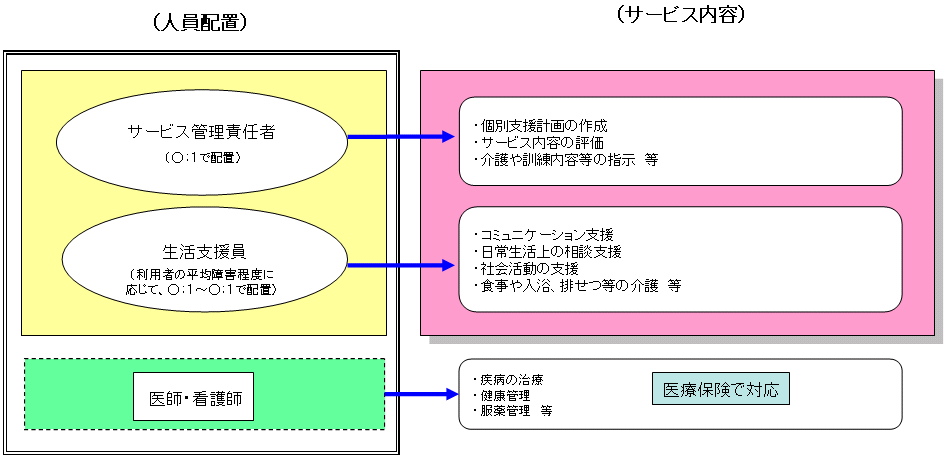
| ※1 |
食費については、医療保険より給付。 |
| ※2 |
利用期間の制限なし(利用者の状態に応じて地域移行を支援)。 |
|
【ポイント】
| 1. |
対象者
| ○ |
ALS患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者、筋ジストロフィー患者及び重症心身障害者について、適切な医療及び常時の介護が提供される環境を確保。 |
|
| 2. |
事業者の指定
| ○ |
利用者への介護を適切に行う体制が確保されているものとして、指定基準を満たしている医療機関を指定。 |
|
| 3. |
人員配置基準
| ○ |
利用者が意思疎通への支援や手厚い介護を要する重度の障害者であることを踏まえ、生活支援員を配置。
その際、事業者ごとの利用者の平均障害程度区分に応じ、指定基準に加えて人員を配置した場合には、報酬上評価。 |
| ○ |
重度の障害者への入院医療の提供にふさわしい人員を配置。 |
|
|
自立訓練(機能訓練)事業
| ○ |
身体障害者に対し、地域生活を営むことができるよう、身体的リハビリテーション、日常生活に係る訓練等の支援を実施。 |
|
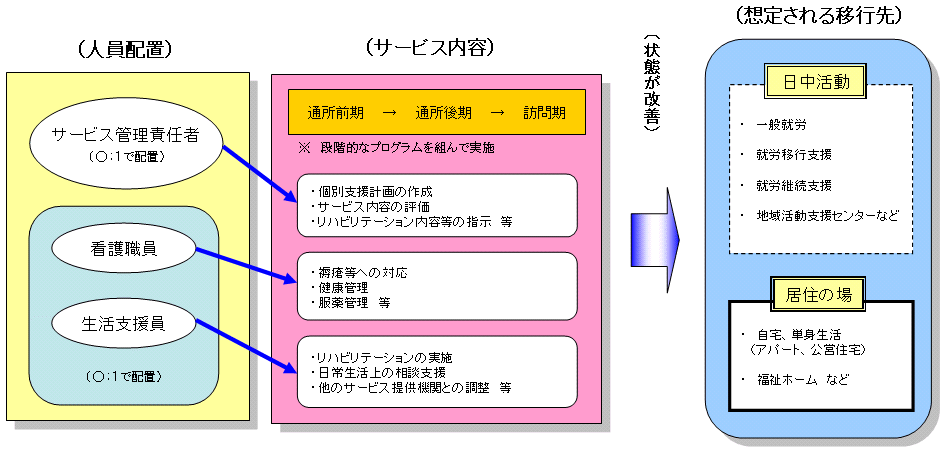
| ※1 |
原則、通所や訪問によるサービスを組み合わせ、必要に応じ施設入所支援と併せて実施。 |
| ※2 |
利用期間を限定。 |
|
自立訓練(生活訓練)事業
| ○ |
知的障害者・精神障害者に対し、地域生活を営むことができるよう、日常生活能力の向上を図り、サービス提供機関との連絡調整を行う等の支援を実施。 |
|
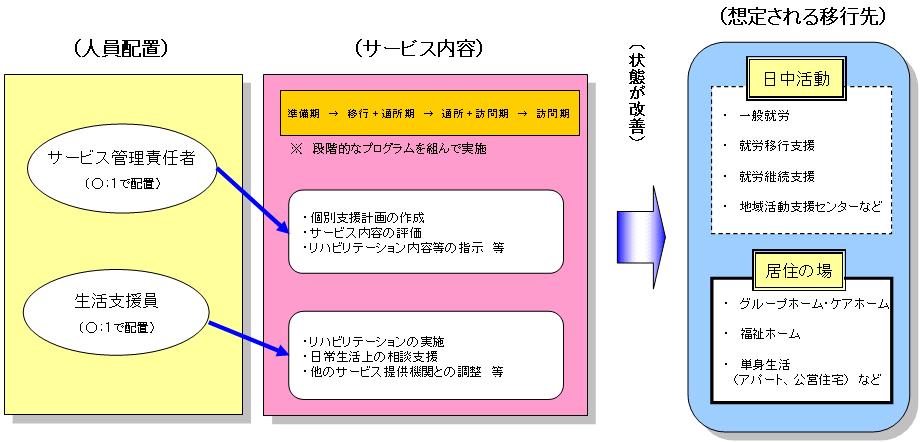
| ※1 |
原則、通所や訪問によるサービスを組み合わせ、必要に応じ短期滞在、施設入所支援と併せて実施。 |
| ※2 |
利用期間を限定。 |
|
【ポイント(機能訓練・生活訓練共通)】
| 1. |
サービスの提供
| ○ |
サービスを効果的・効率的に提供し、的確に目標が達成されるよう、個々の利用者ごとに、個別支援計画により、標準期間(機能訓練1年6ヶ月、生活訓練2〜3年)の範囲内で利用期間を設定し、その間に達成する目標や支援の内容を位置付けるととともに、サービス提供期間を通じた支援プロセスを管理。
|
| ○ |
支援の進捗状況に応じ、通所によるサービスと自宅等の訪問によるサービスを組み合わせ、段階的に実施し、それぞれ報酬上評価。
|
| ○ |
サービス提供の開始に当たり、暫定支給決定期間において、利用者の意思、支援効果の見込み、達成目標等を確認し、これを報酬上評価。
|
| ○ |
利用期間について、標準期間に基づき設定する一定期間の範囲内で更新を可能とし、これを超える場合には、市町村審査会の個別審査により判定。
なお、事業者ごとの平均利用期間が標準期間を超える場合には、報酬を減算。 |
|
|
【機能訓練】
| 1. |
訪問による訓練
| ○ |
病院におけるリハビリテーションの後、居宅における日常生活上の訓練が必要であって、通所によるサービスの利用が困難と認められる等の場合、訪問に限定したサービスを報酬上評価。 |
|
|
【生活訓練】
| 1. |
訪問による訓練
| ○ |
日中は、就労等のため、通所によるサービス利用が困難であって、住まいの場における日常生活面の訓練が必要であると認められる者について、訪問によるサービスと、必要に応じた短期間の滞在を組み合わせるサービスを報酬上評価。 |
|
| 2. |
短期間の施設滞在
| ○ |
短期間の施設への滞在について、(1)生活訓練の一環として、個別支援計画に基づき提供される場合、(2)心身の状況の悪化防止など、緊急の必要性が認められる場合、報酬上評価。 |
|
| 3. |
精神障害者の退院の促進
| ○ |
精神科病院からの病棟転換等を行い、入院患者の退院を促進するよう、夜間を含めた自立訓練事業を行う場合、報酬上一定の評価を行う。 |
|
|
就労移行支援事業
| ○ |
一般就労等を希望する者に対し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労・定着を図る支援を実施。 |
|
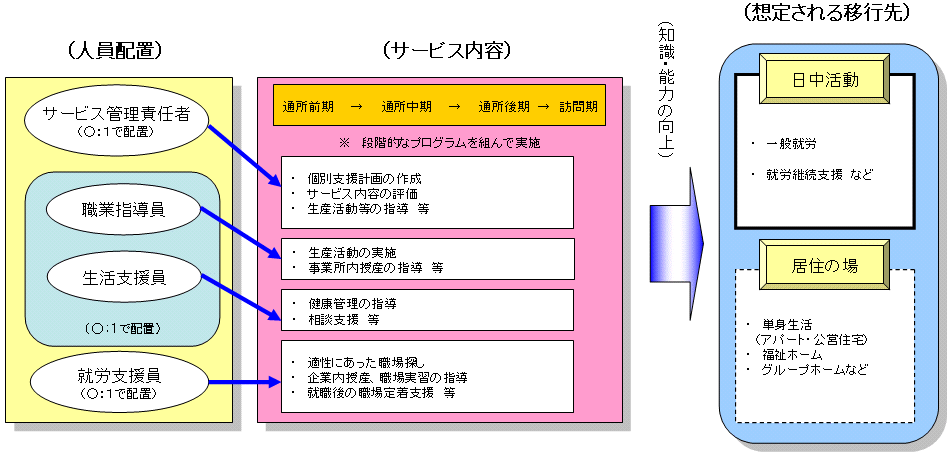
| ※1 |
通所によるサービスを提供、必要に応じ施設入所支援を付加。 |
| ※2 |
利用期間を限定。 |
|
【ポイント】
| 1. |
サービスの提供
| ○ |
サービスを効果的・効率的に提供し、的確に目標が達成されるよう、個々の利用者ごとに、個別支援計画により、標準期間(2年)の範囲内で利用期間を設定し、その間に達成する目標や支援の内容を位置付けるとともに、サービス提供期間を通じた支援プロセスを管理。
|
| ○ |
支援の進捗状況に応じ、通所によるサービスと職場等の訪問によるサービスを組み合わせ、段階的に実施し、これらを報酬上評価。
|
| ○ |
サービス提供の開始に当たり、暫定支給決定期間において、利用者の意思、支援効果の見込み、達成目標等を確認し、これを報酬上評価。
利用期間について、標準期間に基づき設定する一定期間の範囲内で更新を可能とし、これを超える場合には、市町村審査会の個別審査により判定。
なお、事業者ごとの平均利用期間が標準期間を超える場合には、報酬を減算。 |
|
| 2. |
目標(一般就労)の達成度に応じた評価
| ○ |
事業の利用を通じて一般就労し、かつ、その職場に継続して就労する者が、利用者の一定割合に達する場合、これを報酬上評価。 |
|
| 3. |
精神障害者の退院の促進
| ○ |
精神科病院からの病棟転換等を行い、入院患者の退院を促進するよう、夜間を含めた就労移行支援事業を行う場合、報酬上一定の評価を行う。 |
|
|
就労移行支援事業と労働施策の連携
就労継続支援(雇用型・非雇用型)事業
(雇用型)
| ○ |
一般企業での雇用が困難な者に対し、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力の向上を図る支援を実施。 |
(非雇用型)
| ○ |
一般企業等での雇用が困難な者、一定年齢に達している者等に対し、就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図る支援を実施(雇用契約は結ばない)。 |
|
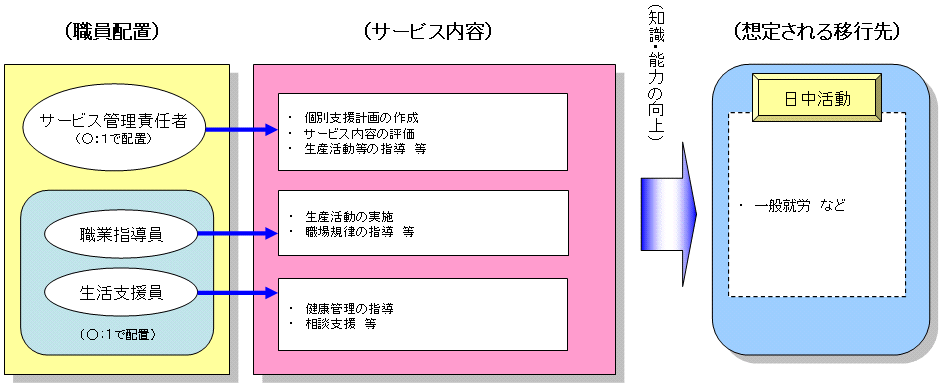
| ※1 |
通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供。 |
| ※2 |
利用期間の制限なし(利用者の状態に応じて、一般就労等への移行を支援)。 |
|
【ポイント(雇用型)】
| 1. |
障害者以外の雇用
| ○ |
生産性の向上を図り、多様な業種において就労機会の拡大を図るため、一定の範囲内で、障害者以外の者の雇用が可能。 |
|
| 2. |
定員規模の緩和
| ○ |
多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、最低定員の基準を緩和し、10人から事業実施が可能。 |
|
|
【ポイント(非雇用型)】
| 1. |
目標工賃の設定
| ○ |
利用者の工賃水準の向上を図るため、事業者ごとに平均工賃の目標水準を設定することとし、平均工賃実績と併せて都道府県知事への報告、公表を行う。 |
|
| 2. |
目標(工賃水準)の達成度に応じた評価
| ○ |
就労等の機会の提供に相応しいサービスを確保する観点に立って、工賃水準に着目して事業の達成度を評価するため、事業者の平均工賃が、地域の最低賃金に対して一定水準(1/3)に達し、かつ、目標水準を上回る場合、報酬上評価を行う。また、平均工賃が地域の最低賃金に対して著しく低い場合、事業者は改善計画を作成するとともに、都道府県が重点的に指導することとし、それでも改善されない場合における減算措置の導入について、実施状況等を踏まえ、今後、検討。
|
| ○ |
事業者の指定にあたり、平均工賃が工賃控除程度の水準を上回ることを要件とする。 |
|
| 3. |
雇用型への移行支援
| ○ |
非雇用型から雇用型への転換を促進するため、事業者の平均工賃が地域の最低賃金の一定水準以上であって、かつ、雇用型事業所への転換計画を作成して取組を強化する等の場合、一定期間に限り、報酬上評価を行う。 |
|
| 4. |
生産活動の利用支援
| ○ |
重度の障害等により、生産活動への従事に当たり手厚い支援を要する者が、利用者の一定割合に達している場合には、これに要する人員配置を報酬上評価する。 |
|
|
児童デイサービスの見直しについて
〈対象者〉
| ○ |
法律上、支援費の対象となる障害児は、18歳未満が対象。 |
| ○ |
ただし、児童デイサービスについては、国庫補助の対象児童を年齢で限定。
早期療育の効果の高い範囲として、「幼児を原則とし、小学生も可」としている。 |
| ○ |
サービス内容は、日常生活における基本的な動作の指導及び集団への適用訓練。 |
〈問題点〉
| ○ |
療育を目的としたサービスであるものの、実態は、療育サービスと放課後対策的なサービスが混在。 |
|
原則として、以下のような整理とする。
| ※ |
市町村は、支給決定の際、当該児童が療育指導を必要とするか否かについて、
児童相談所・保健所に意見を求めることが望ましいものとする。 |
|
|
〈新制度における児童デイサービス〉
○(原則)児童デイサービス
| 対象者 |
: |
療育の観点から個別療育、集団療育を行う必要が認められる児童。(必要に応じ児童相談所・保健所に意見を求める)
就学前児童を原則とするが、小学生から18歳未満の児童も可とする(年齢要件なし)。 |
| 事業内容 |
: |
療育目標を設定した個別プログラムの策定及び評価。
指導員等による児童への個別指導を1日に一定時間以上行う。
個別プログラムに沿った集団療育を行う。 |
| 人員配置 |
: |
指導員又は保育士(現行の配置基準(15:2)より手厚い配置)に加え、サービス管理責任者を必置。
報酬単価:現行の基準単価+α |
|
| ○ |
一定以上の年齢に達している児童など、集団療育が適切であると考えられる児童に対する療育指導の検討
支援費制度において、児童デイサービスを実施している事業者及びその利用者に配慮し、一定の期間内(3年を想定)は現行制度の事業所を指定児童デイサービス事業所とみなす経過措置を設ける。
対象事業者は、支援費制度上の児童デイサービス指定事業者に限り、新規は認めない。
| 対象者 |
: |
療育の観点から、集団療育を行う必要が認められる児童。(必要に応じ児童相談所・保健所に意見を求める)
幼児を原則とするが、小学生から18歳未満の児童も可とする(年齢要件なし)。 |
| 事業内容 |
: |
指導員等の直接的監視のもとに、複数の児童に対し指導・訓練を行う。(必ずしも、1対1での指導時間を必要としない)。個別プログラムの策定。 |
|
|
〈見直し時期〉
| |
平成18年10月〜
| |
(児童デイサービスの在り方については、3年後の障害児サービス全体の見直しの中でも検討を行う。) |
|
|
障害児タイムケア事業
養護学校等下校後に活動する場について確保するとともに、障害児を持つ親の就労支援と家族の一時的休息を目的として、小学校の空き教室等で中高生等障害児を預かるサービス |
施設入所支援
| ○ |
夜間において、介護が必要な者や、通所することが困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者に対し、居住の場を提供するとともに、安定した日常生活が営めるよう、支援を実施。 |
|
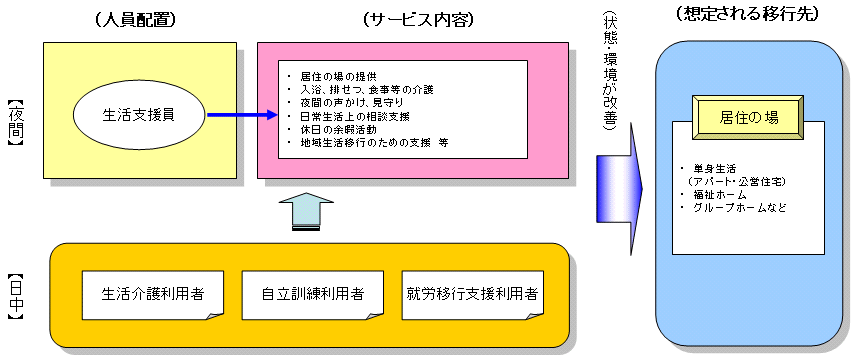
| ※1 |
生活介護利用者については、区分4以上(50歳以上の者にあっては、区分3以上)の者の利用が可能。 |
| ※2 |
自立訓練又は就労移行支援利用者については、地域の社会資源の状況により通所が困難であるなど、特に必要と認められる場合に限り、利用が可能(利用期間は、自立訓練又は就労移行支援の利用期間に限定)。 |
【ポイント】
| 1. |
職員の配置
| ○ |
夜間の介護等に必要な職員については、生活介護と同様、利用者の平均的な障害程度及び重度の障害者の人数に応じ、配置。 |
|
| 2. |
安定的な日常生活の確保
| ○ |
地域生活への移行を進める観点から、退所する利用者に対し、退所後の居住の場の確保、在宅サービスの利用調整等を行った場合に、報酬上評価。
|
| ○ |
適切な内容及び栄養量の食事が確保されるよう、管理栄養士等を配置し、適切な栄養管理を行った場合に、報酬上評価。
|
| ○ |
利用者の入院又は外泊期間については、利用者の日常生活の場を確保する観点から、一定期間居室が確保されるよう、報酬上評価。 |
|
| 3. |
著しく重度の障害者への支援
| ○ |
人工呼吸器を装着したALS患者、重症心身障害や強度行動障害といった、意思の疎通に困難が伴う著しく重度の障害者に対する適切な介護体制を確保するため、これらの者が利用者の一定割合を超える場合において、指定基準に加えて人員を配置したときは、報酬上評価。 |
|
|
共同生活援助・共同生活介護(グループホーム・ケアホーム)事業
| ○ |
日中に就労又は就労継続支援等のサービスを利用している知的・精神障害者に対し、地域生活を営む住居において、日常生活上の相談、介護等の支援を実施。 |
|
【人員配置の構成】
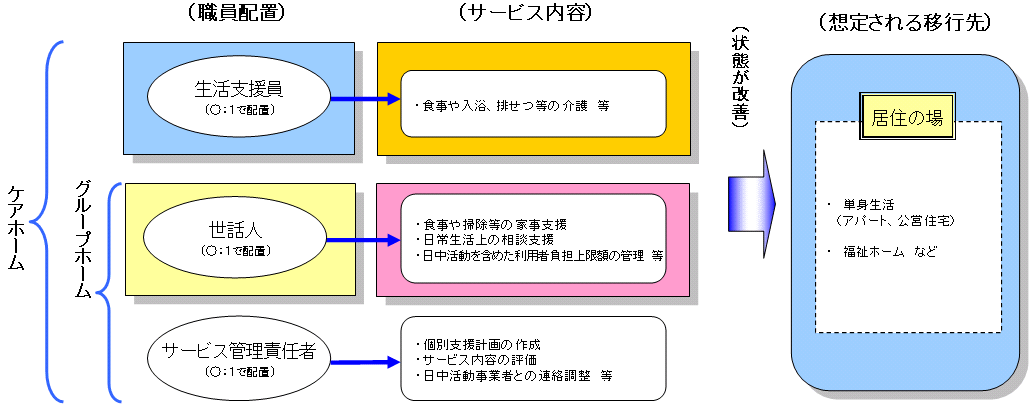
| ※1 |
利用期間の制限はなし(利用者の意向や状態に応じ、単身生活等への移行を支援)。 |
| ※2 |
介護サービスについては、ケアホーム事業者の負担により、ホームヘルプ事業者への委託による提供が可能。 |
|
【ポイント】
| 1. |
指定の単位
| ○ |
個々の住居ではなく、法人ごとに一定範囲の地域内で実施する事業全体に着目して事業者を指定し、人員配置基準を適用。 |
|
| 2. |
介護等の支援を提供する支援体制
| ○ |
サービス管理責任者のほか、利用者の総数及び障害程度区分に応じて世話人及び生活支援員を配置し、報酬上評価。その際、著しく重度の障害者に配慮。
|
| ○ |
ケアホームにおける介護サービスについては、事業者の責任の下、外部事業者への委託が可能。
また、重度の障害により日中活動を利用できない期間について、報酬上評価。
|
| ○ |
夜間の支援を行う義務を事業者に課した上、ケアホームにおいて、夜間、適切な勤務体制を確保した場合には、利用者の障害程度区分に応じ、報酬上評価。
|
| ○ |
小規模な事業所については、世話人や夜勤を確保できないケースがあることから、経過的な措置を実施。 |
|
| 3. |
単身生活等への移行支援
| ○ |
単身生活等への移行を積極的に推進する事業者について、報酬上一定の評価。 |
|
| 4. |
地域移行型ホーム
| ○ |
入所施設や病院の敷地内に設置する場合の取扱いについては、居住の場としての意義、地域生活への段階的移行の促進という観点に立って、「地域移行型ホーム」と位置付けた上、次の条件を満たす場合に限定して認める。
| (1) |
利用期間を限定 |
| (2) |
利用者の地域活動への参加を確保 |
| (3) |
居住の場として相応しい環境を確保 |
| (4) |
地域の居住サービス整備量が十分でない場合に限定 |
|
|
| 5. |
定員規模
| ○ |
一住居当たりの定員について、下限を2人とする一方、上限を10人とする。
また、地域生活移行の受け皿として、居住サービスの量的整備を推進する観点から、既存社会資源を活用する場合には、20人(10人までを1つとする生活単位が2つまで)まで認める等の基準を設定。
なお、一住居の定員が8人以上となる場合は、効率的運営が可能となることを踏まえ、報酬を減算。 |
|
|
グループホームに関する課題と対応の方向
【課題】
| 1. |
サービスの質と責任関係が不明確
| ○ |
重度の判定基準が不明確 |
| ○ |
障害程度に応じた人員配置が義務付けられていない(世話人のみ) |
| ○ |
外部からのホームヘルプ利用が認められている |
|
|
|
→ |
【対応の方向】
| ○ |
障害程度区分により、ケアホーム対象者を明確化
|
| ○ |
障害程度区分に応じた人員配置を義務付け
| * |
著しく重度の障害者に配慮 |
| * |
夜間支援体制を評価 |
|
| ○ |
ケアホーム事業者の責任による介護の提供
| * |
重度障害により日中活動を利用できない期間を評価 |
|
|
|
| 2. |
多数の長期間入所・入院者が存在
| ○ |
グループホームと他サービスがばらばらに提供されている |
| ○ |
グループホームの整備量が不十分 |
|
|
|
| ○ |
居住の場であるグループホーム、ケアホームと日中活動を組み合わせ、生活全体を支援
|
| ○ |
グループホーム、ケアホームの量的整備を推進
|
| ○ |
グループホームからの自立を視野に入れた支援
|
|
|
| 3. |
住居を単位とする小規模な事業運営
| ○ |
4人といった小規模単位でも運営できることを前提 |
|
|
|
| ○ |
夜間等の支援体制を確保できる標準的な事業規模へ移行
|
|
|
グループホーム・ケアホームの事業運営
【ポイント】
| (1) |
個々の住居ではなく、一定の範囲に所在する住居全体を事業者として指定。 |
| (2) |
世話人は、全体の利用者数に対し、配置。これまで、利用者数にかかわらず1人配置とされている仕組みを改め、10人又は6人につき1人以上の水準を確保。 |
| (3) |
サービス管理責任者は、全体の利用者数に対し、30人につき1人以上の水準で配置。 |
| (4) |
生活支援員は、全体の利用者数に対し、利用者ごとの障害程度区分に応じて配置。 |
| (5) |
夜間の適切な支援体制を確保(一定の条件に該当する場合には報酬上別に評価)。 |
| (6) |
1住居の最低利用人員は2人以上。 |
|
【イメージ】
人員配置と評価の仕組み
| ○ |
グループホーム、ケアホームは、日中活動と組み合わせて利用することが基本。 |
| ○ |
世話人は、事業者及び近接した住居の利用者総数に対して配置し、報酬上評価。 |
| ○ |
生活支援員は、個々の利用者の障害程度に応じて配置し、報酬上評価。 |
| ○ |
事業者に対し、夜間における緊急時等の対応を義務付け、さらに夜間支援体制に応じて報酬上評価。 |
|
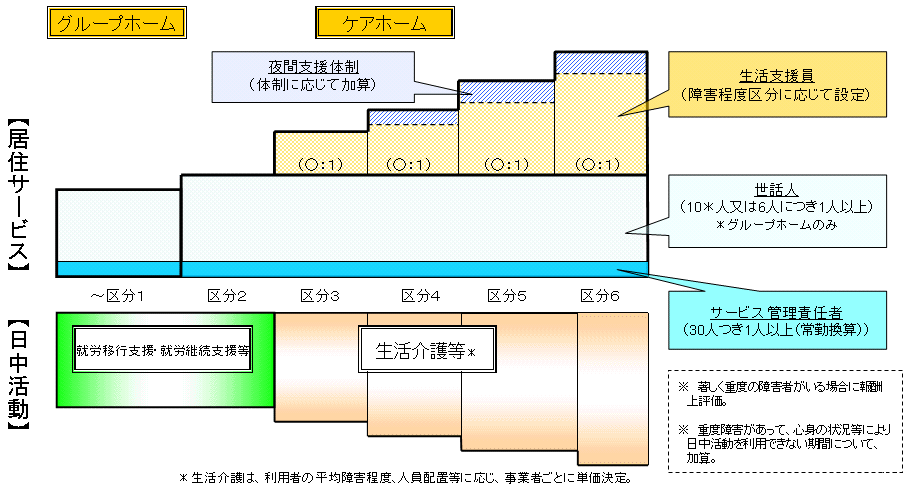
小規模事業者に対する経過措置
| ○ |
グループホーム、ケアホームについて、個々の住居ではなく、一定の範囲内に所在する住居を全体として捉え、標準的な事業規模(30人)への移行を進めることにより、必要な人員配置と安定的な運営の確保を図る。 |
| ○ |
しかしながら、当面、標準規模に達せず小規模で運営せざるを得ない事業者については、利用者ごとの障害程度区分に応じて配置される生活支援員を除き、夜勤や世話人を確保できないケースがあり得る。 |
| ○ |
このため、小規模な事業者でも最小限の夜勤と世話人を確保できるよう、経過的な加算を行う。 |
|
| ○ |
利用者数に応じ、10人*又は6人につき1人以上を配置し、定額で評価する仕組み(*グループホームのみ)
| 《経過措置》 |
利用者が少数の場合、世話人1人分を確保できるよう報酬上評価
|
|
|
| ○ |
夜勤体制を確保する場合、利用者数に応じ、定額で評価する仕組み
| 《経過措置》 |
利用者が少数の場合、夜勤1人分を確保できるよう報酬上評価
| *利用者の障害程度区分が一定以上の場合に限定 |
| *3年間限定(段階的に縮小) |
|
|
|
|
| 注: |
施行時に現に実施している事業者に限定。複数のグループホームを運営している場合、相互に独立して運営されていると認められるものでなければ、全体で事業規模を算定。 |
|
グループホーム、ケアホームのあり方について
−設置場所等に関連する検討−
|
|
|
|
| ○ |
グループホーム、ケアホームの居住の場としての意義は何か。
|
|
|
→ |
| ○ |
地域に住む人と自然に交わる
|
| ○ |
住居から離れた日中活動の場へ通う |
|
|
| ○ |
多数の長期間入所・入院者が存在する中、地域生活への移行をどのように具体的に進めていくか。 |
|
|
→ |
| ○ |
グループホーム、ケアホームの量的整備の推進
| ・ |
新規整備の他、入所施設等からの転換 |
| ・ |
地域住民の理解の深化 |
|
| ○ |
長期入所・入院からの段階的移行の推進 |
|
|
入所施設・病院の敷地内における地域移行型ホームの設置について(案)
|
|
|
|
入所・入院から地域生活への移行プロセスを支える「地域移行型ホーム」と位置付け、以下の条件を満たす場合に限定する。
| ○ |
利用者は、日中、外部の事業所等へ通う
|
| ○ |
経過的な利用とする
|
| ○ |
地域住民との交わりを確保する
|
| ○ |
居住の場としてふさわしい環境を確保する
|
| ○ |
地域のサービス整備量が十分でない場合に限る |
|
|
→ |
| ○ |
個々の利用者の利用期間を、原則2年間と設定。
|
| ○ |
利用者の地域活動への参加を確保
| * |
外部の日中活動サービス等を組み合わせた個別支援計画を作成 |
| * |
運営に関し、地域の関係者等を含めた協議の場を設定 |
|
| ○ |
入所施設・病院から一定の独立性を確保
| * |
共有部門(居間、便所、洗面設備等)を少人数ごとに配置し、入所施設・病院との共有はしない |
|
| ○ |
居住サービスが不足する地域に限定。既存の建物を活用する場合に限ることとし、併せて入所施設や病院の定員を減少。
|
|
|
住居1か所当たりの利用者数について(案)
| ○ |
2人以上から可能 *世話人等による適切なサービス提供を前提 |
|
【原則】
| ○ |
10人まで可能(10人までを1つの生活単位とする居住形態)
| * |
現行精神障害者グループホームは4人以上・上限なし |
|
【既存資源を活用する場合】
| ○ |
20人まで可能
| ・ |
より小規模な生活単位を確保するため、共有部門(居間、便所、洗面設備等)を少人数ごとに配置(10人までを1つとする生活単位が2つまで可能)
|
|
| ○ |
居住サービスが不足する地域において、特に必要があるとして都道府県知事が個別に認める場合、30人まで可能(10人までを1つとする生活単位を3つまで可能)
| * |
入所施設の定員30人以上、福祉ホームの定員5人以上 |
| * |
現行通勤寮の定員20人以上 |
|
| ※ |
多人数の運営により効率化が図られることから、住居1箇所当たりの利用者が8人以上の場合、報酬を減算。 |
|
|
指定相談支援事業について
何らかの障害福祉サービスを利用する者であって、下記のいずれかに該当する者。
| (1) |
入所・入院から地域生活へ移行するため、一定期間(6ヶ月程度を想定)集中的な支援を必要とする者 |
| (2) |
単身で生活している者(家族が要介護状態である等のため、同居していても適切な支援が得られない者を含む。)であって、下記の状態にあるために、自ら福祉サービスの利用に関する調整を行うことが困難であり、計画的な支援を必要とする者
| ○ |
知的障害や精神障害のため自ら適切なサービス調整ができない |
| ○ |
極めて重度な身体障害のため、サービス利用に必要な連絡・調整ができない |
|
| (3) |
重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当する者のうち、重度訪問介護等他の障害福祉サービスの支給決定を受けた者 |
| ※ |
施設入所者、自立訓練の利用者、グループホーム及びケアホーム利用者、重度障害者等包括支援の利用者は、計画的プログラムによる包括的支援を受けていることから対象としない。 |
|
| (1) |
相談支援
| ○ |
生活全般の相談 |
| ○ |
サービス利用に関する情報提供 |
| ○ |
サービス利用計画の作成 |
| ○ |
サービス事業者の担当者会議の開催 |
| ○ |
サービス事業者との連絡調整 |
| ○ |
モニタリング |
| ○ |
利用者負担の上限額管理 等 |
|
| (2) |
サービスの利用に係る自己負担なし。 |
|
| (1) |
サービス利用計画作成費については、先行地域の相談支援の状況やホームヘルプサービスの報酬水準を参考として設定する。 |
| (2) |
併せて、利用者負担の上限額管理を行う対象者については加算を行う。 |
| ※1 |
月に1回以上利用者の居宅を訪問(モニタリング)するなど、適切な指定相談支援が提供されない場合は、報酬を減算する。 |
| ※2 |
新たなサービスであり、対象者の範囲について市町村間でばらつきが生じることが予想されることから、限られた財源を公平に配分する観点から、市町村の障害福祉サービス利用者数(施設入所者、自立訓練の利用者、グループホーム及びケアホーム利用者、重度障害者等包括支援の利用者を除く)の10%に相当する数を基礎として国庫負担額を設定。 |
|
| (1) |
従事者の員数
| ○ |
事業所ごとに、相談支援専門員を一名(常勤換算)以上配置する。 |
|
| (2) |
管理者
| ○ |
事業所ごとに専従の管理者を配置。ただし、事業所の管理に支障のない場合は、当該事業所の他の職務等に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 |
|
|
| (1) |
基本的な考え方
相談支援専門員は、障害特性や障害者の生活実態に関する詳細な知識と経験が必要であることから、実務経験(5年)と障害者ケアマネジメント研修の受講を要件とする。 |
| (2) |
研修の受講
実務経験を有する者又は介護支援専門員の資格を有する者は、国又は都道府県の実施する障害者ケアマネジメント研修を受講し、相談支援専門員になることができる。
| ○ |
過去上記研修を受講したことのある者については、新制度における相談支援の研修(1日程度)を19年度末までに受講しなければならないものとする。 |
| ○ |
現在、相談支援事業に従事し、実務経験の要件を満たす者のうち、これまでに上記研修を受講していない者については、平成19年度末までに国又は都道府県の実施する障害者ケアマネジメント研修を受講することを要件として相談支援専門員の業務を行うことができる。 |
|
|
| 6 |
指定相談支援事業者の相談支援事業の受託について |
| 相談支援事業は、市町村が行う地域生活支援事業の必須事業として位置付けられているが、市町村は下記の条件を満たす指定相談支援事業者に対し、相談支援事業を委託することが考えられる。 |
| ○ |
常時勤務する相談支援専門員を配置して指定相談支援事業を行っている法人であること。 |
| ○ |
事業計画や事業実績について、地域自立支援協議会において評価を受けること。 |
|
指定基準のポイント
| (1) |
障害種別にかかわらず、共通の基準とする。 |
| (2) |
サービスの質の向上の観点から、サービス管理責任者の配置、虐待防止などを新たに規定。 |
| (3) |
利用者のニーズに応じたサービスが身近な地域で提供できるよう、複数の事業を組み合わせて実施する多機能型を新たに位置付け |
|
| ○ |
事業者ごとに、サービス管理責任者を配置し、サービス提供に係る責任を明確化。
|
| ○ |
事業ごとに、サービス提供に直接必要となる職員に限定し、人員基準を設定。 |
|
| ○ |
集会室など、直接サービス提供に係らない設備等について、必置規制を外す。
|
| ○ |
居室の床面積など、面積や規模を定める規制は、最小限とする。
| ※ |
これらにより、空き教室など既存の社会資源の効率的な活用を図る。 |
| ※ |
現行施設については経過措置を講ずる。 |
|
|
(各サービス共通)
| (1) |
個別支援計画の作成、評価等のプロセスの管理
| ○ |
個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を行うプロセスを明確化。 |
|
| (2) |
虐待防止に対する責務
| ○ |
虐待を防止するために必要な措置を講ずる旨の条項を追加。 |
|
| (3) |
障害者自立支援法の理念に沿ったサービスの提供
| ○ |
障害種別にかかわらずサービスを提供するという障害者自立支援法の理念を踏まえつつ、サービスの専門性の確保の観点から必要がある場合には、障害種別により「主たる対象者」を定める。
|
| ○ |
その際、運営規程に定めるとともに、重要事項として事業所内に掲示。 |
|
| (4) |
重度の障害者に対する配慮
| ○ |
重度の障害という要因によりサービス提供を拒否することの禁止。 |
|
| (5) |
利用者負担の範囲等
| ○ |
食費・光熱水費・日用生活品費等。
|
| ○ |
居住系のサービスについては、利用者負担の上限額管理を義務化。その他のサービスは、利用者の求めに応じて実施。 |
|
| (6) |
食事の提供
| ○ |
施設入所支援等について、利用者の希望に応じ、食事の提供を行う応諾義務とする。
|
| ○ |
日中活動サービスについて、事業所の任意とする(利用者に対する事前説明及び同意を前提)。 |
|
| (7) |
多機能型の事業運営の取扱い
| ○ |
複数の事業を組み合わせて実施する多機能型を新たに位置づけ。 |
|
| (8) |
複数の場所で事業を実施する場合の取扱い
| ○ |
本体施設と一体的に運営されていると認められる場合、一つの事業所として取り扱う。 |
|
|
(各サービスに特有の事項)
| (1) |
標準的なサービス提供期間の設定(自立訓練、就労移行支援)
| ○ |
個別支援計画によるサービス提供の目安として、標準的なサービス提供期間を設定。 |
|
| (2) |
生産活動等の取扱い
| 【就労移行支援】: |
職場実習、求職活動支援等の実施 |
| 【就労継続(雇用型)】: |
雇用契約に基づく就労機会の提供、障害者以外の者の雇用の範囲 |
| 【就労継続(非雇用型)】: |
生産活動の実施と工賃の支払い、工賃目標水準の設定・公表等 |
|
| (3) |
外部サービス利用の取扱い(共同生活介護)
| ○ |
介護サービスについて、事業者の責任の下、外部事業者への委託を認める。 |
|
|
| ※ |
これらの他、「重要事項の説明」、「サービス提供の記録」、「衛生管理」等について引き続き規定。 |
|
多機能型の事業運営の考え方
(多機能型により期待される効果)
利用者のニーズに応じ、小規模な形で複数の事業を一体的に運営できるようにすることにより、身近な地域において、多様なサービスの提供体制を確保するとともに、利用者の選択肢の幅を拡大。 |
| ○ |
複数の事業を合わせた事業所ごとの定員は20人以上。 |
| ○ |
事業ごとに定める最低利用人員を満たしている。 |
| ○ |
各事業ごとの定員の上限は定めない。 |
|
| ○ |
各事業の利用人員に応じたサービス提供職員数を事業全体として確保(サービス管理責任者については、事業ごとではなく、合計利用人員に応じて配置)。
|
|
| ○ |
複数の事業を一体的に運営する場合は、多機能型と位置付けることが基本。 |
|
| (1) |
同一のサービス管理責任者によりサービス提供が行われていること。
|
| (2) |
利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われていること。
|
| (3) |
職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合に随時、複数の事業間で相互支援を行える体制にあること。
|
| (4) |
苦情処理や損害賠償等について、一体的な対応ができる体制にあること。
|
| (5) |
事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等について同一の運営規程が定められていること。
|
| (6) |
人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われていること。 |
|
| ○ |
事業ごとに定められている設備基準を満たすこととし、サービス提供に支障がないよう配慮する義務を事業者に課した上で、設備の兼用を可能とする。 |
|
|