| 1 | 平成16年における離職者の離職理由別割合をみると、個人的理由が70.4%、契約期間の満了が13.1%、経営上の都合が8.1%、定年が4.9%であった。 就業形態別にみると、一般労働者については個人的理由が65.4%、契約期間の満了が13.2%、経営上の都合が10.6%であり、パートタイム労働者については個人的理由が79.6%、契約期間の満了が12.9%、経営上の都合が3.5%であった。(厚生労働省「雇用動向調査」(平成16年)) |
| ・ | 離職理由別離職者の割合(単位:%)
|
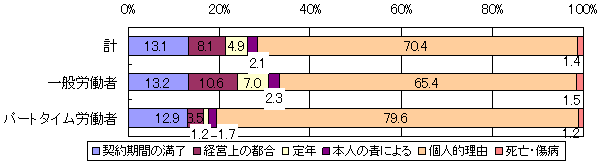
| 2 | 平成17年7〜9月において雇用調整を実施した事業所は、全体の13%であった。 その方法として希望退職者の募集、解雇を行ったものは全体の2%、臨時・季節、パートタイム労働者の再契約停止・解雇を行ったものは全体の1%である。一方、残業規制、配置転換を行ったものはそれぞれ全体の5%であった。(厚生労働省「労働経済動向調査」(平成17年11月)) |
| ・ | 雇用調整の方法別実施事業所割合(事業所規模30人以上の企業を対象に調査)(雇用調整の方法について複数回答 単位:%) |
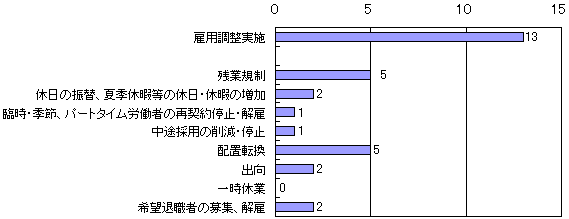
| 3 | ここ5年間において、正規従業員を解雇(懲戒解雇を除く。)したことがある企業は20.2%であり、解雇したことがない企業は77.6%であった。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
| ・ | 正規従業員の解雇の有無(単位:%) |
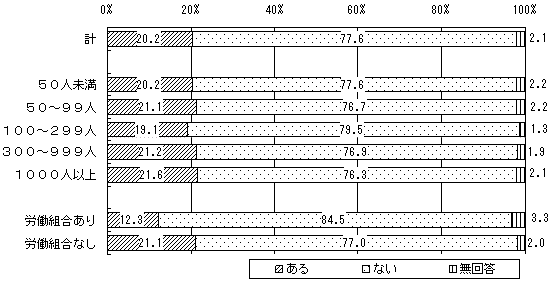
| 4 | 解雇の理由については、「経営上の理由」が49.2%と最も多く、ついで「仕事に必要な能力の欠如」が28.2%、「本人の非行」が24.4%、「職場規律の紊乱」が24.3%などとなっている。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年))
|
| ・ | 解雇の理由(複数回答 単位:%)(ここ5年間に正規従業員を解雇したことがある企業を対象に集計) |
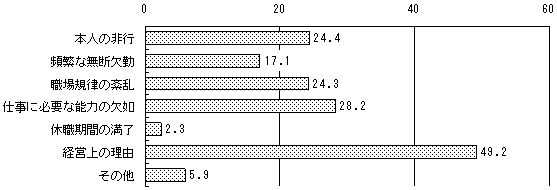
| 5 | ここ5年間に普通解雇をした企業のうち、普通解雇に先立って、警告をした企業が51.3%、是正機会の付与をした企業が46.3%となっている。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
| ・ | 普通解雇に先立つ措置(複数回答 単位:%)(ここ5年間に普通解雇をした企業を対象に集計) |
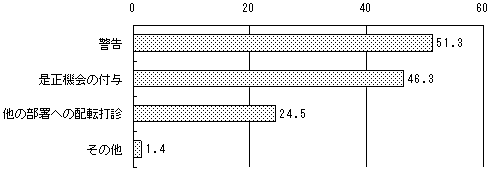
| 6 | 解雇に当たっての手続としては、解雇理由を明示するとした企業が83.9%、解雇日を明示するとした企業が73.5%、従業員本人からの意見聴取をするとした企業が49.5%、退職金の額及び支払時期を明示するとした企業が44.4%となっている。 従業員を解雇する場合の手続を定めている企業は50.7%であり、企業規模300人以上の企業では8割を超える。従業員を解雇する場合の手続を定める形式としては、就業規則が97.1%である。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
| ・ | 解雇に当たっての手続(複数回答 単位:%)(ここ5年間に正規従業員を解雇したことがある企業を対象に集計) |
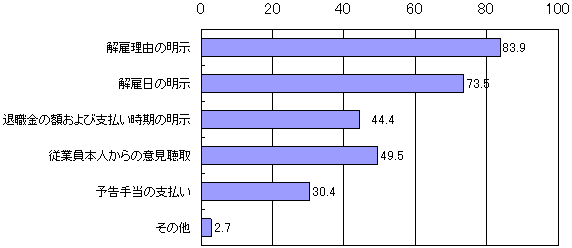
| ・ | 従業員を解雇する場合の手続の定め(単位:%)(ここ5年間に正規従業員を解雇したことがある企業を対象に集計) |
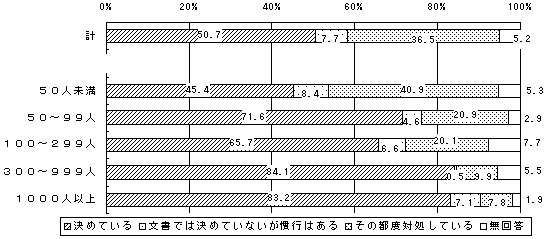
| ・ | 従業員を解雇する場合の手続の定めの形式(複数回答 単位:%)(ここ5年間に正規従業員を解雇したことがあり、従業員を解雇する場合の手続を定めている企業を対象に集計) |
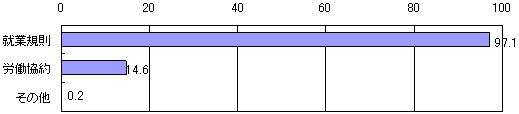
| 7 | 解雇の予告についてみると、1〜2か月程度前に本人に対して解雇する旨を通告する企業が全体の68.1%、整理解雇の場合には84.4%である。 また、解雇に当たっての手続として、予告手当の支払いを行った企業は、全体の30.4%となっている。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
| ・ | 本人への解雇の通告時期(単位:%)(ここ5年間に正規従業員を解雇したことがある企業を対象に集計) |
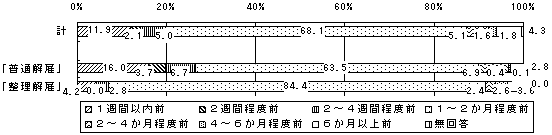
| ・ | 解雇に当たっての手続(再掲)(複数回答 単位:%)(ここ5年間に正規従業員を解雇したことがある企業を対象に集計) |
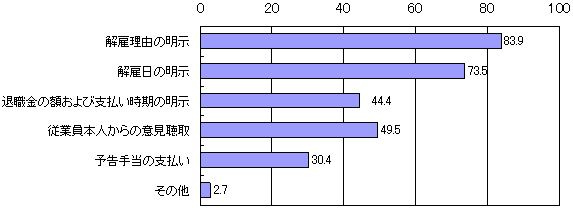
| 8 | 解雇に当たり、特に労働者側と協議をしなかった企業は69.2%である。一方、労働組合のある企業においては、68.2%の企業が労働組合と協議を行っていた。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) 組合員の解雇につき、同意、協議等の何らかの関与を行っている労働組合は84.6%である。(厚生労働省「労働協約等実態調査報告」(平成13年)) |
| ・ | 正規従業員の解雇の際の労働組合や従業員代表との間での手続内容(単位:%)(ここ5年間に正規従業員を解雇したことがある企業を対象に集計) |
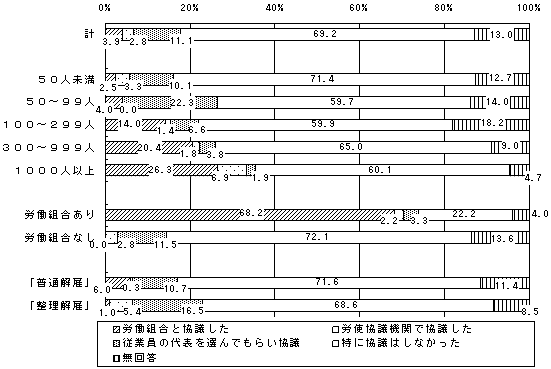
| ・ 一般組合員の解雇についての労働組合の関与(単位:%) |
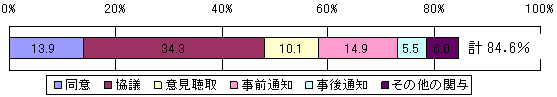
| 9 | ここ5年間に正規従業員を解雇したことがある企業のうち、解雇をめぐって解雇した従業員との間で紛争が起こったことがあった企業は11.9%、なかった企業は85.5%であった。 紛争が起こった企業のうち、解決のためにとった特別の措置については、解決金の支払が38.0%と最も多く、次いで、退職理由の変更が13.4%、解雇のとりやめが1.6%となっている。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
| ・ | ここ5年間で解雇をめぐり発生した個別労働関係紛争の有無(単位:%)(ここ5年間に正規従業員を解雇したことがある企業を対象に集計) |
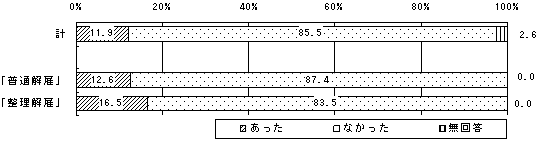
| ・ | 解雇した従業員との間の紛争の解決方法(複数回答 単位:%)(ここ5年間に正規従業員を解雇したことがあり、解雇をめぐって紛争があった企業を対象に集計) |
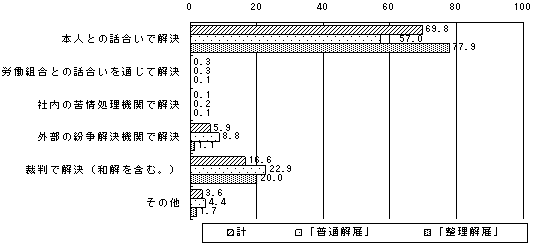
| ・ | 解雇紛争の解決のための特別な措置(複数回答 単位:%)(ここ5年間に正規従業員を解雇したことがあり、解雇をめぐって紛争があった企業を対象に集計) |
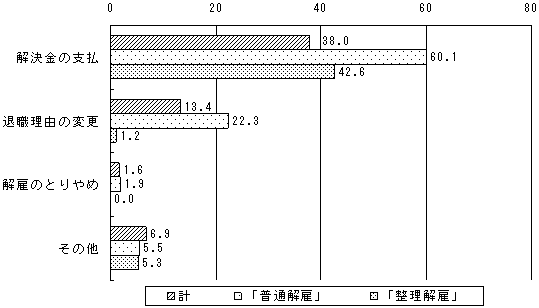
| 10 | 裁判所で争われ、平成13〜15年の3年間に終結した解雇紛争を対象とした調査によると、解雇無効判決を得た後、復帰してそのまま勤務を継続している者は41.2%である。一方で、一度復帰したが離職した者と復帰しなかった者の合計は54.9%であり、その89.3%は解決金の支払いを受けている。 和解について見ると、復帰又は再雇用を認める前提で和解をした者は21.1%である一方、復帰又は再雇用を認めない前提で和解した者は78.2%であり、その86.7%は解決金の支払いを受けている。(労働政策研究・研修機構「解雇無効判決後の原職復帰の状況に関する調査研究」(平成16年)) |
| ・ | 解雇無効判決を得た労働者の復帰状況(解雇事件の担当弁護士に対して、解雇無効判決を得た労働者の状況を調査) |
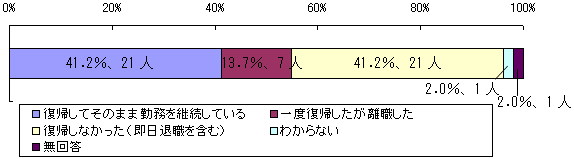
| ・ | 解決金の支払い状況(解雇事件の担当弁護士に対して、解雇無効判決を得た後「一度復帰したが離職した」「復帰しなかった」労働者の状況を調査) |
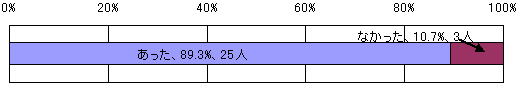
| ・ | 解決金額の状況(解雇事件の担当弁護士に対して、解決金の支払いが「あった」労働者がいる事件ごとに、「一人当たりの解決金」について調査)
|
<解決金額> 最大値:5670万円 最小値:65万円
<過去の賃金以外に支払われる解決金の月額> 最大値:60か月分 最小値:-12か月分
|
| ・ | 復帰に関する和解内容(解雇事件の担当弁護士に対して、和解により紛争を解決した労働者についての和解内容を調査) |
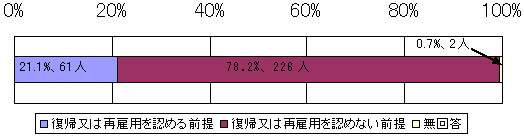
| ・ | 和解後の解決金の支払い状況(解雇事件の担当弁護士に対して、復帰又は再雇用を認めない前提で和解した労働者の状況を調査) |
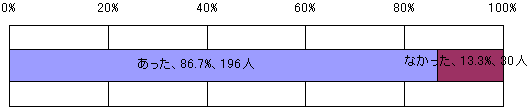
| 11 | 解雇に関する民事上の個別労働紛争相談件数、助言・指導申出件数、あっせん申請受理件数は増加傾向にある。 平成16年度では、相談件数は49,031件であり、民事上の個別労働紛争に関する相談内容全体の27.1%を占めている。助言・指導申出受付件数は1,736件で、助言・指導申出内容全体の31.4%を占めている。あっせん申請受理件数は2,519件であり、あっせん申請内容全体の40.5%を占めている。 相談内容、助言・指導申出内容、あっせん申請内容のいずれについても、解雇に関するものの割合が最も大きい。(厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室調べ) |
| ・ | 解雇に関する民事上の個別労働紛争相談件数(単位:件) |
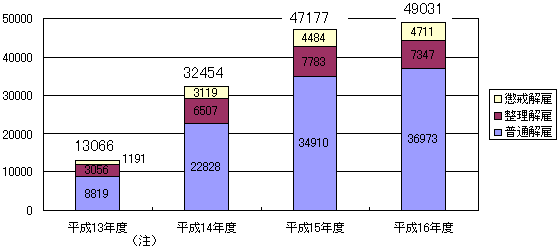 (注)「平成13年度」は平成13年10月から平成14年3月までの数値である。 |
| ・ | 民事上の個別労働紛争相談内容全体のうち、解雇に関するものの割合 |
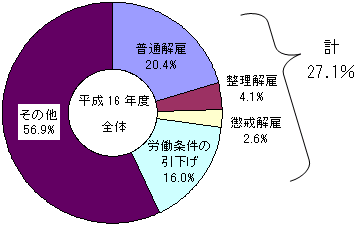
| ・ | 解雇に関する助言・指導申出受付件数(単位:件) |
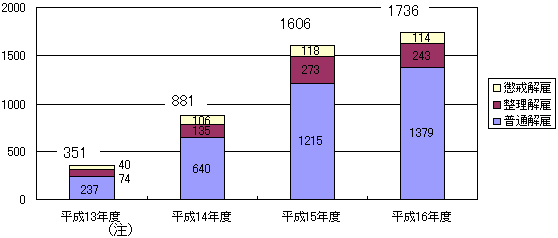 (注)「平成13年度」は平成13年10月から平成14年3月までの数値である。 |
| ・ | 助言・指導申出内容全体のうち、解雇に関するものの割合 |
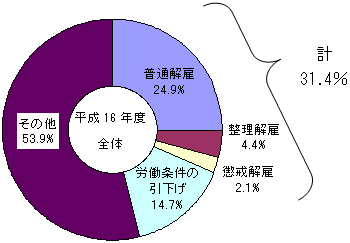
| ・ | 解雇に関するあっせん申請受理件数 |
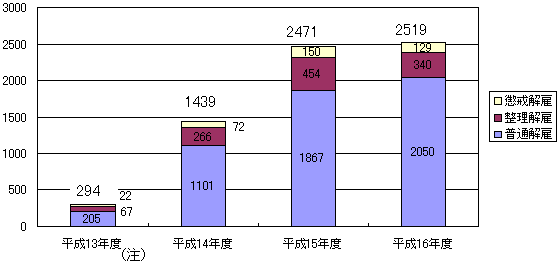 (注)「平成13年度」は平成13年10月から平成14年3月までの数値である。 |
| ・ | あっせん申請内容全体のうち、解雇に関するものの割合 |
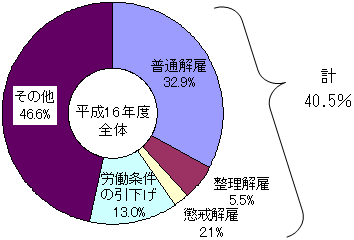
| 12 | 解雇に関する紛争の事例としては、例えば、次のようなものがある。 |
| 【 | 普通解雇に関して解雇回避措置が問題となった例】 顧客からのクレームを理由に解雇通告を受けた労働者が、解雇撤回か配置転換(担当顧客換え)を求めたところ、会社側は、配置転換をする慣習がないため解雇せざるを得ないとしたため、労働者は納得がいかないとして復職(解雇の撤回)又は補償金の支払いを求めたもの。 会社側は、配置転換に関する規定はあるが、配置転換を行った事例はなく、同じ職種の他の労働者はそれぞれの顧客と良好な関係を築いているため、配置転換はできないと主張した。 |
| 【 | 普通解雇に関して事前の警告がなかったことが紛争の背景にある例】 理容師である労働者が採用された直後に、技術が思わしくないとして教育担当者のいる支店に異動を指示された。この労働者は配置転換に応じて同支店において勤務していたところ、異動から約1週間後に、顧客からのクレームを理由として即日解雇された。 労働者は、解雇までに顧客のクレームについて会社側から注意を受けたことはなく、突然の解雇であって解雇理由に納得できないとして、当面の生活保障としての補償金の支払いを求めたもの。 会社側は、労働者の技術レベルが同社での要求水準に達していないことから解雇したと主張した。 |
| 【 | 普通解雇に関して勤務状況改善のための話合いが行われていたが紛争となった例】 労働者が、勤務成績不良を理由として解雇されたが納得がいかないとして、復職(解雇の撤回)又は精神的・経済的損害に対する補償を求めたもの。 会社側は、当該労働者は管理職として採用されたものであって、管理職として期待される勤務ぶりではなく、仕事の改善に向けて話合いを続けてきたが効果がなかったと主張した。 |
| 【 | 整理解雇に関して人選が問題となった例】 会社が新たな機械を導入した後に解雇され、解雇理由について説明を求めたところ「ただのリストラ」との回答であった。 労働者は、新機械の導入によって直接不要となる人員は外注先の人員であって、会社の真意は副業のため週1回定時退社している自分を狙った解雇であると考えられ納得がいかないとして、復職は求めないが、経済的・精神的損害に対する補償金の支払いを求めるとしたもの。 |
| 【 | 整理解雇に関して解雇回避措置がなかったことが紛争の背景にある例】 |
| 【 | 整理解雇に関して労働者への事前説明がなかったことが紛争の背景にある例】 事業場の閉鎖を理由に解雇された労働者が、同部門の他の労働者は別の部門に異動したにもかかわらず、自分だけが何の説明もなく一方的に解雇となったことには納得がいかないとして、復職は求めないが、精神的・経済的損害に対する補償金を求めるとしたもの。 会社側は、当該労働者は日ごろ腰痛を訴えており、本人が以前から希望していた部署はより腰に負担をかける業務であるので、異動は無理と判断して解雇せざるを得なかったと主張した。 |
| 【 | 裁判例:使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になるとの判断が示された例】 会社側と労働組合との間にはユニオン・ショップ協定が結ばれており、会社は、この協定に基づき労働組合から除名された労働者を解雇した。そこで、労働者は雇用関係の存在確認の請求を行ったもの。 判決では、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である」とされ、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇は、労働組合からの除名が無効な場合には解雇権の濫用として無効となるとされた。(日本食塩製造事件 昭和50年最高裁判決) |
| 【 | 裁判例:放送事故を理由とする普通解雇が解雇権の濫用に当たり無効とされた例】 放送会社のアナウンサーであった労働者が、担当する午前6時から10分間のラジオニュースについて、2週間に2回の寝過ごしによる放送事故を起こし、かつ、第二事故については当初上司に報告せず、後に事故報告書を求められて事実と異なる報告書を提出した。そこで、会社側は労働者を解雇した。これに対し、労働者は解雇権の濫用であるとして、従業員としての地位確認の請求を行ったもの。 判決は、労働者の行為は就業規則所定の普通解雇事由に該当するが、「普通解雇事由がある場合においても、使用者は常に解雇し得るものではなく、当該具体的な事情の下において、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効になる」とした上で、この労働者に対し「解雇をもって臨むことは、いささか苛酷に過ぎ、合理性を欠くうらみなしとせず、必ずしも社会的に相当なものとして是認することはできないと考えられる余地がある」として、解雇の意思表示を解雇権の濫用として無効とした原審の判断を是認した。(高知放送事件 昭和52年最高裁判決) |
| 【 | 裁判例:整理解雇の効力についての判断が示された例】 酸素・窒素等の製造販売を営む会社が、赤字の原因となったアセチレン部門の閉鎖を決定し、同部門の従業員全員について就業規則にいう「やむを得ない事業の都合によるとき」を理由として解雇する旨通告した。その際、他部門への配転や希望退職募集措置などは採られなかった。そこで、労働者は、自らが雇用契約上の地位にあることを主張したもの。 判決では、「特定の事業部門の閉鎖に伴い同事業部門に勤務する従業員を解雇するについて、それが就業規則にいう「やむを得ない事業の都合による」ものと言い得るためには、(1)同事業部門を閉鎖することが企業の合理的運営上やむを得ない必要に基づくものと認められる場合であること、(2)同事業部門に勤務する従業員を同一又は遠隔でない他の事業場における他の事業部門の同一又は類似職種に充当する余地がない場合、あるいは同配置転換を行ってもなお全企業的にみて剰員の発生が避けられない場合であって、解雇が特定事業部門の閉鎖を理由に使用者の恣意によってなされるものでないこと、(3)具体的な解雇対象者の選定が客観的、合理的な基準に基づくものであること、以上の三個の要件を充足することを要」するとされ、また、労働者側への説明・協議について、「解雇につき労働協約又は就業規則上いわゆる人事同意約款又は協議約款が存在するにもかかわらず労働組合の同意を得ず又はこれと協議を尽くさなかったとき、あるいは解雇がその手続上信義則に反し、解雇権の濫用にわたると認められるとき等においては、いずれも解雇の効力が否定されるべきであるけれども、これらは、解雇の効力の発生を妨げる事由であって、その事由の有無は、就業規則所定の解雇事由の存在が肯定された上で検討されるべきものであり、解雇事由の有無の判断に当たり考慮すべき要素とはならない」とされた。(東洋酸素事件 昭和54年東京高裁判決) |
| 13 | ここ5年間において個別に正規従業員の希望退職の募集その他の退職勧奨をしたことがある企業は、全体の14.8%であり、企業規模1000人以上の企業においては29.8%である。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
| ・ | ここ5年間での希望退職の募集その他の退職勧奨の実施状況(単位:%) |
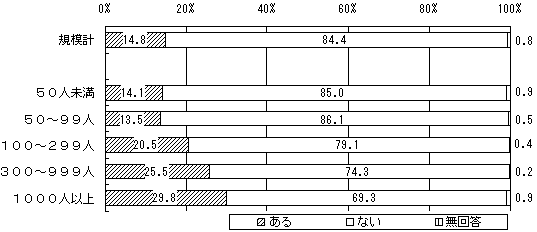
| 14 | 退職勧奨の際の手続については、特に労働者側と協議はしなかったとする企業が55.5%である。一方、労働組合がある企業においては、72.7%の企業で退職勧奨の際に労働組合との協議が行われている。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
| ・ | 退職勧奨の際の手続(単位:%)(ここ5年間に退職勧奨をした企業を対象に集計) |
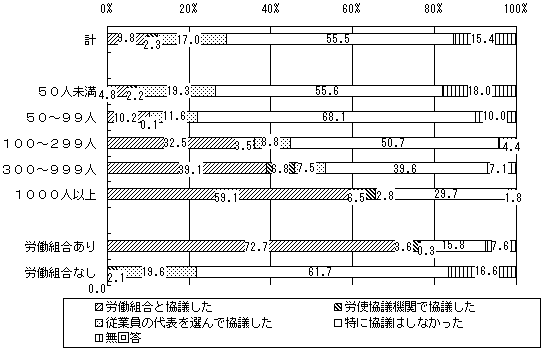
| 15 | 退職勧奨に当たっての退職者に対する特別な措置については、退職金の割り増しを行った企業が38.4%、再就職先のあっせんを行った企業が22.4%、退職前の特別休暇の付与を行った企業が13.8%となっている。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
| ・ | 退職勧奨に当たっての退職者に対する特別な措置(単位:%)(ここ5年間に退職勧奨をした企業を対象に集計) |
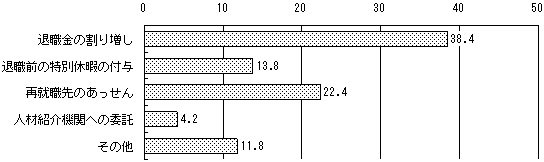
| 16 | ここ5年間に退職勧奨を行ったことがある企業のうち、これに労働者が応じなかったことがある企業は20.0%であった。 この場合の対応としては、応じた人数だけ退職させたとする企業が39.7%、労働者が応じるまでさらに説得したとする企業が30.4%、指名解雇に切り替えたとする企業が23.1%であった。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
| ・ | 退職勧奨に労働者が応じなかったことの有無(単位:%)(ここ5年間に退職勧奨をした企業を対象に集計) |
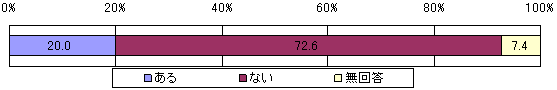
| ・ | 退職勧奨に労働者が応じなかった場合の対処方法(単位:%)(ここ5年間に退職勧奨をし、労働者がこれに応じなかったことがある企業を対象に集計) |
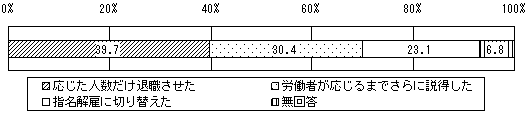
| 17 | ここ5年間に退職勧奨を行ったことがある企業のうち、退職勧奨をめぐって従業員との間で紛争が起こったことがあった企業は8.7%、なかった企業は88.6%であった。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年) |
| ・ | ここ5年間で退職勧奨をめぐり発生した個別労働関係紛争の有無(単位:%)(ここ5年間に退職勧奨をした企業を対象に集計) |
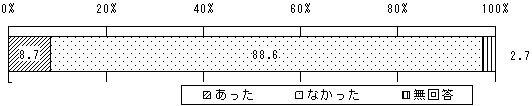
| ・ | 退職した従業員との間の紛争の解決方法(複数回答 単位:%)(ここ5年間に退職勧奨をしたことがあり、退職勧奨をめぐって紛争があった企業を対象に集計) |
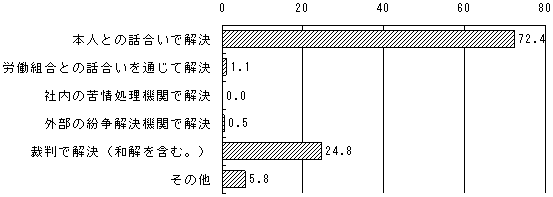
| 18 | 早期退職優遇制度がある企業は、全体の5.4%である。その場合の退職金の加算割合は、大学卒40歳の労働者について128.1%、同じく55歳の労働者について51.6%となっている。 また、過去1年間に希望退職の募集をした企業の割合は、40歳の労働者について41.5%、その場合の退職金の加算割合は145.9%である。(厚生労働省「就労条件総合調査」(平成15年)) |
| ・ | 早期退職優遇制度の有無(単位:%)(労働者30人以上規模の企業で退職給付制度がある企業(全体の86.7%)を対象に調査)
|
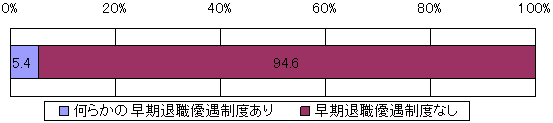
| ・ | 早期退職優遇制度がある企業の割合と、その場合のモデル退職金の加算割合(単位:%)(労働者30人以上規模の企業で退職給付制度がある企業(全体の86.7%)を対象に調査) |
| 大学卒 | 高校卒 | |||||||
| 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | |
| 早期退職優遇制度 がある企業 |
1.2 | 2.2 | 4.0 | 5.0 | 1.2 | 2.0 | 3.7 | 4.8 |
| 加算割合 | 128.1 | 102.4 | 70.3 | 51.6 | 107.9 | 88.6 | 62.9 | 50.8 |
| ・ | 過去1年間に希望退職の募集をした企業の割合と、その場合のモデル退職金の加算割合(単位:%)(早期退職優遇制度がある企業を対象に調査)
|
| 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | |
| 希望退職の募集をした企業 | 41.5 | 38.5 | 21.0 | 26.6 |
| 加算割合 | 145.9 | 111.7 | 139.2 | 77.8 |
| 19 | 従業員が自己都合退職する場合の手続を定めている企業は、全体の68.5%、従業員1000人以上の企業では97.8%である。手続を定める形式としては、就業規則が96.8%である。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
| ・ | 従業員が自己都合退職する場合の手続の定め(単位:%) |
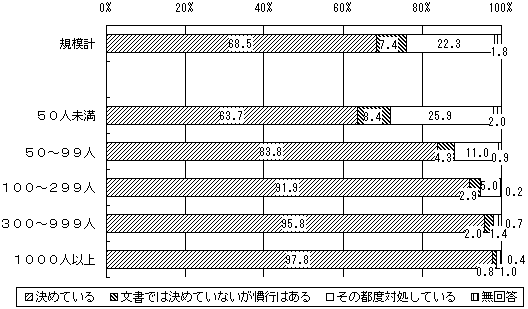
| ・ | 従業員が自己都合退職する場合の手続の定めの形式(複数回答 単位:%)(従業員が自己都合退職する場合の手続を決めている企業を対象に集計) |
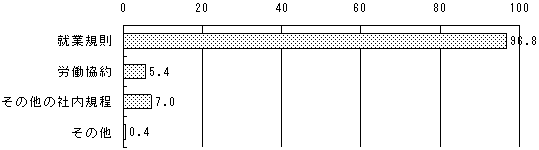
| 20 | 従業員が自己都合により退職する場合の事前の申し出時期については、1か月より前とする企業が33.8%と最も多く、次いで、2週間程度前とする企業が30.0%、1か月程度前とする企業が28.3%となっている。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
| ・ | 自己都合退職の事前の申出時期(単位:%)(従業員が自己都合退職する場合の手続を決めている企業又は文書では決めていないが慣行はある企業を対象に集計) |
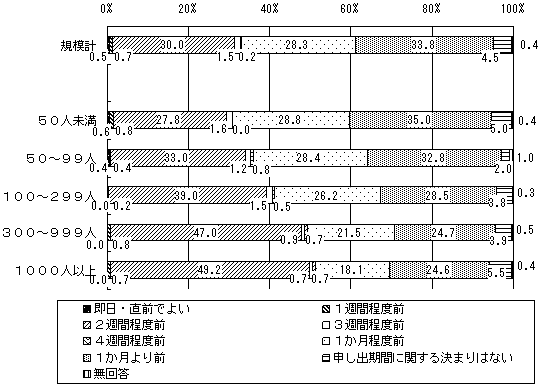
| 21 | 従業員が自己都合退職を申し出た後に取消の意思表示をした場合の取り扱いについては、ケース・バイ・ケースで対応しているとする企業が63.8%であった。そのほか、社内手続の完了前であれば取り消しに応じることもある企業が10.6%、退職の日の前であれば取り消しに応じることもある企業が8.6%、原則として当初の申出どおり退職してもらうとする企業が8.1%であった。(労働政策研究・研修機構「従業員関係の枠組みと採用・退職に関する実態調査」(平成16年)) |
| ・ | 自己都合退職の取消の申出の取扱い(単位:%)(従業員が自己都合退職する場合の手続を決めている企業又は文書では決めていないが慣行はある企業を対象に集計) |
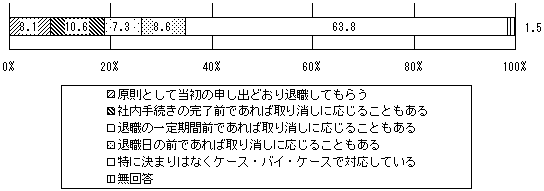
| 22 | 退職勧奨、自己都合退職に関する民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導申出受付件数、あっせん申請受理件数は増加傾向にあり、平成16年度における退職勧奨に関する相談件数は12,614件、自己都合退職に関する相談件数は9,378件に上る。(厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室調べ) |
| ・ | 退職勧奨、自己都合退職に関する民事上の個別労働紛争相談件数(単位:件) |
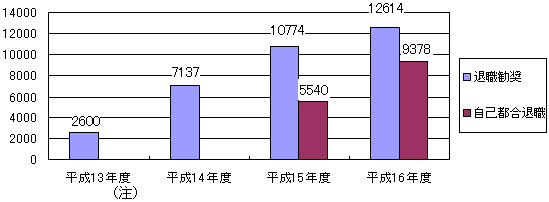
| ・ | 退職勧奨、自己都合退職に関する助言・指導申出受付件数(単位:件) |
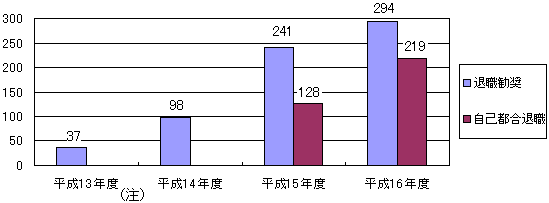
| ・ | 退職勧奨、自己都合退職に関するあっせん申請受理件数(単位:件) |
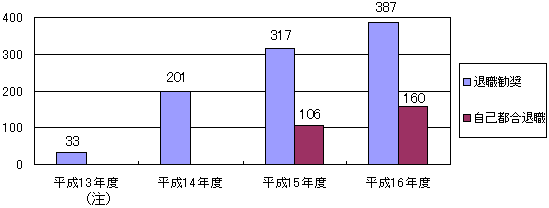 (注)「平成13年度」は平成13年10月から同14年3月までの数値である。 ※「自己都合退職」については、平成15年度から集計対象項目となった。 |
| 23 | 退職に関する紛争の事例としては、例えば、次のようなものがある。 |
| 【 | 退職に関する事例】 労働者が、退職を申し出るメールを社長に送ったが、専務等から慰留を受けこれを撤回しその旨を再度社長にメールした。社長及び専務からは退職意思撤回を聞いた旨の連絡があり、労働者としては今後も業務を継続する意思であった。 ところが、その約4か月後である決算終了時に、他の取締役より「退職を希望する旨のメールを辞表として受理したので翌月をもって退職とする」とされ、退職希望は撤回した旨を言ってもメールは法的に通用するとして聞き入れられなかったとして、精神的損害に対する補償金を求めたもの。 会社側は、労働者が退職を決算業務終了まで延期したものと受け止めたと主張した。 |
| 【 | 退職に関する事例】 1年契約、勤続3年目の有期契約労働者が、同僚社員が仕事をしていないことについて社内監査室と同僚本人に匿名の指摘メールを送信したことを理由に、「本来であれば解雇であるが、一身上の都合により退職するよう」通告され、退職する意思はなかったが選択の余地がなく退職届を提出せざるを得なかったとして、残契約期間の賃金相当額を求めたもの。 会社側はあくまで自己都合退職であると主張した。 |