| 資料2 |
過疎地の医療圏における医師会を中心とした救急医療体制
古川市立病院 救命救急センター
大庭正敏
古川市立病院 救命救急センター
大庭正敏
古川市について
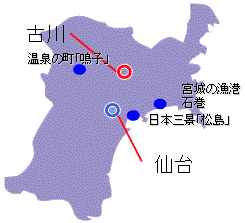 |
|
宮城県の二次医療圏
人口:2,369,489人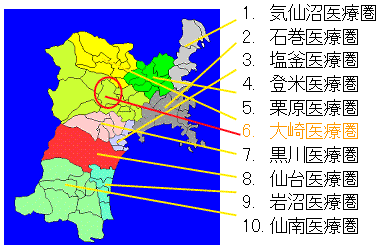 |
宮城県の人口
2,365320人
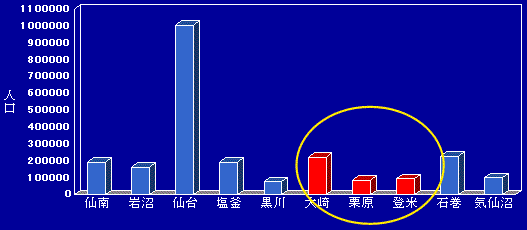
2,365320人
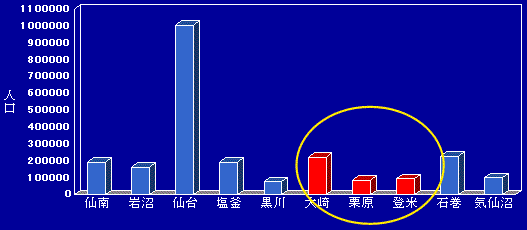
宮城県県北の二次医療圏
推計人口402,239人
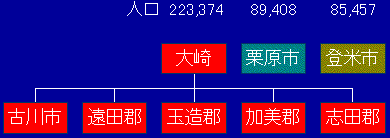
推計人口402,239人
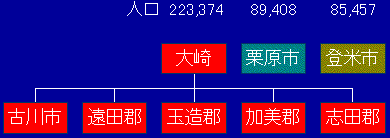
二次医療圏の面積と人口密度
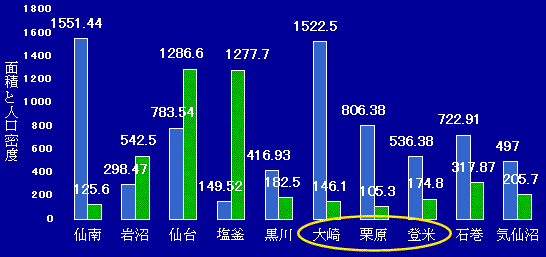
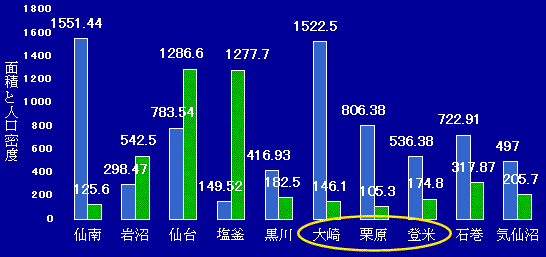
宮城県の医師数人口10万対比較
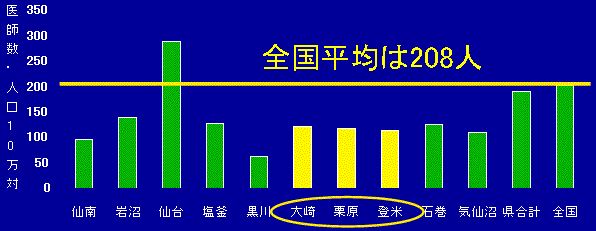
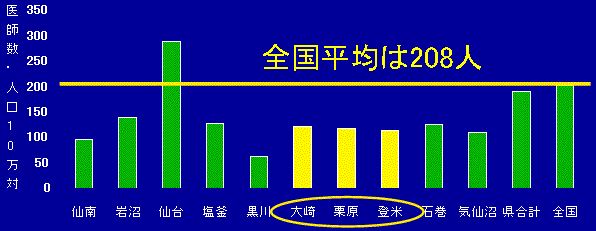
宮城県県北の医療圏
推計人口402,239人
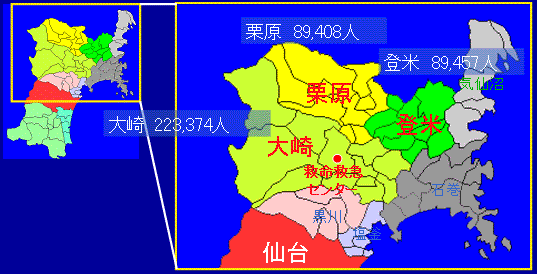
推計人口402,239人
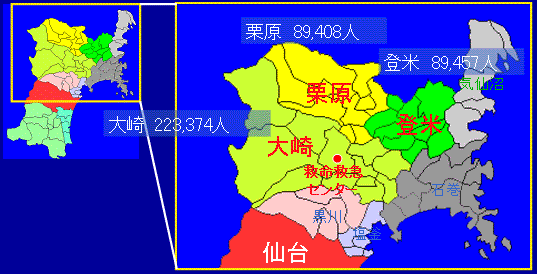
医療体制の背景
| ・ | 10年前までは、脳外科、麻酔科、循環器科などの常勤医が居ない時期が長く続いていた。 |
| ・ | 救急医療に対する医師会の関与が大きい。(開業医の救急医療に対する関心が高い) |
| ・ | 地域の医療施設に対する住民のニーズが高い。 |
| ・ | 平成6年、住民運動により(人口100万人対1箇所)制限外の救命救急センターが開設された。 |
病院と救急隊の位置関係
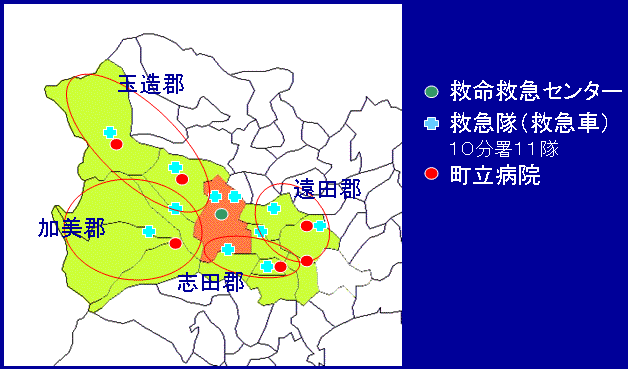
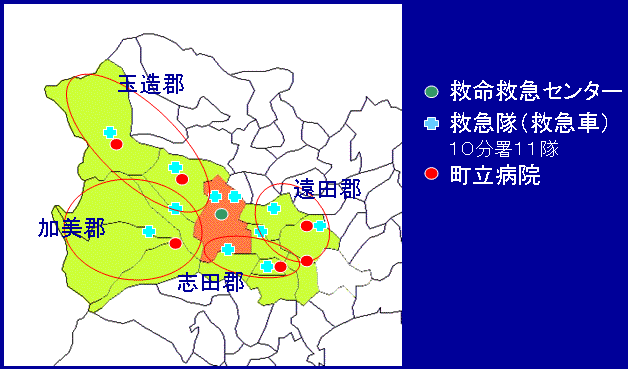
心肺停止患者搬送に要する時間
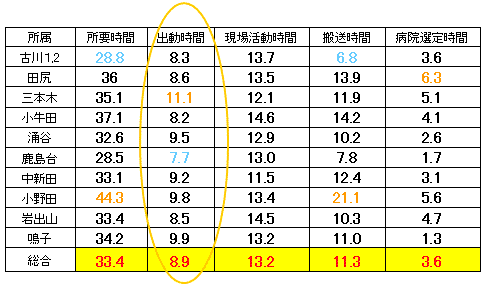
出動時間の全国平均は6.4分!
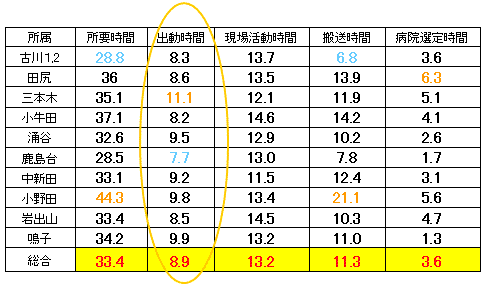
出動時間の全国平均は6.4分!

古川市立病院施設

| 本院・南病棟・救命救急センター・放射線棟のほか、研修棟・保育施設もあり。 |

病院の機能
| 当院は、宮城県大崎医療圏(人口約22万人)の基幹病院として、総合医療を行う中核病院です。 |
主な指定関係
|
 |
病床数
458床(平成17年4月1日現在)

|
診療科、医師数、指導医数、病床数(科ごと)、全科合わせての一日の外来・入院患者数
| 診療科名 | 内科 | 消化器科 | 循環器科 | 外科 | 小児科 | 脳神経外科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | 産婦人科 | 整形外科 | 麻酔科 | 歯科口腔外科 | 泌尿器科 | 皮膚科 | 形成外科 | 精神科 | 放射線科 | リ ハ ビ リ テ | シ ョ ン 科 |
結核 | 感染 | 救急 ・ 他 |
計 |
| 医師数 | 16 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | |||
| 内指導医数 | 16 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 59 | |||
| 認定医・専門医数 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | |||||||
| 病床数 | 74 | 38 | 39 | 58 | 17 | 25 | 8 | 12 | 24 | 41 | 1 | 21 | 3 | 4 | 1 | 8 | 24 | 6 | 54 | 458 | ||
| 一日平均入院患者数 (全科合せて) |
(平成16年3月〜平成17年3月)411.8人 | |||||||||||||||||||||
| 一日平均外来患者数 (全科合せて) |
( 〃 )1035.4人 | |||||||||||||||||||||
| 平均在院日数 (全科合せて) |
( 〃 )14.1日 | |||||||||||||||||||||
| 一日平均救急外来 患者数 |
( 〃 )22.4人 | |||||||||||||||||||||
| 一日平均救急車搬送 患者数 |
( 〃 )8.3人 | |||||||||||||||||||||
医師数・患者数
| ・ | 常勤医師数:60名 |
| ・ | 専門医数:40名 |
| ・ | 研修医数:32名 |
| ・ | 病床総数:458床 |
| ・ | 平均在院日数:14.1日 |
| ・ | 一日平均入院患者数:411.8人 |
| ・ | 一日平均外来患者数:1035.4人 |
| ・ | 救急外来受診数:22.4人 |
| ・ | 救急車搬入患者数:8.3人 |
古川市立病院の概要
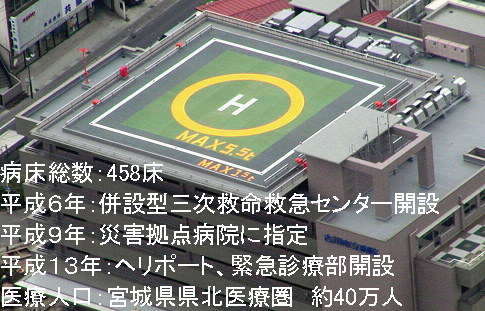
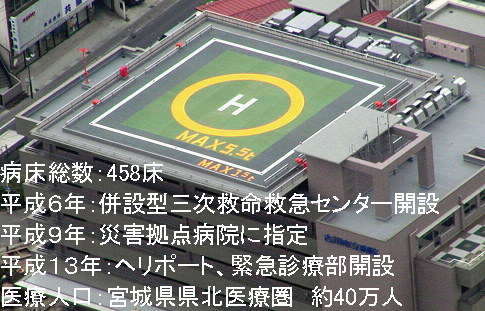
研修医数 32名
|
研修医の出身大学 東北大学・岩手医科大学・ 弘前大学・秋田大学・東京大学 北里大学・藤田保健衛生大学 愛媛大学・信州大学・ 金沢医科大学 |
医療圏の特徴と救急医療体制
| ・ | 面積が広く、人口密度の低い過疎地域である。 |
| ・ | 救急隊による搬送時間が長い。 |
| ・ | 救急医療に対する地域医師会の関与が大きい。 |
| ・ | 救命救急センターの負担を軽減する目的での、古川市医師会による、平日夜間輪番制導入。医療資源が有効に活用されている。 |
| ・ | コミュニティケアレベルの初期救急から最終受入機関としての救命救急センターまで、救急医療に関する役割分担が明確。 |
地域の機能としての救急医療
| ・ | 医療資源を有効に使う
|
古川市(大崎地域)の救急医療体制
・平日夜間(土曜午後)
輪番病院10施設
・休日救急診療担当
(第一次診療機関41施設)
・休日夜間救急診療担当
(第二次診療機関8施設)
・平日夜間(土曜午後)
輪番病院10施設
・休日救急診療担当
(第一次診療機関41施設)
・休日夜間救急診療担当
(第二次診療機関8施設)
“三本柱”の救急医療体制
|
大崎地域の救急診療体制
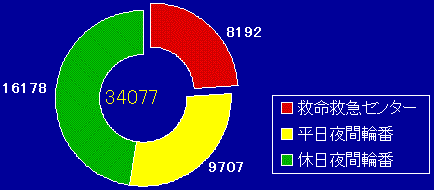
平成16年度
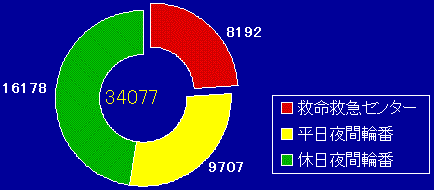
平成16年度
救急医療体制の基本的条件
| (1) | 住民にも救急隊にもわかりやすく、利用しやすい救急医療体制
|
|||
| (2) | 地域単位での救急医療体制の確保
|
|||
| (3) | 地域性の尊重
|
総利用患者数の推移
古川市立病院救命救急センター(平成10〜16年)
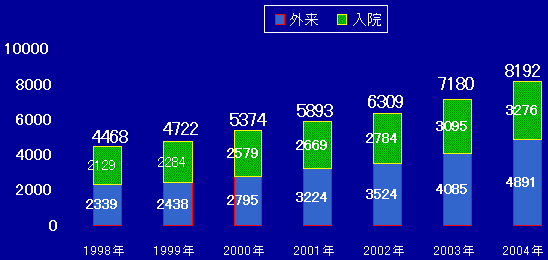
古川市立病院救命救急センター(平成10〜16年)
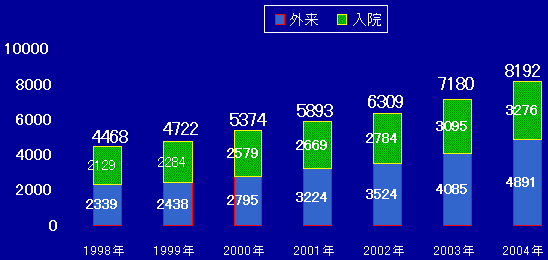
古川市立病院救命救急センター利用患者の動向
| 年度 | 利用患者 総数 |
センター入院 | 本院入院 | 外来帰宅 | CPA | 救急車 | 入院率 |
| 平成8年度 | 3402 | 1296 | 440 | 1608 | 110 | 1228 | 51.0% |
| 平成9年度 | 3916 | 1533 | 408 | 1875 | 126 | 1351 | 49.6% |
| 平成10年度 | 4569 | 1636 | 504 | 2429 | 113 | 1927 | 46.8% |
| 平成11年度 | 4723 | 1763 | 567 | 2393 | 105 | 1984 | 49.3% |
| 平成12年度 | 5700 | 1998 | 708 | 2994 | 144 | 2272 | 47.5% |
| 平成13年度 | 5861 | 1862 | 778 | 3221 | 112 | 2342 | 45.0% |
| 平成14年度 | 6590 | 1818 | 949 | 3595 | 128 | 2408 | 42.0% |
| 平成15年度 | 7180 | 1974 | 1121 | 3931 | 106 | 2480 | 43.1% |
| 平成16年度 | 8192 | 2149 | 1127 | 4739 | 122 | 3051 | 40.0% |
厚生省による救命救急センターの評価
| ・ | ランク付け:当センターはAランク
|
||||
| ・ | 救急医学会認定医訓練施設(認定医が2名以上) |
充実段階A評価
(下記内容をすべて満たす)
(下記内容をすべて満たす)
(平成13年度当院の実績) |
年齢別患者分布(外来)16年度
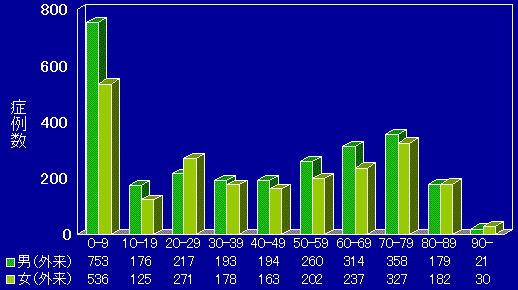
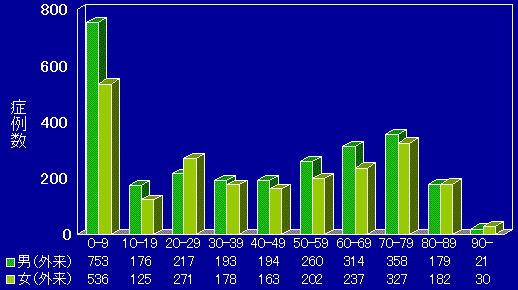
一次救急医療の特徴と問題点
| ・ | 多くは、緊急性の少ない時間外診療である |
| ・ | 救急医療の7〜8割は一次救急である |
| ・ | 一次救急の多くは小児である |
| ・ | 医療側にとっては日常茶飯事でも、親にとっては初めて経験する一大事 |
| ・ | 病院のコンビニ化(いつでも都合のよいときにかかりたい)に対する需要が高まっている。 |
| ・ | 電話相談で対応できることはないのか |
| ・ | 一次救急に隠れた、重篤な疾患を発見することが最も重要(脳卒中、心筋梗塞) |
年齢別患者分布(入院)16年度
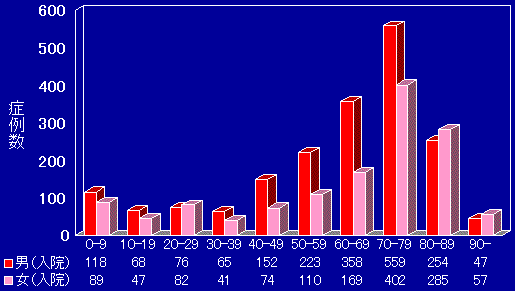
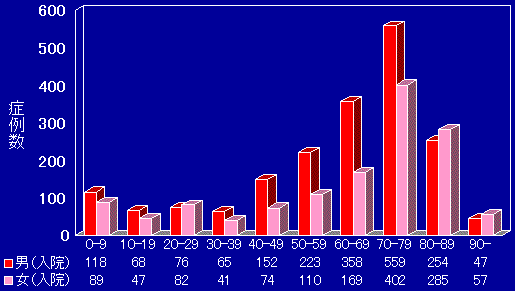
二・三次救急医療の特徴と問題点
| ・ | 病院前救護体制の充実が必要 |
| ・ | 後方病床として受け入れ病院は充足しているか?救急病床の確保は、後方病床が確保が必須条件 |
| ・ | 乳児・高齢者の入院が多い。 |
| ・ | 救急医がいない!救急医の育成は急務! |
| ・ | 着院時心肺停止のほとんどは急性心臓死 |
| ・ | 一次救急救命処置の標準化 |
| ・ | 過疎地では、救急隊と救命救急センターだけで救急医療はできない! |
救命救急センターの診療体制
| ・ | 平日:外科・内科の日直担当医が急患に対応、各専門科の医師に直接紹介もあり。 | ||
| ・ | 研修医1-2名をER専任として配備(平日日中のみ) | ||
| ・ | 夜間・休日:当直医(外科系、内科系常勤医各1名)土日の外科当直は月3回大学より応援。 | ||
| ・ | 専任:救命救急センター長、副センター長(4名)
|
||
| ・ | 兼任:各科医師全て | ||
| ・ | 内科のみレジデント1名をセンター(ICU)専従 |
寄り合い所帯の利点と欠点
利点
|
欠点
|
特殊な病態とは?
| ・ | 急性中毒→内科・外科・精神科で対応OK | ||
| ・ | 熱傷→外科・皮膚科で対応OK | ||
| ・ | 心筋梗塞→循環器科で対応OK | ||
| ・ | 脳卒中→脳神経外科・神経内科で対応OK | ||
| ・ | 心肺停止患者→対応困難
|
||
| ・ | 多発外傷患者→対応困難
|
小児救急について
| ・ | 当院の時間外救急外来患者の多くは小児である。 |
| ・ | 2歳以下が多い。それ以外は平日夜間輪番で対応。多くは当院の再来患者。 |
| ・ | 当院小児科は3名。 |
| ・ | 小児科の患者は、当直の内科医が診察、必要があれば小児科コンサルト。 |
| ・ | ほとんどは当直医で解決可能。常時小児科医が院内待機している必要はない。 |
| ・ | 現有スタッフで解決可能なシステムの構築が必要。 |
救急の標準的初期診療について
| ・ | PTEC(病院前救護) |
| ・ | ACLS(心肺蘇生) |
| ・ | JATEC(避け得た外傷死亡をなくすため) |
| ・ | PALS(小児の救急蘇生) |
| ・ | いずれも米国のオリジナルだが非常によくできたプログラムである。 |
| ・ | 国内で現在急速に普及しつつあり、講習会が常に定員オーバーとなっている。 |
| ・ | 救命士・看護師が非常に熱心である。 |
医師の不足に対する対策
| ・ | 医療資源を有効に使う
|
地域の機能としての救急医療
| ● | 地元開業医:古川ACLS講習会を受講しAEDを購入。 |
| ● | 52才女性が倒れたという往診依頼あり。AEDを持って駆けつけ、往診先でAEDを使用しCPRを行った。 |
| ● | 救急隊到着前に患者は心拍再開し、救命救急センターで治療。冠動脈攣縮、日常生活に復帰。 |
| ● | 地域医師の意欲、ACLS講習が功を奏した貴重な事例。 |
| ● | 開業医は無関心・消極的ではない。意欲のある医師は多い。正しい情報と適切な研修の場を提供すべき。 |
| ● | 救命士が同乗していないためVFを確認しても除細動できない救急隊も多い。全ての緊急車両にAEDを搭載。 |
| ● | 地域の開業医がAEDのの操作に習熟し、日常診療で心肺蘇生を実施できることが到達目標。 |
救急救命士就業前研修
| ・ | 救命救急士資格取得者を終業前に3ヶ月間(480時間)病院内研修させる |
| ・ | 研修場所は、救急外来、手術室、救急病棟(ICU、CCU、HCU)、一般外来、一般病棟(外科、内科、整形外科、脳外科、小児科)、分娩室、最後に救急外来の当直。 |
| ・ | 救命救急センターの稼働状況と、適応患者を理解する。 |
| ・ | 災害時、救命救急センターへの一極集中回避に有効であった。 |
救急救命士教育受け入れ
| ・ | 大崎地域
|
||||||
| ・ | 栗原郡
| ||||||
| ・ | 登米郡
|
||||||
| ・ | 気管挿管実習
|
まとめ
| ・ | 救命救急センターと救急隊のみで救急医療を完結することは、面積が広く医師の充足していない過疎地域では現実的ではない。 |
| ・ | 大崎医療圏の救急医療体制は医師会の関与が大きく、救命救急センターとの間で医療資源を有効に利用した効率の良い協力体制が確立している。 |
| ・ | 救急医療は地域の機能として存在すべきであり、その管理運営は地域としての責務でもある。 |
| ・ | 研修医の救急医療に対する興味と意欲は高い。救急医療は若手医師獲得の有効な手段となりうる。 |