| 資料1 |
医療計画制度と都道府県の権限について
医療計画制度と都道府県の権限に関する意見
医療計画制度と都道府県の権限に関する意見
|
| ○ | 平成17年9月9日 新しい医療計画の作成に向けた都道府県と国との懇談会
|
||||
| ○ | 平成17年10月24日 新しい医療計画の作成に向けた都道府県と国との懇談会
|
||||
| ○ | 平成17年10月27日 経済財政諮問会議
|
||||
| ○ | 平成17年11月1日 関東地方知事会
|
||||
| ○ | 平成17年11月17日 新しい医療計画の作成に向けた都道府県と国との懇談会
|
|
医療サービスの質の向上・効率化と医療計画制度の関係について
| ┌ │ │ │ │ │ │ │ └ |
|
┐ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
| 1. | 病床過剰地域では病院の新規参入が行われず、既存の病院の病床が既得権化。 |
| → | 病床過剰地域では病院の新規参入がないことから、医療サービスの質の競争が起こりにくい状況。 |
| 2. | 病床過剰地域では増床ができず、地域の医療ニーズに的確に対応することが不可能。 |
| → | 病床過剰地域では増床が簡単には認められないことから、質の高い医療サービスを提供している病院が地域の医療ニーズに的確に対応するための円滑な事業展開が阻害されている状況。 |
| 3. | 既存の公立病院の病床の既得権化に伴い、医療資源が官から民へ円滑に移行できないこと。 |
| → | 特に公立病院の病床が固定化してしまい、小児科・産科医療の集約化・重点化など医療資源の再構築が行われず、結果として官から民への円滑な移行が阻害されている状況。 |
|
医療サービスの質の向上と効率化に向けた医療計画制度の弾力的運用方策(案)
|
| → | 地域での医療ニーズと医療サービスの供給状況のギャップを踏まえ、都道府県で検討された今後の医療サービスの提供体制の再構築プランを支援するもの。 |
|
| → | 病床の利用状況を加味した医療計画制度と病床許可制度の見直しを通じて、地域で必要な医療を担う提供主体を官から民へ加速するもの。 |
|
| → | 小児科医療・産科医療などを提供する医療機関の人員配置状況を把握し、情報開示することを通じて、地域の医療サービスの質の向上に向けた医療機能の集約化・重点化を行うもの。 |
| (方策1) | 地域で必要な医療を確保するための医療計画制度の弾力的運用(具体案) |
| 小児救急医療や周産期医療など地域で必要な医療を確保するため、都道府県医療審議会において今後の医療提供体制に関する再構築の方策を議論した結果、地域の既存病床数を全体として「減らす」場合は、当該医療の実施を条件として、病床過剰地域においても、都道府県知事において病院の増床又は新規参入を認めることを可能とする弾力化措置を検討。 |
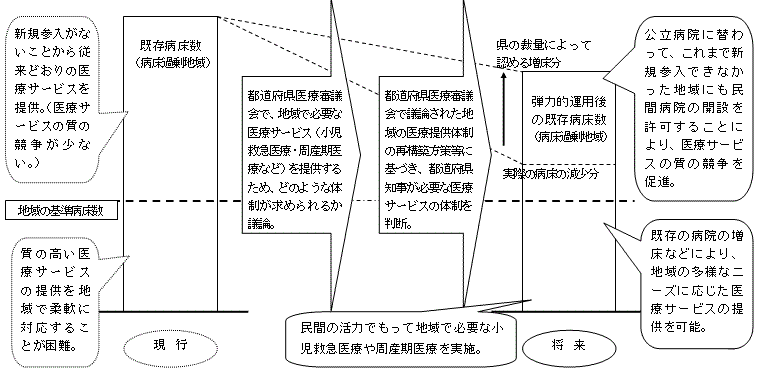
| (方策2) | 地域で必要な医療を支援するための公立病院の病床の有効活用措置(具体案) |
|
(具体案のイメージ)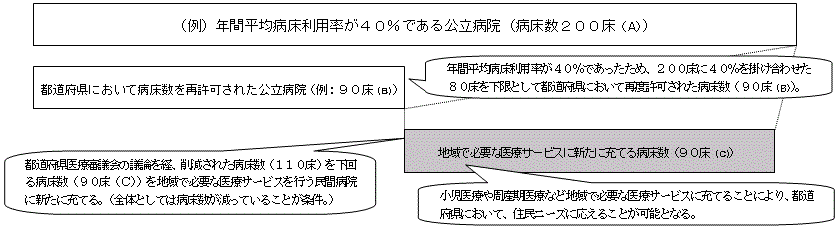
|
| 病床の有効活用に向けた新たな措置に関する留意点 |
| ○ | 地域で必要な医療を担う提供主体を官から民へ加速するため、今般の新たな措置の対象としては、公立病院を念頭に置いている。
|
||||||
| ○ | 一方で、病床の利用状況に応じた基準病床数制度の運用を行う場合、各病院において「不必要な入院を助長させる」という問題が生じる可能性がある。 |
||||||
| ○ | このため、「不必要な入院を助長させる」問題に対しては、次の対応を図ることとする。
|
| (方策3) | 医療機関の人員配置状況の情報開示と医療機能の集約化・重点化について(具体案) |
|
医療サービスの質の向上と効率化に向けた新たな都道府県の権限(創設)について
|
【新たな都道府県の権限(考え方)】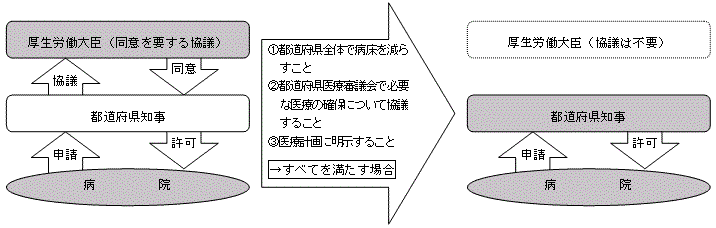 |
| ※ | 許可後、知事は利用状況についての継続的なフォローアップを行うものとする。 |