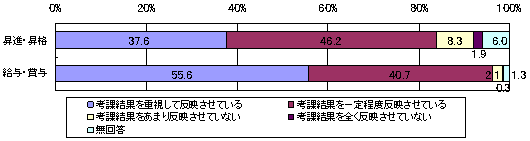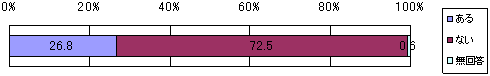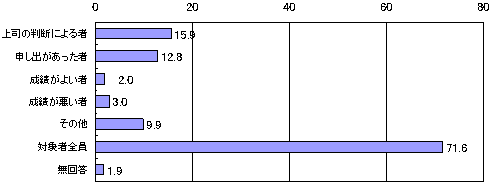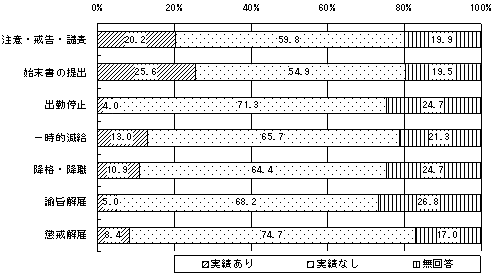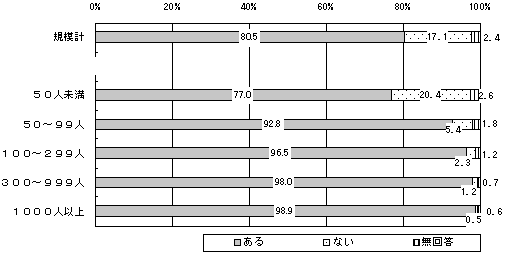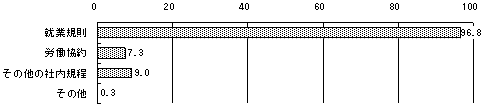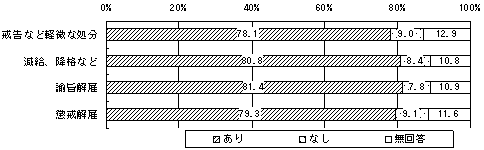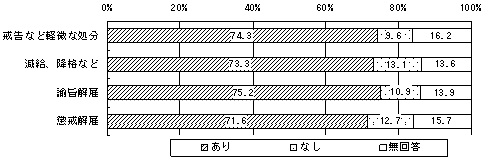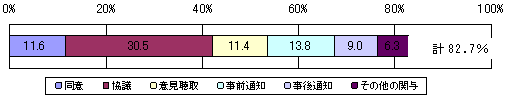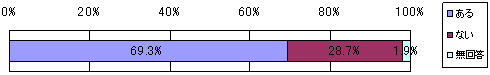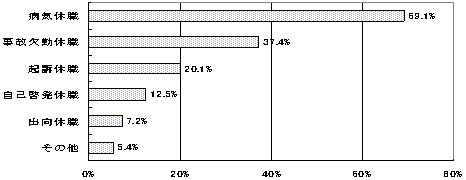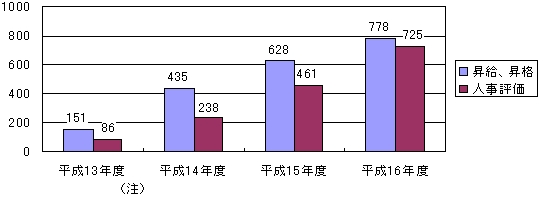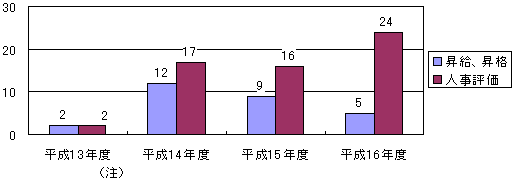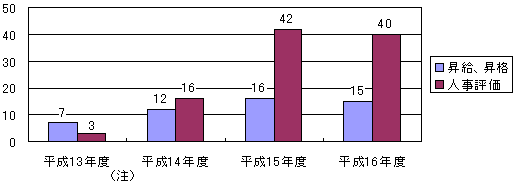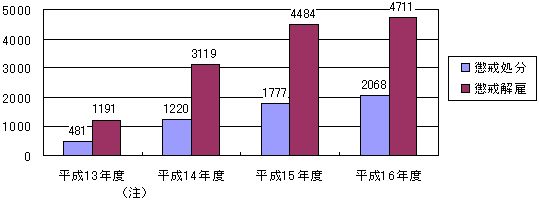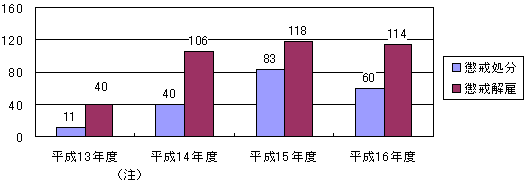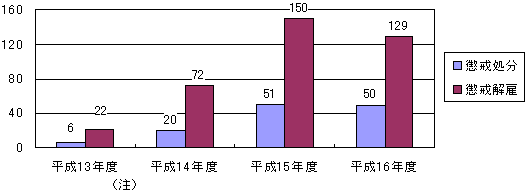| 【 | 労働者が公正な人事評価を求めた例】 |
| 【 | 労働者が人事評価結果の説明を求めた例】
事前の説明なく経営不振及び業績評価を理由に給与及び賞与が減額されたとして、労働者が、減額分の支払い、正当な業績評価及び評価の具体的内容の説明を求めたもの。
会社側は、給与及び賞与の減額は、業績評価の結果と、前年度の業績不振による一律1〜2割カットによるものであり、2割カット分は既に元に戻していると主張した。
|
| 【 | 降格の根拠が問題となった例】
中途採用で入社した労働者について、個別の契約書において、入社時の役職は営業副統括者、職務等級X−2として月給約40万円、二年度目以降は月給・賞与とも業績評価の対象とするとされていた(就業規則の降格規定の有無は不明)。
ところが、入社から5か月後に、業績が上がらなかったことを理由に統括付きへ降格され、職務等級もX−2からX−1へ降格、月給は約40万円から約30万円へ減額と通知された。
労働者は、業績評価はあくまで二年度目以降からの約束であった、また、当初の契約以上に兼務を課せられたため、5か月では業績を上げるために十分な時間がなかったとして、賃金の減額分の差額の支払いを求めた。
会社側は、労働者が降格に合意していたと主張した。
|
| 【 | 降格・降給の手続が問題となった例】
年俸950万円の課長職として採用された労働者が、入社5か月後に部長職を兼ねることになり、年俸1000万円とする旨の昇給辞令を受けた。しかし、1か月後に部長職の兼務を解き、課長職に専念するよう口頭で通知された。その際、降給の辞令は交付されなかった。
夏季賞与については、年俸950万を基準に計算した額が労働者に対して支払われた。これに対して、労働者は、年俸を1000万円から950万円に引き下げることは聞いていない、部長職の兼務を解かれたときも、年俸が下がるものとは理解していなかったとして、差額を請求したもの。
会社側は、部長職の兼務を解くことに労働者が同意した際に、年俸も元に戻ることについても当然了解されたものと考えたと主張した。
|
| 【 | 懲戒の正当性が問題となった例】
労働者が、同僚に対して交友関係に関する中傷をしたとして、これを理由とする懲戒処分通知書が交付され、降格がなされたが、この懲戒処分が不当であるとして、降格に伴って減額された賃金の補償を求めたもの。
会社側は、中傷について労働者は始末書も提出しており、事実であって懲戒は正当であると主張したが、労働者は、確かに始末書は提出したが、定年を控えてトラブルを起こしたくなかったからであり、始末書の提出自体も不本意であったと主張した。
|
| 【 | 懲戒が均衡を欠くかどうか問題となった例】 |
| 【 | 懲戒理由の明示がなかった例】
タクシー運転手である労働者が、タクシー同士の追突事故を起こした。労働者はその後も乗務を続けていたが、一週間後に約20日間の自宅待機を命ぜられた。労働者は入社して10年になり、いままで小さな事故を起こしたことはあるが、自宅待機を命じられたのは初めてである。
労働者は、自宅待機を命じられた際に十分な理由の説明がないこと、通常、待機期間は親睦会の代表が窓口になって会社と話し合い1週間から10日間くらいとなるのが普通であるのに、そのような手続も踏まれず、長すぎると感じることから、納得がいかないとして、休業による経済的・精神的損害に対する補償金の支払いを求めたもの。
会社側は、労働者に追突事故について注意したところ、反省の色が見られず、安全運転が危ぶまれることからやむなく自宅待機を命じたと主張した。
|
| 【 | 懲戒に際して弁明の機会付与の手続が問題となった例】
前社長の死亡後、不正な経理が判明したことからこれを理由に経理担当の労働者が懲戒解雇されたことについて、労働者が、自分は社長の指示に従って職務を行っていたに過ぎないとして、懲戒解雇の撤回を求めたもの。
会社側は、本人から事情を聴取して労働者が他の役員に報告すべき義務を怠っていたと判断し、懲戒解雇理由を説明した際に「わかりました」との回答があったことから、本人が懲戒に値する行為を行ったことを認めたとして懲戒解雇を通知したとする。
一方、労働者は、会社側三人に対して自分一人で説明を聞かされ、理由も分からないまま「わかりました」と言ってしまったと主張した。
|
| 【 | 裁判例:懲戒には、あらかじめ就業規則の規定が必要とされた例】
4月1日から新たな就業規則を実施することとした会社側は、6月2日に労働者代表の同意を得た上で、6月8日に所轄労働基準監督署長に届け出た。新旧の就業規則には懲戒解雇事由が定められており、所定事由があれば懲戒解雇することができる旨定めていた。
会社側は、同年6月15日、同社で設計業務に従事していた労働者が「得意先の担当者らの要望に十分応じず、トラブルを発生させたり、上司の指示に対して反抗的担度をとり、上司に暴言を吐くなどして職場の秩序を乱したりした」との理由で、新たな就業規則の懲戒解雇に関する規定を適用し、労働者を懲戒解雇処分に付した。労働者は、解雇の前に会社側の担当者に対して、就業規則について質問したが、その時点では旧就業規則が労働者の就労場所に備え付けられておらず、担当者は、就業規則は本社に置いてあるから見ることができると回答した。
労働者は、本件懲戒解雇は就業規則に違反して無効であると主張した。
判決では、「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とされ、「そして、就業規則が法的規範としての性質を有する(中略)ものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する」として、就業規則の周知の有無を認定しないまま懲戒解雇を有効とした原審の判断を破棄した。(フジ興産事件 平成15年最高裁判決)
|
| 【 | 休職後の復職先・復職の可能性が問題となった例】
私病により5か月間休職している労働者が、医師から「このままなら翌月より就労可能」と言われたため会社側にその旨連絡したところ、会社が「医師が就労可能と判断しても適切な職場がなければ復職させない」としたとして、就労可能の判断が出れば復職できることの確約を求めたもの。
同時期に会社側は希望退職の募集を行っていたことから、労働者は、会社側が、労働者を希望退職させるよう圧力をかけてきたものと考えた。
|
| 【 | 休職後の完全復職・慣らし勤務が問題となった例】
病気休職中の労働者が、復職可能との診断書を添えて復職を願い出たが認められず、上司に「仕事ができるはずがない」等といわれ復職できなくなったとして、精神的・経済的損害に対する補償を求めたもの。
会社側は、以前、半日勤務等の慣らし勤務について労働者と合意したが、労働者は半日出勤ができずに欠勤(休職)を続けていた状態であり、そのような段階で完全な復職が希望されたことから、勤務ができるかどうか判断できないため再度の慣らし勤務を提案したものであると主張した。 |