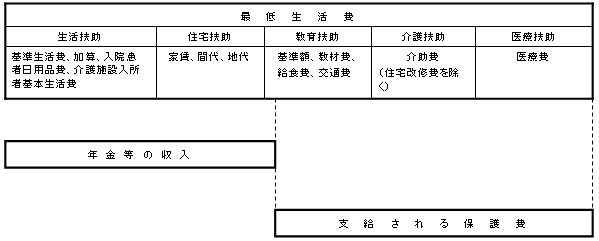今後の論点
平成17年11月18日
総務省
| 生活保護についての基本的考え方は前回提示したとおり。前回の議論を踏まえると、今後、次のような論点について、引き続き議論を深めることが必要。 |
| ○ |
生活保護事務は法定受託事務と位置付けられていることから、全国的な制度設計等における「国の責任」が重いもの。 |
| ○ |
地方自治体は、実施責任を的確に果たしている。 |
| ○ |
今回の提案により、厚労省は法定受託事務の位置づけを変更するのか。変更するとすれば、それは何故かを示すべき。 |
|
(厚労省の主張)
生活保護制度のみ「国の責任で行われるべきもの」とする主張は適当でない。
| ○ |
今回の提案では、国の負担を減らし、一方的に地方の責任・負担が増えるだけだが、国は状況の変化に対して、自らがどのような責任や負担を新たに担うのかを示すべき。 |
|
(厚労省の主張)
国と地方が重層的に役割や費用負担を担うべき。
| ○ |
「高齢者世帯や傷病・障害者世帯が8割を超えている現状においては、自立支援の効果は限定的である」という共通認識がある中で、厚労省の主張を具体的に達成するために、現場関係者も納得する給付の適正化が進む具体的な手法を示すべき。 |
|
(厚労省の主張)
自立助長が円滑に進められ、生活保護制度への過度の依存が回避されるような仕組みにすることが重要。
| ○ |
生活保護は、全国統一的に公平かつ平等に実施されるもの(無差別平等の原則)。 |
| ○ |
生活扶助または住宅扶助の設定権限を地方に移譲する際に、国はどこまで指針を示し、どこまで地方の裁量に委ねるのか。指針が具体的であれば、地方の裁量はない。地方に全て委ねるとすれば、最低生活の内容等に実質的な差が生じるおそれがあるが、それをどのように考えるのかを示すべき。 |
|
(厚労省の主張)
生活保護基準の設定権限を地方に移譲するという厚生労働省の提案は、より地域事情を反映した基準を設定することにより、適正かつ公平な基準とする観点に立ったもの。
| 1 |
生存にかかわるナショナルミニマムの確保は国の責任。 |
|
| 2 |
生活保護は、全国統一的に公平かつ平等に実施されるもの(無差別平等の原則)。 |
|
| 3 |
生活保護及び児童扶養手当の原則は金銭給付。地方の裁量の余地はない。 |
|
| 4 |
地方自治体における保護の実施体制や取組状況等は、保護の動向に影響を与えるものではない。 |
|
| 1 |
生活保護の負担率は、国の責務及びこれまでの経緯に鑑み、現行の水準を維持すべき。 |
|
| 2 |
地方団体ごとに、生活保護の水準に実質的な差が生じることは、国民の最低限度の生活を営むことを保障するという、生活保護の趣旨になじまない。 |
|
| 3 |
衣食住は一体不可分で、最低生活費は一体として保障されるもの。住宅扶助などの一部の扶助だけを地方自治体の責任とすることは、生活保護の体系を崩すもの。 |
|
| 4 |
医療扶助の権限に何の変更もなく、新たな都道府県負担を導入することは、単なる負担転嫁そのもの。 |
|
| 5 |
児童扶養手当の認定基準は全国一律の収入のみであり、地方自治体の裁量の余地は全くない。 |
|
参考資料
(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、
国が生活に困窮する
すべての国民に対し、その
困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その
最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第2条
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、
無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
(生活扶助の方法)
第31条 生活扶助は、
金銭給付によつて行うものとする。(以下略)
(教育扶助の方法)
第32条 教育扶助は、
金銭給付によつて行うものとする。(以下略)
(住宅扶助の方法)
第33条 住宅扶助は、
金銭給付によつて行うものとする。(以下略)
| 平成元年4月3日・衆議院大蔵委員会における小泉厚生大臣答弁 |
(生活保護の国庫負担率を10分の7から10分の8に復元すべきとの質問に対する答弁)
| ○ |
小泉厚生大臣
生活保護というのは国として大事な事業でありますから、ほかの補助率とは違って最高の水準を維持すべきだという考えも持っておりますし、それが最高水準の補助率を維持すべきであるという点で10分の8がいいのか、10分の7.5がいいのか、それは議論があると思いますが、厚生省としては、10分の7.5、4分の3でこれからのいろいろな事業に対して、また生活保護を受ける方々のことを考えて支障はない、これでいいということで今回、4分の3に恒久的に措置したものであるということを御理解いただきたいと思います。 |
| |
■生活保護法(抄)
第8条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。(以下略) |
| ○ |
保護費は、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から収入を差し引いた差額を支給 |
| ○ |
最低生活費は、各扶助の合計額として一体的に算定 |
|
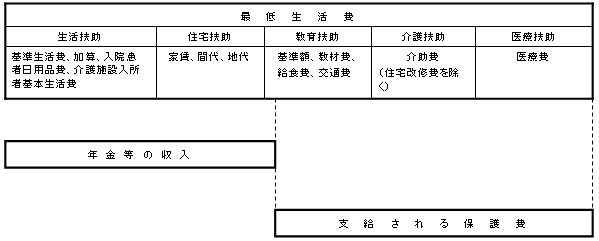
| 地方団体が税源移譲を求める補助金と生活保護との比較表 |
| 地方が改革案(2)で税源移譲を求めているもの(厚労省分) |
地域の創意工夫がより可能な分野の補助金として地方が移譲を求めているもの。
【地域福祉系】
| ○ |
身体障害者福祉費補助金(支援費等分を除く) |
| ○ |
児童福祉事業対策費等補助金 |
| ○ |
セーフティネット支援対策等補助金(ホームレス対策事業分)等 |
| 【保健衛生系】 |
| ○ |
疾病予防対策事業費等補助金 |
| ○ |
保健事業費等負担金((目細)保健事業費負担金)等 |
| 【介護系】 |
| ○ |
在宅福祉事業費補助金(支援費等分を除く) |
| 【地域医療系】 |
| ○ |
医療施設運営費等補助金((目細)救急医療施設運営費補助金等) |
| ○ |
地域医療対策費等補助金 |
| 【子育て系】 |
| ○ |
児童保護費等補助金(支援費等分を除く) |
| ○ |
次世代育成支援対策交付金 等 |
| 【施設系】 |
| ○ |
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 |
| ○ |
次世代育成支援対策施設整備交付金 等 |
| 合計:約4,800億円 |
| ※ |
この他に、厚労省分として、昨年度提案分のものが約3,500億円あり、これをあわせると厚労省分に係る地方の改革提案は約8,300億円となる。 |
|
|
 |
生活保護事務や児童扶養手当支給事務等は、地方自治法に定める法定受託事務として、国が責任をもって制度設計を行い、適正な事務処理に必要な処理基準等をきめ細かく定めるべき事務であり、地方自治体は、国が定めた認定基準への当てはめ、事実認定を行うのみ。 |
|
地方の改革案(2)は、
| ◎ |
年金・生活保護等のように所得再配分をして、所得保障する「金銭給付」は国、
|
| ◎ |
介護・保育等のように地域のニーズにあった現物給付を行う「対人社会サービス」は地方 |
という考え方により提示。 |
|
|